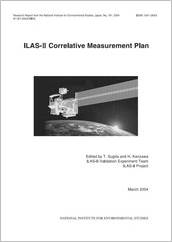人工衛星がとらえた推移
オゾン層(3)
今回は、人工衛星からオゾン層を観測する手法についてお話します。オゾンが高度10~50 kmの成層圏に多く存在することはすでに紹介しました。この上空のオゾン量は、1970年代後半から、米国の人工衛星を用いて測られてきました。
ところで、1982年の南極昭和基地およびハレー基地のオゾンの地上観測により、9月~10月(南極では春先にあたる)に、それまで見られなかったオゾン低濃度領域が現れることが、日・英の科学者によってそれぞれ別個に観測されました。これがいわゆる「南極オゾンホール」の発見です。
オゾンホール発見後、毎年取られていた人工衛星のデータをあらためて見直してみると、1980年代初めごろから南極上空のオゾンが減り始めていたことが判りました。実は、この時期に南極上空で観測されたオゾンのデータは異常に値が低かったため、データがおかしいのではないかということで、公表されずに終わってしまいました。観測データの中に、これまでにないデータが得られたとき、これを観測器の不調と考えるか新たな現象の発見に結びつけられるかは、データを解析する研究者の、観測データに対する姿勢の問題です。
観測データの性質を良く知り、わずかなデータの変化の兆候とその重要さを見逃さなかった人にのみ、新発見の栄誉が与えられることは、科学の歴史の物語るところです。
こうした経緯もありましたが、結果的には、我々はオゾンホールが起こる以前から、それが最大規模に拡大してしまった最近まで、ほぼ連続した、人工衛星によるオゾン観測データを入手出来ました。
下図は、米国の人工衛星センサTOMSが観測した南極上空のオゾン量の、10月の月平均値を示します。この図で、220ドブソンユニット(DU:オゾン層の厚さを表す単位)以下の領域が、「オゾンホール」と定義されています。この図から明らかなように、南極オゾンホールは1980年代初頭から現れはじめ、1980年代から1990年代にかけて拡大の一途をたどっていることが判ります。オゾンホールは2000年頃に最大規模になりましたが、2002年のように、特殊な気象条件のおかげで例外的に小さかった年もあります。いずれにせよ、今後少なくとも10数年間は、オゾンホールの動向を引き続き注視していく必要がありそうです。
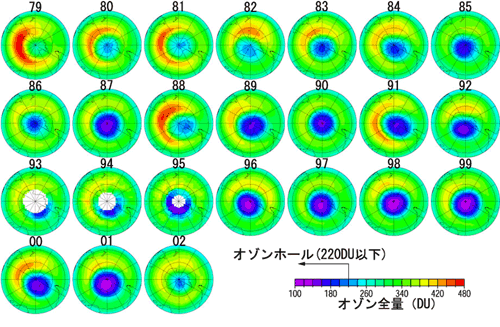
【成層圏オゾン層変動研究プロジェクト 衛星観測研究チーム 総合研究官 中島英彰】
- 研究最前線
- ふしぎを追って
- 市民と研究者と環境
- 私たちと話しませんか「環境の研究」
- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」
- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」
- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」
- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」
- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」
- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」
- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」
- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」
- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」
- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」
- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」
- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」
- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」
- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」
- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」
- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」
- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」
- オゾン層(1)「何がおきているか調査」
- ゴミ(7)「PCBをなくす」
- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」
- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」
- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」
- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」
- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」
- ゴミ(1)「日本での流れを追う」
- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」
- 森林「二酸化炭素収支を観測する」
- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」
- モニタリング「施策を目ざした観測」
- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」
- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」
- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」
- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」
- 温暖化(1)「深刻化するその影響」
- 花粉症(3)「予防するには」
- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」
- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」
- ココが知りたい地球温暖化
- CGER eco倶楽部
- 環環kannkann
- リスクと健康のひろば
- 環境展望台
- 環境展望台「環境技術解説」
- 環境展望台「探求ノート」
- 国立環境研究所動画チャンネル