20年で進んだ破壊
オゾン層(2)
オゾンは、太陽紫外線が強い熱帯・亜熱帯地域の成層圏で、酸素が光分解することによりどんどん作られています。と同時に、オゾンは大気中のさまざまな化学反応により、どんどん破壊されています。
現在の地球大気中のオゾン量は、このどんどん作られ破壊される両方の過程が釣り合ったところで決まっています。オゾンの原料である酸素は、オゾン量の約40~50万倍大気中に存在しますので、酸素と太陽がある限り、地球大気中でのオゾンの生成はなくなりません。 従って、オゾンが破壊される過程が今後どのように変化していくかを注意深く見守ることが、将来のオゾン層を予測する上での重要なポイントとなります。
フロンガスやハロンガスから放出される塩素原子や臭素原子がオゾン破壊を加速し、地球大気のオゾン濃度を薄くすることは、すでにご存知のことと思います。
このオゾン破壊の化学反応が地球温暖化(成層圏では寒冷化となる)によってどのような影響を受けるか、また地球温暖化によって気候が変化し、オゾンの赤道から南極や北極への運ばれ方が変化するならば、それがオゾンホールにどのような影響を及ぼすのか、 そして、温暖化によってオゾン層が回復する時期は遅れるのか、といった研究が盛んに進められています。
私たちの研究室でもこのような問いに答えるため、化学気候モデルと呼ばれるオゾン層の将来予測計算のできる数値モデルを開発して、研究を進めています。 1975年頃の地球大気の状態から出発して、2050年くらいまでのオゾン層変動の連続計算を、国立環境研究所のスーパーコンピュータを使って行っています。
まだテスト段階ですが、図にオゾンホールが顕著になる前の1980年頃(左)と、顕著になった後の2000年頃(右)の南半球の10月のオゾン量の計算値を示します。
1980年頃は南極周辺ではオゾン全量が220ドブソンユニット以上あったのに、2000年頃になると220ドブソンユニット以下(影をつけた部分)の面積が南極大陸の2倍近くまでに達していることがわかります。 この20年間にフロンガスやハロンガスの放出量の増加によって成層圏の塩素量と臭素量が増加し、オゾン破壊が進んだことが、確認されました。
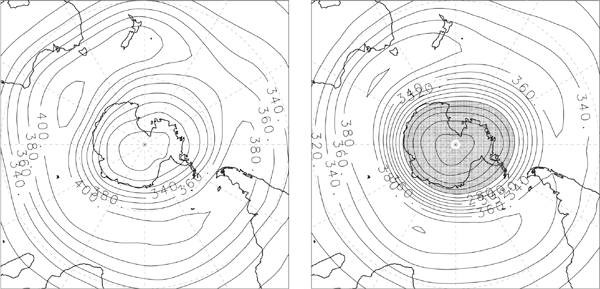
【成層圏オゾン層変動研究プロジェクト オゾン層モデリング研究チーム 主任研究員 秋吉英治】
- 研究最前線
- ふしぎを追って
- 市民と研究者と環境
- 私たちと話しませんか「環境の研究」
- 生物多様性(6)「国道沿いに咲くアブラナ」
- 生物多様性(5)「日本の自然は侵入種だらけ」
- 生物多様性(4)「ダムによる河川の分断の影響」
- 生物多様性(3)「レッドデータブックを知ってますか?」
- 生物多様性(2)「珍しい生き物ってどんな生き物?」
- 生物多様性(1)「大陸移動で生じた?」
- 越境する大気汚染(4)「広域大気汚染のシミュレーション」
- 越境する大気汚染(3)「黄砂を計る」
- 越境する大気汚染(2)「酸性雨の話」
- 越境する大気汚染(1)「広域大気汚染と観測」
- 魚類生息地ポテンシャルマップ「魚の棲みやすい川を考える」
- 水と土(3)「東京湾の現状、増水と影響」
- 水と土(2)「水処理技術、うまく生かせるか?」
- 水と土(1)「黒ボク土 人が作った土?」
- オゾン層(4)「南極でのオゾン破壊はなぜ?」
- オゾン層(3)「人工衛星がとらえた推移」
- オゾン層(2)「20年で進んだ破壊」
- オゾン層(1)「何がおきているか調査」
- ゴミ(7)「PCBをなくす」
- ゴミ(6)「再生品の安全性を考える」
- ゴミ(5)「リサイクル社会の身近な循環技術」
- ゴミ(4)「水素エネルギーを作り出す」
- ゴミ(3)「処分後に土に還るのか?」
- ゴミ(2)「不法投棄を空から捉える」
- ゴミ(1)「日本での流れを追う」
- 摩周湖「汚染の超高感度検出器」
- 森林「二酸化炭素収支を観測する」
- 二酸化炭素「温暖化の原因物質を観測する」
- モニタリング「施策を目ざした観測」
- 温暖化(5)「洋上風力発電の可能性をさぐる」
- 温暖化(4)「京都議定書以降に見えるもの」
- 温暖化(3)「炭素税は対策として有効か?」
- 温暖化(2)「暑く悪天候で大雨増える」
- 温暖化(1)「深刻化するその影響」
- 花粉症(3)「予防するには」
- 花粉症(2)「なぜこんなに増えているのか?」
- 花粉症(1)「症状を悪化させるもの」
- ココが知りたい地球温暖化
- CGER eco倶楽部
- 環環kannkann
- リスクと健康のひろば
- 環境展望台
- 環境展望台「環境技術解説」
- 環境展望台「探求ノート」
- 国立環境研究所動画チャンネル






