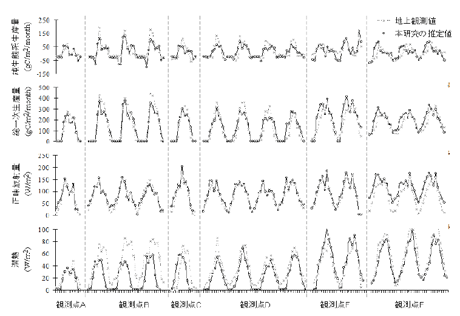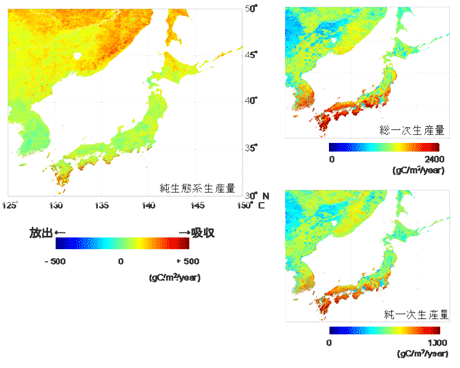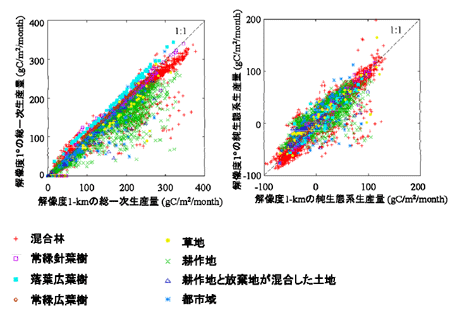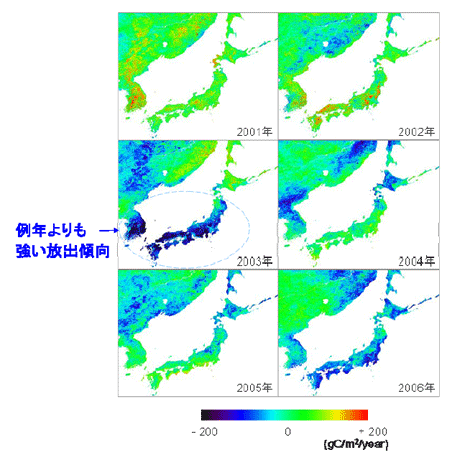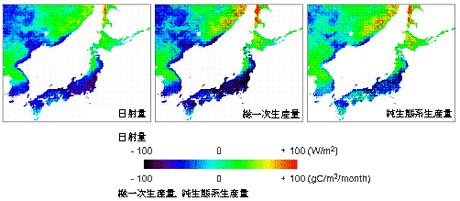自然生態系による炭素収支量の現状把握
− 地域別評価の可能性 −
(名古屋教育記者会、筑波研究学園都市記者会同時発表 )
国立大学法人名古屋大学
大学院環境学研究科助教:佐々井 崇博(052-789-3023)
独立行政法人国立環境研究所
地球環境研究センター陸域モニタリング推進室長:三枝 信子(029-850-2517)
この度、名古屋大学大学院環境学研究科の佐々井 崇博助教と独立行政法人国立環境研究所の三枝 信子地球環境研究センター陸域モニタリング推進室長を中心とする研究グループは、国内の複数大学及びNASAとの共同で、日本域の自然生態系における炭素収支量を1km解像度で解析しました。この研究の特徴は、二酸化炭素収支量の現状把握を目的として、観測データに基づく新たな推定手法を開発したことにあります。地表面の情報を捉える衛星観測データを複合利用することによって、時々刻々と変化する陸域生態系の活動を正確に把握することができます。土壌も含めた自然生態系の炭素収支量を、観測に基づき、これだけ詳細な解像度で広域評価した研究例は世界的にもほとんどありません。
今回の研究結果は、これまで盛んに行われてきた解像度の粗い解析の結果とは大きく異なったことから、日本のような複雑な地形・被覆の地域では少なくとも1km程度の解像度が必要であることを指摘しています。今後は、地理情報システムと組みわせることで、地域毎の炭素収支量の特徴や気象変化・土地利用変化との関係が明らかになり、行政区分ごとの二酸化炭素収支量の評価や管理に貢献することが期待されます。
なお、本研究成果は、平成23年4月5日付(米国東部時間)米国科学雑誌Remote Sensing of Environment電子版に掲載されました。
<研究に関する問い合わせ先>
国立大学法人名古屋大学
大学院環境学研究科助教 佐々井 崇博
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL:052-789-3023 FAX:052-789-3023
独立行政法人国立環境研究所
地球環境研究センター陸域モニタリング推進室長 三枝 信子
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2
TEL:029-850-2517 FAX:029-850-2645
ポイント
・ 衛星観測データを複合利用した新たな陸域炭素収支量の推定手法を開発した
・ 土壌も含めた自然生態系の炭素収支量を1km解像度で推定した
・ 自然生態系の炭素収支量を、観測に基づき、これだけ詳細な解像度で広域評価した研究例は世界的にもほとんどない
・ 日本のような複雑な被覆、地形では少なくても1km程度の解像度で解析する必要がある
・ 他の研究と組み合わせることで、地域毎に炭素収支量を評価することが期待できる
背景
地球温暖化の実態を解明する上で、陸域の炭素収支量を正確に把握することは必要不可欠である。京都議定書の第一約束期間以降も地球温暖化対策に向けた国際的な枠組みを作る動きがあり、その中では陸域生態系が温暖化に与える影響の評価や陸域生態系サービス注1 の定量評価などが挙げられている。しかし、陸域は海洋と比べて収支量の不確定性が大きい。IPCC第四次評価報告書注2 では、1990年代における海洋の炭素収支量を-2.2±0.5 PgC/year(マイナスは吸収を意味する)注3 、陸域を-1.0±0.6 PgC/yearと報告している。中でも、陸域生態系の炭素収支量は-2.6 PgC/year、その不確実性は±1.7 PgC/yearで、大気、海洋を含めたどの炭素量よりも大きな不確実性を持つ。その理由は、地表面の被覆が複雑であることによって生態系の機能が地域間で大きく異なるためだと考えられる。従って、陸域の炭素収支量を正確に算定するためには、より詳細な空間解像度で推定することが不可欠である。衛星観測データに基づく炭素収支量の研究は、これまで緯度経度1度〜数kmメッシュ程度の解像度で計算されることが多かった。しかし2000年以降、時間的にも空間的にも連続的に観測できる地球観測衛星が打ちあがり、1km程度の空間分解能を持つ地表面観測データが入手できるようになった。その結果、現在1km解像度の炭素収支量を計算できるようになりつつある。ただし、炭素収支量を直接観測することはできないため、1kmメッシュの衛星観測データを複合利用する炭素収支アルゴリズムの開発が緊急課題となっていた。
そこで、名古屋大学、国立環境研究所、筑波大学、 NASA Ames研究所、北海道大学、福島大学、岐阜大学の共同研究グループは、独自の衛星データ処理、及び衛星データを複合利用する新たな炭素収支アルゴリズムの開発を行い、観測データに基づく1km解像度の純生態系生産量注4 を推定した。本解析の目標は、極東アジア地域の陸域生態系が、いつどこでどのくらい炭素を吸収、もしくは放出しているかを明らかにすることである。これらの活動は、日本学術振興会科学研究費補助金、環境省地球環境研究総合推進費(平成14〜18年度)、及び国立環境研究所地球環境研究センター陸域モニタリング推進室の委託研究「森林生態系における炭素収支モニタリング」の一環として実施した。
研究の内容
1) 炭素収支アルゴリズムの開発
地上観測、衛星観測データに基づく炭素収支量を計算するため、1km解像度の衛星データを複合利用できる炭素収支アルゴリズムBiosphere model integrating Eco-physiological And Mechanistic approaches using Satellite data (以下、BEAMS)を開発した。BEAMSは、地表面の気象変化、植生タイプや土壌タイプの違い、水・エネルギー収支との相互作用などを統合的に解析できる炭素収支アルゴリズムで、多くの衛星観測データを取り込んで炭素収支量を計算するように記述されている。そのため、複数の衛星センサを跨いで収集された地表面観測データに独自の画像処理を施し、BEAMSの入力データとして整備した。本アルゴリズムの精度評価には、国立環境研究所地球環境研究センターが束ねる観測ネットワークJapanFluxで長期連続観測された二酸化炭素収支量データを用いた。対象サイトは、日本国内が北海道幌延(観測点A)、苫小牧(B)、愛知県瀬戸(F)、岐阜県高山(D、及びE)の計5サイト、日本に隣接する中国Laoshan(C)が1サイトで、計6サイトとなる。検証項目は、純生態系生産量に加え、光合成による炭素吸収量(総一次生産量注5)や正味放射量注6 、潜熱注7 も同時検証した。複数サイトで4つ以上のパラメータを同時に検証した研究は世界的にも稀であり、推定精度の信頼性は既存研究よりも高いものだといえる。
2) 炭素収支解析の結果
2-1 純生態系生産量の空間分布
単位面積あたりの純生態系生産量を解析した結果、ほぼ日本全域の生態系が二酸化炭素を吸収しており、特に北海道中央部・北部や太平洋沿岸部で吸収量が多いことが明らかになった。この空間パターンは、これまで盛んに解析されている植生のみの炭素収支量(総一次生産量や純一次生産量注8 )のパターンとは大きく異なることがわかった。植生は成長速度に応じて二酸化炭素を吸収するため、植生のみの炭素吸収量は温暖な地域(四国や九州など)ほど多く、寒冷な地域ほど少ない。一方、土壌は微生物による有機物の分解によって炭素を大気へ放出し、その活動は地温に依存する。よって、土壌からの放出量は寒冷地域ほど少なく、温暖な地域ほど多い。両者を差し引いた生態系全体の炭素収支量(純生態系生産量)は、見かけ上気温による地域差が小さくなる。
1km解像度の炭素収支データを標高データと比較したところ、本研究で推定された植生の炭素吸収量は高山地帯で低いことがわかった。1km程度の解像度であれば、日本の複雑な地形を十分に考慮できると言える。
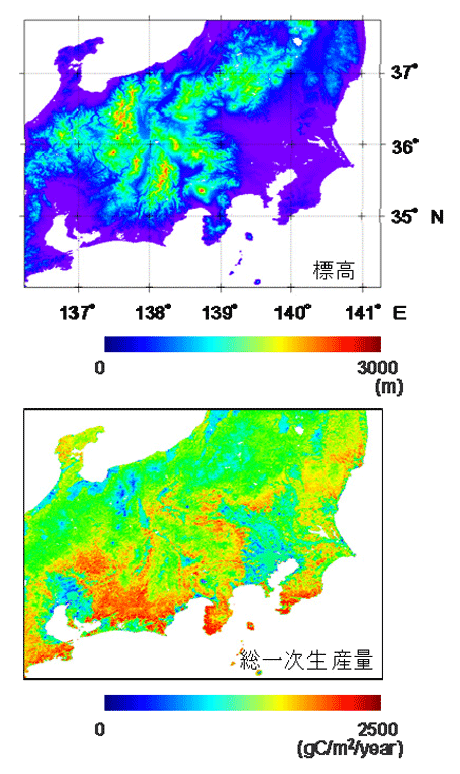
2-2 1km解像度の重要性
解像度の粗さが炭素収支量にどの程度影響するかを調べるために、緯度経度1度解像度で計算された炭素収支量との比較を行った。その結果、総一次生産量と純生態系生産量は、それぞれ±6.95 (gC/m2 /month) 注9 、±9.11 (gC/m2 /month)程度の誤差が生じることがわかった。日本のような複雑な地形・被覆を持つ地域では、少なくても1km程度の解像度で炭素収支量を推定する必要があることを指摘している。
2-3 純生態系生産量の経年変化
純生態系生産量の年積算値と月別値について、例年の平均値からの差(偏差)を調べたところ、年間積算値の変化幅よりも月別値の変化幅の方が大きいことがわかった。年間積算値の変化幅は、一年あたり±200 (gC/m2 /year)程度であった。最も大きな変化を示した年は2003年で、例年よりも180〜200(gC/m2 /year)程度放出が多かった。更に、2003年の月別値を調べたところ、最も大きな変化を示した月は7月で、例年の7月と比べて一月あたり50 (gC/m2 /month)以上、炭素放出量が多い地域があった。2003年7月に純生態系生産量が大きく変化した理由は、梅雨前線の長期停滞が挙げられる。梅雨前線の長期停滞によって太陽光が雲で遮られ、地表面の日射量や気温が大きく減少した。十分な光と温度を得られないために光合成活動が抑制されて植生による炭素吸収量が大きく減り、また土壌微生物は十分な温度が得られないために有機物の分解活動が抑制されて放出量が減った。この二つの効果は純生態系生産量に対して相殺関係にあるため、両者をそれぞれに分けて調べた。その結果、二つの減少のうち、植生による吸収量の減少率が土壌微生物による放出量の減少率を上回ったことがわかった。植生による吸収量が最も減った地域では、例年からの差が100 (gC/m2 /month)を超える地域もあった。ただし、月別値の変化幅と比べると、年間積算値の変化幅にはあまり差が生じなかった。このことから、自然生態系がその一時的な変化の中で生き抜くために炭素吸収量をリカバーするなんらかの環境応答をしている可能性がある。変動要因や環境応答は地域によって異なるとも推測されることから、今後は気象・植生データとの比較や気候区分、植生区分単位での炭素収支解析を行っていく予定である。
成果の意義
今回開発した手法は、空間スケールや解像度が衛星観測データによって決まる。近い将来、国内外の研究機関がより高度な衛星センサを打ち上げる予定であるため、今後はより詳細な解像度での炭素収支評価が期待される。炭素収支データを地理情報システム(GIS)と組み合わせ、地域別の自然生態系による炭素収支量を集計すれば、地域別の炭素収支評価が可能となる。また、人為的に自然生態系の炭素収支量を管理する研究とも組みわせれば、地域毎の炭素収支量の特徴や気象変化・土地利用変化との関係が明らかになり、行政区分ごとの評価にも貢献することが期待できる。
用語説明
-
1、生態系サービス人類が生態系から得るあらゆる利益を表す。例えば、食料や水などの生産物、気候変化の制御、光合成による酸素の供給など。
-
2、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)PCC(気候変動に関する政府間パネル)は、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画 (UNEP)により設立された組織。
-
3、PgC/year1年あたりに生態系が吸収、もしくは放出する炭素の総量(ペタグラムカーボン)。1 gCは、質量1グラムの炭素をさし、1 PgC(ペタグラムカーボン)=1.0 x 1015 gC(グラムカーボン))となる。
-
4、純生態系生産量植生の光合成活動による炭素吸収量から、植生の呼吸による炭素放出量と土壌微生物活動による炭素放出量を差し引いた自然生態系の炭素収支量を表す。
-
5、総一次生産量人植生の光合成活動による炭素吸収量を表す。
-
6、正味放射量太陽からの放射エネルギーから、地表面で反射される放射エネルギーを差し引いた放射エネルギー量。
-
7、潜熱地表面から水が蒸発する時に使われる熱エネルギー量。
-
8、純一次生産量植生の光合成活動による炭素吸収量から、植生の呼吸による炭素放出量を差し引いた植生の炭素収支量を表す。
-
9、gC/m2 /month1月あたり、単位面積あたりに生態系が吸収、もしくは放出する炭素の総量(グラムカーボン)。
【論文名】
Sasai, T., N. Saigusa, K.N. Nasahara, A. Ito, H. Hashimoto, R.R. Nemani, R. Hirata, K. Ichii, K. Takagi, T.M. Saitoh, T. Ohta, K. Murakami, Y. Yamaguchi, T. Oikawa, Satellite-driven estimation of terrestrial carbon flux over Far East Asia with 1-km grid resolution, Remote Sensing of Environment, doi:10.1016/j.rse.2011.03.007., in press.