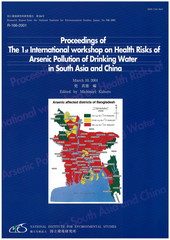環境中のヒ素とその健康影響
特集 ヒ素の健康影響研究
野原 恵子
ヒ素は地球を構成する元素としては微量成分ですが、単体やさまざまな無機ヒ素化合物、有機ヒ素化合物として、自然界の鉱物、水、堆積物や、また食べ物などに含まれ、環境中に広く分布しています。生体内ではppbオーダーで存在して生命機能の維持に働く超微量元素のひとつとも言われていますが、有害性が高く、ヨーロッパなどでは古くから毒薬として使用されていました。また微量であっても長期間摂取することによって慢性ヒ素中毒による健康被害をもたらすことが知られています。
ヒ素は生物に対する毒性も強いことから、殺虫剤や除草剤、防カビ剤などとして世界中で多用され、環境中に放出されてきました。その結果、職業的に曝露された人や周囲の住民に慢性ヒ素中毒が発生し、角化症などの皮膚疾患や発癌、および代謝疾患、神経疾患、免疫抑制など、生涯にわたる深刻な健康被害が報告されています。これらのヒ素を含む農薬の使用は日本ではすでに禁止されていますが、世界ではいまだに使用されている地域があります。日本での事例としては、宮崎県土呂久鉱山および島根県笹ヶ谷鉱山で鉱石からの亜ヒ酸の製造によって環境汚染がおこり、住民に慢性ヒ素中毒がおこっていたことが1970年代初めに報告されています。
また現在大きな環境問題の一つになっているのが、バングラデシュとその周辺地域や台湾、中国など世界各地で発生している井戸水の無機ヒ素汚染です。バングラデシュの例では、1970年代からため池などの表層水よりも「衛生的」な水を得るために井戸を掘って地下水を利用し始めたところ、その水に地層から高濃度の無機ヒ素の混入があり、健康被害が発生しています。濃度の高いところでは、1 mg/L以上のヒ素が検出されています。しかしヒ素の健康被害が確認されてもなお、技術的、経済的な理由から安全な水の確保が実現できない地域が多く、慢性ヒ素中毒の患者数は世界で数千万人にも上るといわれています。また井戸水の過剰なくみ上げなどが地層中のヒ素の地下水への溶出を促進することによってヒ素汚染を拡大させることから、ヒ素による健康被害は今後さらに広がる可能性も指摘されています。
我が国では、水道水についてはヒ素(ヒ素およびその化合物)に対して水道法水質基準値(0.01 mg/L)が定められています。しかし井戸水については、それより高濃度のヒ素が含まれるケースが見つかっています。また日本人はヒ素の含有量が高い海藻や魚介類を食する習慣があることから諸外国と比較してヒ素を多く摂取しており、一部の高曝露群では健康に悪影響を及ぼしうる量のヒ素を摂取している可能性も指摘されています。
このようにヒ素は私たちの身の回りに常に存在し、健康被害をおこしうる元素です。このような状況から、ヒ素の健康へのリスクを評価するために、曝露の実態調査や、また生体への影響を評価するために必要な毒性メカニズム研究や代謝機構の研究がさらに必要であると考えられています。
私たちは先導研究プログラム「小児・次世代環境保健研究プログラム」をはじめとしたプロジェクトにおいて、ヒ素の健康影響に関する研究を進めています。特に、胎児期などの発達期は化学物質に対する感受性が高いことが示されており、この時期の曝露が生まれた子の成長後に生涯にわたる影響をもたらすことや、さらに継世代的に影響を及ぼすことが懸念されています。このような現象には「エピジェネティクス」という遺伝子機能の調節機構が関係することが明らかにされつつあります。私たちは特にこれらの新たな問題に着目し、ヒ素の作用メカニズムの解明を目指して研究を行っています。本特集号では、ヒ素の発がん増加作用について、エピジェネティクスの関与に着目した研究を【シリーズ先導研究プログラムの紹介】で紹介します。また、ヒ素が「細胞老化」という現象を引きおこすことが免疫系の抑制につながることを明らかにした研究を【研究ノート】で紹介します。これらのヒ素の毒性や生体影響は、実はヒ素の化学形態によって大きく異なります。この点については【環境問題基礎知識】で詳しく解説しました。
これらの研究結果からヒ素が生体にいかに作用するかを明らかにすることによって、ヒ素の健康影響をより確実に把握することが可能になります。そこから、ヒ素の悪影響を効果的に防ぐ方法へとつなげていきたいと考えています。
執筆者プロフィール

スポーツ観戦が好きで、テレビで見かけるとほぼどの競技でもはまります。最近は研究室や身の回りのアスリートたちの筋肉論がおもしろいです。