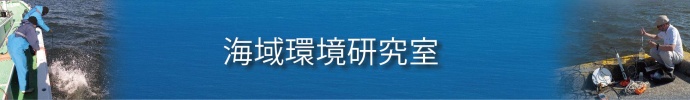海域環境研究室
- 2025年7月10日環境研究総合推進費S-23沿岸環境・生態系デジタルツインプロジェクトのウェブサイトを立ち上げました
- 2022年12月8日東日本大震災の津波で変化した沿岸生態系が回復-震災後10年にわたる延べ500人余の市民ボランティアとの調査で判明-
-
2022年12月8日ニュースで研究成果が紹介されました
東日本大震災の津波で激変した干潟の生態系 約7年で回復 10年間の調査で判明(ニュース元にリンク) - 2022年8月3日株式会社商船三井技術部技術研究所と「燃料用重油・潤滑油類の主要炭化水素の事前網羅的分析とデータベース化」に係る共同研究を開始しました
- 2022年3月12日NHKスペシャルで震災後の干潟調査の結果が紹介されました
海域環境研究室では、良好な沿岸環境と生態系の保全・再生・創出をめざしています。そのために、有機物や栄養塩類等の循環、植物プランクトンや底生動物といった生物の個体群や群集の動態、さらに自然災害や気候変動の影響と将来予測について研究を進めています。現場観測・室内実験・数値モデル解析を組み合わせ、沿岸環境を変動させるメカニズムの解明に取り組んでいます。
A) 沿岸環境の気候変動影響評価・予測・適応研究
近年、沿岸域では気候変動の影響が顕在化し、藻場の磯焼けや魚介類の急減など、水温上昇が主な原因とみられる生態系の変化が各地で報告されています。いま海で起きている変化は気候変動によるものなのか?今後の気候変動は沿岸環境・生態系にどのような影響を及ぼすのか?それに対して我々はどう対応すればよいのか?これらの問いに答えるため、長期モニタリングデータの解析、植物プランクトンや底生動物の観測・実験、数値シミュレーションによる将来予測等の研究を進めています。これらの研究成果は気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)において公開され、気候変動の影響評価や適応策の検討に活用されています。
A-PLAT「瀬戸内海の水環境への気候変動影響」
A-PLAT「R版DECOMPを用いた水温・水質データの季節調整によるトレンド解析」
B) 沿岸における災害環境研究
東日本大震災の津波は、臨海部備蓄油の海域への流出や干潟環境の大規模な変化(仙台市蒲生干潟)などを引き起こし、沿岸環境と生態系に大きな影響を及ぼしました。私たちは震災後、東北地方の干潟や沿岸域における環境影響評価と回復過程の解明に取り組んできました。気仙沼湾や大船渡湾では、津波により流出した油由来の底質残留炭化水素についての経年モニタリングを行い、蒲生干潟では津波攪乱後の底質環境や植生帯、底生動物の経年変動を追跡し、干潟生態系の回復過程を記録しています。さらに、各地の海岸において、防潮堤等の復旧工事と生態系保全との両立にむけた調査研究にも取り組んでいます。
資料リンク:39-2.pdf
関連論文:宮城県蒲生潟の海岸エコトーンにおける地形,植生,底質および底生動物への東日本大震災の影響と2023年までの移り変わり
C) 沿岸環境・生態系のデジタルツイン技術開発
日本の沿岸域では、長年の取組みにより水質の改善が進む一方で、かつての豊かな生態系の回復には至っていません。今後、生物多様性や生産性を高め、ネイチャーポジティブに繋げるためには、海域の特性に応じたきめ細かな対応が求められ、地域の取組みがより一層重要となります。藻場・干潟の保全・再生など、地元の方々の活動がどれくらいの効果や価値を創出するのか?それを統合的に評価するとともに予測結果を市民や民間企業の方々に分かりやすく伝えるためのデジタルツインの開発を進めています。
環境研究総合推進費S-23のホームページ
D) 陸域~沿岸〜外洋をつなぐ物質動態の統合シミュレーションシステム開発
日本沿岸は外洋に比べ生物生産性が高く、豊かな生態系と水産資源を支えています。その基盤となる栄養物質は、黒潮・親潮などによる外洋からの供給に加えて、河川や地下水を通じて陸域からももたらされています。しかし、その定量的な実態や人間活動による変化は未解明な点が多く、物質動態の把握と影響評価が急務となっています。私たちは、この課題に応えるため、物理過程(陸水・海水の流れ)と生物地球化学過程(物質の供給・変質)の数値モデリング手法を駆使し、陸域から外洋までを包括する日本沿岸の統合シミュレーションシステムの開発を進めています。これにより、陸域からの物質供給が沿岸域の生物生産や生態系に果たす役割を明らかにし、沿岸海洋の持続的な利用と保全に貢献することをめざしています。
(文部科学省科研費 学術変革領域A マクロ沿岸海洋学, https://macrocoast.jp)
E) 沿岸環境における陸起源物質動態に関する研究
河川出水によって沿岸に形成されるプリュームは、生物生産に必要な栄養塩だけでなく、赤潮や貧酸素水塊の原因となる汚濁物質や懸濁物質(赤土など)も含んでいます。気候変動による豪雨・出水の増加や下水処理場の季節別管理運転の導入により、こうした出水プリュームの監視の重要性が高まっています。私たちは自治体や研究機関と連携し、海色衛星観測、ドローン空撮、自動観測船などを活用した先端的観測を活用し、汚濁物質指標としての有色溶存有機物(CDOM)や生物生産指標としてのクロロフィルa濃度のマッピング技術の開発を行っています。対象海域は、大阪湾、伊勢湾、東京湾などの都市沿岸域に加え、七尾湾・広湾・恩納村沿岸などの自然環境が豊かな海域を含めることで、地域・海域特性に応じた陸起源物質の水質・生態系への影響把握を進めています。
F) 海洋開発現場における環境モニタリング技術開発
海底熱水鉱床や深海レアアース泥の開発は、将来の資源確保に向けて国際的に注目され、わが国でも実証研究が進められています。こうした大規模な海洋開発では、環境への影響を的確に把握し、持続可能な利用につなげるためのモニタリング技術が重要です。私たちは内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「海洋安全保障プラットフォーム」に参加し、開発サイトで活用可能な「水質健全性評価システム」の開発を進めています。現場海水を用いた「洋上バイオアッセイ」と、光合成活性を指標として水質異変を連続監視する「ファイトアラートシステム」を統合し、操業現場で迅速かつ定量的な水質評価の実現をめざしています。さらに、操業や事故に伴って発生しうる濁水や有害物質の拡散をリアルタイムに把握・予測するため、ドローン空撮を活用した簡易予測技術の開発にも取り組んでいます。これらの研究を通じて、海洋開発現場における環境影響リスクの早期検知と影響予測を実現し、持続的な海洋利用の推進に貢献することをめざしています。
環境儀 https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/72/72.pdf
G) 地方環境研究機関との沿岸海域に関する共同研究
日本の沿岸海域(公共用水域など)では、過去40年にわたって水質観測が継続され多くのデータが蓄積されてきました。私たちは、全国の地方環境研究機関と協働し、長期観測データを活用した水質変動の解析や、さまざまな海域における懸濁態・溶存態有機炭素、クロロフィルa、栄養塩類の分析、多項目水質計を用いた底層溶存酸素量(DO)の現場観測などを行っています。これらの観測結果や数値シミュレーションを通じて、近年水質環境基準項目に追加された底層DOや豊かな海を実現する上で重要な栄養塩類の管理など、各自治体が推進する水環境施策に資する知見提供を進めています。
資料リンク:H29-H31.pdf R2-R4.pdf
-
室長
-
上級主幹研究員
-
主幹研究員
-
上級主幹研究員
-
主任研究員(琵琶湖分室兼務)
-
主任研究員
-
特別研究員
-
特別研究員