第5回全国公害研究所交流シンポジウム
所内開催又は当所主催のシンポジウム等の紹介
安藤 満
全国各地の地方公害研究所と本研究所及び環境庁との研究の交流を目指した本シンポジウムも、今年で5回目を迎え、発表も非常に充実した内容となっている。シンポジウムのテーマは、担当の保健部、生理部と環境庁が打ち合わせの上、現在最も解明の急がれる「浮遊粒子状物質(SPM)汚染の現状と今後の課題」に決定した。全国の地方公害研究所に講演発表についてアンケートを郵送し、シンポジウムへの参加と希望を提案してもらい、内容の決定を行った。右のプログラムにシンポジウムの内容を記載している。
SPMはディーゼル車の普及と道路網の発達につれ、今後、特に汚染のリスク評価が必要となる研究分野といえる。SPMはまた、その物理的性状、化学的組成、生体影響が多彩なため、学際性に富んだ研究分野である。本シンポジウムも、学際性をもたすよう担当部一同苦慮した。プログラムのパネルディスカッションは、交流シンポジウムとして始めての試みであるが、学際的テーマに対する内容の充実を図ったものである。司会の小泉副所長をはじめ、パネリストの努力の結果、SPM問題の解決のために、学際的協力が不可欠なことが共通認識となったことが、本シンポジウムの大きな成果であったように思う。
(あんどう みつる、セミナー委員会シンポジウム担当委員、環境保健部環境保健研究室)

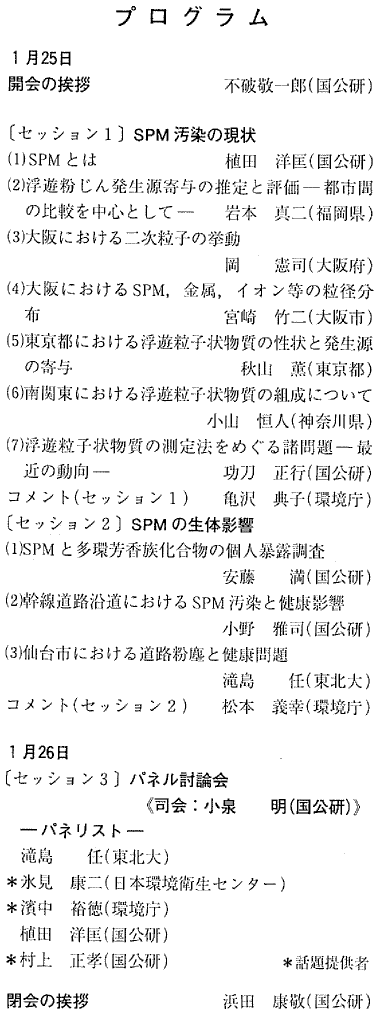
目次
- 国立環境研究所としての新展開巻頭言
- 野外研究を大切に論評
- 地方公害研究所と国立公害研究所との協力に関する検討会(第9回)の報告所内開催又は当所主催のシンポジウム等の紹介
- 広域都市圏における交通公害防止計画策定のための環境総合評価手法に関する研究特別研究活動の紹介
- 環境水中に見いだされる新たな汚染物質経常研究の紹介
- 環境汚染のリスクアセスメント − 健康リスク評価の問題点を中心として −環境リスクシリーズ(3)
- 故岩田敏研究員を偲んでその他の報告
- 快適な暮らしの代償としてのリスク環境リスクシリーズ(4)
- 都市大気汚染の解明へのアプローチ研究ノート
- INSTAC計画に参加して海外出張報告等
- 土の緩衝能−土の土としての機能−経常研究の紹介
- Duke大学での研究生活海外からの便り
- 土壌生態系への重金属の影響研究ノート
- 新刊・近刊紹介
- 主要人事異動
- 編集後記


