- 予算区分
- SP 重点研究プログラム
- 研究課題コード
- 1620SP020
- 開始/終了年度
- 2016~2020年
- キーワード(日本語)
- 循環型社会,循環資源,3R,廃棄物処理,アジア
- キーワード(英語)
- sound material cycle society,recyclable materials,3R,waste management,Asia
研究概要
推進戦略に基づき、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進する技術・社会システムの構築、廃棄物の適正処理と処理施設の長寿命化・機能向上に資する研究・技術開発、バイオマス等の廃棄物からのエネルギー回収を推進する技術・システムの構築に取り組む。
本研究プログラムでは、以下の5つの課題に取り組む。
(1) 日本の生産消費活動が国際サプライチェーンを通じて誘引する資源消費、環境負荷、社会影響の解析と将来シナリオ別持続可能性の評価。
(2) 日本およびアジア地域における資源循環の主要な技術プロセスにおける随伴物質の挙動の把握と資源利用に伴う環境影響評価、及び循環資源の長期的なフロー・ストックの推計手法の開発と複数の循環施策シナリオの評価。
(3) マクロからミクロまでの様々な社会動向に対応し他の環境政策・公共政策と接合する、循環型社会を実現するための転換方策のビジョン提示と各方策の具体化及び効果推計。
(4) 日本を含めたアジア圏における各地域の環境・経済・社会に適合した持続可能で強靭な廃棄物の処理システムの提示と、都市特性、経済状態、社会受容性を与条 件とし、廃棄物処理計画の上位にある都市計画などと調和した将来の廃棄物処理制度・システムの評価手法確立と将来像の提示、並びに焼却技術や埋立技術及び その他の関連技術についての統合的な技術システムの開発と高度化。
(5) 廃棄物系バイオマスを多様かつ複合的に利活用できる次世代型の燃料・エネルギー化技術の開発、CO2以外の環境負荷物質の挙動把握、実証を通じた燃料・エ ネルギー等の適切な利用法の提案、及び資源回収を重視した次世代型の中間処理技術の開発と新規廃棄物等の適正処理の安全性の評価・確認。
研究の性格
- 主たるもの:政策研究
- 従たるもの:技術開発・評価
今年度の研究概要
(1)については、前年度と継続して将来像の解析に必要となるシナリオに応じた技術、ライフスタイル、貿易データの整備を進める。日本経済がサプライチェーンを通じて誘引する資源利用に伴う環境影響、社会影響を含めた多様なリスク要因の解析とその将来シナリオを定量的に描き、社会の持続可能性に資する資源管理方策を提示することを目指して、シナリオおよび各種のデータ整備を中心に、モデルの開発および時系列データの拡充を進める。
(2)については、資源利用の高効率化とリスク低減のための、技術プロセスおよび循環資源のフロー・ストック管理のシナリオの評価と対策の提言を行う。具体的には、リサイクル施設情報を用いたフロー解析、経気道や経皮の曝露評価試験ならびに有害性を掛け合わせたリスク評価、さらに電気電子機器とプラスチックのリサイクルなどを対象としたシナリオ評価を行う。
(3)については、一般廃棄物処理・地域循環共生圏に関する全国モデルを改良し、収集モデルを組み込むとともに、焼却施設の統合や集約処理の研究を継続する。人口減少や高齢化、自治体廃棄物行政の変化等の社会変化や政策介入をふまえたシナリオ分析については、継続して実施し、分析シナリオを改める。さらに、今後の資源循環システムの評価指標として、質的側面を把握するリサイクル率の指標開発に着手する。高齢化については、ごみ集積所管理についての調査と分析を行う。さらに、物質循環の質の向上に係る事例の類型化と、製品ストックの活用に係る分析を継続して実施する。
(4)については、アジア新興国を対象としたごみ発生原単位及び収集率の推計方法を検討する。衛生施設を組み入れた開発事業の提案書を作成し、実装に向けた取り組みを進めるとともに、アジア都市廃棄物の固形燃料転換に係る効率化と環境負荷削減について検証する。また、埋立地浸出水の人工湿地および植生浄化に関する現地実証的な検討を行う。さらに、有害物質を埋め立てる処分場の長期的な安全性評価のためのシナリオづくりに着手するとともに、汚濁水域に起因する派生バイオマスの低炭素型の活用及び省エネ型排水処理技術の開発を進める。東南アジアでの分散型生活排水処理技術及びその性能評価試験方法の現地化のための調査・試験を継続して実施する。
(5)については、バイオ燃料製造技術の開発では、都心部分散型のメタン発酵施設の運転管理に資するモニタリングシステム構築のため、油脂の嫌気性分解に起因する高級脂肪酸の簡易・迅速な抽出操作および検出の各段階の要素技術を開発する。バイオ燃料利用技術の開発では、都市部におけるデュアルバイオ燃料製造システムを設計し、実証化を目指す。また、メタン発酵施設における環境汚染物質等の挙動を調査し、挙動の再現を目的に挙動予測モデルにおける入力パラメータを精緻化する。熱処理技術の開発では、熱処理技術の開発では、焼却残渣へ移行する重金属等の由来となる廃棄物種を探索し、焼却主灰中金属の選別手法の検討や他の熱処理による貴金属回収技術開発に着手する。
課題代表者
寺園 淳
- 資源循環領域
- 上級主席研究員
- 博士(工学)
- 工学
担当者
-
中島 謙一資源循環領域
-
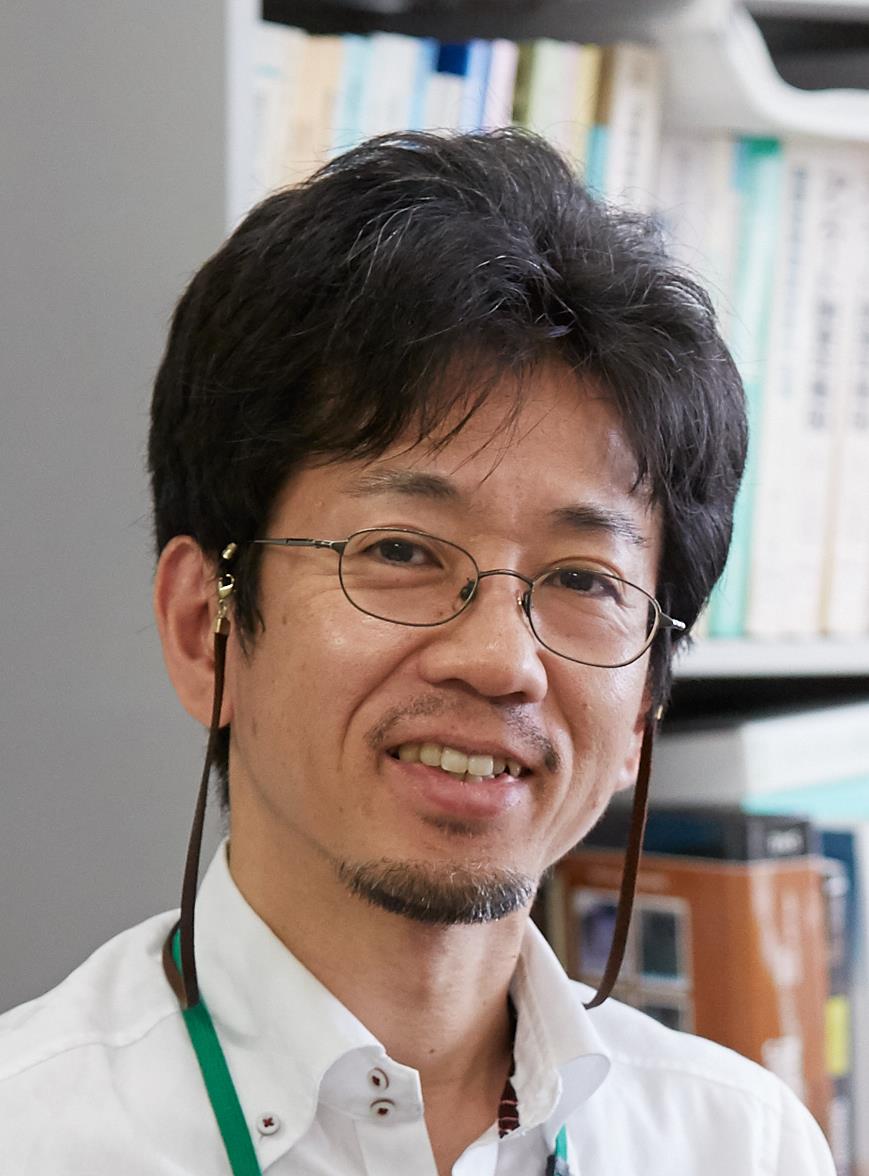 田崎 智宏資源循環領域
田崎 智宏資源循環領域 -
山田 正人資源循環領域
-
倉持 秀敏資源循環領域
-
大迫 政浩企画部
-
南齋 規介資源循環領域
-
小口 正弘資源循環領域
-
鈴木 剛資源循環領域
-
梶原 夏子資源循環領域
-
横尾 英史
-
吉田 綾資源循環領域
-
 稲葉 陸太資源循環領域
稲葉 陸太資源循環領域 -
 河井 紘輔資源循環領域
河井 紘輔資源循環領域 -
 多島 良資源循環領域
多島 良資源循環領域 -
 蛯江 美孝企画部
蛯江 美孝企画部 -
徐 開欽
-
 小林 拓朗資源循環領域
小林 拓朗資源循環領域 -
石垣 智基資源循環領域
-
 遠藤 和人福島地域協働研究拠点
遠藤 和人福島地域協働研究拠点 -
肴倉 宏史資源循環領域
-
山本 貴士資源循環領域
-
森岡 涼子
-
松神 秀徳資源循環領域
-
小島 英子
-
尾形 有香資源循環領域
-
落合 知
-
Hu Yong
-
高田 恭子
-
角谷 拓生物多様性領域
-
 山野 博哉生物多様性領域
山野 博哉生物多様性領域 -
 茶谷 聡地域環境保全領域
茶谷 聡地域環境保全領域 -
 中山 祥嗣環境リスク・健康領域
中山 祥嗣環境リスク・健康領域 -
磯部 友彦環境リスク・健康領域
-
 小林 弥生環境リスク・健康領域
小林 弥生環境リスク・健康領域 -
 松橋 啓介社会システム領域
松橋 啓介社会システム領域 -
藤井 実社会システム領域
-
西嶋 大輔
-
久保田 利恵子
-
伊藤 浩平
-
由井 和子
-
花岡 達也社会システム領域
-
 珠坪 一晃地域環境保全領域
珠坪 一晃地域環境保全領域 -
岡寺 智大地域環境保全領域
-
 小野寺 崇地域環境保全領域
小野寺 崇地域環境保全領域 -
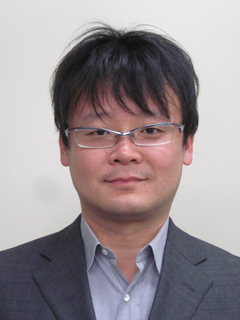 石森 洋行資源循環領域
石森 洋行資源循環領域


