第3回NIES国際フォーラム開催報告:持続可能なアジアの未来に向けて
【行事報告】
研究事業連携部門
国立環境研究所(以下、「NIES」という。)では、東京大学、アジア工科大学院(AIT)、及びアジアの様々な研究機関とともに、アジアの持続可能な未来に関して目指すべき方向についての議論を促進することを目的に、2015年度からNIES国際フォーラムを毎年度開催しています。また、この国際フォーラムを通じて、アジア地域の研究機関との研究ネットワークをさらに発展・充実させることも目指しています。
「第3回NIES国際フォーラム/3rd International Forum on Sustainable Future in Asia」は、2018年1月23日~24日にマレーシアの首都クアラルンプールにおいて、現地研究機関の研究者のほか政府関係者など、講演者も含めて約150名もの出席者を得て開催し、アジアの環境問題について多様な角度から発表と議論を行うことができました。

今、国際社会は、持続可能な社会の実現に向けた動きを加速しています。2015年3月に仙台防災枠組2015-2030(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)の採択、続いて9月に国連持続可能開発サミットで「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals, SDGs)」が採択されました。さらに11月にはCOP21でパリ協定(Paris Agreement)が合意されました。このように、持続可能な開発や気候変動問題を世界が一体として取り組む重要な課題として捉え、その解決への道を模索しています。
この一方で、私たちが住むアジアの状況は、人口増加とともに、急速な工業化、都市化の影響などから、様々な環境問題が起こっています。例えば、今回の開催国であるマレーシアを含む東南アジア地域は熱帯林を多く有し、生物多様性を維持するためにはその保全を進めることが重要です。しかし実際は、森林伐採などによる生物多様性の消失や、二酸化炭素排出の増加が進んでしまうなどさまざまな問題を抱えています。
これらを踏まえて、今回のフォーラムでは、アジア地域でも重要な課題である「気候変動の適応策と緩和策」、「生物多様性」そして「環境モニタリング」の3つのテーマを取り上げました。本稿では各セッションのまとめと、フォーラムの最後に提示した共同声明について報告します。


まず、主催機関、共催機関、開催国の研究機関の代表からそれぞれ開会の挨拶がありました。それぞれに今回のフォーラムの開会を祝すとともに、2日間で展開される議論への期待が添えられました。
続いて行われた基調講演では、マレーシア大統領科学顧問のZakri博士の講演に始まり、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)の住特任教授、マレーシア森林研究所(FRIM)のHarun副所長の3名の講演がありました。特に、Zakri博士の講演では、「マレーシアの持続可能な未来」を主題に様々な話題に触れながら、科学と政策をつないでいくことが、難しい側面はあるけれどもとても重要である点を強調しました。
セッション1の「気候変動の適応策と緩和策」では、昨今アジアでも増加している気候変動によるリスクへの対策として、適応策や緩和策について科学的知見に基づいて適切な行動を取っていくためにはどうすれば良いのか、そして適応策と緩和策の相乗効果を高めるにはどうすべきか、といった問いに迫りました。8人の講演者が気候変動の適応策や緩和策に関して多様な研究フィールド、異なる視点から研究成果を発表しました。発表と議論の中では科学者と政策決定者が緊密に連携することの重要性と、適応策と緩和策の連携もまた喫緊の課題であるということが強調されました。最後に、これらの課題解決が気候変動時代における社会の「転換」に不可欠だとされました。
続いて、セッション2の「生物多様性」では、SDGsの目標15を話題提供のきっかけとして、研究成果の発表と議論が行われました。目標15は「陸の豊かさも守ろう」に関する目標で、「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」という内容です。マレーシア含め近隣の熱帯諸国は世界的に見ても生物多様性が豊かでありながら、一方で急速な生物多様性の損失の危機に脅かされています。アジアの熱帯林の保全は目標15の達成に不可欠とも言えます。NIESは、FRIMとマレーシアプトラ大学(UPM)と1990年からパソの森林公園を拠点に共同して研究活動を行ってきました。その研究成果も含め、生物多様性の保全のためにこれまで発見されたことや、マレーシアの熱帯林で行なわれている生物多様性に関する様々な研究活動、そして生物多様性の損失の主な要因などが報告されました。セッションのまとめでは、この会議が目標15を達成するための国際的な協働の出発点となることへの強い期待を述べました。
最後にセッション3の「環境モニタリング-変わりゆく世界の熱帯生態系」では、熱帯生態系が二酸化炭素、メタン、二酸化窒素の収支と、その地球上での役割の重要性について着目した研究成果の報告が行われました。将来の人口増加など様々な要因があるなかで、二酸化炭素等の温室効果ガスの動態がどのように変化していくのかをモニタリングすることは、今後アジア地域で温室効果ガス排出削減目標とそのための緩和策の効果的実施や促進にあたってとても重要です。このセッションでは、観測、実験、モデル研究といった多角的なアプローチから様々な知見が紹介されるとともに、最後には熱帯生態系と気候変動、人口増加、緩和策と適応策の相互作用に関して最新の研究成果を共有するために、マレーシアと近隣の国々とのさらなる協働を進める重要性を強調しました。

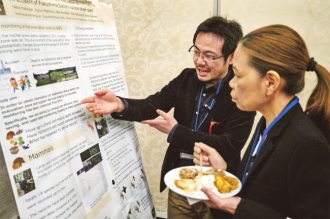
また、今回各セッションでの発表とは別に、ポスターセッションも行いました。ポスターはフォーラムの3セッションに関する内容に留まらない幅広い研究テーマについて、NIES及びマレーシアも含めた関連研究機関の成果について総勢24名によるポスター発表を行いました。また、短時間でのポスター内容紹介(フラッシュプレゼンテーション)も実施して、参加者との活発な議論が行われていました。
最後に今後の研究協働への期待を込めて、NIES、東大IR3S、AIT、UTM、及びFRIMがアジア太平洋域における今後の環境問題解決に向けた研究連携の強化し、議論を牽引していくべく共同声明を発表しました。声明の中では次の3つの点を強調しました。(1)気候変動問題においては適応策と緩和策両方を同時に充実することを目指すことが喫緊の解決策として考慮される必要がある、(2)アジアの研究機関のネットワーク強化と国際的かつ多様な分野や関係先をまたぐような研究プログラムによって連携を拡大する必要がある、そして(3)政府機関、市民団体、産業界と緊密に協働することが重要である、ということです。こうして、今後さらなる研究活動をネットワークを強固にしながら進めていく意思を示しました。
アジアの多くの参加者の方々と共に、アジアの持続可能な未来に向けた議論の場を持つことができました。登壇者、参加者の皆様のそれぞれの今後の活動の上で、新しいアイディアや課題解決に向けたさらなる行動につながっていくことを期待しています。
目次
- 統合研究の意義
- 世界及びアジアを対象とした持続可能シナリオの開発に関する研究
- 気候変動抑制の鍵は賢明な政策にあり!?(2018年度 37巻1号)
- 持続可能な開発目標への道筋
- 国際応用システム分析研究所での海外研修を通して
- AIM (Asia-Pacific Integrated Model) の開発を通じた人材育成
- 「第37回地方環境研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告
- 平成29年度の地方公共団体環境研究機関等と国立環境研究所との共同研究課題について
- 「第33回全国環境研究所交流シンポジウム」報告
- 国立研究開発法人国立環境研究所 公開シンポジウム2018『水から考える環境のこれから』開催のお知らせ
- 新刊紹介
- 表彰
- 木漏れ日便り
- 人事異動
- 編集後記


