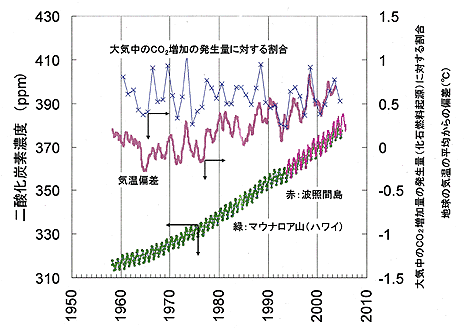温室効果ガスの長期的濃度変動メカニズムとその地域特性
【シリーズ重点研究プログラム:「地球温暖化研究プログラム」から】
向井 人史
地球温暖化に関しての長期的な見地からの研究プログラムが新たな中期計画の中で今年度から始まることが既に前号で紹介されている。この地球温暖化研究プログラムは,主に4つの中核研究プロジェクトからなっているが,ここではその中でも温室効果ガスの観測に関する中核研究プロジェクト1について紹介を行う。このプロジェクトは各種温室効果ガスの高精度観測を基にそれらの濃度変動メカニズムやその地域ごとの特性を明らかにしようとするものである。観測のプロジェクトはもう一つあり,衛星を用いた二酸化炭素等の観測が中核研究プロジェクト2として存在する。両者は密接に関連し,中核1のプロジェクトから衛星の観測に基礎データを提供して行くと言う構造になっているが,中核2の内容は今後順次紹介される予定であるので,ここでは,まず中核1プロジェクトに関する背景や内容を説明する。
これまでも温室効果ガスの観測は国立環境研究所で行われてきたが,その歴史はまだ浅く15年程度の観測実績があるに過ぎない。しかし,これからさらにその傾向が明らかになるであろう温暖化と言う現象の現れは,短い物でも50年程度の時間を考えなければならない。その際にどのように温室効果ガスの濃度が今後推移するのかという問題は非常に重要である。温室効果ガスの大気中濃度と気温の上昇は密接に関係していると考えられるので,いかにその濃度を安定化させるかということに問題解決の本質がある。
二酸化炭素の観測のパイオニアであるCharles Keelingはハワイのマウナロアにおいて1958年から観測を開始し,約50年にわたるデータを提供し,この研究に多大な貢献をしてきた。この間に,二酸化炭素の濃度変化が毎年一定でないことや,排出された二酸化炭素が自然界に吸収されていることなど数々の重要なことを明らかにしてきた。しかし,非常に残念なことに昨年6月20日に77歳の生涯を閉じた。TRENDSというデータベースには1958年3月の彼の二酸化炭素観測値が315.71ppmであったことが示されているが,現在の大気の二酸化炭素濃度はもうすでに380ppmを超えているので,約70ppmがここ50年間に増加してしまったことがわかる。その間に,人間活動による化石燃料消費やセメント生産による二酸化炭素発生量合計は,23億トン-炭素/年(1958年)から73億トン-炭素/年(2003年)に増加し,二酸化炭素の濃度増加を加速させてきたことになる。
これまでの国立環境研究所の温室効果ガスの観測研究は,発生した二酸化炭素の自然の吸収量の大きさを調べることに重きがおかれていた。発生した人為起源の二酸化炭素が,海洋や植物に吸収されていることはわかっていたが,どの程度の量が海洋に移動し,どの程度が陸上植物に吸収されているのかを定量化することが大きな課題であった。これは,京都議定書における,二酸化炭素の森林の吸収量を評価する際にも,こういった科学的知見が重要な意味を持つと考えられていたためでもある。その方法として,大気中の酸素濃度の変化を調べるという新しい方法に注目し,その測定法などを検討してきた(詳細は本号8頁からの記事を参照)。一方では,海洋や陸域でのその時々の二酸化炭素吸収量を高頻度で測定し年間の収支を求めたり,現場での炭素現存量を正確に測定することで,長期的な蓄積量から年間の吸収量をとらえようとする試みも行われてきた。そのため,北太平洋での船舶による観測や大きな吸収源であると考えられるシベリアなどでの調査も行ってきた。
本プロジェクトでは,これまで行ってきた観測研究に立脚しつつ観測範囲を広域化し,さらにターゲットである温室効果ガスの種類を拡大することを考えている。二酸化炭素の温室効果に占める割合は,直接発生する長寿命のガスの中で約半分であり,残り半分はメタン,フロン,亜酸化窒素などのガスが受け持っており,その動向にも注目しておく必要がある。また,オゾンやエアロゾルなども不確定性は大きいものの,その温室効果に対する寄与はむしろ大きく,その長期的変動を押さえておく必要があると考えている。
ここでの観測の主な着眼点は,気候変動と人為的な活動の変化による温室効果ガスの濃度変動やそれに絡む吸収量などのフラックスの変動の地域性を見ていくというところにある。温室効果ガスの内,二酸化炭素,メタン,亜酸化窒素などは生物界において炭素循環や窒素循環の一要素として,自然界を循環しており,その循環量は二酸化炭素を例にすると,人為起源の発生量よりも一桁多い量である。そのため自然の中での循環量の変化がこれらの大気の濃度の変動を大きく左右することが予想されている。例えば,エルニーニョの時に大気や海洋の変化が起こり,結果的に自然界の吸収量が減少し二酸化炭素濃度増加が大きくなることや,氷期と間氷期で二酸化炭素やメタン濃度の差があったことは,良く知られている話である。したがって,人為起源の発生量の増加のみならず,気候変動がこれらの物質の循環にどのように影響を与えるかを調査して行くことが,今後の濃度の予測を行う上で重要な知見となる。また,人間活動による自然改変に起因して温室効果ガスの発生量や物質収支が地域的に変化している可能性もある。例えば森林火災や過放牧などを含む自然改変などによる影響なども,その寄与量を長期的には押さえなければならない。しかも,重要な点は,これらの物質循環の応答は地域性がある点である。陸域でも海洋でも,地域ごとに物質循環は異なっており,地域ごとに気候応答特性を把握しなければならない。
フロンなどのフッ素系炭化水素,オゾン,エアロゾルなどの物質は,むしろ人間活動を含めた放出量の変化が大きく左右しており,地域的にその発生量の増加の方に気をつける必要がある。人工的に作られた代替フロンなどは,二酸化炭素よりも大きな温室効果を示すため,新たな成分が大気に蓄積していることにも注意を払わなくてならない。いずれにせよ,このような現在起こっている地域ごとの大気の状況や物質循環が,気候変化や人間活動に対してどのように応答しているのかを正確に記録しておくことが非常に重要な作業である。
本プロジェクトでは,このように温室効果ガスの発生や吸収,またその輸送現象を広く把握するために,今後大きな経済成長を遂げると見込まれるアジア-オセアニア域に着目し,これらの地域での大気,海洋,陸域の観測を展開する。観測をより広く行うために,沖縄や北海道にある観測所(波照間,落石)を利用するほか,太平洋を航行する民間の定期貨物船や定期航空路線を用いる。これらにより,グローバルな温室効果ガス分布の変化や濃度変化の緯度別傾向,二酸化炭素の陸域・海洋の発生吸収源の分離,温室効果ガスの収支の長期変動の原因,シベリアなどを含むアジア-オセアニアの地域的発生源の特徴などを解明する。その代表的方法として,酸素濃度や同位体(安定同位体や放射性同位体)濃度などの新たな指標成分の活用方法を検討し,大気中の温室効果ガス収支,またその変動を引き起こす人為的寄与や自然における変動メカニズムを長期的見地から明らかにしたい。
同時に地域的な物質循環の変動の特徴をとらえるために,陸域の二酸化炭素のフラックス観測をアジア地域で進める。この際には,植物の総光合成速度のあらたな観測法の開発や,土壌や,植物の各パーツの応答特性などにも着目していく。当面の観測は,富士北麓観測サイトや中国の草原,シベリアなどの場所で行う。また太平洋を中心とする海洋二酸化炭素フラックスの観測を充実させるために,北太平洋に加え西太平洋においても海洋と大気間の二酸化炭素分圧差を観測し,海洋への二酸化炭素吸収フラックスを求め,海域的分布や季節変化,年々変化という側面から環境因子との関係を調査する。
最終的には,ここで得られた結果が今後の温室効果ガスの濃度予測をより良く行えるようにするための布石になるように願っている。そのために,広域大気観測で得られたデータを基に,モデル計算を用いて地域的な温室効果ガスの発生量やその変化量を推定することを試みることも予定している。
執筆者プロフィール:
キーリングがハワイで測定データを出し始めた1958年は東京タワーの完成した年でもあるが,筆者の生まれた年でもある。有名な360ccの車や即席ラーメンが誕生した年でもある。そのころに戻れば,日本のCO2排出量は今の6分の1。増えた70ppmを何とかする方策を日夜考えている。