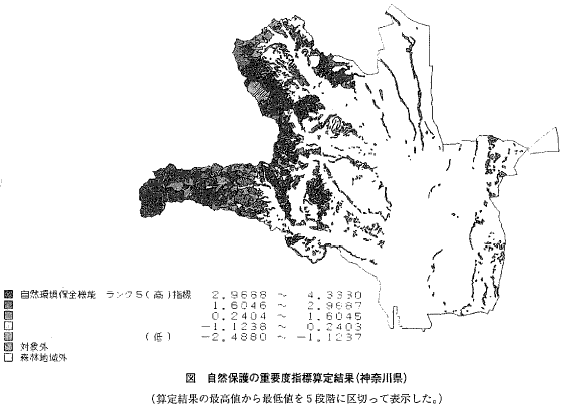自然保護指標の作成
研究ノート
青柳 みどり
いかにして「現在残っている自然環境を適正に維持管理していくか」を考えることは,我々環境研究者の使命の一つであろう。筆者らは神奈川県について「自然保護の指標」の作成を試みた。この指標の特徴は,以下の2点にある。
- 森林を中心に相対的に自然度の低い地域まで対象に含めて,“環境指標”の考え方と手法を取り入れた評価を行ったこと。
- 複数の自然保護専門家の知識を集約化して,評価項目ごとの評価関数を設定したこと。
個々の評価関数を総合したものを「自然保護の重要度指標」とし,以下の式を用いて算定した。
Y=V×H×E×S
ここで,Yは対象群落または林班(森林管理の単位)の自然保護重要度の評価値,V,H,E,Sは個々の評価関数で,Vは植生自然度評価値,Hは群落のまとまりの大きさ評価値,Eは特定生物相評価値,Sを土壌の回復困難度評価値である。それぞれは,専門家の一対比較法による重要度評価の判断から得た。神奈川県中部における算定結果を5段階表示した例を図に示す。この結果,面積の広い広葉樹代償植生の群落が高い評価を受けた。
この指標体系をより一般的に適用するためには次のような問題点が残されている。まず第一には,何物にもかえ難いとされた自然をどう評価に取り入れるのかという問題である。今回は当初から神奈川県を対象に調査を設計したので,比較的都市近郊の森林の評価になった。原生に近い森林などの場合に同様の調査で可能だろうか。第二には,算定にあたって,データの制約が大きいことである。将来的に比較可能なデータをどのように整備していくのか考えなければならない。
これからフィールドワークの積み重ねによるデータの積み重ねとともに,「自然をいかにうまく管理していくか」について効果的な方法が求められるであろう。
(あおやぎ みどり,総合解析部環境経済研究室)