波照間−地球環境モニタリングステーションにおけるエアロゾルとオゾンの測定
研究ノート
内山 政弘
「波照間ー地球環境モニタリングステーション」は八重山列島・西表島の南60kmに位置する日本最南端の有人島・波照間島の東端に設けられている。波照間ステーションの目的は北西太平洋の大気中の二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの長期変動の観測であるが,波照間島には中国大陸,フィリッピン,太平洋などから風が吹き込んで来る(図1)。そこで採取している大気サンプルが海洋性のものか否かの判別のためにトレサー物質の測定が必要となる。波照間ステーションではこのトレーサー物質として,1)海洋性気団では極端に濃度が低いことが知られているオゾン,2)海洋性エアロゾルが殆ど存在しない粒径0.5μm以下の粒子濃度の測定を行っている。実際には,波照間ステーションの観測塔の上端(海抜40m)から採取した大気中のオゾン濃度と粒子(0.3μm〜0.5μm)濃度を測定している。粒子濃度の最低値は0個/L最高値は30000個/Lであり,オゾン濃度の最低値は10ppb以下,最高値は80ppbであった。大気中のエアロゾルは陸地において産業活動(油燃焼など)に起因する粒子あるいは土壌粒子として大量に大気中に供給される。これらの粒子の濃度は波照間島まで海を渡って来る間に拡散により指数的に減少すると考えられる。粒子濃度の対数をオゾン濃度に対してプロットするとこれらの間に相関が認められた(図2)。このことはこれらの物質がいずれも陸地の影響のトレサーとして適当であることを示している。従って,粒子濃度とオゾン濃度が共に低いことは,波照間島が海洋性気団に覆われている良い指標になると考えられる。
(うちやま まさひろ,大気圏環境部大気動態研究室)
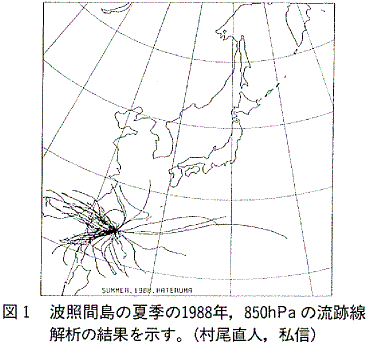
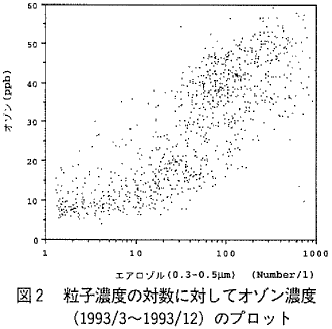
目次
- 有限地球観と地球科学
- 創立20周年記念式典を挙行
- 20周年記念特別研究発表会報告論評
- 海産円石藻による物質循環と凝結核形成省際基礎研究の紹介
- 地下水中における硝酸性窒素の起源に関する研究プロジェクト研究の紹介
- 故高橋弘氏を偲ぶ
- “Enhanced tolerance to photooxidative stress of transgenic Nicotiana tobacum with high chloroplastic glutathione reductase activity” Mitsuko Aono, Akihiro Kubo, Hikaru Saji, Kiyoshi Tanaka and Noriaki Kondo: Plant and Cell Physiology,34(1),129-135,(1993)論文紹介
- 自由連想法とクラスター分析による水辺に対する住民意識の研究論文紹介
- 新刊・近刊紹介
- 主要人事異動
- 編集後記


