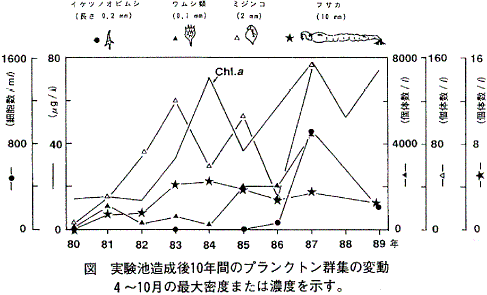実験池における富栄養化過程とプランクトン群集の相互作用について
経常研究の紹介
岩熊 敏夫
研究所構内の湿地を掘り下げて造られた実験池(面積約0.4ha、最大水深4.2m)の富栄養化の過程とそれに伴う生態系の変化を長期的に追跡している。造成後10年以上を経過し、生物相互作用についての新しい知見が得られたので報告する。この池は自然湖沼と比較して、地形的に単純で水質や生物の代表地点を選びやすい、水収支や負荷量を把握しやすいなどの調査上の利点がある。隣接する実験水路を通して地下水が流入し(滞留時間は約2か月半)、リンの年負荷量は霞ヶ浦や湯の湖等の富栄養湖の約2倍にも相当する。
実験池の主要なプランクトンは以下のとおりである。光合成を行う生物すなわち一次生産者では、ケイ藻のほかに渦大型のベン毛藻類のイケツノオビムシ(Ceratium)、一次生産者を直接食べる二次生産者では小型のワムシ類と大型のミジンコ(Daphnia)、そしてこれらの二次生産者を待ち伏せして捕食するフサカ幼虫(Chaoborus、昆虫)。魚類を放流していないため、フサカ幼虫が食物連鎖の最上位に位置している。
1980年の造成後1983年までは、池の富栄養化が進行するに伴い、動植物プランクトンの量が増加した。クロロフィルa濃度、大型のミジンコの個体数、フサカ幼虫の個体数のいずれもが上昇している。1984年以後は最大クロロフィルa濃度は70μg/l以上までに増加した。この時期にはプランクトン群集に質的な変化が見られ、植物プランクトンでは渦ベン毛藻のイケツノオビムシが優占し、春季〜夏季に大発生するようになり、動物プランクトンでは小型のワムシ類が増加した(図)。
フサカは餌として動物プランクトン、特に大型のミジンコを好むとされていたが、この池ではベン毛藻類の大発生時にはそれを餌にしていることが分かった。近年、フサカなどの無せきつい動物の捕食者の水界生態系における役割が注目を集めている。フサカの増加は、大型動物プランクトンの選択的除去→小型藻類の増加と競争する小型動物プランクトンの増加という波及効果をもたらすことがこれまでに報告されている。しかしながらフサカが餌を藻類に切り替えられることはあまり知られていなかった。この実験池の場合には、ベン毛藻類の抑制→競争する小型藻類の増加→大型動物プランクトンの増加という波及効果が、餌の切り換えによってもたらされる可能性がある。
捕食者が食物連鎖網の栄養段階のすぐ下の生物だけでなく、2段階下の生物も食べることが生物群集の安定化に寄与しているかどうかは、今後、実験的に解明される必要がある。一方で、大型動物プランクトンではなく小型動物プランクトンやベン毛藻類を餌にしている時期にはフサカの成長速度が低下する傾向も観察されており、餌の質が個体群に及ぼす影響も検討していく必要がある。