好酸球とぜん息
研究ノート
河越 昭子
近年、アレルギーの症状を訴える人が増えている。ぜん息発症の約2/3にもなんらかのアレルギー学的機序の関与が推定されている。このアレルギーは、元々は寄生虫に対して作っていた特異的分子(抗体)を花粉やダニなどの体の中に入ってきた異物(抗原)に対して作ってしまったことによって起こる。その抗体が付着した肥満細胞と呼ばれる細胞を抗原が刺激すると肥満細胞から様々な物質が放出されてアレルギーの諸症状が現われるのである。
好酸球は肥満細胞と同じ抗体を付着して寄生虫を排除するの機能を持つ細胞である。図に示すように、クリスタル状の核を持つ顆粒が酸性染色液でよく染まるために好酸球と呼ばれる。好酸球は健康人の血中にはわずかしか存在しないが、寄生虫感染やアレルギー性疾患が起きると増加する。ぜん息患者では特に気管や肺に好酸球が増加するので、気管や肺の洗浄液中の好酸球を調べることがぜん息の診断に用いられている。ここで紹介するのは、大気汚染物質とぜん息との関連を検討するために大気汚染物質を暴露して好酸球の動態を検討した結果である。
グラフは、ハートレイ系雄性モルモットに硫酸ミストを暴露した実験における好酸球の動態についてのデータである。3.2mg/m3の硫酸ミストを14日暴露したところ、モルモットの気管粘膜では好酸球は清浄空気群の約4倍に増加した。同時に粘液を持つ細胞数と粘液分泌の増加などのぜん息様の形態的変化が認められた。また好酸球が集積した部位で周囲の細胞の傷害が認められた。
このように、好酸球は気道の細胞に対する傷害能を持つほかに、気道を狭める物質を産生することが知られている。このことは好酸球がぜん息や気道アレルギーの発症とその悪化に関与する可能性を示すものである。一方、好酸球には肥満細胞が放出するアレルギー症状を起こす物質の作用を中和する幾つかの酵素が存在することから、好酸球がアレルギー反応を鎮静化する役割を持つことも考えられている。このように、両面の作用を持つ好酸球の機能の解明はぜん息やアレルギーの克服に結びつくに違いない。
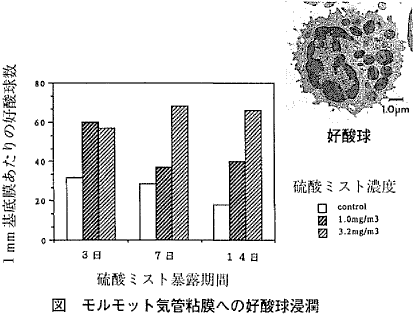
目次
- 改組後1年巻頭言
- 大気汚染研究の新たな展開論評
- 海野英明氏を悼むその他
- 国立環境研究所における海洋研究プロジェクト研究の紹介
- 実市街地を対象とした自動車排気ガスの拡散予測〜「広域都市圏における交通公害防止計画策定のための環境総合評価手法に関する研究」から〜プロジェクト研究の紹介
- 「大気化学国際協同研究計画/東アジア・北太平洋地域研究(IGAC/APARE)計画会議(第2回)」の開催その他の報告
- ザンビアにおける家畜と野生動物との関係経常研究の紹介
- 手軽で簡便な地盤沈下観測システム経常研究の紹介
- 東京都心商業地(銀座周辺)の環境研究ノート
- ADEOS衛星搭載RISの光学的設計研究ノート
- メーヌ大学音響研究所にて海外からのたより
- アジア太平洋地域における地球温暖化問題に関する研究ワークショップ報告その他の報告
- 環境週間についてその他
- 新刊・近刊紹介
- 表彰
- 編集後記


