ADEOS衛星搭載RISの光学的設計
研究ノート
湊 淳
宇宙開発事業団で1995年に打ち上げられるADEOS衛星に、環境庁が提案し採用されたセンサーの一つとしてRIS(Retroreflector In-Space)が搭載される。RISは、レーザーを用いた地上と衛星間の長光路吸収の測定を目的とした新形状の空洞型キューブコーナーリフレクターで、オゾン層破壊や地球温暖化に関係する大気微量分子の高精度の測定が期待されている。RISを用いた観測に関する研究開発は地球環境研究グループオゾン層研究チームで行われているが、筆者はRISの光学的設計に携わってきた。
空洞型キューブコーナーリフレクターは、平面鏡を3枚直角に張り合わせたもので、どの方向から入射した光も入射方向に正確に反射させる性質を持つため長光路吸収測定で広く利用されている。ところが衛星が高速(約7km/s)で移動している場合、光行差という現象により反射光の方向がわずかにずれてしまう。RISの場合は、地上で約50m反射光の位置がずれることになる。この現象は、相対性理論の中のローレンツ変換により説明できる。そこで、RISでは3枚の鏡のうち1枚にわずかな曲率を付けた鏡面形状のリフレクターを新しく考案して用いる。1面に曲率をもたせることにより、反射光が衛星の進行方向に広がり地上局で反射光を受信することが可能となる(図)。
反射光の計算機シミュレーションにより最適な鏡面形状のを決定した。計算機内に曲面リフレクターのモデルを入力し、平面波が入射した場合の反射光の波面を計算し、これをホイヘンスの原理によって地上まで伝搬したときの光の強度分布を計算し評価した。新形状リフレクターを使用することにより地上局において十分な反射光が受信され、光行差がある場合の測定が可能となった。
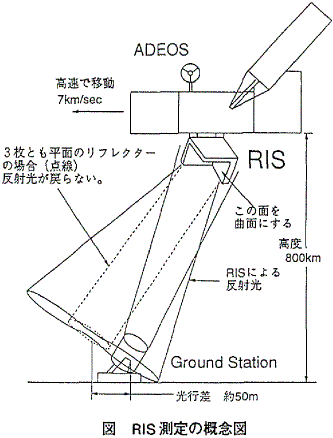
目次
- 改組後1年巻頭言
- 大気汚染研究の新たな展開論評
- 海野英明氏を悼むその他
- 国立環境研究所における海洋研究プロジェクト研究の紹介
- 実市街地を対象とした自動車排気ガスの拡散予測〜「広域都市圏における交通公害防止計画策定のための環境総合評価手法に関する研究」から〜プロジェクト研究の紹介
- 「大気化学国際協同研究計画/東アジア・北太平洋地域研究(IGAC/APARE)計画会議(第2回)」の開催その他の報告
- ザンビアにおける家畜と野生動物との関係経常研究の紹介
- 手軽で簡便な地盤沈下観測システム経常研究の紹介
- 東京都心商業地(銀座周辺)の環境研究ノート
- 好酸球とぜん息研究ノート
- メーヌ大学音響研究所にて海外からのたより
- アジア太平洋地域における地球温暖化問題に関する研究ワークショップ報告その他の報告
- 環境週間についてその他
- 新刊・近刊紹介
- 表彰
- 編集後記


