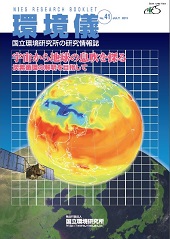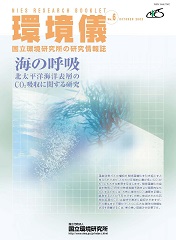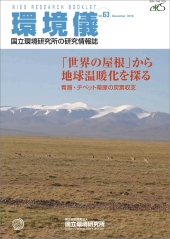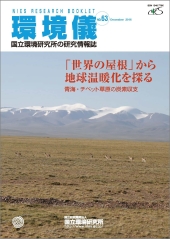2016年12月28日
過去の環境儀から
これまでの環境儀から、炭素収支や炭素循環に関するものを紹介します。
No.51 旅客機を使って大気を測る
─国際線で世界をカバー
現在、日本航空(JAL)が運航する8機の国際線定期旅客便を使って大気中の二酸化炭素(CO2)濃度の全球的な観測が実施されています。このように民間の旅客機でCO2濃度を常時測定する計画は世界で初めてであり、地球上のCO2の循環を理解する上で貴重なデータが毎日のように得られています。本号では、国立環境研究所が気象研究所などと共同で行っている、国際線定期旅客便を使った温室効果ガスの観測プロジェクト(CONTRAILプロジェクト)の取組みを中心に紹介しています。
NO.41 宇宙から地球の息吹を探る
─炭素循環の解明を目指して
環境省、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構は、共同で衛星GOSAT(愛称「いぶき」)を打ち上げ、二酸化炭素など大気中の温室効果ガスを宇宙から観測しています。本号では、国立環境研究所がGOSATプロジェクトにどのように貢献してきたかを紹介しています。
NO.28 森の息づかいを測る
─森林生態系のCO2フラックス観測研究
地球温暖化問題に取り組むうえで、地球レベルの炭素循環の理解は不可欠です。本号では、これまで継続的に観測することが難しかった森林全体のCO2吸収・放出量の観測に取り組んだ「森林生態系炭素収支モニタリング」プロジェクトを紹介しています。
NO.6 海の呼吸
─北太平洋海洋表層のCO2吸収に関する研究
海洋の炭素循環を明らかにしようとするとき、広大な海洋をどのように観測するかが最初に突き当たる課題です。国立環境研究所では、貨物船を使って北太平洋でのCO2測定を行いました。本号では、その測定の実際と、延べ38往復の航海などにより取得した豊富なデータの解析から得られた成果を紹介しています。
目次
関連記事
表示する記事はありません