河床付着生物膜による栄養塩の一時貯留・変換機能
研究ノート
井上 隆信
人為的な汚濁が進行していない河川では,複雑な生態系が維持されている。その構成要素の一つとして,水深の浅い河床の礫上に形成される河床付着生物膜が存在する。この生物膜はケイ藻や緑藻類等の藻類が中心であり,一次生産者として川魚や底生動物等の餌となり,河川生態系を維持する源となっている。
河床付着生物膜の働きを定量的に評価することを目的として,茨城県涸沼川でのフィールド調査を中心とした研究を1987年より進めてきた。その結果,大きな流量変動が頻繁に生じる河川では,河床にまで光が届く流量安定時の増殖とともに,降雨に伴う流量増大時の剥離流出が,生物膜の現存量変化に大きな影響を与えることを明らかにした。富栄養化の要因物質である窒素・リンの栄養塩に着目すると,生物膜は流量安定時の増殖によって取り込んだ栄養塩を流量増大時に剥離流出するまでの間一時貯留する機能と,溶存態から懸濁態へ栄養塩を変換させる機能を有している。また,調査結果を基に作成した河床付着生物膜の現存量変化モデル式を用いたシミュレーションの結果では,生物膜による流量安定時の溶存態リンの削減効果が大きいことが明らかとなった(図)。流量増大時には土やシルト等の懸濁物質も多量に流出するため,剥離流出した生物膜は,下流域の湖沼・内湾などの閉鎖性水域に流入後,この懸濁物質とともに沈殿し底質となる。底層が貧酸素とならない水域では底質からのリンの溶出は少なく,生物膜として流入したリンは水系の物質循環から外れる。このように,河床付着生物膜は,河川から閉鎖性水域への栄養塩の供給時期と供給形態に関しても重要な役割を果たしている。
上流の山地から下流の閉鎖性水域まで,豊かな水系を維持するための機能を生態系は有していると考えられる。豊かな水系を取り戻すためには,このような生態系を回復させる必要がある。そのためにも,生態系の有する機能を一つずつ定量的に明らかにしていくことは重要であろう。
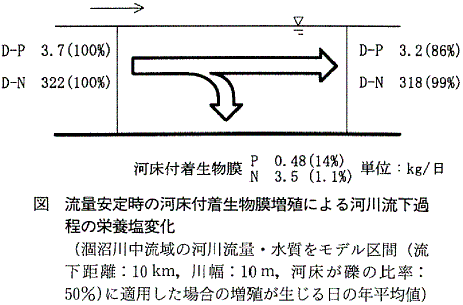
目次
- 新しい課題(地球環境変化)に対応するために巻頭言
- 退任に際して − 基礎研究のすすめ −
- 研究生活を振り返って
- 環境負荷の構造変化から見た都市の水質問題の把握とその対応策に関する研究プロジェクト研究の紹介
- 微小試料中の元素の存在量および同位体比の精密測定法の開発と応用省際基礎研究の紹介
- "Thermal decomposition of tetrachloroethylene" Akio Yasuhara Chemosphere, 26, 1507-1512 (1993)論文紹介
- "Dynamics and energy balance of the Hadleycirculation and the tropical precipitation zones: Significance of the distribution of evaporation." Atusi Numaguti:Journal Atmospheric Science, 50, 1874-1887.(1993)論文紹介
- 森林の小さな生物の消長 − 倒木上の植生遷移 −研究ノート
- 国際環境協力への期待 −タイ環境研究研修センターにおける経験−ネットワーク
- 新刊・近刊紹介
- 編集後記


