森林の小さな生物の消長 − 倒木上の植生遷移 −
研究ノート
清水 英幸
苔むす鬱蒼とした森林の中で,悠久の時の流れを感じることがある。しかし,森が現在の状態になるのにどれほどの時間を要したか? また,遷移の過渡期なのか極相なのか?生物と環境に関する研究の中で,遷移に関する研究は時間的制約や再現性などから最も困難な課題の一つであろう。1987年,奥日光環境観測所が建設され,気象,大気などの環境の長期モニタリングが開始された。我々はこの機会に,伐採されたばかりの生きの良いミズナラなど5種の樹木の幹を,周辺の落葉広葉樹林,常緑針葉樹林,カラマツ植林や河辺など,10地点に設置した。そして,調査区画を設定し,倒木上の植生の遷移過程と環境に関する長期的な調査研究を,分類学・生態学の研究者と共同で始めた。
これまでに得た結果の一部を以下に示す (図1,2参照)。(1)伐採前の樹木の幹には,ニセウチキウメノキゴケ (Myelochroa irrugans) などの地衣類や,ビロウドゴケ (Pylaisiella intricata),カラヤスデゴケ (Frullania muscicola) などの蘚苔類が着生していたが,これらは一部の地点を除き,伐採後1年以内に衰退もしくは枯死した。(2)倒木設置後1年半頃から,コモチイトゴケ (Pylaisiadelpha tenuirostris) などの蘚苔類が一時的に増加したが,その後,ハネヒツジゴケ (Brachythecium plumosum),アオギヌゴケ (Brachythecium populeum) などが優占してきた (図1)。さらに現在では,コツボゴケ (Plagiomnium acutum) など本地域の倒木上の極相的な種が出現している。(3)倒木の種や設置地点により,出現植物の種類や量は著しく異なった。ミズナラやハルニレの倒木では遷移が速く,カラマツでは比較的遅かった。伐採により日照条件が良くなった地点では,蘚苔類の代わりにカワラタケ (Coriolus versicolor) などの菌類や,トゲカワホリゴケ (Collema subflaccidum) などの地衣類が出現した。また,比較的暗く下層植生に蘚苔類が多い常緑針葉樹林の地点では遷移が遅かった (図2)。このような植生遷移の差異には光や温湿度,倒木腐朽度など微環境の影響が重要であると思われるが,現在解析中である。
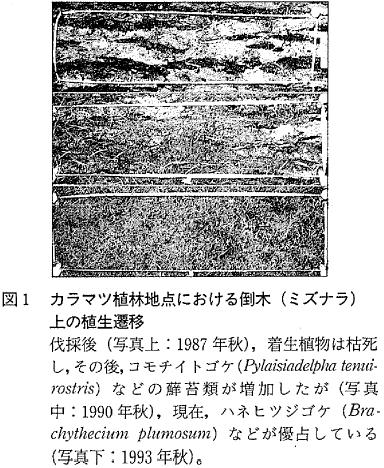
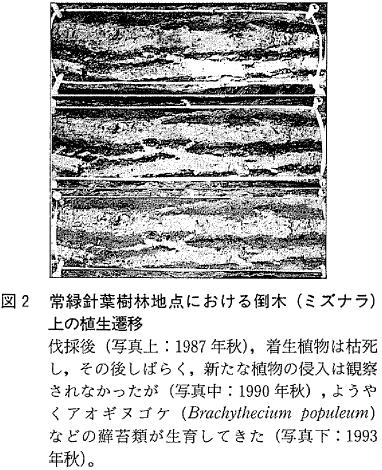
本調査から我々は多くの知見を得たが,倒木上における蘚苔類植生の遷移の進行が,地点によってはかなり速いことなど,文献の知識や経験などからたてた予想と異なる結果もいくつかあった。我々がいかに自然を把握していないかを思い知ることともなった。倒木上の植生調査と微環境計測に関しては長期的視野で研究を継続すると共に,今後,野外での蘚苔類の生理活性の計測や,環境制御室で生長と環境要因との関係検討なども行い,森林生態系における植生の遷移と環境に関して総合的に研究を進める予定である。
酸性雨や地球温暖化などが問題となっている現在,大気成分を含めた環境を継続計測している比較的人為影響の少ない奥日光地域は,生物と環境のモニタリング基地として貴重であり,多くの研究者の利用が期待される。現在,植物相や動物相の調査も行っているが,近未来に環境悪化などによって,森の生物種に顕著な変化が起こらないことを望んでいる。
目次
- 新しい課題(地球環境変化)に対応するために巻頭言
- 退任に際して − 基礎研究のすすめ −
- 研究生活を振り返って
- 環境負荷の構造変化から見た都市の水質問題の把握とその対応策に関する研究プロジェクト研究の紹介
- 微小試料中の元素の存在量および同位体比の精密測定法の開発と応用省際基礎研究の紹介
- "Thermal decomposition of tetrachloroethylene" Akio Yasuhara Chemosphere, 26, 1507-1512 (1993)論文紹介
- "Dynamics and energy balance of the Hadleycirculation and the tropical precipitation zones: Significance of the distribution of evaporation." Atusi Numaguti:Journal Atmospheric Science, 50, 1874-1887.(1993)論文紹介
- 河床付着生物膜による栄養塩の一時貯留・変換機能研究ノート
- 国際環境協力への期待 −タイ環境研究研修センターにおける経験−ネットワーク
- 新刊・近刊紹介
- 編集後記


