ヒ素の化学形態と生物影響ならびに環境動態
論文紹介
柴田 康行
1) "Selenium and Arsenic in Biology: Their Chemical Forms and Biological Functions" Y. Shibata, M. Morita & K. Fuwa, Adv. Biophys., 28, 31-80 (1992)
2) "Arsenic and Organoarsenicals" Y. Shibata and M. Morita, in "Analysis of Contaminants in Edible Aquatic Resources", J.W. Kiceniuk & S. Ray, eds., VCH Publ., New york, 159-173 (1994)
海の生物は,周囲の海水と比較して3〜4桁,あるいはそれ以上の濃度のヒ素を体内に蓄積している。ヒ素は毒性の高い元素で,水道水や環境水質基準の規制対象にもなっているが,日本人の食生活では,魚や海藻など海洋生物由来の食品を経由したヒ素の取り込み量が多い。したがって,海洋生物中のヒ素が毒性の高い形で存在しているのかどうかは,人の健康影響を考える上で極めて重要な意味を持つ。また,人為的なヒ素汚染が起こった場合の健康影響を考える上で,ヒ素の生態中/環境中の動態(循環,生物濃縮,化学/生物変換など)に関する知見は欠かせない。上記の二つの総説は,筆者らが数年間にわたって行った海洋生物中ヒ素の化学形態に関する研究成果を集約したものである。
図1にいくつかのヒ素化合物について,実験動物における半数致死量を対数スケールで示した。このように,毒性はヒ素化合物の化学的な構造(化学形態)によって大きく異なっている。また,ヒ素の化学的な反応性や生物への吸収,代謝等も化学形態によって異なる。すなわち,ヒ素の環境動態を解明し,健康影響評価を行うためには,化学形態を明らかにした上で定量を行う,いわゆる化学形態分析が必要である。筆者らはそのための分析方法として,高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と高感度元素分析装置であるICP質量分析装置を結合したHPLC−ICP/MSを開発し,一方で海洋生物から新たなヒ素化合物を単離,精製,構造決定して,同定のための標品を増やす作業を行って,合せて15種類の有機,無機ヒ素化合物の同定,定量法を確立した。そして,この化学形態分析法を用いて,様々な海の動植物のヒ素の分析を行った。図2にこれまで海洋生物から見つかり標品としたヒ素化合物の化学構造を示す。これらのヒ素化合物の多くはイオン性のもので,その分離にはイオン交換クロマトグラフィーが有効である。しかしながら,真空装置であるICP/MSに高い濃度の塩溶液を連続して導入することが困難なため,通常の陽イオン,陰イオン交換樹脂のシステムではうまくいかず,新たな分離方法の確立が重要なポイントになる。本研究では,イオン対クロマトグラフィーと呼ばれる手法で良い分離条件を確立できたことが突破口となり,多くのヒ素化合物を確実に分離・同定・定量できるシステムを確立することができた。
これまでの研究の結果,次第に明らかになってきた海洋生態系におけるヒ素の化学形態の分布をまとめれば,「豊かな多様性と規則性」とでも言えるのではないかと思う。海藻には,ヒ素糖(図2X〜XV)と総称される複雑な一連の有機ヒ素化合物が,生物種の分類に従って規則的に含まれている様子が明らかになってきた。例えば,X,XIはすべての種類に存在する一方,XIIは褐藻のみに,しかも主要成分の一つとして認められる。また,ワカメの脂溶性ヒ素化合物は,このヒ素糖の一つ(XI)の末端のグリセリン基に脂肪酸がついたヒ素脂質であることも明らかになった。一方,動物はいずれもアルセノベタイン(VIII)と呼ばれる有機ヒ素化合物を普遍的に,主成分として有していることが明らかになってきた。アルセノベタインは海藻にはいまだ見つかっていない。また,ムラサキイガイやカキ,ハマグリ等の二枚貝には,アルセノベタインのほかに海藻に含まれるのと同じヒ素糖の仲間が主成分として含まれていること,また特に大型のハマグリにテトラメチルアルソニウムイオン(VI)が多いことも明らかになった。
魚介類からこれまで見つかったヒ素化合物の大部分は,化学的には4級アルキルヒ素と呼ばれる構造をとっている。この形は一般に化学的に安定であり,またアルセノベタインに代表されるように強い毒性を示さない場合が多い。一方,海藻のヒ素(ヒ素糖)は主に3級アルキルアルシンオキサイド型の化学構造をとっている。この化合物はpH4付近で解離し,また還元的条件下では容易に還元されて反応性の高い3級アルキルアルシンに変化するなど,化学的に活性の高い構造である。予備的な検査の結果では,これらヒ素糖化合物に強い変異原性は認められなかったが,今後丁寧な毒性評価が必要であろう。一方,魚介類のアルセノベタインについては,餌経由で吸収,蓄積された2次的なものと考えられ,何が本当の生産者か,またこれが海水中ヒ素濃度を直接反映するかどうかも分かっていない。さらに,特定の種,あるいは特定の季節にのみ毒性上問題となる無機ヒ素(ヒ酸)が認められたようなケースも見つかっている。
人為的な汚染の影響やその早期発見のための分析指標を明らかにするためには,海洋生態系の食物連鎖を通じたヒ素の蓄積,変換の過程をていねいに追っていくことが結局は早道と考えられ,今後もこうした観点からの研究を継続していきたいと考えている。
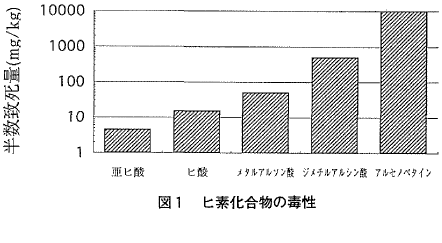
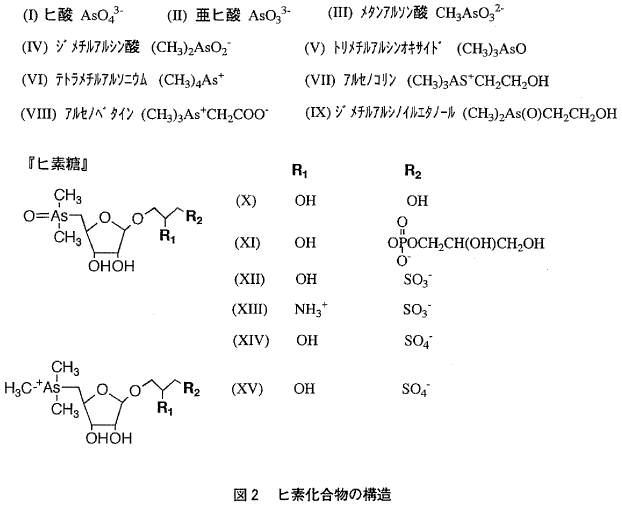
執筆者プロフィール:
東京大学理学部生物化学科卒業,理学博士
〈専門〉環境化学,生物無機化学。化学形態分析,同位体分析,局所分析を通じた,元素の環境動態の追跡
〈趣味〉音楽鑑賞,古本屋巡り


