“Pulmonary Clearance and Toxicity of Intratracheally Instilled Cupric Oxidein Rats.”Seishiro Hirano, Hisae Ebihara, Soichi Sakai, Naomi Kodama andKazuo T. Suzuki:Archives of Toxicology, 67, 312-317 (1993)
論文紹介
平野 靖史郎
大人が1日に呼吸する空気の体積は約15〜20m3,重量にすると約18〜24kgにもなる。1日の飲食量が数kgであることを考え合わせれば,汚染された空気を呼吸することにより肺が受ける負荷が,いかに大きいものであるかが分かる。一例を挙げると,タバコを20本喫煙することにより約1.5μg のカドミウムが肺より吸収され,喫煙者の血中カドミウム濃度は非喫煙者の約2倍,妊婦の羊水中では約3倍であったとの報告がある。このことは,高濃度のカドミウムに汚染された地域の住民を除けば,喫煙者はカドミウムの多くを肺より摂取していることを意味する。
我々の研究グループでは,過去6年間,経気道的に暴露した重金属の肺からの消失過程と毒性に関する研究を行ってきている。ここに紹介する論文はその一環であり,主として精錬や化石燃料の燃焼に伴って大気中に放出されると考えられている酸化銅のラット肺における代謝と,肺胞腔に逸脱してくる酵素などを指標とした毒性評価に関する報告である。
銅換算で50μgの酸化銅をエーテル麻酔下のラットの気管内に投与した。肺における酸化銅の半減期を肺の銅含量の経時変化より算出したところ,37時間と推定された。一方,水溶性の銅化合物である硫酸銅のラット肺における半減期は7.5時間であった。気管支肺胞洗浄液(肺に生理食塩水を注入し,肺胞腔を洗った後回収した液のことで,様々な生体構成成分や細胞が含まれている)中の銅濃度を可溶性画分と細胞性画分に分けて測定したところ,試験管内では不溶性の酸化銅も肺胞腔内では徐々に溶解していることが明らかとなった。
ところで,銅はカドミウムや水銀と同様,生体内で重金属の解毒に関与すると考えられているメタロチオネインというタンパクを誘導することが知られている。図に示したように,酸化銅を投与したラットの肺組織では,投与1〜2日後をピークとして銅を結合したメタロチオネインの生成が認められ,また,肺の銅−メタロチオネイン濃度は用量依存的に上昇した。しかし,肺のメタロチオネイン濃度がピークとなる投与2日後には,気管支肺胞洗浄液中の銅濃度は対照値に比べ有意に高かったものの,肺組織中の銅濃度は対照値に比べむしろ低下していた。したがって,肺における銅の代謝解毒過程において,メタロチオネインの役割は小さいものと考えられる。
次に,肺に沈着した酸化銅の急性毒性を評価するため,気管支肺胞洗浄液中のタンパク量,酵素活性や白血球数などを測定した。これらの炎症指標は,いずれも投与1〜3日後をピークとして上昇し,その後対照値へと戻った。また,これらの指標は,用量依存的に上昇する傾向を示した。
気管支肺胞洗滌液中の炎症指標の中でも,銅の用量に対して特に高い相関関係を認めた乳酸脱水素酵素,タンパク量などを毒性の指標として,酸化銅と硫酸銅のラット肺に及ぼす影響を比較した。しかし,用いる指標により酸化銅と硫酸銅の影響の順序が異なっており,肺における急性毒性に関する限りでは,酸化銅と硫酸銅との間に有意な差異はないものと結論した。
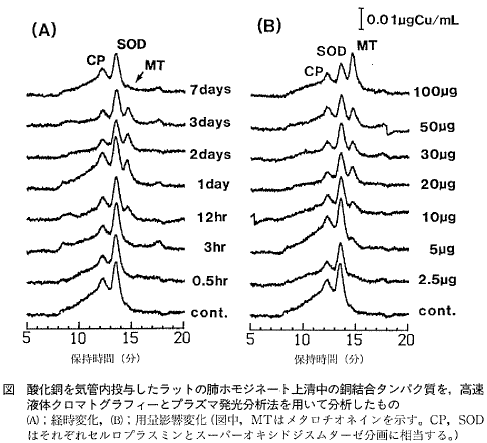
目次
- 環境研究への期待
- 新任にあたって論評
- バイカル湖と霞ヶ浦論評
- “酸性雨”に関する最近の研究プロジェクト研究の紹介
- 有害廃棄物の処理に伴うリスクの評価プロジェクト研究の紹介
- “Vertical profiles of temperature and ozone observed during DYANA Campaignwith NIES ozone lidar system at Tsukuba”Hideaki Nakane, Sachiko Hayashida, Yasuhiro Sasano, Nobuo Sugimoto,Ichiro Matsui and Atsushi Minato:Journal of Geomagnetism and Geoelectricity, 44, 1071-1083 (1992)論文紹介
- 特別研究ワークショップ「ディーゼル排気微粒子(DEP)の生体影響」ネットワーク
- 国際シンポジウム「生物多様性−その複雑性と役割」
- 新刊・近刊紹介
- 主要人事異動
- 編集後記


