微笑みの国・タイから − 森林の生活・砂漠の生活 −
海外からのたより
恒川 篤史
昨年9月より,JICA専門家としてGRID(Glonal Resource Information Database)−バンコクに派遣されている。ここに来るときには,ひょっとして現地で手に入らないかもしれないと思い,磁気テープやフロッピィディスクを山のように携えてきたものだった。今となっては笑い話だが,私にとってタイ国のイメージとはそのようなものだった。
ここでの主な仕事は,インドにおける砂漠化データベースの開発である。ラジャスタン州を対象として,人口,土地利用などの社会経済的データ,気候,土壌などの自然的データ,そして植生荒廃,土壌荒廃からなる砂漠化データを地理情報システムを用いてデータベース化している。
先週は祝日が続いたので,クリスチャンのミッションにジョインして,1週間ほどタイの東北部に行ってきた。カレン族の部落に寝泊まりしながら,衛生的な飲み水の確保や排水システムの改善などのお手伝いをしてきた。
砂漠化地域を見慣れているせいか,私にとってタイの農村部の生活は随分と新鮮に思えた。何よりも水が豊富にある。今年の2月に訪れたケニアのツーゲン族の「乾いた生活」とタイのカレン族の「湿った生活」が対照的に感じられた。
ケニアのツーゲン族の部落では,水場は16kmも離れたところにあった。1週間に一度,背中に水筒をかついで水を汲みにいく。1日がかりの重労働だ。水は飲んだり,食事に使い,洗濯や水浴には使わない。
タイのカレン族の部落では,泉から水がひかれていて,十分とはいえないながらも飲み水がある。洗濯や水浴は近くの小川に行く。小川といっても,流れはチョボチョボ程度で,しかも濁った水だった。私もはじめはこのような水で水浴するのはいやだと思ったが,慣れてしまえばまったく気にならなかった。
雨が豊富に降れば植物はよく育つ。植物の成長は人々の生活を豊かにする。たとえば食生活。カレン族の畑では米やトウモロコシがとれ,山にはバナナやパパイヤが植えられている。食生活は豊かといってよい。一方,ツーゲン族の主な食糧は,家畜の肉と血とミルクである。野菜はほとんどとらない。
家の広さも違う。カレン族の家は平均したら80m2くらいだろうか。素材は竹などの植物材料がふんだんに使われている。家の中は壁によっていくつかの部屋に区切られている。一方,ツーゲン族の家は広さ30m2くらい。ふつうは1室で,そのなかに数人が暮らしている。
燃料は両部落とも薪炭材に頼っているが,その使用量にも大きな差がある。
人々の生活が,食べ物や,家,エネルギーから労働にいたるまで自然環境から強い制約を受けているように思えて興味深かった。
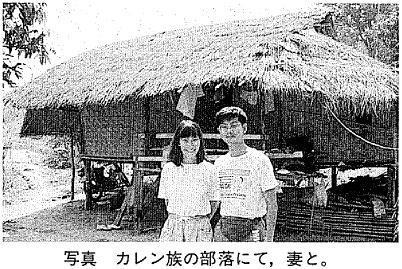
目次
- 天の目と人の目巻頭言
- 健康影響評価研究に思うこと論評
- 光化学スモッグ,そして地球環境 − 公害研・環境研での18年 −論評
- 有用微生物を活用した小規模排水処理技術の開発と高度化に関する研究プロジェクト研究の紹介
- オゾン層破壊に関与する光化学反応の解明に関する研究 − 光化学反応の実験的解明 −プロジェクト研究の紹介
- “Effects of coexisting linear alkylbenzenesulfonates on migration behavior of trichloroethylene in porous media” Kazuho Inaba and Tatemasa Hirata, Environmental Technology,13,259-265 (1992)論文紹介
-
“Mast cell response to formaldehyde 1.Modulation of mediator release” Hidekazu Fujimaki, Akiko Kawagoe, Elyse Bissonnette, Dean Befus:Internati-onal Archives of Allergy and Immunology,98,324-331(1992)
“Mast cell response to formaldehyde 2.Induction of stress-like proteins” Hidekazu Fujimaki, Toru Imai, Dean Befus:International Archives of Allergy and Immunology,98,332-338(1992)論文紹介 - 知られざる湿原ネットワーク
- 環境研修センター設立20周年記念式典その他の報告
- 表彰・主要人事異動
- 編集後記


