標高1656mの研究学園都市
海外からのたより
天野 耕二 林田佐智子
昨年9月から家族3人で米国コロラド州ボウルダーに来ています。
天野はコロラド大学の土木・環境・建築工学部に附属する水資源・環境政策支援システム研究センター(CADSWES)で河川流域管理システムに関する研究を行っています。ホストのスティーブ・チャプラ教授は水質予測モデリングの分野で活躍中です。1988年に設立されたCADSWESでは,オブジェクト指向プログラミングという計算機手法を活用した水資源管理システムや環境政策支援システムの開発を主たる研究テーマとしています。土木・環境工学や計算機科学の研究者に加えて合衆国政府(環境保護庁,地質調査所,開拓局など)やコロラド州政府の政策担当者も実際に参加して実に効率的な学際研究プロジェクトが運営されています。研究の中身もさることながら,大規模な計算機ネットワークによって20数名ものスタッフの成果を見事に統合する洗練されたプロジェクト管理のノウハウには感動を覚えます。
林田は米国海洋気象局(NOAA)のエアロノミー研究所で成層圏オゾンの破壊に関する研究を行っています。エアロノミー研究所は成層圏微量成分の研究では長い歴史を持ち,観測,理論,実験と三拍子揃った研究の推進方法には学ぶべきものが多くあります。研究所には8つの研究グルーブがあり,約100人が働いています。その一部はCIRES(環境科学共同研究機構)というコロラド大学との研究協力機関からの職員です。ホストのスーザン・ソロモン博士は南極オゾンホールの研究であまりに有名ですが,ボウルダーにはNCAR(国立大気物理学研究所)もあり,他にも多くの著名な大気科学者が活動しています。この街は大気科学のメッカといえましょう。さらに素晴らしいのは,お互いの機関の研究協力が密接であることです。例えばソロモン博士はNCARの客員になっていますし,セミナーの掲示もお互いに出し合っています。
こちらに来てから2歳の誕生日を迎えた娘はコマース・チルドレン・センターという保育所に通っています。毎日,英語日本語ごちゃまぜの言葉で米国人の保母や子供たちと遊び回り,1年間の米国生活で吸収するものは父母よりも多いのではないかと思われます。忘れるのも早いかもしれませんが。
ボウルダーにはコロラド大学の広大なキャンパスを中心に政府機関や民間の研究所などがあり,つくばとよく似た研究学園都市という感じです。アメリカの街としては大変治安がよいことでも知られていますが,それはよきにつけあしきにつけ「閉ざされた場所」であることも意味していて,多民族国家であるアメリカの中ではやや特殊な街であるとも聞いています。
標高1656mにある便利で安全な街だということで,最近はマラソン選手の高地トレーニングの場所としても有名になりました。車を30分ほど走らせればロッキーの大自然に囲まれるという土地柄で,街の住民にはアウトドア志向の人達が数多く見かけられます。コロラドはもともと楽天的な西部開拓者の世界であり,それは学園都市ボウルダーのもうひとつの顔になっています。
いわゆる「古き良きアメリカ」の開拓者精神を満喫できる幸運にも恵まれたわけですから,先端的な研究情報だけではなく,最近何かと問題が複雑になりつつある日米関係をポジティブに考えていけるような経験を大切にしていきたいと思います。新しい若い大統領の誕生で,多くのアメリカ人たちも明るい未来に希望を託するようになりましたから。
(はやしだ さちこ,地球環境研究グループオゾン層研究チーム)
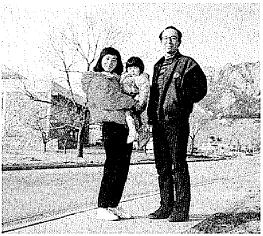
目次
- 地球化時代の幕開けに研究者に望む巻頭言
- 研究所の管理運営における課題− 研究職との懇談から抽出されたもの −論評
- 都市大気汚染研究における可視化の役割りプロジェクト研究の紹介
- シベリア凍土地帯における温暖化フィードバックの研究プロジェクト研究の紹介
- 「第12回地方公害研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告その他の報告
- “A numerical study of nonlinear waves in a transcritical flow of stratified fluid past an obstacle”Hideshi Hanazaki:Physics of Fluids A-Fluid Dynamics,4,2230-2243(1992)論文紹介
- 藍藻毒(Microcystin)の化学と毒性 彼谷邦光:環境化学,2,457-477(1992)論文紹介
- 光合成色素構成比による水界中の植物プランクトン綱別存在量の測定研究ノート
- バイカル国際生態学研究センターと環境科学ネットワーク
- 第8回全国環境・公害研究所交流シンポジウムその他の報告
- 主要人事異動
- 編集後記


