研究所の管理運営における課題− 研究職との懇談から抽出されたもの −
論評
所長 市川 惇信
1992年初頭から研究員・研究補助員,主任研究員,および室長・総合研究官・研究管理官とクラス別の懇談会をもってきた。1回の出席者数を10名以内として行ってきたが,92年10月には各クラスともほぼ一巡した。この時点でこれらの意見に基づき,研究職から見た現在の研究所の管理運営上の課題を整理する。もとより,意見は均一ではなく互いに矛盾するところもあるが,その奥に共通するところを抽出する努力をした。
1.抽出された課題
1990年7月の改組以来,新しい体制への研究者の適応はそれなりに進んでいる。したがって,旧体制への郷愁が主となった改組直後の意見とは異なり,新体制のもとで仕事をした上での問題点の指摘が見られた。
(1)研究所として明確なビジョン・研究計画を設定すること
本研究所が地球環境・自然環境へ展開した結果として,この認識が現れたと考えられる。「公害」時代には,研究は自ずから方向付けされていた。これに対して,地球環境・自然環境研究にはすべての学問分野が関連することから,ビジョンと研究計画の必要性,すなわち「研究領域の重点化」が強調されたといえる。
(2)研究企画機能を充実すること
地球環境研究グループにおいて研究企画,とくに総合推進費の幹事役として所外研究者を含めた研究調整の仕事,が研究者の負担となり,研究実践のための時間が食われている。これに伴い,企画機能の充実が切望されており,その帰結として研究企画という仕事を適切に評価することの重要性が認識されている。
(3)研究支援を組織化すること
研究支援機能を独立した組織として復活することに強い要望がある。個々の研究者がそれぞれ自分を支援することの非効率性が認識され,また,支援技術水準の低下の不安が強い。
(4)研究チームの編成換えを円滑にすること
改組の前提となった「総合グループの研究チームの円滑な編成換え」を保障する方策が必要である。この方策が見えないため,総合グループではチームの存続が図られ,また基盤部門では総合グループへの移行に不安をもつこととなる。結果として,特別研究が各研究部の既得権となっていたことを改善しようとした改組が,かえって「特別研究を総合研究チームの既得権としてしまった」との指摘がある。
(5)研究活動を組織化する新しい枠組を作ること
改組以後,研究室が事実上解体し研究者が個人ベースで活動する傾向がでてきた。これを組織化する新しい枠組を作る必要がある。これに関連して,室長・部長等の管理職に任期を設定することが提案されている。
(6)長期継続的な基盤研究を可能とすること
長期にわたる基盤的研究を支える継続的な研究費が少なくなっている。継続が必要な基盤的テーマを選定した上で,それを長期に保証する方策が望まれている。
(7)高額な設備の整備を可能とすること
研究費がこま切れであるため高額の機器の購入整備が困難となっており,機器の陳腐化が心配されている。
(8)所内での各種の情報の流通をよくすること
所内における情報の流通がよくない。これが,無用な疑念を生み出す土壌となっている。
2.課題への対処
(1)将来計画策定小委員会の設置
研究推進委員会の下部組織として標記の小委員会を設置し,課題(1)〜(5)に加えて,地球環境研究の重点化,センター・オブ・エクセレンス育成計画への対応,を諮問した。現在その答申を待っている。
(2)研究者の階層と管理の階層の分離
課題(2),(4),(5) への処置の一つとして,研究者の成熟度による階層と管理の階層を分離することを考え,第一歩として上位の研究職「主任研究官」を設けた。研究者としての成熟度は室長等と同等とする。将来,室長等は主任研究官への特命的な任務とすることも考えられる。
(3)企画,支援等の業務の評価
論文になる仕事について,外部の学術社会による評価を受けたもの,すなわち学術論文として受理・発表されたものは,内部でそのまま評価すればよい。内部独自の評価を要するのは,研究所にとって不可欠な企画・支援・調査・国際的活動など,外部に評価が存在しない業務である。これらを適切に評価する方策を至急確立する必要がある。
3.研究職一人ひとりの現状と将来展望
現在の研究所の中で,研究者一人ひとりがどのように現状を認識し展望をもっているかを調査票により探った。回答の総数は62で,研究職全体の約 1/3である。内訳は,研究員14(23%),主任研究員25(40%),室長等23(37%),所属は,地球関係15(24%),地域18(29%),基盤31(50%)である。括弧内は回答総数に対する%である。データが少ないのでクロス集計はできない。単純集計の結果を図1〜7に示す。紙面の都合で説明しないが,これを調査票に記入した人々への調査結果報告と見なして頂きたい。
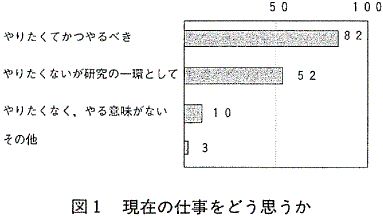
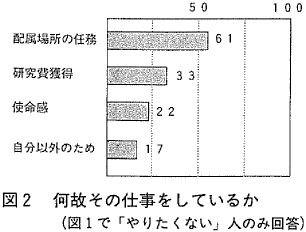
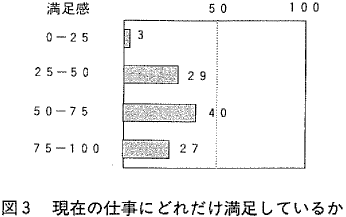
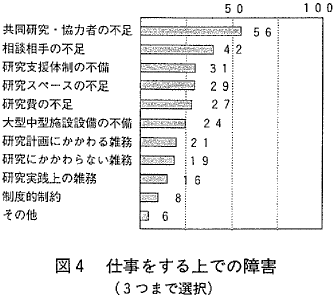
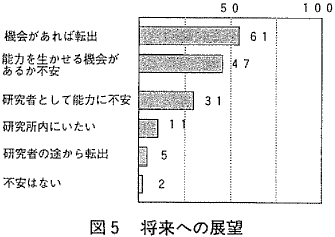
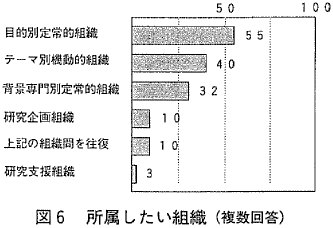
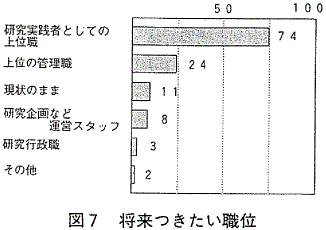
目次
- 地球化時代の幕開けに研究者に望む巻頭言
- 都市大気汚染研究における可視化の役割りプロジェクト研究の紹介
- シベリア凍土地帯における温暖化フィードバックの研究プロジェクト研究の紹介
- 「第12回地方公害研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告その他の報告
- “A numerical study of nonlinear waves in a transcritical flow of stratified fluid past an obstacle”Hideshi Hanazaki:Physics of Fluids A-Fluid Dynamics,4,2230-2243(1992)論文紹介
- 藍藻毒(Microcystin)の化学と毒性 彼谷邦光:環境化学,2,457-477(1992)論文紹介
- 光合成色素構成比による水界中の植物プランクトン綱別存在量の測定研究ノート
- バイカル国際生態学研究センターと環境科学ネットワーク
- 第8回全国環境・公害研究所交流シンポジウムその他の報告
- 標高1656mの研究学園都市海外からのたより
- 主要人事異動
- 編集後記


