バイカル国際生態学研究センターと環境科学
ネットワーク
河合 崇欣
「豊かなるザ・バイカルの……」,東シベリア南西部のモンゴルとの国境近く,日本の総面積の1.5倍にも及ぶ広大な集水域に絨毯のような寒帯針葉樹林を擁して,世界最深,最古,最大容量の淡水湖,バイカル湖が清澄な水をたたえて横たわる。
1988年11月,旧ソ連邦・科学アカデミー最高幹部会議は,バイカル湖を世界の科学者に開放し,国際共同研究を花開かせるために,バイカル国際生態学研究センター(BICER)を開設することを決定した。以来,アメリカ,ベルギー,日本,連合王国(イギリス),スイス等を中心に延べ400名を超す研究者がロシアの研究者を含めた国際共同研究のためにバイカル湖を訪れている。日本では,1991年3月に大学教官や研究者が集まって,日本BICER協議会(奥田節夫会長)を設立し,環境研に事務局をおいた。既に50余名が現地を訪れた。
バイカル湖誕生後,3千万年の間に積もった4,000mを超す湖底堆積層は幾度も繰り返された氷河期をも貫いて,気候・環境変動と生物相の変化を途切れることのない精密な記録として保持している。また,長い時間をかけて独自の進化を遂げてきた1,000種を超える固有生物種はそれらの遺伝子の中に環境適応と進化の歴史を刻む。この2つを同時に調べることによって,環境変化が種の存続に与える影響についての定量的な知見が得られると期待される。環境問題解決にとって不可欠の情報である。既に多くの科学的な研究成果の蓄積があって,かつ,このような研究をできる場所は,世界中にも数少ない。日本からは1日で到達できる有利な位置にあり,私たち日本の研究者に対する期待は大きい。
(かわい たかよし,地球環境研究グループ酸性雨研究チーム)
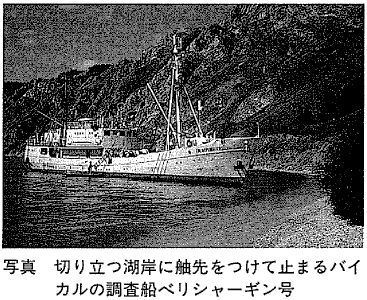
目次
- 地球化時代の幕開けに研究者に望む巻頭言
- 研究所の管理運営における課題− 研究職との懇談から抽出されたもの −論評
- 都市大気汚染研究における可視化の役割りプロジェクト研究の紹介
- シベリア凍土地帯における温暖化フィードバックの研究プロジェクト研究の紹介
- 「第12回地方公害研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告その他の報告
- “A numerical study of nonlinear waves in a transcritical flow of stratified fluid past an obstacle”Hideshi Hanazaki:Physics of Fluids A-Fluid Dynamics,4,2230-2243(1992)論文紹介
- 藍藻毒(Microcystin)の化学と毒性 彼谷邦光:環境化学,2,457-477(1992)論文紹介
- 光合成色素構成比による水界中の植物プランクトン綱別存在量の測定研究ノート
- 第8回全国環境・公害研究所交流シンポジウムその他の報告
- 標高1656mの研究学園都市海外からのたより
- 主要人事異動
- 編集後記


