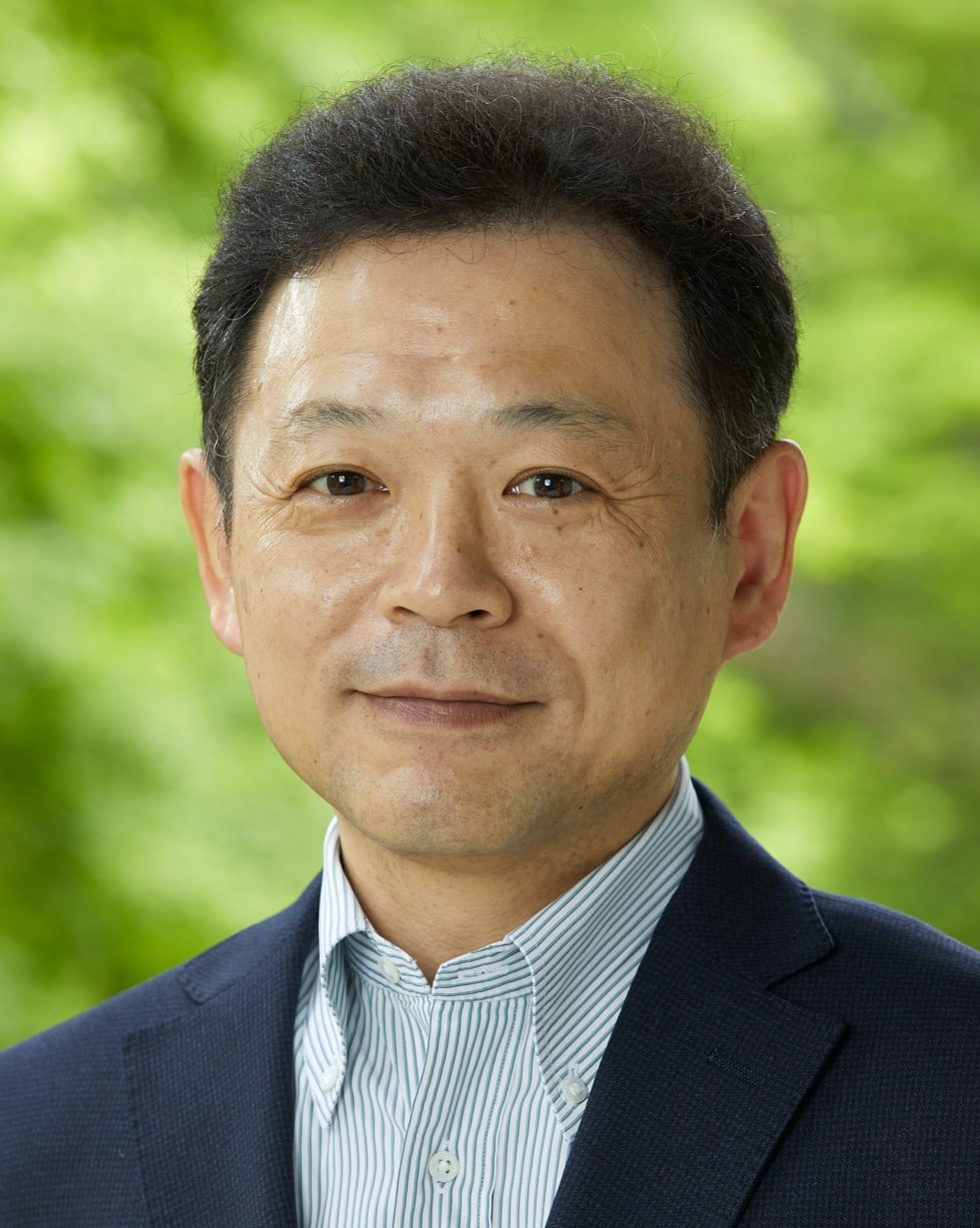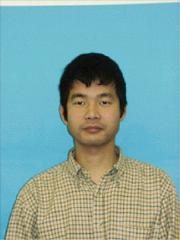- 研究課題コード
- 2125AA125
- 開始/終了年度
- 2021~2025年
- キーワード(日本語)
- リスク管理,包括的モニタリング,生態影響予測,
- キーワード(英語)
- risk management,comprehensive monitoring,ecological impact prediction,
研究概要
緊急時に備えるべき化学物質の管理システムやモニタリング体制の在り方等、化学物質のマネジメントへの取組として、災害を含めた突発的事故に対処するための情報基盤構築とリスク管理体制の体系化に加えて、それら発災による化学物質の影響を迅速且つ的確に把握するための包括的調査手法の開発と実用化を図り、リスクに対処する科学的手法と将来的な化学物質の管理システムの方向性を環境施策に反映させる。
研究の性格
- 主たるもの:行政支援調査・研究
- 従たるもの:モニタリング・研究基盤整備
全体計画
3年程度で過去事例の解析に基づいた災害事故時における化学物質のリスク管理体制を体系化する。一方、漏洩した化学物質の迅速な汚染実態の推定とその曝露評価の点では、親水性の調査優先物質についてデータベース利用に基づく迅速簡易同定定量システムの基礎データを収集するとともに、災害時環境疫学及び環境曝露をより効果的に調査可能なツールと手法を開発する。また、陸域で漏洩・放出された化学物質の溜まり場となる沿岸海洋生態系に着目し、事例解析も含めた定量的な災害影響予測法を提案する。また、5年を目途に、早期復興に求められるリスクに対処する科学的手法と将来的な化学物質の管理システムを行政に提供する。これらの取組により、緊急時を想定した化学物質のリスク管理基盤の構築に加えて、漏洩した化学物質の汚染状況、災害時環境疫学及び環境曝露を迅速かつ適切に把握可能なツールを開発し、リスクに対処する科学的手法と将来的な化学物質の管理システムの方向性を環境施策に反映させる。
今年度の研究概要
サブテーマ1「緊急時における化学物質の管理システムの在り方の解明」では、2023年度に実施した第1回地環研机上演習のフィードバックを踏まえて、D.Chem-Coreのシステム改良やマニュアル整備を進める。また2024年度中に実施予定の第2回地環研机上演習に向けて演習デザインやアンケート項目を改善するとともに、これらの演習結果やアンケート結果の解析を実施する。サブテーマ2「緊急時における化学物質の迅速調査手法の開発」では、AIQS-LCの利活用拡大に向け、他機種への適用等の汎用化や、解析支援ソフトの開発を進める。また地方環境研究所への実装に取り組む。ペン型セミアクティブ大気サンプラーではHCBD以外の揮発性化学物質を対象に適用性の検証を進める。一方、沿岸生態系の変動予測では津波、台風、復旧工事のような攪乱イベントによる干潟への影響について、蒲生潟でこれまでに得られた植生、底質及び底生動物データを用いた解析を実施する。また、引き続き船舶燃料油、および潤滑油等に含まれる炭化水素の分析を行い、環境影響と残留性が懸念されるPAHの多寡の原因を検討し、さらにこれまで分析を行った結果についてデータベース作成に着手する。また、今年1月に能登半島地震で発生した津波で転覆した船舶から港内に燃料油が流出したのを受けて、底質中の炭化水素汚染実態調査を行う予定である。サブテーマ3「緊急時の健康影響と曝露調査ツールの開発や調査体制の構築」では、 米国災害時研究対応(DR2)のアジアネットワーク構築のため、NIHと共同でワークショップ(WORKSHOP DISASTER RESEARCH RESPONSE (DR2) NETWORK in ASIA)を開催し、とりまとめる。過年度作成した英語版の災害時疫学ツールの日本版について、データベースで公開準備を行う。
外部との連携
環境省環境調査研修所、地方環境研究所(40機関)、東北大学、横浜国立大学、大阪大学、高知大学、日本大学、宮城教育大学、東邦大学、岩手医科大学、NPO法人日本国際湿地保全連合、株式会社自然教育研究センター、公益財団法人ふくしま海洋科学館、大船渡市市民環境課、出光興産株式会社、National Institutes of Health (US)、北九州市立大学、大阪市立環境科学研究センター、滋賀県立大学