環境中の化学物質総リスク評価のための毒性試験系の開発に関する研究(特別研究)
平成10〜12年度
国立環境研究所特別研究報告 SR-41-2001
1.はじめに
化学物質は、人類の生活の向上に計り知れないほどの大きな貢献をしたが、一方で環境中に放出された化学物質がヒトの健康や生態系に対して様々な有害影響をもたらしている。現在では、いわゆる「公害」のような特定の化学物質による重篤な環境汚染はみられなくなったものの、汚染の実態はますます複雑化、深刻化している。多くは微量ではあるが無数の化学物質による複合汚染であり、ダイオキシン類のように非意図的に生成されたもの、さらには環境中で変換されたものも存在しうる。従って、化学分析によってこれらすべてを検出、同定し、定量するのは事実上不可能であり、現実には環境基準、要監視項目等に指定された一部の化学物質が化学分析によってモニタリングされているのみである。このため、極めて重大な有害性を持つ物質が見過ごされている可能性も存在しうるわけであり、実際、昨今大きな社会的関心を集めている内分泌撹乱化学物質は、その典型例であるといえよう(図1)。それらを検出・評価できる試験系の開発が待たれている。環境基本計画にも示されているように、環境を汚染しヒトの健康や生態系への有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質のリスク評価は、環境リスク対策の重要な柱である。
比較的早くから環境モニタリングに使われてきている変異原性試験は、ヒトや実験動物での発癌との関連がかなり明らかにされているうえ、試料中に存在する化学物質の種類に関係なく変異原性という指標で判定し、通常の化学分析では漏れてしまうものまで網羅しうる。本特別研究では、様々な生物学的評価試験法(バイオアッセイ)を用いて、試料中に存在するいわゆる一般毒性(急性、亜慢性毒性)の総体(総括的な毒性の強さ)を反映しうる新たな有害性総合評価指標を確立することを目的とした。
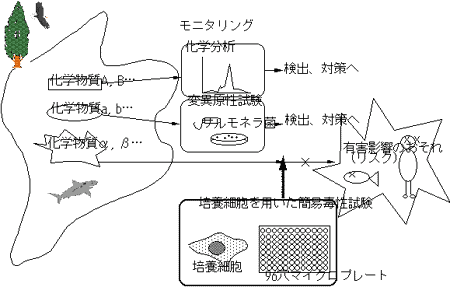
2.研究の概要
本特別研究では、培養細胞を用いたin vitro(試験管内での)毒性試験をはじめとする各種バイオアッセイ法を用いて、環境媒体の有害性を総体として評価できる指標の確立を目指した。従って、これらのアッセイ系は、個別物質の毒性評価に用いられる毒性試験法とは、当然求められる条件が異なってくる。その条件としては、安価に且つ迅速に再現性のよいデータが得られること、未知物質を含む混合物試料にも対応可能であること、そしてできればヒトでの毒性値を反映しうること、等が挙げられる。そのためには、I)環境試料への適用を前提とした現行の各種バイオアッセイ法のvalidation(有用性評価)、II)環境試料への適用に伴う問題点の洗い出しと対策法の検討、III)化学分析に匹敵するような高感度なバイオアッセイの確立といったステップを踏む必要があり、以下のサブテーマを中心として研究を進めた。
i.In vitro毒性試験値の毒性学的意義付け
国際的なin vitro毒性試験のvalidationプログラムであるMEICとの共同で、各細胞に共通の基本機能に対する毒性、基礎細胞毒性(Basal Cytotoxicity)と、ヒトで急性毒性が発現する際の血中濃度との間の相関を見いだし(図2)、短期一般毒性の指標としての基礎細胞毒性の利用の可能性を示した。
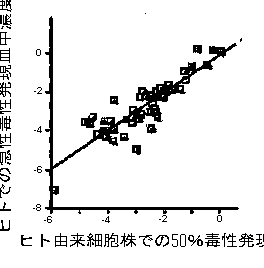
ii.バイオアッセイ法の標準化と簡便化
将来発展性のある試験法の確立と、より利用価値が高い試験データの蓄積のための第一歩として、特に環境試料への適用を念頭に置いて、in vitro細胞毒性試験をはじめとする各種バイオアッセイ法のvalidationを行った。具体的には、環境中でその影響が危惧されている化学物質を32種類リストアップし(表1)、研究所内外の研究者にそれぞれの試験系での毒性評価を依頼して、提供された試験データについての解析、評価を行った。その結果と、MEICプログラム等他のvalidationプログラムでの成果並びにその勧告等を参考にして、主として用いるべき試験法の組み合わせを策定し、それらに必要な材料(細胞、培地等)のキット化を試み、外部機関への試験的配布も行った。
| 1. 2-Aminoanthracene | 12. Sodium Arsenite | 23. Potassium dichromate |
| 2. Benzo(a)pyrene | 13. Thiuram | 24. Triphenyltin chloride |
| 3. Bis-phenol-A | 14. Tributyltin chloride | 25. Phenol |
| 4. Di-2-ethylhexyl phthalate | 15. 2,4,5-Trichlorophenol | 26. Benthiocarb |
| 5. 2,5-Dichlorophenol | 16. Trp-P-2 (Acetate) | 27. Hexachlorophene |
| 6. 2,4-D | 17. Paraquat | 28. Triclosan |
| 7. Formaldehyde | 18. Cadmium chloride | 29. Mercuric chloride |
| 8. Methylmercury chloride | 19. Lindane (gamma-HCH) | 30. Cupric sulphate |
| 9. 4-Nitroquinoline-N-oxide | 20. Malathion | 31. Potassium cyanide |
| 10. p-Nonylphenol | 21. Maneb | 32. DMSO |
| 11. Pentachlorophen | 22. Nickel chloride |
iii.混合物試料を対象としたバイオアッセイの実施
未知物質を含む混合物試料という現実の環境試料の評価に先立って、5〜20種類の化学物質からなる混合物試料を13種類調製し、それらについてin vitro細胞毒性試験を実施、化学物質単独の場合の試験結果との比較解析を行った。毒性作用が相加的である場合に混合物試料のEC50は0.4前後となるよう設定していたが、実際多くの混合物試料のEC50は0.4あたりに集約しており(図3)、混合物の毒性作用を相加的と仮定しても、不確実性係数として10をみておけば、大きな過誤は生じないものと考えられた。従って、未知物質を含む混合物試料という現実の環境試料の評価においても、in vitro細胞毒性試験を用いて、個々の物質に由来する有害性の積算値として総体的に評価できる可能性が示された。
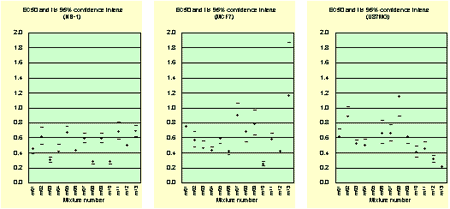
iv.環境試料を対象とする際の技術的問題点の洗い出しと対応法の検討
環境試料を対象としてバイオアッセイを実施する際の技術的問題点を洗い出して、それらへの対応法を検討した。特に排水試料の場合、浸透圧の影響が結果を大きく左右する場合があり、浸透圧標準液を用いた補正が有効であることを示した(図4)。さらに、低毒性の環境試料をも評価対象とするために、有害性の定量的な回収ができる減圧濃縮法を確立、霞ヶ浦等の湖水試料中に存在する有害性が検出可能となり(図5)、バイオアッセイによる環境モニタリングへの道を開いた。
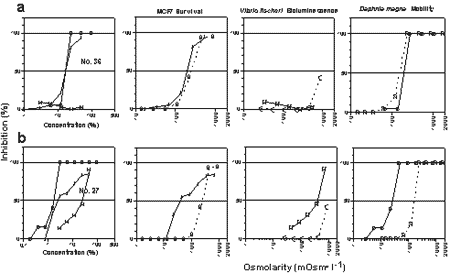
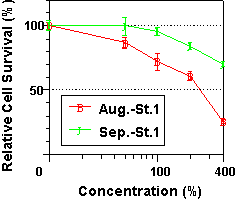
3.今後の検討課題
平成10年度より12年度まで実施した本特別研究「環境中の化学物質総リスク評価のための毒性試験系の開発に関する研究」によって、基礎細胞毒性試験をはじめとするいくつかのバイオアッセイ系が、環境(水)中に存在する有害性を総合的に評価する試験法として有用であり、実利用可能であることが示された。
今後は、これらの簡易なバイオアッセイ系のバッテリー(組合せ)を実用化し、実際の環境管理への導入と活用を試みる必要がある。具体的には、以下のような項目について、さらに検討を加える必要があろう。
i.各種バイオアッセイのキット化と供給体制の確立
本特別研究で得られた成果を基にして、新規のバイオアッセイ法としてヒト由来培養細胞を組合せ用いた細胞毒性試験法をキット化し、供給体制を整える。
ii.バイオアッセイ適用対象の選定と評価
バイオアッセイ系の適用対象として、湖水・河川水、各種事業所排水等が挙げられるが、適用に際しての有用性評価と問題点について、特に検出される有害性の分類とその低減対策に重点を置いて検討する。
iii.バイオアッセイ指標のスコア化
前項に関連して、低減対策の優先取組施設を設定し、低減目標を定めるためにも、バイオアッセイ指標のスコア化が必要となる。管理対象に応じた、各バイオアッセイ値の重み付けを行い、数値化する。
iv.自治体の協力を得たバイオアッセイパイロット事業の実施
未知物質を含む混合物という環境中での化学物質の存在形態を考えれば、従来の毒性学、リスク科学にはとらわれない新たな発想と戦略が必要となるが、現段階では、環境化学物質によるヒトの健康に対する有害性を総合的に評価するためのバイオアッセイ系は、未だ完全なものはできあがっていない。しかし、いくつかのバイオアッセイを組合せ用いることにより、ヒトに対する急性毒性を反映した評価も可能となる。これらの試験法は、限界が見えつつある現行の個別物質の規制に基づく環境管理システムでカバーできない部分を補うものであり、米国で既に導入されているWET (Whole Effluent Toxicity)プログラム、TIE (Toxicity Identification Evaluation)/TRE (Toxicity Reduction Evaluation)プログラムと並ぶ次世代の環境管理システムとなりうるものである。バイオアッセイで得られた値が、例えば排水管理に関して言えばBOD、CODと並ぶような総合指標値として利用されるようになることが期待される。
独立行政法人国立環境研究所
統括研究官
森田昌敏
Tel:0298-50-2332,Fax:0298-50-2570
用語解説
-
in vitro(試験管内での)毒性試験実験動物(ラット、マウスなど)を用いて行われるin vivo(生体内での)毒性試験に対し、培養細胞や微生物などの微小生物を用いて試験管(培養容器)内で行われる毒性試験を指す。
-
validation(有用性評価)試験法が特定の目的のために信頼のおけるものであることを明らかにする作業。
-
変異原性突然変異を誘起する活性のことで、遺伝子(DNA)に対する傷害作用が基本となっている。
-
生物学的評価試験法(バイオアッセイ)化学分析に基づく評価試験にたいし、生物個体、培養細胞等を用いて、生物による応答を指標として行う評価試験
-
MEIC(Multicenter Evaluation of In vitro Cytotoxicity)国際的なin vitro試験法の有用性評価プログラムの一つで、スカンジナビア細胞毒性学会が中心となっている。
-
短期一般毒性毒性は、暴露期間に応じて急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性に分類され、またその種類によって発癌性、神経毒性、免疫毒性等に分類されるが、その中で、急性・亜急性の致死毒性に相当するような毒性を指す。
-
EC50(50% effective concentration)最大反応の50%の反応がもたらされる濃度。
-
不確実性係数基準値等を定める際に参考とする毒性試験データの信頼性、種間差、種内差等によりもたらされる不確実性を補償するための係数。
-
減圧濃縮法環境水試料などの水溶液について、溶媒(水分)のみを真空ポンプを接続した装置によって蒸発させ、溶質を濃縮する方法。
-
WET(Whole effluent toxicity)プログラム米国環境保護庁(EPA)が採っている排水規制の一つで、排水放出先の河川等に生息する水生生物を用いて、バイオアッセイにより排水中に存在する毒性の総体的を評価し、必要に応じて低減対策が命じられる。
-
TIE/TRE(Toxicity identification evaluation/Toxicity reduction evaluation)WETによって排水中に規制値以上の毒性が存在していることが明らかになった場合、その毒性の由来を明らかにして、毒性を低減するために用いるべき処理方法を探索するプログラム。











