培養細胞を用いた化学物質の評価の試み −基礎細胞毒性値の評価指標としての有用性−
研究ノート
国本 学
人間活動に伴って環境中に放出されたり,環境中で非意図的に生成された化学物質(例えば種々の有機塩素化合物等)は,大気,水,食品等の媒体を介して我々の体内に取り込まれるため,それらがどの程度有害であるかについては重大な関心がもたれている。既に膨大な種類存在し,さらにその数が増加しているこれら化学物質の安全性評価は,緊急の課題である。
毒性試験の中心となってきた動物実験は現在でも最も重要で信頼性の高いものであるが,多種類の化学物質を迅速に評価するのには様々な制約があり,また動物愛護の観点からも,動物実験に代わる方法の開発が急がれている。現在までに哺乳類細胞を用いた多くの in vitro(試験管内の)試験が開発・提案されてきたが,OECD毒性試験ガイドラインでは遺伝毒性試験としていくつかリストされているだけで,遺伝毒性以外の一般毒性の試験法では皆無である。これは,生体内での吸収,分布,代謝等の毒物動態学的過程までも取り入れた試験系がまだ確立されていないためである。もう一つの大きな問題点は現在のところ試験方法に統一的基準がなく,結果の相互比較が不可能に近いことである。化学物質の評価指標として利用されるためには,何等かの基準の設定と組織的な取り組みが必須である。これらを解決するための試みが,学会等を中心にして世界中でなされている。中でも,筆者も参加しているSSCT(The Scandinavian Society of Cell Toxicology)を中心とするMEIC(Multicenter Evaluation of In vitro Cytotoxicity)のアプローチは注目に値する。MEICでは,ヒトでの急性毒性発現用量が判明している化学物質を 50種(別表)選定し,哺乳類細胞を用いた毒性試験を行っている各国の研究機関にその毒性試験を依頼し,各研究機関から提供された 50%毒性発現濃度データの解析・評価を行っている。筆者らの提供した2種類の培養神経細胞における 50%増殖阻害濃度データを含め,多くの試験法間で毒性データの良い相関が認められたことから,これらが各細胞に共通の基本的機能に対する毒性,すなわち基礎細胞毒性(Basal Cytotoxicity)を反映するものと考えられた。さらに,急性毒性発現血中濃度との間にも良好な相関が見いだされ,複数のin vitro試験を組み合わせることによって,短期一般毒性の指標として基礎細胞毒性の利用が可能であることが示されつつあり,今後の展開が期待される。
真に動物実験に代替しうる培養細胞を用いたin vitroの毒性試験系を確立するためには克服すべき課題は山積しており,一朝一夕に解決できるものではなく,毒性発現機構の解明,新たな毒性指標の確立等,基礎的なデータの蓄積なくしてはなし得ない。
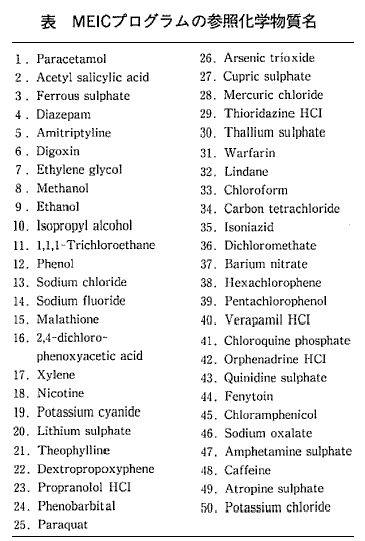
目次
- 小さな実践の積み重ねの大切さ巻頭言
- 環境健康研究への夢 −部長就任のご挨拶に代えて−論評
- 所内研究発表会報告
- 砂漠化と人間活動の相互影響評価に関する研究プロジェクト研究の紹介
- "Chemical Composition of the Winter Precipitations at Mt. Zaoh − Indication of the Transport of Soil Particles from the Asian Continent to Japan" Masahiro Utiyama, Motoyuki Mizuochi, Katsutoshi Yano and Tsutomu Fukuyama : Journal of Aerosol Research, Japan 7(1), 44-53 (1992).論文紹介
- “Growth and grazing of a heterotrophic dino-flagellate, Gyrodinium dominans, feeding on a red tide flagellate, Chattonella antiqua" Yasuo Nakamura, Yuichiro Yamazaki and Juro Hiromi: Marine Ecology Progress Series, 82,275-279 (1992)論文紹介
- 平成7年度地方公共団体公害研究機関と国立環境研究所との共同研究課題について
- 平成7年度国立環境研究所予算案の概要について
- 主要人事異動
- 編集後記


