環境基本法時代における環境研究の展開
巻頭言
主任研究企画官 久野 武
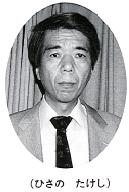
昨年は懸案だった環境基本法がようやく陽の目をみた。従来の公害事象を克服することを目的とする公害対策基本法の世界から脱却し,地球環境や自然保護,ライフスタイルの変換までも環境というキーワードで鳥瞰しうる視座をようやく得ることができたのである。もとより,このこと自体は事実としてとうに語られてきたし,わが研究所もそのためにこそ平成2年に改組を敢行したのであるが,それが法律レベルで認知されたということの意味はやはり小さくないであろう。今後この基本法の視座のもとにわが研究所における研究を展開していかねばならないのだが,その基盤は確保されているであろうか。
予算は改組以後順調な伸びを見せてきたものの施設・設備の老朽化,陳腐化という課題には対応が困難であった。しかし数次にわたる補正予算という神風が吹き,画期的な前進が図られることになったし,建設省予算による環境遺伝子工学実験棟も竣工しバイテク研究も本格的に開始された。
このようにわが研究所には明るい展望がつぎつぎと開けてきたのだが,残念ながら肝心の人員増は極めて困難な状況にある。しかも研究領域が従来の公害事象から地球環境や生態系まで大きく拡がってきているわけであるから,個々の研究者が抱えきれないほどの研究課題に窒息してしまうおそれなしとしない。つまり人員増が困難でかつ安易な戦線縮小も許されないというアポリア(難題)のなかにある。
この解決のために叡智を結集しなければならないのだが,まずはわが研究所総体としていまどれだけの研究課題を抱えているのかという即自的な現状把握の強化とそれらの研究課題が相互にどういう関連を持っているのか,持ち得るのかという対自的な現状認識,すなわちいわば研究マップの作成を行い,全所員の共通認識とすることが第一歩ではないかと考えている。
目次
- 環境リスク研究の課題論評
- 関西地域における春季高濃度大気汚染の生成機構調査プロジェクト研究の紹介
- 人工衛星搭載レーザーレーダーを用いた大気環境の評価に関する研究プロジェクト研究の紹介
- “Role of Heterotrophic Bacteria in Complete Mineralization of Trichloroethyleneby Methylocystis sp. Strain M.”Hiroo Uchiyama, Toshiaki Nakajima,Osami Yagi and Tadaatu Nakahara:Applied and Environmental Microbiology,58,3067-3071 (1992)論文紹介
- 日本国内の113湖沼におけるCOD環境基準の達成状況論文紹介
- 平成6年度地方公共団体公害研究機関と国立環境研究所との共同研究課題についてその他の報告
- 人骨をもちいた生物学的モニタリング研究ノート
- 二酸化窒素暴露と出生による酸素環境変化がラット肺におよぼす影響研究ノート
- 共同実験2棟(仮称)の建築についてその他の報告
- 地球環境研究総合推進費研究発表会ネットワーク
- 主要人事異動
- 編集後記


