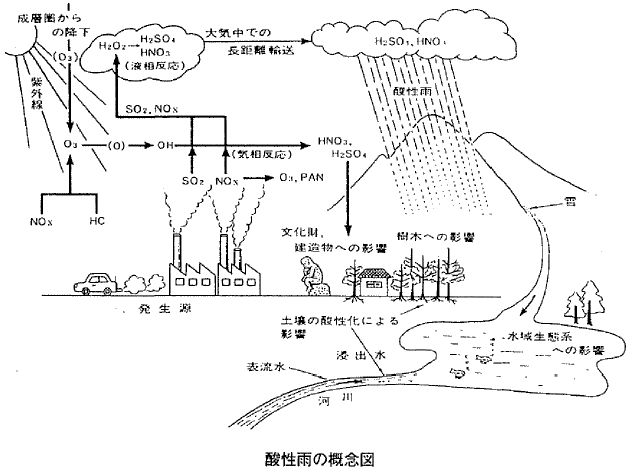酸性雨総合研究
プロジェクト研究の紹介
溝口 次夫
酸性雨が湖沼や河川を酸性化し、そこに生息している魚介類や水生生物を死に至らしめ、また、森林や歴史的建造物などを損傷していることはよく知られている。ヨーロッパ大陸北東部や北米大陸東部では20年以上も前から酸性雨によるこれらの被害が顕在化している。我が国でも最近関東地方や北九州地方の一部でスギやモミなどの樹木の枯損が見られるが、今のところそれ程大きな被害ではない。しかし我が国でも欧米とあまり変わらない酸性雨が降っていることもこれまでの調査で明らかにされている。
酸性雨の原因である二酸化硫黄や窒素酸化物は石炭や石油などの化石燃料の燃焼に伴って大気中へ放出されるものである。我が国を含めた東アジア地域はヨーロッパ大陸や北米大陸に次いで化石燃料の消費量が多い地域であり、今後さらに増加するものと推測されている。
酸性雨総合研究は環境庁が今年度から新たに設けた地球環境研究総合推進費のもとで行われている。酸性雨は地球の温暖化現象やオゾン層の破壊などと共に地球的規模の環境問題として位置付けられている。もちろん、酸性雨は国際的あるいは大陸的規模の環境問題ではあるけれども、同時に一国内の地域の環境問題としても重要である。
酸性雨という言葉について、この総合研究では樹木などへの影響の観点から、単に酸性の降雨だけでなく、乾性の酸性降下物及びガス状の酸性物質や酸化性物質を含めたものを広義に酸性雨と定義する。
研究計画
酸性雨の前駆体物質である二酸化硫黄や窒素酸化物の大気中への放出、それらの大気中での反応による酸性物質(硫酸や硝酸)の生成、エアロゾルや雲などへの取り込みとそれらの輸送及び地表面への沈着のプロセス、地表面での樹木などへの影響や土壌及び水域(湖沼、河川)を酸性化するメカニズムを明らかにするため、以下の研究を進めている。
(1)東アジア地域における酸性雨の動態解明に関する研究
東アジア地域において地上の発生源から大気中へ放出された二酸化硫黄や窒素酸化物が大気中でヒドロキシルラジカルなどの過酸化物と反応して硫酸や硝酸に酸化されるメカニズムと、それらがエアロゾルや雲に取り込まれて輸送され、地上へ到達するプロセスを明らかにするため、次の研究を行っている。
| (1) | 酸性雨及び関連物質の輸送等を明らかにするための地上モニタリング地点の選定とモニタリングの実施 |
| (2) | 東シナ海を中心とした東アジア地域における大気の流れの解析 |
| (3) | 東アジア地域の二酸化硫黄や窒素酸化物の発生源分布と発生量の推定及びそれらのデータベースの構築 |
| (4) | 航空機観測のための微量酸化性物質計測システムの開発 |
| (5) | 酸性霧の生成と汚染物質が霧に取り込まれるプロセスの研究 |
(2)自然植物系における酸性雨の影響に関する研究
酸性雨が樹木等に与える影響を同定、定量するために国環研での高性能の暴露チャンバー実験及びフィールドでの調査や実験を行う。初年度は次の研究を開始している。
| (1) | 樹木へ及ぼす影響が大きいと考えられる酸性霧暴露チャンバーの開発とそれを用いた実験 |
| (2) | 実験に供する針葉樹(スギやモミ)の育成方法の開発 |
| (3) | フィールドにおいて樹木の枯損の原因を明らかにするためのオープントップチャンバー*法及び配置法による実験手法の開発 |
| (4) | 高感度分析法を用いた樹木各部の元素分析法の確立と樹木枯損原因の追求 |
| (5) | 赤外線画像計測法を用いた樹木枯損の早期評価法の確立 |
| (6) | 酸性降下物のモニタリングのための指標植物の検索 |
-
オープントップチャンバー大気汚染質の植物影響を評価するための野外実験用チャンバーで上部の開いている形式のもの
(3)酸性降下物の陸水、土壌への影響機構に関する研究
我が国の酸性降下物量は欧米とあまり変わらないにもかかわらず、湖沼や河川の酸性化は進行していない。陸水域の酸性雨による影響は土壌の酸性化から始まる。我が国の土壌中での酸性降下物の挙動を明らかにし、土壌中和能の定量化や各陸水域の酸性化予測などを行う。
| (1) | 酸性降下物量の計測と陸水域酸性化予測のためのモニタリング地点の選定とモニタリングの実施 |
| (2) | 酸性化しやすいと推定される湖沼や河川の調査 |
| (3) | 土壌中和能推定のための研究 |
| (4) | 降雨流出水質に及ぼす酸性雨の影響の研究 |
| (5) | 湖沼や河川の酸性化が水生生物相に与える影響の研究 |
以上の研究を実施する体制は酸性雨研究チームの構成員5名のほかに、基盤研究部門から10数名の参加を得てプロジェクトチームを構成している。また、大学及び多くの地方自治体の研究機関の協力を得ている。酸性雨の現象解明やその及ぼす影響などの研究は地方自治体も大きな関心を寄せており、またフィールドでの研究が必要であるため、今後も地方自治体との共同研究体制を密にしていくことが必要である。