魚の導入による湖沼の生物群集の変化と生態系管理
Summary
湖沼など閉鎖性の強い水域では生態系が微妙なバランスの上に成り立っており、外部から生物種を導入すると湖沼の生態系が大きく変わります。たとえば食物連鎖の頂点に位置する魚が入ってくると、下位にいる小動物や動植物プランクトンの種類や量が変化し、水質も変わります。
1 ハクレンを用いたバイオマニピュレーションの有効性
ハクレンの導入によってアオコや他の動植物プランクトンの種類や量、水質にどのような影響が出るかを調べるため、霞ヶ浦臨湖実験施設の港内に6基の隔離水界をつくり実験を行いました。
(1)ハクレンの導入によるアオコの制御と湖の透明度
実験の結果、ハクレンを導入することでアオコの量は確実に減りました。しかし、アオコとともにハクレンのエサとなる動物プランクトンの量も減少したため、動物プランクトンのエサとなっていた小型の植物プランクトンは増加しました。したがって、ハクレンの導入により植物プランクトン全体量の減少や湖水の透明度の増加は必ずしも期待できないことが示されました。
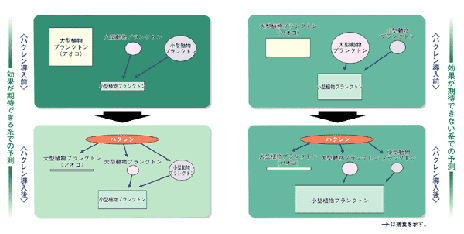
一方、「効果が期待できない系」は、アオコはそれほど多くなく、大型動物プランクトンが多い環境です。ここにハクレンを導入すると大型動物プランクトンがハクレンに食べられ減るため、トロフィック・カスケード効果により小型植物プランクトンが増え、結果的に植物プランクトンの総量はハクレンを導入する前と変わらなくなるか、もしくは、増える場合もあります。そのため透明度は回復しません。
(2)湖沼管理への応用と問題点
ハクレンが重要な水産資源となっている中国では、ハクレンにアオコを食べさせ漁獲することで、アオコやその要因である窒素・リンの除去を、コストをそれほどかけることなくできます。しかしハクレンを導入する湖沼にミジンコなどの大型動物プランクトンが比較的豊富にいると、植物プランクトンの総量を抑制したり透明度を上げる効果は期待できません。またハクレンの導入によってプランクトン群集が小型化し、超小型のピコプランクトンも増えてしまいます。これを取り除くことはかなり難しく、湖沼の水を飲料水などに利用することが困難になります。
2 魚種の変化が十和田湖の生態系に与えた影響
十和田湖では、重要な水産資源であるヒメマスの漁獲量が1985年に急に落ち込み、それに代わって80年代前半に予期せずに導入されたワカサギの漁獲量が増えました(図2)。また同じ頃から湖の透明度が低下し(図3)、COD濃度が高くなっていることが明らかになりました。そこでワカサギの増加がヒメマスの減少や水質の悪化にどのような影響を及ぼしているかを調査しました。
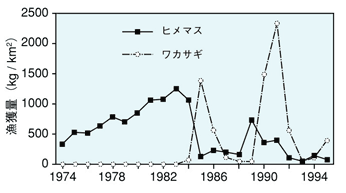
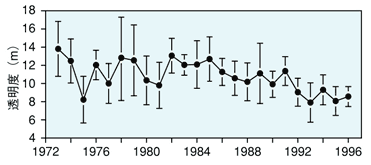
(1)動物プランクトン群集の変化
まずヒメマスのエサになる動物プランクトン群集の変化を調べました(図4)。ハリナガミジンコなどの大型の動物プランクトンの量が多い時期とヒメマスの漁獲量が多い時期はほぼ一致しています。しかし、ワカサギの導入後こうした大型の動物プランクトンが減り、それまでは見られなかった小型のゾウミジンコが増えました。
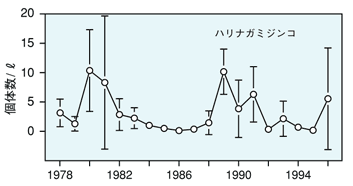
(2)ヒメマスが獲れなくなった理由
秋田県水産振興センターがヒメマスとワカサギの胃の内容物を調べたところ、ヒメマスは漁獲量が多い時期はハリナガミジンコなどをよく食べていましたが、漁獲量が少ない時期はユスリカの幼虫やさなぎ、ヨコエビ、昆虫を食べており、ゾウミジンコなどは食べていませんでした。一方、ワカサギはその漁獲量と無関係に常に、大型のプランクトンやユスリカの幼虫やさなぎに加え、ゾウミジンコなども食べていました。
ヒメマスとワカサギはともに大型の動物プランクトンを主食としていますが、ヒメマスが小型の動物プランクトンを食べることができないのに比べ、ワカサギはこれを食べることができます。ヒメマスの漁獲量がワカサギのそれに比べ極端に減少したのは、小型の動物プランクトンを食べることができるかできないかという食性のわずかな差が影響していると考えられます。
(3)ワカサギの導入と透明度
ハリナガミジンコは、大型から小型まで広範囲の大きさの植物プランクトンをエサとして大量に食べることができます。そのため1984年までの十和田湖の生態系は植物プランクトンのほとんどがハリナガミジンコに食べられ、それがヒメマスへと効率よく転換されていたと考えられます。
しかしワカサギが導入されると、大型のハリナガミジンコは急速に減少し、ヒメマスが食べられない小型のゾウミジンコが優占してしまいました。小型の動物プランクトンは、食べることのできるエサの大きさが限られ、量も少ないため、湖水中に残る植物プランクトンが増加し、これが透明度の低下をもたらしたと考えられます。


