気候モデルによる地球温暖化研究の成果から
Summary
地球上のさまざまな地域から、台風や豪雨、熱波、ハリケーンなどの異常気象が報告されています。原因として地球温暖化との関連性が指摘されていますが、その実態は科学的には解明されていない部分が多いといえるでしょう。将来このような異常気象が増加するかどうかを予測するには、より精度の高い気候モデルの計算が必要です。温暖化予測の基礎データとなる過去100年と未来100年の気候モデルの計算に取り組んだ、当研究プロジェクトの概要をご紹介します。
近年の昇温傾向は人間活動に起因
気候モデルを用いた地球温暖化予測では、使用する気候モデルの信頼性が重要になります。そこで、この分野においてはその一助として、20世紀の気候再現実験が行われてきました。しかし、従来の研究では、煤(すす)に代表される炭素性エアロゾルの増加など一部の重要な気候変動要因が加味されていないために、結果は不十分であるとされていました。
今回の研究プロジェクトで野沢徹主任研究員が主導した「20世紀の気候再現実験」は、いままで加味されなかった変動要因を最大限考慮して計算していることが、大きな特徴です。
考慮された気候変動要因は8つ。(1)太陽エネルギーの変動 (2)大規模火山噴火に伴い成層圏にまで到達したエアロゾルの変化 (3)温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハロカーボン)濃度の増加 (4)1970年代半ば以降の成層圏オゾン濃度の減少 (5)人間活動に伴う対流圏オゾン濃度の増加 (6)工業活動に伴う二酸化イオウ(硫酸エアロゾルの原因物質)排出量の増加 (7)人間活動に伴う煤などの炭素性エアロゾル排出量の増加 (8)土地利用変化((1)〜(2)は自然起源、(3)〜(8)は人為起源の気候変動要因)
「20世紀の気候再現実験」の結果、すべての気候変動要因を考慮した場合、モデルは20世紀前半(1901〜1950年)や近年(1971〜2000年)の温暖化傾向および20世紀中盤(1941〜1980年)の緩やかな寒冷化傾向を、地球全体で平均した地上気温だけでなくその地理分布も含め、きわめて正確に再現しています。これは世界に先駆けて、現状で考えられるほぼすべての気候変動要因を考慮した成果であると考えられます。例えば、20世紀中盤におけるアジアやアフリカ、南米での寒冷化傾向は、炭素性エアロゾルの増加を考慮することにより、その再現性が向上したことを確認しました(図4)。
観測された地上気温の変動要因を推定するために、人為起源のみ、自然起源のみなど、さまざまな気候変動要因を切り分けて実験を行った結果、1970年以降の顕著な温暖化傾向は、すべての気候変動要因を考慮した場合にはより正確に再現されていますが、自然起源の気候変動要因のみ考慮した場合には、まったく再現できていません(図2)。このことから、近年(20世紀最後の30年程度)の温暖化傾向は人間活動に伴うものであることが強く示唆されます。人為的な気候変動要因には、温室効果ガスの増加に伴う温暖化と、対流圏エアロゾルの増加による寒冷化とに大別されますが、前者が後者を大きく上回るために温暖化傾向が顕在化しているものと考えられます。
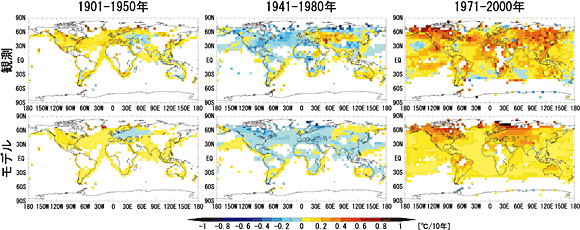
100年後の地球の気候を予見する
江守正多研究室長主導による「地球温暖化予測計算」は、2100年まで未来100年間の地球温暖化の見通しを予測するものです。このような気候モデル計算では、大気・海洋を格子に分割して解析します。格子の細かさを解像度といい、解像度を高くするほど詳細な予測が可能になります。640台のベクトル計算機を高速ネットワークで接続したスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使うことで、解像度が飛躍的に高まり、大気100km、海洋が20km程度まで、精度の高い予測計算が可能になりました。地球全体の大気・海洋を計算するものとしては、現時点(2006年1月)で世界最高の解像度を持っています。
1900〜2000年については、温室効果ガス濃度やエアロゾル排出量など野沢主任研究員のデータを与えて計算し、2001〜2100年は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が作成した将来シナリオの2パターンについて計算しています。一つは、未来社会が経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「A1B」(2100年の二酸化炭素濃度が720ppm)、もう一つは環境重視と仮定した「B1」(2100年の二酸化炭素濃度が550ppm)です。計算の結果、全地球平均の気温は過去30年(1970〜2000年)の平均に比べて、未来シナリオ「A1B」は4.0℃、「B1」は3.0℃上昇。降水量は前者が6.4%、後者が5.2%の増加となりました。大規模な地理分布では、北半球の高緯度地域で気温の上昇が大きいなど、従来からの予測と同様の結果が確認されました。
そして、2071〜2100年で平均した日本の夏の日平均気温はシナリオ「A1B」では4.2℃も上昇し、真夏日の日数も約70日増加(図5)。降水量も平均的に増加し、豪雨の頻度も高まると予測されました(図6)。これは、熱帯太平洋の昇温と関係して日本の南側が高気圧偏差となり、これが日本付近に低気圧偏差をもたらすと同時に暖かく湿った南西風をもたらすからです。さらに大陸の昇温と関連して日本の北側が上空で高気圧偏差となり、梅雨前線の北上を妨げることが主因とみられます(図7)。豪雨の頻度が高まるのは、大気中の水蒸気量が増加することで、ひと雨当たりの平均降雨量が増えるからと考えられます。
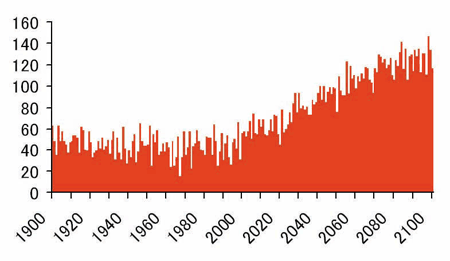
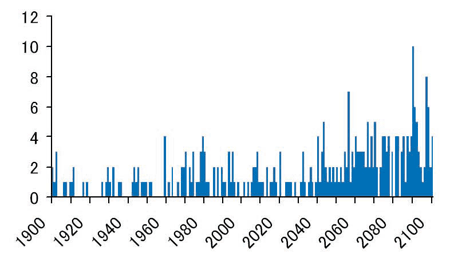
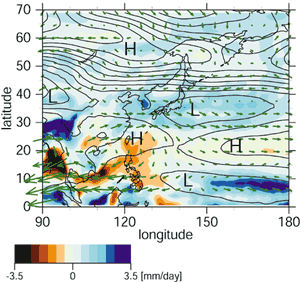
気候を予測し、精度を高める意義
気温上昇量の絶対値の予測には大きな不確実性があります。気候にもたらされる年々の自然の揺らぎは大きく、必ずしも真夏日や豪雨が年を追って単調に増加するとは限りません。同様に、特定の年の異常気象を地球温暖化と関連づけることもまた、難しいといえます。
「IPCC第3次評価報告書」(2001年)でも、気候モデルを用いた計算によって20世紀後半の昇温傾向は人間活動、前半は自然起源に起因するという可能性が指摘されていました。しかし、当時の計算では、いくつかの重要なプロセスや気候変動要因を考慮していませんでした。当研究では、それらの問題点を改善し、現状で考え得るほぼすべての気候変動要因を考慮していることで、従来の知見の信頼性をより高めることができています。
過去100年の地球の平均地上気温の変化を再現する「20世紀の気候再現実験」と、2100年までの未来100年に渡る見通しを予測する「地球温暖化予測計算」が、互いに相互補完的な役割をしていることも、当プロジェクトの大きなポイントといえるでしょう。
過去を検証して未来を予測する気候モデルによる地球温暖化研究は、21世紀の世界が進むべき方向を示す国際世論の形成に大きな影響を及ぼす重要な研究なのです。


