研究者に聞く
Interview
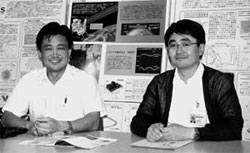
中島英彰(写真左)
成層圏オゾン層変動研究プロジェクト衛星観測研究チーム総合研究官
横田達也(写真右)
社会環境システム研究領域情報解析究室室長
成層圏オゾン層変動研究プロジェクト衛星観測研究チーム総合研究官
横田達也(写真右)
社会環境システム研究領域情報解析究室室長
人工衛星を使って「オゾン層変動の機構解明」の研究に取り組んでいる横田達也さん,中島英彰さんに,研究のねらい,成果などをお聞きました。現在,横田さんは衛星から送られてくるデータを解析する計算手法の高度化の研究,中島さんはオゾン層破壊機構の研究を続けています。
研究の動機
-
Q:昨年(2002年)12月に打ち上げられたADEOS-IIにはILAS-II(ILASの後継機)が搭載され,その運用も順調と聞きます。今後の成果が大いに期待されますが,まずILAS-IIの前身であるILASに始まった研究のきっかけからお願いします。横田:20年ほど前に顕在化したオゾン層破壊の問題は,原因となるフロン等の排出対策は進みましたが,オゾン層の破壊は現在なお進行中で,紫外線による人の健康や生態系への影響が懸念されています。これは地球規模の大気環境問題が,対策をとってもすぐには解決しないことを示しています。
さて,当時もっとも大きな地球環境問題であったこのオゾン層破壊に対して,日本でも「何か世界に貢献できることをしなければ」という気運が高まっていました。すでに南極のオゾンホールも観測されるなどオゾン層の研究は高まりを見せていましたが,オゾン層破壊のメカニズムを知る上で鍵となるオゾン濃度の詳細な高度分布は,オゾンゾンデやオゾンライダーなどによって地上の限られた地点でしか観測できませんでした。
そのような中,1988年に宇宙開発事業団が,地球環境を観測する人工衛星ADEOS搭載のセンサーの公募を行い,環境庁(当時)は,国立公害研究所(当時)の研究者と協力して大気を測るセンサーを提案しました。それがILASとして採択されたわけです。
当時私は環境情報部に所属し,電子計算機を用いて環境の研究をしていました。その手法の1つに,「人工衛星が観測する光が大気中をどのように伝わるかを計算するシミュレーションプログラム」がありました。それを使えば,センサーから得られたデータを元に,オゾンなどの高度別濃度を正確に見積もることができます。こうした計算機シミュレーションによってILAS装置の仕様を決めるための研究が必要となり,それを機にプロジェクトに参加しました。15年前の話です。
中島:私が国立環境研究所に入ったのは1997年の10月です。それまでは名古屋大学で成層圏や対流圏大気の研究をしていました。もともと人工衛星のデータは大気を直接測ったものではないため,信ぴょう性の確認が必要で,気球や飛行機からのデータと合わせて検証することが要求されます。ILASの場合,人工衛星の軌道の関係から北極や南極の付近しか観測しませんから,気球を使った実験は日本ではできません。そこで,1997年2〜3月にスウェーデンのキルナで行われた気球観測や地上分光観測の実験に大学のスタッフとして参加しました。ILASと関わるようになったのはその頃からです。
宇宙からの観測とアルゴリズム計算
-
Q:衛星を使って宇宙からオゾン層の観測を行っているんですね。どのような方法で行うのですか。横田:ILASによるオゾン観測には大きな特徴があります。これまでの多くの衛星搭載観測センサーは,宇宙から地球の方向に視野を向けて測っていました。しかしその方法では,地上から宇宙まで合計したオゾン量はわかっても,オゾンがどの高さにどれくらいあるかという高度分布の情報は測りにくいのです。私たちが開発したILASは,いわば宇宙から地球の大気層を横方向に「串刺し」に透かして太陽光線を観測する方法をとっています。つまり横方向から観測することで,衛星の動きによって観測する大気の高さが次々に変わるので,高度ごとの細かな情報を得ることができます。さらに光の通ってくる大気層の距離は長くなり,たとえば垂直に測れば1kmの厚さの大気層を水平方向に観測することにより約230kmにわたって観測することができます。つまり大気中に存在する気体をより多く通過した光のスペクトルを観測することにより,精度の高い観測ができるわけです。このような観測方式を太陽掩蔽法(たいようえんぺいほう)と呼んでいます。
-
Q:ILASが観測して,そこから地上に送られてきたデータはどうするのですか。横田:ここで求めようとしているのは高度別のオゾン濃度ですね。順に説明します。ILASには光を波長によって分ける分光器と,それによって分けられた波長別の光を受ける受光素子があります。大気層を透かしてみた太陽光は,オゾンなどの気体により特定の波長の光が吸収されて減衰します。受光素子はこの減衰した光を捉え,データとして地上に送ります。地上では,そのデータを大気を通さずに観測した太陽光のスペクトルデータと比較し,大気透過率を算出します。次に,あらかじめオゾン濃度などを想定したシミュレーションモデルで大気透過率を計算し,それらの条件をいろいろ変えた計算を繰り返して,最終的には送られてきた大気透過率とぴったりと合うようなオゾン濃度などを求める,というのが大きな流れです。
ところで,衛星から送られてくるデータの中にはちゃんと観測された信号とじゃまなノイズが混じっています。このことに注意しながらデータ処理を行い,正しい結果を出さなければなりません。つまり,計算結果が正確に大気の状況を表わしていることを科学的に示さなくてはならないのです。
そのようなさまざまな状態を想定しながら,ILASが実際に宇宙で測っているものにできるだけ近い状況を,計算機上に作り上げていきます。オゾン,メタン,水蒸気などの気体について,高さごとの濃度や大気の温度などを仮定してモデルに入れると,計算機がそれに応じたILASが観測するはずの大気透過率を理論的に算出します。次にILASが実際に観測した大気透過率(スペクトル情報)と比べて,それらの食い違いを小さくするように,仮定した大気中の気体の濃度を調整し直します。これを何度も繰り返して比較と調整を行い,もうこれ以上食い違いが小さくならないという状況になったときに,この仮定した濃度を現実の濃度として答え(処理結果)にします。このような解法を「非線形最小二乗推定法」と呼んでいます。 -
Q:衛星で観測した大気透過率を直接加工して答えを得るのではなく,観測した大気透過率と同じような大気透過率データを計算機を使って作り出し,それらを比べることで答えを出すのですか。横田:はいそうです。このような答えを導き出す手順というか,考え方をアルゴリズムと呼んでいます。
-
Q:アルゴリズムとは何ですか。横田:アルゴリズムは,コンピュータを利用してどのように問題を解決していくか,という考え方を表わしたものです。一つの例として,ILASの観測した大気透過率の計算アルゴリズムを紹介します。
物質はすべてそれ固有の波長の光や熱を吸収する性質を持っています。そうですね,赤い花を頭に浮かべてください。可視光が当たると赤い色以外の光を吸収し,赤い色を反射するので,私たちは反射して目に入った赤を認識し,「赤い花」だとわかるのです。ILASは太陽光線を分光(プリズムが太陽光を虹の7色に分割するように波長別の光に分けること)して観測します。ターゲットのオゾン,メタンなどが大気中にあれば,それ固有の波長のところに光の吸収(吸収線)が現われますら,成分ごとの濃度がわかります。ILASの観測する赤外波長帯(6〜12μm)の範囲にはいろいろな物質の吸収線が数十万本もあります。これらの1本1本について吸収量を計算します(図1緑線)。さらに観測装置特性などを含めて計算して出てきた結果がこのスペクトルです(図1赤線)。吸収線の数が非常に多いことからもこれを得るまでにはたいへんな計算が必要なことがおわかりと思います。それらをいかに精度を落とさず,しかもむだなくスムーズに計算していくかを考えるのが計算アルゴリズムのプログラミングの技術です。アルゴリズムは常に進歩していかなければなりません。
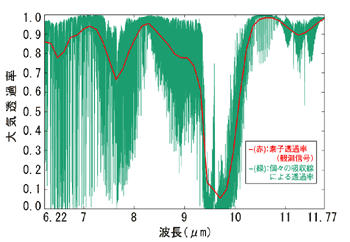
図1 大気透過率と吸収線のシミュレーション計算例
-
Q:どのように進歩していくのですか。横田:たとえばILASが最初に観測した1996年9月18日の赤外観測スペクトルですが(図2),観測したものが赤,計算したものが青で示されています。けっこう一致しているように見えますが,少しずれている部分もあります。この解析によって求めたオゾンや硝酸の濃度は他の手法の方法で観測したデータと比較的よく一致していましたが,二酸化窒素や水蒸気については思いもよらない値が出てしまいました。対応に四苦八苦していたとき,当時プロジェクトに招へいしていたアメリカ・デンバー大学のBlatherwick博士から「6μm付近に酸素の吸収があるはず」と指摘され,アルゴリズムを修正して計算したところ,水蒸気と二酸化窒素の解析結果が格段によくなりました。さらに数年後,水の連続吸収に関する新しい理論式をアルゴリズムに取り入れたところ,低い高度での二酸化窒素のデータがさらによくなりました。気体による光の吸収量を計算するための,室内実験に基づく吸収線に関するデータも年々改訂されています。このように,理論を現実に近づけるためにはバージョンアップの作業を続けていく研究が必要となります。この一つひとつが進歩といえます。
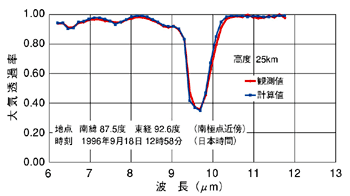
図2 ILASによる初観測データ(赤外波長域)
オゾン層破壊について,ILASデータの解析から
-
Q:アルゴリズムに関してはおぼろげながら理解できました。次にILASのデータから見えてきたことを教えて下さい。中島:最近,極成層圏雲(PSC)という特殊な雲がオゾン層破壊に重要な役割を果たしていることがわかってきました。PSCは高さ15〜20kmの成層圏にできる硝酸や水蒸気などから成る雲で,南極や北極で発生します。これらの地域は,冬の間一日中太陽が地平線から顔を出さない極夜になり,上空の成層圏は−80℃以下の低温にまで下がります。PSCはそのような条件下で発生します。私たちはILASによってPSCに取り込まれる気体濃度の変動の様子と雲の成長の様子を,非常に精密に観測することができました。
また,ILASが観測を行った1997年の2月から4月にかけて,北極域でこれまでにないほど大きなオゾン破壊が起こり,その状態をILASが高度別に連続して観測することに成功しました。衛星からのオゾン破壊とPSC,さらにそれを構成するガスの同時観測は,世界的に見ても初めての例で,ILASだから可能となったものです。しかも,その後観測データの詳細な解析を行い,オゾン層破壊の速度を求めることにも成功しました。
ILASは1日14回北極上空を観測します。その時に太陽掩蔽法により1km四方で長さ230kmの空気層を順次測定します。数日間観測を続けるうちに,北極上空にある空気塊は移動しますが,これを流跡線解析という手法で計算し,流れてゆく空気塊中の組成変化を追いかけます。具体的には衛星が観測を行った空気塊について複数のペア(日にちを変えて観測した,同じと思われる観測空気塊のペア)を選び出し,それらのオゾン濃度の観測値を比較(マッチ解析と呼ぶ)します。これによって,時間とともにオゾンが破壊されていく速度を見積もっていくわけです。
これまで多数のオゾンゾンデ観測データを使い,マッチ解析によってオゾンの破壊速度を導き出した例はありましたが,宇宙から観測を行う衛星センサーでは「高度分解能が粗いため同様な解析は不可能だろう」というのが世界の研究者の一般的な考えでした。この困難な解析をILASでは,比較的高い高度分解能と数多くの観測データの解析を行うことで成功させたのです。
さらに,ILASがPSCを観測した数日後に,その空気塊が流れていった場所でオゾンが破壊されていることも突き止め,まさに理論的に予測されたことを初めて観測で明らかにすることができました。 -
Q:なんかすごいですね。ところでILASの観測地点はいつも同じなのですか。中島:地球は自転していますから、少しずつずれていきます。
-
Q:流れる風の傾向もまちまちだと思いますが中島:それらを全部計算します。この風は北極を1周するのにおよそ1週間から10日くらいかかります。
-
Q:その解析を3カ月分行ったのですね。中島:はい。図3は,それらすべての解析結果をまとめて1枚の図に描いたものです。この絵(図3)が最初にできあがった時には,「やった」と思いました。また,多くの海外の研究者からもこの結果は高く評価されました。衛星によるマッチ解析が可能であるということを,世界に先がけて示したわけです。この結果は,ILAS観測の大きな成果の一つです。
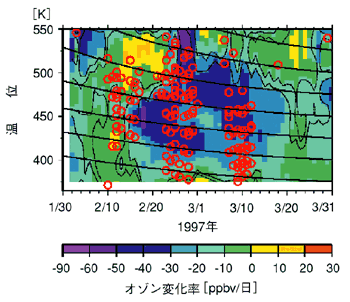
図3 ILAS観測によって明らかになった1997年初期の北半球高緯度でのオゾン変化率
ILASプロジェクトの協力体制
-
Q:ILASプロジェクトは15年続いています。その間,実際の研究以外に衛星センサーといったハードの開発など,かなり幅の広い活動が要求されたと思います。苦労話をお聞かせ下さい。横田:ILASでの衛星観測としての太陽掩蔽法,そしてそれを専用に解析するコンピュータシステムの開発など,これらはすべて日本で初めて行うもので,試行錯誤の連続でした。もともとこのプロジェクトは環境庁(当時)のリーダーシップの下に開始されたものですが,準備段階からILASセンサーの概念,基本仕様などに関しては国内外の各大学や国立研究機関の研究者の助言を得ながら,事実上国立公害研究所(当時)が引っ張ってきたという歴史があります。プロジェクトの中心にいたのは衛星観測研究チームの総合研究官だった笹野泰弘さん(現:大気圏環境研究領域長,成層圏オゾン層変動研究プロジェクトリーダー)でした。ILASがADEOSのセンサーとして採択された後,1990年から笹野さんがリーダーとなってプロジェクトを推進し,国内外の研究者を組織化しました。その結果ILASのデータを有効に活用することができ,オゾン層破壊の解明に一歩も二歩も近づいてきました。この功績は非常に大きいと思います。
今回の研究では民間との協力体制の構築も大きな役割を果たしました。たとえば,重要なテーマであったアルゴリズムのソフトウェア化を担当した富士通エフ・アイ・ピーは,開発当初から現在までずっと常駐してプログラミングの構築,バージョンアップを続けています。また当時の研究員の話ですが,鈴木睦さん(現:宇宙開発事業団)は機器のハードウェアに強く,ILASを製作した松下技研(当時)と密にコンタクトを取って指導していました。鈴木さんは計算機に関しても詳しい方で,当時高速計算にはスーパーコンピュータが主流という中,ILASのデータ処理には小さなコンピュータを並列して使用する分散処理計算機の方が向いているという結論を出し,日本で初めてIBMの並列処理計算機を本格的に利用した処理システムを導入しました。
導入した計算機システムは,そのままでは持てる性能を十分には発揮しません。鈴木さんは日本IBMの基礎研究所の方と協力してプログラムの高速化を行いました。そういった先人の苦労話はたくさんあります。 -
Q:最近ではどうですか。横田:ILAS-IIからの初めての観測データが今年の1月20日に取得されました。ところがその前日にコンピュータがダウンしたのです。当日朝一番に計算機メーカーの人にきてもらって調べてもらったところ,一番大事な計算機の基板がだめになっていたのです。メーカーの人に探してもらったら,運良く在庫が水戸にあったのでバイク便で送ってもらい修理が完了しました。データチェックの開始は3時間ほど遅れましたが,なんとか事なきを得ました。最先端といわれる研究ですが,実はバイク便の助けが必要だったんですよ(笑!)。
中島:ILAS-IIの検証実験はこれからです。来年の3月,4月にスウェーデンのキルナで行う計画になっています。そこからまた何か新しい知見が生まれるかも知れません。たいへん楽しみです。 -
Q:期待しています。ありがとうございました。
メモ
-
流跡線解析とはある時刻にある地点・ある高度にあった空気塊が,時間とともにどのように流れていくかを全球気象データの3次元風速を元に追跡し,別の時刻にはどの場所のどの高度にあるかという計算を行う手法。
-
オゾンの話:地球と大気の関係酸素分子(O2)は安定した物質ですが,紫外線など強烈なエネルギーが加わると反応が起こってオゾン(O3)が生成します。オゾンは酸化力が強く,その特性を利用して業務用では殺菌・消毒・脱臭に使用されていますが,都市大気中では目やのどの痛みを引き起こす光化学オキシダントの主成分として知られており,人体には有害な物質です。
一方,高度10〜60kmにある成層圏ではオゾンは有害な紫外線をカットするフィルターの役割を果たしています。遺伝子の構成物質であるDNAの吸収波長とオゾンの吸収波長がよく一致しているので,結果的にオゾンが生物にとって有害な紫外線を防いでくれるのです。
大気中のオゾンの90%は成層圏にあり,残り10%は地上から高度10kmくらいまでの対流圏にあるといわれています。オゾンは赤道周辺の上部成層圏で発生します。ところがそこに留まらず,大気とともに高緯度地域へ運ばれ,下降するにつれて数十倍に圧縮されます。その結果,高緯度地域の下部成層圏は高濃度のオゾンがたまることになります。これがオゾン層です。
オゾンの全量を表わすには,大気中のオゾン全体を地上の標準状態(0℃,1気圧)に圧縮したと仮定して,その厚さをcmで表わし,さらに1000倍した値を使います。これを,ドブソン・ユニット(DU)と呼びます。
大気全体を標準状態に圧縮した場合,その厚さは約8kmに相当しますが,オゾン全量は500DU以下ですので,厚さは5mmにもなりません。ちなみに地球の直径は約12,700kmですが,地球の大気の厚さは成層圏まで含めても地上から約50km程度です。地球と大気はまるでリンゴとリンゴの皮ともいえます。その皮のさらにほんの薄層に当たるのがオゾン層です。このように,私たちはまさに薄氷のようなオゾン層によって有害な紫外線から守られていることがわかります。


