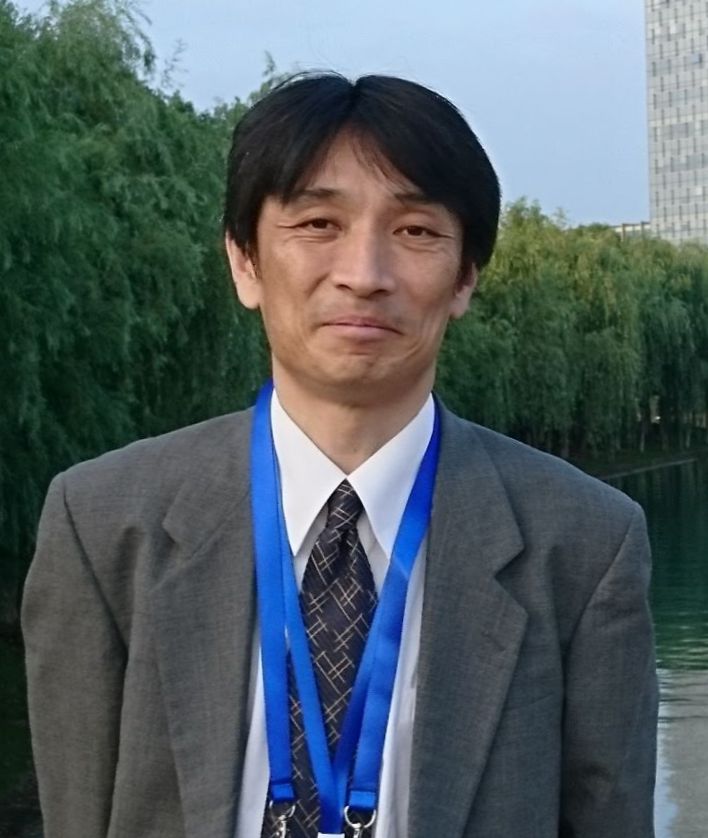- 予算区分
- 5-2501
- 研究課題コード
- 2527BA006
- 開始/終了年度
- 2025~2027年
- キーワード(日本語)
- 黄砂,モニタリング,経済影響
- キーワード(英語)
- Asian dust,monitoring,economic impact
研究概要
黄砂の発生および飛来量は、気象や発生源の地表面状態に大きく左右され、年によって大きく変動す る。2021 年の大規模黄砂、2022 年冬季の黄砂など激甚化やレジームシフトの影響が指摘されているが、 この変動を駆動する要因は明らかにされていない。そのため、現在の黄砂予測では年々変動や特異な黄 砂現象を定量的に予測できていない。黄砂は呼吸器系疾患に代表される様々な健康被害を引き起こす。 PM2.5 における黄砂の寄与の増加が指摘されているが、黄砂による社会経済コストの評価は行われてい ない。また、我が国は砂漠化対処条約に基づき、黄砂発生源国の対策支援義務を負っており、効果的な黄 砂発生源対策の立案と実証が求められている。
本課題では、「予測」「影響評価」「対策立案」の一連の流れを研究目的とした。地理情報システム(GIS)を用いることで、数値モデル、現地調査、衛星計測、地上モニタリングで得られた様々なデータを一つの 空間情報として統合する。統合されたデータベースを活用し、気象、地表面状態など様々な側面から黄砂 の年々変動のメカニズムを解明する。その結果から2〜3ヶ月先の黄砂の活発度を予測する黄砂中期予 測システムを開発する。健康便益評価ソフトを応用し、黄砂による死亡・通院等が経済に与える影響を評 価するシステムを開発し、黄砂による経済コストの推移を評価する。黄砂が大量に発生する地域(経済 性)、現地の植生やその特性(地域性)、経済コスト低減効果(効率性)を考慮した発生源対策に資する候 補地選定手法を確立させる。 本研究の成果は、予測の実施により国民生活の改善・健康維持に寄与し、黄砂飛来量の削減及び黄砂に よる経済被害減少に資する政策への反映が期待できる。また、日中韓黄砂共同研究(TEMM-DSS)、世界 気象機関砂塵嵐警戒評価計画、砂漠化対処条約関連事業といった国際的な取り組みにも貢献することが できる。(以上は推進費全体の概要)
研究の性格
- 主たるもの:応用科学研究
- 従たるもの:モニタリング・研究基盤整備
全体計画
ライダー観測ネットワーク(AD-Net)、大気環境常時測定監視局(AEROS)におけるエアロゾル観測データを収集し、PM2.5 濃度に対する黄砂の寄与割合を評価し、その推移を明らかにする。それらの黄砂観測データから、日本に飛来する黄砂の水平・鉛直分布の年々変動について明らかにする。大気汚染便益評価ツールを黄砂に応用することで、黄砂による経済影響を評価手法の開発を行う。数値モデルによるシミュレーション結果やモニタリングで得られたデータを入力することで黄砂の経済影響を推計する。発生源の変動による将来予測結果も利用して経済影響の推移を評価する。
今年度の研究概要
ライダー観測ネットワーク(AD-Net)、大気環境常時測定監視局(AEROS)のPM2.5およびSPM濃度データ、韓国のPM2.5およびPM10濃度データを収集 し、GIS 統合データベース上に整備する。PM2.5 と SPM濃度、PM2.5とPM10濃度からPM2.5 濃度における黄砂の寄与割合を推定する手法を開発する。経済影響評価を行うために、アメリカ環境保護局(EPA)で開発された健康便益評価モデル(BenMAP-CE)を導入し、黄砂データを利用できるようにする。
外部との連携
本研究は九州大学応用力学研究所の弓本桂也教授が研究代表者を務める推進費5-2501「数値モデル、現地調査、衛星計測を統合した黄砂の中期予測、経済影響評価手法及び発生源対策立案手法の開発」のサブテーマ4として実施する。その他のサブテーマ担当機関は気象庁気象研究所、東京大学、鳥取大学、山口大学、千葉大学、筑波大学である。