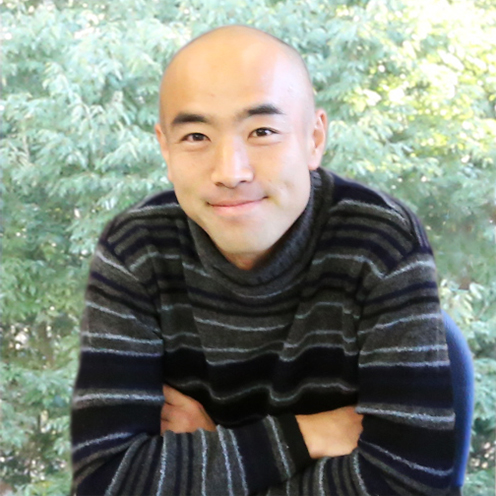- 予算区分
- 2-2401
- 研究課題コード
- 2426BA003
- 開始/終了年度
- 2024~2026年
- キーワード(日本語)
- 気候変動,極端現象,適応
- キーワード(英語)
- climate change,extreme events,adaptaion
研究概要
社会や生態系に影響する気象・気候現象(CID: climatic impact-driver,気候影響駆動要因)は,複数のものが同時,連続または多地点で発生(複合CID)すると,単独の時より影響が大きくなり得る。また,単独のCIDの極端なものは,多くの場合複数の気象・気候条件の複合(複合気象・気候要因)によって生ずる。さらに,グローバル化が進む中で,複数地点でのCIDの同時発生が輸入価格の高騰など社会的に大きな影響をもたらしうる。気候変動により気象災害が頻発化・激甚化するなか,これらの「複合現象」の実態把握と予測を行い,影響評価や適応策に反映する必要性の認識が高まっている。しかし,日本やアジア太平洋域を対象とする複合現象の研究はまだ乏しい。
本研究では,再解析データや観測データ,CMIP6やd4PDFなどの現在および将来気候についての膨大なシミュレーションデータにもとづき,日本とアジア太平洋域の複合現象を対象とした研究を展開する。影響評価にとって重要なCIDの情報を整理し,複合CIDが再解析データや気候モデル実験データの中でどう表れるか,関係する気象・気候要因は何か, どう将来変化するのかを示す。さらに,複合気象・気候要因がCIDの発生頻度や強度にどのように影響するかを定量化し, メカニズムを明らかにする。
本研究は,査読付き論文等を通じて科学的な情報を提供し,IPCC等の,環境問題や適応政策に関する国際的な枠組みに貢献する。また,影響評価研究者に対し,気候変動による自然災害への影響等に関する研究を行う際に有用な情報を提供する。これらを通して適応策等の環境政策に貢献し,公開講座等を通して社会にわかりやすく情報を発信する。
研究の性格
- 主たるもの:基礎科学研究
- 従たるもの:応用科学研究
全体計画
文献調査や影響評価研究者との情報交換を行って,日本やアジア太平洋域における気候影響駆動要因(CID)の情報を収集・整理し,課題全体に共有することで,分析する気候変数や極端気象現象,地域,季節などを選択するための情報を与える。その上で,いくつかの影響評価分野(例えば農業や火災など)を取り上げて,その分野で重要なCIDの複合現象の発生頻度や強度がどのように変化するのかを,気候モデル実験出力データ(CMIP6, d4PDF等)や観測データ,再解析データ等の分析から明らかにする。得られた知見を,サブテーマ1-3と協力して影響評価・適応研究者やA-PLAT, AP-PLATに提供する。
今年度の研究概要
文献調査や影響評価研究者との情報交換等を通じて,日本・アジア太平洋域の影響評価研究と適応策検討において重要なCIDの抽出を行って課題全体に情報提供する。影響評価にとって重要な場所や季節(例えば農産物の主要生産地や栽培期間)等の情報も整理して提供する。また,観測データ,再解析データ,気候モデル実験データ等を収集し,予備解析を行う。
外部との連携
研究代表者:堀之内 武(北海道大学)