流域からの栄養塩の流入変動と海域生態系変質に関する研究
Summary
東アジアを中心として、流域での施肥・消費の増加とダム建設・流路改変の複合作用が窒素、リン、ケイ素の流下に影響しさらに海域生態系を変質させることが懸念されます(シリカ欠損仮説)。国立環境研究所では、この仮説の検証をキーワードとし、モデル水系として琵琶湖-淀川-瀬戸内海を選び、主に地球環境総合推進費による研究を行ってきました(「研究のあゆみ」)。ここではその主要部分のあらましをご紹介します。
陸の静水域では
琵琶湖を仮想大ダム湖と想定して、流入河川(野洲川など)、流出河川(瀬田川など)で計測を行った結果、流入する溶存ケイ酸(DSi)の7-8割が琵琶湖でトラップされることが確認できました。一方、信州大学による信濃川水系の犀川ダムでは、DSiの減損は低流量期をのぞいて顕著でなかったことから、シリカ欠損は静水域の平均滞留時間(容積/流量)が比較的長い場合に顕著になることが確認できました。
瀬戸内海、特に播磨灘では
瀬戸内海域について、フェリーの連続取水系を利用して各栄養塩などを長期・高頻度で観測しました。経度区画ごとに長期平均をとると(図4)、各栄養塩ともに「東高西低」で、N、P流入などの人為影響が阪神地域側で強いことがわかります。「海域のシリカ欠損指標」を、DSi流入河川水のDSi保存性を仮定した場合のあり得べき値とDSi観測値との差で定義すると、これが「西高東低」となり、海域へのN、P流入もシリカ欠損につながることがみてとれます。
全データのうち、播磨灘中央部の各栄養塩データの時系列的変化をみると(図5)、各栄養塩ともに、冬季に高くその後早春にかけて減ってゆくことがわかります。見やすくするため、DIN、DSiをそれぞれ横軸、縦軸として1年間の季節変化の軌跡を示したのが図6です。ここで定義した「DSi切片」がマイナスであれば春季ブルーム終了時にDSiが枯渇してDINが残ることになり、ケイ藻が不利になると推定されます。
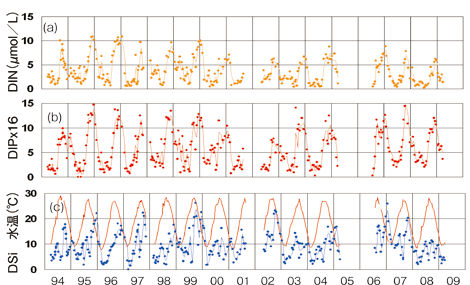
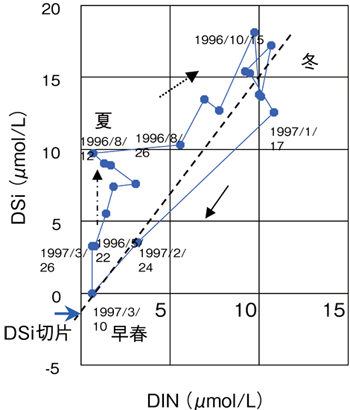
DIN、DSi年平均値と「DSi切片」の長期変化
DINとDSiの各年の年間平均値を時系列表示すると(図7)、DINが長期的に減少してきたことがわかります。DSi年平均値は振れが大きいですが漸増といえるでしょう。ただし、両データをみるとDSiのほうがDINより明らかに高く、一見シリカ欠損が起こりそうにありません。ところが、前述のDSi切片は増加傾向、すなわち1990年代ではマイナスだったのが2000年代からプラスに転じたことがみてとれます。すなわち、春季ブルーム終了時にDSiが枯渇する傾向があったが、現今ではDINが枯渇するようになったことが推定されます。鍵は春季大増殖期間の両栄養塩の減率比Δ DSi/ Δ DIN(図6中の破線の傾き)が1.5~2であり、レッドフィールド比の定説値(N/:Si≒1)より大幅に大きかったことにあります。
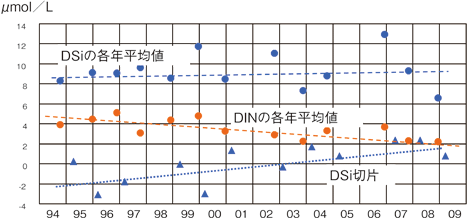
有害赤潮との因果関係は?
水産庁の「瀬戸内海の赤潮」によれば、1970年代に顕著だった渦鞭毛藻赤潮の発生が長期的に減少傾向にあります。一方、近年はケイ藻赤潮が盛んになり、養殖ノリの色落ちの原因ではとの推測もあります。また、行政施策もあってNとPの流入は減りつつあります。このような長期的な事象の符合から、進行基調でなく回復基調についてですが、「シリカ欠損仮説」は概ね検証されたといえるでしょう。ただし、以下のように、一見この仮説と矛盾するようなポイントもみられました。「瀬戸内海の赤潮」で読みとれるケイ藻赤潮/非ケイ藻赤潮の各発生場所(図8)とDSi/DIN比の分布(図4)を比べると、東端の大阪湾奥では、DSi/DIN相対比が最低であるのにケイ藻赤潮が基調です。また、非ケイ藻類による有害赤潮が起こるのは主に夏ですが、実はこの時期にはDSi/DIN比は高くなっているので(図8)、これも一見シリカ欠損仮説と矛盾します。
1つ目のポイントについては次のように説明できるでしょう。大阪湾東部については、DSiが琵琶湖で低下したとはいっても淀川経由で常時流入するのでケイ藻が不利になりません。事実、淀川河口から離れてなおかつDSi/DIN比がある程度低い播磨灘が非ケイ藻赤潮がよく起こる海域になっています。
2つ目のポイントについては、ビェンファンら(1982)によって明らかにされた「円心ケイ藻は、栄養塩、特にDSiが枯渇すると沈降を速める」という実験結果から説明できるかもしれません。すなわち、春にDSiが枯渇するとケイ藻が沈降して上層で希薄になってしまい、その後のDSiの河川流入でDSi/DIN比が高い状態になります。この状態で、ケイ藻類の後塵を拝していた非ケイ藻類が増殖できるようになります。少なくともN、Pの増減だけでは非ケイ藻赤潮の発生は説明できません。そして、フェリーの利用で、季節サイクルとその経年変化を観測できたことにより、実態が観やすくなったといえるでしょう。
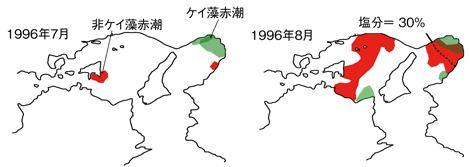
クラゲ増加との因果関係は?
リチャードソン(2010)による「クラゲの暴走」という総説論文は、その人為的影響要因として、i)富栄養化によるクラゲの餌増加、ii)クラゲ幼生付着場所の増加、iii)クラゲと競合関係にある魚への漁獲圧、iv)貧酸素海域拡大(クラゲのほうが魚より貧酸素耐性がある)などと同時に、v)シリカ減少説を挙げています。すなわち、シリカ潤沢時の「高活性食物連鎖」(図1右上部分)が、シリカの低下につれて「低活性食物連鎖」(図2右上部分)に移り変わるという説です。この総説では、「研究者に聞く!!」脚注1)の論文が引用されているので、この研究もなにがしかの貢献になったといえるでしょう。ただし、人為影響要因のほとんどが魚よりクラゲに有利に働くので、シリカ減少による事象だけを取り出すことが難しく、今後の研究に残された課題が大きいといえるでしょう。


