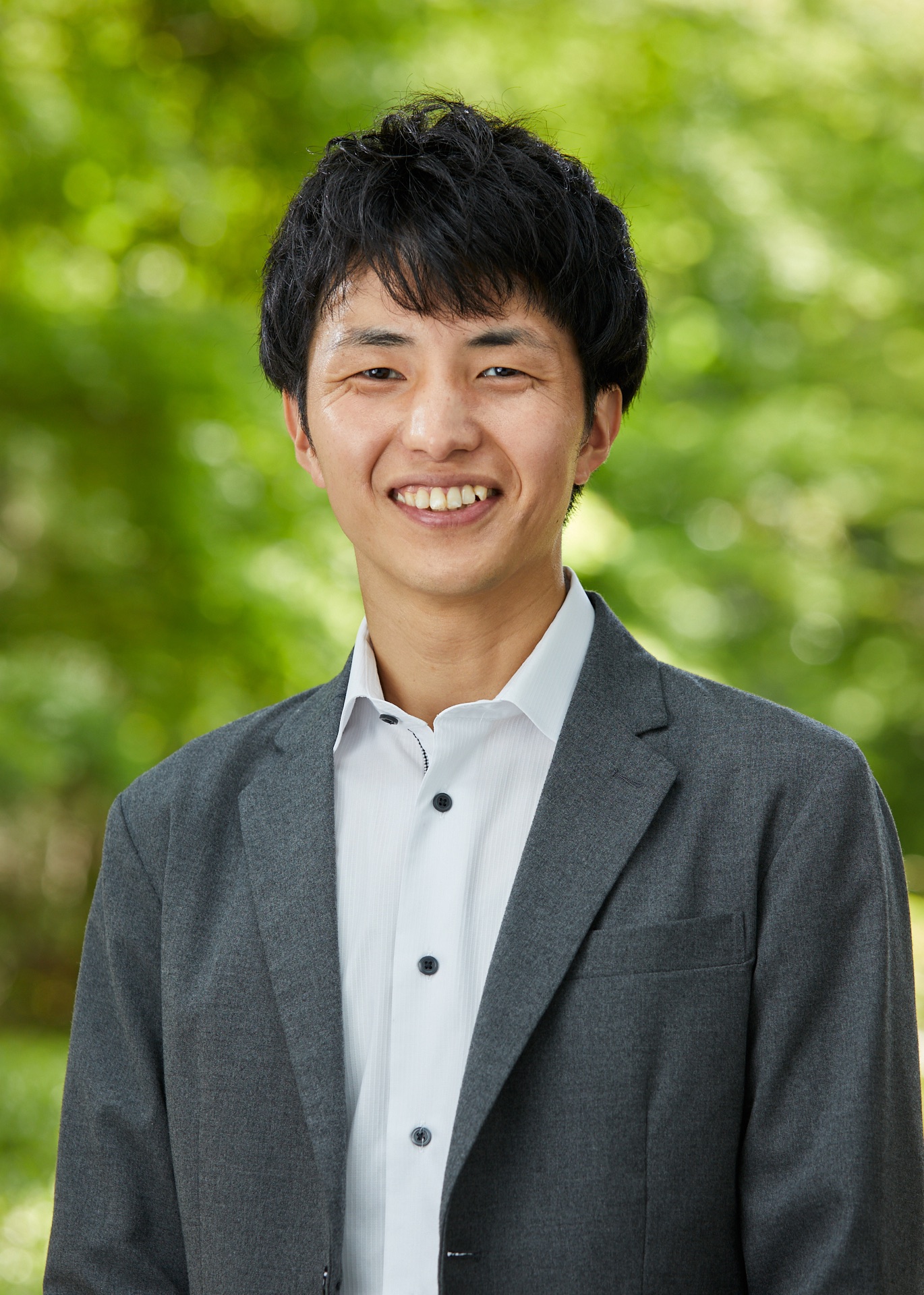- 予算区分
- 海外特別研究員
- 研究課題コード
- 2527ZZ001
- 開始/終了年度
- 2025~2027年
- キーワード(日本語)
- Japan nested-MRIO,トリプルクライシス,フットプリント分析
- キーワード(英語)
- Japan nested-MRIO,Triple Planegary Crisis,Footprint analysis
研究概要
シドニー大学統合持続可能性研究センターにJSPS海外特別研究員として在籍し、脱炭素社会に向けた物質フロー転換が国内外の地域に与える「地球の三重危機」への影響を地⽅⾏政単位で定量化するモデルを構築し、プラネタリーヘルスと整合する地域経済とその達成経路を明らかにする研究を実施する。派遣先機関で研究する意義は、世界有数の多地域間産業連関(MRIO)作成機関における研究活動、世界最高峰の国際共同研究ネットーワークへの参画、の2点に集約される。派遣先機関は世界最高レベルの研究成果を継続的に発信し続けているだけでなく、国連やIPCC、国際政府機関への貢献も多く、学術成果を政策立案者への提言に昇華させる点でも類稀な実績がある。その結果、国内外からも優秀な研究者や留学生が集まり、高いレベルでの成果発信を支えている。そのため、派遣先機関は本研究課題による成果の質と発信の双方を最大化する上で、最適な環境であると言える。
研究の性格
- 主たるもの:応用科学研究
- 従たるもの:基礎科学研究
全体計画
本研究課題の⽬的は、⽇本が脱炭素社会を達成する物質フローの転換経路を特定し、その過程で地域経済(産業・消費)が受ける影響を定量化することである。加えて、脱炭素社会に向けた物質フローの転換が、同時にプラネタリーヘルス達成とも整合しているか検証することである。システム⼯学と数理計画法を基本とする(1)Japan-Australia nested-MRIOの開発、(2)物質フロー・「地球の三重危機」データベース開発、(3)Planetary healthと整合する転換経路探索、(4)政策・対策の提言、の手順により、上記の⽬的を達成する。なお、地域の産業構造を考慮した物質管理⽬標と地⽅⾏政単位での物質フロー転換への適応策に関する提⾔を⽬指し、対象とする国内の地⽅⾏政単位は政令指定都市(20 都市)とそれ以外の地域を都道府県(47地域)に集約した67地域とする。また、国外は物質フロー転換による影響主体となりうる主要な資源産出国および⽇本の主要な輸⼊相⼿国(中国・⽶国・豪州)を含む163 カ国とする。さらに、国外地域への影響分析の事例として、⽇本への資源の輸出量、「地球の三重危機」への影響およびデータの⼊⼿可能性を考慮し、豪州を州および特別地域(7 地域)に分割する。2050 年の脱炭素社会達成に向けた物質フロー転換経路を最適化計算によって特定し、国内外の地域の経済影響および「地球の三重危機」への影響を定量化する。なお派遣期間を考慮し、本研究では「地球の三重危機」への影響指標は、気候変動については「GHG排出量」、⾃然と⽣物多様性損失については「⽣物多様性損失」、⼤気汚染と廃棄物については「PM2.5(空気動⼒学径2.5μm以下の粒⼦状物質)発⽣量」を対象とする。なお、研究初年は3⽉〜9⽉に⼿順(1)、10⽉〜翌年2⽉に⼿順(2)に注⼒しnested-MRIO とインベントリデータ完成を⽬指す。最終年は 3 ⽉〜9 ⽉に⼿順(3)の最適化モデルの構築、同年10⽉〜12⽉にその分析に注⼒し、翌年1⽉〜2⽉に⼿順(4)における戦略・対策オプションを整備する。
今年度の研究概要
本年度は、派遣先機関と共同で、(1)Japan-Australia nested-MRIOの開発に着手する。
外部との連携
シドニー大学(オーストラリア)
- 関連する研究課題
- 27206 : PJ1_物質フローの重要転換経路の探究と社会的順応策の設計
- : 資源循環分野(ア先見的・先端的な基礎研究)
- 27246 : 社会システム分野(ア先見的・先端的な基礎研究)
課題代表者
畑 奬
- 社会システム領域
脱炭素対策評価研究室 - 研究員
- 博士(環境学)
- システム工学,土木工学