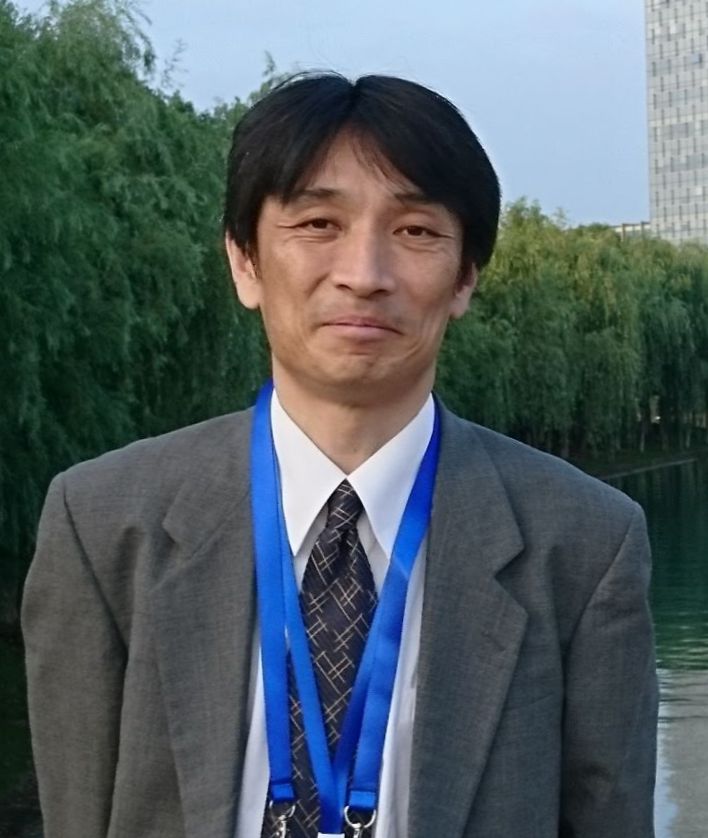- 研究課題コード
- 2427CD001
- 開始/終了年度
- 2024~2027年
- キーワード(日本語)
- 大規模火山噴火,火山噴出物,広域分布検出
- キーワード(英語)
- giant volcanic eruptions,volcanic products,wide area detection
研究概要
火山噴火に際しては,地下のマグマ蓄積量の評価から噴火活動の終了予測につなげるために噴出物の計測が必要である.一方,大規模噴火の発生により火山近傍の観測施設は破壊され計測が困難となることが想定される.したがって,火山から十分離れた場所にて広範囲で高密度かつ高頻度で計測する手法の確立が必要となる.本研究では,遠方まで拡散する火山噴出物である火山灰と火山ガスの噴出量を日本列島に分布する観測網にて把握する.そのために,大気汚染物質観測網にて火山灰と火山ガスの測定手法を,地震観測網とインフラサウンド観測網にて観測される振動から火山灰と火山ガスの放出量を間接的に推定する手法を開発する.観測網が充実しており噴火が頻発している桜島火山を手法の開発および検証の対象とする.
研究の性格
- 主たるもの:応用科学研究
- 従たるもの:技術開発・評価
全体計画
広域での火山噴火影響を検出するシステムとしてA.広域火山放出物監視システム、B.広域噴火励起地震監視システム、C.広域噴火励起音波監視システム、の3種を構築する。このうちA.広域火山放出物監視システム(国立環境研究所・京都大学防災研究所)では、大気汚染状況監視システム(そらまめくん)によるSPM/PM2.5/SO2広域観測データと桜島周辺に配置されたエアロゾルライダーデータ・地上設置の微粒子検出計(OPC)を用いて火山噴出物の分布・濃度を推定する。そらまめについては過去の大規模噴火に準ずるイベントのデータ解析から外部要因を配して火山由来の影響を広域で検出する手法を検討する。微粒子検出計は太陽電池パネル装備・携帯電話網通信により完全に自立した観測を行えるものとし、当初は桜島火山観測所において性能評価やライダーとの比較を行い、その後は桜島周辺に各種風向にも対応できる配置を検討してネットワーク化を行う。
今年度の研究概要
国立環境研究所では、既存の大気汚染状況監視システム(そらまめくん)のPM2.5/SPM/SO2データから広域における火山噴火影響を他の大気汚染要素から分離して検出する手法を開発する。小型可搬型の微小粒子検出装置を桜島周辺に配置して火山灰を検出することで、既存のライダーシステムによる火山灰観測との対応を明らかにする。
外部との連携
本研究の課題代表者は京都大学防災研究所の中道治久教授であり全体の取りまとめと火山噴火活動の観測・解析を行う。インフラサウンドによる大規模噴火広域観測は、高知工科大学の山本真行教授が担当する。
- 関連する研究課題
課題代表者
清水 厚
- 地域環境保全領域
広域大気研究室 - 上級主幹研究員
- 博士(理学)
- 物理学,地学