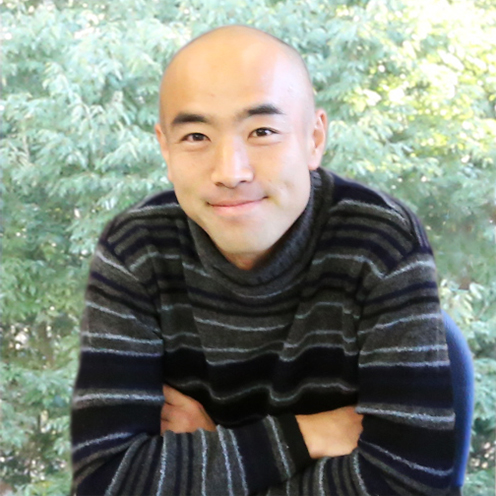- 予算区分
- JPMEERF20241001
- 研究課題コード
- 2426BA001
- 開始/終了年度
- 2024~2026年
- キーワード(日本語)
- 二酸化炭素除去,シナリオ分析,気候変動,脱炭素,緩和策
- キーワード(英語)
- Carbon dioxide removal,Scenario analyses,Climatic change,Decarbonization,Mitigation
研究概要
全球平均気温上昇を1.5℃以内に抑える所謂1.5℃目標が国際社会の共通の気候目標となっている。1.5℃目標の達成には、温室効果ガス(GHG)排出削減だけでなく、二酸化炭素除去技術(CDR)を用いて大気中からCO2を大規模に吸収する必要があるとされ、その規模は10GtCO2/年レベルと推計されている。こういった知見の創出には統合評価モデルという将来のGHG排出やエネルギー等を推計するモデルが用いられる。しかし、既存研究は、?CDR技術の種類が限られる、?CDRの量や技術の選択により生じる生物多様性等の気候変動以外の地球環境問題や貧困等の開発問題への波及的影響が不明、という課題がある。
そこで本研究は、日本を含む世界を対象として長期気候安定化を目指す排出パス、それを実現するCDRの選択肢、及びその社会・経済・環境の含意を提示する。そのために各種CDR技術の導入量と共にエネルギーや土地利用などの社会・経済・環境に関わる指標を現状から2100年までの複数の定量的シナリオとして示す。本研究は、日本国内の2030-40年の排出削減目標、2050年の長期目標の評価・再検討に対する情報提供、IPCC等の国際的な報告書への研究知見のインプット等を通じて、環境行政へ貢献する。
定量化作業には統合評価モデルAIMを用い、以下2点を新たに開発する。その第一は、新しいCDR技術をエネルギー・土地利用・経済モデルに実装する点であり、その第二は、貧困・飢餓・格差・健康・生物多様性・大気汚染影響等の社会・経済・環境への影響を整合的・統合的に評価できるモデルへ拡張する点である。整合的に定量シナリオを描くために、サブテーマ内/間で緊密に連携し、データ授受を行う。シナリオの設計にあたっては、A) CDRの量、B) CDRのポートフォリオ(技術オプションの組み合わせ)を考慮し、わかりやすい代表的な3、4つ程度のシナリオを提示する。加えて、社会的・倫理的・政治的な観点から統合評価モデルの出力を解釈する。
研究の性格
- 主たるもの:政策研究
- 従たるもの:行政支援調査・研究
全体計画
日本を含む世界全体の1.5℃気候安定化を満たす2100年までのGHG排出パスとその内訳、及びその時のエネルギー、土地利用、経済の状態を、CDRの可能性を考慮した複数のシナリオとして示す。さらに、それらのシナリオ下における主要な社会・経済・環境の波及的影響を示す。ここで、社会・経済的な影響としては、以下の5点、すなわち貧困・飢餓・健康・経済成長・格差を扱い、環境影響は以下3点、すなわち気候、生物多様性、大気質を扱う。既存研究では植林とBECCSに限られていた統合評価モデルのCDR技術種を大幅に拡張し、課題全体として上記のシナリオ情報をもとにして、「CDRの量とCDRのポートフォリオの選択肢としてありうる将来の選択肢としてどのようなものであるか?」、「上記選択肢の社会的・経済的・環境的観点から見たそれぞれのメリットデメリットは何か?」という核心的な研究の問に答えることを目指す。
今年度の研究概要
課題全体で使う入力データの準備を行う。人口、GDPなどは同分野で標準的に用いられるSSPの情報が2023年に更新されたので、それを整理し、最新情報と整合的な0.5°のグリッドデータを準備する。気候データは1.5℃気候安定化目標に相当する気候情報のバイアス補正を行う。
影響評価モデルの開発・改良を行う。用いるモデルの多くはこれまでにも運用されてきたモデルであるが、データの更新や新しいモジュールの追加を行う。例えば、貧困や飢餓モデルについては、最新の世界銀行の情報等をもとにパラメータを更新し、近年のCOVID19の影響等を考慮可能とする。大気質及びその健康影響は、全球大気化学輸送モデルと健康分野でよく使われる健康影響モデルを用いて屋外大気汚染をこれまで扱ってきた。本課題では、屋内大気汚染を扱えるようなモデルを新たに開発する。生物多様性モデルは対象種の拡充などを行う。
外部との連携
研究代表機関は京都大学で、国立環境研究所はサブテーマ2の代表機関として参画する。各サブテーマの研究体制は以下の通り。
サブテーマ1:京都大学、立命館大学、名古屋大学
サブテーマ2:国立環境研究所、森林総合研究所、産業技術総合研究所、東京大学
課題代表者
高橋 潔
- 社会システム領域
- 領域長
- 博士(工学)
- 土木工学,工学
担当者
-
土屋 一彬社会システム領域
-
高倉 潤也社会システム領域
-
朝山 慎一郎社会システム領域
-
Silva Herran Diego社会システム領域