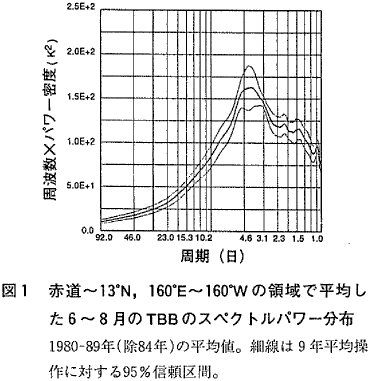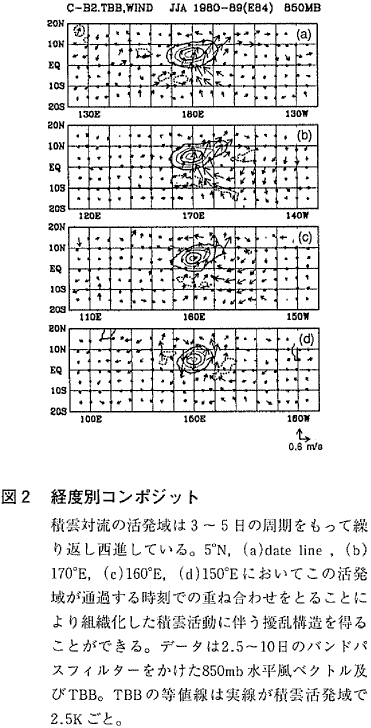熱帯域における雲の組織化の研究
経常研究の紹介
高薮 縁
気象衛星の画像で赤道付近の海上に注目すると、しばしば数百kmスケールの雲の塊が見られる。これは高度10数kmの対流圏界面を突き抜けるほどに発達した積乱雲の集団とそれに伴う「アンビル」と呼ばれる水平100kmスケールのかなとこ雲とから構成されている。海面水温が高い熱帯域では大量の水蒸気が大気に供給され、条件付不安定な成層となっている。つまり、海面上の空気が持ち上げられると大きな浮力を得、このように非常に高い積雲が形成されるのである。
背の高い積雲対流は水蒸気や熱(や物質)を上部対流圏・下部成層圏まで効率的に運び上げる。また、雲は太陽光の反射や赤外放射の吸収・射出により大気の放射収支にも大きな効果を持つ。このようにして雲は全球大気のエネルギー収支や大循環に重要な役割を果たしているので、気候問題を扱う上でも雲の効果を正確に把握することが必要である。
さて、個々の積乱雲のスケールは数十km、寿命はたかだか数時間である。しかし、その集団である100kmスケールの雲クラスターの寿命は1日前後、雲クラスターが波長数千kmの大気擾乱と結合して組織化したときなどは、集団としての振る舞いは数日スケールで追跡できる。さらに、赤道付近で顕著な30〜60日周期の大気の変動も積雲対流の効果が支配していると考えられている。このように積雲対流が組織化して大きな空間・時間スケールを持つようになると大気大循環や大気−海洋相互作用に及ぼす影響も大きくなる。したがって、組織化のメカニズムを知ることは、雲と大規模場との相互作用を理解する上で重要である。本研究では、数日周期、数千km規模の熱帯大気擾乱と積雲対流の組織化の機構についてデータ解析を行っている。
データは雲の指標として「ひまわり」の赤外相当黒体輻射温度(TBB)データ(1度格子、3時間ごと)、及び気象変数は欧州中期予報センター(ECMWF)の客観解析データ(2.5度格子、12時間ごと)を主に用いている。客観解析データは、データの少ない地域ではモデル依存性が高い。しかし、雲データを参照した解析により実際の積雲対流の活動と力学的につじつまの合う結果を得られれば、それが現象の本質を表していると考えることができる。最近気象衛星データが10年にわたって蓄積されてきており、これを用いた解析ができるようになった。
例えば雲の時系列データをスペクトル解析することにより卓越する組織化の時間スケールを知ることができる。図1は、6〜8月の雲データから計算した9年平均のスペクトルパワー分布である。4.17日周期のピークが顕著に見える。これは積雲活動がこの周期の大気擾乱と結合して組織化していることを示している。
熱帯大気の3〜5日周期で西進する擾乱の存在は、雨の降り方と関係するため地域的には古くから知られ「偏東風波動」と総称されているが、その構造や生成・維持のメカニズムは場所等の条件によっても異なっている。図2は、積雲対流活動と結合した下層風の擾乱構造が経度によりどのような違いを示すかを表している。
大気の運動方程式から赤道域には固有の構造を持ったいくつかの種類の波動が存在することが示されている。積雲対流擾乱はそのある特定の波動に近い構造をもって見えている。たとえば図2(a)の場合には雲域に吹き込む赤道越え気流とその東方の赤道上に4000kmスケールの時計回りの循環が見られる。高度場偏差の構造などと併せてみると、このシステムは赤道上の混合ロスビー重力波と呼ばれる波動の特徴を示し、両半球で4日強の周期のシーソー的な振る舞いをしながら西進している。一方、図2(d)に見られる擾乱は対流域と重なる低気圧性(反時計回り)の渦が特徴的であり、これは外力に強制されたロスビー波の構造である。
このように(a)と(d)とは共に3〜5日の周期性を持つ積雲対流擾乱であるが、力学的構造は異なっている。これは、擾乱の乗っている平均場の構造が太平洋上では経度により大きく異なるためであると考えられる。現在、年々の変化にも着目して平均場の違いによる擾乱の選択性についての研究を進めている。また、積雲対流擾乱の生成・維持のメカニズムをより直接的に解析するためには、今後予定されているTOGA-COARE国際観測等により得られるデータに期待するところが大きい。