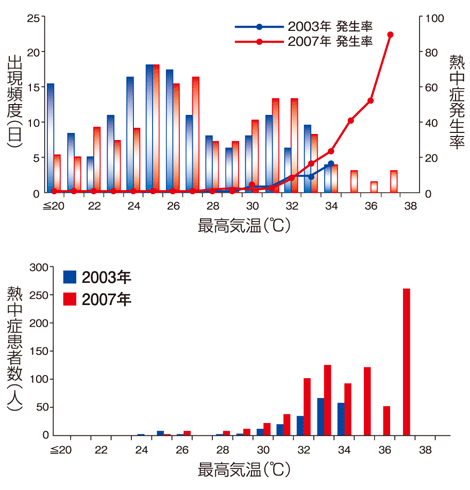熱中症患者の発生状況と今後の予測
Summary
地球温暖化による気温上昇に伴って増加が予想される熱中症。その影響評価を行うため、東京都及び全国政令指定都市の救急搬送データから熱中症患者の発生状況を掌握し、日最高気温などとの関係、地域や性別、年齢別などによるちがいを分析すると共に、熱中症予防のための情報提供を行っています。
地球温暖化による健康への影響は、国や地域によって異なります。具体的には、下痢性疾患の増加、動物媒介性感染症の増加、光化学オキシダント濃度の上昇による循環器・呼吸器系疾患の増加、熱ストレスなどがあげられます。途上国では、下痢性の疾患による小児の死亡や、マラリアやデング熱といった動物媒介性感染症が大きな問題となっています。しかし、日本の場合は、上水道が整備されているため、不衛生な水が原因となる下痢性疾患の心配はありません。動物媒介性感染症についても流行地域からはずれており、海外旅行者が現地で感染して帰国するケースはあるものの、帰国後に二次的な感染を引き起こすリスクはそれほど大きくないと考えられます。
日本の場合は、直接的な影響として、熱ストレスやその典型である熱中症が、間接的な影響として、温暖化によって上昇すると予想される大気中の光化学オキシダントによる循環器や呼吸器系の疾患の患者の増加、が予測されています。ここでは、熱ストレスの典型である熱中症リスクについて紹介します。
熱中症患者は増加傾向にある
人口動態統計(厚生労働省統計情報部)によれば、熱中症による死亡者は増加傾向にあり、2007年の死亡者は904名でした。救急搬送データを見ても、熱中症患者は増加傾向にあり、2007年夏には東京都及び17政令指定都市で5000名を超える熱中症患者が搬送されています。
国立環境研究所では、2003年から全国の主要都市(2008年では東京及び17政令指定都市、沖縄県、滋賀県草津市)の消防局の協力を得て、救急搬送された熱中症患者情報を収集し、ホームページから随時情報提供を行っています。対象地域の人口は、日本全国の4分の1くらいをカバーしており、日本全体のおよその傾向はつかめていると考えています。
これらのデータによる、性別・年齢階級別患者数、発生場所、日最高気温別発生率は以下のとおりです。
性別・年齢階級別患者数
性別では男性が全体のおよそ3分の2を占めています。年齢階級別に見ると、男性では19~39歳、40~64歳、65歳以上がそれぞれ25~30%を占めているのに対し、女性では65歳以上が過半数を占めています。人口当たりの患者数は、65歳以上が最も多くなっています。
発生場所
19~39歳、40~64歳では屋外での作業中を中心に比較的多様な場所で発生していますが、7~18歳では学校、特に運動中、65歳以上では自宅(居室)での発生が特徴としてあげられます。
日最高気温別発生率
同じ日最高気温に対する1日当たりの患者数を見ると、25℃あたりから患者が発生し、31℃を超えると急激に増加します。
これを年齢別に見ると、7~18歳、19~39歳、40~64歳では35℃、36℃を超えると、わずかではあるものの発生率の上昇が鈍っています。激しい運動や作業を控えたり作業中の休憩をふだんより多くとるなどの自発的な対策の結果と考えられます。一方、高齢者では気温の上昇に伴って発生率も単調に上昇しています。高齢者の多くは1日の大半を自宅で過ごしているため、高温でも普段と同じように生活し、特別の対策がとられなかったと考えられます。
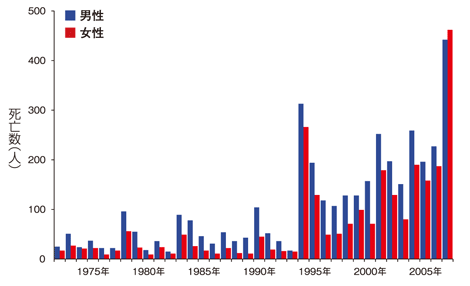
1995年以降に限って見ると、死亡者数には増加傾向が見られます。第一の要因は人口の高齢化です。死亡率の高い高齢者の増加によって熱中症による死亡者が増加しています。2000年以降では、全死亡者のうち、男性の52%、女性の85%が65歳以上の高齢者です。もう1つの要因は、猛暑の年(1994年、2004年、2007年)の高い死亡率と冷夏の年(2003年)の低い死亡率に示される気温との強い関係です。温暖化と高齢化による、熱中症死亡者の増加が懸念されます。
熱中症の予防と対策
国立環境研究所ではホームページから熱中症予防情報を提供しています。都道府県単位で、当日と翌日の3時間ごとのWBGT(暑さ指数)の予報を提供しています。WBGTは気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した指数で、熱中症の危険度を表すのに適しています。
熱中症は高温にさらされることにより引き起こされますが、それに加えて高齢者、小中高生の運動、青壮年(19~39歳、40~64歳)の激しい作業などによりリスクが高まります。このようなリスク集団に対しては適切な対策が必要です。高齢者に対しては予防情報の適切な伝達や居住環境の改善、小中高生の運動については学校での指導の徹底、青壮年の激しい作業については職場の管理者による指導・監督があげられます。また、寒冷地では、ルームエアコンの普及あるいはその代替策など、今後予想される暑熱日への対応が急がれます。
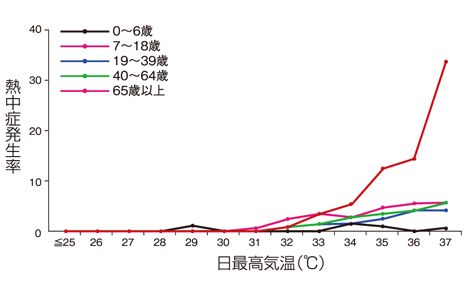
熱中症の将来予測
地球温暖化によって、今後、日本全体でどれだけの熱中症患者が発生するかという予測にも取り組んでいます。
日最高気温あるいはWBGTとの関係から、それぞれの気温でどれだけの患者が発生するかを推定することができます。これをベースにして、将来気温が上昇した場合を予測します。ただし、熱中症患者予測の場合には、年平均気温ではなく、毎日の気温が問題になります。年平均気温が上昇しても、極端に暑い日が増えなければ、熱中症の発生にあまり影響しません。しかし、平均気温はそれほど上がらなくても、極端に暑い日が増加すると、影響が非常に大きくなります。国立環境研究所や気象庁が発表している予測には、毎日の最高気温も示されていますので、最高気温でクラス分けし、患者数を推定していきます。地域別、及び年齢別の予測も行います。
現段階での予測では、気温の上昇がそれほど大きくない気候モデルに基づいた場合、2030~2040年ぐらいまで、患者発生数に顕著な増加は認められず、2007年とそれほど変わらないと見られます。ただし、2100年ぐらいになると患者数は今の2倍くらいに増加すると考えられます。また、もう少し大きな気温上昇を予測しているモデルの場合には、2倍では収まらず、地域によっては3倍あるいは4倍になることも予想されます。