気候変動への適応策と緩和策:科学的知見に基づくアクションのために

セッション1:気候変動への適応策と緩和策
国際社会は、脱炭素社会や急速に増している気候変動のリスクに対して強靭な地域となっていくための転換点に立っています。気候変動リスクは、特に経済成長のさなかにあるアジア地域にとっては確実に脆弱性を強めるでしょう。適応的かつ緩和的対策は、地球温暖化影響を科学的に予測したうえで、よりスマートな経済成長と公共福祉のためにより大きな危機感をもって考慮されるべきです。適切な行動を促進しつつ、私たちは、いかにしてネットワークを通じて対策を強めることができるかを考え、そして各機関や研究者同士の協働のもと脆弱性の低減のためのよりよい仕組みの構築に焦点をあてる必要があります。科学だけでは解決策を出すことはできないので、適切な政策決定を促進するために科学者は政府と密接にかかわることもまた重要です。
このセッションでは、適応策と緩和策をつなぐようなともに効果を高めるような行動について、双方向的に議論します。これらの問題に対して、アジアにおける適応策と緩和策のシナジーをもたらすためにどうすればよいかという両側面からアプローチしていきます。
科学と政策をつなげる
このセッションでは8人の登壇者がそれぞれ異なるテーマで発表しました。
-
春日文子氏 国立環境研究所 シニアフェロー/Future Earth国際本部事務局・日本ハブ事務局長
-
Ho Chin Siong氏 マレーシア工科大学 教授
-
Rizaldi Boer氏 ボゴール農業大学 教授
-
Oleg V. Shipin氏 アジア工科大学院 准教授
-
藤田壮氏 国立環境研究所 社会環境システム研究センター センター長
-
福士謙介氏 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構 教授
-
王勤学氏 国立環境研究所 地域環境研究センター 主席研究員
-
Marti Diah Setiawati氏 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構 プロジェクトリサーチャー


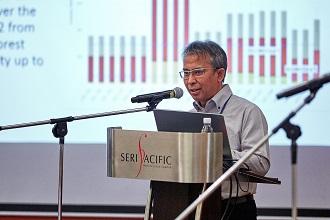





提供された話題は多岐に渡りました。フューチャーアース、マレーシアにおける科学と政策、森林伐採指標による排出リスク指標、観測、社会モニタリング、適応策に関するイニシアティブ、モンゴルにおける永久凍土への影響、そして気候変動による健康への影響などです。
発表内容の多くは、アジア内の様々な地域や、科学や工学など異なる分野に焦点をあてていました。その中でも共通して述べられていたのが、科学の力だけでは地球全体の、そして各地域の環境問題を解決することはできないけれども、「科学と政策をつなげる」という共通の課題と行動が社会全体の「転換」をもたらすだろうということです。気候変動研究、モニタリングと観測、定性的モデル研究とシミュレーションと同様に、課題解決を起点とした研究や社会の中の様々な役割の人々との協働が、科学者にとって課題です。同時に、科学的知見は気候変動時代における社会の転換にとっては不可欠であるという認識を共有しました。


次号では「生物多様性」のセッションについて報告します。このセッションではSDGs(持続可能な開発目標)など重要なキーワードも登場します。今後どういった展望を掲げるのか、などの点についてご紹介したいと思います。
(文・杦本友里(研究事業連携部門)・芦名秀一(企画部国際室))
(写真・成田正司(企画部広報室))







