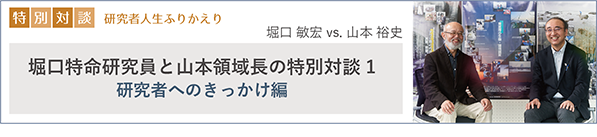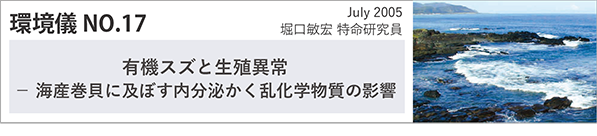2025.11.19
特別対談 Vol. 2
堀口特命研究員と山本領域長の特別対談
~そして国環研へ編
堀口 敏宏 vs. 山本 裕史
堀口敏宏特命研究員と環境リスク・健康領域の山本裕史領域長との特別対談。「研究者へのきっかけ編」では、大学入学前から大学院時代までのお話でした。 今回は、堀口特命研究員の博士課程の研究と国環研での研究(の一部)について語っていただいた「~そして国環研へ編」です。最後に若い世代へのメッセージもあります。

偶然の巡り合わせのようで、全部が繋がっている
イボニシのインポセックス*1 に着目
山本: 有機スズの問題に着目されて(「研究者へのきっかけ編」参照)、その後どんな研究をされたのですか。
堀口: その後いろいろあったのですが、最終的にインポセックスにつながっていくわけです。修士課程を修了する目前の1990年1~2月頃、愛知県水産試験場の冨山実さんがバイ(貝)の種苗生産をしようとしてバイを飼っているが、卵を産まない。NHKニュースによると、イギリスでは有機スズが原因でバイの仲間がインポセックスになり産卵できなくなるという内容だったが、愛知水試で飼っているバイの雌にペニスがあるという話を聞いたんですね。それで、修士論文を終えて2月に愛知水試の冨山さんを訪ねると、イギリス発のインポセックスの論文と同じことが目の前で起きていて、さらに当時の伊勢湾ではバイがほとんど獲れなくなっていた。急いで東京に戻り、清水先生に報告して、博士課程の研究テーマを巻貝のインポセックスに変更することにしました。最初の大学院入試に落ちて、1年間足踏みしたわけですが、結果的には、修士と博士の境目の時期にインポセックスに出会うことになって、研究テーマの変更がしやすかった。
山本: なるほど。そういう偶然の巡り合わせで、大学入試の時から全部が繋がっていますね。そうでなかったら有機スズの問題にも気付かなかっただろうし、研究もされてなかっただろうし。そのタイミングがあったからこそ、バイの話に繋がったってことですね。博士課程の有機スズの研究は東大の清水先生の研究室で進めたんですか?
堀口: はい。まずインポセックスの研究をバイでやるかどうか。伊勢湾は東京からは遠いし、バイを漁師に獲ってもらわないといけない。さらに、ほとんどバイが獲れなくなっていたから、無理だという話になった。その時に神奈川県油壷の東大理学部附属三崎臨海実験所で採れるイボニシにインポセックスが出ているという話を聞いて、早速油壷に行ったんです。イボニシだったら潮間帯にいるので自分で採れるし、三崎臨海実験所を拠点にできるので動きやすい。ただ、インポセックスを調べるといっても、私にはオスメスを正確に判別できなかった。1960年代の葉山海岸のイボニシの性比についてペニスの有無で雌雄判別して、だいたい1対1だという報告が日本貝類学会の「ちりぼたん」という雑誌に掲載されていた。有機スズ汚染の影響がなければ、ペニスの有無で雌雄判別ができたはずですが、1990年5月時点では全てのイボニシにペニスがあり、どれが雄で、どれがインポセックスか、区別できませんでした。
山本: その1960年代のデータがあったから、その後インポセックスが出ているっていうのが分かったんですね?
堀口: 当時、日本ではインポセックスの調査はほとんどされていなくて、データはないに等しかった。そもそも、ペニスの有無といった簡便な方法ではなくて、解剖して組織や器官の特徴からイボニシの雌雄を判別できる人が、少なくとも私の周りにはいなかった。そこで、当時、臨海実験所の修士課程2年だった尾田正二さんに手伝ってもらい、イボニシの解剖に挑戦しました。まず、イボニシを採ってきて、殻を割り、軟体部を観察しました。卵巣や精巣、輸卵管を観察するつもりだったのですが、区別がつかない。当時は初夏、イボニシの産卵期だったので、雄ならば精子を持っていました。生殖腺からピンセットでごく一部を取ってきて生理食塩水につけて顕微鏡で観察すると、精子がいれば泳ぐから雄だと分かると尾田さんから言われて、それで二人で頑張って悪戦苦闘した。しかし、なかなか前進しない。そもそも、雌の証である輸卵管を正確に見分けることができない。さらに後日判明するのですが、インポセックスが重症になると卵巣で精子を作ることがあるため、精子で雄を見出す作戦は上手くいきませんでした。
山本: 形態を見ることでしか、当時はなかなか判別できなかったってことですね。
堀口: はい。自分で雌雄判別の基準をつくる必要がありました。これは輸卵管のようだからメスだろう、でも精子がいると、雌という判定は間違いなので、輸卵管の判別基準を修正しなければいけない。それで最初から全部やり直し。何度も雌雄判別の基準を作って、これで判別できると思ってもまたダメということの繰り返しでした。結果的に、私が解剖でオスメスを正確に判別できるようになるまで二年間かかりました。正確な雌雄判別ができないと、インポセックスを判定できないので、研究を先に進められず、四苦八苦しました。
山本: その熟練に二年かかって、やっとデータが取れるようになったということですね。

正常なメスのみで構成される集団だった。そこから“反撃”が始まった
国立公害研究所(現、国環研)との出会い
山本: イボニシの雌雄判定での苦労と同時期に、分析でも苦労されたんですよね。
堀口: 有機スズの分析も必要だったのですが、これもまた難儀でした。東大分析化学研究室の山崎先生から、有機スズの分析技術が一番なのは、つくばの国立公害研究所(現、国環研)だと伺いました。それは森田昌敏先生が率いていた計測技術部の白石寛明さんが作った分析法でした。それで1990年5月につくばを訪れましたが、公害研から国環研に組織が変わる直前で忙しい時期だったにもかかわらず、森田先生にきちんとアポを取らずに訪問してしまった。それで、東大分析化学研究室出身の岡本研作さんと話をさせていただいた、ちょうどそこへ寛明さんが来られたので、ご挨拶と一言二言交わしただけでこの時は東京へ戻りました。それから半年ほど経って、東京で開催された環境科学会で寛明さんが声を掛けてくださった。その後の進捗を尋ねられたので「全然だめです、全く目途がたちません」とお話ししたところ、「森田さんがOKしたら一緒にやってもいいよ」と言ってくださった。
山本: それは博士課程の何年生の時ですか。
堀口: 博士課程1年の秋でした。まだ解剖で四苦八苦していた時期ですが、将来、有機スズ分析は必須になるので何とか前進したいと必死でした。それで、1991年3月に、今度は山崎先生に連れられて森田先生を訪ねると、「有機スズやりたいの?じゃあ白石君を呼んで」と秘書を通じて寛明さんを呼んでくださり、話がスッとまとまった。それで翌月から国環研に来ることになり、日帰りのつもりでしたが、既に泊まり込むことになっていて、国環研での研究が始まりました。
山本: どれぐらいの頻度で来られたんですか?
堀口: 1991年4月から1993年3月までずっと国環研に住み込み。毎週月曜日に大学のゼミに出席する時だけ東京の下宿へ帰り、それ以外は全部国環研。
山本: そうなんですね。分析は結構大変だったんですか?
堀口: 有機スズ分析は一般的な農薬の3倍手間がかかると寛明さんから言われましたが、本当に大変でした。博士課程3年の秋からは博士論文を書き始めないといけないから、データを出すための時間はあと1年半しかなかったんです。当時、多くの大学院生は修士と博士の5年分のデータで博士論文を書いていた。自分は有機スズとインポセックスのデータを1年半で出さなきゃいけない。人の3倍働かないと追いつかないと、とにかく毎日必死で働きました。結果として、1日おきに徹夜の生活で、連日の徹夜もざらでした。更に、月に1回は油壷へサンプリングに出かけていたのですが、夕方までつくばで分析、一度東大に帰って車に機材を積んで、またつくばに戻って別の機材を積み増して、臨海実験所に着くのは早くて夜11時。翌朝からイボニシのサンプリングでした。
山本: サンプリングは何人ぐらいで?
堀口: 基本的に全部一人です。
山本: それはすごいですね。
堀口: 2日かけてイボニシを採って、3日目に臨海実験所の方に手伝ってもらい、海水と底泥を取る。それからつくばに帰って、すぐに分析のための抽出作業を始めるので、ほぼ徹夜。初期の頃の2~3ヶ月は、朝9時から翌朝5時まで働いていましたね。
山本: 今では考えられないですね。分析していたのは水ですか?泥ですか?
堀口: イボニシなどの生物のほか、海水も底泥も全部。
山本: それは、大変でしたよね。
堀口: 他にも印象的な出来事が結構ありました。当時インポセックスの出現率が日本全国どこでも100%でした。つくばに来て間もない頃、寛明さんが自然海岸で船もほとんど見えない茨城県の平磯に連れて行ってくれましたが、平磯でも正常なメスが採れなかった。だから学会発表した時に、「君はペニスを持った雌は異常だと言うが、100%そうなら、結局イボニシはそんなもんじゃないの。ペニスのないメスはいないんじゃないか」と意地悪な質問をされた。それで、鳥取、島根や石川、本州最南端の潮岬、三重などに行きましたが、結局どこで採っても正常なメスがいなかった。その時、交通遺児育英会の大学奨学生の同期だった北澤和彦さんがNHK新潟放送局にいて、彼を訪ねて新潟に行ったついでに、できるだけ人間の影響が少ない所へ行きたいと思い、佐渡へ行きました。朝早く新潟港を出港して両津港に着いて、目的地は決めていなくて、その日のうちに新潟へ戻らないといけないから時間がないと思って、発車間際のバスに飛び乗った。それは、偶然、相川行きのバスだった。小一時間揺られて、海が見えてきたので「ここでいいや」とバスから降りたら、そこは砂浜の海岸で、「あちゃ~。イボニシは砂浜にはおらんわ。大失敗!」と頭を抱えた。沖を見るとテトラポッドがあったので、あそこまで泳げば、イボニシを採れるんじゃないかと。ただ、水泳パンツを持っていないから、仕方なく、パンツ一丁でテトラまで泳いで渡った。案の定、イボニシがいたので採って、つくばへ戻った。これが正常なメスのみで構成される集団だったんです。それで大喜びで大騒ぎ。そこから“反撃”が始まって、インポセックスを再現する様々な実証実験を行うきっかけとなったわけです。
山本: 博士課程2年ですか。もう残り一年ぐらいしかない時ですね。
堀口: それで、後に環境ホルモン報道の中で伝えられた、“50メートルのプールに目薬1滴程度のトリブチルスズでインポセックスが起きる”という実験データの取得に繋がります。博士課程3年の4月に再度佐渡に行って、車の中に寝泊まりしながらイボニシを採りました。早朝の天気予報によると、海が段々時化てくるということだったので、今日やるしかないと決心し、朝9時から15時まで6時間ぶっ通しで波打ち際と沖のテトラポッドを何度も往復して、イボニシを約950個体採った。それを使って、イボニシのインポセックス再現実験をすることができたんです。

産卵風景(黄色い房が、受精卵が多数入った卵嚢.卵嚢を岩棚に産み付ける)。
イボニシ(新腹足目アッキガイ科)は、岩礁潮間帯に棲む殻高2~3cm程度の肉食性巻貝。
研究者としての視点と世論に訴える時のインパクトも考慮して
国環研への入所と環境ホルモンプロジェクト
堀口: ちょうどその頃、公務員試験を受験することになりました。寛明さんに再三勧められて、国家公務員試験を受けたのですが、イボニシの実験に夢中だったので、受験勉強にはさっぱり身が入らなかった。幸運なことに、試験問題に漁業白書の読んだところが出たり、有機スズの時事問題が出たり、フィールド調査にちなんだ問題が出たりと、運よく筆記試験に通りました。
山本: 国環研に入るには、当時は公務員試験を受けられたんですよね。
堀口: 多くは国家公務員試験だったと思います。私は水産系の試験を受けたので、面接の前の省庁回りは水産庁でした。また、面接試験では水産庁の参事官の方から「君は環境庁が第一希望と書いているが、なんで?」と聞かれて、噓を言っても辻褄が合わなくなると思ったので、申し訳ないですけどと、全部正直に話しました。正直に話したのが良かったのか、無事に合格したんです。
山本: 1993年4月に国環研に入られて、最初から有機スズの研究を?
堀口: いえ、最初は環境標準試料の担当で、1996年ぐらいまで担当しました。ただ、標準試料の仕事の後は、他の研究もしてよかったので、例えば、ホタテの貝柱を用いた標準試料作製時には、北海道の常呂で材料のホタテの入手に関する仕事を行った後、北海道北部でインポセックス調査などをさせてもらいました。
山本: 貝の研究もされていたってことですね。
堀口: はい、細々と。
山本: 1996年からまた違う仕事に?
堀口: 地域環境研究グループの有害廃棄物対策研究チームに配属されました。ちょうどその頃から欧米で環境ホルモンに対する注目度が高まって、後の環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクトへと繋がっていきます。
山本: 環境ホルモンプロジェクトではどういうところに注目されたのですか?
堀口: 少し遡って私が博士課程のころですが、化審法*2 ではTBTOというトリブチルスズ化合物の中の1物質だけが全面禁止された。つまり、TBTOだけがスケープゴートにされた。1990年1月にTBTOが化審法の第一種特定化学物質*3 に指定された時に、それ以外のトリブチルスズ13物質は単なる指定化学物質だったんですね。指定化学物質は製造及び輸入数量を事後報告すればよかったので、いわば、使い放題でした。本質的には、ポリマータイプ*4 のトリブチルスズが船底塗料の主原料だったので、これこそ使用禁止にすべきだったにもかかわらず、実際にはそうならなかった。その背景にはTBTOとその他のトリブチルスズ13物質の魚類への蓄積性に差があるとした通産省(当時)の判断が関わっていたのですが、その判断が科学的に妥当か疑問でした。そのため、当時は、有機スズをいかに市場から締め出すか、ばっかり考えていました。
山本: そもそも代替物質であり、基本的に船底防汚剤として同じ作用を持っているので、毒性などがそれほど違うということはないわけですよね。
堀口: その通りです。また、外国籍の船も日本に来るので国際的にも対応しないとダメだと考えていました。1990年10月に運輸省(当時)が、国内の航行船舶全てに対してトリブチルスズの使用禁止の通達を出し、併せて、国際的にも網をかけるべきだということで、翌11月にIMO(国際海事機構)のMEPC(海洋環境保護委員会)で有機スズ全廃を提案しました。ところがこの時は、関係国に対する根回しが不十分であったために決議のみが採択され、何の実効性もないままで終わってしまった。
山本: 国際的な問題は、また別の問題や利害関係がある、先進国と途上国の問題もあるので、なかなか難しいですよね。最終的にその問題は暫くかかったのですか。
堀口: 環境ホルモンに社会的な関心が集まる直前の96年ぐらいでしたけど、有機スズ全廃条約づくりをオランダ、ノルウェーと日本が共同でIMOに提案しました。それに先立ち、環境庁(当時)で検討会が作られて、私もそこに参加して、有機スズの国際的な規制の必要性に関する理論武装を担当させていただきました。イボニシは非漁獲対象種で商業価値がない。バイは漁獲対象種だけど、知名度が高くない。というので、高級食材のアワビに注目した。雄にペニスがない原始的な巻貝のアワビ類にも有機スズが悪さをしていると考えられたが、実際はどうかと学問的にも関心があった。アワビ類の漁獲量は年々下がっていて、漁獲量の減少が激しいところは、有機スズの汚染が激しいところと地域的に重なる。十分可能性があると考えていました。
山本: 商業的な有用性でアワビに注目されたってことですか。
堀口: 研究者としての視点と世論に訴える時のインパクトも考慮して、それでアワビを研究対象に選びました。その後、外交的なせめぎ合いが数年続いて、1999年10月のロンドンでのIMOの外交会議で、僅差で有機スズ全廃条約を作るということが可決されました。その時点では2003年1月1日以降全廃条約が発効する予定だったのですが、遅れに遅れて、2008年9月17日にやっと発効しました。
山本: ご自身で、それも大学院生で、社会を動かしたっていうのは、すごいですね。
堀口: 当時の国環研には、いろんな人がいて、各研究者がデータを出せたし、発表もできた。それに対して、なんかこう自由の風が吹いていた。自分次第ですよ。自分が体を動かせばデータが出せる。

想像力を膨らませる、そこも重要じゃないか
若い世代に伝えたいこと
山本: 学生時代の経験から、いろいろなお話を伺いましたが、今の若い世代に伝えたいことはありますか。
堀口: 一言で言うと、世のため人のために頑張ってほしい。私自身も交通遺児育英会で世のため人のために生きよということは、よく言われてきて、常に世のため人のためという言葉が私の中にはあった。自分自身でいえば父に親孝行もできないままであったことを考えたり、支えてくれているたくさんの人のことを考えたら、少しは人様の役に立たないと申し訳ないなって思いがあって、現在に至るわけなので。もちろん自分の生活が成り立たないと周囲のことを考える余裕がないから、自分の生活をしっかり支えていくのは、それはそうだと思う。ただ、あわせて、社会の不公正とか、不条理に対しても目を向けて、自分のためだけじゃなくて、世のため人のために頑張る人になってほしいと思います。
山本: 今は学生さんが、環境に関連することになかなか興味を持たない。あるいは、自分の近くのことしか興味を持てない人が多いような気がします。そういう人たちに、どういう風に伝えたら変わっていくでしょうか。今は、最初からそもそも大学院に行かなくて、先ずはライフワークバランスを考えるとかですね。その人たちに、世のため人のためにやりましょうって、なかなか通用しないところがありますが、どんな風に伝えれば、そういった気持ちが出てくるか、何かありますか?
堀口: 私の周りには若い人はあまりいないので、感覚としてよくわからないけど。どういう風に生きていきたいの?というのは聞くと思いますね。
山本: 今どうしても、環境に興味を持たず、目の前にあるものとして、その先の不条理とかが見えにくくなっているので、そういったものに対して戦っていく、あるいは、おかしいものを突き詰めていく、といったところは、なかなか難しいですね。教育の問題も課題なのか、わからないですが。
堀口: 教育の問題もあるかもしれないけど、本人が自分が生きている社会に目を向けようと思わないとダメなんじゃないかな。例えば報道を見て、ガザであんなひどいことが行われている。それを見ても何も感じないんだろうか。世界で起きていることの現実を見た時に、そこで感じるものが何かあるんじゃないか。それが取っ掛かりになるのではないかと思いますね。
山本: 何かおかしいとか、何か不条理なこととか、それこそ戦争は分かりやすいことだと思います。
堀口: 今、あらゆるものの値段、物価が高いですよね。それで、十分に食べられないということや、生きること自体が大変な部分もある。ボヤっと生きているだけで本当にいいんだろうか。本当に今のままでいいの?何かおかしいんじゃないの?と。
山本: どういうメディア、手段を使えば、今、ある意味で気づいていない、そういう人たちを変えられると?
堀口: 現実に起きていることに目を向けたら、何か感じるんじゃないか、さらに、そこから想像力を膨らませる、そこも重要じゃないかと思いますよ。
山本: 個人的には、環境に対して研究している人間は、想像力があって初めて環境研究ができると思います。何か不幸なことが起こっているかもしれないと。人のところはイメージできるけど、さらに広げて、そこにいる生き物に対しても想像力を働かせるってなかなか難しいと思うんです。人を思いやる、それから生き物を思いやる。生き物を思いやることによって自分にも返ってくる。今、想像力がなくてイメージできないというのが背景にあるので、そこをもう少し上手く想像力を持ってもらうようにやっていくしかないですね。
堀口: 私はスマホを持っていないのだけど、スマホいじっている時間が長すぎじゃないですか。現実に目を向けろよ、っていう。
山本: スマートフォンというのは、自分の好きなメディア、自分のやりたいことの近くしか見ないで、情報がだんだん特化していく。当然のことながら嫌な情報はシャットアウトして、自分の都合のいい情報だけ取ってくることができる。逆に言うと、それによってわかることもあると思うんです。自分が知りたい情報というのも知ることができるけど。そこのところ、選んでやってしまっている。多分そこの問題なんですかね。
堀口: そこは結構大きいんじゃないのかな。だからテレビも新聞も見ない、となると、世界でこんなひどいことが、許しがたいことが起きているということを知ることすら、もしかしたら、放棄しているんじゃないかと思いますね。
山本: そうなんですよね。自分に都合が悪いことをシャットアウトして、自分の都合のいいことだけってことはありますね。
堀口: 想像力以前の話ですね。だからまず現実の社会に目を向けてほしい。そして、想像してほしい。自分がその戦火に包まれるようなところにいたら、そこに自分が立っていたらどう思うか、そんなことを、とにかく現実を見て想像してほしい。でないと世のため人のためにはできない。
山本: そのとおりですね。
堀口敏宏特命研究員の大学院時代と国環研との出会いを中心に、
最後は若い世代への熱いメッセージも頂きました。
次回は、「長年の研究を深掘り編」です。国環研での長年の研究、
【インポセックス】、【東京湾の定点調査】、【原発事故後の福島調査】について、
専門的な内容を含めてお話を伺いました。
*1 インポセックス:
アルファベットではimposex と表記される。Smith (1971) によって初めて用いられた造語であり、その語源はimposed sexual organs であるとされる。Smith (1971)ではimposex の定義が巻貝と寄生虫との関係の中で述べられており、やや複雑であるが、簡単に言えば、雌の巻貝に雄の生殖器(ペニスと輸精管)が形成される現象、あるいは雄の生殖器を持った雌の巻貝を指す。疑似雌雄同体であり、奇形の一種とみられるが、重要なことは、インポセックスが重症になると産卵不能が伴う場合がある(子孫を残す雌の機能が失われる場合がある)ことである。重症のインポセックスに付随した産卵不能の様式には、輸卵管末端(産卵口)の閉塞、卵巣における精子形成(卵巣の精巣化を含む)、輸卵管の開裂などが知られている。
B. S. Smith: Proc. Malac. Soc. Lond., 39, 377-378 (1971)
*2 化学物質審査規制法(化審法):
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」という。PCB(ポリ塩化ビフェニル)のように環境中に残留しやすく、また、魚類に蓄積しやすく、さらに哺乳類に対する毒性が強い化学物質の製造、輸入及び使用を厳しく規制するための法律として1973年に制定され、何度かの改正がなされてきた。環境への残留性(微生物による分解性)、魚類における蓄積性、哺乳類への長期毒性の観点から既存化学物質及び新規化学物質が審査・評価され、その結果、規制が必要とされるものは、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、指定化学物質に指定される。1973年の化審法制定時には通産省と厚生省(いずれも当時)が共管し、環境庁(当時)は意見を述べることしかできなかった。2001年及び2004年の法改正により、環境省も所管することとなり、環境中の動植物への影響にも着目することになった。
*3 第一種特定化学物質:
化学物質審査規制法(化審法)の第一種特定化学物質には、環境中に残留しやすく、また、魚類に蓄積しやすく、さらに哺乳類に対する毒性が強い化学物質が指定される。第一種特定化学物質は、原則として、その製造、輸入及び使用が全面的に禁止される(いわゆる、全面禁止)。一方、第二種特定化学物質は、環境中に残留しやすく、哺乳類への長期毒性が疑われるものの、魚類への蓄積性が低いと判定された化学物質が指定される。第二種特定化学物質は、製造や輸入の前にその予定数量に関して通産省と厚生省(当時)の許可を必要とする(いわゆる、事前届出/許可制)。また、指定化学物質は環境中に残留しやすい化学物質が指定され、魚類への蓄積性や哺乳類への長期毒性が審査されるが、当面は、その製造や輸入の数量実績を通産省と厚生省(当時)に毎年報告すればよい(いわゆる、事後報告)。トリブチルスズ化合物14物質のうちの1種であるTBTOは、1990年1月に第一種特定化学物質に指定されたが、この時点では、その他のトリブチルスズ化合物13物質は指定化学物質のままであった。また、トリブチルスズ化合物と同様に、船底防汚塗料や漁網防汚剤等に使用されてきたトリフェニルスズ化合物7物質も、1990年1月の時点では、指定化学物質のままであった。その後の国会審議などを経て、1990年9月にTBTOを除くトリブチルスズ化合物13物質とトリフェニルスズ化合物7物質が第二種特定化学物質に指定された。しかし、化審法の構造上、第二種特定化学物質が第一種特定化学物質へと格上げ規制されることはない。
*4 ポリマータイプ:
トリブチルスズ化合物のうち、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が 8 のもの)を指す。化審法の第二種特定化学物質に指定されているトリブチルスズ化合物13物質の中の1種。船底防汚塗料などに大量に使用されていたトリブチルスズ化合物は、化審法の第一種特定化学物質に指定されたTBTOでなく、実は、このポリマータイプであった。また、TBTOの第一種特定化学物質への指定は1990年1月であったが、TBTOの国内向け出荷は実際には1988年8月末で停止していた。したがって、1990年1月のTBTOの第一種特定化学物質への指定によって、トリブチルスズ化合物による汚染の低減効果がどの程度であったかは疑わしかった。さらに、1990年1月時点ではこのポリマータイプのトリブチルスズ化合物は指定化学物質であり、製造や輸入数量の実績報告が必要ではあったものの、使用そのものは可能であった。
| 進行・構成・編集 | 環境リスク・健康領域 今泉 圭隆・林 千晶 |
|---|---|
| 写真撮影 | 企画部広報室 成田 正司・堀口 敏宏 |
- インタビュアー・進行・構成
- 環境リスク・健康領域林 千晶・今泉 圭隆
- 写真撮影
- 企画部広報室成田 正司
Profile / Message

山本 裕史 YAMAMOTO Hiroshi  NIES研究者紹介
NIES研究者紹介
環境リスク・健康領域 領域長
経歴:京都市出身。テキサス大学大学院でPh.D.取得。その後、徳島大学総合科学部准教授。2016年に国立環境研究所へ。生態毒性研究室長等を経て、2024年から現職。
息子に続き娘も一人暮らしを始め、最近は愛犬と近所の散歩をするのが癒し。また、諸外国への出張が多くあり、日本の化学物質管理制度の世界からの周回遅れが気になるが、何とか世界に誇れる化学物質管理制度の導入に向けてもうひと踏ん張りしたいと考えている。
 NIES研究者紹介
NIES研究者紹介
Profile / Message

堀口 敏宏 HORIGUCHI Toshihiro  NIES研究者紹介
NIES研究者紹介
環境リスク・健康領域 特命研究員
経歴:三重県松阪市出身。東京水産大学、東大大学院(修士・博士)を経て、1993年国立環境研究所へ。現在に至る。
趣味(?)は空手。学生時代に極真会の道場で稽古していたが、中途半端であった。今、一人で稽古しています。魚介類のスケッチも嫌いではありません。見た人から「友達みたい」と言われましたが、相手(魚介類)は何とも思っていない、片思いです。カラオケの十八番は鳥羽一郎さんの「兄弟船」。
 NIES研究者紹介
NIES研究者紹介