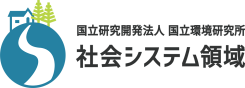中山間地域の持続可能性:新しい価値観を考える

中山間地域の持続可能性:新しい価値観を考える
前編「“地域に貢献したい”:農村計画学のアプローチから」はこちら:http://www.nies.go.jp/social/interview08a_nakamura.html
後編では、中村さんが所属している地域環境創生研究室が取り組んでいる福島県新地町や三島町で地域に密着した研究活動に関連したお話しを聞きました。
現在の主な研究内容はどのようなものですか?
当初はフィールドが新地町だけだったので、新地町での調査研究にかなり時間を割いてたんですけど、2016年の夏ぐらいから福島県の西側の奥会津地域にある三島町という自治体と連携したプロジェクトも立ち上がりまして、最近は新地町と三島町で50%ずつくらいの時間配分になっています。三島町とは2017年の8月に連携協定も締結してオフィシャルな関係もできたので、町の色々な取り組みを支援しています。
三島町ではまずアンケート調査をいくつか実施して、集めた情報を分析して町にお返しし、それをもとに今後の進め方について話し合うといった双方向のやり取りを重視しながらやっていこうと思っています。
それはどういったアンケート調査ですか。
もう一つは、これは三島町だけの問題ではありませんが、山を所有している人たちが、自分たちの山の境界を把握できていないという問題があります。管理も面倒くさいから相続をしたくないとか、そういう問題が今、日本のあちこちであります。そういった問題についても意識調査をしてみましょうという話もあります。
新地町についても三島町についても、どれぐらいのスパンで展望を考えていますか。

「くらしアシストシステム」も、どちらかと言うとエネルギーの見える化のほうにフォーカスしていましたが、元々地域で色々な情報を共有してもらうために作ったシステムなので、これらの機能をうまくまちづくりに取り入れられないか、相談しているところです。
*3)くらしアシストシステム:各家庭の電力消費量の見える化を通じた省エネの取り組みの推進と、地域の様々なくらしの情報の共有を目的として開発された独自のシステム。2014年から町内約80世帯を対象に実証試験が続けられています。初期は各家庭に専用のタブレットを配布し、利用してもらっていましたが、今はそれ以外のシステムからも情報を見られるようになりました。
※新地町での研究については過去の環境儀でも紹介されています。
http://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/60/02-03.html
あのタブレットの情報は、役場の人も見られるんですか。何かに活用されたりしてるんでしょうか。
今はスマートフォンでも見れるようになっていますが、まだ具体的な活用にまでは至ってないのが現状です。我々と役場の今後の課題ですね。そういった状況はありますが、あと2~3年ぐらいで取り組んでいくんだろうなと思っています。
三島のほうは、今の中長期計画内(2016~2020年度)でひと段落するぐらいのスパンでやっていこうというところです。今は情報を集めている段階ですが、今後は補助事業も活用しながら何らかの木質バイオマスのエネルギーシステムを入れていこうという流れにできれば…と町役場とも議論しています。まずは5年を目安にやってみようかというところですね。
一方で、町としてはずっと続いていくからこそ、その限られた期間であっても、それがいかに存続できるかが大事なのかなと思いますが、どうでしょうか?

産業として成り立たせることが難しいんですね。
価値観をつくるのはすごく難しいイメージです。
難しいですよね。森林とか農地には多面的な機能があるという話がありまして、例えば水田は、お米を作る以外にも、雨が降ったときに水を貯めるダムの役割があると言われており、「トータルで見ると、農業以外にもこんなに多様な価値があるんだよ」ということになります。
生態系サービスの話も同様で、そういったグローバルな議論にうまく乗っかって、それを「日本だと、奥会津だとこうだよね」と応用していく。実際はそう簡単な話ではないんですが、そういったいう視点も参考になると思います。
最後に今後やっていきたいことや考えていきたいことは何でしょうか。
「不便なら移住すればいいのでは?」とかですか?
「暮らしの機能」だけではなくて、「住まいの価値観」みたいなものもありますよね。
中村さんはいろんな価値観を考える過程に立たれるのかなという印象です。
そうですね。最初に言った混住化のときもそうですけど、日本の歴史の中で、この100年ぐらいで価値観がものすごく揺れているので、どこかに収束していく話ではないと思います。まぁ面白い時代ですよね、そういう意味でも。今は都市住民の農村回帰というか、「農村に住みたい若者が増えています」といった話も聞きますよね。昔であれば、基本的に農村から都会に人が出ていくというのが、それこそ明治時代から戦後にかけてずっとあった話なんですけど、その価値観が揺れ始めたというのも非常に興味深いと思います。
最後に
中山間地域の住まいに関する新しい価値観を作っていくことは簡単ではないかもしれません。それでも、自分なりの立ち位置を大事にしながらこれからも研究活動を進めていって、いつかまたその後の話を伺ってみたいです。
(聞き手:杦本友里 社会環境システム研究センター)
(撮影:成田正司 企画部広報室)