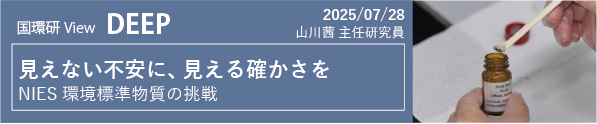2025.08.08
研究者インタビュー Vol. 2
環境標準物質とは ~そして、その開発に携わるということ
山川 茜
試料瓶の ふたを開けた瞬間、微かに排気ガスやガソリンの混ざったにおいが立ち上った。
「これが、現在開発中の大気粉じんの環境標準物質です。」
国立環境研究所(NIES)の一室。棚に整然と並ぶ小瓶には、この粉じんをはじめ、土壌や生物など、幅広い種類の環境標準物質が保管されていた。
環境標準物質――聞きなれないその存在は、じつは私たちの安全な暮らしを下支えしている。たとえば、土壌や空気中の微粒子にどんな化学物質が含まれているのか。それは、どれだけ健康に影響を与えるのか。環境標準物質とは、それらを正確に測るときに欠かせない、「ものさし」だ。
環境標準物質とは、どんなもので、どうやって作られているのか。その現場を訪ね、研究者に話を聞いた。

都市由来の粒子を模した黒い粉末で、環境分析の基準として期待されています。
都市の空気の縮図を、2年かけて集めました
Q. この茶色の瓶がNIESの標準物質の瓶ですね。この瓶に入っている黒い粉は何ですか?
これは現在開発中の環境標準物質、「都市粉塵(としふんじん)」です。幹線道路と高速道路が交差し、交通量の多い地点に設置された集塵フィルターに付着した粉じんを原料としています。周囲には高層ビルが立ち並び、近くには住宅地も広がるなど、都市部に特徴的な環境条件が重なった地点です。集められた粉じんには、車からの排出粒子やブレーキダスト、摩耗したアスファルト、周辺の土壌など、都市ならではの物質が数多く含まれています。一見ただの黒い粉ですが、都市の大気に漂う粒子の集合体で、まさに“都市の大気の縮図”と言える試料です。

環境標準物質を使うことで初めて「この数値は信用できる」と言える
Q. 標準物質とは何ですか?何のために使うのですか?
標準物質とは、「測定の正確さを保証するための基準となる試料」です。
環境試料の化学分析において標準物質が必要になる理由はとてもシンプルで、測る値に信頼性を持たせるためです。私たちは、環境試料を対象に標準物質を作っていて、「環境標準物質」と呼んでいます。
たとえば、ある研究所が「この土壌は1kgあたり鉛を100mg含んでいます」と報告したとします。でも、別の研究所が同じ土を測って「1kgあたり200mgでした」と言ったら、どちらの結果が正しいのか判断できませんよね。
実際、土壌汚染対策法では、鉛およびその化合物について「土壌1kgにつき150mg以下であること」と基準が定められています。100mgか200mgかでは、基準を超えているかどうかという重大な違いが生まれてしまいます。
こうしたときに必要になるのが、成分値があらかじめ正確に決められた“基準”です。
この“基準”を使って分析法や装置の精度を確認すれば、「異なる機関や測定者でも、ほぼ同じ結果になる」という“基準”が手に入ります。つまり、環境標準物質があることで、私たちは初めて「この数値は信用できる」と言えるようになるのです。
レシピ通りに料理をしても、作り手で味が違ってしまうのと同じ
Q. そもそも、分析値ってそんなにばらつくものなんですか?
はい、実は意外とばらつきが出るものなんです。
その理由は、大きく分けて「装置」、「手法」、「人」にあります。
まずひとつ目は、装置の違いです。同じ種類の分析装置でも、製造時のわずかな個体差や、使い続けることで起きる劣化などにより、出てくる数値が微妙に変わることがあります。温度や湿度といった周囲の環境条件も影響しますし、そもそも測定前にしっかりと装置を調整しておかないと、信頼性の高い結果は得られません。
次に、手法による違いです。分析は「試料を装置に入れて終わり」ではありません。たいていの場合、試料を溶かしたり、成分を取り出したりする「前処理」という工程が必要です。この前処理の方法や条件(温度、時間、使う薬品など)によって、結果が変わってしまうことがあります。
これに関連して、作業する人によっても差が生じることがあります。秤量や試薬の取り扱いなど、分析の現場では多くの作業が人の手で行われています。例えば、ちょっとした混ぜ方のクセが、結果に影響することもあります。レシピ通りに料理をしても、作り手で味が違ってしまうのと同じような状態が起こります。
こうしたさまざまな“見えない誤差”をコントロールし、誰が・どこで・いつ測っても「ほぼ同じ結果」が得られるようにするために、環境標準物質が役立ちます。環境標準物質は、実際の試料に近い成分を持っているので、分析の手順全体が正しく行われているかを確認するのに使います。ただし、分析装置そのものの精密な校正(キャリブレーション)には、専用の高純度な標準物質を使うのが一般的です。
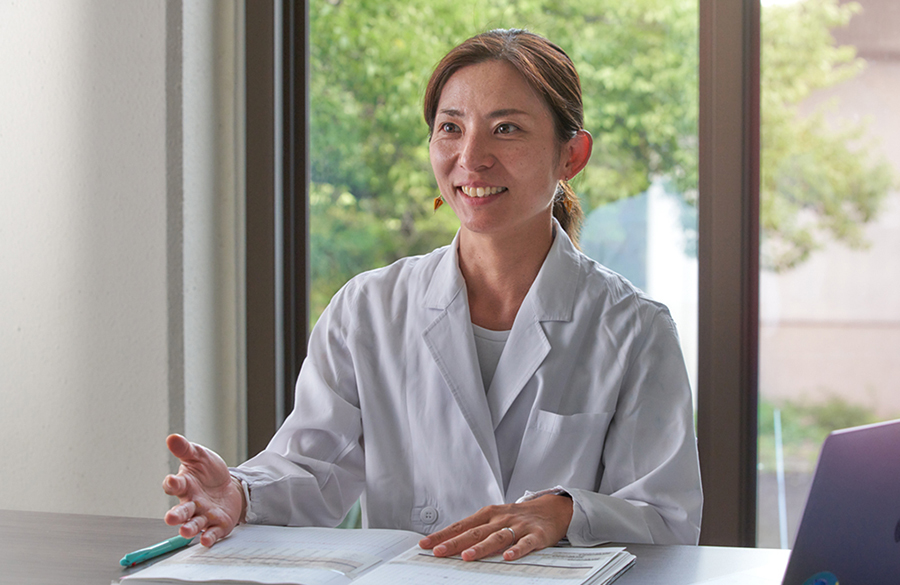
5年がかりの開発も。完成の瞬間は、チームの喜び
Q. NIESの環境標準物質は、どのようにして作られているのですか?
まず、開発の第一歩は「検討」です。社会的なニーズや、行政現場からの要請を踏まえて、どのような標準物質が必要とされているかを見極めます。現在開発中の「都市粉塵」は、かつて頒布していた類似の標準物質(NIES CRM No. 28 都市大気粉塵)が廃番となり、再開を望む声が多く寄せられたことがきっかけでした。一方で、研究の進展から新たな環境標準物質が生まれることもあります。たとえば、「新しい分析技術で今まで測れなかった成分が測定できるようになったから、それに対応する環境標準物質も作ろう」といった“研究者側からの要請”です。研究者の好奇心や技術への挑戦が、新たな環境標準物質開発の出発点になることも少なくありません。
対象が決まったら、原料を集めます。都市粉塵の場合は、東京都内の交通量が多い道路に設置されていた集塵フィルターを提供していただきました。
次に、開発の中で最も重要な工程が「均質化」です。標準物質は、どこを取っても同じ成分組成でなければなりません。大きな異物を取り除き、粒の大きさをふるいで揃えたうえで、全体をむらなく丁寧に混ぜ合わせ、瓶に詰めます。ただ、実際の環境中の粉じんは粒の大きさもさまざまです。あまり細かく篩いすぎてしまうと、現実の粉じんの特徴と離れてしまう心配もあります。そこで、均質性と現実性のバランスが保てるようにふるいの目の大きさも慎重に選ぶことが、標準物質作りの大事なポイントの一つとなります。
そして最後に行うのが測定です。瓶ごとに成分値にばらつきがないか、時間の経過によって成分が変化しないかなどを確認したうえで、国内外の分析機関と連携して成分値を決定します。すべての工程を終えた後に、認証書を添えて頒布できる状態となります。
標準物質の開発には多くのステップがあり、完成までに5年ほどかかることもあります。手間のかかる作業ではありますが、完成の瞬間は特別です。標準物質が完成したときは、チームでささやかにケーキを囲んでお祝いするのが恒例になっています。

回収した粉じんをふるいにかける作業(中央左右)。粉じんを瓶詰めする様子(右上下)。

信頼性の高い標準物質を提供し続けることが、私たちの重要な使命
Q. 丁寧な工程を経て作られていることがよくわかりました。では、そもそもNIESでは、いつ頃から環境標準物質の開発を始められたのでしょうか?
NIESでは、1979年に日本初の環境標準物質「リョウブ」を頒布したのが始まりです。リョウブは、落葉広葉樹の一種で、高さ7〜9メートルほどに育ち、夏には白い小さな花を咲かせます。この植物は、ニッケルやコバルトなどの重金属を濃縮する性質を持ち、土壌の汚染の程度を植物を通じて評価するための試料として活用されました。
当時、日本では高度経済成長の影響により、大気汚染や水質汚濁といった環境問題が深刻化していました。そうした背景の中で、環境中の物質を正しく測るためには、信頼できる“基準”が必要とされるようになったのです。NIESはこの社会的な要請に応えるかたちで、環境標準物質の開発に着手しました。
その後も、環境問題の多様化に伴い、粉じん、土壌、生物組織、さらにはヒトの頭髪や尿といった試料まで、幅広い媒体に対応した標準物質の開発を進めてきました。
現在では、国内でも他の研究機関や学会が標準物質を頒布していますが、環境分野における標準物質のパイオニアとしての立場を、NIESは今も担い続けています。今後も、環境試料の化学成分を正しく測るために、信頼性の高い標準物質を提供し続けることが、私たちの重要な使命です。

学生時代に自分なりの“標準物質もどき”を作ったりもしていました
Q. 開発に携わっている方は、もともと環境標準物質の開発に興味があってNIESに入所されたのですか?
私が担当するようになったのはここ5年ほどで、それ以前の長い歴史があります。環境標準物質の開発に最初に着手されたのは、岡本研作先生です。先生は後に物質工学工業技術研究所(現在の産業技術総合研究所)に移られ、そちらでも環境分析用の標準物質の取り組みを立ち上げられました。まさに、国内におけるパイオニアです。
その後、数多くの研究者がNIESでこの仕事に携わってきました。私が現在の業務を引き継いだのは、佐野友春先生からです。私以外のチームメンバーは皆、環境化学や計測技術の発展に長く関わってこられた強者ぞろいです。私はもともと宇宙化学を専門にしていました。学生時代からポスドクまでは、隕石の化学分析を通じて初期太陽系における固体物質の進化を研究していました。環境化学は全く無縁だったわけですが、宇宙の研究でも「正しく測る」ことには強くこだわってきました。隕石はごくわずかしか使えない貴重な試料です。その中から可能な限り多くの化学情報を引き出すため、分析手法の開発にかなり時間をかけていましたし、大量に手に入る地球の岩石を使って、自分なりの“標準物質もどき”を作ったりもしていました。今振り返ると、分析結果に信頼性を持たせるという意味では、今の環境標準物質の仕事と驚くほど通じるところがあります。
頼りになるのは長年の経験からくる“判断力”や“技術”です
Q. NIESの環境標準物質は、どのような体制で開発を進めているのですか?
実は、環境標準物質の開発にメインで携わっているのは、現在わずか4人です。担当研究者が全体を取りまとめ、高度な技術を持つ専門スタッフ2名と、事務スタッフ1名が開発・品質管理から広報まで幅広い業務を担っています。また、必要に応じて、他の研究者や職員の協力も得ながら進めています。NIESは研究対象が非常に多岐にわたるため、その道を専門としている研究者の知見を取り入れられるのは大きな強みです。
標準物質作りは、見た目には「ものをつくる作業」に見えるかもしれませんが、実は“人の技術と判断”がとても重要です。たとえば「粉じん」とひとくちに言っても、採取する場所や方法によって原料の性質が変わります。前回の「都市大気粉塵」と同じ方法をそのまま使えば良いというわけではなく、毎回、慎重な検討と試行錯誤が欠かせません。
その際に頼りになるのが、長年の経験からくる“判断力や“技術”です。ISOのガイドライン(国際的に定められた標準物質作製の手順書)に沿って作製を進めていますが、環境標準物質は自然由来の原料を使うため、毎回少しずつ性質が違ってきます。そうした違いを見極めながら作製するには、やはり経験豊かな技術者の判断が欠かせない場面も残っています。
原料の処理から均質化、瓶詰め、分析といったすべての工程は、技術スタッフが丁寧に行っています。スタッフは、研究者の判断を実際の作業に落とし込む橋渡し役でもあり、その経験と判断力が標準物質の品質を大きく左右します。
私自身も作業に関わっていますが、その所作は本当に見事で、一朝一夕に身につくものではありません。一つひとつ教わりながら、少しずつ自分の体にもその感覚を覚え込ませているところです。
そうした日々の作業は、歴代の担当者が積み重ねてきた知恵と工夫の上に成り立っています。“技術の伝承”があるからこそ、環境標準物質の品質と信頼性を今日まで保ち続けることができています。チームの人数は多くありませんが、その分だけ一体感は強く、「自分たちがこの基盤を支えている」という実感と誇りを持って日々の業務に取り組んでいます。
測ることへの信頼を支えるために、環境標準物質は今日もつくられています。
時間と手間、そして技術と思考の積み重ねが、これからも社会を支えていくのです。
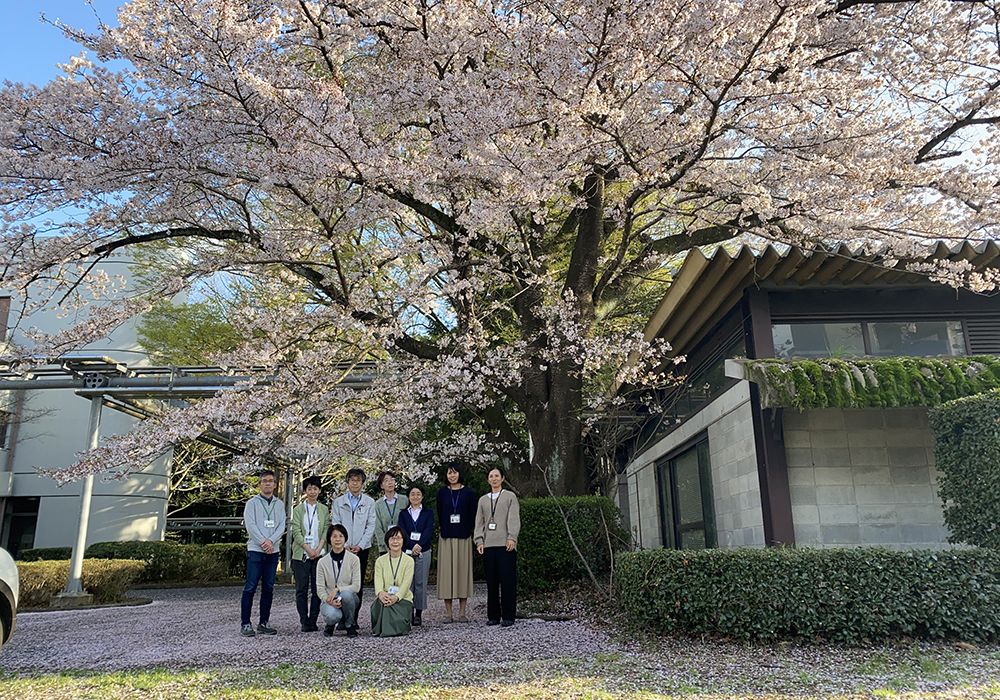
(左上:高澤室長、永野さん、佐野先生、大西さん、稲益さん、家田さん、山川、左下:宇加地さん、肥後さん)
| インタビュアー・進行・構成 | 環境リスク・健康領域 林 千晶・山川 茜 |
|---|---|
| 写真撮影 | 企画部広報室 成田 正司、基盤計測センター CRM提供 |
- インタビュアー・進行・構成
- 環境リスク・健康領域林 千晶・今泉 圭隆
- 写真撮影
- 企画部広報室成田 正司
Profile / Message

山川 茜 YAMAKAWA Akane  NIES研究者紹介
NIES研究者紹介
環境リスク・健康領域 基盤計測センター 環境標準研究室 主任研究員
経歴:兵庫県出身。岡山大学大学院自然科学研究科修了。2013年国立環境研究所入所。専門は地球化学。
趣味:テニス(ベテランJOPでの勝利を目指して週末は練習や試合に明け暮れています。)
 NIES研究者紹介
NIES研究者紹介