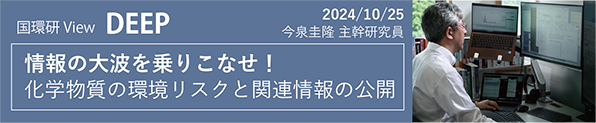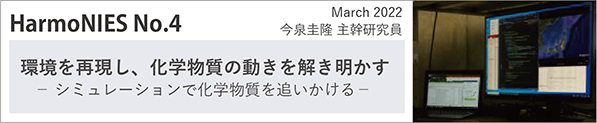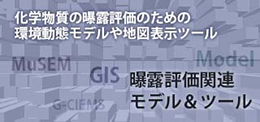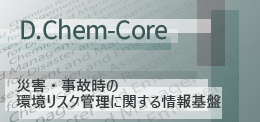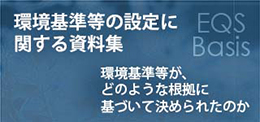2025.03.11
研究者インタビュー Vol. 1
情報革新の大波に翻弄されつつサバイバル
~環境研究者がなぜ複雑なウェブサイトの構築に携わっているか~
今泉 圭隆

環境研究の研究者としてはあまり例がありませんが動的なウェブサイト(利用者がウェブページ上で行った行為によってページの内容や表現などが変わるサイト)を自身で開発・構築している研究者へのインタビュー記事です。研究者が自ら開発しているのはなぜか、またそんな経験からくる苦労や喜びなど、他の公開記事では知りえない裏話をいろいろと伺いました。
国立の研究機関だからこそできる利便性の高いウェブサイトを
Q1. 今泉さんはWebkis-Plus(https://www.nies.go.jp/kisplus/  )というウェブサイトの構築や運用に携わっていますね。まずそのWebkis-plusについてご説明いただけますか。
)というウェブサイトの構築や運用に携わっていますね。まずそのWebkis-plusについてご説明いただけますか。
このサイトでは化学物質の環境リスク*1 に関連する情報を広く、様々な情報源から収集し、公開しています。多くの化学物質は我々の生活を豊かに、便利にしてくれます。しかし、一部の化学物質は人や生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。それぞれの化学物質について、悪影響を及ぼす可能性がないかどうかを様々な観点で評価している(その化学物質が“危険”なのか調べる)のですが、その一部に環境リスク評価という、環境中に存在する化学物質の悪影響を評価する枠組みがあります。Webkis-plusでは環境リスク評価に関連して、様々な組織が評価した化学物質の有害性や環境中への排出量、環境中での検出状況、環境分析法などを公開しています。(関連情報は、「国環研DEEP:情報の大波を乗りこなせ!化学物質の環境リスクと関連情報の公開」(https://www.nies.go.jp/kokkanken_view/deep/column-20241025.html#gsc.tab=0  )や「HarmoNIES No.4: 環境を再現し、化学物質の動きを解き明かす」(https://www.nies.go.jp/kanko/harmo/harmonies04-j.html
)や「HarmoNIES No.4: 環境を再現し、化学物質の動きを解き明かす」(https://www.nies.go.jp/kanko/harmo/harmonies04-j.html  )、「曝露評価シミュレーションモデル&ツール:環境モデルの背景」(https://www.nies.go.jp/rcer_expoass/background.html
)、「曝露評価シミュレーションモデル&ツール:環境モデルの背景」(https://www.nies.go.jp/rcer_expoass/background.html  )などをご覧ください。)
本サイトではいくつかの省庁の公表データなども集めて公表しています。これらの情報は各省庁でも公開されているのですが、各省庁のサイトでは他の省庁の情報を含めてまとめて公開されることはあまりありません。我々は、環境リスクに関連する情報に絞って、複数の省庁などで公開している情報を収集・整理することで利便性の高い情報サイトとしてWebkis-plusを構築し公開しています。情報源に依らず関係する情報を収集し公開できるのは、省庁の所掌範囲に囚われることが少ない独立行政法人(国立研究開発法人)だからこそです。また、新規性が求められる一般的な研究業務とは性質がやや異なる情報公開サイトの構築・運用を長期間実施できているのは、行政対応的な業務を実施することができる研究機関だからこそです。なお、限られた予算の中で新しい機能の追加やIT技術の進展に対応するために、システム開発および運用の大部分は数少ない内部スタッフで進めています。私もその中の一人です。
)などをご覧ください。)
本サイトではいくつかの省庁の公表データなども集めて公表しています。これらの情報は各省庁でも公開されているのですが、各省庁のサイトでは他の省庁の情報を含めてまとめて公開されることはあまりありません。我々は、環境リスクに関連する情報に絞って、複数の省庁などで公開している情報を収集・整理することで利便性の高い情報サイトとしてWebkis-plusを構築し公開しています。情報源に依らず関係する情報を収集し公開できるのは、省庁の所掌範囲に囚われることが少ない独立行政法人(国立研究開発法人)だからこそです。また、新規性が求められる一般的な研究業務とは性質がやや異なる情報公開サイトの構築・運用を長期間実施できているのは、行政対応的な業務を実施することができる研究機関だからこそです。なお、限られた予算の中で新しい機能の追加やIT技術の進展に対応するために、システム開発および運用の大部分は数少ない内部スタッフで進めています。私もその中の一人です。

ウェブシステムを長く維持していくには、自分で開発し、自分で世話をしていくのが最善
Q2. なぜ研究者ご自身で開発されているのですか?
それには私自身の経験や関心と、歴史的経緯が関係しています。もともとプログラミングの授業は好きでしたし、プログラム関連のバイトに携わったこともありました。また、学生時代の研究でも数値計算のプログラムを構築したこともあり、IT関連のことは好きでした。そういった意味で、元々の地盤は多少ありました。
私が国立環境研究所に入所した2004年頃から、Webkis-Plusの関連事業に関わっていますが、その当時は、外部の業者に大規模なウェブシステム(データベースと連携したウェブサイト)の構築を依頼していました。その後、限られた予算の中でシステムを維持していくために、システム公開後に必要になったシステム改修や改良は私を含む内部の担当者で進めるしかありませんでした。
ウェブシステムは土台となるシステム(Windows、Linuxなど)の上に構築されています。土台のシステム側が更新・変更されると、その上に構築したシステム側も大規模な改修が必要になることがあります。一方で、研究予算は、ある新しいことを進める場合は獲得しやすいのですが、既存のものを更新する(でも、できることは変わらない)という場合には獲得しにくい傾向にあります。仮に予算獲得を目指すとしても、どの程度の費用が必要か把握する必要があり、そのためにはウェブサイトの設計図が必要になり、そのためには最新のウェブ関連の知識を身につけることが必要になりました。調べていくと、ウェブシステムの開発の世界はまさに日進月歩であり、無料で便利なモノが沢山あることが分かり、それらを上手く使うと比較的簡単にシステムの一部を構築できそうだということに気づきました。また、中に入れるデータの形があらかじめ決まっているデータベースというものは、色々な例外が起こりうる化学物質情報との相性があまり良くないです。例えば、分離が難しいため一つの物質として扱っていたものが、分析技術の発展により区別できるようになったとか、混合物としてしか製造できないため一つの物質として扱っていたものが、新たな製造方法が開発されて混合物のうちの重要な成分だけ選択的に作れるようになったとか、そういった事例があります。このような例外が少しでもあるとデータベース化する際にすごく苦労します。したがって、化学物質の知識がないとデータ構造を設計することが難しいです。こういった状況を踏まえて、限られた予算の中でウェブシステムを長く維持していくには、自分で開発し、自分で世話をしていくのが最善なのではという考えに至ったのです。
データやプログラムに関する本質的な知識とセンスが必要
Q3. そもそもシステム開発の知識はなかったとのことですが、この仕事を進める中でどんなご苦労がありましたか?
入所時には、基本的なプログラミングとデータベースの基礎的知識はありました。逆にいえば、それしかありませんでした。大量かつ多様なデータを公開し、かつ利便性が高いウェブシステムの開発には様々なレベルの知識が必要でした。試行錯誤のために自分でサーバを構築したり、外部からの攻撃に対抗するためにサーバへの攻撃方法と対策を学んだり、ウェブサイトの基本的知識(HTMLやCSS、サーバサイドプログラミングとクライアントサイドプログラミングなど)を理解する必要がありました。また、大量データを利用したサイトなので、速さ(利用者の操作に応じて適切な結果を画面に表示する速さ)を保つことが重要かつ難しいです。ただ動くプログラムを作ることと、高速に動くプログラムを作ることでは難易度がかなり違います(後者の方がはるかに困難)。後者のためには、データやプログラムに関する本質的な知識とセンスが必要になります。
ITの世界は進化が速いため、ほんの数年前の常識が通用しない場合もあります。私はウェブシステムの開発・運用だけをしている訳ではないため、継続的に知識を得ることが難しく、システム改修などの必要に迫られるたびに最新情報(の一部)を勉強して対応しています。
これらの苦労が周りに伝わりにくいことがつらいと感じることはたまにあります。ウェブシステム開発の知識は環境研究に携わる上で必ずしも必要ではないからです。その状況を理解はしていますが、寂しさはあります。なので、謙遜の美徳には反しますが、このような場で表明できてうれしいです(笑)

システム構築という技術だけにとどまらず、普段の研究活動を進める上で参考になる示唆を得られる
Q4. いろいろなご苦労がわかりました。ご苦労ばっかりにも感じますが(笑)。では、逆に喜びはありますか?
IT技術の中の新しい考え方や技術を学ぶのは知的好奇心が満たされて楽しいです。良いプログラム(ソースコード)とはどういうものかという技術的な話題の中に、非常に人間くさい経験から導きだされたルール・方針があるなど、システム構築という技術だけにとどまらず、普段の研究活動を進める上で参考になる示唆を得られる時もあります。もちろん、サイトへの問い合わせや学会等で外部の方から感謝や称賛の言葉をいただくこともあり、そういった際には長年運用してきて良かったと感じます。外部の方の研究発表などで我々のサイトからデータを引用していただいていた時なども世のためになっていることを実感できてうれしいです。
国立環境研究所には、私が開発に深く関わった「環境基準等の設定に関する資料集」(https://www.nies.go.jp/eqsbasis/  )と災害・事故時の環境リスク管理に関する情報基盤D.Chem-Core(https://www.nies.go.jp/dchemcore/
)と災害・事故時の環境リスク管理に関する情報基盤D.Chem-Core(https://www.nies.go.jp/dchemcore/  )というサイトも公開されています。Webkis-Plusの構築の経験を活かした成果であり、知識・経験を有効活用できている点も個人的には満足しています。
)というサイトも公開されています。Webkis-Plusの構築の経験を活かした成果であり、知識・経験を有効活用できている点も個人的には満足しています。
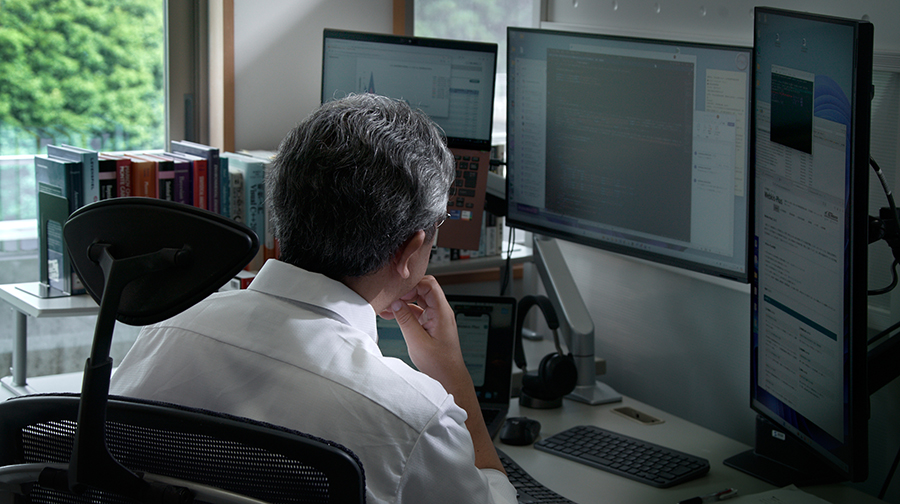
「今と将来のために最も重要なことは何か」を常に考えること
Q5. なるほど、様々な知識や経験を生かして様々なシステムの開発や運用を担当しているのですね。それでは最後に今後の抱負と、研究者を志す高校生・大学生へのメッセージをお聞かせください。
IT技術は進化し続けています。そのため、既存のシステムは徐々に古くなっていき、いつか必ず改修が必要になります。将来もしかしたらAI技術の進化によって、情報の収集・整理と公開という仕事はAIが簡単に実現してくれるようになるかもしれません。そんな“近い”将来を想像すると二つの相反する思いが頭によぎります。一つは、「AIがどこまで信用できるのか、間違った情報が含まれている時に人間はそれに気づくことができるのか、やはり信頼できる情報を公開することに意味があるのではないか」ということ、もう一つは「AIが実現してくれたら、“無意味なこと”に時間を割くのではなく、もっと重要なことに貴重な時間を割くべきではないか」ということです。どちらが正しいかは分かりません。でも、重要なことは、「今と将来のために最も重要なことは何か」を常に考えることだと思っています。それは、このWebkis-Plusというシステムの開発・維持だけでなく、私の研究活動全般に当てはまることです。それがどこまで実践できているかは・・・あまり自信がないですが、引き続き精進していきたいと思います。
研究者になろう・なりたいと考えている方へのメッセージというのはおこがましいので、高校生・大学生だった頃の自分に伝えるつもりで。身の回りや世の中のこと全てに興味・関心を持って、なぜ今そうなっているか、過去からどのように変化してきたか、将来どうなっていくか、考えて・想像してみてください。文系理系とかの枠に囚われず、言語、地理、文化、政治、科学、いまこれを読んでいるスマホやパソコンなど様々なものに関心を向けて知的好奇心を育んでください。将来必ず血肉となって役に立ちますよ。
*1 環境リスク:
環境リスクという用語の意味は明確には定まっていません。時代とともにその概念は変わって、あるいは広がってきています。
例えば、中西準子・益永茂樹・松田裕之編の「演習 環境リスクを計算する」(岩波書店、2003年)では、
環境リスクとは、「環境にとって良くない出来事」、つまり「環境保全のために回避したい出来事」が起きる確率(生起確率)である。
と記載されています。環境省環境リスク初期評価のホームページ(https://www.env.go.jp/press/press_02533.html  )では、
)では、
様々な産業活動や日常生活で利用される化学物質、また焼却等に伴い非意図的に発生する化学物質が、大気、水、土壌等の環境媒体を経由して環境の保全上の支障(人の健康及び生態系に好ましくない影響)を生じさせる蓋然性
(環境リスクの説明になるように著者(今泉)が文章を編集しました)
と説明されています。鈴木規之の「環境リスク 再考」(丸善、2009年)では、
広く一般的な、環境の安全に対する懸念
(本書の中で、一般的に用いられる環境リスクという言葉について、確率論としてのリスクとは別の概念であり両者は区別すべきと指摘されています)
と記載されています。
| インタビュアー・進行・構成 | 環境リスク・健康領域 林 千晶・今泉 圭隆 |
|---|---|
| 写真撮影 | 企画部広報室 成田 正司 |
- インタビュアー・進行・構成
- 環境リスク・健康領域林 千晶・今泉 圭隆
- 写真撮影
- 企画部広報室成田 正司
Profile / Message

今泉 圭隆 IMAIZUMI Yoshitaka  NIES研究者紹介
NIES研究者紹介
環境リスク・健康領域 リスク管理戦略研究室 主幹研究員
経歴:長野県出身。東京大学大学院工学系研究科修了。2004年国立環境研究所入所。専門は環境工学。
趣味:バスケ観戦(Bリーグの某青いチームのファンです。退職したら画像解析とAI技術、データベース、プログラミングスキルを駆使するアナリストとしてチーム編成に関わるという妄想が。私が元気なうちに日本一になってくれ!!)
最近うれしかったこと:長年懸案だったブリ大根を美味しく作れるレシピに出会った。
 NIES研究者紹介
NIES研究者紹介