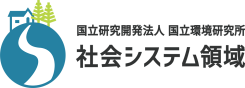統合研究プログラムの「統合」って?
vol.7-2 増井 利彦 室長<後編>
2017.9.7
インタビュー対象
前編に引き続き、増井利彦室長にお話を聞いていきます。後半では、昨年度から始まった課題解決型研究プログラムの一つである「統合研究プログラム」について伺いました。プログラムのタイトルにある「統合」とは、何を、どのように統合することを指すのでしょうか。

インタビュー内容<後編>
続いて統合研究プログラムについて伺いたいのですが、どんなプログラムですか?
これまで環境研や、ほかの研究機関でも取り組まれてきた「持続可能」というキーワードを、「統合」というものに置き換えてやっているプログラムかなと個人的には思っています。2017年4月の国立環境研究所ニュース(リンク)でも原稿を書きました。
環境研の前の期の中期計画で実施していた「持続可能社会転換方策研究プログラム」とか、社会環境システム研究センターが行ってきた特別研究とか、持続可能についてのいろいろな研究プロジェクトがありました。温暖化だけではなくて、いろんな問題に取り組んできたんですけれども、それを発展させることが統合研究プログラムの役割なのかなと、思っています。
統合というのがキーワードなんですが、まず何を統合するのかがすごく重要です。低炭素、資源循環、自然共生、安全確保、あと福島で取り組んでいる環境創生プログラム。そういういろんな課題での取り組みを統合していく。それぞれの問題ごとに、今は答えを出そうとしていますが、例えば同時に解決するという視点で見たときにどういう問題があるのか。環境問題だけではなく、社会、経済を併せて取り組んだときに、どういう答えが出てくるのか。そういうことも考えていきたいです。
環境研の前の期の中期計画で実施していた「持続可能社会転換方策研究プログラム」とか、社会環境システム研究センターが行ってきた特別研究とか、持続可能についてのいろいろな研究プロジェクトがありました。温暖化だけではなくて、いろんな問題に取り組んできたんですけれども、それを発展させることが統合研究プログラムの役割なのかなと、思っています。
統合というのがキーワードなんですが、まず何を統合するのかがすごく重要です。低炭素、資源循環、自然共生、安全確保、あと福島で取り組んでいる環境創生プログラム。そういういろんな課題での取り組みを統合していく。それぞれの問題ごとに、今は答えを出そうとしていますが、例えば同時に解決するという視点で見たときにどういう問題があるのか。環境問題だけではなく、社会、経済を併せて取り組んだときに、どういう答えが出てくるのか。そういうことも考えていきたいです。
それは共同研究を強化していくということですか。

そうですね。一つは、AIMもまさにそうなんですけれども、統合評価モデルではいろいろな学問領域を統合して、解決策を検討しようとしています。一方で、これまでの個別の学問は、どちらかというと1つの専門性に向かってすごく細かく深く原因を解明して、答えを追求していくというものでした。そうやって解決策を練るとか、検討するのが従来の科学のやり方です。しかし温暖化のようなグローバルで複雑な問題は、1つの専門性だけで解決されるような問題ではありません。いろいろな分野の知見を集めて、それらを組み合わせて最も有効な解を見いだしていこうという、そういう考え方が統合評価であり、それを定量的に示そうとしたのが統合評価モデルです。
その考え方に基づいて、AIMももともと温暖化問題の解決のためだけのものだったんですけれども、それをさっき言った循環の話とか、自然共生だとか、他の分野にさらに拡張していくことが統合研究の一つの形なのかなと思っています。
課題解決に向けた統合も一つなんですけれど、その手法も統合していくことが重要になってきます。統合研究プログラムが示している5つの軸の中では、その手法の統合があまり明確にされていません。本当は、物理学や化学の話、工学的な話と経済学の話というように、いろんな学問分野があって、それらも統合していくことが必要です。それは単に1つにまとめるというよりかは、問題解決に向けてその概念を共有するような、そういうことが必要になっていくのではないかと思っています。
その考え方に基づいて、AIMももともと温暖化問題の解決のためだけのものだったんですけれども、それをさっき言った循環の話とか、自然共生だとか、他の分野にさらに拡張していくことが統合研究の一つの形なのかなと思っています。
課題解決に向けた統合も一つなんですけれど、その手法も統合していくことが重要になってきます。統合研究プログラムが示している5つの軸の中では、その手法の統合があまり明確にされていません。本当は、物理学や化学の話、工学的な話と経済学の話というように、いろんな学問分野があって、それらも統合していくことが必要です。それは単に1つにまとめるというよりかは、問題解決に向けてその概念を共有するような、そういうことが必要になっていくのではないかと思っています。
専門性を超えて、共通の認識や目標を作っていくようなイメージですか?
超えてというか、それぞれの専門性のエッセンスを提供してもらい、われわれからも結果をフィードバックするというイメージです。その上で、環境・社会・経済の課題に対して取り組んでいくということですね。そのための場を提供しつつ、解決策や改善策を見いだしていくことが統合研究の役割かなと思います。
「持続可能」という概念が1980年代にできてから、ずっと使われ続けていますが、概念がぼんやりとしてるから、どのようにも解釈できて、それが今でも残っている理由の一つなんだろうとは思います。それでも、これだけ浸透していて使われているということは、それなりに魅力的な用語ではあると思うので、そういうものを使いながら、実際にどう問題を解決できるのかということを見ていけたらとは思っています。
具体的にどう統合していくのかが一番課題だと思うんですが、いかがですか?

そうですね。そこはやっぱり難しいです。これまでの科学の流儀や、論文を書くためのいろいろな流儀に従って論文を書こうとすると、問題解決に向けた提案まで十分に手が回らなくなるかもしれません。かといって、問題解決のほうに強い思い入れを持ってしまうと、今度は研究として取り組むべきところがおろそかになる可能性があり、なかなか新しいものができなくなったりします。そういったバランスの難しさはありますね。
しかし、環境研として取り組む限りにおいては、今後さらにいろんな問題が出てくる可能性があるので、何か一つの答えを出す以外に、解決策に至る方法論の研究をしないといけませんね。何らかの問題が出てきたときに、環境の視点、あるいは社会とか経済をどう考えていくのか、そういう方法論的なところも何か提示できたらなと思っています。
しかし、環境研として取り組む限りにおいては、今後さらにいろんな問題が出てくる可能性があるので、何か一つの答えを出す以外に、解決策に至る方法論の研究をしないといけませんね。何らかの問題が出てきたときに、環境の視点、あるいは社会とか経済をどう考えていくのか、そういう方法論的なところも何か提示できたらなと思っています。
答えそのものよりそれに至る考え方を作るんですね。
解決策まで出そうとすると、客観的なものだけではなく、主観的なものも入ってきます。今の科学研究はなるべく主観を排除する傾向がありますが、それでも主観は、絶対にはなくなりません。場面ごとにどう考えていくかについて、主観は入ったとしても、やり方としては客観的に、どういう問題でも適用できますよ、とか、あるいは、誰がやっても同じような答えが出ますよ、という、そういうものを目指していきたいと思っています。
しかし、おそらくそれだけでは十分ではないので、実際には具体的にこういうふうにすればいいですよと示せるような、主観が入ったものとなりますが、具体的なロードマップも出さないといけないんでしょうね。
抽象的な考えのところは大事だろうなとは思いつつ、やはり具体的にどうするのかが気になりますよね。
そこが一番難しいとこですね。すべての人が関わる問題なんで、すべての人が主体的に関わってほしいですけれど、そうしてしまうと、いろんな意見が出てしまって収拾がつかなくなることも多分ありますよね。それぞれの範囲でできることは何なのかを考えてもらえるきっかけをまず用意できればと思っています。
最後に、増井さん個人として、今後の目標ややっていきたいことがあれば教えてください。

いろいろやりたいんですけど、そのための時間をつくるっていうのが、厳しいかなっていうのが正直なところではあります(苦笑)。
今までは、モデルを開発したり論文を書いたりすることを仕事でずっとやってきてはいますけれど、環境の問題は、世の中が本当にうまく回るというか、問題解決もできることが非常に重要なんじゃないかなと最近思うようになってきました。ツールや論文として新しい知見を見つけることももちろん重要です。それとともに、一般の方にも分かりやすく伝えることも重要です。何か新しいライフスタイルに変わるとか、製品開発に役立つなど、そういうものにつなげていただけるように、なるべく分かりやすいかたちで伝えていくためのアウトリーチが重要ではないかなと思っています。
例えば、将来のシナリオを作るにしても、モデルの研究者は、将来の人口はこれくらいになるということを様々な文献からある程度は見通せますけれど、それ以外のライフスタイルの変化だとか、あるいは産業構造などを研究者だけでこういう文献があったからと引用してくるのは、それはそれですごく問題があるんじゃないかと思うようになっています。
ステークホルダー会合というものがあるように、いろんな人たちの意見を聞きながらそこで出た意見を反映するとこういう結果が出ますよと示してみる。研究者とは違った意見も含めて、もう一度議論しながら、将来を作り上げていく。そういうことをできたらなと強く思っています。
あとはやっぱり、次の世代の人たちの指導というか育成ですね。幸いなことに東京工業大学で教える機会があるので、若い学生たちといろいろ議論はしてます。彼らの新しい考え方はこちらにもすごく刺激になる。そういう彼らの考えているものを、僕自身が今までに開発してきたモデルで実際定量化していくような、そういうプロセスはやっていて非常に楽しいです。
新しいものにどんどん作り替えていくことは非常にいいなと思いますし、もっと取り組みたいと思いますね。新しいものを作って、発信していきたいなと思っています。
今までは、モデルを開発したり論文を書いたりすることを仕事でずっとやってきてはいますけれど、環境の問題は、世の中が本当にうまく回るというか、問題解決もできることが非常に重要なんじゃないかなと最近思うようになってきました。ツールや論文として新しい知見を見つけることももちろん重要です。それとともに、一般の方にも分かりやすく伝えることも重要です。何か新しいライフスタイルに変わるとか、製品開発に役立つなど、そういうものにつなげていただけるように、なるべく分かりやすいかたちで伝えていくためのアウトリーチが重要ではないかなと思っています。
例えば、将来のシナリオを作るにしても、モデルの研究者は、将来の人口はこれくらいになるということを様々な文献からある程度は見通せますけれど、それ以外のライフスタイルの変化だとか、あるいは産業構造などを研究者だけでこういう文献があったからと引用してくるのは、それはそれですごく問題があるんじゃないかと思うようになっています。
ステークホルダー会合というものがあるように、いろんな人たちの意見を聞きながらそこで出た意見を反映するとこういう結果が出ますよと示してみる。研究者とは違った意見も含めて、もう一度議論しながら、将来を作り上げていく。そういうことをできたらなと強く思っています。
あとはやっぱり、次の世代の人たちの指導というか育成ですね。幸いなことに東京工業大学で教える機会があるので、若い学生たちといろいろ議論はしてます。彼らの新しい考え方はこちらにもすごく刺激になる。そういう彼らの考えているものを、僕自身が今までに開発してきたモデルで実際定量化していくような、そういうプロセスはやっていて非常に楽しいです。
新しいものにどんどん作り替えていくことは非常にいいなと思いますし、もっと取り組みたいと思いますね。新しいものを作って、発信していきたいなと思っています。
そうですね。世の中も人の感覚もどんどん新しくなりますよね。

そうですね。統合評価モデルのグループでは、コンソーシアムというのがあって、国際的な大きな流れを作っています。そこに日本が深く関わっていくのは、言葉の問題含め、いろいろな課題があって、難しいところもあります。真っ正面から取り組んでいくことも、一つのやり方ではあるんですけれど、研究者の数や時間など資源も限られている中で、そういう方法で進めていくのがいいのかなと考えることがあります。少し視点を変えて、みんながまだ取り組んでいないことや、あるいは、あまり注目されていないところに、きちんと今のうちから取り組んでおくのも研究の進め方の一つです。5年後、10年後に、それは非常に大切なことだったと認めてもらえるような、そういったかたちで取り組めたらとは思っています。
その一つの例が、アジアでいろいろ取り組んできたことです。これまで欧米の統合評価モデルのグループは先進国を中心に研究してきました。最近になって途上国と連携して取り組むようになりました。環境研のAIMのグループの場合は、20年以上前からモデル開発といったことをアジアの途上国の人たちと一緒にやってきています。そのため、アジアを対象に研究するなら環境研のAIMのグループに声を掛ければ、アジアのいろんな人たちも参加してくれるという、そういう信頼ができています。そういう中での日本的な、あるいはアジアで研究しているからこその独自性は、大切にしていきたいと思っています。
その一つの例が、アジアでいろいろ取り組んできたことです。これまで欧米の統合評価モデルのグループは先進国を中心に研究してきました。最近になって途上国と連携して取り組むようになりました。環境研のAIMのグループの場合は、20年以上前からモデル開発といったことをアジアの途上国の人たちと一緒にやってきています。そのため、アジアを対象に研究するなら環境研のAIMのグループに声を掛ければ、アジアのいろんな人たちも参加してくれるという、そういう信頼ができています。そういう中での日本的な、あるいはアジアで研究しているからこその独自性は、大切にしていきたいと思っています。
確かに、アジアが今後どうなるかは、かなり注目されるところでしょうね。
はい、それもあっていろんな国がアジアにどんどん進出してきています。けれども、単にアジアの状況がどうかということだけじゃなくて、アジアの人たちの人材育成も含めて取り組んでいけたらとは思っていますね。
いろいろ課題もやりたいこともあるようですので、これからも頑張ってください!
お話しありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に
第7回インタビューでは、増井利彦室長にAIM(アジア太平洋統合評価モデル)と統合研究プログラムについてお話しいただきました。AIMは20年以上積み重ねてきた研究活動をさらに発展させていくようです。統合研究プログラムについては、「統合」の対象は様々ですが、それぞれの統合によって、環境問題に対する新しい考え方や解決策が生み出されることを期待していきたいです。
(聞き手:杦本友里 社会環境システム研究センター)
(撮影:成田正司 企画部広報室)
インタビュー実施:2017年1月19日
(聞き手:杦本友里 社会環境システム研究センター)
(撮影:成田正司 企画部広報室)
インタビュー実施:2017年1月19日