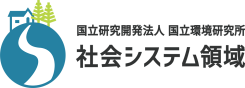要旨:This study examines the effects of environmental tax policies in a dynamic model of a polluted small open economy in which there are two sources of pollution, consumption and production, controlled by consumption and income taxes, and accumulated pollution affects a negative effect on household's utility. In a decentralized dynamic competitive equilibrium under exogenous tax rates, we show that whereas a permanent increase in each of the consumption and income taxes unambiguously reduce the steady-state stock of pollution, a temporary increase in these taxes may lead to more pollution in the long run, suggesting that more stringent environmental policy might be ineffective if the regulation is only temporary. We also derive the social optimal solution and examine the optimal tax paths to achieve the social optimum. If distaste and leisure effects are sufficiently strong, tax rates decrease along the optimal path as pollution increases over time, and if these effects are not so strong, the opposite occurs.
報告者2:生藤昌子(筑波大学)
演題:Environmental policy in a stagnant economy (with Yoshiyasu Ono, ISER Osaka University)
要旨:Using a dynamic optimization model of a monetary economy in which persistent unemployment occurs, we examine the effects of environmental policies on aggregate consumption and pollution emission in a stagnant economy with persistent deflation. If full employment is achieved, environmental policies, such as imposing an emission tax to restrict pollution and employing labor in the public pollution-abatement sector, naturally crowd out commodity production and hence decrease consumption. If unemployment prevails, however, those environmental policies stimulate private consumption by expanding total employment and mitigating deflation. Their effects on welfare are also examined.
第16回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2018年7月24日(火)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室
使用言語:日本語
報告者:木曽貴彦(アバディーン大学)
演題:A Subsidy Inversely Related to the Product Price
要旨:This paper proposes a new subsidy scheme for promoting a target good’s consumption, where subsidy payment is inversely related to the good’s price. Under imperfect competition, this scheme makes the demand faced by producers more elastic, thereby reducing their power to raise prices and increasing subsidy pass-through to consumers. Compared to commonly-used specific or ad valorem subsidies, it can lower government expenditure for inducing a given output, and flexibly adjust the incidence on producers. Simulations based on an actual U.S. subsidy programme on electric vehicles indicate up to 50?81% reductions in government spending if it replaces the current specific subsidy.
第15回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2018年5月9日(水)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 循環・廃棄物研究棟 3階会議室
使用言語:英語
報告者:山﨑 晃生(カルガリー大学)
演題:The Competitiveness Impacts of Carbon Tax: Evidence from British Columbia
要旨:In the recent years, many jurisdictions have been considering a carbon pricing policy as their future climate action plan. To better inform policymakers and the public about the potential costs and benefits of such policies, I investigate the impacts of British Columbia’s carbon tax. I use detailed confidential micro-level data to estimate its impacts on the competitiveness of plants and firms in BC. The findings from my research suggest that the carbon tax induces job shifts across industries while the net aggregate employment effect is rather small. However, it does impose costs in the manufacturing sector in the short-run, leading to declines in output, employment, and productivity. Yet, such negative shocks can be eased by recycling the tax revenue. These findings can be useful for designing the future carbon tax policy in other jurisdiction.
第14回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2018年4月13日(金)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 循環・廃棄物研究棟 3階会議室
使用言語:日本語
演者:伊芸 研吾(独立行政法人 国際協力機構(JICA)研究所)
演題:実務者と共同で行うインパクト評価:南アフリカにおける障害平等研修のインパクトに関するランダム化比較試験の紹介
共催:科研費補助金 挑戦的研究 (萌芽)「ランダム化比較試験を用いた環境・エネルギー政策研究の手法確立」
(研究代表者:野村久子 研究分担者:横尾英史、久保雄広、鈴木綾 研究協力者:小林 庸平、ケン・ヘイグ)
要旨:近年Evidence-Based Policy Makingが提唱されていることを受けて、研究者と実務者の距離が狭まり、共同で政策的介入のインパクトを評価する機会が増えている。しかし、研究者と実務者の利害が一致しないことは往々にしてあり、実りあるインパクト評価の実施のためには、双方の意向に配慮し調整することが重要であるといえよう。今回のセミナーでは、報告者がJICAのプロジェクト専門家と実施中の南アフリカにおける障害平等研修のインパクト評価の事例をもとに、分析結果と共に評価デザインの設計などの研究プロセスの詳細を紹介する。
第13回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2018年3月9日(金)14:00-16:00
場所:国立環境研究所 循環・廃棄物研究棟 3階会議室
使用言語:英語
演者:Prof. Jan R. Magnus(Vrije Universiteit Amsterdam (Department of Econometrics and Operations Research))
演題:Expected Utility and Catastrophic Risk in a Stochastic Economy-Climate Model (joint with Masako Ikefuji, Roger J. A. Laeven, and Chris Muris)
第12回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年10月6日(金)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 第二会議室(研究本館I 3階)
使用言語:英語
演者:Douglas MacMillan (University of Kent)
演題:The economics of conservation and sustainable land use
第11回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年10月4日(水) 9:45-11:15
場所:国立環境研究所 地球温暖化化研究棟 交流会議室
使用言語:英語
演者・演題:Prof. Ferdinando Villa(bc3, Spain)
「Characterizing beneficiaries in integrated ecosystem services assessments: an artificial intelligence approach (TDB)」
話題提供:
Dr. Ronald C. Estoque (国立環境研究所, 社会環境システム研究センター)
「Future changes in Southeast Asia’s forest cover and its ecosystem service value under the shared socioeconomic pathways: Initial results for the Philippines (TDB)」
第10回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年7月21日(金)15:00-17:00
場所:国立環境研究所 循環・廃棄物研究棟 3階会議室
演者・演題:
山口臨太郎(九州大学)
「Corruption, institutions and sustainable development: Theory and evidence from inclusive wealth」
高橋遼(学習院大学)
「When do consumers stand up for the environment? Evidence from a large-scale social experiment to promote environmentally friendly coffee」
第9回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年5月11日(木)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 第2会議室(研究本館I 3階)
演者:杉本興運(首都大学東京 助教)
演題:地理空間情報を応用した観光行動研究の潮流
第8回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年4月14日(金)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 循環・廃棄物研究棟 3階会議室(前)
演者:手島健介(メキシコ自治工科大学)
演題:Offshoring Health Risks: The Impact of the U.S. Lead Regulation on Infant Health in Mexico
共催:資源循環研究プログラムPJ2「循環資源及び随伴物質のフロー・ストックにおける資源保全・環境影響評価」
第7回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2017年2月7日(火)15:30-17:00
場所:国立環境研究所 第2会議室
演者:青柳恵太郎(株式会社グローバル・グループ21ジャパン)
演題:フィールド実験における実務者連携のコツ:JICAにおけるRCT実践の経験から
コメンテーター:野村久子(九州大学 農学研究院)
第6回 経済学者によるアマゾンの環境と開発研究のセミナー
日時:2016年5月27日(金)15:00-17:00
場所:国立環境研究所 第2会議室
演者:高崎善人(東京大学大学院経済学研究科 教授)
プログラム:
15:00-16:00 Peruvian Amazon Rural Livelihoods and Poverty (PARLAP)
16:00-17:00 研究論文発表・質疑応答
Title: Environmental and market determinants of economic orientation among rain forest communities:
evidence from a large-scale survey in western Amazonia
Authors: Oliver T. Coomes, Yoshito Takasaki, Christian Abizaid and J.Pablo Arroyo‐Mora
第5回 歴史人口学セミナー
日時:2015年12月7日(月)15:00-16:30
場所:国立環境研究所 第2会議室
プログラム:
日本列島における地域人口の長期的変化-資源・環境・文明システムとの関連から考える-(歴史人口学/静岡県立大学 学長 鬼頭 宏)
ワークショップ
日時:2015年3月13日(金)14:00-17:50、14日(土)9:30-12:20
場所:国立環境研究所 第2会議室・第1会議室
プログラム:
【1日目】
Critical capital stock and optimal steady states in a continuous time aggregate growth model with convex-concave production function(早稲田大学 赤尾健一)
Consumption salience, learning and information acquisition: Evidence from a field experiment(武蔵大学 松川勇)
Job Change and Self-Control of Waste Pickers: Evidence from a Field Experiment in the Philippines(国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター・環境経済連携グループ 横尾英史)
フィリピンの漁業者に対するフィールド実験(武蔵大学 田中健太)
【2日目】
送電事業者の戦略的行動を考慮した再生可能エネルギー普及促進制度の効果(早稲田大学 庫川幸秀)
Environmental Policy Decisions Incentives and the Possibility of Environmental Improvements in China(早稲田大学 澤田英二)
気候変動が中国の死亡率に与える影響についての実証研究(上智大学/国立環境研究所 環境経済連携グループ長 日引聡)
第4回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2015年3月6日(金)9:30-11:00
場所:国立環境研究所 第2会議室
プログラム:
国立公園ブランドを考える -保全とレクリエーションのトレードオフ-(京都大学大学院博士課程 久保雄広)
第3回 環境経済評価連携研究グループ・セミナー
日時:2015年1月23日(金) 15:30-18:00
場所:国立環境研究所 第2会議室
プログラム:
赤土流出対策の費用効率的な対策の経済学的検討(長崎大学環境科学部 堀江哲也)
ボルネオ先住民の森の生物多様性と生態系サービス -地域社会のニーズを考慮した生物多様性保全に向けて-(国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 竹内やよい)
第2回 環境経済評価連携研グループ・セミナー
日時:2014年12月5日(金) 15:30-17:30
場所:国立環境研究所 第2会議室
プログラム:
廃村の生態学~土地利用と放棄の歴史から考える将来の生物多様性保全策~(生物・生態系環境研究センター 深澤圭太)
社会と生態系のつながりを評価する: 地理的・定量的生態系サービス評価の試み(社会環境システム研究センター 大場真)
ダンプサイト・ウェイストピッカーの転職促進方法の検討-フィリピン・イロイロ市のごみ処分場におけるフィールド実験-(資源循環・廃棄物研究センター 横尾英史)
第1回 キックオフセミナー
日時:2014年11月7日(金) 15:30-17:30
場所:国立環境研究所 第2会議室
プログラム:
演題1:これまでの研究成果の紹介及び環境経済学の全体像と今後のグループの運営について(連携研究グループ長:日引 聡)
演題2:生態系研究における環境経済評価研究の意義(生物・生態系環境研究センター室長 山野博哉)
演題3:環境経済評価連携グループで取り組むべき研究テーマ(社会環境システム研究センター室長 亀山康子)
全体討論