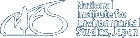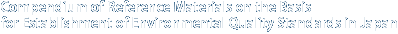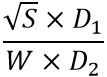Chapter 2. Water Quality
(1) Overview
(a) Outline of Environmental Quality Standards, etc., for Water Pollution
With regard to environmental quality standards for water pollution, the standards are broadly divided into areas of public waters (surface water) and groundwater.
Since the initial period, the target of standards has been the water quality of areas of public waters. Standards for water quality are divided into “Environmental Quality Standards for the Protection of Human Health” and “Environmental Quality Standards for the Conservation of the Living Environment.”
“Environmental Quality Standards for the Protection of Human Health” have been established to cover hazardous heavy metals and chemicals. Standards considering health effects are often established taking into account the effects of drinking water (mainly tap water), but for substances that concentrate in living organisms (i.e., bioaccumulative substances), effects manifested through food such as fish are also taken into account. For the former, in accordance with the concept of establishing drinking water quality standards, the tolerable daily intake (TDI, per body weight) is first determined by applying uncertainty factors to values such as no observed adverse effect level (NOAEL) obtained from the results of animal studies. Then, a certain percentage (often 10% in Japan) is allocated to the TDI for drinking water, and by assuming a standard body weight and amount of drinking water per day (for a Japanese person, 50 kg and two liters), an assessment value of water quality is determined. When considering toxicity, such as carcinogenicity, in cases where a threshold cannot be established, the assessment value is determined as a level where the cancer risk from drinking water is sufficiently small to be deemed acceptable (Virtually Safe Dose, VSD). In cases where the exposure level indicated by monitoring results in areas of public waters exceeds these levels, the assessment value is defined as an environmental quality standard. In the latter case, a standard value is determined taking into account the allowable concentrations in fish and shellfish as food products in consideration of accumulation in fish and shellfish. In both cases, in principle, one uniform standard value is established for the entire area of public waters.
Substances that are related to the protection of human health but for which the detection level in areas of public waters, etc., is sufficiently low compared to the water quality assessment value are not immediately regarded as environmental quality standard items, but are identified as “items to be monitored,” which require ongoing accumulation of knowledge. For them, there is ongoing monitoring of water quality in areas of public waters, etc., in order to monitor trends.
With regard to the “Environmental Quality Standards for the Conservation of the Living Environment,” as the term “living environment” is defined as “including property closely related to human life, as well as flora and fauna closely related to human life, and their growing environments,” standard values are established considering the purpose of water utilization, such as drinking water, fisheries, or industrial water, for items considering the state of “dirty water” and impacts on oxygen consumption of fish and aquatic environments, such as organic pollutants, shown by indicators such as biochemical oxygen demand (BOD) or chemical oxygen demand (COD), or suspended solid (SS), etc. In addition, in order to prevent the deterioration of the aquatic environment due to eutrophication in lakes and closed sea areas, environmental quality standards have been established for nitrogen and phosphorus, which are nutrients, and the amount of dissolved oxygen in the bottom layer (bottom layer DO), for specific water areas.
With regard to the living environment items, based on the results of surveys on the relationship between water quality, and water utilization and the actual condition of the habitat of fish and shellfish for the fishing industry, different standard values are established for rivers, lakes, and sea areas, according to the purpose of water utilization in the water area. Then, the national or prefectural government makes the categorization into classes determining which water area should be assigned to which rank. The national government makes the categorization into classes for important water areas that span multiple prefectures, while the categorization of other water areas is delegated to prefectures.
Since 2003, environmental quality standards for water pollution for the conservation of aquatic life, targeted at harmful substances, have also been established as an item in the living environment item category. Considering that, as stated above, “conservation of the living environment” includes “flora and fauna closely related to human life, and their growing environments,” the focus is on the protection of useful aquatic organisms, their prey, and their growing environments. In practice, from the perspective of preventing impacts on the survival of aquatic organisms at the population level, target values should be set at levels that enable the population to be maintained. Target values are derived from the results of ecotoxicity tests for fish and shellfish and their prey living in each water area; and as with human health items, a comparison of environmental concentrations based on monitoring results is done. Determination is made as to whether each item should become an item for environmental quality standards or an item to be monitored. Stricter values may be applied particularly to spawning areas and water areas used during sensitive larval periods.
With regard to groundwater, pollution control measures were introduced in 1989 by revisions to the Water Pollution Prevention Act, and numerical targets for the measures were established in the initial period as evaluation standards by a notice issued by the director general of the Water Quality Bureau (Environment Agency), and then established as environmental quality standards in 1997. Environmental quality standards for groundwater are set from the standpoint of protecting human health by taking into account the effects that occur via drinking water, and items to be monitored are also established. The standard values and guideline values for groundwater are, in principle, the same as those for areas of public waters. However, some items are different from items for areas of public waters because there are substances generated in the underground environment and substances that are more easily detected than in surface water. Living environment items have not been established.
The monitoring method for each item and the evaluation method for the status of achievement of environmental quality standards are established according to the characteristics of the category and item.
(2) History of Establishment of the Standards
Initial Stages of Establishment
With regard to environmental quality standards for water pollution, the standards were drafted in the initial period by the Economic Planning Agency, which had jurisdiction over the Water Quality Control Act and played a coordinating role in water administration. On March 31, 1970, the Director-General of the Economic Planning Agency consulted the Chair of the Water Quality Council on “Basic Policy for Establishing Environmental Standards for Water Pollution,” including basic principles and methods for establishing environmental quality standards, and environmental criteria (including items and standard values) that should constitute the content of environmental quality standards. Such a consultation document was submitted to the Water Quality Council along with materials on the basis for establishing concrete figures. As of the same date, the Council issued an advisory report stating that it had no objections to the consultation document on the condition of text revisions being made in two places.
Among these, with regard to environmental quality standards related to the protection of human health (human health items) the recommendation indicated unified standard values for areas of public waters for seven items, namely cyanide, methylmercury, organophosphorus, cadmium, lead, chromium (hexavalent) and arsenic. Concerning the items related to conservation of the living environment (living environment items), the recommendation indicated standard values by type of water area for rivers, lakes, and sea areas, and by purpose of use of water area, in terms of pH, BOD (rivers) or COD (lakes and sea areas), SS (rivers and lakes), and DO.
Based on this advisory report, a cabinet decision was made on the environmental quality standards for these items on April 21, 1970. Subsequently, on May 29, 1971, a cabinet decision was made that methylmercury should be divided into total mercury and alkyl mercury, and that total coliform count should be added as a living environment item. Furthermore, on May 25, 1971, Cabinet decided that n-hexane extract (oil content) should be added as a living environment item (for sea areas).
On December 28, 1971, the Environment Agency, after taking over the tasks from the Economic Planning Agency, a notification was issued on “Environmental Quality Standards for Water Pollution,” establishing eight environmental quality standards for health items and five environmental quality standards for living environment items for rivers, lakes, and sea areas.
Subsequently, based on progress in techniques to measure mercury (total mercury and alkyl mercury), a public notification of revision of the standard values was issued on September 30, 1974 in response to an advisory report by the Central Council for Environmental Pollution Control in April that year. PCBs were added on February 3, 1975, in response to an advisory report by the Central Council for Environmental Pollution Control in November 1974, bringing the total number of human health items to nine.
Subsequent Establishments and Revisions
i) Human Health Items
With regard to human health items among the environmental quality standards for water pollution, in response to moves by the Ministry of Health and Welfare to revise drinking water quality standards, the Central Council for Environmental Pollution Control was consulted in September 1992 “Regarding the addition of items to environmental quality standards for water pollution related to the protection of human health.” In response to the resulting advisory report in January 1993, 15 new items were established and 2 items were revised, and a public notification was issued by the Environment Agency on March 8 that year.
Along with this, among substances for which the status of detection in areas of public waters, etc., does not immediately make them subject to environmental quality standards even though they may be related to the protection of human health, 25 substances deemed to require ongoing accumulation of knowledge were designated as “items to be monitored.” For these substances, water quality in areas of public waters, etc., is to be continuously measured in order to monitor trends. With regard to items to be monitored, guideline values for assessing water quality measurement results were established in accordance with the concept of environmental quality standard items, and prefectural governors were notified.
With regard to environmental quality standard items for the protection of human health, items to be monitored, and associated standard values and guideline values, revisions and additions have subsequently been made, when necessary, based on the accumulation of scientific knowledge.
With regard to for dioxins, environmental quality standards were established for water pollution in 1999, and for sediment in 2002, respectively, based on the Act on Special Measures against Dioxins.
ii) Living Environment Items (excluding section iii)
With regard to the living environment items, environmental quality standards for nitrogen and phosphorus in lakes were established in 1982, and in sea areas in 1993, respectively, from the perspective of measures to address eutrophication.
In addition, environmental quality standards related to bottom layer DO were established in 2016 for lakes and sea areas as an index that is easy for the public to understand intuitively and helps people understand direct impacts on habitats and the reproduction of aquatic organisms such as fish and shellfish, and on the growth of aquatic plants such as seaweed grass. From a similar point of view, target values for coastal water clarity were set as “local environmental targets,” which are expected to be established by local communities.
In 2021, total coliform count was revised to E.coli count, a new hygienic microbial indicator.
iii) Conservation of Aquatic Life
With regard to environmental quality standards for hazardous substances from the perspective of the conservation of aquatic life, consideration began in around 2000, in parallel with the introduction of assessment and management in consideration of the effects on flora and fauna under the Act on the Regulation of Manufacture and Evaluation of Chemical Substances and the Agricultural Chemicals Regulation Act. Based on the description in the second Basic Environment Plan (adopted in December 2000) regarding the necessity to consider environmental quality standards that take into account impacts on aquatic organisms, and based on recommendations regarding the necessity of water quality targets for ecosystem conservation in an environmental performance review of Japan (January 2002) by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Central Council for the Environment was consulted in November 2002 on the “Establishment of environmental quality standards for the conservation of aquatic life.” Consequently, in response to a September 2003 advisory report, the decision was made to establish those environmental quality standards as a part of the living environment items. Such standards were established first for zinc in November that year, bringing the total to three items. Guideline values have also been established for six items to be monitored.
iv) Groundwater
With regard to groundwater, assessment values were established in the initial period by a notice issued by the director general of the Water Quality Bureau (Environment Agency). In 1996, the Central Council for the Environment was consulted on the “Establishment of environmental quality standards for groundwater pollution.” In response to the resulting March 1997 advisory report, environmental quality standards for 23 items were established on March 13 that year. Items to be monitored in groundwater were established in March 1993, in combination with areas of public waters.
With regard to environmental quality standard items and items to be monitored, as well as associated standard values and guideline values, revisions or additions have subsequently been made, when necessary, based on the accumulation of scientific knowledge. Some items differ from those for areas of public waters.
With regard to dioxins, groundwater was also included when environmental quality standards for water pollution were established in 1999 based on the Act on Special Measures against Dioxins.
(c) Reference
・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その1)、水道公論、2012年1月号、pp.26-38 【NIES保管ファイル】
・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その2)、水道公論、2012年2月号、pp.36-42 【NIES保管ファイル】
・坂本弘道(2012)「水質汚濁に係る環境基準」原案(昭和45年)の設定作業に携わって(その3)、水道公論、2012年3月号、pp.46-56 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
(d) Explanatory Literature
・坂本弘道(2015)「水質汚濁に係る環境基準」草案(昭和45年)の設定作業に携わって、水環境学会誌、38(5)、pp.156-161
・(社)日本水環境学会(1999)日本の水環境行政、ぎょうせい、pp.4-77
・(社)日本水環境学会(2009)日本の水環境行政・改訂版、ぎょうせい、pp.1-108
(2)人の健康の保護に関する環境基準及び要監視項目(公共用水域)
①設定の考え方
(昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」より)(抜粋)
第1 環境基準設定の基本原則
水質汚濁に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)は、基本的には、次の原則に則して設定するものとする。
ア 環境基準は、公害対策基本法第9条の規定に基づき、国民の健康を保護しおよび生活環境(公害対策基本法第2条第2項でいう生活環境とする。以下同じ。)を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであること。
イ 環境基準は、公共用水域の水質汚濁防止のために各般にわたり講じられる行政の目標として設定されるものであること。
ウ 環境基準は、国民の健康の保護に係る場合は、常に維持されるべきものであり、また、生活環境の保全に係る場合は、公共用水域が通常の条件の下にある場合において維持されるべきものであること。
エ 環境基準は、諸般の状況にかんがみ、直ちに達成することが困難と考えられる場合においては、達成すべき期限を明らかにし、その期限内における達成が期せられるべきものであること。
第2 環境基準設定の方式(抄)
1 国民の健康の保護に係る環境基準
これについては、国民の健康の保護は、絶対的に確保されるべきものとされていることにかんがみ、全公共用水域につき一律に設定することとする。
(中略)
第4 環境基準の一環として定めるべき事項(抄)
(中略)
1 公共用水域の水質の測定方法
環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。
(中略)
イ 国民の健康の保護に係る項目については、公共用水域の水量の如何を問わず随時測定するものとすること。
(中略)
2 環境基準の達成期間及び達成の方途
(1)国民の健康の保護に係る環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。
(中略)
第5 環境基準の見直し(抄)
環境基準は、次により適宜改定することとする。
ア 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等
(中略)
ウ 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等
(参考資料)
・昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」 【NIES保管ファイル】
(平成5年1月18日・中央公害対策審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について(答申)」より)(抜粋)
2.基本的考え方
(1)項目の選定
現在得られている健康影響等に関する知見、公共用水域等における検出状況等から判断して、水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると考えられる物質については、公害対策基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準の項目(以下「環境基準項目」という。)に追加することが適当である。
現在、生産・使用されている化学物質の中から環境基準とすべき項目を選定するに当たり、今回は、科学的知見の現状や内外の検討の動向を踏まえ、水道水質に関する基準について検討がなされた項目を中心に、類似又は関連する化合物で対応を要すると考えられる項目を含め、我が国における当該物質の生産・使用状況や公共用水域等における検出状況等を勘案しつつ、環境基準項目の追加及び既定項目の見直しを検討した。
なお、発がん性のおそれがある物質については、従来環境基準を設定していなかったが、このような物質についても我が国の水道水質に関する基準が設定されたこと等の動きを踏まえ、今回は環境基準項目への追加を検討した。
(2)基準値の設定
環境基準項目の基準値は、我が国、米国及び国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況等をもとに検討した。まず飲料水経由の影響(主として長期間の飲用を想定した影響)については、WHO等が飲料水の水質基準設定に当たって広く採用している方法をもとに、他の暴露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたる連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分考慮するとの観点から、新たな水道水質に関する基準の検討に際し採用された考え方及びその数値を基本とし、さらにその上で、水質汚濁に由来する食品経由の影響(長期間の摂取を想定した影響)についても、現時点で得られている魚介類への濃縮性に関する知見を考慮して、基準値を検討した。
(3)適用方針
人の健康の保護に関する環境基準については、健康への影響という観点から広くみた場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響、水域からの大気への循環等も考慮する必要があること、さらに、人の健康の保護に関する環境基準の設定が、実質的に水生生物等への影響を含め広く有害物質による環境汚染の防止に資することも念頭におくことが望ましいと考えられることから、これまでどおり河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当と考えられる。
(中略)
3.新たな環境基準項目及び基準値(抄)
(中略)
(3)環境基準達成状況の評価
基準値は、主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、公共用水域等の水質については長期間にわたる平均的なレベルを基準値以下に維持する必要がある。このため、公共用水域における環境基準の達成状況は、基本的には年間平均値により評価することが適当である。ただし、全シアンについては急性毒性が懸念されることから、最高値により評価することが適当である。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値と定めているので、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断することが適当である。
なお、基準値は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできる限り清浄な状態を維持するよう留意するものとする。
(4)自然的原因による検出値の評価
水銀、鉛、ヒ素等については、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等において検出される可能性がある。
この場合、これらの項目についても、基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないことから、従来より河川において自然的原因によることが明らかな場合に別途評価値を定めていた総水銀を含め、一律の値(総水銀であれば0.0005mg/L以下)を設定することが適当である。
なお、公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。
4.環境基準項目についての今後の措置(抄)
(1)公共用水域等の監視の実施
環境基準項目については、水質汚濁防止法第15条に基づく都道府県知事による公共用水域及び地下水の常時監視の対象として位置づけ、これまでどおり水質の汚濁の状況の把握に努める必要がある。今回の改定によりこれまでよりかなり項目数が増えることから、監視体制の一層の充実が不可欠である。
環境基準の達成状況等を適切に評価するため、測定計画の策定に当たっては、物質の特性、使用状況等を考慮し、年間を通した公共用水域等の状況が的確に把握できるよう配慮すべきである。公共用水域の場合、水域を代表する各地点で各月1回以上の測定が望ましいと考えられるが、水質汚濁の状況、排出水の汚染状態等からみて汚染のおそれの少ない地点については測定回数を減じ、汚染のおそれがある地点の監視を強化すること等により効果的に監視を実施することが適当である。
(中略)
5.要監視項目の設定(抄)
今回、環境基準項目に追加することが適当と判断された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについては、「要監視項目」として位置づけ、継続して公共用水域等の水質測定を行い、その推移を把握していくことが適当である。
(中略)
要監視項目については、水質測定結果を評価する上での指針値を設定することが適当と考えられ、環境基準項目に準じた考え方で検討すると別表3(略)のとおり設定することが適当である。なお、指針値は、長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であり、一時的にある程度この値を超えるようなことがあっても、直ちに健康上の問題に結びつくものではないことに留意して水質測定結果を評価すべきである。
また、要監視項目の多くは魚介類への濃縮性が低いと考えられるが、濃縮性について更に詳細に検討する必要があると考えられる項目もみられるので、引き続き知見の集積に努める必要がある。
要監視項目については、国及び地方公共団体において、物質の特性、使用状況等を考慮し体系的かつ効果的に公共用水域等の水質測定を行い、その結果を踏まえて必要に応じ水質汚濁の未然防止のための措置を講じるとともに、測定結果を国において定期的に集約し、その後の知見の集積状況も勘案しつつ、環境基準項目への移行等を機動的に検討する必要がある。
(参考資料)
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について(答申)」 【NIES保管ファイル】
(解説文献)
・早水輝好(1993)水質環境基準の改定について、水環境学会誌、16(4)、pp.224-230
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
| 項目 | 基準値 | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 平成23年10月27日 | 改定 |
| 全シアン | 検出されないこと (定量限界0.1mg/L) | 昭和46年12月28日 | 当初「シアン」から平成5年3月8日に名称変更 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | 改定 |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 | 令和3年10月7日※ | 改定(令和4年4月1日施行) |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | 改定 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 昭和49年9月30日 | 改定 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと (定量限界0.0005mg/L) | 昭和49年9月30日 | 改定 |
| PCB | 検出されないこと (定量限界0.0005mg/L) | 昭和50年2月3日 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 改定 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成26年11月17日 | 改定 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| チウラム | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |
| ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |
| ほう素 | 1mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更・改定 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 当初要監視項目から変更 |
| ダイオキシン類(水質)※ | 1 pg-TEQ/L以下 | 平成11年12月27日 | |
| ダイオキシン類(水底の底質)※ | 150 pg-TEQ/g以下 | 平成14年7月22日 |
※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定
(備考)
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2(略)において同じ。
3 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
(評価方法)
(常時監視等の処理基準抜粋)
第2 水質汚濁防止法関係
1.常時監視(法第15条関係)(抄)
(中略)
(3)測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合
1)人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準
①水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の達成状況は、同一測定点(公共用水域にあっては、当該測定点は表層における地点とする。)における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、測定値が定量下限値未満であった検体については、定量下限値を用いて平均値を算出することとする。
②ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断する。
③さらに総水銀については、告示別表1備考1及び地下水告示別表備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に定量下限値未満が含まれていない場合には、総検体の測定値がすべて0.0005mg/Lであることをいい、定量下限値未満が含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であることをいうものとする。
(中略)
⑤自然的原因による検出値の評価
ア.公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。
イ.ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(平成11年3月12日環水企第89-2号、環水管第68-2号)によること。
(中略)
2.測定計画(法第16条関係)(抄)
(中略)
イ.測定頻度
(ア)環境基準項目
ア)人の健康の保護に関する環境基準項目については、毎月1日以上各日について4回程度採水分析することを原則とする。このうち1日以上は全項目について実施し、その他の日にあっては、水質の汚濁の状況、排出水の汚染状態の状況等から見て必要と思われる項目について適宜実施することとする。
(以下略)
(参考資料)
・令和3年10月7日・環境省水・大気環境局長「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(環水大水発第2110073号・環水大土発第2110073号) https://www.env.go.jp/hourei/add/e82.pdf 【NIES保管ファイル】
(公共用水域の水質のダイオキシン類の常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
1.常時監視の調査測定方法(抄)
公共用水域の水質の常時監視については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号環境庁水質保全局長通知)に準じて行うこととする。この場合、水域を代表する地点での調査測定が望ましいが、発生源及び排出水の汚濁状態、水域の利水状況等を考慮して、個別水域ごとに効果的な監視体制の整備を図ることとする。
(中略)
公共用水域の水質及び地下水質に係るダイオキシン類の測定は、日本工業規格K0312に定める方法によることとし、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(平成13年5月31日環水企第92号環境省環境管理局水環境部長通知)を参考にして、水環境中のダイオキシン類監視の適切な実施を図ることとする。
公共用水域の水底(海域にあっては平均潮位時に、その他の水域にあっては平水位時において、水底であるものに限る。)の底質の常時監視については、「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」によって行うほか、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について」(平成14年7月22日付け環水企第117号、環水管第170号環境省環境管理局水環境部長通知。以下「施行通知」という。)の記の第3の2「測定方法について」のイ及びウを参考にされたい。また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法については、施行通知の記の第3の4「測定地点の選定について」を参考にされたい。
2 調査測定結果の評価方法
水質環境基準の達成状況は、測定地点ごとに年間平均値により評価することとする。
底質環境基準の達成状況は、施行通知の記の第3の4「評価について」に示したように、測定結果ごとに、また、測定地点ごとに評価することとする。
(参考資料)
・平成13年5月31日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」(環水企93号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000166.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年7月22日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準の改正について」(環水企118号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000167.html 【NIES保管ファイル】
・平成17年6月29日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について」(環水企発第050629003号・環水土発第050629003号) http://www.env.go.jp/air/tech/suisitukizyunkaisei0506h17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成20年4月1日・環境省水・大気環境局長「「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について(通知)」(環水大発第080401002号・環水土発第080401001号) http://www.env.go.jp/air/dioxin/suisitu0804h20.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○カドミウム
1.基準値
(当初)0.01mg/L以下
(現行)0.003mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定)
平成23年7月22日・中央環境審議会答申
平成23年10月27日・環境省告示第94号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:(カドミウム)青白色の柔らかい金属塊状物あるいは灰色の粉末で展性があり80℃にすると脆くなり湿った空気に暴露すると光沢を失う、(塩化カドミウム)無色無臭の吸湿性結晶、(酸化カドミウム)無臭で茶色の結晶または非結晶性粉末、(硫酸カドミウム)白色の結晶
・比重:(カドミウム)8.6、(塩化カドミウム)4.1、(酸化カドミウム)6.95(非結晶)、(硫酸カドミウム)4.7
・水への溶解性:(カドミウム)溶けない、(塩化カドミウム)よく溶ける、(酸化カドミウム)溶けない、(硫酸カドミウム)755g/L(0℃)
・環境中での挙動:リン鉱石から生産される化学肥料中の不純物として土壌に拡散される。水への溶解度はpHの影響を受けやすく、懸濁状態又は沈殿状態であっても酸性になると溶解しやすくなる。環境水では主に底質や懸濁物質として存在する。
(2)生産量等
(平成19年)
(カドミウム)生産量1,933t、輸出量847t、輸入量1,455t
(塩化カドミウム)不明
(酸化カドミウム)不明
(硝酸カドミウム)製造・輸入量3,239t
(3)主な用途
(カドミウム)カドミ系顔料、ニッケル・カドミウム電池、合金、メッキ、蛍光体
(塩化カドミウム)写真、メッキ、顔料の製造原料、触媒
(酸化カドミウム)電気メッキ
(硝酸カドミウム)陶磁器着色剤、電池、カドミウム塩の原料
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・水生生物保全環境基準 目標値設定項目(目標値0.03~10μg/L)
・水道水質基準 0.003mg/L
・食品規格(米に対する基準) 0.4ppm
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版、2004年) 0.003mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準(2009年版) 0.005mg/L
・EU飲料水水質基準(1998年) 0.005mg/L
※JECFAでは平成22年6月に、カドミウムの半減期が例外的に長いことから、PTWIによる設定よりも暫定耐容月摂取量(PTMI)による設定が妥当であるとの判断に基づき、PTWIを撤回し、新たにPTMIの値を25μg/kg体重/月(1日あたり0.8μg/kg体重)としている。
6.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
<業種別届出排出量(公共用水域)>
(平成18年度)
非鉄金属製造業(625kg)、金属鉱業(36kg)、電気機械器具製造業(4kg)、化学工業(1kg)、窯業・土石製品製造業(0.6kg)、金属製品製造業(0.6kg)
(平成19年度)
非鉄金属製造業(524kg)、金属鉱業(29kg)、電気機械器具製造業(2kg)、金属製品製造業(0.9kg)、化学工業(0.6kg)、窯業・土石製品製造業(0.1kg)
(平成20年度)
非鉄金属製造業(478kg)、金属鉱業(20kg)、電気機械器具製造業(2kg)、金属製品製造業(1kg)、化学工業(0.6kg)、窯業・土石製品製造業(0.2kg)
(注)一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、下水道業を除く。
7.環境中における検出状況(改定時)
<公共用水域>(基準値0.003mg/L)
(平成16年度)測定4,587地点、検出55地点、超過7地点、10%超過55地点
(平成17年度)測定4,485地点、検出41地点、超過9地点、10%超過41地点
(平成18年度)測定4,450地点、検出52地点、超過5地点、10%超過52地点
(平成19年度)測定4,400地点、検出39地点、超過4地点、10%超過39地点
(平成20年度)測定4,310地点、検出33地点、超過6地点、10%超過33地点
<地下水>(基準値0.003mg/L)
(平成16年度)測定3,247地点、検出14地点、超過2地点、10%超過14地点
(平成17年度)測定3,092地点、検出10地点、超過2地点、10%超過10地点
(平成18年度)測定3,166地点、検出13地点、超過3地点、10%超過13地点
(平成19年度)測定3,160地点、検出6地点、超過3地点、10%超過6地点
(平成20年度)測定2,871地点、検出4地点、超過1地点、10%超過4地点
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
厚生省の「飲料水中のカドミウムの暫定基準設定のための調査研究」の報告によると、飲料水中のカドミウムは0.01ppm以下であるべきであると結論している。その根拠としては、まず第1に、地表水及び地下水において亜鉛の1/100~1/150程度量のカドミウムが含まれており、飲料水の基準は亜鉛が1ppm以下となっているので、この場合0.01ppm以下のカドミウムが含まれていると推定される。第2に、自然界のカドミウムは通常、飲料水および各種の飲食物に含まれた形で、人間及び動物に摂取され、その大部分は体外に排泄される。しかしながら、その1部分は、消化管より吸収されて、血中に移行し、そして通常その殆どは尿とともに、体外に排泄されるが、吸収された量が、尿中に排泄される量を超えた場合に、カドミウムは体内に蓄積され、いろいろの悪影響を起こすものと考えられる。第3に、飲料水中のカドミウムの許容量について諸外国の例をみると、WHO国際基準、アメリカ基準、ソビエト基準では0.01ppmとされており、またWHOヨーロッパ基準では0.05ppmとされている。以上の結果とりあえず、わが国における飲料水中のカドミウム含有量の暫定基準は、0.01ppm以下としている。
なお、上水道の浄水過程においてもカドミウムを除去することは困難である。
また、魚類、稲等動植物におけるカドミウムの蓄積のメカニズムについては、現在のところまだ明らかではないが、とりあえず、飲料水の基準程度であれば問題はないと考える。
以上の点からして、カドミウムは0.01ppm以下であることが適当と考えられる。
(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)
WHOにおいては新たな知見を含めて検討がなされたが、水道水質に関する基準の改定案は微量重金属調査研究会(1970)をもとに現行どおり0.01mg/L以下としており、現行の環境基準値も水道水質基準を踏まえて設定されていることから、今回は改定しない。
(平成23年・改定時)(答申抜粋)
1.はじめに(抄)
(中略)
カドミウムについては、FAO/WHO合同食品規格委員会において、平成18年7月に精米を始めとする食品群に対する基準が設定され、国内では食品安全委員会において、平成20年7月にカドミウムの耐容週間摂取量(TWI)が設定された。このような状況を踏まえ、食品衛生法に基づくカドミウムの規格基準が見直され平成22年4月に公布された※他、環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準のうち、農用地の土壌に係るカドミウム基準が見直され平成22年6月に公布された。また、水道法に基づく水質基準についてもカドミウムの基準値が見直され平成22年4月に公布されたところである。
今回は、新たな毒性情報が明らかとなったカドミウムに関する基準値の見直しについて検討し、報告をとりまとめた。
※原文に変更を加えている
(中略)
3.検討結果
(1)水道水質基準及び土壌環境基準(農用地)の改訂等を踏まえた検討
平成20年7月に食品安全委員会より示された耐容週間摂取量(7μg/kg体重/週)は、国内外における多くの疫学調査や動物実験による知見のうち、特に、一般環境における長期低濃度ばく露を重視し、日本国内におけるカドミウム摂取量が腎近位尿細管機能に及ぼす影響を調べた2つの疫学調査結果を主たる根拠として設定された。
平成22年4月の水道水の水質基準改定においては、平成20年に見直された食品安全委員会による食品健康影響評価結果を用いて、水質基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化している。また、同評価結果を用いた食品規格基準の改正により、0.4mg/kgを超えるカドミウムを含む米が、公衆衛生の見地から販売等が禁止される食品に位置付けられることを踏まえ、土壌の汚染に係る環境基準についても、米1kgにつき0.4mg以下であることという内容で平成22年6月に公布された。
カドミウムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.01mg/Lを0.003mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て、従来通り水質環境基準健康項目とすることが適当である。
(中略)
イ 基準値
カドミウム汚染地域住民と非汚染地域住民を対象とした疫学調査結果から、14.4μg/kg体重/週以下のカドミウム摂取量は人の健康に悪影響を及ぼさない摂取量であり、別の疫学調査結果から、7μg/kg体重/週程度のカドミウムばく露を受けた住民に非汚染地域の住民と比較して過剰な近位尿細管機能障害が認められなかったことを受け、カドミウムの耐容週間摂取量は総合的に判断して7μg/kg体重/週とすることが妥当とした食品安全委員会の評価結果注)を用いると、耐容一日摂取量は1μg/kg体重/日となる。カドミウムのばく露経路のうち、水より摂取する割合を10%、体重50kg、飲用水量2L/日として、基準値を0.003mg/Lとした。
注)食品安全委員会 評価書
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20090109006
9.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.259-265 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成23年7月22日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2301.pdf 【NIES保管ファイル】
○全シアン
1.基準値
検出されないこと(定量限界0.1 mg/L)
2.測定方法
日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号(名称:シアン)
(名称変更)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号(名称:全シアン)
4.基礎情報(名称変更時、調査報告書より)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等(シアン化物)
・通常金属シアン化物、すなわちシアン化水素HCNの塩のことを言う。
・シアン化水素は非常に弱い酸で、揮発性を持つ。
・アルカリ金属、アルカリ土類、タリウム(Ⅰ)などの塩はイオン性結晶であり、水に可溶で、水溶液は加水分解のため強いアルカリ性を示す。
・銅、亜鉛、カドミウム、鉛(Ⅱ)などは共有結合性の強い難溶性の結晶である。鉄(Ⅱ)、鉄(Ⅲ)などはシアン錯塩のみが知られている。
・有機シアン化物は一般にニトリルと呼ばれ、CN-、HCNを遊離することはごく稀である。
・環境中のシアン化物の起源はほとんどが人為のものであるといってよい。
・シアン化水素、シアン化アルカリなどは、水中でHCNとCN-となって共存しているが、中性付近では大部分がHCNの形をとっており、pHの上昇とともにCN-の形に移行する。HCNの形のものは空気中に揮散しやすいがCN-の形のものは揮散しにくい。水中のHCN、CN-はかなり不安定であり、水と反応してギ酸やアンモニアを生ずる。
・シアン化物のうち、重金属のシアノ錯体は一般的には難溶性であるために、水質汚染を起こす対象にはなりにくい。
(2)生産量等
・シアン化ナトリウム:29,152t(平成元年)
(3)主な用途
・シアン化水素:アクリロニトリル、アクリル酸樹脂、乳酸その他の有機合成原料、農薬・殺鼠剤の原料
・シアン化ナトリウム:金の青化製錬、顔料の原料、非鉄金属からの銅・銀の抽出、メッキ、医薬品など
5.毒性情報及び各種基準値(名称変更時、調査報告書より)
(1)環境水水質基準
・水産用水基準(1965) <0.01ppm
・EPA(1982) 3.77mg/L
(2)飲料水水質基準
・WHO(1971) <0.05ppm
・USPHS(1962) <0.01ppm(給水停止処置基準)、<0.2ppm(飲料不適基準)
・水道水質基準 検出されないこと(<0.01ppm)
6.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
シアンの経口致死量については、人間の事故による事例、動物実験の結果に基づく考察等により、ほぼKCNでは、150mg/人~300mg/人と考えられており、これをCN-に換算した場合、60mg/人~120mg/人がLD50の致死量と考えられる。またこれについては、さらに37.8mg/人という低い値を致死量とする説もある。
シアン等の劇物については、通常100倍程度の安全率を見込み、その許容限度を1mg/人と定めることが出来る。通常、人間が一回に飲料する水の量は500ml程度であるから、飲料時における許容濃度は一応2mg/L、すなわち2ppmと考えられよう。水道水についてはこれに、さらにどの程度の安全率を見込むかについては諸説がある。諸外国の例をとればヨーロッパのWHO基準では0.2ppm、ソ連では0.1ppm、アメリカでは0.01ppmと、まちまちである。わが国の飲料水の水質基準は、この中でも比較的厳しいアメリカのUSPHSの飲料水水質基準を参考として0.01ppmと定めている。すなわち、この値は、現在のJIS規格に基づく測定では検出限界値以下である。
なお、シアンについては、上記の水道等飲料水に対する配慮のみならず、環境衛生等国民健康の面からしても公共用水域の水質については、検出されないこと、と定めることが適当である。
(平成5年・名称変更時)(専門委員会配付資料抜粋)
WHOにおいては新たな知見を含めて検討がなされたが、水道水質基準について基準の継続性を考慮して、現行値どおり0.01mg/L以下としている。ただし検査方法を変更して、従来はシアンイオンのみを測定していたものを、塩素消毒の際に生成される塩化シアンを含めて検査することとしている。
公共用水域等においては、工場・事業場から金属とシアンの錯体が主に排出されることを踏まえ、これらを含めたシアン化合物を測定することとしており、検出限界を0.1mg/Lに定めて「検出されないこと」をもって環境基準としている。この方法では塩化シアンの測定はできないが、塩化シアンは一般的に不安定で環境中では存在しにくいものと考えられる。一方、人の健康への影響をもたらすのは主として無機シアンであるが、工場排水起源のシアンを把握して水質を管理するためには現行どおりシアン錯体を含めたシアン化合物を測定する方法を用いた方が望ましいと考えられる。WHO飲料水水質ガイドラインでは、無機シアンとして従来の0.1mg/Lから0.07mg/L(人の体重50kgに換算すると0.06mg/L)に改定される見込みであるが、わが国において無機シアンを含んだシアン化合物として、従来どおり「検出されないこと」(検出限界0.1mg/L)という環境基準を維持することは概ね妥当と考えられる。
なお、項目の名称を、水道水質に関する基準と区別するため、分析法として採用しているJISの呼称を用いて「全シアン」と変更する。また、シアンについては急性毒性も懸念されることから、基準値は現行どおり最高値で設定する。
7.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.168-175 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○鉛
1.基準値
(当初)0.1mg/L以下
(現行)0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の54に定める方法
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・蒼白色の柔らかい金属、酸化皮膜形成(不動態)、化合物中で+2価、+4価
・融点327℃、沸点1,750℃、海水濃度0.003μg/L程度、平均地殻存在量13mg/kg
(2)生産量等
(平成元年度)
・金属鉛 生産量260,000t、輸出量25,000t、輸入量78,400t
(3)主な用途
・金属鉛:鉛管、鉛板、蓄電池、電線被覆、はんだ、活字
・二酸化鉛:ゴムの硬化剤
・硝酸鉛:マッチ、爆薬
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
(1)発がん性評価
・IARC 無機鉛:グループ2B、有機鉛:グループ3
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.05mg/L(長期的目標値0.01mg/L)
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.05mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 Action Level 0.015mg/L、MCLG Zero mg/L
・EC MAC 0.05mg/L
・カナダ MAC 0.05mg/L、OG 0.001mg/L
6.魚介類への濃縮性(改定時)
・濃縮性は中程度と考えられるが、さらに詳細な検討が必要。
7.環境中における検出状況(改定時)
(平成2年度)
<公共用水域>
25,520検体中0.1mg/Lを3検体超過、最大値0.17mg/L、0.01mg/Lで285検体超過(超過率1.1%)
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
急性中毒として可溶性鉛塩の経口致死量は、成人で10gである。鉛の人体に対する毒性は、急性的なものよりは、累積的毒性であるが、すべての人に安全であると見做し得る摂取量は明らかにされていない。AWWA(アメリカ合衆国水道協会)では、鉛の人体における蓄積は、1日当たり0.3mgから1.0mgの間にあるとしており、摂取量が1.0mgを超えると明らかに排出量を上廻って体内に蓄積されるようになる。
また、好気性バクテリアに対する有毒濃度は1.0ppmであり、バクテリアによる有機物の分解は0.1~0.5ppmの鉛によって抑止されるという報告もある。
我が国の「水質基準に関する省令」(厚生省令41年)では飲料水中の鉛の含有量は0.1ppm以下に定ており、上水道の浄水過程で鉛を除去、分解することは困難であることなどから考えて、公共用水域の水質は、飲料水水質と同程度以下の含有であるべきであると考えられる。
(平成5年・改定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ、幼児に対する暫定耐用週間摂取量0.025mg/kg/week(JECFA(1987)、Zieglerら(1978)、Ryuら(1983))をもとに、TDI相当値0.0035mg/kg/day。
幼児体重を5kg、飲料水寄与率を50%、1日あたりの飲料水摂取量を0.75Lとすると、計算値0.0117mg/Lとなり、これより水質評価値0.01mg/L。
水道水質基準においては、USEPA(1991)の算出式をもとにLacey (1985)、Maes (1991)のデータより、子供、乳児について血中鉛濃度10μg/L以下となるレベルから水道水質基準値0.05mg/Lとしている。
(中略)
8.対処方針(案)
新しい評価値としては、Ryuら(1983)をもとに0.01mg/Lが得られるが、水道水質に関する基準としては、日本人の血液中の鉛濃度・暴露量が世界的にみても低いレベルにあることを考慮して0.05mg/L以下とし、鉛毒性の蓄積性を考慮して長期的目標値を0.01mg/Lと設定している。
環境基準値としては、鉛毒性の蓄積性、鉛管からの溶出により環境水中の濃度より水道水中の濃度が高くなる可能性があることなどから、0.01mg/Lに設定するのが適当と考えられる。
なお、鉛は自然界にも広く存在することから、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。
9.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.243-249 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○六価クロム
1.基準値
(当初)0.05mg/L以下
(現行)0.02mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)
1 日本産業規格K0102の65.2.1に定める方法による場合
原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。
2 日本産業規格K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(日本産業規格K0102の65.の備考11のb)による場合に限る。)
試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
3 日本産業規格K0102の65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合
2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定)
令和3年7月19日・中央環境審議会答申
令和3年10月7日・環境省告示第62号(令和4年4月1日施行)
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・外観:(クロム)灰色粉末、(重クロム酸アンモニウム)橙色~赤色・結晶、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))橙色~赤色・結晶、(クロム酸ナトリウム)黄色/吸湿性結晶(無水物)・黄色/潮解性結晶(四水和物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))赤色~橙色/吸湿性結晶(無水物)・赤色~橙色/潮解性結晶(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))無臭/暗赤色・潮解性結晶/薄片/顆粒状粉末、(クロム酸ストロンチウム)黄色・結晶性粉末、(クロム酸亜鉛)黄色・結晶性粉末、(クロム酸カリウム)黄色結晶
・融点:(クロム)1,900℃、(重クロム酸アンモニウム)180℃で分解、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))398℃・500℃で分解、(クロム酸ナトリウム)762℃(無水物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))357℃・400℃で分解(無水物)、(酸化クロム(三酸化クロム))197℃・250℃以上で分解、(クロム酸ストロンチウム)分解する、(クロム酸亜鉛)316℃・440℃以上で分解、(クロム酸カリウム)968℃
・沸点:(クロム)2,642℃、(クロム酸カリウム)1,000℃
・密度:(クロム)7.15g/cm3、(重クロム酸アンモニウム)2.15g/cm3、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))2.7g/cm3、(クロム酸ナトリウム)2.7g/cm3(無水)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))2.5g/cm3(無水)・2.348g/cm3(25℃)(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))2.7g/cm3、(クロム酸ストロンチウム)3.9g/cm3、(クロム酸亜鉛)3.4g/cm3、(クロム酸カリウム)2.73g/cm3(18℃)
・水溶解性:(クロム)不溶、(重クロム酸アンモニウム)36g/100mL(20℃)(よく溶ける)、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))12g/100mL(20℃)(よく溶ける)、(クロム酸ナトリウム)53g/100mL(20℃)(よく溶ける)(無水物)・可溶(四水和物)、(重クロム酸ナトリウム(二クロム酸ナトリウム))236 g/100mL(20℃)(非常によく溶ける)(無水物)・可溶(二水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))61.7g/100mL(よく溶ける)、(クロム酸ストロンチウム)0.12g/100mL(15℃)(溶けにくい)、(クロム酸亜鉛)不溶、(クロム酸カリウム)62.9g/100mL(20℃)(よく溶ける)
・溶解性(その他):(クロム)希塩酸:反応・硫酸:反応、(重クロム酸アンモニウム)酸:反応、(重クロム酸カリウム(二クロム酸カリウム))酸:反応、(クロム酸ナトリウム)アルコール:僅かに可溶(四水和物)、(酸化クロム(三酸化クロム))硫酸:可溶、(クロム酸ストロンチウム)希塩酸:可溶・硝酸:可溶・酢酸:可溶、(クロム酸カリウム)アルコール:不溶
・環境中での挙動:
クロムは、主としてクロム鉄鉱(FeO・Cr2O3)として産出される。天然中に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは人為起源であるとみられる。
水域において、溶解性六価クロムの主な化学種は、HCrO4-及びCrO42-であり、その割合はpHに依存する。高濃度(0.4gCr/L超)では、2量体(例えば、HCr2O7-やCr2O72-)を形成する。環境中に存在する六価クロムの化学種は、三価クロムよりも溶解性は高いが、バリウムイオンが存在すると相対的に溶けにくいバリウム塩を生成する。このような塩の生成は、環境中における六価クロムの溶解性を制限する。
水域における全クロムの多くは、粒子状で存在する。
六価クロムの三価クロムへの還元は、表層水ではある程度起こり、特に酸素が欠乏した環境下で起こる。Fe(II)や有機物が多い環境下では、還元されやすい。
三価クロムは、通常の環境条件では容易に、又は直ちに六価クロムへ酸化されない。三価クロムの酸化は、酸性溶液中では鉱物表面へアニオン吸着した六価クロムにより制限され、中性からアルカリ性の溶液中ではCr(OH)3の沈殿を生じるために制限される。
六価クロムは、懸濁態や底質の正に帯電した部分へ吸着する。六価クロムの吸着は、pHが高くなり溶解性の陰イオンと競合すると減少する。
地下水では、六価クロムの還元は低酸素濃度の状態や還元状態において起こる。地下水中の酸化マンガンは、三価クロムを溶解性の高い六価クロムへ酸化するが、酸化マンガン濃度が十分でない場合には、水溶性の三価クロムを酸化しない。
底質中の六価クロムは、主にオキソアニオンとして存在し、好気的な条件下では移動性は大きい。六価クロムの三価クロムへの還元は、嫌気的な条件下で起こる。
(2)生産量等
(平成30年度)
・酸化クロム 製造・輸入量:7,000t以上~8,000t未満
・重クロム酸カリウム 製造・輸入量:1,000t未満
・クロム酸ストロンチウム 製造・輸入量:1,000t未満t
(3)主な用途
(重クロム酸アンモニウム)グラビア印刷の写真製版、染料・染色、有機合成の酸化剤・触媒
(重クロム酸カリウム)顔料の原料、染色用剤、酸化剤・触媒、マッチ・花火・医薬品などの原料、着火剤
(クロム酸ナトリウム)酸化剤
(重クロム酸ナトリウム)クロム化合物の原料、顔料・染料などの原料、酸化剤・触媒、金属表面処理、皮なめし、防腐剤、分析用試薬
(クロム酸)顔料の原料、窯業原料、研磨材、酸化剤、メッキや金属表面処理
(クロム酸ストロンチウム)塗料や絵の具の原料
(クロム酸亜鉛)錆止め塗料の原料
(クロム酸カリウム)クロム酸塩の製造、酸化剤、媒染剤、顔料、インキ
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第4版) 0.05mg/L(総クロム)(毒性データに不確実性があるため暫定値)
・Codexナチュラルミネラルウォーターに関するコーデックス規格 0.05mg/L(総クロム)
・EU飲料水指令 0.05mg/L(総クロム)
・U.S. EPA水質環境基準 0.05mg/L(総クロム)、飲料水基準 0.1mg/L(総クロム)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
<業種別届出排出量(六価クロム化合物;公共用水域)>
(平成25年度)
パルプ・紙・紙加工品製造業(1,098kg)、鉄鋼業(140kg)、金属製品製造業(133kg)、非鉄金属製造業(98kg)、プラスチック製品製造業(56kg)、輸送用機械器具製造業(47kg)、化学工業(29kg)、繊維工業(13kg)、金属鉱業(11kg)
(平成26年度)
パルプ・紙・紙加工品製造業(1,100kg)、鉄鋼業(165kg)、金属製品製造業(132kg)、非鉄金属製造業(112kg)、輸送用機械器具製造業(47kg)、プラスチック製品製造業(43kg)、化学工業(37kg)、繊維工業(25kg)、金属鉱業(14kg)
(平成27年度)
パルプ・紙・紙加工品製造業(1,090kg)、鉄鋼業(150kg)、非鉄金属製造業(111kg)、金属製品製造業(94kg)、輸送用機械器具製造業(58kg)、化学工業(30kg)、繊維工業(30kg)、プラスチック製品製造業(16kg)、金属鉱業(14kg)
(平成28年度)
パルプ・紙・紙加工品製造業(1,110kg)、鉄鋼業(175kg)、金属製品製造業(84kg)、非鉄金属製造業(80kg)、輸送用機械器具製造業(52kg)、化学工業(28kg)、繊維工業(23kg)、プラスチック製品製造業(20kg)、金属鉱業(13kg)
(平成29年度)
パルプ・紙・紙加工品製造業(280kg)、鉄鋼業(159kg)、金属製品製造業(108kg)、非鉄金属製造業(82kg)、輸送用機械器具製造業(53kg)、繊維工業(20kg)、金属鉱業(14kg)
(注)審議会答申より公共用水域への10kg/年以上の業種別届出排出量を抜粋。ただし下水道業、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業を除く。
7.環境中における検出状況(改定時)
<公共用水域>(基準値0.02mg/L)
(平成27年度)測定3,892地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%
(平成28年度)測定3,918地点、検出2地点、超過0地点、超過率0%
(平成29年度)測定3,906地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%
(平成30年度)測定3,820地点、検出6地点、超過0地点、超過率0%
(令和元年度)測定3,785地点、検出0地点、超過0地点、超過率0%
<地下水>(基準値0.02mg/L)
(平成27年度)測定2,625地点、検出3地点、超過2地点、超過率0.09%
(平成28年度)測定2,708地点、検出4地点、超過1地点、超過率0.04%
(平成29年度)測定2,673地点、検出2地点、超過0地点、超過率0%
(平成30年度)測定2,664地点、検出1地点、超過1地点、超過率0.04%
(令和元年度)測定2,640地点、検出4地点、超過1地点、超過率0.04%
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
クロムの経口致死量はうさぎ一匹当り2gとシアン等に比較してその毒性は少ない。
一般的に、0.1ppmを超えると吐き気がしたり、ひどい時には腸、じん臓等を犯したり、皮膚を腐蝕させたりするが、0.1ppm以下だと無害だといわれている。「厚生省令」では、飲料水中のクロム(6価)は安全性を見込んで0.05ppm以下としている。
クロムは、浄水過程において除去することが困難なため、国民の健康の面からも、公共用水域においては、飲料水の基準程度が適当と考えられる。
(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)
WHO飲料水水質ガイドライン改定案(第2版ドラフト)においては、毒性は六価のクロムの値を用い、三価のクロムは十分な毒性評価ができないが、安全側で判断するために全クロムとしての新しいガイドライン案を従来の0.05mg/Lのままで暫定値として設定している。また、水道水質に関する基準においては、クロムの毒性については従来どおり六価のものに着目することが妥当として現行どおり六価クロムとして0.05mg/L以下としている。これらのことを勘案し、環境基準値も従来どおり六価クロムとして0.05mg/L以下と設定する。
(令和3年・改定時)(答申抜粋)
2.検討事項
平成30年9月に、内閣府食品安全委員会において、六価クロムのTDIが1.1μg/kg体重/日と評価されたことを受けて、令和2年4月に水道水質基準の基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正された。このような状況を踏まえて、水質環境基準健康項目の基準値の見直しを行った。
水質環境基準健康項目及び要監視項目の選定の考え方については、令和2年中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)」(令和2年5月中央環境審議会)の2.(2)に記載された考え方を基本とした。
3.検討結果(抄)
(1)水道水質基準の改正等を踏まえた検討
六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lを0.02mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても、公共用水域等における検出状況からみて、従来通り水質環境基準健康項目とすることが適当である。
1)基準値の導出根拠
内閣府食品安全委員会において、2年間飲水投与試験においてみられた、雄マウスの十二指腸のびまん性上皮過形成に基づき算出したBMDL10値0.11mg/kg体重/日を基準点とし、不確実係数100を適用して、六価クロムのTDIが1.1μg/kg体重/日と設定された。
また、水道水質基準の改正においては、食品中のクロムは三価の状態で存在するとされているが、飲料水以外からの六価クロムの摂取経路が確かに無いとは言えないため、水の飲用の寄与率は60%とするのが適当とされた。
これらの結果を踏まえ、六価クロムのTDI 1.1μg/kg体重/日に対し、水の飲用に係る寄与率を60%、体重50kg、1日当たりの摂取量2L/日として、基準値を0.02mg/Lとした。
(以下略)
9.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.250-258 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月19日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第6次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0302.pdf 【NIES保管ファイル】
○砒素
1.基準値
(当初)0.05mg/L以下
(現行)0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・灰色、金属光沢のもろい結晶、乾燥した空気中、常温では安定
・加熱すると多くの金属と反応しヒ化物となる
・+5、+3、-3価で存在、比重5.73、融点817℃(36atm)
・一般水域において0.001~0.008mg/L程度ヒ酸(H3A5O4)として存在
・海水濃度2.3μg/L程度(ヒ酸(H3AsO4)として存在)
・平均地殻存在量1.8mg/kg 土壌中ではヒ酸として鉄、アルミニウムの酸化物に吸着
(2)生産量
(平成元年、推定)
・金属ヒ素42t、ヒ酸(H3AsO4)約100t
(3)主な用途
・金属ヒ素:半導体材料(高純度)、合金添加(低純度)
・亜ヒ酸:農薬、殺鼠剤、漁網・皮革の防腐剤
・ヒ酸:木材防腐剤、医薬品原料
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ1
・U.S. EPA グループA
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.05mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L(暫定)
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.05mg/L(暫定)、MCLG Zero mg/L(暫定)
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.022μg/L(飲料水及び水生生物経由)
・EC MAC 0.05mg/L
・カナダ MAC 0.05mg/L、OG 0.005mg/L
6.魚介類への濃縮性(改定時)
水中におけるヒ素の化学的挙動は複雑であり、溶解性の存在状態は様々である。ヒ素の各存在状態における相対的な毒性も生物種によって大きく異なる。低位にある水生生物は魚よりも濃縮性が高い可能性があるが、高位の水生生物では、各種の知見から生物濃縮係数を求めると300~3,000程度の値が得られ、体内代謝が早いとの知見もある。
濃縮性は中程度と考えられるが、さらに詳細な検討が必要。
7.環境中における検出状況(改定時)
(平成2年度)
<公共用水域>
23,289検体中3検体で0.05 mg/Lを超過(最大値0.08 mg/L)、152検体で0.01 mg/Lを超過(超過率0.7%)
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
砒素の経口致死量は成人で100~130mgであり、5~50mgで急性中毒をおこすといわれている。砒素の場合は、急性中毒はさることながら蓄積による慢性中毒が問題である。慢性中毒は一般に飲料水として常用している場合(参考)(1)(略)のように0.21~1.4ppm以上含有されていると、その危険があるといわれている。「厚生省令」によると飲料水中の砒素は安全性を見込んで0.05ppm以下となっている(参考)(2)(略)。また、浄水過程において砒素を除去することはほとんど困難である。
砒素の蓄積の危険性からいって、飲料水のみならず、その他公共用水域においても、飲料水と同程度の基準が適当と考えられる。
(平成5年・改定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ暫定1日耐用摂取量(TDI相当値)0.002mg/kg/day(JECFAによる)をもとに、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を20%とすると、計算値0.01mg/Lとなり、これより、水質評価値0.01mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
新しい評価値としてGranthamら(1977)、Cebrianら(1983)をもとに0.01mg/Lが得られ、水道水質に関する基準も0.01mg/Lに改定される見込みである。現行の環境基準値も水道水質に関する基準を踏まえて設定されていることから、環境基準値についても0.01mg/L以下とすることが適当と考えられる。
なお、ヒ素は自然界にも広く存在することから、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。
9.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.266-273 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○総水銀及びアルキル水銀
1.基準値
(当初閣議決定時)検出されないこと(メチル水銀として)
(当初告示)総水銀:検出されないこと(定量限界0.02mg/L)、アルキル水銀:検出されないこと(定量限界0.001mg/L)
(現行)総水銀:0.0005mg/L以下、アルキル水銀:検出されないこと(定量限界0.0005mg/L)
2.測定方法
(総水銀)昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
(アルキル水銀)昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:メチル水銀)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和45年4月21日・閣議決定
(改定:メチル水銀を総水銀とアルキル水銀に改める)
昭和45年5月29日・閣議決定
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(再改定)
昭和49年4月・中央公害対策審議会答申
昭和49年9月30日・環境庁告示第63号
4.基礎情報(水銀として)(見直し検討時、調査報告書より)
(1)物理化学的性状
・常温で液状のただ一つの金属。銀白色、金属光沢を有する重い液体。固体はスズ白色、金属光沢をもち、すこぶる展性、延性に富む。純水銀は乾燥気中、常温で安定。塩素とは常温で激しく反応する。濃硝酸には溶けるが、希硝酸・塩酸には不溶。金、銀、銅、亜鉛、カドミウム、スズ、鉛など多くの金属とアマルガムを形成する。
・比重13.59、融点38.87℃、沸点356.58℃、溶解度2×10-6g/100mL
(2)生産量等
(平成元年)
(水銀)生産量:6,151kg、輸出:205t、輸入:92t
(塩化第二水銀)生産量:30.5t
(酸化第二水銀)生産量:83.5t
(3)主な用途
(水銀)
・乾電池、水銀塩類の原料、蛍光灯、歯科用・合金用アマルガムの原料として用いられる。
(塩化第二水銀)
・塩化ビニル生産の触媒、マンガン電池の陰極用、殺菌剤・防腐剤・駆除剤などの医薬品
(酸化第二水銀)
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時、調査報告書より)
・水産用水基準 <0.004mg/L(全水銀)
・WHO飲料水水質ガイドライン(1971) 1µg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準(1973) 2µg/L
・FAO/WHO・PTWI(1989) 200µg(メチル水銀)
6.魚介類への濃縮性(見直し検討時、調査報告書より)
・塩化水銀:植物で18~8,537、貝類で190~664、水生昆虫で138~19,600、魚類で5~26
・メチル水銀化合物:植物で8~2,950、水生昆虫で2,460~8,470、魚類で222~8,033
7.基準値の根拠の概要
(昭和45年・当初設定時(メチル水銀))(審議会配付資料抜粋)
1.国民の健康に係る項目(抄)
(2)メチル水銀
メチル水銀はその蓄積により水俣病のごとき神経系統の疾病の原因となることが判明しており、過去の発症は主としてメチル水銀等を多量に蓄積した魚介類を反復摂取することにより生じている(参考(略)参照)。このように長期間にわたる蓄積という点に着目するとメチル水銀は「検出されないこと」が望ましい。また上水道においても、浄水処理過程での除去・分解は困難である。
以上の点からして、メチル水銀は「検出されないこと」とするのが適当と考えられる。
(中略)
別表1 国民の健康に係る環境基準
(項目)メチル水銀
(基準値)検出されないこと
(測定方法)昭和43年7月29日経済企画庁告示第7号に規定するガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法の両方法
(昭和45年・改定時(アルキル水銀、総水銀))(審議会配付資料抜粋)
1 基準値(抄)
(1)下記の項目、基準値、および測定方法を別表1 人の健康に係る環境基準に加える。
(項目)アルキル水銀
(基準値)検出されないこと
(測定方法)昭和43年7月29日経企庁告示第7号に規定するガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法
(項目)総水銀
(基準値)検出されないこと
(測定方法)ジチゾン吸光光度法(別添1(略))
注)メチル水銀の項目、基準値および測定方法は削除する。
(中略)
2 具体的数値の設定について(抄)
(1)アルキル水銀
アルキル水銀のうち、メチル水銀については、水俣病等を通じて、その毒性が明らかにされ、水質環境基準として既に「検出されないこと」と定められている。しかし、下表(略)のようにアルキル水銀の急性毒性は、むしろ炭素数の増加と共に強くなる。また慢性毒性については、国立衛生試験所の池田氏によるとエチル水銀はメチル水銀の1~2割低いとされ、神戸大喜田村教授の研究では各アルキル水銀のうちメチル水銀の慢性毒性が最も強く、エチル水銀はそれより1~3割低く、さらに炭素数の増加と共に慢性毒性は減少するとされている。
以上のことから、エチル水銀等その他のアルキル水銀もメチル水銀と大差ない毒性を持つと考えられ、またそれらが公共用水域に排出される可能性も大きいことにかんがみ、従来の健康に係る環境基準に定められた「メチル水銀」を「アルキル水銀」に変更し、基準値を「検出されないこと」とする。
(中略)
(3)総水銀
無機水銀の場合、その致死量は75~300mg(Smith氏)と言われ、喜田村教授等の動物実験によれば昇汞(HgCl2)のLD50は10~37mg/kgである。また0.25~0.35mg/人・日 以上水銀を摂取すると、体内蓄積が起るとされている。(上田教授等)
厚生省の試算によると、食物から摂取される水銀量は次のようである。
米 (平均摂取量)350g/日×(水銀濃度)0.1ppm=0.035mg/日
動物性食品 (平均摂取量)200g/日×(水銀濃度)0.1ppm=0.02mg/日
米以外の植物性食品 (平均摂取量)750g/日×(水銀濃度)0.01ppm=0.0075mg/日
計 0.0625mg/日
(ただし、食品中の水銀濃度については安全を考え最高値をとった。)
従って、飲料水からの許容量は0.25~0.063=0.187mg/日となり、1人1日1~2Lの飲料水を飲むとして、成人についての最大許容量は0.1~0.2ppmとなる。これに加熱等による水銀蒸散(約50%)および安全率を考慮し、また、厚生省生活環境審議会の答申によると、水道の浄水施設では水銀除去は期待できないので、水道原水の水質基準を飲料水基準と同じく「検出されないこと」(検出限界0.02ppm)としていること等により、一応、ジチゾン吸光光度法(検出限界0.02ppm)により「検出されないこと」とした。なお、諸外国の飲料水基準は、アメリカおよび西ドイツハンブル州では0.05ppm、ソ連では0.005ppmと定められているが、水銀の基準値を定めている国は少ない。
一方、水中の無機水銀が魚体へどのように蓄積するかについては、喜田村教授らの実験によると次のとおりである。(表略)
蛋白質との吸着に関しては水銀イオンも有機水銀もそれほど差異がないことから、エラ呼吸による水銀吸収については、水溶性であれば、無機、有機とも差はないとも言われ、また、排泄については、無機水銀の方が有機水銀に比して速度が速く、推定では無機水銀はメチル水銀の3~10倍の排泄速度を持つと言われる(厚生省資料)。従って、無機水銀はアルキル水銀ほどの蓄積性はないが、ある程度までは蓄積する可能性もあると考えられる。以上のことから総水銀については、比較的簡便で普及度も高いジチゾン吸光光度法(検出限界0.02ppm)により「検出されないこと」とするのが適当と考えられる。
(昭和49年・再改定時)(答申抜粋)
1.基準値の改訂の背景(抄)
公害対策基本法第9条に基づく「水質汚濁に係る環境基準」は、昭和46年12年28日(環告59号)に告示されたところであるが、水銀については「人の健康の保護に関する環境基準」の8項目のうち、アルキル水銀、総水銀の2項目として設定されている。現在の環境基準値は、アルキル水銀については、これを多量に蓄積した魚介類を反復摂取することによる人体影響と、上水道の浄水処理過程における除去分解の困難性などから判断して、設定当時採用が妥当とされた測定方法により「検出されないこと」となっている。この場合の測定方法は、ガスクロマトグラフ法および薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法の両方法によるものであり、定量限界は0.001ppmてある。
また、総水銀については人体内への蓄積が起こる限界値とされていた摂取量のうち、食品からの摂取量を差し引いた飲料水からの摂取量を基として求め、上水道の浄水処理過程における除去分解の困難性、さらに安全率を考慮して、当時行政上利用可能であった、ジチゾン吸光光度法により、「検出されないこと」とされている。この場合の定量限界は0.02ppmである。
このように現在の水銀に関する環境基準は、アルキル水銀、総水銀のいずれも人体内への蓄積に配慮しているものの、むしろ測定の定量限界から、十分といえないながらもやむをえないものとしてそのレベルが定められている。
また、水銀に関する排水基準については、水銀以外の有害物質の排水基準が環境基準の10倍値となっているのに対し、その定量限界の不十分さを考慮して環境基準と同じとしている。
しかしながらその後において、①分析技術の進歩と分析機器の普及にともなって、低濃度の水銀分析が可能となったこと、②水銀に関する魚介類の暫定的規制値が定められたこと、③環境汚染と魚介類汚染に関するデータが増加し、相互関係の考察が可能となってきたことなどの科学的知見が拡大してきたことにかんがみ、緊急を要する水銀汚染問題の解決を目標として、環境基準および排水基準をより適切な内容に改訂するよう提言するものである。
2.基本的な考え方(抄)
(中略)
(環境基準関係)
(1)水中の水銀が食物連鎖等を通じて魚介類中に濃縮・蓄積されて、その結果、食品としての許容量を超えてはならないとする考え方に基づき定めるものとする。
(2)自然界における水中の水銀の存在状態および測定方法の精度について配慮するものとする。
(中略)
3.環境基準関係因子の考察
(1)魚介類の暫定的規制値
魚介類の暫定的規制値は、厚生省による総水銀0.4ppm、メチル水銀0.3ppmを用いる。
(2)生物濃縮と濃度比(抄)
生物濃縮は、水あるいは底質中の水質が、えらまたは細胞膜を通して体内に入る経路と、食物連鎖によって、プランクトン、中小動植物を経由して体内に入る経路が考えられる。その濃度の程度は、魚介類の生態によって著しく異なるものであり、また、長期生存することによって増加することも知られている。
また、食物連鎖による場合には、一時的に多量の水銀が入って体内濃度がたかまることがある。
このような環境水と生物間の水銀の量的関係を示す指標として濃度比(生物体の元素濃度/環境水中の元素濃度)が用いられ、この濃度比の値は両者間の含有物質量ならびに生物学的な平衡状態では一定値をたもつことが期待されているが、生物学的平衡には関連する因子が多く、複雑で必ずしも一定とはならない。
水銀の濃度比に関する知見としては、その濃度比は、無機水銀の場合数十程度と低く、メチル水銀において、1×104~105程度となるといわれている。このことは、環境水中には現在の測定方法ではメチル水銀が殆ど検出されていないにもかかわらず、魚介類中の総水銀100に対し、メチル水銀が10~90%(平均的にみて60~70%)を占めていること、ならびに魚体内において無機水銀が有機化することは一般的にありえないこと等から推察できる。
このことから、総水銀については、仮に100倍に濃縮されるものと考えれば、環境水の許容濃度は0.004ppmとなり、また、アルキル水銀については濃度比を1×104~105と考えて、環境水の濃度は0.000003~0.00003ppmと試算される。
このように生物濃縮や濃度比についてはあるていどの知見はあるが、その知識は必ずしも十分ではないので、とりあえず48年7月から10月にかけて行なわれた「水銀等有害物質に関する全国環境調査結果」について水質と魚介類中の総水銀量から、現象的に考察して環境水中の許容濃度を定めることが適当である。
水中のアルキル水銀については、事実上測定が不可能であり、濃縮の割合を裏付けすることはできないが、総水銀については、同一水域の水質と魚介類中の総水銀含有量を各々の水域についてみると別図1(略)のとおりである。その環境水中の水質値は、水俣湾においてND~0.0033ppmとなっており、水6検体中、3検体(50%)で0.0005ppm以上の水銀が検出されている。以下、酒田港地先(6.5%)、八代海(6.4%)、有明海(2.2%)において検出されているが、徳山湾以下の水域については水中からは水銀は検出されていない。水質中の総水銀が検出されるのは、主として底質中の水銀含有量の高い区域で検出されていることから、底質中の水銀の溶出によるものもあろうが、むしろ水銀を含有する底質が懸濁したものや、水銀を濃縮したプランクトン等を測定したことによるものであると推論されている。また、底質中の総水銀が、それぞれの水域の暫定除去基準値を越える水域は、水俣湾のほぼ全域および徳山湾と酒田港の一部である。
一方、これらの水域に生息している魚についてみると、厚生省の魚に対する暫定的規制として示している総水銀0.4ppmを超える魚が水俣湾及び徳山湾においてそれぞれ129検体中26検体、489検体中65検体が捕獲されている。
これらの結果を総合的にみて、現在迄の調査結果では、魚介類の汚染は、むしろ底質中の水銀の含有量に重要な関係があるものと考えるのが妥当であろうが、底質対策で補完しながら少なくとも現象的にみて環境水質が0.0005ppmから0.001ppm程度に保たれるならば十分な安全率をもって、海域、湖沼の魚介類中の水銀含有量は暫定的規制値以下にとどまることを示しているといえる。
(3)自然界の水の水銀含有量
諸外国ならびにわが国の公共用水域における水銀含有量に関する資料をとりまとめると、おおむね次のようである。
わが国の周辺水域の非汚染水域の総水銀含有量は、0.0001ppm程度であり、また、比較的汚染されていると考えられる水域は0.0002~0.0050ppm程度とみなされる。
また、河川水については、47年度の都道府県調査(中間集計)によると、12,009検体中、0.02ppm以上の検定数は4検体(0.03%)、また、0.0001~0.002ppm(過半数は0.0005ppm)を定量限界として検出されものは、565検体(4.7%)を占める。水銀鉱山または鉱床を有する河川および都市内または都市近郊河川において、とくに高い検出率を示しているが、厚生省が行った調査によれば、水道水源として利用されている河川においては72検体中0.001ppmを超えるものはなかった。
また、河川中の水銀濃度と湖沼海域中の水銀濃度を比較すると、都市河川のように工場排水等の人工的要素にもとづくものはさておいても、水銀鉱床地帯で岩石、土壌等からの溶出という自然的要素とその流動性によって、河川の方が湖沼海域よりも水銀濃度が高い場合がある。
また、アルキル水銀については、現在の測定方法では検出されていない。
(中略)
5.総合的考察
(1)環境基準は次のとおりとする。
総水銀 0.0005ppm以下
ただし、河川において、自然的原因によりこれを超える場合には、0.001ppmまで許容出来るものとする。
アルキル水銀 検出されないこと
環境基準を以上述べたような現状の意見に基づいて総合的に考察すると次のようである。
(イ)環境水中の総水銀含有量を0.0005ppm~0.001ppm程度に保つことにより、魚介類についての暫定的規制値である総水銀0.4ppmは十分に確保できるものと推察される。
ただし河川においては、岩石、土壌等のからの溶出という自然的要因により海域、湖沼よりも、水銀濃度が高い場合があることから、総水銀の環境基準はその原因が自然的な要因に基づくことが明らかな場合0.001ppmまで許容されるものとしたことにかんがみ魚介類への影響を把握する観点からこのような場合にあっては当該河川の魚介類の監視を行うとともに必要に応じて食事指導等の施策を行っていくことが適当である。
(ロ)メチル水銀については、魚介類への蓄積を考慮すればできるだけ低いことが望ましい。測定の定量限界値(0.0005ppm)も十分ではないので「検出されないこと」とすることが適当である。
(ハ)その他
①これらの基準は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできるかぎり現状を維持するよう留意するものとすること。
②総水銀の環境基準値は生物濃縮を考慮して決定されたものであるから、その基準値は年間平均値として達成維持されるべきものとすることが適当である。
③アルキル水銀については、このレベルでは生物濃縮の観点から魚介類の汚染がないとはいえないので、その基準値は最大値とするとともに暫定的規制値に基づく食品監視等によっておぎなうことが適当である。
(以下略)
(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)
(総水銀)
現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。
なお、総水銀の環境基準値は、一般的には年間平均値として0.0005mg/L以下と設定されているが、河川においてその汚染が自然的原因の場合によることが明らかである場合に限り、0.001mg/L以下とされている。しかし、環境基準値自体は自然的原因の場合と人為的原因の場合とで異なる性格のものではないことから、「0.0005mg/L以下」を全国一律で適用すべきものとして設定し、公共用水域等において自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合においては、これまでの判断基準も勘案しつつ、評価に当たってこのことを十分考慮することとする。
(アルキル水銀)
アルキル水銀及びPCBについては、相当の年数にわたり不検出が続いているが、有害性が明らかな物質であり、残留性の高い物質であることから引続き環境基準として設定することとする。
現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。なお、それぞれの基準値の設定の考え方は基本的には慢性毒性が根拠となっているが、いずれも「検出されないこと」をもって基準値を定めていることから、各地点における基準達成の判断は、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって行うことが適当と考えられる。
8.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和45年5月・経済企画庁国民生活局「水質汚濁に係る環境基準の項目追加について」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和49年4月・中央公害対策審議会「水銀に係る環境基準、排水基準ならびにその検定方法の改定について」 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.159-167 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○PCB
1.基準値
検出されないこと(定量限界0.0005mg/L)
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
3.設定経緯
昭和49年11月29日・中央公害対策審議会答申
昭和50年2月3日・環境庁告示第3号
4.基礎情報(令和2年の資料より)
・正式名称:Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)
・水に極めて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する。
・熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換体の熱媒体、ノンカーボン紙など様々用途で利用されてきたが、現在は製造・輸入ともに禁止されている。
・昭和49年(1974年)に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき製造及び輸入が原則禁止された。
・PCB廃棄物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業者が長期間保管し続けてきており、平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)が制定され、処理体制の整備を図った上で定められた年月までに処理を終えることとされている。
・化学物質の審査及び製造等に関する法律:第一種特定化学物質
5.毒性情報及び各種基準値(日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会(2016)、令和2年の資料より)
(1)毒性情報
・脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されている。
・一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されている。
(2)発がん性評価
・IARC(2015年) グループ1
・日本産業衛生学会(2016年) 第1群
6.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(答申抜粋)
1 基本的考え方
水質の環境基準、排水基準及び底質の除去基準の設定に当たっては、次のような基本的な考え方に基づき検討を行った。
(1)水中及び底質中のPCBが、直接あるいは食物連鎖を通じて魚介類に濃縮、蓄積されて、その結果、食品としての暫定的規制値(3ppm)を超えないとする考え方に基づき定めるものとする。
(2)公共用水域におけるPCBの存在状態及びPCBの測定方法の精度について配慮するものとする。
(中略)
3 関係因子の考察
(1)魚介類の食品基準(暫定的規制値)
PCBに係る魚介類の暫定的規制値は、食品衛生調査会が昭和47年8月14日付けで厚生大臣に対して行った答申を勘案して、内海内湾(内水面を含む。)の魚介類(可食部)については3ppmとする。
(2)濃縮比(抄)
PCBの魚介類の生体内への蓄積は、水中あるいは底質中のPCBが、えらを通して体内に入る経路と、食物連鎖によってプランクトン、ベントス等を経由して体内に入る経路が考えられる。その蓄積の程度は、魚介類の生態、とくに食性によって著しく異なるものであり、また、同一魚種についても季節的に変動し、かつ、長期間生存することによって増加することも知られている。また、食物連鎖による場合には一時的に多量のPCBが入って体内濃度が高まることがあるが、何れは生物学的平衡状態になるものと考えられている。このように魚体内のPCB含有量は、各種の要因の影響をうけて著しく変動する。
一般的には食物連鎖による生体内への蓄積は、水棲哺乳動物及び大型肉食性魚類の主要な蓄積経路であり、これに反し環境水からの直接摂取による蓄積は、水棲無脊椎動物や一般魚類にとってはもっとも重要な蓄積経路と考えられている。
PCBの直接摂取による濃縮比を求めるに当って、PCBの魚介類に関する食品基準値は、可食部(主として筋肉部をさしていると考えられる)に対するものであるので、ここで用いるPCBの濃縮比は次のように定義するものとする。
PCBの濃縮比=魚介類の可食部のPCB濃度/環境水中のPCB濃度
このように定義したPCBの濃縮比に関しては、いくつかの事例がある。表-1(略)に示すごとく5,667~8,582であり、平均7,360である。実験に使われているハマチ、ウナギは比較的PCBを蓄積しやすい魚であること、実験の環境水のPCB濃度は1~5ppbのオーダーであるが、実際上魚介類の汚染が問題になる濃度はもう少し下のレベルになるので濃縮比はさらに若干高くなること、並びに食物連鎖などの要因を勘案した場合PCBの濃縮比は10,000程度とするのが適当であろう。
この濃縮比が妥当であることを裏付ける資料としては、次のようなものがある。すなわち、スウェーデンのハンセンは魚の各部の濃縮比を求め、イシモチ(Spot)を用いた実験において試料全体の濃縮比は37,000に対し、筋肉部の濃縮比は7,600と報告しており、従って両濃縮比の比率は4.87倍の値となる。
魚種、魚令等の相異によって、この比率は変化すると思われるが、試料全体の濃縮比は筋肉部のそれの5倍程度と見ることができる。従って、上記の可食部の濃縮比にして10,000は魚全体の濃縮比に換算すれば50,000程度に相当すると考えられる。
これは米国政府PCB合同対策本部報告(表-2(略)参照)の12,000~76,000と比較しても妥当なものといえる。
(中略)
4 環境基準値
PCB 検出されないこと。(定量限界値 0.0005ppm)
環境水中のPCB濃度は次式によって求めるものとする。
環境水中のPCB濃度(ppm)=魚介類の可食部のPCB濃度(ppm)/魚介類の可食部のPCB濃縮比=3ppm/10,000=0.0003ppm
一方水中のPCBの定量限界は0.0005ppmであるので、環境基準値は「検出されないこと」(定量限界値0.0005ppm)とすることが適当である。
この基準は、このレベルまでの汚染を許容することを意味するものではなく、現在清浄な水質はできるかぎり現状を維持するよう留意するものとする。
(平成5年・見直し検討時)(専門委員会配付資料抜粋)
アルキル水銀及びPCBについては、相当の年数にわたり不検出が続いているが、有害性が明らかな物質であり、残留性の高い物質であることから引続き環境基準として設定することとする。
現行の環境基準値は食品経由の健康影響を主に考慮して設定しており、今回は見直しを行わない。なお、それぞれの基準値の設定の考え方は基本的には慢性毒性が根拠となっているが、いずれも「検出されないこと」をもって基準値を定めていることから、各地点における基準達成の判断は、年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって行うことが適当と考えられる。
7.参考資料
・昭和49年11月29日・中央公害対策審議会「PCBに係る水質の環境基準、排水基準及び底質の暫定除去基準並びにその分析方法の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会(2016)許容濃度の暫定値(2016)の提案理由、産業衛生学雑誌、58(5)、pp.213-249 https://doi.org/10.1539/sangyoeisei.S16002
・令和2年3月・環境省・経済産業省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)」 https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full9.pdf 【NIES保管ファイル】
8.解説文献
・奥井英夫・今井千郎(1975)PCBの環境基準・排水基準及び底質の暫定除去基準について、工業用水、201、pp.11-16 【NIES保管ファイル】
○ジクロロメタン
1.基準値
0.02mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の芳香のある水より重い液体、沸点40℃、不燃性、非引火性
・湿気により加水分解 水溶解度20g/L(20℃)
・水からの揮散小、揮発性は他の揮発性有機塩素化合物と比べて小
・土壌吸着性低、生分解性低
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量73,111t、輸出量3,871t、輸入量6,933t
(3)主な用途
・溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、フロン113の代替物質)
・ウレタン発泡助剤、エアロゾルの噴射剤、冷媒、抽出溶媒
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.02mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) なし
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.02mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
527検体中98検体検出、検出率18.6%、検出範囲0.00004~0.012 mg/L
<地下水>
859検体中35検体検出、検出率4.1%、最大値0.12mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水質ガイドラインの根拠データ(Serotaら(1986))をもとに、NOAEL 6mg/kg/dayより、不確定係数を1,000(発がん性を考慮)として、TDI 0.006mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.015mg/Lとなり、これより水質評価値0.02mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において比較的広くかつ高いレベルで検出がされていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Serotaら(1986)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.02mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.20-26 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○四塩化炭素
1.基準値
0.002mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の液体、水に難溶、水溶解度0.8g/L(20℃)、沸点76.7℃、比重1.63
・揮発性、大気中で安定、オゾン層破壊の原因物質のひとつ、土壌吸着能低
・地下に浸透、生分解性低
・土壌中では嫌気状態でクロロホルムを経て二酸化炭素まで分解される
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量57,530t 輸出量37t 輸入量44,219t
(3)主な用途
・フルオロカーボン類の原料、溶剤、機械洗浄剤、殺虫剤、重合停止剤
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.002 mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.003 mg/L(暫定)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.002 mg/L(暫定)
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005 mg/L、MCLG Zero mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.004 mg/L(飲料水及び水生生物経由)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和2年度~平成3年度)
<公共用水域>(評価値0.003mg/L)
(平成2年度)3,342検体中超過 2検体
(平成3年度)3,922検体中超過 4検体
<地下水>(評価値0.002mg/L)
(概況調査)
(平成2年度)2,116検体中超過 1検体
(平成3年度)1,965検体中超過 0検体
(定期モニタリング調査)
(平成2年度)591検体中超過 3検体、最大値0.008mg/L
(平成3年度)803検体中超過 20検体、最大値0.099mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインでの根拠データ(Brucknerら (1986))をもとに、NOAEL 1mg/kg/dayより、不確定係数1,000(発ガン性を考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.000714mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00179mg/Lとなり、これより、水質評価値0.002mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Brucknerら(1986)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.002mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.35-43 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○1,2-ジクロロエタン
1.基準値
0.004mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の油状液体、揮発性(揮発性有機塩素化合物の中では揮発性低)
・水溶解度9g/L(20℃)、沸点83.7℃、比重1.25
・蒸気圧が高く大気へ移行しやすい、土壌吸着性低、地下に浸透可
・生物難分解性
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量2,463,902t 輸出量769t 輸入量616,406t
(3)主な用途
・塩化ビニルモノマー、ポリアミノ酸樹脂の原料、樹脂原料、溶剤、洗浄剤
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.004mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.03mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.0094mg/L(飲料水及び水生生物経由)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
574検体中35検体検出、検出率6.1%、検出範囲0.00001~0.061mg/L
<地下水>
1,091検体中28検体検出、検出率2.6%、最大値0.073mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドライン、USEPA-HAの根拠データ(NCI (1978))をもとに、体表面積修正を採用して、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.004mg/L(WHOでは体表面積修正を不採用)。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1978)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.004mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.49-56 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○1,1-ジクロロエチレン
1.基準値
(当初)0.02mg/L以下
(現行)0.1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
(改定)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第78号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:特徴的な臭気のある、揮発性、無色の液体。蒸気は空気より重い。酸化されやすく、酸素と接触すると過酸化物を生成し、加熱や衝撃によって爆発することがある。
・比重:1.2(20℃/4℃)
・水への溶解性:2.4g/L(25℃)
・ヘンリー定数:2,640Pa-m3/mol(24℃)
・揮発性の為にほとんどが大気中に移行する。地表水を汚染した1,1-ジクロロエチレンは速やかに揮散する。
・水中での加水分解半減期は、pH4.5~8.5においては6~9か月と測定されている(U.S.NLM: HSDB, 2002)。
・生分解性については、クローズドボトルを用いた化審法に基づく好気的生分解性試験(28日間)のBOD分解率は、被験物質濃度が9.7mg/Lの条件で0%であり、難分解性と判定されている(通商産業省, 1991)。また、1,1-ジクロロエチレンは容易には生分解されないが、馴化などの条件が調えば好気的条件下や嫌気的条件下で生分解されると評価されている(NITE&CERI初期リスク評価書, 2005)。
・化審法に基づくコイを用いた6週間の濃縮性試験で、水中濃度が0.5mg/L及び0.05mg/Lにおける濃縮倍率はそれぞれ2.5~6.4及び13未満であり、濃縮性がない又は低いと判定されている(通商産業省, 1991)。
・土壌吸着性は低く、地下に浸透すると地下水を汚染する。
(2)生産量等
・製造・輸入量は2,249tであるがこれは自家消費分を含まない(経済産業省, 2003)。
・また、平成13年における1,1-ジクロロエチレンの製造量(中間原料分)を約60,000tと推定している(NITE&CERI, 2003)。
(3)主な用途
・塩化ビニリデン系繊維、フィルム等の合成原料
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・水道水質基準(新) 0.02mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.03mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 0.03mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版1次追補版) 検出状況が低いためガイドライン値を設定せず
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.007mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
<公共用水域>
(平成19年度)1,799kg(下水道業を除く排出量:225kg)、合計:100,692kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
620検体中18検体検出、検出率2.9%、検出範囲0.00001~0.00028mg/L
<地下水>
1,132検体中91検体検出、検出率8.0%、最大値0.056mg/L
(平成21年・改定時)
<公共用水域>(基準値0.1mg/L)
(平成16年度)測定3,670地点、検出12地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成17年度)測定3,600地点、検出1地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成18年度)測定3,625地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成19年度)測定3,638地点、検出2地点、超過0地点、10%超過0地点
<地下水>(基準値0.1mg/L)
(平成16年度)測定2,077地点、検出141地点、超過6地点、10%超過61地点
(平成17年度)測定2,026地点、検出161地点、超過6地点、10%超過64地点
(平成18年度)測定1,890地点、検出158地点、超過5地点、10%超過53地点
(平成19年度)測定1,843地点、検出133地点、超過5地点、10%超過51地点
9.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHOの根拠データ(Quastら (1983))をもとに、LOAEL 9mg/kg/dayより、不確定係数1,000(発ガン性、LOAEL使用を考慮)として、TDI 0.009mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0225mg/Lとなり、これより、水質評価値0.02mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Quastら(1983)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.02mg/L以下とする。
なお、この物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンなどから環境中において生成されると言われており、その挙動について引き続き知見の集積に努める必要がある。
(平成21年・改定時)(答申抜粋)
ア 基本的整理及び基準値
WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を0.1mg/Lとすることが適当である。(具体的な導出根拠については下記イ参照)
新たな毒性評価に対応した基準値変更後の値で現況の検出状況を評価した場合、地下水においては、この値及びこの10%値を超過する事例が毎年見られるが、公共用水域においては、この値及びこの10%の値を超過する事例は過去10年間にわたり見られない状況である。
用途・使用方法、物質の特性等を勘案すると、現行の排水規制を前提にすれば、今後、公共用水域から見直し後の基準値の10%を超えて検出される可能性は低いことが予想される。このため、公共用水域における常時監視について重点化・効率化を行うべきである。
イ 基準値の導出根拠
平成16年答申において採用した毒性評価と平成20年の水道水質基準改訂の際の検討の根拠となる食品安全委員会が食品健康影響評価で採用した根拠論文は同じである。しかし、その毒性評価については、「ラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響で、LOAEL 9mg/kg体重/日が最も鋭敏なエンドポイントである。しかし、NOAELが得られていないことから、WHO第3版追補(2005)と同様にNOAELに近い値として導き出されているBMDLを用いることが、最も適当と考えられる。」としている。このことを踏まえ、具体的には以下のとおり算定した。
Quastら(1983)のラットを用いた2年間の飲水投与試験による肝臓への影響からBMDL10を4.6mg/kg体重/日と算定し、不確実係数を100としてTDIを46μg/kg体重/日と算定した。これに、水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.1mg/Lとした。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.73-79 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成20年5月29日・食品安全委員会「水道水評価書(1,1-ジクロロエチレン)」 https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20080411001&fileId=002 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○シス-1,2-ジクロロエチレン
1.基準値
0.04mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:特徴的な臭気のある、無色の液体
・比重:1.28(20℃)
・水への溶解性:3.5g/L(20℃)、5.1g/L(20℃)
・ヘンリー定数:413Pa-m3/mol(25℃)
・当該物質は1,2-ジクロロエチレンから塩化ビニルモノマーや1,1-ジクロロエチレンを製造する過程での副生成物であり、触媒や製造条件によりシス体とトランス体の比率が異なる。
・製造過程及び溶剤として使用される過程で環境中に放出されると、その揮発性のために多くが大気中に移行する。地表水を汚染したものは速やかに大気中に揮散する。
・水中では安定であるとの報告(日本環境管理学会, 2004)があり、化審法では難分解性と判定されている(通商産業省, 1990)。底質を用いた嫌気的生分解性試験でのGC測定での分解率は16週間で99%以上であった(Wilsonら, 1986)。嫌気的な生分解生成物としては、クロロエチレン(塩化ビニル)が報告されている(Barrio-Lageら, 1986)。
・オクタノール/水分配係数(logPow)は1.83(測定値)であることから、化審法に基づく濃縮性試験では、濃縮性がない、または低いと判定されている(通商産業省, 1990)。
・土壌吸着性は低く、地下に浸透する。地下水中では多くの場合、トリクロロエチレンと共存している。
(2)生産量等
不明
(3)主な用途
・化学合成の中間体、溶剤、染料抽出剤、香料、熱可塑性樹脂の製造等
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準(新) 0.04 mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.07mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(見直し検討時)
<公共用水域>(平成19年度)
(シス体)3,414kg(下水道業を除く排出量:342kg)、合計:3,762kg
(トランス体)40kg(下水道業を除く排出量:40kg)、合計:10,627kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
699検体中51検体検出、検出率7.3%、検出範囲0.00001~0.0045mg/L
<地下水>
1,047検体中177検体検出、検出率16.9%、最大値2.0mg/L
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(基準値0.04mg/L)
(平成16年度)測定3,673地点、検出22地点、超過0地点、10%超過1地点
(平成17年度)測定3,602地点、検出14地点、超過0地点、10%超過3地点
(平成18年度)測定3,631地点、検出13地点、超過0地点、10%超過2地点
(平成19年度)測定3,647地点、検出17地点、超過0地点、10%超過1地点
<地下水>(基準値0.04mg/L)
(平成16年度)測定2,258地点、検出480地点、超過162地点、10%超過428地点
(平成17年度)測定2,159地点、検出516地点、超過173地点、10%超過429地点
(平成18年度)測定2,030地点、検出478地点、超過152地点、10%超過418地点
(平成19年度)測定1,979地点、検出465地点、超過160地点、10%超過422地点
9.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
トランス体についてのWHOの根拠データ(Barnesら (1985))をもとに、NOAEL 17mg/kg/dayより、不確定係数1,000(短期実験を考慮)として、TDI 0.017mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲用水量2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0425mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Barnesら(1985)をもとに0.04mg/L以下とする。
なお、この物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどから環境中において生成されると言われており、その挙動について引き続き知見の集積に努める必要がある。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
③(シス、トランス)-1,2-ジクロロエチレンについて
ア 基本的整理
公共用水域における各異性体の平成10年度以降の自治体の測定による検出状況は、シス及びトランス両異性体とも環境基準値等を超えるものはないが、シス体は環境基準値の10%の値を超過する検出が数箇所で毎年見られている一方で、トランス体は指針値の10%の値の超過も見られていない。
PRTRによる公共用水域への排出量(平成13年度から平成19年度)が、シス体で3,414から7,461kg/年(下水道からの排出量を除く場合、113から514kg/年)、トランス体で10から40kg/年で推移しているが、現在、両異性体ともに意図された製造はほぼ行われておらず、他の化学物質を製造する際に副生成されているものが主と考えられる。
一方、シス体が検出された箇所でトランス体の測定を同時に行っている箇所は数箇所しかないが、それらの箇所でシス体及びトランス体それぞれの濃度を足し合わせてもシス体の現行基準値あるいはトランス体の現行指針値である0.04mg/Lを超えるものはない。
なお、副生成される過程でのシス体、トランス体別の生成割合は不明であるが、両者の生成過程が同じであることを考えれば、シス体が基準値の10%を超えて検出された地点では、トランス体が検出される可能性は完全には否定できない。少なくともシス体が基準値の10%を超えて検出された地点でのトランス体の監視の強化を図るべきである。
地下水においては、地下水水質測定結果によれば、シス体は過去5年間毎年超過が見られ、トランス体は過去5年間で平成16年度及び平成17年度にそれぞれ1箇所の超過が見られる。基準値等の10%を超える検出はシス体、トランス体共に毎年継続して確認されている。
地下水における1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)はトリクロロエチレン等が嫌気性条件下にある地下水中で分解して生成した可能性があり、トランス体が存在する場合には、多くの場合シス体も存在する状況が見られる。また同一地点同サンプルのシス体及びトランス体の測定結果において、異性体個別では基準値及び指針値を超えないものの、両異性体の和が0.04mg/Lを超える箇所が過去5年間で3箇所あった。
以上のことから、公共用水域においては今後とも、シス-1,2-ジクロロエチレンについては健康保護に係る水質環境基準項目としトランス-1,2-ジクロロエチレンについては要監視項目とする必要がある。一方、地下水においては、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を地下水環境基準項目とすべきである。これに伴い、トランス-1,2-ジクロロエチレンについては地下水に関する要監視項目から削除すべきである。
イ 基準値について
地下水環境基準値はWHO飲料水水質ガイドライン第3版及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、シス体及びトランス体の和で0.04mg/Lとすることが適当である。なお、公共用水域における基準項目であるシス体の基準値及び要監視項目であるトランス体の指針値は引続き0.04mg/Lとすることが適当である。具体的な導出根拠は以下のとおり。
ウ 基準値の導出根拠
Barnesら(1985)のマウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験による雄マウスの血清中酵素の増加等を根拠としたNOAEL17mg/kg/dayから不確実係数1,000(短期実験を考慮)を適用して、TDI 0.017mg/kg/dayと算定した。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.04mg/L以下とした。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.80-85 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,1,1-トリクロロエタン
1.基準値
1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:無色透明の揮発性液体で特有の甘い臭いがある。不燃性。ゆっくり加水分解して塩化水素を発生する。
・比重:1.3(20℃/4℃)
・水への溶解性:4.4g/L(20℃)
・ヘンリー定数:500Pa-m3/mol
・主として製造過程及び溶剤として使用される過程で、環境中へ放出される。揮発性が強いため、大気中へ容易に揮散する。大気中では、光化学反応で生成されたヒドロキシラジカルと反応して緩やかに分解する。
・化審法に基づく好気的生分解性試験(被験物質濃度100mg/L、14日間、活性汚泥濃度30mg/L)のBODによる分解率は0%であり、難分解性と判定されている(通商産業省, 1992)。嫌気的条件下では、メタン発酵菌及び硫酸還元菌により分解されることが報告されており、これらの混合菌を用いた実験室内試験では分解の半減期は1日から16週間である(ATSDR, 1993)土壌中では緩やかに嫌気分解され(6日間で16%)、嫌気分解の主要な生成物は1,1-ジクロロエタンであり、これも緩やかにクロロエタンに分解されると報告されている(ATSDR, 1993)。
・化審法に基づく生物濃縮性試験(42日間)でのBCFは、試験濃度0.3mg/Lで0.7~3.0、試験濃度0.03mg/Lで0.9~4.9であることから、低濃縮性であると判定されている(通商産業省, 1992)。
・土壌に浸透したものは吸着されずに、地下水に浸入してゆっくり加水分解される。
(2)生産量等
(平成13年)
・生産量40,516t 消費量9,009t 出荷量31,475t 輸出量12,885t
(平成17年)
・輸出量6,524t 輸入量0.01t
(3)主な用途
・試薬、合成原料
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準値 0.3mg/L(水質管理目標設定項目目標値)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 2mg/L(暫定)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 検出状況が低いためガイドライン値を設定せず
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.2 mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(見直し検討時)
<公共用水域>
(平成19年度)9,209kg(下水道業を除く排出量:1,810kg)、合計:17,493kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
(平成2年度~平成3年度)
<公共用水域>(評価値1 mg/L)
(平成2年度)4,914検体中評価値超過0検体
(平成3年度)6,147検体中評価値超過0検体
<地下水>(評価値1 mg/L)
(概況調査)
(平成2年度)4,514検体中超過 0検体
(平成3年度)5,135検体中超過 0検体
(定期モニタリング調査)
(平成2年度)1,626検体中超過 30検体、最大値2.8mg/L
(平成3年度)2,268検体中超過 3検体、最大値6.4mg/L
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(基準値1mg/L)
(平成16年度)測定3,718地点、検出15地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成17年度)測定3,643地点、検出3地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成18年度)測定3,653地点、検出6地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成19年度)測定3,700地点、検出4地点、超過0地点、10%超過0地点
<地下水>(基準値1mg/L)
(平成16年度)測定2,320地点、検出282地点、超過3地点、10%超過8地点
(平成17年度)測定2,123地点、検出288地点、超過1地点、10%超過8地点
(平成18年度)測定1,820地点、検出230地点、超過0地点、10%超過6地点
(平成19年度)測定1,631地点、検出204地点、超過0地点、10%超過4地点
9.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(McNuttら (1975))をもとに、NOAEL 1,365mg/m3(吸入曝露)より、不確定係数1,000(短期実験を考慮)として、TDI 0.58mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値1.45mg/Lとなり、これより、水質評価値1mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンと同じような用途で使用されており、公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることなどから、環境基準項目とする。水道水質に関する基準の検討の中では水道水が有すべき性状に関する項目として、臭味発生防止の観点から基準値を0.3mg/Lと定めているが、環境基準としては他の有機塩素系化合物と同様に健康への影響を考慮して基準値を設定することとし、McNutt(1975)をもとに評価値を設定して1mg/L以下とする。
なお、水道水源においては、水道水質に関する基準を満足できるような水質を確保するよう管理していくことが望ましい。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
その他の現行の基準項目についても他の項目と同様に検出状況等から、点検を行ったところ、1,1,1-トリクロロエタンについても1,1-ジクロロエチレンと同様に、地下水においては、基準値及びこの10%の値を超過する事例は見られているものの、公共用水域においては、基準値及びこの10%の値を超過する事例は過去10年間にわたり、見られない状況である。また、用途・使用方法、物質の特性等を勘案すると、現行の排水規制を前提にすれば、今後、公共用水域から基準値の10%を超えて検出される可能性は低いことが予想される。このため、1,1,1-トリクロロエタンについても公共用水域における常時監視について重点化・効率化を行うべきである。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.57-65 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,1,2-トリクロロエタン
1.基準値
0.006mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色の液体、沸点113.8℃、比重1.44、水に難溶
・水溶解度4.5g/L(20℃)、揮発性、水中から大気に蒸散する傾向、土壌吸着性低、生分解性低
(2)生産量等
不明
(3)主な用途
・溶剤、1,1-ジクロロエチレン(塩化ビニリデン)の原料、粘着剤、ラッカー、テフロンチューブの生産に利用
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ3
・U.S. EPA グループC
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.006mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG 0.003mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.006mg/L(飲料水及び水生生物経由)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
532検体中21検体検出、検出率3.9%、検出範囲0.00003~0.029mg/L
<地下水>
728検体中35検体検出、検出率4.8%、最大値0.023mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
USEPA-HAの根拠データ(NCI (1978))をもとに、体表面積修正を採用して、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.006mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1978)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.006mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.66-72 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○トリクロロエチレン
1.基準値
(当初)0.03mg/L以下
(現行)0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
(改定)
平成26年9月11日・中央環境審議会答申
平成26年11月17日・環境省告示126号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:無色の液体で、水より重い。臭気があり不燃性である。揮発性有機化合物。
・融点、沸点:-84.8℃、86.7℃
・比重:1.4559(25℃/4℃)
・蒸気密度:4.53(空気=1)
・蒸気圧:7.8kPa(20℃)
・ヘンリー定数:998Pa-m3/mol(25℃、測定値)
・換算係数:1ppm=5.46mg/m3、1mg/m3=0.183ppm(気体、20℃)
・オクタノール/水分配係数:logKow=2.42(測定値)
・水溶解度:1.28g/L(水、25℃)
・土壌吸着係数:Koc=68(推定値)
(2)生産量等
・平成20年:生産量70,693t、出荷量68,859t
・平成21年:生産量47,533t、出荷量62,321t
・平成22年:生産量47,745t、出荷量50,216t
(3)主な用途
・従来、衣料のドライクリーニング用及び金属機械部品の脱脂洗浄剤、医薬品、香料、ゴム、塗料、樹脂等の溶剤として使用されてきた。今日では、代替フロンガスの合成原料としての用途が多くなっている。
・現在では主に代替フロンガスの合成原料(全体の52.6%)及び機械部品や電子部品の脱脂洗浄剤(全体の43.2%)として使用されている。洗浄剤としては、羊毛や皮革から余分な油分を取り除くためにも使われている。また、工業用溶剤として、油脂、樹脂、ゴムを溶解したり、染料や塗料を製造する時の溶剤などに使用されたりしている(全体の4.0%)ほか、わずかではあるが試薬としても用いられている(全体の0.2%)。
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト))・水道水質基準:0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第4版) 0.02mg/L(暫定)
・EU飲料水指令・水質環境基準 0.01mg/L(飲料水指令は、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの和)
・U.S. EPA飲料水基準 0.005mg/L
6.魚介類への濃縮性(改定時)
・化学物質審査規制法に基づくコイを用いた6週間の濃縮性試験で、水中濃度が0.070mg/L及び0.007mg/Lにおける濃縮倍率はそれぞれ4.3~17.0及び4.0~16.0であり、濃縮性がない又は低いと判定されている(経済産業省,1979)。トリクロロエチレンの生物濃縮係数(BCF)の測定値は、ブルーギルでは17、ニジマスでは39であったとの報告がある(Lyman,1981)。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
(平成19年度)
届出:(大気)4,540,011kg、(公共用水域)2,289kg、(土壌)0kg、埋立:0kg
届出排出量合計:4,542,300kg
届出移動量合計:2,382,005kg(うち下水道への移動量 10kg)
(平成20年度)
届出:(大気)3,665,450kg、(公共用水域)2,096kg、(土壌)0kg、埋立:0kg
届出排出量合計:3,667,547kg
届出移動量合計:2,007,625kg(うち下水道への移動量 5kg)
(平成21年度)
届出:(大気)3,322,297kg、(公共用水域)2,256kg、(土壌)44kg、埋立:0kg
届出排出量合計:3,324,597kg
届出移動量合計:1,917,946kg(うち下水道への移動量 7kg)
(平成22年度)
届出:(大気)3,371,192kg、(公共用水域)2,056kg、(土壌)0kg、埋立:0kg
届出排出量合計:3,373,248kg
届出移動量合計:1,924,561kg(うち下水道への移動量 9kg)
(平成23年度)
届出:(大気)3,195,828kg、(公共用水域)2,223kg、(土壌)0kg、埋立:0kg
届出排出量合計:3,198,051kg
届出移動量合計:1,832,158kg(うち下水道への移動量 6kg)
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
<公共用水域>(評価値0.03mg/L)
(平成2年度)11,415検体中超過 0検体
(平成3年度)11,528検体中超過 1検体
<地下水>(評価値0.03mg/L)
(概況調査)
(平成2年度)5,817検体中超過 44検体、超過率0.8%
(平成3年度)6,158検体中超過 27検体、超過率0.4%
(定期モニタリング調査)
(平成2年度)1,916検体中超過 208検体、最大値11mg/L
(平成3年度)2,571検体中超過 289検体、最大値11mg/L
(平成26年・改定時)
<公共用水域>(基準値0.01mg/L)
(平成19年度)測定3,743地点、検出15地点、超過0地点、10%超過11地点
(平成20年度)測定3,667地点、検出10地点、超過0地点、10%超過7地点
(平成21年度)測定3,642地点、検出7地点、超過0地点、10%超過6地点
(平成22年度)測定3,633地点、検出6地点、超過0地点、10%超過5地点
(平成23年度)測定3,582地点、検出7地点、超過0地点、10%超過6地点
<地下水>(基準値0.01mg/L)
(平成19年度)測定3,948地点、検出89地点、超過27地点、10%超過85地点
(平成20年度)測定3,658地点、検出75地点、超過15地点、10%超過68地点
(平成21年度)測定3,676地点、検出49地点、超過9地点、10%超過45地点
(平成22年度)測定3,366地点、検出50地点、超過9地点、10%超過46地点
(平成23年度)測定3,285地点、検出46地点、超過7地点、10%超過41地点
9.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドライン(1984)及びUSEPA-HAの根拠データ(NCI (1976))をもとに、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.03mg/L(水道水質基準での採用算定方法)。
WHO飲料水水質ガイドライン改定案の算出過程に準じれば、Bubenら(1985)をもとに、LOAEL 100mg/kg/dayより、不確定係数3,000(発ガン性、LOAEL使用、短期実験を考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.0238mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0595mg/Lとなる。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1976)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.03mg/L以下とする。
(平成26年・改定時)(答申抜粋)
3.検討結果
(1)水道水質基準の改定等を踏まえた検討
平成22年9月に、食品安全委員会において、トリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)が1.46μg/kg体重/日と評価されたことを踏まえ、平成23年4月の水道水質基準の改定においては、WHOの飲料水水質ガイドライン第3版1次追補において示された飲料水の直接経口摂取以外の入浴時における吸入ばく露及び経皮ばく露量を考慮し、トリクロロエチレンの水質基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lへと強化した。
トリクロロエチレンの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.03mg/Lを0.01mg/Lに見直すことが適当である。また、変更する基準値に基づいた場合においても、公共用水域等における検出状況から見て、従来通り水質環境基準健康項目とすることが適当である。
1)基準値の導出根拠
食品安全委員会において、妊娠期のラットにトリクロロエチレンを飲水投与した場合における胎児の心臓異常発生の影響が確認された生殖・発生毒性試験に基づき、耐容一日摂取量(TDI)を1.46μg/kg体重/日と設定した注)。
また、WHOの飲料水水質ガイドライン第3版1次追補では、トリクロロエチレンの揮発性及び脂溶性を考慮し、入浴頻度の高い国では入浴時における吸入ばく露及び経皮ばく露など追加的なばく露も考慮すべきとの指摘がされており、我が国の水道水質基準においてもWHOの指摘に基づき、飲料水の摂取相当量を従来の2L/日から5L/日(入浴時における吸入ばく露量及び経皮ばく露量を含める)へと変更し、寄与率も従来の10%から70%へと変更した。
これらの結果を踏まえ、トリクロロエチレンの耐容一日摂取量(TDI)1.46μg/kg体重/日に対し、寄与率を70%、体重50kg、飲用水量相当量5L/日として、基準値を0.01mg/Lとした。
注)食品安全委員会 評価書
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya201006114402)公共用水域等における検出状況
平成14年度以降の公共用水域等におけるトリクロロエチレンの検出状況は、別紙1(略)のとおりである。公共用水域等における水質測定計画に基づく測定結果によると、公共用水域では、基準値(0.01mg/L)の超過事例は過去2年間あり、平成15年度と平成16年度にそれぞれ1地点、合計2地点で超過している。また、地下水では、超過事例が毎年度あり、平成14年度から平成23年度に延べ259地点で超過している。
(以下略)
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.1-10 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成26年9月11日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2602.pdf 【NIES保管ファイル】
○テトラクロロエチレン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の液体、水に難溶、水溶解度0.15g/L(20℃)、不燃性、沸点121℃
・比重1.62、揮発性、生分解性低
・有機物含有量が多い土壌には吸着されるが一般には吸着性低
・嫌気状態でゆっくり分解されトリクロロエチレン、ジクロロエチレン、塩化ビニルを生成
(2)生産量等
(平成2年度)
・生産量91,148t、輸出量2,406t、輸入量35,243t
(3)主な用途
・脱脂洗浄剤、ドライクリーニング溶剤、フロン113の原料、医薬品、香料
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・UEPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.01mg/L(暫定)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.04mg/L(暫定)
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.008mg/L(飲料水及び水生生物経由)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(平成2年度~平成3年度)
<公共用水域>(評価値0.01mg/L)
(平成2年度)11,419検体中超過 8検体、超過率0.1%
(平成3年度)11,541検体中超過 5検体、超過率0.0%
<地下水>(評価値0.01mg/L)
(概況調査)
(平成2年度)5,817検体中超過 79検体、超過率1.4%
(平成3年度)6,158検体中超過 44検体、超過率0.7%
(定期モニタリング調査)
(平成2年度)1,936検体中超過 429検体、最大値38mg/L
(平成3年度)2,564検体中超過 539検体、最大値72mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドライン(1984)及びUSEPA-HAの根拠データ(NCI (1977))をもとに、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.01mg/L(水道水質基準での採用算定方法)。
WHO飲料水水質ガイドライン(改定案)の算出過程に準ずれば、Bubenら(1985)、Hayesら(1986)をもとにNOAEL 14mg/kg/day、不確定係数1,000(発ガン性を考慮)として、TDI 0.014mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.035mg/Lとなる。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準項目とする。基準値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NCI(1977)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.01mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.11-19 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○1,3-ジクロロプロペン
1.基準値
0.002mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・水より重い淡黄色の液体、沸点約108℃、揮発性、疎水性
・水溶解度2.7g/L(シス体25℃)、2.8 g/L(トランス体25℃)
・土壌吸着はされにくい、土壌中で生分解
(2)生産量等
(平成2農薬年度)
・原体生産量4,432t、原体輸出量0t、原体輸入量953t
(3)主な用途
・土壌くん蒸剤、殺線虫剤
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.002mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.02mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域及び地下水>
1,243検体中58検体で検出、検出率4.7%、検出範囲0.00009~0.020mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドライン、USEPA-HAの根拠データ(NTP (1985))をもとに、体表面積修正を採用して、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.002mg/L(WHOでは体表面積修正を不採用)。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案して環境基準項目とする。基準値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.002mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.143-149 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○チウラム
1.基準値
0.006mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・白色結晶、比重1.29、融点155℃、水に難溶、クロロホルムに可溶
・酸性条件で水及び土壌中において分解、光分解性、土壌吸着性高
(2)生産量等
(平成2農薬年度)
・原体生産量517t、国内流通量428.7t
(3)主な用途
・農薬(種子消毒剤、茎葉散布剤、混合剤として病害防除)
・ゴムの硫黄加硫促進剤兼硫黄供与型加硫剤
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.006mg/L
・水道水質基準(新) 0.006mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,186検体中26検体検出、検出率2.2%、検出範囲0.0002~0.0019mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.0023mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00575mg/Lとなり、これより、水質評価値0.006mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等において比較的高いレベルでの検出がみられることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案して環境基準項目とする。基準値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.006mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.84-90 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○シマジン
1.基準値
0.003mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・白色結晶、水・有機溶剤に難溶、自然環境中で比較的安定、土壌中の移動性小、有機物含有量が小さい土壌では地下浸透の可能性有り
(2)生産量等
(平成2農薬年度)
・原体輸入量259t、国内流通量244.9t
(3)主な用途
・トリアジン系除草剤(野菜、豆類、芝等)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.003mg/L
・水道水質基準(新) 0.003mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.002mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.004mg/L、MCLG 0.004mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,593検体中241検体検出、検出率15.1%、検出範囲0.00002~0.012mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.0013mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00325mg/Lとなり、これより、水質評価値0.003mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案して環境基準項目とする。基準値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.003mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.91-100 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○チオベンカルブ
1.基準値
0.02mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色から淡黄色の液体、比重1.16、融点3.3℃、水に難溶
・水溶解度0.02g/L(20℃)、有機溶媒に可溶
・土壌に吸着されやすい、塩素により易分解
(2)生産量等
(平成2農薬年度)
・原体生産量4,798t、原体輸出量2,504t
(3)主な用途
・チオールカーバメート系除草剤(稲、野菜、豆類等)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・水道水質基準(新) 0.02mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,386検体中195検体検出、検出率14.1%、検出範囲0.000022~0.017 mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI0.009mg/kg/day(食品衛生法に基づく農産物に係る農薬の残留基準設定の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0225mg/Lとなり、これより、水質評価値0.02mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案して環境基準項目とする。基準値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.02mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.206-212 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○ベンゼン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・水より軽い無色液体、揮発性、凝固点5.5℃、沸点80.1℃、水に難溶
・水溶解度1.8g/L(20℃)、有機溶媒に可溶
・土壌吸着性低、有機物の多い土壌には吸着される、生分解は可能、光・空気に対して安定
(2)生産量等
(平成2年度)
・需要実績305,500t
(3)主な用途
・染料、溶剤
・合成ゴム、合成皮革、合成顔料等多様な製品の合成原料
・ガソリン中に1%前後含有
(純ベンゼン生産量の約半分はスチレンモノマーの原料)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ1
・U.S. EPA グループA
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.00066mg/L(飲料水及び水生生物経由)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
546検体中87検体検出、検出率15.9%、検出範囲0.00001~0.0023mg/L
<地下水>
984検体中102検体検出、検出率10.4%、最大値0.0022mg/L
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(IRIS (1990))をもとに、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.01mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性が明らかな物質であり、公共用水域等において比較的広く検出されていることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、環境基準項目とする。基準値としては、IRIS(1990)をもとに発がん性のおそれを考慮して、0.01mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.150-159 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○セレン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁告示第16号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・灰色の光沢のある固体、室温で安定、融点217℃、比重4.8
・主な原子価は-2、+4、+6
・多くの金属、非金属元素としてセレン化物をつくる、平均地殻存在量0.05mg/kg(地域的変動大)、海水濃度0.1μg/L程度
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量470t、輸出量374t、輸入量58t
(3)主な用途
・ガラス、窯業
・半導体材料、光電池、コピー感光体
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ3
(2)各種基準値
・水道水質基準(新) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.01mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.01mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.05mg/L、MCLG 0.05mg/L
・U.S. EPA水質クライテリア(1986) 0.01mg/L(飲料水及び水生生物経由)
・EC MAC 0.01mg/L
・カナダ MAC 0.01mg/L、OG 0.002mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(平成2年度)
<表流水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値0.01mg/L)
282地点中5地点で評価値超過、超過率1.8%
<ダム・湖沼水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値0.01mg/L)
89地点中評価値超過なし
<地下水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値0.01mg/L)
696地点中4地点で評価値超過、超過率0.6%
8.基準値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Longneckerら(1991), Yangら(1983), Jaffeら(1976))をもとに、人に対するNOAEL 0.004mg/kg/dayより、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.01mg/Lとなり、これより、水質評価値0.01mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性が明らかな物質であり、公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、環境基準項目とする。基準値としては、Longneckerら(1991)、Yangら(1983)、Jaffeら(1976)をもとに、0.01mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.280-286 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
1.基準値
10mg/L以下
2.測定方法
硝酸性窒素にあっては日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては日本産業規格K0102の43.1に定める方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第14号
4.基礎情報
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等(要監視項目設定時)
・窒素は土壌には本来含まれず、自然状態の窒素起源は微生物による窒素固定
・環境水中の硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の起源の多くは、肥料、人、動物の排出物
(2)主な用途(環境基準設定時)
・肥料、火薬製造、ガラス製造など
5.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
・現行水道水質基準 10mg/L
・水道水質基準改定案 10mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 10mg/L(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素と分けて設定せず)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 設定の考え方は現行どおり、ただし値としては以下のとおり;50mg/L(NO3換算(=11.3mg-N/L))、3mg/L(NO2換算(=0.9mg-N/L))、各々の測定値とガイドライン値の比の和が1以下
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL及びMCLG 10mg/L(硝酸性窒素)、1mg/L(亜硝酸性窒素) 10mg/L(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)
・EC MAC 50mg/L(NO3換算)、0.1mg/L(NO2換算)、GL 25mg/L(NO3換算)
・カナダ OG 0.001mg/L(硝酸性窒素)、0.001mg/L(亜硝酸性窒素)
6.環境中における検出状況
(平成5年・要監視項目設定時)
(平成2年度)
<表流水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値10mg/L)
804地点中1地点で評価値を超過、超過率0.1%
<ダム・湖沼水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値10mg/L)
221地点中評価値超過なし
<地下水>(水道原水(最高値、出典:水道統計)、評価値10mg/L)
2,761地点中20地点で評価値を超過、超過率0.7%
(平成11年・環境基準設定時)
(平成6~8年度)
<河川>
測定4,263地点、指針値(10mg/L)超過:5地点(0.1%)、10%超過:1,872地点(43.9%)
<湖沼>
測定990地点、指針値(10mg/L)超過:0地点(0%)、10%超過:36地点(3.6%)
<海域>
測定1,634地点、指針値(10mg/L)超過:0地点(0%)、10%超過:80地点(4.9%)
<地下水>
測定5,548地点、指針値(10mg/L)超過:259地点(4.7%)、10%超過:3,224地点(58.1%)
7.基準値の根拠の概要
(平成5年・要監視項目設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
3.水質評価値の算出
USEPA-HAの根拠(Walton (1951))をもとに、乳児に対するメトヘモグロビン症防止の観点より、水質評価値10mg/L(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の合計として定める。)。
(中略)
5.対処方針(案)
水道水質に関する基準では従来より、乳児のメトヘモグロビン症の防止の観点から、Walton(1951)をもとに硝酸性窒素と亜硝酸性窒素との合計値で10mg/L以下と定められている。特に地下水から比較的高いレベルで検出される事例が報告されているが、環境中の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度を抑制するためには窒素化合物の環境中の挙動についてなお知見を集積する必要があることから、当面、要監視項目として位置づけるとともに上記の値を指針値として設定し、水道水源を中心に公共用水域等の監視を行うことが適当と考えられる。
(平成11年・環境基準項目設定時)(答申抜粋)
Waltonら(1951)による硝酸性窒素濃度と乳児におけるメトヘモグロビン血症発生との関連に関する調査結果をもとに、水道水質基準も勘案し、指針値を現行のとおり硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計で10mgN/Lとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準健康項目とする。
なお、定量的評価が定まっていないものの亜硝酸性窒素単独での毒性についても指摘されていることから、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」で環境基準健康項目とすることにより行われるモニタリングの中で亜硝酸性窒素単独での濃度も明らかにし、公共用水域等における亜硝酸性窒素単独での状況の把握に努めることが重要である。
8.参考資料
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・環境庁「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る中央環境審議会答申について」(参考1)環境基準健康項目に追加すべきと提言されている項目について http://www.env.go.jp/press/files/jp/464.html 【NIES保管ファイル】
○ふっ素
1.基準値
0.8mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第14号
4.基礎情報
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等(要監視項目設定時)
・特異臭のある黄緑色気体、液体は淡黄色
・不活性元素を除き全ての元素と直接フッ化物を作る、常温でアルカリ金属、タリウムと反応
・平均地殻存在量625mg/kgと13番目に多い元素、海域にはppmオーダーで存在することが知られている
(2)生産量等(要監視項目設定時)
(平成元年度)
・(フッ化水素酸)生産量237,900t
・(フッ化ナトリウム)生産量約4,400t
・(ケイフッ化ナトリウム)生産量約6,600t
(3)主な用途(環境基準設定時)
・鉄鋼、アルミニウムなどの精錬、ガラス加工、電子工業など
5.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
(1)発がん性評価
・IARC (水道用無機フッ素化合物)グループ3
(2)各種基準値
・現行水道水質基準 0.8mg/L
・水道水質基準改定案 0.8mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 1.5mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 1.5mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準(フッ化物として)MCL 4mg/L、MCLG 4mg/L
・EC MAC 0.7~1.5mg/L
・カナダ MAC 1.5mg/L、OG 1.0mg/L
6.魚介類への濃縮性(要監視項目設定時)
・濃縮性に関する情報なし
7.環境中における検出状況
(平成5年・要監視項目設定時)
(平成2年度)
<表流水>(水道原水(最高値、出典:水道統計))
799地点中評価値超過は1地点、超過率0.1%
<ダム・湖沼水>(水道原水(最高値、出典:水道統計))
217地点中評価値超過は3地点、超過率1.4%
<地下水>(水道原水(最高値、出典:水道統計))
2,752地点中評価値超過は10地点、超過率0.4%
(平成11年・環境基準設定時)
<河川>
測定3,663地点、指針値(0.8mg/L)超過:34地点(0.9%)、10%超過:2,391地点(65.3%)
<湖沼>
測定143地点、指針値(0.8mg/L)超過:0地点(0%)、10%超過:64地点(44.8%)
<海域>
測定663地点、指針値(0.8mg/L)超過:458地点(69.1%)、10%超過:653地点(98.5%)
<地下水>
測定1,750地点、指針値(0.8mg/L)超過:16地点(0.9%)、10%超過:549地点(31.4%)
8.基準値の根拠の概要
(平成5年・要監視項目設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
斑状歯発生の予防の観点より0.8mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
自然界に広く分布する元素であり、人にとって有益な面もあるが、斑状歯を発生させるおそれがあることから、その予防の観点より水道水質に関する基準として従来より0.8mg/L以下に定められており、飲料水として長期的な摂取をする場合の影響に留意することが重要と考えられる。このため、要監視項目として位置づけるとともに上記の値を指針値として設定し、水道水源を中心に公共用水域等の監視を行うことが適当と考えられる。
(平成11年・環境基準設定時)(答申抜粋)
斑状歯発生の予防の観点から、水道水質基準も勘案し、指針値を現行のとおり0.8mg/Lとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、フッ素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されており、海域以外でも指針値を超えるレベルで検出されているところがあることから、環境基準健康項目とする。
なお、海域におけるフッ素は2-3(2)の特例に該当することから、海域には環境基準を適用しないこととする。また、海域以外においても、汽水域において明らかに海水の影響により基準値を超過した場合、その他明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.274-279 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・環境庁「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る中央環境審議会答申について」(参考1)環境基準健康項目に追加すべきと提言されている項目について http://www.env.go.jp/press/files/jp/464.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年3月12日・環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長・水質管理課長「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(環水企第89-2号・環水管第68-2号) http://www.env.go.jp/hourei/05/000060.html 【NIES保管ファイル】
○ほう素
1.基準値
(当初)0.2mg/L
(現行)1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第14号
4.基礎情報
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等(要監視項目設定時)
・黒色のかたい固体、常温空気中では安定、300℃以上で酸化され高温では激しく燃焼、原子価は通常+3価であるがこれに従わないものが多い、比重2.45、融点2,000~2,500℃程度、海水中にはppmオーダーで存在することが知られている
(2)生産量等(要監視項目設定時)
(平成元年度)
・(ほう酸)生産量0t、輸入量27,000t
・(ほう砂(無水ナトリウム塩(Na2B4O7))生産量0、輸入量64,500t(精製ほう砂)
(3)主な用途(環境基準設定時)
・ガラス、陶磁器、ほうろう、メッキ工業など
5.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
(1)発がん性評価
・U.S. EPA グループD
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.2mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.3mg/L
・EC GL 1.0mg/L
・カナダ MAC 5.0mg/L、OG 0.01mg/L
6.魚介類への濃縮性(要監視項目設定時)
・濃縮性は中程度と考えられる。
7.環境中における検出状況
(平成5年・要監視項目設定時)
・我が国での調査事例は収集できなかった。
(平成11年・環境基準設定時)
(平成6~8年度)
<河川>
測定1,089地点、指針値(1.0mg/L)超過:81地点(7.4%)、10%超過:279地点(25.6%)
<湖沼>
測定48地点、指針値(1.0mg/L)超過:1地点(2.1%)、10%超過:3地点(6.3%)
<海域>
測定208地点、指針値(1.0mg/L)超過:207地点(99.5%)、10%超過:207地点(99.5%)
<地下水>
測定503地点、指針値(1.0mg/L)超過:2地点(0.4%)、10%超過:58地点(11.5%)
8.基準値の根拠の概要
(平成5年・要監視項目設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Weirら (1972))をもとに、NOAEL 8.8mg/kg/dayより、不確定係数100として、TDI 0.088mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水料を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.22mg/Lとなり、これより、水質評価値0.2mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性に関する知見、水道水質に関する基準の設定状況を踏まえ、要監視項目とし、今後公共用水域等における水質データの蓄積に努めることとする。その際、自然的原因によるものが存在することに留意する必要がある。指針値としては、Weirら(1972)をもとに、0.2mg/L以下とする。
(平成11年・環境基準設定時)(答申抜粋)
Price(1996)によるラットの生殖毒性試験をもとに、現行の指針値の根拠であるTDI(1日耐容摂取量)0.088mg/kg/dayを0.096mg/kg/dayに変更し、さらに、厚生省が平成6~9年に行ったマーケットバスケット調査(日常摂取する各種の食品(約90種類)を市場(マーケット)より購入し、各々の平均摂取量を試料として、食品経由の各汚染物質のヒトへの暴露量を明らかにする調査)の結果を踏まえて飲料水経由でのほう素の暴露寄与率を40%として、指針値を現行の0.2mg/Lから1.0mg/Lに変更することとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、ほう素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されており、海域以外でも指針値を超えるレベルで検出されているところがあることから、環境基準健康項目とする。
なお、海域におけるほう素は2-3(2)の特例に該当することから、海域には環境基準を適用しないこととする。また、海域以外においても、汽水域において明らかに海水の影響により基準値を超過した場合、その他明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.307-311 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・環境庁「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る中央環境審議会答申について」(参考1)環境基準健康項目に追加すべきと提言されている項目について http://www.env.go.jp/press/files/jp/464.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年3月12日・環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室長・水質管理課長「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(環水企第89-2号・環水管第68-2号) http://www.env.go.jp/hourei/05/000060.html 【NIES保管ファイル】
○1,4-ジオキサン
1.基準値
0.05mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表8に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成16年2月26日中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
(改定:環境基準項目)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第78号
4.基礎情報(環境基準設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:特徴的な臭気のある無色の液体
・比重:1.03(20℃/4℃)
・水への溶解性:水に任意に混和する
・ヘンリー定数:0.29Pa-m3/mol(20℃)
・水と混和するため、水からの揮散に関するデータはない。蒸気圧が小さいため、水の蒸発に伴いある程度は揮散すると思われる。
・水中では加水分解される化学結合はないと考えられており(U.S.NLM; HSDB, 2001)、化審法に基づく好気的生分解性試験(28日間)でも、BOD分解率が0%であり難分解性と判定されている(通商産業省, 1976)。また、下水処理場による除去率も最大で25%であり除去が非常に困難であることが報告されている(庄司ら, 2001)。
・また、化審法に基づく試験結果より生物濃縮性がない又は低いと判定される。コイの42日間のBCFは水中濃度が1mg/L及び10mg/Lにおいて、0.3~0.7及び0.2~0.6であった(通商産業省, 1976)。
・土壌分配係数は小さく、土壌に放出された場合には地下水にまで到達する。蒸気圧が低い(37mmHg、25℃)ため、乾燥土壌からは大気に揮散すると考えられる。大気中ではヒドロキシラジカルとの反応により速やかに分解し、半減期は6.69から9.6時間である。反応生成物は、ケトンやアルデヒドと推定される。ジオキサン/NO系でも同程度の半減期が得られている。
(2)生産量等
(平成19年)
・生産量 4,500 t
(3)主な用途
・合成皮革用・反応用の溶剤、塩素系溶剤の安定剤、洗浄溶剤、医薬品合成原料
5.毒性情報及び各種基準値(環境基準設定時)
・水道水質基準値 0.05mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版一次追補版) 0.05mg/L
6.環境への排出等の状況(PRTR)
(平成16年・要監視項目設定時)
<公共用水域>
(平成13年度)23,200kg、合計:183,034kg
(平成21年・環境基準設定時)
<公共用水域>
(平成19年度)46,169kg(下水道業を除く排出量:46,169kg)、合計:135,508kg
7.環境中における検出状況
(平成16年・要監視項目設定時)
<公共用水域>(指針値 0.05mg/L)
(要調査項目)
(平成12年度)76地点中超過0地点(0.0%) 10%値超過2地点(2.6%)
(化学物質と環境)
(平成4~13年度)347地点中超過1地点(0.3%) 10%値超過16地点(4.6%)
<地下水>
(地下水実態調査)(指針値 0.05mg/L)
(平成2年度)200井戸中超過1井戸(0.5%) 10%値超過9井戸(4.5%)
(要調査項目)
(平成12年度)15井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過0井戸(0.0%)
(平成21年・環境基準設定時)
<公共用水域>(基準値0.05mg/L)
(平成16年度)測定471地点、検出1地点、超過0地点、10%超過1地点
(平成17年度)測定550地点、検出15地点、超過0地点、10%超過6地点
(平成18年度)測定698地点、検出13地点、超過2地点、10%超過10地点
(平成19年度)測定766地点、検出7地点、超過0地点、10%超過6地点
<地下水>(基準値0.05mg/L)
(平成16年度)測定86地点、検出50地点、超過13地点、10%超過43地点
(平成17年度)測定260地点、検出8地点、超過0地点、10%超過2地点
(平成18年度)測定280地点、検出6地点、超過0地点、10%超過1地点
(平成19年度)測定280地点、検出13地点、超過1地点、10%超過5地点
8.基準値の根拠の概要
(平成16年・要監視項目設定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
公共用水域等において指針値の超過が見られるものの限定的な検出状況であること、またその中には汚染原因が不明なものも含まれることから、現時点においては、要監視項目として設定し、公共用水域等の検出状況、1,4-ジオキサンの取扱い状況、環境への排出状況等についての知見の収集に努める必要がある。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.05mg/L)を超過する地点(423地点中1地点、超過率0.2%)、指針値の10%値(0.005mg/L)を超過する地点(423地点中18地点、超過率4.3%)がある(要調査項目存在状況調査、化学物質と環境)。
地下水において、指針値を超過する地点(215地点中1地点、超過率0.5%)及び指針値の10%値を超過する地点がある(215地点中9地点、超過率4.2%)(地下水実態調査、要調査項目存在状況調査)。
イ.指針値
Yamazakiら(1994)のラットを用いた飲水投与試験での肝腫瘍発症率に線形マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量として、指針値を0.05mg/Lとした。
(平成21年・環境基準設定時)(答申抜粋)
(1)平成16年答申において課題としてあげられた事項についての検討(抄)
(中略)
②1,4-ジオキサンについて
ア 基本的な整理
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域水質測定結果によると、平成18年度に2箇所現行の指針値超過事例があり、現行指針値の10%値を超えるものが平成16年度以降毎年ある(1から10個所)。地下水水質測定結果によると、平成16年度に13箇所、平成19年度に1箇所現行指針値超過事例があり、現行指針値の10%値を超えるものが平成16年度以降毎年ある(1から43箇所)。このほか、これまで現行指針値を超える汚染により水道の取水が停止された事例も複数あり、水道の取水停止につながるおそれのあった公共用水域等への流出事例もある。
PRTRデータによると公共用水域への排出量も多く、当該物質の特性を見ると水へ混合しやすく大気への揮発性は低い。また水環境中での分解性も低い。このため、一度排出された場合には大気への揮発や水環境中での分解による濃度低減は生じにくい。
このようなことから、当該物質については健康保護に係る水質環境基準項目および地下水環境基準項目とすべきである。
イ 基準値
現行の要監視項目の指針値として設定している、0.05mg/Lを、健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
(中略)
(2)WHO飲料水水質ガイドライン及び水道水質基準の改定等を踏まえた検討(抄)
(中略)
①1,4-ジオキサンについて
ア 基準値について
WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補におけるガイドライン値の設定根拠は、水道水質基準の改訂の際の検討の根拠と同一の健康影響評価も基にして設定されている。具体的には、同一試験についてマルチステージモデルを使用した手法と、TDIを使用した手法と二通りの評価を行っているが、結果はほぼ等しいとしている。
また、水道水質基準の平成20年の改定の際の検討においては、従前の水道水質基準設定の評価と食品安全委員会による清涼飲料水に係る当該物質の健康影響評価の結果に若干の違いがあるが、同一試験に係る評価方法の違いに起因していることから、当該物質の基準値を変更していない。
以上のことから、従来より要監視項目の指針値として設定していた、0.05mg/Lを、健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
イ 基準値の導出根拠
Yamazakiら(1994)のラットを用いた飲水投与試験での肝腫瘍発症率に線型マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量として、2.1μg/kg体重/日と算定。これに、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.05mg/Lとした。
(以下略)
9.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○ダイオキシン類(水質)
1.基準値
1pg-TEQ/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0312に定める方法
3.設定経緯
平成11年12月10日・中央環境審議会答申
平成11年12月27日・環境庁告示第68号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
ダイオキシン類は、大気、土壌、水域の全ての環境媒体を通じ、摂食、呼吸等により人体に摂取される。また、ダイオキシン類は、各環境媒体への直接の排出のみならず、大気から土壌、土壌から水域といった環境媒体間の複雑な移行により環境濃度が形成されるという特徴を持っている。
環境庁が、平成10年度に行った「ダイオキシン類緊急全国一斉調査」の結果によればダイオキシン類の環境中濃度は、全国平均で大気では約0.23pg-TEQ/m3、土壌では約6.5pg-TEQ/g、公共用水域水質では約0.40pg-TEQ/L、地下水質では約0.081pg-TEQ/L、底質では約7.7pg-TEQ/g-乾重量であり、水生生物では約2.1pg-TEQ/g-湿重量であった。この結果からも、種々の経路を経由した環境媒体や水生生物へのダイオキシン類の移行の状況がうかがわれる。なお、ダイオキシン類は水に溶けにくく、水中では主としてプランクトンや微細粒子に含まれる形で存在する。これらのダイオキシン類が水生生物中に濃縮・蓄積されると考えられることから、水質の測定に際しては、水中に浮遊する微細粒子等に含まれるダイオキシン類も含めて、水質濃度を求めている。
一方、飲料水を含む食品からのダイオキシン類の摂取量は、「食品からのダイオキシンの一日摂取量調査」(平成10年度、厚生省研究班)により明らかにされている。この調査によると、我が国における食品及び飲料水からの平均的なダイオキシン類の摂取量は約2.00pg-TEQ/kg/日であり、このうち魚介類が約1.41pg-TEQ/kg/日を占めている。また、環境媒体からのダイオキシン類の直接摂取量は、環境中の濃度から、大気経由が0.07pg-TEQ/kg/日、土壌経由が0.0084pg-TEQ/kg/日と算出されており、食品からの摂取を合わせると、現時点での日本の合計ダイオキシン類摂取量は平均的にみて2.1pg-TEQ/kg/日程度と推定される。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)各種基準値
○水質環境基準
(ア)米国
i)環境基準
Clean Water Actの下で、水質環境基準については、EPA(環境保護庁)が「クライテリア」を示し、各州が基準を設定する。EPAは、2,3,7,8-TCDDについて次の「クライテリア」を示している;2,3,7,8-TCDD:0.013pg/L。
なお、この値の算定根拠は、TDIに基づくものではなく、10-6の発がんリスクを見込み、飲料水からの直接ばく露経路と魚類への濃縮を経由したばく露経路を考慮している。
EPAの「クライテリア」は各州に対し拘束力を持つものではなく、各州がどのような基準値を設定するかは各州の裁量に委ねられている。
実際上、米国各州が設定している水質環境基準値は、0.0013pg/L(ヴァーモント州など)から20pg/L(ミネソタ州、提案中)まで多様である。
(中略)
(イ)カナダ
カナダでは現在、人の健康の保護の観点からは基準設定がなされていない。しかしながら、カナダ環境保護法に基づく水生生態系保護のための環境ガイドライン案(0.038pg-TEQ/L)が示されている。
なおこの数値は、ニジマス幼生の28日間生長阻害試験の最低影響濃度(LOEL)に基づいており、またPCDD類及びPCDF類のTEQ換算値に適用されるものである。
(ウ)オランダ
オランダでは、地表水についてはダイオキシンの基準はないが、土壌について暫定介入基準値(1000pg-TEQ/g)が設けられているほか、その濃度の土壌と平衡状態にある地下水濃度として、地下水の基準値(1pg-TEQ/L)が設定されている。(これらの値は1997 WHO-TEQを採用しており、従ってCo-PCBまで含んだ値である)
(エ)上記以外の諸国について
上記のほか、オーストラリア、ドイツ、英国、オランダ、イタリア、フランス、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スイス、ニュージーランド、韓国、EUについても調査したが、人の健康の観点から設定された水質環境基準は、いずれの国においても設定されていない。
○耐容一日摂取量(TDI)
・1990年(平成2年)WHO欧州地域事務局専門家会合報告書:10pg/kg/日
・1996年(平成8年)厚生省ダイオキシンのリスクアセスメントに関する研究班:10pg/kg/日
・1997年(平成9年)環境庁ダイオキシンリスク評価検討会:健康リスク評価指針値として5pg/kg/日
・1998年(平成10年)WHO欧州地域事務局・国際化学物質安全性計画(IPCS)専門家会合:1~4pgTEQ/kg/日。当面の最大耐容摂取量は4pgTEQ/kg/日。究極的に1pgTEQ/kg/日未満に低減。
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・ダイオキシン類の水質から生物への濃縮率は、5,000~10,000程度と考えられる。
※濃縮率10,000:PCBの水質環境基準で用いられた濃縮率
濃縮率5,000:平成10年度全国調査データに基づく、水質の全国平均値(0.40pg-TEQ/L)及び水生生物濃度の全国平均値(2.1pg-TEQ/g)の比。米国環境保護庁が2,3,7,8-TCDDのクライテリアで用いたとされる濃縮率
7.環境中における検出状況(設定時)
(平成10年度)
(WHO1997 TEQ(DD+DF))
検体数:204、検出濃度:0~12pg-TEQ/L、算術平均:0.38pg-TEQ/L、中央値:0.089 pg-TEQ/L
(WHO1997 TEQ(DD+DF+Co-PCB))
検体数:204、検出濃度:0.0014~13pg-TEQ/L、算術平均:0.40pg-TEQ/L、幾何平均:0.12pg-TEQ/L、中央値:0.11pg-TEQ/L
8.基準値の根拠の概要(答申抜粋)
3 対象項目及び基準値
(1)対象項目
ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類として、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)が規定されており、同法に基づく水質環境基準は、ここで規定されたダイオキシン類を対象項目とすることが適当である。
なお、同法では環境基準を「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」と規定しており、健康項目の環境基準として設定することが適当である。
(2)基準値
①飲用水としての利用を考慮する基準値の算定
WHOの「飲料水水質ガイドライン」では、TDIが設けられた物質について、水経由の曝露を評価する場合、通常はTDIの10%を飲料水に割り当てるという取り扱いがなされているが、他の媒体を経由した曝露が大きいことが明らかな場合には、TDIの1%が割り当てられている。
WHOのこの一般的な取り扱いに基づき、ダイオキシン類は飲用水以外の経路からの曝露が大きいことを考慮して、TDIの1%を割り当てることとする。平成11年6月に取りまとめられた「ダイオキシン類の耐容一日摂取量(TDI)」(中央環境審議会、生活環境審議会及び食品衛生調査会)に基づきTDIを4pg-TEQ/kg/日とすると、体重50kgの人が1日当たり2Lの水を飲むとして、水質の基準値は1pg-TEQ/Lとなる。
②生物濃縮の観点からの検証・評価
ダイオキシン類の摂取は、生涯にわたり、また、種々の食品・媒体からの摂取を通じ、全体としてTDIの範囲内であることが重要であることを考慮すると、各水域での要求水質は、少なくとも平均的に見てTDIに対応した内海魚のダイオキシン類濃度を確保するものである必要がある。
魚介類を平均の1.5倍量摂食している人について安全性が要求される魚介類の平均濃度を試算し、生物濃縮係数を10,000倍、5,000倍程度と仮定して魚介類濃度から水質濃度を求めると、要求される水質の平均濃度は各々0.27pg-TEQ/L、0.54pg-TEQ/L程度となる(※)。
一方、我が国の公共用水域の水質濃度は、平成10年度ダイオキシン類緊急全国一斉調査によると、全国平均として約0.40pg-TEQ/Lであるが、現在水質濃度が1pg-TEQ/Lを超える水域について、環境基準の設定に伴い対策が行われ、その水質が全て1pg-TEQ/L以下に改善されるとすれば、公共用水域の平均水質濃度は0.27pg-TEQ/L以下となる。
ダイオキシン類について、魚介類経由の摂取を考慮し、生物濃縮率から本格的に水質環境基準を求めるには種々の科学的知見が不足しているが、現時点で得られる知見に基づき、いくつかの仮定を置いた試算から求められる平均的な要求水質濃度と水質環境基準により達成される平均的な水質濃度レベルは、概ね対応する水準になるものと考えられる。
なお、平均量の魚介類を摂食する人について同様の試算を行うと、要求される公共用水域の平均水質濃度は、0.45pg-TEQ/L、0.90pg-TEQ/L程度となり、現状の平均水質は、これらの値より低濃度となっている。
③環境基準の値
以上を勘案し、ダイオキシン類の水質環境基準値は、1pg-TEQ/Lとすることが適当である。
※:平成10年度の調査を基にした国民の平均的ダイオキシン類摂取量約2.1pg-TEQ/kg/dayのうち、魚介類からの摂取量は1.41pg-TEQ/kg/dayであるが、ダイオキシン類の各摂取経路への分配割合が一定と仮定すると、TDIの4pg-TEQ/kg/dayに対応する魚介類経由の摂取量は、2.7pg-TEQ/kg/dayであり、これを体重50kgの人で見ると、魚介類から1日あたり135pg-TEQのダイオキシン類の摂取となる。
・国民は1日あたり平均70pg-TEQのダイオキシン類を魚介類から摂取しているが、そのうち概ね既存文献データに基づき、1/3を外海魚から、2/3を内海魚(内海、内湾魚及び沿岸魚)から摂取していると想定する。また、厚生省データにより魚介類の摂食重量は、1日当たり平均100gであり、そのうち外海魚が3/4、内海魚が1/4を占めると想定する。
・魚介類を平均の1.5倍量摂食している人(内海魚・外海魚をともに平均的な魚種構成・産地とする)の場合、外海魚のダイオキシン類濃度は一定と考えると、外海魚から35pg-TEQ/dayを摂取していることになり、内海魚からの摂取は差し引き100pg-TEQ/dayとなる。
・魚介類1.5倍摂食者のTDIに対応する内海魚の平均的ダイオキシン類濃度はこれを内海魚の摂食重量(平均の1.5倍で37.5g/日)で除して求めると2.7pg-TEQ/gとなり、ダイオキシン類の水質から生物への濃縮率を10,000(PCBの水質環境基準で用いられた濃縮率)、5,000(平成10年度全国調査データに基づく、水質の全国平均値(0.40pg-TEQ/L)及び水生生物濃度の全国平均値(2.1pg-TEQ/g)の比を取ると、2.1×1000/0.40≒5000、米国環境保護庁が2,3,7,8-TCDDのクライテリアで用いたとされる濃縮率)と仮定し、要求平均水質濃度を求めると10,000の場合0.27pg-TEQ/L、5,000の場合0.54pg-TEQ/Lとなる。ここで仮定した生物への濃縮率は、食習慣等を踏まえた「見かけ」の濃縮率というべきものである。
・なお、ここでは基準検証のため、一定の魚介類多食者を想定したものであるが、個人的なレベルではより極端な摂取の偏りもあり得ることについて留意する必要がある。
4.適用のあり方
ダイオキシン類の水質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響等も考慮する必要があることから、これまでの健康項目に係る水質環境基準と同様に、河川、 湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当である。
(以下略)
9.参考資料
・平成11年12月10日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について(答申)」(別添1)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=1398&hou_id=1904 【NIES保管ファイル】
○ダイオキシン類(水底の底質)
1.基準値
150pg-TEQ/g以下
2.測定方法
「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(平成21年3月環境省水・大気環境局水環境課)」に掲げる方法
3.設定経緯
平成14年6月24日・中央環境審議会答申
平成14年7月22日・環境省告示46号
4.基礎情報(設定時)
(略)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(略)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
(略)
7.環境中における検出状況(設定時)
(平成11年度調査結果)
平成11年度、環境庁は全国の公共用水域等の水質、底質、水生生物及び地下水質のダイオキシン類の調査を行った。各都道府県毎に環境基準点を基本とし、各10地点程度を選定し、底質については全国で542地点で調査を行った。
その結果、ダイオキシン類濃度の平均値は5.4pg-TEQ/g、濃度範囲は0.066~230pg-TEQ/gであった。
(平成12年度常時監視結果)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、都道府県知事及び同法の政令市の長は、大気、水質(底質を含む)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告することとされている。
平成12年度の公共用水域の底質調査は、全国1,836地点で行われた。これらの調査地点は公共用水域の水質調査地点と同一地点を原則としつつ、都道府県及び政令市により水域を代表する地点等として選定された。
常時監視の結果、ダイオキシン類濃度の平均値は9.6pg-TEQ/g、濃度範囲は0.0011~1,400pg-TEQ/gであった。
公共用水域の底質については、平成11年度と比較し、平均値が高くなっていたが、これは、一部の調査地点が、これまでの調査の結果からダイオキシン類汚染が明らかとなった地点を考慮して選定されていることも影響していると考えられる。
8.基準値の根拠の概要(答申抜粋)
2.底質環境基準の必要性
底質中ダイオキシン類については、生物濃縮による魚への取り込み、水への巻き上げ及び溶出が考えられるが、他方、環境媒体の中でダイオキシン類に係る環境基準及び対策のための数値基準が設定されていないのは底質だけである。
一方、平成11年度に環境庁が実施した調査において、底質のダイオキシン類濃度と当該地点で採取された魚介類中のダイオキシン類濃度との間には、相関係数は小さいものの、有意な正の相関が認められる。このため、環境基準を設定し対策を実施することにより、底質濃度が低減されれば、魚介類ダイオキシン類濃度の低減が期待できる。我が国におけるダイオキシン類摂取の状況をみると、魚介類からの取り込みが全体の約75%を占めており、魚介類中のダイオキシン類濃度の低減により、人の摂取量の低減が期待できる。
また、底質は絶えず水に接触しており、ダイオキシン類に汚染された底質は、水への巻き上げ及び溶出により、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっている。この観点からも、底質環境基準を設定し、対策を実施することが必要である。
3.底質環境基準の性格
現在、ダイオキシン類については、大気、水、土壌といった各媒体毎に環境基準が設定され、かつ、排出規制が実施されているところ、これら規制により、発生源からの発生負荷量は低減してきている。このため、公共用水域の底質に供給されるダイオキシン類はここ数年で大幅に減少し、更に今後とも減少していくことが予想される。
また、水への巻き上げ及び溶出、魚類の摂食等による取り込みが懸念される底質表層部分の濃度については、コアサンプルのデータを見ると近年下がる傾向にあり、規制の進展により今後更に低減することが期待される。
このため、ダイオキシン類について、人の健康を保護するための行政目標として底質環境基準を設定するにあたり、まず勘案すべき事象は、現存する汚染底質の対策である。かかる観点から、ダイオキシン類の底質環境基準については、汚染底質について対策を講じるための数値基準として設定することが適当である。
4.基準値
(1)基本的考え方
底質中ダイオキシン類が人の健康に影響を及ぼす恐れは、魚介類への取り込み並びに底質から水への巻き上げ及び溶出の2つの影響経路からが考えられる。
①魚介類への取り込みを考慮する方式について
ダイオキシン類については国民摂取実態から魚介類を経由した摂取が多いことが既知の事実であり、また、平成11年度に環境庁が行った調査では、底質中ダイオキシン類濃度と魚介類中ダイオキシン類濃度との関係においては、相関係数が小さいながらも有意な正の相関があることが分かっている。
他方、ダイオキシン類については、国民の平均的なダイオキシン類摂取量が耐容一日摂取量(Tolerable Daily Intake。以下「TDI」という。)に比較して小さく、バランスのとれた食事が大切と整理されている。また、食品としての魚介類の許容上限値が定められていない。
このため、現時点では、対策実施のための底質環境基準の設定において、基準値導出に必要な諸条件が不足しており、この観点から数値を設定することは困難な状況にある。
②水への影響を考慮する方式について
底質中ダイオキシン類は、ダイオキシン類の水への供給源(汚染源)となっており、その影響の程度を勘案して設定するという方式については、底泥中の間隙水の濃度に着目して底質濃度を規定する分配平衡法と、実際にダイオキシン類に汚染された底泥を用いて水への振とう分配試験を行い、水質への影響を考慮する方法の2種類がある。他にも様々な手法が考えられるが、現時点でデータが得られており、算定が可能な手法として、本報告では、これら両者の手法を勘案して環境基準値を設定することとした。
(2)設定手法
①分配平衡法
底質の間隙水中の化学物質濃度は底質の固相における濃度と平衡状態を形成しており、底質固相の濃度は底質の有機物濃度によって変動する。つまり、平衡条件下にある底質と水との間の化学物質の分配係数は、①固相中濃度と間隙水濃度との比、及び②有機炭素と水との分配係数と、底質の有機炭素の割合との積、の2つの方法で表すことができる。模式的には、下記の(1)式の様に書くことができる。
Kp = Cs/Cd = foc・Koc (1)
Kp:底質中、固相と間隙水の分配係数
Cs:固相の化学物質濃度
Cd:間隙水中の化学物質濃度
foc:有機炭素割合(%)
Koc:有機炭素と水との分配係数(cm3/g-org.C)
logKocは、logKow(オクタノール-水分配係数)を変数として換算式から算定することができる。換算式としては複数の学説があるが、本報告では、①PCBのlogKowの値を主に解析しており、②諸外国で底質基準値を水質環境基準値から導出する際に実際に用いられている、下記の式を用いるものとした。
logKoc = 1.03×logKow-0.61
logKowの値は、ダイオキシン類の異性体ごとに異なっており、概ね6~8であるが、本報告では、米Federal Register(1995年3月23日付)に掲載された、栄養連鎖上、濃縮係数が最も大きいとされるlogKowの数値である6.9を用いるものとする。
logKoc = 6.50
(1)式は下記の様に書くことができる。
(Cs×(1/foc))/Cd = Koc (2)
間隙水濃度に水質環境基準値である1pg-TEQ/L(1×10-3pg-TEQ/mL)、有機炭素濃度を5%(同手法を用いる独仏と同じ数値)とし、代入すると、
Cs = 157 pg-TEQ/g
となり、概ね、150pg-TEQ/gとなる。
※平成11年度に環境庁が実施した調査結果では、例えば、東京湾の調査地点(20地点)の底質に含まれるダイオキシン類について、異性体ごとに毒性等量換算後の重み付けをして計算したところ、logKowの数値の範囲は6.9~7.2であった。
※間隙水濃度については、底質からの水への移行のみを考えた場合に水質濃度は底質間隙水濃度を超えないこと、また、底生生物への影響を考慮し、水質環境基準濃度とした。
②振とう分配試験結果
高濃度のダイオキシン類を含む底質からの、水質への巻き上げ及び溶出の程度を把握するため、平成13年度に環境省において高濃度の底泥の振とう分配試験を実施し、その結果を検討した。
試験対象底泥として、国内の海域及び河川からそれぞれ2検体を採取し、振とう分配試験を行い、試験水中のSS濃度を通常状態まで低減させた場合を計算した。この結果、試験水濃度が水質環境基準である1pg-TEQ/Lに対応する底質濃度の全試験結果の平均値は196pg-TEQ/gであった。
(3)数値
(2)①及び②の結果を比較すると、②の振とう分配試験結果から導出した数値は、①の分配平衡法で導出した値と比較して大きい数値である。一方、振とう分配試験結果の解析は現時点で得られているデータに基づくものであり、多様な底泥の全てを代表しているとは断言できないことを勘案し、①及び②の結果から、ダイオキシン類の底質環境基準値は150pg-TEQ/gとすることが適当である。
(4)一日摂取量との関係
ダイオキシン類については、食品としての魚介類の許容上限値が定められていないが、他方、国民の平均的なダイオキシン類摂取量については毎年調査が実施されていることから、これらの結果を用いて、本報告で提案する底質環境基準値まで対策を実施した場合の、ダイオキシン類の一日摂取量の試算を行った。
平成12年度におけるダイオキシン類常時監視結果から、底質150pg-TEQ/g以上の濃度地点について、提案している基準値150pg-TEQ/gまで濃度を低減させた場合、全体の底質濃度の平均値は、計算上、現行の9.6pg-TEQ/gから7.8pg-TEQ/gとなる。
魚介類摂取量のうち、内海魚及び外海魚のダイオキシン類の平均濃度を平成10~12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告及び野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告から計算する。更に、内海魚と外海魚の摂取割合を仮定し、また、内海魚からの摂取量が底質濃度の低減に比して低減すると仮定した場合の、魚介類を経由したダイオキシン類の平均一日摂取量を計算、この結果から、食品経由でのダイオキシン類の平均一日摂取量を推定すると、1.7pg-TEQ/kg/dayとなる。
※これらの計算には下記の数値を用いた。
①内海魚及び外海魚平均濃度
平成10~12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告における野菜、魚介等個別食品中ダイオキシン類濃度等に関する調査研究報告に示された個別食品毎の濃度結果から計算し、内海魚平均2.0pg-TEQ/g、外海魚平均1.2pg-TEQ/gとした。この場合、摂取重量割合を勘案した平均値は1.4pg-TEQ/gとなる。なお、平成10~12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告によれば、魚介類からの摂取量は71pg-TEQ/dayであり、単純に魚介類一日摂取重量の3カ年平均値でこの数値を除すと、0.74pg-TEQ/gとなる。
②内海魚と外海魚の摂取重量割合
内海魚4分の1、外海魚4分の3とした。
③1日魚介類平均摂取量
平成9~11年国民栄養調査結果から、平均96gとした。
④体重
50kgとした。
⑤魚介類からのダイオキシン類の摂取割合
平成12年度ダイオキシン類の食品経由総摂取量調査研究報告から、76%とした。
5.適用
ダイオキシン類の底質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、間接的に飲料水及び魚介類経由の食物摂取による影響を考慮する必要があることから、他の健康項目同様、河川、湖沼、海域を問わず、全公共用水域に適用することが適当である。
9.参考資料
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/020626b-4.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表1 (参考)平成11年度公共用水域における底質及び水生生物のダイオキシン類濃度調査結果 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_13.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表2 平成12年度ダイオキシン類環境測定結果(公共用水域 底質)の濃度分布 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_14.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表3 ダイオキシン類の人暴露の経路と、環境基準・対策基準の設定状況 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_15.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表4 ダイオキシン類の排出総量の推移 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_16.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表5 平成10年度ダイオキシン類コアサンプリング調査(年代別ダイオキシン類測定)結果について https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_17.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表6 宍道湖の年代別ダイオキシン類濃度 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_18.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表7 生物湿重量ベース(全体)-底質のダイオキシン類散布図 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_19.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表8 ダイオキシン類異性体とKowの値 https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_2021.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表9 Trophic Level 2,3,4におけるFood-Chain Multiplies(食物連鎖乗数) https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_22.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)図表10 振とう分配試験の結果について https://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_232425.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成14年6月24日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁のうち水底の底質の汚染に係る環境基準の設定等について(答申)」(参考資料)ダイオキシン類一日摂取量の試算に用いた諸元 http://www.env.go.jp/council/toshin/t093-h1403/sanko_26.pdf 【NIES保管ファイル】
④要監視項目及び指針値(一覧)(令和3年10月7日現在)
| 項目 | 指針値 | 通知日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| トランス-1.2-ジクロロエチレン※ | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/L以下 | 平成16年3月31日 | 改定 |
| イソキサチオン | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ダイアジノン | 0.005mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| イソプロチオラン | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| プロピサミド | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| EPN | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | 当初有機燐として環境基準項目→要監視項目に変更 |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| クロルニトロフェン(CNP) | - | 平成6年3月15日 | 改定(指針値削除) |
| トルエン | 0.6mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| キシレン | 0.4mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ニッケル | - | 平成11年2月22日 | 改定(指針値削除) |
| モリブデン | 0.07mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| アンチモン | 0.02mg/L以下 | 平成16年3月31日 | 当初設定→指針値削除→再設定 |
| 塩化ビニルモノマー※ | 0.002mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| 全マンガン | 0.2mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| ウラン | 0.002mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下(暫定)(PFOSとPFOAの合計値) | 令和2年5月28日 |
※トランス-1.2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーについては、地下水に関して、平成21年に環境基準項目に定められている(トランス-1,2-ジクロロエチレンはシス体と合わせた1,2-ジクロロエチレンとして定められており、塩化ビニルモノマーは平成28年にクロロエチレンと名称変更されている。)。その他の項目は地下水についても要監視項目とされている。
⑤項目ごとの指針値及び設定根拠
○クロロホルム
1.指針値
0.06mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の液体、水溶解度8.2g/L(20℃)、高揮発性で特有の臭い、麻酔作用、土吸着性低
・光によりゆっくり分解、容易に地下に浸透、生分解性不明
・浄水処理や排水処理により非意図的な生成もみられる
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量37,000t(推定) 輸出量185t 輸入量30,965t
(3)主な用途
・フッ素系冷媒であるクロロジフルオロメタンの原料、麻酔剤、消毒剤、溶剤
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2(総トリハロメタンとして)
(2)各種基準値
・現行水道水質基準 0.10mg/L(総トリハロメタンとして)(通知)
・水道水質基準改定案 0.06mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) 0.03mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.2mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.1mg/L(総トリハロメタンとして)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
66検体中37検体検出、検出率56.1%、検出範囲0.00001~0.024mg/L
<地下水>
1,093検体中83検体検出、検出率7.6%、最大値0.015mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Jeorgensonら (1985))をもとに、体表面積修正を採用し、リスク外挿法線形多段階モデルによるライフタイム70年に対する発がんリスク10-5の評価より、水質評価値0.06mg/L(WHOは体表面積修正を非採用)。
(中略)
8.対処方針(案)
塩素消毒の副生成物として人体に取り込まれるおそれがあることから、水道水質に関する基準の中では基準項目とされている。この物質自体としても広く生産・使用されており、公共用水域等においても検出されていることから、有機塩素系化合物として何らかの対応が必要と考えられるが、検出レベルは比較的低いことから、要監視項目として設定する。指針値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Jeorgensonら(1985)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.06mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.27-34 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○トランス-1,2-ジクロロエチレン
1.指針値
0.04mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:特徴的な臭気のある、無色の液体
・比重:1.26(20℃)
・水への溶解性:6.3g/L(25℃)
・ヘンリー定数:950Pa-m3/mol(25℃)
・当該物質は1,2-ジクロロエチレンから塩化ビニルモノマーや1,1-ジクロロエチレンを製造する過程での副生成物であり、触媒や製造条件によりシス体とトランス体の比率が異なる。
・主に光化学反応的にヒドロキシルラジカルを生成する反応によって大気中から除去される。推定半減期は、シス及びトランス異性体について、それぞれ8.3日、3.6日である。表流水中と表土中のほとんどは、揮発すると考えられる。また、この化合物は、表面下の土を浸透して地下水に達する可能性がある。
・1,2-ジクロロエチレンは、水中で安定であるとの報告がある(日本環境管理学会, 2004)。化審法に基づく好気的生分解性試験(クローズドボトル法、28日間)では、被験物質濃度が2.32mg/L及び6.06mg/Lの条件において、BODによる分解率は0%であり、難分解性と判定されている(通商産業省, 1990)。また、嫌気的な条件下では生分解され難いが長期間の誘導期間の後に生分解される可能性があると評価されている(NITE&CERI初期リスク評価書, 2008)。
・生物蓄積性についてはオクタノール/水分配係数(logPow)が1.92(実測値)であることから、化審法に基づく濃縮性試験では、濃縮性がない、または低いと判定されている(通商産業省, 1990)。
・嫌気性生物分解によって、地下水から両異性体が除去される可能性があり、そのときの半減期は13~48週程度である。
(2)生産量等
不明
(3)主な用途
・カフェイン・香料など熱に敏感な物質の抽出溶剤、ワックス、アセチルセルロースなどの溶剤
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準改定案 0.04mg/L(水質管理目標設定項目目標値)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版) 0.05mg/L(シス及びトランスの和として)
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.1mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(見直し検討時)
<公共用水域>(平成19年度)
(トランス体)40kg(下水道業を除く排出量:40kg)、合計:10,627kg
(シス体)3,414kg(下水道業を除く排出量:342kg)、合計:3,762kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
602検体中3検体検出、検出率0.5%、検出範囲0.00001~0.004mg/L
<地下水>
1,093検体中52検体検出、検出率4.8%、最大値0.016mg/L
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.04mg/L)
(平成16年度)測定978地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成17年度)測定982地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成18年度)測定935地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成19年度)測定957地点、検出3地点、超過0地点、10%超過0地点
<地下水>(基準値0.04mg/L)
(平成16年度)測定891地点、検出18地点、超過1地点、10%超過7地点
(平成17年度)測定911地点、検出17地点、超過1地点、10%超過8地点
(平成18年度)測定1,007地点、検出23地点、超過0地点、10%超過13地点
(平成19年度)測定995地点、検出26地点、超過0地点、10%超過17地点
9.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Barnesら (1985))をもとに、NOAEL 17mg/kg/dayより、不確実係数1,000(短期実験を考慮)として、TDI 0.017mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0425mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベルが比較的低いことから、要監視項目とする。指針値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Barnesら(1985)をもとに0.04mg/Lとする。
なお、この物質はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどから環境中において生成されると言われており、その挙動について引き続き知見の集積に努める必要がある。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
ア 基本的な整理
公共用水域における各異性体の平成10年度以降の自治体の測定による検出状況は、シス及びトランス両異性体とも環境基準値等を超えるものはないが、シス体は環境基準値の10%の値を超過する検出が数箇所で毎年見られている一方で、トランス体は指針値の10%の値の超過も見られていない。
PRTRによる公共用水域への排出量(平成13年度から平成19年度)が、シス体で3,414から7,461kg/年(下水道からの排出量を除く場合、113から514kg/年)、トランス体で10から40kg/年で推移しているが、現在、両異性体ともに意図された製造はほぼ行われておらず、他の化学物質を製造する際に副生成されているものが主と考えられる。
一方、シス体が検出された箇所でトランス体の測定を同時に行っている箇所は数箇所しかないが、それらの箇所でシス体及びトランス体それぞれの濃度を足し合わせてもシス体の現行基準値あるいはトランス体の現行指針値である0.04mg/Lを超えるものはない。
なお、副生成される過程でのシス体、トランス体別の生成割合は不明であるが、両者の生成過程が同じであることを考えれば、シス体が基準値の10%を超えて検出された地点では、トランス体が検出される可能性は完全には否定できない。少なくともシス体が基準値の10%を超えて検出された地点でのトランス体の監視の強化を図るべきである。
地下水においては、地下水水質測定結果によれば、シス体は過去5年間毎年超過が見られ、トランス体は過去5年間で平成16年度及び平成17年度にそれぞれ1箇所の超過が見られる。基準値等の10%を超える検出はシス体、トランス体共に毎年継続して確認されている。
地下水における1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)はトリクロロエチレン等が嫌気性条件下にある地下水中で分解して生成した可能性があり、トランス体が存在する場合には、多くの場合シス体も存在する状況が見られる。また同一地点同サンプルのシス体及びトランス体の測定結果において、異性体個別では基準値及び指針値を超えないものの、両異性体の和が0.04mg/Lを超える箇所が過去5年間で3箇所あった。
以上のことから、公共用水域においては今後とも、シス-1,2-ジクロロエチレンについては健康保護に係る水質環境基準項目としトランス-1,2-ジクロロエチレンについては要監視項目とする必要がある。一方、地下水においては、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を地下水環境基準項目とすべきである。これに伴い、トランス-1,2-ジクロロエチレンについては地下水に関する要監視項目から削除すべきである。
イ 基準値について
地下水環境基準値はWHO飲料水水質ガイドライン第3版及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、シス体及びトランス体の和で0.04mg/Lとすることが適当である。なお、公共用水域における基準項目であるシス体の基準値及び要監視項目であるトランス体の指針値は引続き0.04mg/Lとすることが適当である。具体的な導出根拠は以下のとおり。
ウ 基準値の導出根拠
Barnesら(1985)のマウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験による雄マウスの血清中酵素の増加等を根拠としたNOAEL 17mg/kg/dayから不確実係数1,000(短期実験を考慮)を適用して、TDI 0.017mg/kg/dayと算定した。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.04mg/L以下とした。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.86-91 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,2-ジクロロプロパン
1.指針値
0.06mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・水より重い無色の液体、揮発性、沸点95℃程度、疎水性で水に難溶、水溶解度2.7g/L(20℃)、有機溶媒に可溶、自然発生源はない
・生分解性・土壌吸着性殆どなく地下水に移行しやすい、大気中では光分解可能
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量2,266t
(3)主な用途
・溶剤、テトラクロロエチレン・四塩化炭素の原料
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ3
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.06mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.02mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.005mg/L、MCLG Zero mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
606検体中26検体検出、検出率4.3%、検出範囲0.00001~0.002mg/L
<地下水>
934検体中9検体検出、検出率1.0%、最大値0.033mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Brucknerら (1989))をもとに、LOAEL 100mg/kg/dayより不確定係数3,000(発がん性、LOAEL使用、毒性データ不足を考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.0238mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0595mg/Lとなり、これより、水質評価値0.06mg/L(WHOでは不確定係数10,000で算定)。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベルが比較的低いことから、要監視項目とする。指針値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、Brucknerら(1989)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.06mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.132-138 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○p-ジクロロベンゼン
1.指針値
(当初)0.3mg/L以下
(現行)0.2mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:強い臭気のある無色~白色の結晶
・比重:1.2
・水への溶解性:溶けない
・環境中での挙動:ジクロロベンゼン類は有機物量が多い土壌に強く吸着すると考えられ、地下水へほとんど移行しないと思われる。土壌中では好気的条件で徐々に生物分解される。土壌表面では主に揮発が起こると思われる。水中でのジクロロベンゼン類は主に堆積物への吸着と水生生物への生物蓄積により減少すると考えられる。表流水では、加水分解、酸化あるいは光分解ではなく蒸発が重要である。ジクロロベンゼン類は馴化された微生物により好気的条件の水中で生物分解される。しかし、湖沼堆積物あるいは地下水中のような嫌気的条件では生物分解されないと考えられる。
(2)生産量等
不明
(3)主な用途
・染料中間物、殺虫剤、有機合成、調剤、防臭剤、農薬
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・水道水質基準改定案 0.3mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(第2版) 0.3mg/L
・WHO飲料水水質ガイドライン(第3版ドラフト) 0.3mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.075mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
<公共用水域>
(平成13年度)1,336kg、合計:100,985kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
(昭和63年~平成4年度)
<公共用水域>
521検体中108検体検出、検出率20.7%、検出範囲0.00001~0.002mg/L
<地下水>
984検体中65検体検出、検出率13.8%、最大値0.07mg/L
(平成16年・改定時)
(平成6~13年度)
<公共用水域>(新たな指針値0.2mg/L)
(要監視項目)6,001地点中超過0地点(0.0%) 10%値超過0地点(0.0%)
<地下水>(新たな指針値0.2mg/L)
(要監視項目)1,955井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過0井戸(0.0%)
9.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(NTP (1987))をもとに、LOAEL 150 mg/kg/dayより、不確定係数1,000(発ガン性、LOAEL使用考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.107mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.268mg/Lとなり、これより、水質評価値0.3mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベルが比較的低いことから、要監視項目とする。指針値としては、水道水質に関する基準の検討状況を勘案し、NTP(1986)をもとに発がん性のおそれを考慮して0.3mg/L以下とする。
(平成16年・改定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
従来の指針値0.3mg/LをNaylorら(1996)の知見をもとに0.2mg/Lに見直すべきである。変更する指針値に基づいた場合においても公共用水域等の検出状況から見て従来通り要監視項目とすることが適当である。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.2mg/L)及び指針値の10%値(0.02mg/L)を超過する地点はない(要監視項目調査結果)。
地下水において、指針値及び指針値の10%値を超過する地点はない。(要監視項目調査結果)。
イ.指針値
Naylorら(1996)のビーグル犬を用いた経口投与試験で、肝毒性を根拠にしたNOAEL 10mg/kg/dayに不確実係数100を適用して、1週間5日投与を考慮してTDIは0.0714mg/kg/dayとなる。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayから、新たな指針値を0.2mg/Lとした。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.117-125 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
○イソキサチオン
1.指針値
0.008mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・微黄色の液体、水に難溶、有機溶媒に易溶、アルカリに対して不安定、大気への揮散小、土壌中の半減期15~40日程度
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量267t 原体輸出量18t 国内流通量189t
(3)主な用途
・殺虫剤(稲、ミカン、とうもろこし、りんご等)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.008mg/L
・水道水質基準改定案 0.008mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,314検体中42検体検出、検出率3.2%、検出範囲0.0003~0.0022mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.003mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0075mg/Lとなり、これより、水質評価値0.008mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域における検出レベルが比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.008mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.28-34 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○ダイアジノン
1.指針値
0.005mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・純品:無色の液体、工業用品:淡黄赤色透明液体
・水難溶度0.040mg/L(20℃)、アセトン・エーテル・ベンゼン・キシレンに易溶、強いアルカリで加水分解、酸性で徐々に分解、大気に揮散、土壌吸着小、水系への流出可能性有り
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量2,399t 原体輸出量1,842t 原体輸入量280t
(3)主な用途
・有機燐系殺虫剤(比較的毒性が低く広範囲な害虫に有効)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.005mg/L
・水道水質基準改定案 0.005mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,969検体中70検体検出、検出率3.6%、検出範囲0.000009~0.0038mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.002mg/kg/day(食品衛生法に基づく農産物に係る農薬の残留基準設定の際の評価及びThe Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives;JECFAの評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.005mg/Lとなり、これより、水質評価値0.005mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において検出されているが、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.005mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.35-43 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○フェニトロチオン(MEP)
1.指針値
0.003mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・原体:黄褐色油状液体(純度95%)、精製品:淡黄色、水に難溶
・アルコール、エーテル、芳香族炭化水素に可溶、脂肪族炭化水素に難溶
・酸性に安定、アルカリ性に比較的不安定、生分解性有り、土壌中での残留性小、水中での残留性無
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量7,232t 原体輸出量4,210t
(3)主な用途
・有機燐系殺虫剤(稲、果樹、野菜、豆類、茶、一般樹木、山林等)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.01mg/L
・水道水質基準改定案 0.003mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,903検体中71検体検出、検出率3.7%、検出範囲0.0007~0.0022mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.005mg/kg/day(食品衛生法に基づく農産物に係る農薬の残留基準設定の際の評価及びJECFAの評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を2%とすると、計算値0.0025mg/Lとなり、これより、水質評価値0.003mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において検出されているが、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.003mg/L以下とする。
(平成11年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成5年に設定した指針値0.003mg/Lと公共用水域等における検出状況を比較すると、公共用水域等における検出率は比較的低く、指針値超過地点は1地点であり、農薬による影響は時期が限られていることを考慮して環境基準健康項目には移行しないが、引き続き要監視項目として年間を通した濃度が適切に評価されるようにモニタリングを行う必要がある。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.50-64 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○イソプロチオラン
1.指針値
0.04mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・白色結晶性の粉末、水に難溶、有機溶媒に易溶、環境水中では比較的安定、物理的に土壌に吸着、低温ほど高吸着、土中に長く残留
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量717t 原体輸出量23t
(3)主な用途
・ケテンジチオアセタール系の殺菌剤(稲のイモチ病等)、制虫剤(ウンカ類)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.04mg/L
・水道水質基準改定案 0.04mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,700検体中182検体検出、検出率10.7%、検出範囲0.00001~0.0076mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.016mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.04mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域における検出レベルが比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.04mg/L以下とする。
(平成11年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成5年に設定した指針値0.04mg/Lと公共用水域等における検出状況を比較すると、公共用水域等での検出率は比較的低く、検出レベルも比較的低いことから、環境基準健康項目には移行せずに引き続き要監視項目とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.65-74 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○オキシン銅(有機銅)
1.指針値
0.04mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・黄緑色の粉末、水・有機溶媒に難溶、熱に安定、土中の懸濁物とともに水系にでる可能性有り、光に対して安定
(2)生産量等
(平成元年度)
・原体生産量457t 原体輸出量560t
(3)主な用途
・殺菌剤(果樹、野菜、花等の糸状菌病)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.04mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,156検体中14検体検出、検出率1.2%、検出範囲0.000016~0.016mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.017mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0425mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
水道水質に関する基準には含まれていないが、公共用水域における検討状況を勘案して、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.04mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.44-49 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○クロロタロニル(TPN)
1.指針値
(当初)0.04mg/L以下
(現行)0.05mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁水質保全局長通知(環水企第58号・環水管第49号)
4.基礎情報(当初設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・白色結晶、水に難溶、水溶解度0.0006g/L(25℃)、酸性から中性域で安定、アルカリ性領域でゆっくり分解、光・紫外線に安定、微生物により分解可能
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量4.387t 原体輸出量2,705t
(3)主な用途
・アリルニトリル系の殺菌剤(適用広範で茎葉散布、土壌灌注、ハウス内のくん煙、くん蒸等)
5.毒性情報及び各種基準値(当初設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.04mg/L
・水道水質基準改定案 0.04mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(当初設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,614検体中12検体検出、検出率0.7%、検出範囲0.000005~0.011mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.015mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0375mg/Lとなり、これより、水質評価値0.04mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域における検出レベルが比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.04mg/L以下とする。
(平成11年・改定時)(答申抜粋)
平成5年の指針値策定以後、農薬登録保留基準改正に当たりADI(1日許容摂取量)が0.015mg/kg/dayから0.018mg/kg/dayに変更されたことを踏まえ、指針値を0.04mg/Lから0.05mg/Lに変更する。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.75-83 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○プロピサミド
1.指針値
0.008mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・白色結晶、酸アミド系の接触型非ホルモン型除草剤、水に難溶、土壌中の持続性長(20~40日程度)、土壌中の移行性は中程度
(2)生産量等
(平成2年度)
・指定流通量26.6t
(3)主な用途
・「カーブ」の商品名で50%含有の水和剤のみが流通
・選択性土壌処理剤でイネ科、広葉の一年性雑草の除草
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・ゴルフ場使用農薬に係る暫定水質目標 0.008mg/L
・水道水質基準改定案 0.008mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,281検体中38検体検出、検出率3.0%、検出範囲0.00002~0.0041mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.003mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0075mg/Lとなり、これより、水質評価値0.008mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において検出されているが、使用量が少ないことを考慮し、水道水質に関する基準の検討状況も勘案して要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.008mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.101-107 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○EPN
1.基準値及び指針値
(当初:環境基準値)(有機燐(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)として)検出されないこと(検出限界0.1mg/L)
(現行:指針値)0.006mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:環境基準項目)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(要監視項目設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・原体は淡褐色の油状液体、純品は淡黄色の結晶、融点36℃、比重1.27、難揮発性、水に難溶、有機溶媒に可溶、アルカリ性で加水分解、土壌吸着されやすい、大気への揮散は小、土壌中の半減期3~60日、塩素・オゾンにより短時間で分解
(2)生産量等
(平成2年度)
・原体生産量443t 原体輸出量483t 国内流通量203t
(3)主な用途
・有機燐系殺虫剤(稲、果樹、野菜等)
5.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
・水道水質基準改定案 0.006mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(要監視項目設定時)
・濃縮性は中程度と考えられるがさらに詳細な検討が必要。
7.環境中における検出状況(要監視項目設定時)
(平成2年度~平成4年度)
<公共用水域>
905検体中2検体で検出、検出率0.2%、検出範囲0.0012~0.0013mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(審議会配付資料抜粋)
(3)有機リン
パラチオン、メチルパラチオン、EPN、メチルジメトン等の有機リン系統の農薬は毒性が強い。例えばパラチオンのマウスに対するLD50(半数致死濃度)は6mg/kgである。一方同じ有機リン系統の農薬でもMEPのごときは、LD50が788mg/kgとパラチオンに比べて毒性が約120分の1程度のものもみうけられる。(参考表(略))
このように有機リン系統の農薬にも、その毒性に大きな差があり、国民の健康の面からして、毒性の強い上記の4種について規制すれば十分と考えられる。またTEPPについては、特定毒物であるが、現在生産を行っていないこと、及び仮に使用しても水に溶解すればただちに分解し、毒性が消失することが判明しているので、規制対象から削除した。
(平成5年・要監視項目設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.0023mg/kg/day(食品衛生法に基づく農産物に係る農薬の残留基準設定の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00575mg/Lとなり、これより、水質評価値0.006mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
従来有機燐として環境基準項目に定められているのは、急性毒性が高いパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNであるが、このうちEPNを除く3物質については、農薬としての登録が失効して15年以上が経過しており、EPNについても生産・使用実績が環境基準設定当時より減少している。また、公共用水域においては、昭和47年度以降、20年間にわたり有機燐としては検出されていない状況にある。このため、有機燐として急性毒性を考慮して定めた現行の環境基準は削除して差し支えないと考えられる。
しかしながら、EPNについては現在生産、使用が続けられており、またその他の3物質についても生産が全く禁止されているわけではないので、急性毒性が高い物質であることも考慮して、当面現状の排水規制は継続することが適当と考えられる。また、EPNについては、公共用水域において低いレベルでの検出事例があることも考慮して、要監視項目として位置づけ、これまでの安全性評価に関する知見に基づき、他の農薬と同様に慢性毒性を勘案して指針値を0.006mg/L以下と設定して必要な監視を行うこととする。
9.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書(EPN)」、pp.1-8 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書(パラチオン)」、pp.9-15 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書(メチルパラチオン)」、pp.16-22 【NIES保管ファイル】
・平成4年10月・日本水環境学会「平成4年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書(メチルジメトン)」、pp.23-27 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○ジクロルボス(DDVP)
1.指針値
(当初)0.01mg/L以下
(現行)0.008mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁水質保全局長通知(環水企第58号・環水管第49号)
4.基礎情報(当初設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・淡黄色の液体、特異な臭気、比重1.415、揮発性、水中で容易に加水分解、土壌に吸着されにくい、鉄に対する腐食性、塩素により容易に分解
(2)生産量等
(平成元年度)
・原体生産量1,195t
(3)主な用途
・非ホルモン型接触性除草剤(水田初期に使用)
5.毒性情報及び各種基準値(当初設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ3
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.01mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(当初設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,196検体中30検体検出、検出率2.5%、検出範囲0.00002~0.001mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.004mg/kg/day(食品衛生法に基づく農産物に係る農薬の残留基準設定の際の評価及びJECFAの評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.01mg/Lとなり、これより、水質評価値0.01mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域における検出レベルが比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.01mg/L以下とする。
(平成11年・改定時)(答申抜粋)
平成5年の指針値策定以後、食品衛生調査会がADIを0.004mg/kg/dayから0.0033mg/kg/dayに変更したことを踏まえ、指針値を0.01mg/Lから0.008mg/Lに変更する。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.200-205 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○フェノブカルブ(BPMC)
1.指針値
(当初)0.02mg/L以下
(現行)0.03mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁水質保全局長通知(環水企第58号・環水管第49号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色の結晶、僅かに芳香、水に難溶、有機溶剤に可溶、弱酸、強塩基に不安定、土壌に吸着されにくい、塩素により分解されない、水中の残留性高
(2)生産量等
(平成元年度)
・原体生産量1,183t
(3)主な用途
・カーバメイト系殺虫剤(主に稲、従として果実、野菜等)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・水道水質基準改定案 0.02mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
1,164検体中97検体検出、検出率8.3%、検出範囲0.00001~0.0027mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.006mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.015mg/Lとなり、これより、水質評価値0.02mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域における検出レベルが比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.02mg/L以下とする。
(平成11年・改定時)(答申抜粋)
平成5年の指針値策定以後、食品衛生調査会がADIを0.006mg/kg/dayから0.012mg/kg/dayに変更したことを踏まえ、指針値を0.02mg/Lから0.03mg/Lに変更する。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.213-218 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○イプロベンホス(IBP)
1.指針値
0.008mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の液体、比重1.103、不揮発性、水に難溶、水溶解度1g/L(18℃)、有機溶媒に易溶、塩基性、紫外線に不安定、比較的長時間土壌中に存在
(2)生産量等
(平成元年度)
・原体生産量1,174t
(3)主な用途
・有機燐系殺菌剤(稲のイモチ病、穂がれ)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・水道水質基準改定案 0.008mg/L(監視項目)
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
313検体中44検体検出、検出率14.1%、検出範囲0.00002~0.0018mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.003mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0075mg/Lとなり、これより、水質評価値0.008mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において比較的広く検出されているが、検出レベルは比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.008mg/L以下とする。
(平成11年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成5年に設定した指針値0.008mg/Lと公共用水域等における検出状況を比較すると、公共用水域等における検出率は比較的低く、指針値超過地点は3地点であり、農薬による影響は時期が限られていることを考慮して環境基準健康項目には移行しないが、引き続き要監視項目として年間を通した濃度が適切に評価されるようにモニタリングを行う必要がある。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.225-230 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
○クロルニトロフェン(CNP)
1.指針値
(当初)0.005mg/L以下
(現行)数値を定めない
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表1の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成6年3月15日・化学物質水質保全検討会報告
平成6年3月15日・環境庁水質保全局長通知(環水管第43号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・黄褐色白色の結晶粉末、無臭、比重1.62、融点107℃、不揮発性、水・アルコールに難溶、ベンゼン、キシレンに可溶、土壌に吸着されやすい
(2)生産量等
(平成元年度)
・原体生産量1,412t
(3)主な用途
・ジフェニルエーテル系除草剤(稲等)
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
・残留農薬安全性評価委員会における一日摂取許容量(平成6年) 設定しない
・農薬取締法に基づく農薬登録保留基準(平成6年) 設定しない(削除)
・暫定水質管理指針値(平成6年) 0.0001mg/L以下
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は中程度と考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
762検体中148検体検出、検出率19.4%、検出範囲0.000005~0.0006mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
ADI 0.002mg/kg/day(農薬取締法の登録の際の評価)より、人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.005mg/Lとなり、これより、水質評価値0.005mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域において比較的広く検出されているが、検出レベルは比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、これまでの安全性評価に係る知見に基づき、0.005mg/L以下とする。
なお、この物質は土壌中においてアミノ体として残留するとの指摘もあり、更に知見の集積が必要である。
(平成6年・改定時)
(クロルニトロフェン(CNP)に係る残留農薬安全性評価委員会評価抜粋)
1 経緯
除草剤として昭和40年に農薬取締法に基づき登録されたクロルニトロフェン(以下CNPという。)については、本委員会で、昭和52年に当時において入手可能な動物試験等の科学的知見に基づいて、一日摂取許容量(ADI)を0.00204mg/kg/日と設定して、今日に至っている。
最近、新潟大学医学部山本正治教授は、平成4年度対がん10ヵ年総合戦略プロジェクト研究報告等で、新潟平野部における胆のうがん死亡率とCNPとの関連の可能性を指摘した研究結果をまとめている(別添参照(略))。この研究は、胞のうがんとCNPとの関連性に着目した疫学研究としては最初のものである。
これを受け、本委員会は平成5年12月24日より4回にわたり、山本教授により実施された疫学研究及び現時点における入手可能な動物試験等のデータにより、CNPの安全性について検討した。
2 安全性評価
本委員会は、山本教授の疫学研究を検討の結果、新潟平野部におけるCNPの推定暴露量と胆のうがん死亡率の地域的な相関関係が認められるものと考える。
しかしながら、CNPの推定暴露量の指標とした5市における水道水中の濃度が最近の2カ年に限られていること及び新潟県の胆のうがんの死亡率は昭和30年代よりすでに高く、その後の増加率も全国平均と大きな差はないことから時間的な相関関係についてはまだ十分明確でないと考える。また、CNPと胆のうがんの因果関係については、現時点までの疫学研究結果及び各種動物試験等の知見を総合的に検討したが、明確にすることは困難であった。
この因果関係を明らかにするためには、疫学研究及び動物試験の両面からのアプローチが必要である。疫学研究については、過去の暴露状況の把握の困難さ及び担のうがんの発生率の低さ等の問題を考慮すると、これ以上の研究を実施することは困難と考える。動物試験としては、例えば、CNP及びそのアミノ体の胆のうがん発生メカニズムに着目した長期毒性/発がん性試験及び体内濃縮に関する試験等を実施することが必要であると考えられる。
3 一日摂取許容量の設定
CNPの一日摂取許容量(0.00204mg/kg/日)は標準的な手法に沿って設定されたものであり、今日まで妥当なものであった。
しかし、今回示された新たな知見により、少なくともCNPと胆のうがん死亡率に関し地域的な相関関係は認められると考える。ただし、前述のように、現時点では、因果関係を明確にすることは困難であり、これを明確にするための各種研究は相当長期間を必要とする。
従って、因果関係の有無が明らかとなるまでの間は、予防的な観点も取り入れ、一日摂取許容量を設定しないことが妥当と考える。
(要監視項目クロルニトロフェンについて(化学物質水質保全検討会)抜粋)
1 経緯
クロルニトロフェン(CNP)については、平成5年3月8日付け水質保全局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」において、要監視項目として位置づけられている。
クロルニトロフェンに係る一日摂取許容量については、本年3月7日に厚生省に設置されている残留農薬安全性評価委員会において、クロルニトロフェンと胆のうがんの因果関係の有無が明らかとなるまでの間は、予防的な観点も取り入れ、一日摂取許容量を設定しないことが妥当と考えられる旨の結果がとりまとめられた。
これを受けて、農薬取締法に基づく農薬登録保留基準については、環境庁においてクロルニトロフェンに係る一日摂取許容量が設定されるまでの間は現行の同農薬登録保留基準を設定しないこととし、その間の新たな登録は行わないことが妥当である旨の本年3月10日付け中央環境審議会答申を踏まえ、関連告示の改正が行われることとなっている。
また、現在登録されているクロルニトロフェンの扱いについては、3月7日に環境庁から農林水産省に対して要請が行われ、農林水産省では、関係製造業者からのクロルニトロフェンの製造及び販売を自粛する旨の報告も勘案し、原則として同農薬を使用しないこと等を関係都道府県知事等へ指導している。
クロルニトロフェンに係る水道の水質管理については、厚生省において、今後クロルニトロフェンが使用されなくなることを前提としたうえで、当面の暫定的な対応として、「暫定水質管理指針値」を定め、必要に応じ浄水処理の強化による対応も含め万全を期すこととされている。
2 クロルニトロフェンに係る要監視項目について
(1)指針値の取扱い等
クロルニトロフェンの指針値は、これまで入手可能な科学的知見により設定された一日摂取許容量に基づいて0.005mg/L以下と設定されたものであるが、今般、クロルニトロフェンに係る一日摂取許容量は、因果関係の有無が明らかとなるまでの間は、設定しないことが妥当との残留農薬安全性評価委員会の結果が示されたことから、同期間中はクロルニトロフェンに係る要監視項目の指針値は設定しないこととする。
これにより、水質測定結果を評価する上での数値がブランクとなるが、将来科学的知見が蓄積されて新たな数値が設定された場合においては検出状況等によっては環境基準健康項目の検討の対象となりうるものとして、引き続き要監視項目として位置づけ、公共用水域及び地下水の水質測定を行い、その推移を把握していくことが妥当である。
(2)公共用水域等における水質測定
公共用水域等における要監視項目の水質測定に当たっては、地域の実状に応じ環境基準健康項目の主要な測定地点等で水質を測定することとされていることから、クロルニトロフェンに係る水質測定地点の選定に当たっても、クロルニトロフェンの散布場所等の使用実績、水道水の取水口の位置等の地域の実状を十分勘案していく必要がある。また、クロルニトロフェンの水質測定の時期については、クロルニトロフェンの散布時期等を勘案して、的確に実施していく必要があり、特に、クロルニトロフェンが除草剤として通常田植前後にたん水状態で使用されることから、田植時期を中心としてその前後において水質測定頻度を高める必要がある。
なお、水質測定の結果「クロルニトロフェンが検出されること」とは、平成5年4月28日付け環境庁水質保全局水質規制課長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」の中で定められているクロルニトロフェンに係る測定法により測定した場合において、0.0001mg/L以上のクロルニトロフェンが検出される場合とする。
(3)クロルニトロフェンが検出された場合の対応
水質測定の結果、クロルニトロフェンが検出された場合には、その水系におけるクロルニトロフェンの検出状況等について調査し、あわせてクロルニトロフェンに係る水道の水質管理を迅速に行えるよう水道事業者に連絡するとともに、クロルニトロフェンが公共用水域へ飛散・流入しないよう関係部局、関係行政機関等とも連絡・連携を密にしていく必要がある。
3 その他
クロルニトロフェンの代替物として利用される農薬に関する公共用水域における存在状況等の情報収集に努めていく必要がある。
また、残留農薬安全性評価委員会において、動物試験としては、例えば、クロルニトロフェン及びそのアミノ体の胆のうがん発生メカニズムに着目した長期毒性/発がん性試験及び体内濃縮に関する試験等を実施することが必要であることが指摘されていることから、引続きこれらの情報の収集に努めていく必要がある。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.219-224 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月7日・残留農薬安全性評価委員会「クロロニトロフェン(CNP)に係る残留農薬安全性評価委員会評価」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月7日・生活環境審議会水道部会水質専門委員会「クロルニトロフェン(CNP)に関する当面の対応について」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月10日・環境庁長官「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第1号イの環境庁長官の定める基準の設定について(諮問)」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月10日・中央環境審議会「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第1号イの環境庁長官の定める基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月15日・平成5年度化学物質水質保全検討会(第1回)配付資料 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月15日・化学物質水質保全検討会「要監視項目クロルニトロフェンについて」 【NIES保管ファイル】
・平成6年3月15日・環境庁水質保全局長「クロルニトロフェン(CNP)について」(環水管第43号) 【NIES保管ファイル】
○トルエン
1.指針値
0.6mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明な水より軽い液体、揮発性、疎水性で水に難溶、水溶解度0.52g/L(20℃)、有機溶媒に可溶、有機物含有量の多い土壌に吸着され易い、生分解可能
(2)生産量等
(平成2年度)
・需要実績1,184,000t
(3)主な用途
・染料、香料、有機顔料、ポリウレタン、可塑剤、合成繊維、漂白剤、医薬品
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・U.S. EPA グループD
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.6mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(1984) なし
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.7mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 1mg/L、MCLG 1mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
542検体中122検体検出、検出率22.5%、検出範囲0.00001~0.25mg/L
(1地点を除けば検出範囲は0.00001~0.0032mg/Lとなる。)
<地下水>
984検体中136検体検出、検出率13.8%、最大値0.32mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(NTP (1990))をもとに、LOAEL 312mg/kg/dayより、不確定係数1,000(短期実験、LOAEL使用を考慮)として、1週間5日投与を考慮して、TDI 0.223mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.558mg/Lとなり、これより、水質評価値0.6mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベルは全国的にみれば比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、NTP(1990)をもとに、0.6mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.160-167 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○キシレン
1.指針値
0.4mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明な水より軽い液体、芳香臭、しばしば蛍光を発する、疎水性で水に難溶、有機溶媒に可溶、水溶解度0.15~0.17g/L(20℃)、有機物含有量の多い土壌に吸着、可燃性、生分解は可能、化審法の分解性評価では良分解
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量174,512t(o-体)、11,874t(m-体)、1,393,329t(p-体)
(3)主な用途
・塗料、農薬、医薬品の溶剤
・染料、有機顔料、香料、可塑剤、合成樹脂等の原料
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・U.S. EPA グループD
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.4mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.5mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 10mg/L、MCLG 10mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
436検体中45検体検出、検出率10.3%、検出範囲0.00002~0.011mg/L(1地点を除けば検出範囲は0.00002~0.0025mg/L)
<地下水>
984検体中73検体検出、検出率9.9%、最大値0.065mg/L
8.指針値の根拠の概要(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(NTP (1986))をもとに、NOAEL 250mg/kg/dayより、不確定係数1,000(毒性データ不足を考慮)として、1週間5日間投与を考慮、TDI 0.0179mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0448mg/Lとなり、これより、水質評価値0.4mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベルは全国的にみれば比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、NTP(1986)をもとに、0.4mg/L以下とする。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.174-194 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
○フタル酸ジエチルヘキシル
1.指針値
0.06mg/L以下
2.測定方法
平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表3の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・無色透明の油状液体で僅かながら水より軽い、疎水性で水に難溶、水溶解度0.15~0.17mg/L(20℃)、有機溶媒に可溶
・可塑化効率、耐揮発性、低温柔軟性等可塑剤として要求される性質を有する
・土着吸着されやすい、生分解性有り
(2)生産量等
(昭和63年度)
・生産量273t 出荷量263t
(3)主な用途
・可塑剤、絶縁媒体
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.06mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.008mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.006mg/L、MCLG Zero mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
(昭和63年度~平成4年度)
<公共用水域>
65検体中50検体検出、検出率76.9%、検出範囲0.00018~0.023mg/L
<地下水>
185検体中60検体検出、検出率32.4%、最大値0.022mg/L
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Morton(1979))をもとに、NOAEL 2.5mg/kg/dayより、不確定係数100として、TDI 0.025mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0625mg/Lとなり、これより、水質評価値0.06mg/L(WHOでは寄与率1%で算定)。
(中略)
8.対処方針(案)
公共用水域等における検出レベル全体としては比較的低いことから、水道水質に関する基準の検討状況も勘案し、要監視項目とする。指針値としては、Morton(1979)をもとに、0.06mg/L以下とする。
(平成11年・見直し検討時)(答申抜粋)
Morton(1979)によるラットの亜急性毒性試験をもとに、指針値を現行のとおり0.06mg/Lとする。
なお、フタル酸エステル類については内分泌攪乱作用の疑いがあるとされ、この方面からの検討も必要ではあるが、現在のところまだ十分な知見が得られていないと判断されることから、今回は内分泌攪乱作用に関する評価は行っていない。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、フタル酸ジエチルヘキシルは指針値超過地点は1地点であり、また、全体的に検出レベルは低く、水道水質に関する基準において監視項目とされていることも勘案すると、全国的な対策を取る必要はないと考えられる。したがって、環境基準健康項目には移行せずに引き続き要監視項目とする。
なお、1地点とはいえ指針値超過地点があることから、要監視項目として発生源の存在状況を考慮しつつ重点的なモニタリングを行い、指針値超過地点が見つかった場合には、地方自治体においてその発生源を把握し、地域の実情に応じて個別に対応をとることが重要である。
9.参考資料
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○ニッケル
1.指針値
(当初)0.01mg/L以下
(現行)数値を定めない
2.測定方法
日本産業規格K0102の59.3に定める方法又は平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表4若しくは付表5に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁水質保全局長通知(環水企第58号・環水管第49号)
4.基礎情報(当初設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・銀白色の輝く金属、展延性に富む、水に不溶
・塊状は極めて安定、粉状は発火性
・濃硝酸には不働、平均地殻存在比75mg/kg、海水濃度0.228~0.693μg/L
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量21,900t
(3)主な用途
・特殊鋼、電熱線、めっき、貨幣鋳造、顔料、触媒原料
5.毒性情報及び各種基準値(当初設定時)
(1)発がん性評価
・IARC グループ3
・U.S. EPA グループD
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.01mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.02mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 MCL 0.1mg/L、MCLG 0.1mg/L
・EC MAC 0.05 mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は中程度と考えられる。
7.環境中における検出状況(当初設定時)
(平成2年度)
204検体中5検体検出、検出範囲0.02~0.03mg/L、検出限界0.02mg/L(2県で測定された結果)
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Ambroseら (1976))をもとに、NOAEL 5mg/kg/dayより、不確定係数1,000(毒性データ不足を考慮)として、TDI 0.005mg/kg/dayとなる。人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.0125mg/Lとなり、これより、水質評価値0.01mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性に関する知見、水道水質に関する基準の検討状況を踏まえ、要監視項目とし、今後公共用水域等における水質データの蓄積に努めることとする。指針値としては、Ambroseら(1976)をもとに0.01mg/L以下とする。
(平成11年・改定時)(答申抜粋)
現行では、Ambroseら(1976)によるラットの2年間慢性毒性試験をもとにTDIを0.005mg/kg/dayとしているが、これは定量的評価を確定するには十分な試験ではなく、WHOが平成10(1998)年の評価において暫定的な値としたことも勘案し、暫定的なTDIとして0.005mg/kg/dayとする。これより、従来の飲料水経由の摂取の観点から指針値を導くとすると、現行のとおり0.01mg/Lとなる。
しかしながら、毒性についての定量的評価を確立するには十分な試験結果がない状況で指針値を示すことは、不確定な毒性評価をもとに環境中の存在状況について適切とはいえない評価を誘導する可能性があることから、これを考慮してニッケルについてはこれまでの指針値を削除する。
なお、定量的評価が定まっていないとはいえある程度の毒性があることがわかっている本物質が公共用水域等において比較的広く検出されていることから、引き続き要監視項目として発生源の存在状況を考慮しつつ重点的なモニタリングを行い、毒性評価が固まった時点で環境中の存在状況を評価し環境基準健康項目への移行について迅速に検討することが必要である。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.293-300 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○モリブデン
1.指針値
0.07mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の規格68.2に定める方法又は平成5年4月28日・環境庁水質保全局水質規制課長通知(環水規第121号)付表4若しくは付表5に掲げる方法
3.設定経緯
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・還元されたものは灰色の粉末、焼結あるいは融解すると曇りのある白色金属
・極めて安定、化合物中では±0,+2,+3,+4,+5,+6価で存在、6価が最も安定、比重10.28、融点2,622±10℃、平均地殻存在量1.5mg/kg、海水濃度0.1~0.5μg/L
(2)生産量等
(平成元年度)
・生産量707t
(3)主な用途
・(モリブデン)特殊鋼、真空管、耐熱材料、抵抗体、触媒、潤滑剤、電子材料
・(モリブデン酸ナトリウム)試薬、飼料添加剤、顔料
・(モリブデン酸アンモニウム)試薬、顔料、触媒
・(二硫化モリブデン)潤滑剤、触媒
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性評価
・U.S. EPA グループD
(2)各種基準値
・水道水質基準改定案 0.07mg/L(監視項目)
・WHO飲料水水質ガイドライン(改定案(第2版ドラフト)) 0.07mg/L
6.魚介類への濃縮性(設定時)
・濃縮性は低いと考えられる。
7.環境中における検出状況(設定時)
・我が国での調査事例は収集できなかった。
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Chappellら (1979))をもとに、人に対するNOAEL 0.2mg/L(飲料水曝露)より、不確定係数3(必須元素を考慮)として、計算値0.067mg/Lとなり、これより、水質評価値0.07mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性に関する知見、水道水質に関する基準の検討状況を踏まえ、要監視項目とし、今後公共用水域等における水質データの蓄積に努めることとする。指針値としては、Chappellら(1979)をもとに0.07mg/L以下とする。
(平成11年・見直し検討時)(答申抜粋)
Chappellら(1979)によるヒトでの調査をもとに、指針値を現行のとおり0.07mg/Lとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、モリブデンは指針値超過地点が3地点であり、また、自然状態でモリブデンが含まれている海水の影響を除けば全体的に検出レベルは低く、水道水質に関する基準において監視項目とされていることも勘案すると、全国的な対策を取る必要はないと考えられる。したがって、環境基準健康項目には移行せずに引き続き要監視項目とする。
なお、3地点とはいえ指針値超過地点があることから、要監視項目として発生源の存在状況を考慮しつつ重点的なモニタリングを行い、指針値超過地点が見つかった場合には、地方自治体においてその発生源を把握し、地域の実情に応じて個別に対応をとることが重要である。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.312-317 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○アンチモン
1.指針値
(当初)0.002mg/L以下
(現行)0.02mg/L以下
2.測定方法
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)の付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法
3.設定経緯
(当初)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:指針値削除)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁水質保全局長通知(環水企第58号・環水管第49号)
(再改定:指針値再設定)
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(平成21年・見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:(アンチモン)銀白色で光沢があり硬くてもろい金属又は暗灰色の粉末、(三酸化アンチモン)白色の結晶性粉末、五酸化アンチモン:黄白色粉末
・比重:(アンチモン)6.7(25℃)、(三酸化アンチモン)5.2ないし5.7(結晶構造により異なる)、(五酸化アンチモン)3.8
・水への溶解性:(アンチモン)不溶、(三酸化アンチモン)26mg/L(20℃)、(五酸化アンチモン)微溶
・環境中への放出の大部分は、アンチモン又は酸化アンチモンの製造時に精錬所から放出されるスラグによるものである。大気中には微粒子として放出され、大気中オキシダントにより酸化されて三酸化二アンチモン(Sb2O3)となると考えられている。水系への放出は、通常微粒子と関連しており、移動後河川河口部などの堆積層に沈降する。水中で溶解しているものも懸濁物、生体、堆積物への移行等があり、また種々の条件で酸化・還元を受ける。
・溶解性のものは、自然水系の好気条件下では、溶存しているアンチモンの大部分はSb(Ⅴ)であり、Sb(OH)6-が主要な水溶性分子種と考えられる(Raiら, 1984)。水中に存在する化学種としては、Sb(Ⅲ)、Sb(Ⅴ)化合物及び微生物のメチル化により生成したメチルスチボン酸又はジメチルスチボン酸の4種が知られている事例がある。水中や土壌中に存在するアンチモン化合物は一般的には非揮発性であるが、底質中などの還元状態下で還元され、微生物によりメチル化されるとトリメチルスチビンのような高揮発性物質になり、容易に大気中へ揮散すると考えられる(Andreaeら, 1983)。
・アンチモンは土壌中のコロイドに強く吸着され、コロイド微粒子と共に地下水中を移動する。堆積物からの水中への再放出は、pHの影響を強く受け、pHが高くなると急に増加する。有害廃棄物処理場からのアンチモンの検出率は、米国では12%前後で、その濃度は幾何平均値で8~17ppm程度である。アンチモンはヨウ化アルキル或いは臭化アルキルと反応して塩を作るので、精錬鉱滓の埋立でこれが起こると、アンチモンの地中移動性を大きく高めることになる。
・化審法に基づくNa[Sb(OH)6]の濃縮性試験(28日間)では、低濃縮と判定されている。水中濃度が98.7μgSb/L及び9.9μgSb/LにおけるBCFは0.84及び5.6未満である(経済産業省, 2002)。
(2)生産量等
(平成19年)
・生産量:三酸化アンチモン7,939t、五酸化アンチモン約300t
・輸出量:三酸化アンチモン2,222t
(3)主な用途
・金属アンチモン:半導体合金、セラミックス、活字型、鋳型、はんだ
・三酸化アンチモン:各種樹脂、ビニル電線、帆布・紙・塗料等の難燃助剤、高級ガラス清澄剤、ほうろう、吐酒石、合成繊維触媒原料、顔料
・五酸化アンチモン:各種樹脂・繊維の難燃剤、顔料、ガラス清澄剤、電子材料原料
5.毒性情報及び各種基準値(平成21年・見直し検討時)
・水道水質基準値(水質管理目標設定項目目標値) 0.015mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第2版) 0.005mg/L(暫定値)
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版) 0.02mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.006mg/L
・EU飲料水水質基準 0.005mg/L
6.魚介類への濃縮性(当初設定時)
・濃縮性は中程度と考えられる。
7.環境への排出等の状況(PRTR)
(平成16年・再改定時)
<公共用水域>
(平成13年度)4,090kg、合計:13,690kg
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>
(平成19年度)10,953kg(下水道業を除く排出量:10,953kg)、合計:902,181kg
8.環境中における検出状況
(当初設定時)
鉱山排水の影響のある河川において、最大0.38mg/Lのレベルで検出された事例がある。
(平成16年・再改定時)
(平成6~13年度)
<公共用水域>
(要監視項目)4,880地点中超過28地点(0.6%) 10%値超過105地点(2.2%)
<地下水>
(要監視項目)2,075井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過13地点(0.6%)
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.02mg/L)
(平成16年度)測定1195地点、検出173地点、超過6地点、10%超過9地点
(平成17年度)測定849地点、検出150地点、超過6地点、10%超過19地点
(平成18年度)測定845地点、検出158地点、超過5地点、10%超過17地点
(平成19年度)測定946地点、検出116地点、超過5地点、10%超過22地点
<地下水>(指針値0.02mg/L)
(平成16年度)測定588地点、検出98地点、超過2地点、10%超過5地点
(平成17年度)測定508地点、検出9地点、超過1地点、10%超過6地点
(平成18年度)測定521地点、検出15地点、超過2地点、10%超過10地点
(平成19年度)測定507地点、検出28地点、超過1地点、10%超過9地点
9.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会配付資料抜粋)
5.水質評価値の算出
WHO飲料水水質ガイドラインの根拠データ(Schroederら (1970))をもとに、LOAEL 0.43 mg/kg/dayより、不確定係数500(LOAELの使用を考慮)として、TDI 0.00086 mg/kg/dayとなる。
人の体重を50kg、1日あたりの飲料水量を2L、飲料水の寄与率を10%とすると、計算値0.00215mg/Lとなり、これより、水質評価値0.002mg/L。
(中略)
8.対処方針(案)
有害性に関する知見、水道水質に関する基準の検討状況を踏まえ、要監視項目とし、今後公共用水域等における水質データの蓄積に努めることとする。指針値としては、Schroederら(1970)をもとに0.002mg/L以下とする。
(平成11年・改定時)(答申抜粋)
現行ではSchroederら(1970)によるラットの生涯試験をもとにTDIを0.86μg/kg/dayとしているが、これは定量的評価を確立するには十分な試験ではなく、暫定的なTDIとして0.86μg/kg/dayとする。これより、従来の飲料水経由の摂取の観点から指針値を導くとすると、現行のとおり0.002mg/Lとなる。
しかしながら、毒性についての定量的評価を確立するには十分な試験結果がない状況で指針値を示すことは、不確定な毒性評価をもとに環境中の存在状況について適切とはいえない評価を誘導する可能性があることから、これを考慮してアンチモンについてはこれまでの指針値を削除する。
なお、定量的評価が定まっていないとはいえある程度の毒性があることがわかっている本物質が公共用水域等において比較的広く検出されていることから、引き続き要監視項目として発生源の存在状況を考慮しつつ重点的なモニタリングを行い、毒性評価が固まった時点で環境中の存在状況を評価し環境基準健康項目への移行について迅速に検討することが必要である。
(平成16年・再改定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
従来から要監視項目として挙げられていたものの、指針値を設定していなかった項目である。過去の検出状況を見ると、今回の指針値を超過する状況も見られるが、非常に限定的な水域において検出されており、また、その中には自然由来によると考えられる検出も含まれている状況にある。これらを踏まえ、当面要監視項目として設定し、公共用水域等における検出状況等の知見の収集に努めることとするが、その結果を踏まえ3年を目途に環境基準項目に追加するか否かについて再度検討を行う。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.02mg/L)を超過する地点(平成6~14年度延べ5,716地点中延べ31地点(地点数の重複を除けば8地点)、超過率は0.5%)及び指針値の10%値(0.002mg/L)を超過する地点(平成6~14年度延べ5,716地点中延べ120地点(地点数の重複を除けば48地点)、超過率2.1%)がある(要監視項目調査結果)。
地下水において、指針値を超過する地点はないが、指針値の10%値を超過する地点がある(2,350地点中13地点、超過率0.6%)(要監視項目調査結果)。
イ.指針値
Poonら(1998)のラットを用いた飲水投与試験結果についてのLynchら(1999)による再評価から、肝及び骨髄毒性を根拠にしたNOAEL 6mg/kg/dayに不確実係数1,000を適用してTDIは6μg/kg/dayとなる。水の寄与率10%、体重50kg、飲料水量2L/dayから指針値を0.02mg/Lとした。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共水域水質測定結果によると、公共用水域では、現行指針値を超過するものが平成16年度から19年度まで毎年あり(5から6箇所)、現行指針値の10%を超過するものが平成16年以降毎年ある(9から22箇所)。地下水水質測定結果によると地下水では、超過するものが毎年1から2箇所超過するものがあり、現行指針値の10%を超過するものが毎年ある(5から10箇所)。
現在人為的な影響により指針値を超過すると考えられるものは、地下水において1箇所あり、所管する県において、指導及び継続的な監視が行われている。一方、公共用水域においては3箇所あるが、これらの水域については、当該水域を所管する県市において、今後環境用水の導入や排水処理技術のさらなる研究等を行う予定である。これらの結果を踏まえた上でアンチモンの取扱いについて再度検討すべきである。
その間、引きつづき要監視項目とし、公共用水域等における検出状況の知見の収集を継続する必要がある。その際には、現在検出が見られる箇所以外の公共用水域等においても人為的な影響による汚染が起こりえないかモニタリングを強化すべきである。
また、水中でのアンチモン化合物の動態が複雑であるため、水環境中での動態に関して、実測調査も含め知見の収集を継続する必要がある。
10.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.301-306 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○塩化ビニルモノマー
1.指針値
0.002mg/L以下
2.測定方法
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)の付表1に掲げる方法
3.設定経緯
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:特徴的な臭気のある無色の気体
・比重:0.9(液体;20℃/4℃)
・水への溶解性:8.81g/L(25℃)
・ヘンリー定数:2,820Pa-m3/mol(24℃)
・環境中では、塩化ビニルモノマーはほぼ完全に蒸気相で存在し、また、水酸基ラジカルおよびオゾンと反応し、最終的にはホルムアルデヒド、一酸化炭素、塩酸、ギ酸などを形成する。その半減期は1~4日である(WHO, 1999)。
・日光または酸素がない状態では安定であるが、空気、光あるいは熱に曝されると重合する。
・塩化ビニルモノマーは水溶解性が比較的低く、微粒子物質および沈殿物への吸着能が低い。表層水に取り込まれた塩化ビニルモノマーは揮発によって除去される。表層水からの揮発について報告された半減期は約1~40時間である(WHO, 1999)。
・地面に放出された場合には、土壌に吸着されず、地下水にすぐに移動し、そこで二酸化炭素と塩素イオンまで分解されることもあれば、あるいは数か月間または数年間にもわたって変化せずにとどまることもある。塩化ビニルモノマーはトリクロロエチレン等の分解産物として地下水で報告されている(WHO, 1999)。
・水環境中では加水分解はされず、水の付加反応による半減期は10年以上(Gangolli, 1999)や数年(GDCh BUA, 1989)の報告がある。
・また、化審法に基づくクローズドボトルを用いた好気的成分解性試験(28日間)では、難分解性と判定されている。被験物質濃度2.04mg/L及び10.2mg/LのBODに基づく分解率は16%及び3%である(通商産業省, 1997)。一方、特定の菌や類似構造の物質に馴化された菌には生分解されると考えられる(NITE&CERI初期リスク評価書, 2005)。
・生物濃縮性はオクタノール/水分配係数(logPow)の測定値が1.46であることより、濃縮性がない、又は低いと判定される(通商産業省, 1997)。
・BCF測定値には次のデータが存在する。10未満(ゴールデンイドフィッシュ)、40(藻類)(Freitag, 1985)。
(2)生産量等
(平成19年)
・生産量3,141,659t 輸出量902,431t
(3)主な用途
・ポリ塩化ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン-塩化ビニル共重合体の合成原料
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準値(要検討項目目標値) 0.002mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第2版) 0.005mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版) 0.0003mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.002mg/L
・EU飲料水水質基準 0.0005mg/L
6.環境への排出等の状況(PRTR)
(当初設定時)
<公共用水域>
(平成13年度)15,552kg、合計:821,320kg
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>
(平成19年度)7,665kg(下水道業を除く排出量:7,665kg)、合計:303,341kg
7.環境中における検出状況
(当初設定時)
<公共用水域>(指針値0.002mg/L)
(要調査項目)
(平成11年度)147地点中超過0地点(0.0%) 10%値超過1地点(0.7%)
(化学物質と環境)
(平成9年度)43地点中超過0地点(0.0%) 10%値超過1地点(2.3%)
<地下水>(指針値0.002mg/L)
(地下水実態調査)
(平成5年度)272井戸中超過4井戸(1.5%) 10%値超過7井戸(2.6%)
(要調査項目)
(平成11年度)23井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過1井戸(4.3%)
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.002mg/L)
(平成16年度)測定504地点、検出1地点、超過1地点、10%超過1地点
(平成17年度)測定538地点、検出1地点、超過1地点、10%超過1地点
(平成18年度)測定715地点、検出9地点、超過1地点、10%超過4地点
(平成19年度)測定648地点、検出10地点、超過1地点、10%超過10地点
<地下水>(基準値0.002mg/L)
(平成16年度)測定173地点、検出41地点、超過31地点、10%超過40地点
(平成17年度)測定268地点、検出22地点、超過17地点、10%超過21地点
(平成18年度)測定311地点、検出48地点、超過39地点、10%超過46地点
(平成19年度)測定345地点、検出79地点、超過58地点、10%超過74地点
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
地下水において指針値の超過が見られるが、ジクロロエチレン類の分解生成物として塩化ビニルモノマーが検出されるといった知見もあり、塩化ビニルモノマーの検出が同物質による汚染の結果とは必ずしも言えない状況にある。このため、現時点においては、要監視項目として設定し、共存物質を含めた公共用水域等の検出状況、環境中での挙動等の知見の収集に努める必要がある。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.002mg/L)を超過する地点はないが、指針値の10%値(0.0002mg/L)を超過する地点がある(190地点中2地点、超過率1.1%)(要調査項目存在状況調査結果、化学物質と環境)。
地下水において、指針値を超過する地点(295地点中3地点、超過率1.0%)及び指針値の10%値を超過する地点がある(295地点中8地点、超過率2.7%)(地下水実態調査結果、要調査項目存在状況調査結果)。
イ.指針値
Feronら(1981)のラットを用いた経口投与試験での肝細胞がん発症率に線形マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量は0.0875μg/kg/dayとなる。体重50kg、飲用水量2L/dayとして、指針値を0.002mg/Lとした。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
3.検討結果
(1)平成16年答申において課題としてあげられた事項についての検討(抄)
①塩化ビニルモノマーについて
ア 基本的な整理
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域における自治体の水質測定計画による調査及び環境省が実施した要監視項目等存在状況調査の結果(以下「公共用水域水質測定結果」という。)によると、現行の指針値を超過したものが、平成16年度、17年度、18年度にそれぞれ1箇所あるが、これらは、全て同一の地点における事例で、地下においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解したものが雨水管より漏洩したものであり、現地では既に漏洩防止策を講じ現在は指針値の超過は見られなくなっている。また、このほかには指針値を超える検出は、平成19年度に1箇所見られるが、同箇所で継続的な超過はみられない。現行指針値の10%を超えるものが毎年ある(1から10箇所)。
また、都道府県の地下水測定計画に基づく測定結果及び自治体独自で実施している地下水の水質調査結果(以下「地下水水質測定結果」という。)によると、指針値の超過事例が毎年あり(17から58箇所)、現行指針値の10%を超えるものは、平成16年度以降毎年数十箇所ある。これらのほとんどが、嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられるが、トリクロロエチレン等の汚染事例から推測すれば、同様の原因による塩化ビニルモノマーによる地下水汚染がさらにあるのではないかと懸念される。
このようなことから、当該物質について、公共用水域に関しては、引き続き要監視項目とし検出状況の把握につとめる必要がある。その際には、汚染された地下水の湧出による影響がないかあるいは工場事業所等からの排水等の影響がないか十分に留意すべきである。また地下水に関しては、あらたに地下水環境基準項目とすべきである。
イ 基準値等
現行の要監視項目としての指針値を改訂する新たな知見は平成16年答申後になく、現行の指針値である0.002mg/Lを公共用水域における要監視項目の指針値とするとともに、地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
(中略)
(別紙2)環境基準項目等(新規基準項目及び改訂項目)の設定根拠
1.塩化ビニルモノマー(抄)
(中略)
5.指針値の導出方法等
Feronら(1981)のラットを用いた経口投与試験での肝細胞がん発症率に線型マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量は0.0875μg/kg/dayとなる。体重50kg、飲用水量2L/dayとして、指針値を0.002mg/Lとした。
9.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○エピクロロヒドリン
1.指針値
0.0004mg/L以下
2.測定方法
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)の付表2に掲げる方法
3.設定経緯
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:刺激臭のある無色の液体
・比重:1.2(25℃/4℃)
・水への溶解性:60g/L(20℃)
・ヘンリー定数:3.08Pa-m3/mol(25℃)
・エピクロロヒドリンの蒸気圧は16.4mmHg(25℃)であり、大気中ではガス状で存在すると考えられる。大気中ではOHラジカルと反応し、半減期は36日と推定される。
・水中では、溶存態で存在する。予測される大気への揮散の半減期は、河川及び湖沼で、それぞれ、19時間および12日である。加水分解が起こり、その半減期は蒸留水で8.2日、模擬海水で5.3日である。また、化審法に基づく好気的生分解性試験(28日間)では、被験物質濃度100mg/L、活性汚泥濃度30mg/Lの条件において、BOD分解率は18%であったが、加水分解生成物の3-クロロ-1,2-プロパンジオールの同一の生分解試験において、BOD測定での分解率は68%であり、良分解性と判定されている。このことから、エピクロロヒドリンは、良分解性と判定されている(通商産業省, 1975)。
・また、オクタノール/水分配係数(logPow)が計算値で0.45~3.2であることから生物濃縮性は低いと考えられている(NITE&CERI初期リスク評価書, 2007)。
・土壌中では、小さなKocの値(40)から大きな移動性を持つと考えられる。湿った土壌(ヘンリー定数(3.04Pa-m3/mol))や乾燥土壌(高い蒸気圧)からの大気への揮散が容易に起こると考えられる。また、湿った土壌では加水分解が起こる。馴化した土壌や表流水では生分解が起こる。
(2)生産量等
(平成19年度)
・生産量111,308t 輸出量12,520t 輸入量17,225t
(3)主な用途
・エポキシ樹脂・合成グリセリン・界面活性剤等の合成原料、繊維処理剤、溶剤、可塑剤、安定剤
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準値(要検討項目目標値) 0.0004mg/L(暫定値)
・WHO飲料水質ガイドライン(第2版) 0.0004mg/L(暫定値)
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版) 0.0004mg/L(暫定値)
・EU飲料水水質基準 0.0001mg/L
6.環境への排出等の状況(PRTR)
(当初設定時)
<公共用水域>
(平成13年度)1,869kg、合計:97,116kg
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>
(平成19年度)5,332kg(下水道業を除く排出量:5,332kg)、合計:68,161kg
7.環境中における検出状況
(当初設定時)
<公共用水域>(指針値0.0004mg/L)
(要調査項目)
(平成12年度)76地点中超過2地点(2.6%) 10%値超過5地点(6.6%)
<地下水>(指針値0.0004mg/L)
(地下水実態調査)
(平成7年度)20井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過0井戸(0.0%)
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.0004mg/L)
(平成16年度)測定478地点、検出2地点、超過0地点、10%超過2地点
(平成17年度)測定538地点、検出8地点、超過2地点、10%超過4地点
(平成18年度)測定660地点、検出13地点、超過3地点、10%超過11地点
(平成19年度)測定684地点、検出11地点、超過:4地点、10%超過9地点
<地下水>(指針値0.0004mg/L)
(平成16年度)測定109地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成17年度)測定204地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成18年度)測定229地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
(平成19年度)測定222地点、検出0地点、超過0地点、10%超過0地点
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
公共用水域において指針値の超過が見られるものの限定的な検出状況であること、また、測定地点が少ないなどから、現時点においては、要監視項目として設定し、公共用水域等の検出状況等の知見の収集に努める必要がある。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.0004mg/L)を超過する地点(76地点中2地点、超過率2.6%)及び指針値の10%値(0.00004mg/L)を超過する地点がある(76地点中5地点。超過率6.6%)(要調査項目存在状況調査結果)。
地下水においては、指針値及び指針値の10%値を超過する地点はない(地下水実態調査結果)。
イ.指針値
Westerら(1985)のラットを用いた経口投与試験で、前胃の腫瘍が認められたLOAEL 2mg/kg/dayに発がん性を考慮し不確実係数10,000を適用して、TDIは0.14μg/kg/dayとなる。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、指針値を0.0004mg/Lとした。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域水質測定結果によると、指針値を超過するものが平成17年、18年及び19年に数箇所(2から4箇所)あり、地下水水質測定結果ではこれまで指針値を超過するものはない。現行指針値の10%を超過するものが、公共用水域では平成16年以降毎年あり(2から11箇所)、地下水では平成16年度以降はない。
指針値の根拠となる毒性情報に不確かさがあることから、公共用水域及び地下水ともに引き続き要監視項目とし、検出状況等の知見の収集に努める必要がある。
9.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○全マンガン
1.指針値
0.2mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。)
3.設定経緯
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:(マンガン)赤灰色又は銀色のもろい金属、(塩化マンガン)桃色単斜晶系結晶、(二酸化マンガン)黒銅色針状結晶又は無定型粉末、(過マンガン酸カリウム)暗紫色結晶、赤色金属光沢の斜方系稜状
・比重:(マンガン)7.2、(塩化マンガン)2.0、(二酸化マンガン)5.0、(過マンガン酸カリウム)2.7
・水への溶解性:(マンガン)不溶、(塩化マンガン)723g/L(25℃)、(二酸化マンガン)不溶、(過マンガン酸カリウム)5.1 g/L(25℃)
(環境中での挙動)
・元素状および無機のマンガンは大気中では浮遊粒子状物質として存在する可能性がある。地表水中では、マンガンは溶存および懸濁体として存在する。マンガンは遊離の金属では存在せず、多くの場合、酸化物等の化合物で存在する(IPCS, 1981)。環境中ではMn2+、Mn3+、Mn4+の電化状態が一般的であるが、水中では、Mn2+が最も安定であり、不溶性のMn3+、Mn4+化合物は有機物に還元されて水溶性のMn2+化合物になる(不破, 1986)。
・嫌気的条件の地下水では溶存態のマンガンレベルが上昇していることがある。pH4~7では、ほとんどの水中で2価の形態であるが、より高いpHではより高度に酸化された形態のものも出現する。マンガンは、有機物含量と陽イオン交換能に依存して土壌に吸着しうる。
・化審法に基づく過マンガン酸カリウムを用いた濃縮性試験では、水中濃度が0.1mgMn/L及び0.01mgMn/Lの条件で、BCF=8未満及び81未満であり、高濃縮性ではないと判定されている(経済産業省, 2002)。また、BCFの推定値として、近海魚では35~930との報告がある(Folsomら, 1963)。環境水中のマンガン濃度に影響を受けるものの、一般的には、藻類や甲殻類のような下等生物のBCFは大きく、魚類等の高等生物のBCFは小さいと考えられる(NITE&CERI初期リスク評価書, 2008)。
(2)生産量等
(平成19年)
・輸出量:66t(マンガン)、24,138t(二酸化マンガン)
・輸入量:91,080t(マンガン)、18,300t(二酸化マンガン)
(3)主な用途
(金属マンガン)ステンレス、特殊鋼の脱酸および添加材、銅などの非鉄金属の添加材
(塩化マンガン)染色工業、医薬品、塩化物合成の触媒、塗料乾燥剤
(二酸化マンガン)乾電池、酸化剤、フェライト、マッチ原料、ガラス工業、漂白剤原料
(過マンガン酸カリウム)マンガン・鉄などの除去剤、臭気・有機物の除去剤、繊維・樹脂等の原料
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準値(性状) 0.05mg/L
・水道水質基準値(水質管理目標設定項目目標値) 0.01mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第2版) 0.5mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版) 0.5mg/L
・WHO飲料水質ガイドライン(性状) 0.1mg/L
・U.S. EPA飲料水水質基準(性状) 0.05mg/L
・EU飲料水水質基準 0.05mg/L
6.環境への排出等の状況(PRTR)
(当初設定時)
<公共用水域>
(平成13年度)1,036,245kg、合計:4,637,753kg
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>
(平成19年度)814,951kg(下水道業を除く排出量:339,674kg)、合計:6,383,899kg
7.環境中における検出状況
(当初設定時)
<公共用水域>(指針値0.2mg/L)
(要調査項目)
(平成13年度)50地点中超過2地点(4.0%) 10%値超過29地点(58.0%)
(水道統計(原水:表流水・ダム・湖沼))
(平成12年度)1,296地点中超過97地点(7.5%) 10%値超過719地点(55.5%)
<地下水>(指針値0.2mg/L)
(地下水実態調査)
(平成7年度)20井戸中超過0井戸(0.0%) 10%値超過4井戸(20.0%)
(水道統計(原水:地下水))
(平成12年度)3,099井戸中超過224井戸(7.2%) 10%値超過698井戸(22.5%)
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.2mg/L)
(平成16年度)測定479地点、検出75地点、超過3地点、10%超過41地点
(平成17年度)測定808地点、検出649地点、超過31地点、10%超過364地点
(平成18年度)測定916地点、検出594地点、超過24地点、10%超過395地点
(平成19年度)測定889地点、検出543地点、超過20地点、10%超過432地点
<地下水>(指針値0.2mg/L)
(平成16年度)測定165地点、検出118地点、超過39地点、10%超過-地点
(平成17年度)測定272地点、検出108地点、超過24地点、10%超過71地点
(平成18年度)測定387地点、検出106地点、超過40地点、10%超過89地点
(平成19年度)測定465地点、検出134地点、超過33地点、10%超過93地点
8.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(答申抜粋)
人が高用量を摂取したとき神経毒性兆候を示すとの報告もあるが、通常の摂取量では毒性発現は見られない。米国IOM(Institute of Medicine)の食品栄養委員会(The food and Nutrition Board)によるNOAEL 0.22mg/kg/day(人での平均摂取量の最大値)に不確実係数3(水からのマンガンの生物学的利用可能度が上昇する可能性を考慮して)を適用し、TDIは0.073mg/kg/dayとなる。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、指針値を0.2mg/Lとした。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域水質測定結果によると、指針値を超過するものが平成16年度以降毎年あり(3から31箇所)、指針値の10%を超えるものが平成16年度以降毎年ある(41から432箇所)。地下水水質測定結果によると、指針値を超過するものが平成16年度以降毎年あり(24から40箇所)、指針値の10%を超えるものが平成17年度以降毎年ある(71から93箇所)。
地下水における指針値を超過する箇所の超過原因は、原因不明の事例を除き、還元状態における溶出等の自然由来と考えられている。
公共用水域における指針値を超過する水域における超過原因として、工場事業所からの排水の影響のみで超過すると明確に断定できる箇所はなく、自然由来による影響や有機汚濁により還元状態となった底質からの溶出による影響などが複雑に関係している。このため、今後とも監視を継続するとともに、環境中でのマンガンについて人為由来かあるいは自然由来かに係る調査やバックグラウンド濃度の状況や底質を含む水環境中での動態等に関する調査をさらに行ったうえで、再度全マンガンの取り扱いを検討すべきである。
9.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○ウラン
1.指針値
0.002mg/L以下
2.測定方法
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)の付表4の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
4.基礎情報(見直し検討時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・物理的性状:(ウラン)黒~茶色の結晶あるいは黒~茶色の粉末、(二酸化ウラン)黒~茶色の結晶あるいは黒~茶色の粉末、(六フッ化ウラン)無色~白色の潮解性結
・比重:(ウラン)19.0、(二酸化ウラン)11.0、(六フッ化ウラン)5.09
・水への溶解性:(ウラン)不溶、(二酸化ウラン)不溶、(六フッ化ウラン)反応する
・ウランは、天然鉱物からの浸出、原子力産業からの排出、石炭等の燃料の燃焼、ウランを含むリン酸肥料の使用などによって環境中に存在する。
・水環境においては4価及び6価の状態で存在する(ATDSDR, 2000)。
(2)生産量等
(平成18年)
・輸入量:702t(天然ウラン)、840t(濃縮ウラン)、27t(劣化ウラン)
・輸出量:4kg(劣化ウラン)
(3)主な用途
・主に原子核燃料
5.毒性情報及び各種基準値(見直し検討時)
・水道水質基準値(水質管理目標設定項目目標値) 0.002mg/L(暫定値)
・WHO飲料水質ガイドライン(第2版) 0.002mg/L(暫定値)
・WHO飲料水質ガイドライン(第3版) 0.015mg/L(暫定値)
・U.S. EPA飲料水水質基準 0.03mg/L
6.環境中における検出状況
(当初設定時)
<公共用水域>(指針値0.002mg/L)
(要調査項目)
(平成13年度)50地点中超過4地点(8.0%) 10%値超過12地点(24.0%)
<地下水>(指針値0.002mg/L)
(地下水実態調査)
(平成10年度)139井戸中超過2井戸(1.4%) 10%値超過3井戸(2.2%)
(平成21年・見直し検討時)
<公共用水域>(指針値0.002mg/L)
(平成16年度)測定466地点、検出123地点、超過47地点、10%超過79地点
(平成17年度)測定567地点、検出274地点、超過93地点、10%超過168地点
(平成18年度)測定652地点、検出217地点、超過75地点、10%超過162地点
(平成19年度)測定743地点、検出199地点、超過61地点、10%超過146地点
<地下水>(指針値0.002mg/L)
(平成16年度)測定154地点、検出74地点、超過0地点、10%超過6地点
(平成17年度)測定230地点、検出30地点、超過1地点、10%超過18地点
(平成18年度)測定252地点、検出24地点、超過0地点、10%超過10地点
(平成19年度)測定272地点、検出20地点、超過0地点、10%超過10地点
7.指針値の根拠の概要
(当初設定時)(答申抜粋)
3.検討結果(抄)
公共用水域等において指針値の超過が見られるが、測定地点が少なく、また、汚染源が不明で自然的要因と考えられる事例もあることから、現時点においては、要監視項目として設定した上で、公共用水域等での挙動、検出地点における原因究明など今後とも知見の収集に努める必要がある。
ア.検出状況
公共用水域において、指針値(0.002mg/L)を超過する地点(50地点中4地点、超過率8.0%)及び指針値の10%値(0.0002mg/L)を超過する地点がある(50地点中12地点、超過率24.0%)(要調査項目存在状況調査結果)。
地下水において、指針値を超過する地点があり(139地点中2地点、超過率1.4%)、指針値の10%値を超過する地点がある(139地点中11地点、超過率7.9%)(地下水実態調査結果)。
イ.指針値
Gilmanら(1998)のラットを用いた飲水投与試験で、最低用量で腎毒性が見られたことからLOAEL 0.06mg/kg/dayに不確実係数100(この用量での変化が最小限であることを考慮して)を適用し、TDIは0.0006mg/kg/dayとなる。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして指針値を0.002mg/Lとした。
(平成21年・見直し検討時)(答申抜粋)
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域水質測定結果によると、河川に関して平成16年、18年及び19年に数箇所の指針値超過が見られ、海域に関しては平成16年度以降毎年数十箇所(43から93箇所)で指針値超過が見られる。地下水水質測定結果によると、平成17年に1箇所指針超過が見られる。公共用水域、地下水ともに平成16年以降毎年多数の箇所で指針値の10%値超過が見られる。
河川における超過事例は、ほとんどが海水の影響を受けたものと考えられ、その他は地質由来の影響と考えられる。海域においては海水中に含まれる自然由来のウランが影響をしていると考えられる。地下水については測定箇所が海域に近い場所であるため、海水の影響と考えられる。現状では人為的な汚染は見られないことから、今後とも公共用水域及び地下水ともに要監視項目として監視を行っていくべきである。
8.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
1.指針値
0.00005mg/L以下(暫定)(PFOS及びPFOAの合計値とする。)
2.測定方法
令和2年5月28日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号)の付表1に掲げる方法
3.設定経緯
令和2年5月27日・中央環境審議会答申
令和2年5月28日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
○PFOS
※特記しない限り、カリウム塩の値
・物理的性状:無色の液体で、水より重い。臭気があり不燃性である。揮発性有機化合物。
・融点:>400℃
・沸点:不明
・蒸気圧:0.85Pa(酸、25℃、MPBPWIN)、1.9×10-9Pa(25℃、MPBPWIN)
・logPow:4.49(U.S. EPA、推定値)、実測不可(ATSDR)、2.57(デンマーク水理環境研究所:DHI)
・水溶解度:519mg/L(20±0.5℃)、680mg/L(24~25℃)、570mg/L、370mg/L(淡水)、12.4mg/L(未ろ過海水)、25mg/L(ろ過海水)、12.4mg/L(天然海水、22~23℃)、20.0mg/L(3.5%NaCl溶液、22~24℃)
・土壌吸着定数(Kd):18.3(粘土)、9.72(ClayLoam)、35.3(SandyLoam)、7.42(河川底質)
・土壌吸着定数(Koc):374(ClayLoam)、1,260(SandyLoam)、571(河川底質)
・生分解性:(分解率)BOD 0%、TOC 6%、LC-MS 3%、試験期間:4週間、被験物質濃度:100mg/L、活性汚泥濃度:30mg/L
・光分解性:25℃における間接光分解の半減期は3.7年以上
・加水分解性:分解はまったく示さない、半減期は41年以上
・生物濃縮係数(BCF):2.0~4.2(試験生物:コイ、試験期間:28日間、試験濃度:50μg/L)、<5.1~9.4(試験生物:コイ、試験期間:28日間、試験濃度:5μg/L)
○PFOA
・物理的性状:個体で水溶性である。空気中に揮発しにくい。
・融点:54.3℃(酸)、157~165℃(165℃で20%が分解)
・沸点:188℃(酸、760mmHg)、189℃(酸、736mmHg)
・蒸気圧:0.031mmHg(=4.2Pa)(酸、25℃、外挿値)、0.02mmHg(=3Pa)(酸、20℃、外挿値)、6×10-5mmHg(=8×10-3Pa)(20℃、外挿値)
・logPow:2.06(デンマーク水理環境研究所:DHI)、4.81(U.S. EPA、推定値)、6.3(国際労働機関:ILO)
・水溶解度:9.5×103mg/L(酸、25℃)
・土壌吸着定数(Kd):4.25~8.86(土壌(Drummer))、0.41~0.83(土壌(Hidalgo))、1.19~2.84(土壌(CapeFear))、1.82~4.26(土壌(KeyPort))
・土壌吸着定数(Koc):73.8~111(土壌(Drummer))、53.0~108(土壌(Hidalgo))、95.9~229(土壌(CapeFear))、48.9~115(土壌(KeyPort))
・生分解性:BOD 5%、TOC 3%、HPLC 0%(酸として)、BOD 7%、TOC 0%、HPLC 0%(アンモニウム塩として)、試験期間:4週間、被験物質濃度:100mg/L、活性汚泥濃度:30mg/L
・光分解性(OHラジカルとの反応性(大気中)):半減期130日(F(CF2)2COOH~F(CF2)4)
・加水分解性:半減期:235年(外挿値、25℃、速度定数はpHが5.0、7.0、9.0の各試験を纏めて算出)
・生物濃縮係数(BCF):ニジマス:BCF=2,900(肝臓)、3,100(血漿)、丸ハゼ:BCF=約2,400(全魚体)、210~850(試験生物:コイ、試験期間:58日間、試験濃度:20μg/L)、200~1500(試験生物:コイ、試験期間:58日間、試験濃度:2μg/L)、1,124(試験生物:ブルーギル(可食部)、試験期間:62日間、試験濃度:86μg/L)、4,013(試験生物:ブルーギル(非可食部)、試験期間:62日間、試験濃度:86μg/L)、2,796(試験生物:ブルーギル(魚全体)、試験期間:62日間、試験濃度:86μg/L)
(2)生産量等
・PFOS、PFOAについては直近の製造輸入なし
(3)主な用途
・(PFOS)半導体工業、金属メッキ、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真工業、泡消火剤
・(PFOA)繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・EFSA(2018)
TWI 13ng/kg/week(PFOS)、6 ng/kg/week(PFOA)
・U.S. EPA(2016)
TDI 20ng/kg/day(PFOS、PFOAの合計として)
目標値 70ng/L(割当率20%、PFOS、PFOAの合計として)
・カナダ Health Canada(2018)
TDI 60ng/kg/day(PFOS)、21ng/kg/day(PFOA)
目標値 600ng/L(割当率20%、PFOS)、200ng/L(割当率20%、PFOA)
6.環境中における検出状況(設定時)
<公共用水域>(指針値50ng/L)
(平成24年度)測定95地点、検出95地点、超過1地点
(平成25年度)測定92地点、検出92地点、超過1地点
(平成26年度)測定91地点、検出91地点、超過0地点
(平成27年度)測定48地点、検出48地点、超過0地点
(平成28年度)測定48地点、検出48地点、超過0地点
<地下水>
上記年度において測定なし
7.指針値の根拠の概要(答申抜粋)
1.はじめに(抄)
ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)については、その有害性や蓄積性等から、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)の第4回締約国会議において平成21年5月に附属書B(制限)への追加掲載が決定され、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の改正(平成22年4月1日施行)により第一種特定化学物質に指定された。
ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)については、昨年4月29日から5月10日にかけて開催されたPOPs条約の第9回締約国会議において、附属書A(廃絶)に追加されることが決定した。
我が国の水道水の水質管理に係る枠組みにおいては、PFOS及びPFOAは、これまで要検討項目(毒性評価が定まらない物質や水道水中の存在量が明らかでない物質等を対象とした項目で、知見・情報の収集に努めていくべきもの)として位置づけられてきたが、近年、各国・各機関において、飲料水の目標値の設定に関する動きがあり、知見が蓄積しつつあることや、我が国における水道水からの検出状況などを踏まえ、厚生労働省は、浄水施設における水道水の水質管理を適切に行う観点から、PFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に位置づけ、PFOS及びPFOAの合計値として暫定目標値50ng/Lを、令和2年4月1日に施行した。
環境省においては、平成26年3月にPFOS及びPFOAを要調査項目に位置付け、これまで知見の集積を図ってきたところであるが、このような状況も踏まえ、PFOS及びPFOAに関する最新の知見や水環境中における検出状況等を整理し、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等における取扱いの見直しを行い、今般、その結果を取りまとめた。
(中略)
3.検討結果(抄)
(中略)
(1)目標値について
従来、水質環境基準等において、目標値(基準値または指針値)を設定する場合は次の式に基づいて設定している。
目標値[ng/L]=耐容一日摂取量[ng/kg/day]×体重[kg]×水の飲用に係る寄与率[%]/1日当たりの摂取量[L/day]
1)水の飲用に係る寄与率(割当率)
従来、水質環境基準等を設定する際に水の飲用に係る寄与率(割当率)(以下「寄与率」という。)には、様々な曝露経路(主に食品、飲料水)からの摂取の割合に関する適切な情報が得られない場合は10%が採用されてきた。PFOS及びPFOAについては、食品群(魚貝類、藻類、肉類、乳製品、卵製品、野菜製品、果実製品等)及び生物からの検出事例が報告されており、必ずしも水からの摂取が主要な曝露経路であるとする明確な根拠は今のところないことから、寄与率は同様の場合においてこれまで採用してきた10%を用いることが適当である。
2)体重及び1日当たりの摂取量、耐容一日摂取量
体重及び1日当たりの摂取量については、従来通り50kg及び2L/dayを用いることが適当である。また、耐容一日摂取量(以下「TDI」という。)については、厚生労働省が水道水の暫定目標値を設定した際と同じ考え方を採用し、近年、各国・各機関が行った毒性評価のうち妥当と考えられる評価値の中から、安全側の観点より最も低い値を採用することとし、PFOSについては、米国がラット2世代試験で得られた母動物を交配前から授乳期まで強制経口投与した場合の児動物における体重減少を根拠にした無毒性量(以下「NOAEL」という。)0.1mg/kg/dayを、生理学的薬物動態モデル(以下「PBPKモデル」という。)で補正したヒト曝露量相当のNOAEL 0.00051mg/kg/dayに不確実係数30を適用して、参照用量(以下「RfD」という。)として設定した20ng/kg/dayを採用した。また、オーストラリア・ニュージーランド食品基準機構(FSANZ)も米国(USEPA)と同様にラットの2世代試験結果を用いており、NOAELも母体及び児の体重増加減少を根拠に0.1mg/kg/dayとし、NOAELの平均血清濃度(7.14mg/L)とクリアランスからヒト曝露量相当のNOAELとして0.0006mg/kg/dayを求め、米国(USEPA)と同様の不確実係数30を適用してTDIを20ng/kg/dayと算出している。
PFOAについては、米国(USEPA)が、Lauら(2006)により報告されたマウスの妊娠期強制経口投与曝露による胎仔の前肢近位指節骨の骨化部位数の減少や雄の出生仔の性成熟促進を根拠にした最小毒性量(以下「LOAEL」という。)1 mg/kg/dayからPBPKモデルで補正したヒト曝露量相当のLOAEL 0.0053mg/kg/dayを求め、不確実係数300を適用してRfDとして設定した20ng/kg/dayを採用した。
3)目標値の導出
以上のことから、PFOS及びPFOAともに、その目標値は以下のとおり導出される。
目標値[ng/L]=20[ng/kg/day]×50[kg]×0.1/2[L/day]=50ng/L
なお、米国(USEPA)では、PFOSとPFOAの総濃度(合計値)を生涯健康勧告値70ng/Lとしているが、この理由として、PFOSとPFOAのRfDは類似の発達影響に基づいて算出されていること、また、飲料水中にPFOSとPFOAは同時に見られることから、安全側の観点から合計値として生涯健康勧告値を導出しており、厚生労働省でも同様の考え方を採用して、PFOS及びPFOAの合計値を暫定目標値として設定している。
PFOS及びPFOAは水環境中においては異なる挙動を示すといった明確な根拠は今のところ報告されていないことから、安全側の観点から目標値の導出においてもPFOSとPFOAの合計値として50ng/Lとすることが適当である。
(2)要監視項目に位置付けることについて
水質環境基準健康項目及び要監視項目の選定の考え方等については、2.(2)(略)に記載された考え方を基本としており、人の健康への影響を評価した毒性情報等に関する知見については米国(USEPA)、欧州食品安全機関(EFSA)、オーストラリア・ニュージーランド食品基準機構(FSANZ)等で様々な有害性評価値が提案されるなど、ある程度の知見が集積しつつある。
また、我が国における生産・使用等の実態等については、国内外の法規制等を受け、我が国における排出源は限定されているものと考えられるが、水環境中における検出状況については公共用水域及び地下水から検出される状況が確認されており、水環境中における検出状況については引き続き注視する必要があることから、要監視項目に位置付けることが適当である。
(3)指針値(暫定)とすることについて
我が国の水環境に係る基準値及び指針値、特に直接飲用による影響については、WHOの飲料水の水質ガイドライン値の設定の際に採用している方法等を基に検討を行ってきた。しかし、PFOS及びPFOAについては、現時点で飲料水の水質ガイドライン値は設定されていない。また、近年、各国・各機関において、毒性評価や目標値等の設定が行われており、一定の知見が蓄積されつつあるものの、TDIの値は各国・各機関において相当のばらつきが見られている状況であり、国際的にもPFOS及びPFOAの評価が大きく動いている時期でもある。
他方、我が国においては公共用水域及び地下水からPFOS及びPFOAが検出される状況が確認されており、監視強化の観点からも目安となる値を示すことは意義があると考えられることから、現時点で毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であるものの、各国・各機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考に、指針値(暫定)とすることが適当である。
8.参考資料
・令和2年5月27日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0202.pdf 【NIES保管ファイル】
(3)生活環境の保全に関する環境基準(水生生物保全関係以外の項目)及び地域環境目標
①設定の考え方
(昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」より)(抜粋)
第1 環境基準設定の基本原則
水質汚濁に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)は、基本的には、次の原則に則して設定するものとする。
ア 環境基準は、公害対策基本法第9条の規定に基づき、国民の健康を保護しおよび生活環境(公害対策基本法第2条第2項でいう生活環境とする。以下同じ。)を保全するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであること。
イ 環境基準は、公共用水域の水質汚濁防止のために各般にわたり講じられる行政の目標として設定されるものであること。
ウ 環境基準は、国民の健康の保護に係る場合は、常に維持されるべきものであり、また、生活環境の保全に係る場合は、公共用水域が通常の条件の下にある場合において維持されるべきものであること。
エ 環境基準は、諸般の状況にかんがみ、直ちに達成することが困難と考えられる場合においては、達成すべき期限を明らかにし、その期限内における達成が期せられるべきものであること。
第2 環境基準設定の方式(抄)
(中略)
2 生活環境の保全に係る環境基準
(1)これについては、次に掲げる理由から水域の利水の態様を共通にする水域群ごとに設定することとする。
ア 各公共用水域の利水目的は、極めて多岐多様であり、将来の利水目的をも勘案して設定されるべき環境基準を全国一律で設定することは、行政目標として適当でないと考えられること。
(中略)
(2)水域群の設定は、具体的には、次により行なうこととする。
ア 公共用水域の利用の態様を拠りどころとして、別表2(略)の水域類型の欄に掲げるとおり、水域類型を作成する。
イ 水質汚濁防止を図る必要がある公共用水域のすべてにつき、次に掲げる事項に十分留意しつつ、それぞれが該当する水域類型を指定することとする。
(ア)水質汚濁に係る公害が著しくなっており、または著しくなるおそれのある水域を優先すること。
(イ)当該水域の現在の利用目的および将来の利用目的の推移につき配慮すること。
(ウ)当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
(エ)当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
(オ)目標達成のための施策との関連に留意しつつ、その達成期間につき配慮すること。
(中略)
第4 環境基準の一環として定めるべき事項(抄)
(中略)
1 公共用水域の水質の測定方法
環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。
(中略)
イ 生活環境の保全に係る項目については、6時間間隔で1日に4回程度測定すること(河川にあっては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあっては低水位以上の推移等通常の状態にある場合に限り行うものとする。)とすること。なお、この場合、河川及び湖沼については、渇水時等通常な状態とはいえない場合についても、参考資料を得るため、適宜測定を行うこととする。
(中略)
2 環境基準の達成期間及び達成の方途
(1)国民の健康の保護に係る環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。
(2)生活環境の保全に係る環境基準は、おおむね、次の区分により、3の施策の推進とあいまちつつ、可及的速やかにその達成維持を図るものとする。
ア)現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質汚濁が生じているもの、または生じつつあるものについては、5年以内に達成することを目処とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。
イ)水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、アの水域以外のものについては、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。
(中略)
第5 環境基準の見直し
環境基準は、次により適宜改定することとする。
ア)科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等
イ)水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域の変更
ウ)水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等
(参考資料)
・昭和45年3月31日・水質審議会「水質汚濁に係る環境基準の設定の基本方針について(答申)」 【NIES保管ファイル】
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
| 項目 | 基準値(類型ごとに異なる) | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 河川:6.0~8.5 湖沼:6.0~8.5 海域:7.0~8.3 | 昭和46年12月28日 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 河川:≦1~10mg/L | 昭和46年12月28日 | |
| 化学的酸素要求量(COD) | 湖沼:≦1~8mg/L 海域:≦2~8mg/L | 昭和46年12月28日 | |
| 浮遊物質量(SS) | 河川:≦25~100mg/L 等 湖沼:≦1~15mg/L 等 | 昭和46年12月28日 | |
| 溶存酸素量(DO) | 河川:2~7.5mg/L≦ 湖沼:2~7.5mg/L≦ 海域:2~7.5mg/L≦ | 昭和46年12月28日 | |
| 大腸菌数 | 河川:≦20~1,000CFU/100mL 湖沼:≦20~300CFU/100mL 海域:≦20~300CFU/100mL | 令和3年10月7日 | 当初「大腸菌群数」から改定(令和4年4月1日施行) |
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 海域:検出されないこと | 昭和46年12月28日 | |
| 全窒素 | 湖沼:≦0.1~1mg/L 海域:≦0.2~1mg/L | 湖沼:昭和57年12月25日 海域:平成5年8月27日 | |
| 全燐 | 湖沼:≦0.005~0.1mg/L 海域:≦0.02~0.09mg/L | ||
| 底層溶存酸素量 (底層DO) | 湖沼・海域:2.0~4.0mg/L≦ | 平成28年3月30日 |
(評価方法)(常時監視等の処理基準抜粋)
第2 水質汚濁防止法関係
1.常時監視(法第15条関係)(抄)
(中略)
(3)測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合
(中略)
2)生活環境の保全に関する環境基準
①BOD、CODの環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価
ア.類型指定された水域におけるBOD及びCODの環境基準の達成状況の年間評価については、環境基準点において、以下の方法により求めた「75%水質値」※2が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
※2 75%水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値をもって75%水質値とする。(0.75×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)
(中略)
ウ.複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
②大腸菌数の環境基準の達成状況の評価
ア.大腸菌数については、類型指定により区分された水域ごとに達成又は非達成の評価を行うことは要しないが、個々の環境基準点において、環境基準に適合しているか否かを判断する。
イ.大腸菌数の環境基準の達成状況は、環境基準点において、以下の方法により求めた「90%水質値」※3が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、環境基準を達成しているものと判断する。
※3 90%水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値をもって90%水質値とする。(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)
③湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
ア.湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
イ.複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
④海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価
ア.海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
イ.複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
⑤湖沼及び海域における底層溶存酸素量の環境基準の達成状況の評価
令和3年底層DO答申※2.(3)及び2.(4)を参考として、類型区分された水域ごとに判断すること。
※令和3年7月30日・中央環境審議会「底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(答申)」
(中略)
イ.測定頻度
(ア)環境基準項目
(中略)
イ)生活環境の保全に関する環境基準項目については、次によることとする。
a.通年調査
環境基準点、利水上重要な地点等で実施する調査にあっては、年間を通じ、月1日以上、各日について4回程度採水分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。なお、底層溶存酸素量の調査に当たって、可能であれば、水生生物の生息・再生産の場を保全・再生するうえで重要な地点においては連続測定調査を行うことが望ましい。
b.通日調査
a.の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあっては、年間2日程度は各日につき2時間間隔で13回採水分析することとする。
c.一般調査
前記以外の地点で補完的に実施する調査にあっては、年間4日以上採水分析することとする。
(参考資料)
・令和3年10月7日・環境省水・大気環境局長「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(環水大水発第2110073号・環水大土発第2110073号) https://www.env.go.jp/hourei/add/e82.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月30日・中央環境審議会「底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0304.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○河川(湖沼を除く。):水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数
1.基準値
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 | ||
| AA | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 |
| A | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
| B | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU/100mL以下 |
| C | 水道3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | - |
| D | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | - |
| E | 工業用水3級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | - |
(備考)
1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
3 (略)
4 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
5 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
6 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
(注)
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
2.測定方法
・pH:日本産業規格K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置※によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・BOD:日本産業規格K0102の21に定める方法
・SS:昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表9に掲げる方法
・DO:日本産業規格K0102の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置※によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・大腸菌数:昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表10に掲げる方法
※水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和45年4月21日・閣議決定(大腸菌群数を除く)
昭和45年5月29日・大腸菌群数を追加
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定:大腸菌数)
令和3年7月19日・中央環境審議会答申
令和3年10月7日・環境省告示第62号(令和4年4月1日施行)
4.基準値の根拠の概要
(1)水素イオン濃度(pH)(審議会配付資料抜粋)
通常、日本の河川のpHは、感潮域を除けば7.0前後である。例えば厚生省調査による昭和42年度に1日平均5,000 m3以上取水した水道事業で表流水を水源とするところのpHは(表-1(略)、表-2(略))のようになっており、pH7.0前後の水質が多いことがわかる。また、水道用水としてpHが8.5をこえると化学反応面からいって塩素殺菌力が低下し、一方6.5以下であると、処理を行う上で凝集効果に悪影響を及ぼすと言われている。またこの6.5~8.5の範囲は、水道管や給水装置の腐食防止の面でも望ましい数値といえる。
また、水浴についても、アメリカ合衆国内務省による水質汚濁に関する調査資料によるとpHがこの範囲を逸脱すると眼に対して刺激を与えるとしている。
水産動植物の生育、増殖の面からすれば、農林省の水産増殖資料によると、最も生産的な河川のpHは大部分6.5~8.5の間にある。これを超すと、栄養素の多くは結合しはじめ、植物に摂取されなくなり、飼料生物の生産性は低下し、ひいては全体の生産性が低下するとしている。
農作物のうち、特に水稲に与える影響としては、実験的データおよび一般的傾向として、生育に適したpH値は6.0~7.5の範囲といわれる。pHが低いと、稲は根の発育不良、土壌中の塩基の流亡による土壌の老朽化等により生育不良となる。一方、pHが高すぎると、鉄欠乏をおこし、黄化現象を呈するが、pH8程度でも草勢(草丈×茎数)、茎数、着粒穂長、枝梗、頴花数等種々の面で生産性の低下を来たす。(表-3(略)、表-4(略)参照)
(2)生物化学的酸素要求量(BOD)(審議会配付資料抜粋)
河川の水質汚濁の一般指標としては、CODよりむしろBODの方が汚濁の状況を明確に表わしていると考えられる。
BOD 1ppm以下の河川は、一般的にいって、自然公園内等ほとんど人為汚染のない河川であり、自然景観の面からすれば、もっとも適しているといえる。
水道用水の取水現状を上水道(給水人口5,000人以上の水道)について見た場合、(表-5(略))のようになっており、BOD 1ppm以下の水道が水源数で全体の40%、取水量で30%になっている。この数値は、給水人口5,000人以上の水道を対象にしたものであり、これより給水人口の少ない簡易水道については、その水源の大半がBOD 1ppm以下の水源から取水していると考えられる。また簡易水道等小規模水道においては、その管理能力にも乏しく、水質の安全性の面からいって、BOD 1ppm以下が適当と考えられる。また、同じく、参考(表-5(略))によると、BOD 3ppm以上の水源数は全体の約8%、水量で約14%となっており、それ以下はすべて3ppm以下の水を給水していると推定される。「厚生省令」の飲料水水質基準の項目にBODは含まれていないが、一般の汚濁指標として取り上げた場合、浄水処理過程でBOD 3ppm以上の水質を飲料水に適する水質にすることは、通常、一般の処理方法では難しいと考えられる。
また、河川の自浄機能を考慮すれば、正常な河川環境の保全の立場からは、BOD 4ppm程度が必要とされている。
水産動植物に対するBODの影響については、貧腐水性水産生物のうちでも谷川等の清水性の水域に住むヤマメ、イワナ等についてはBOD 2ppm以下、アユ、サケ等貧腐水性生物については3ppm以下が、また、中腐性の水域に生育するコイ、フナ等については5ppm以下であることが必要と考えられる。
また、環境保全の面では臭気限界からいって、DOとの関連で考えればBOD 10ppm以下が適当である。
(3)浮遊物質量(SS)(審議会配付資料抜粋)
河川における浮遊物質量は、主として水産生物の生育が問題となる。水産部門の研究及び一般的見地によると、25ppm以下であれば正常な生産活動が維持でき、また50ppm以下であれば、魚類のへい死等の被害発生は防止されるとされている。
また、清浄な河川といえども自然汚濁により25ppm程度になることは予想される。
水道用水としては緩速ろ過方法による場合は、その設計施設基準によると、一般に濁度30度以下が理想的であると言われており、これをSS 30ppmとすれば、25ppmはこの範囲内にある。
農業用水に対するSSの影響は、珪砂、産業排水等の無機質微粒子の流入堆積により土壌の透水性が悪化することにより、生育が阻害される。これについては、福岡および愛知農試の成績から厚さ3cmの堆積が許容限度であり、これからして用水中のSSは100ppm以下となる。
環境保全の観点からすれば、日常生活において不快感を生じない限度としてごみ等の浮遊が認められない方が適当と考えられる。
(4)溶存酸素(DO)(審議会配付資料抜粋)
資源調査会の水質汚濁防止に関する勧告(昭26.1)※によると、その等級分類の中で比較的水質の良好な水域については7.5ppm以上となっている。(表-8(略))
水産用水の面からすれば、サケ、マス等のふ化の際の環境条件としてはDO 7.0ppm以上が適当であり、その他一級の水産生物の成育は6.0ppm以上が適しているという説もあるが、一方また、オハイオ河の水産用水の流水基準は5.0ppm以上となっている。
また、農業用水としては、5ppm以下であると、根ぐされ等の障害が生ずるとしている。(参考(略)参照)
環境保全上の基準としては嫌気性醗酵を防止し、臭気が生じない限度として2ppm以上が適当である。
※原文に変更を加えている
(5)大腸菌数
(当初設定時)(大腸菌群数)(審議会配付資料抜粋)
「厚生省令」では、飲料水中の大腸菌群数は「検出されないこと」となっており、厚生省生活環境審議会の答申によると、水道で行う塩素滅菌により死滅させうる大腸菌群数の安全限界値は50MPN/100mLであるとしている。一方、水道における浄水処理による大腸菌群の除去率は、緩速ろ過処理では約99%、急速ろ過処理では通常の管理下においても約95%、高水準管理下において約98%とされている。
このことから、通常の浄水操作を想定した水道2級では、1,000MPN/100mLが、また高度な浄水操作を想定した水道3級では2,500~5,000MPN/100mLが水道原水としての安全限界と言える。また、厚生省の調査によると、別図(略)のように現在水道で取水している表流水では1,000MPN/100mL以下のものが最も多く、5,000MPN/100mLを超過するものは特異であるという結果になっている。
また、同じく厚生省生活環境審議会の答申では、「水浴場」の基準としては、大腸菌群数は1,000MPN/100mL以下が適当であるとしている。
以上のことから、大腸菌群数の基準値は、生活環境に係る環境基準として、AA類型50MPN/100mL以下、A類型1,000MPN/100mL以下、B類型5,000MPN/100mL以下とするのが適当であるとされたものである。
(令和3年・改定時)(答申抜粋)
2.生活環境項目としての環境基準の大腸菌群数の見直しについて(抄)
(中略)
(2)今回の検討事項
1)生活環境項目環境基準における大腸菌群数の課題
大腸菌群数の測定には、ふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌も含まれると考えられ、実際に、環境省が実施した水質調査結果(参考資料の2.(2)(略))によると、水環境中において大腸菌群が多く検出されていても、大腸菌が検出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみられた。
2)基本的考え方
水道水質基準では、大腸菌がふん便汚染の指標として適当と判断されたが、当時の培養技術では大腸菌のみを簡便に検出する技術はなかったことから、大腸菌群が採用された。今日では、簡便な大腸菌の培養技術の確立により、水道水質基準が改正され、大腸菌群に代わり大腸菌がふん便汚染の指標として採用されている。
このことから、生活環境項目環境基準における衛生微生物指標としては、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標として大腸菌数が一つの候補として考えられる。その他、候補になり得る指標として、わが国の水浴場の水質判定基準ではふん便性大腸菌群数、米国(USEPA)のRecreational Water Quality Criteriaや欧州連合のBathing Water Directiveでは水浴水質基準として腸球菌がある。
しかしながら、このうちふん便性大腸菌群は、温血動物のふん便中の大腸菌が一般に高温耐性であることから、高温培養して大腸菌群の中からふん便由来の細菌類の検出を目的として設定されたものである。このため、大腸菌群よりふん便汚染としての指標性は高いものの、この条件で測定した場合でもふん便汚染を受けていない水や土壌に存在する細菌が検出される場合があることから、大腸菌よりふん便汚染の指標性は低い。
また、腸球菌は、ふん便汚染の指標として、大腸菌群やふん便性大腸菌群より指標性が高いとされており、米国(USEPA)や欧州連合では、腸球菌と水泳者の胃腸疾患等の罹患率の関係から導出された腸球菌が水浴水質基準として採用されている。一方で、環境省が国内の海域において実施した水質調査結果(参考資料の2.(4)(略))によれば、腸球菌が検出された地点は少なく、検出された地点においてもその値は大腸菌数に比べて非常に小さく、衛生微生物指標として腸球菌を採用することは難しいと考えられる。
以上より、生活環境項目環境基準の大腸菌群数については大腸菌数へ見直すことが適当である。
3.大腸菌数の環境基準値設定の検討について
(1)大腸菌数の環境基準値設定の基本的考え方
生活環境項目環境基準における大腸菌数の環境基準値の設定にあたっては、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することとした。
(2)大腸菌数の環境基準値の導出方法
各利用目的の適応性における大腸菌数の環境基準値の導出方法は以下の通りである。
1)水道1級、水道2級、水道3級
・大腸菌群数の環境基準値設定時に、水道利用については、各水道等級の浄水処理方法における水道原水の安全限界値から設定されていたが、浄水場の現状を踏まえると、同様の考え方による設定は実態に即していない。
・大腸菌は水道水質基準の一つの項目として位置づけられており、水道原水となりうる河川及び湖沼の大腸菌の存在状況を把握する必要性は高い。また、生活環境項目環境基準として位置付けることで、河川及び湖沼において大腸菌数が一定のレベル以下となるよう水環境に係る施策が講じられることが期待され、これにより水道原水に係る汚濁対策の推進につながる。そのため、引き続き、水道利用の観点から大腸菌数の環境基準値を設定することとした。
・具体的な数値については、水道1級相当、水道2級相当、水道3級相当の浄水処理方式を導入している浄水場原水の大腸菌数の実態(年間の測定値の90%値)の分布から(参考資料の3.(略))、水道1級は100CFU※/100mL以下、水道2級は300CFU/100mL以下、水道3級は1,000CFU/100mL以下を導出した。
※コロニー形成単位(Colony Forming Unit)の略
2)水浴
・米国(USEPA)では水泳者の胃腸疾患と罹患率の関係から導出された大腸菌数が水浴水質基準として採用されている(参考資料の4.(略))。この値を参考に300CFU/100mL以下を導出した。
3)自然環境保全
・現行の大腸菌群数の基準値設定には自然環境保全の利用目的は考慮されていない。一方、現行のBODの環境基準値設定時には、BODのAA類型の利用目的として自然環境保全が考慮されており、その考え方は「BOD 1mg/L以下の河川は一般的にいって、自然公園内等ほとんど人為的汚濁のない河川であり、自然景観の面からすれば、もっとも適しているといえる。」とされている。
・大腸菌数についても自然環境保全の利用の観点から、ほとんど人為汚濁のない清涼な水環境を目指す値を設定することには意義があると考え、AA類型において自然環境保全の観点から環境基準値を導出することとした。
・海域A類型においても自然環境保全の観点から考え、現在自然公園等に指定されている水域の水質を保全していくことには意義がある。
・具体的には、人為的なふん便汚染が極めて少ないと考えられる地点の大腸菌数の実測値から(参考資料の5.(1)(略))、河川・湖沼は20CFU/100mL以下、自然公園等に指定されている海域の大腸菌数の実測値から(参考資料の5.(2)(略))、海域は20CFU/100mL以下を環境基準値として導出した。
なお、環境基準の利用目的の適応性の欄に水産があるが、現時点で公共用水域における大腸菌数の水産への影響について整理された知見はないことから、今般の見直しに当たり、水産利用の観点から大腸菌数の環境基準値の検討は行っておらず、引き続き大腸菌数の水産への影響に関する知見の集積に努めていく。
(中略)
(5)大腸菌数の監視及び評価方法
大腸菌数の監視及び評価方法については、以下の点を基本とする。
1)測定地点及び測定頻度
測定地点及び測定頻度については、従来の公共用水域の水質の汚濁の状況の常時監視のための水質調査方法である「水質調査方法」(昭和46年9月30日環水管30号)に準じて行う。
2)評価方法
大腸菌数については、今後も類型指定により区分された水域ごとに達成又は非達成の評価を行うことは要しないが、個々の測定地点(環境基準点)については環境基準値に適合しているか否かの判断を行うことが適当である。
個々の測定地点については、以下の理由のとおり年間の測定値の90%値により評価することが適当である。
環境基準の調査回数は、毎月1日以上、各1日について4回程度採水分析することを原則とするとされている。大腸菌数は衛生微生物指標として採用するため、これらの測定値のうち最大値で評価することが望ましいと考えられるが、大腸菌数の測定値は対数正規分布に従う特性があることから、これら12回のうち、最大値を採用すると過剰に厳しい評価となる可能性が懸念される。
一方で、12回の測定値のうち、最大値とその次点の値の2つ以上を除外した場合、例えば、夏季に2か月続けて環境基準値を超過するような傾向が見られる水域が存在した場合に、季節的な特徴を捉えられなくなる可能性が考えられることから、年2回以上の測定値を除外することは望ましくない。
このため、年12回の測定値のうち、最大値1つを除外できる90%値評価が、水質管理の面から適当であると考えられる。
90%値は、年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ(0.9×n)番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値とし((0.9×n)が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる)、この値を環境基準値に照らして評価する。
各1日に4回程度採水分析を行った測定値の日間平均値については、幾何平均値を求めるものとする。
5.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和45年3月・経済企画庁国民生活局「(参考)水質環境基準の基準値の説明」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和45年5月・経済企画庁国民生活局「水質汚濁に係る環境基準の項目追加について」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月19日・中央環境審議会「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(第2次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0301.pdf 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・環境庁水質保全局水質管理課(1975)新訂・水質汚濁防止法の解説、中央法規出版、pp.30-66 【NIES保管ファイル】
○湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖):水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数
1.基準値
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | COD | SS | DO | 大腸菌数 | ||
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 |
| A | 水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
| B | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 15mg/L以下 | 5mg/L以上 | - |
| C | 工業用水2級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | - |
(備考)
1 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
2 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
3 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。
4 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
(注)
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は特殊な浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
2.測定方法
・pH:日本産業規格K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置※によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・COD:日本産業規格K0102の17に定める方法
・SS:昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表9に掲げる方法
・DO:日本産業規格K0102の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置※によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・大腸菌数:昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表10に掲げる方法
※水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和45年4月21日・閣議決定(大腸菌群数を除く)
昭和45年5月29日・大腸菌群数の追加
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定:大腸菌数)
令和3年7月19日・中央環境審議会答申
令和3年10月7日・環境省告示第62号(令和4年4月1日施行)
4.基準値の根拠の概要
(1)水素イオン濃度(pH)(審議会配付資料抜粋)
河川の説明に準ずる。
(2)化学的酸素要求量(COD)(審議会配付資料抜粋)
湖沼の場合、水質汚濁の一般指標としては、プランクトンの影響、その他湖沼のメカニズムを勘案すればBODよりもむしろCODが適当と考えられる。
COD 1ppm以下は、ほとんど人為的汚染がないと考えられ、これらの湖沼は自然景観等に適している。
水道用水としては「厚生省令」による飲料水の水質基準は、過マンガン酸カリウム消費量で10 ppm以下となっており、これをCODに換算すると2.5ppm以下となる。
厚生省の調査によると、湖沼のCODの実態は参考(表-6(略))の通りであり、COD 3 ppm以上のところはほとんどないことがわかる。これに湖沼の現状ならびに処理過程の技術能力を勘案すれば、水道用水の適応性としては環境基準の別表(略)のような数値になると考えられる。
つぎに、水産用水の面では、貧栄養湖型と富栄養湖型に分類し、貧栄養湖型のうちでも非常に清浄な水域を好む水産生物にはCOD 1ppm以下、貧栄養湖型のうち普通程度のもの、及び富栄養湖型のうち比較的清浄な水域を好む水産生物については3ppm以下が適当である。また、普通程度の富栄養湖型の水産生物については5ppm以下が適当である。
水浴については、COD 3ppm以下であれば問題はないと考えられる。
また、農業用水としては、CODが高いと土壌の還元の促進等により、稲の根の活力は低下し、根ぐされが発生する。したがって愛知県農業試験所の成績等からすると6ppm以下が望ましい。
その他、工業用水、環境保全の面からすれば、COD 8ppm以下で十分である。
(3)浮遊物質量(SS)(審議会配付資料抜粋)
湖沼のSSについては、一般に透明度が3mの時1ppm以下といわれている。また、貧栄養湖の場合は透明度が5m以上である場合が多く、一方富栄養湖では透明度が小さく、5m以下が多いようである。ちなみに、理科年表によると、摩周湖の最大透明度は41.6m、支笏湖のそれは25.0mとなっている。したがって、このような自然景観的な湖沼では一般にSS 1ppm以下と考えられる。
また、びわ湖南湖のSSは1.4~7.3ppm、北湖は0.9~3.1ppmである。比較的汚濁の進んでいるといわれる諏訪湖のSSは7.0~15.7ppmであり、また印旛沼は5.2~14.1ppmとなっている。
これら湖沼の実情を勘案すると、別表2(略)のごとき基準値が適当と考えられる。
環境保全の面では、河川同様、日常生活において不快感を生じない限度として、ごみ等の浮遊が認められないこととする。
(4)溶存酸素(DO)(審議会配付資料抜粋)
一般的に比較的清浄な湖沼のDOは7.5ppm以上と考えられる。また、水産用水として、アユ、サケ等は7.5ppm以上あれば十分である。その他、コイ、フナ等一般の水産生物の生育阻害の限度としては6ppmといわれているが、プランクトンの存在によっては、その影響によりDOの低下をきたすことがあり、これらを勘案して5ppm以上としている。
また、環境保全の点からして、臭気発生の限界として、2ppm以上としている。
(5)大腸菌数
(当初設定時)(大腸菌群数)(審議会配付資料抜粋)
河川と同様とした。
(令和3年・改定時)
河川の項を参照。
5.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和45年3月・経済企画庁国民生活局「(参考)水質環境基準の基準値の説明」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成30年10月31日・中央環境審議会水環境部会生活環境項目環境基準専門委員会(第9回)資料2「生活環境項目環境基準における大腸菌群数について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y0916-9/mat02.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月19日・中央環境審議会「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(第2次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0301.pdf 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・環境庁水質保全局水質管理課(1975)新訂・水質汚濁防止法の解説、中央法規出版、pp.30-66 【NIES保管ファイル】
○湖沼:全窒素及び全燐
1.基準値
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全燐 | ||
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 |
| Ⅱ | 水道1、2、3級(特殊なものを除く)、水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| Ⅲ | 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Ⅳ | 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| Ⅴ | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
(備考)
1 基準値は、年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。
(注)
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種:コイ、フナ等の水産生物用
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
2.測定方法
・全窒素:日本産業規格K0102の45.2、45.3、45.4又は45.6(日本産業規格K0102の45の備考3を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法
・全燐:日本産業規格K0102の46.3(日本産業規格K0102の46の備考9を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法
3.設定経緯
昭和57年11月18日・中央公害対策審議会答申
昭和57年12月25日・環境庁告示第140号
昭和60年7月15日・環境庁告示第29号(備考2の追加)
4.基準値の根拠の概要(基準値の適用範囲を含む)
(1)環境基準値について(環境基準に係る答申抜粋)
1 基本的な考え方
湖沼の窒素及び燐に係る環境基準の設定に当たっては、次のような基本的な考え方に基づき検討を行った。
①水中の窒素及び燐の濃度が上昇し水域が富栄養化すると、透明度の低下等による景観の悪化、水道水の異臭味や浄水場のろ過障害の発生、魚介類の斃死等の水域の利用上の障害が生ずる。
②これらの障害は、主として藻類等の増殖によるものである。
③藻類等の増殖は、基本的には窒素及び燐の濃度により支配されるものである。
以上のことから、湖沼の窒素及び燐に係る環境基準は、水中の窒素及び燐が藻類等を増殖させることなどによる障害を防止するため、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定めるものとする。
2 水域の利用目的と環境条件
(1)自然環境保全
水域が富栄養化すると藻類等の増殖のため透明度が低下するとともに、水は緑色ないしは褐色を呈する。この結果、自然景観が悪化するなど自然探勝等の利用上好ましくない状態になる。
我が国において、透明度が十分維持されている湖沼は、摩周湖、支笏湖等であり、これらの湖沼の水質を勘案し、自然環境保全上の観点からその基準値としては、窒素(全窒素をいう。以下同じ。)が0.1mg/L以下、燐(全燐をいう。以下同じ。)が0.005mg/L以下であると判断される。
(2)水道
水域の富栄養化による水道の障害としては、水道水の異臭味障害や増殖した藻類等によるろ過池の目づまり等の浄水操作上の障害があるが、浄水操作の方法によって障害の内容も異なるので、この点を踏まえ検討した。
(i)水道1級
水道1級(ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの)にあっては、緩速ろ過の過程で臭気物質等の分解除去が行われるため、異臭味水の問題はないと考えられるが、原水中の藻類等の増殖によりろ過池が目づまりを起こしろ過能力が著しく低下することがある。
このように緩速ろ過池にろ過障害を起した水源湖沼には、琵琶湖(南湖)、村山貯水池、野尻湖等がある。これらと障害のない水源湖沼の水質を勘案し、水道1級の基準値としては、窒素が0.2mg/L以下、燐が0.01mg/L以下であると判断される。
(ii)水道2級及び3級
水道2級(沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの)、又は、水道3級(前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの)にあっては、原水中の藻類等の増殖により凝集沈殿池等における薬品使用量の増加や急速ろ過池のろ過持続時間が短縮する等、浄水操作上の各種障害を引き起こすことがある。このような障害を起こした水源湖沼には霞ヶ浦、相模湖、畑貯水池等があり、これらと障害のない水源湖沼の水質を勘案して浄水施設の正常な機能を維持する観点からは、窒素が0.4mg/L以下、燐が0.03mg/L以下であることが望ましい。
また、これらの浄水操作では、臭気物質等の除去は困難であるので、水道水の異臭味障害を引き起こすことがある。
最近では、全国各地に異臭味水の発生がみられるが、日本水道協会異臭味対策専門委員会等が取りまとめた多くの障害発生水域の事例や障害を起こしていない水源湖沼の水質を勘案すると、かび臭等の異臭味水の発生を防止する観点からは、窒素が0.2mg/L以下、燐が0.01mg/L以下であることが望ましい。
ただし、水道3級のうち臭気物質等の除去が可能な特殊な浄水操作を行うもの(以下「特殊なもの」という。)にあっては、浄水施設の正常な機能を維持することが必要であり、このような観点から、窒素が0.4mg/L以下、燐が0.03mg/L以下であることが望ましい。
これらの結果から水道2級及び3級(特殊なものを除く。)の基準値としては、窒素が0.2mg/L以下、燐が0.01mg/L以下、水道3級(特殊なもの)の基準値としては、窒素が0.4mg/L以下、燐が0.03mg/L以下であると判断される。
(3)水浴
水浴については、水域が富栄養化すると藻類等の増殖のため、水が濁り異臭がつくなど不快感をもよおすようになる。
現在水浴場として利用されている代表的な湖沼は、琵琶湖(北湖)である。琵琶湖(北湖)は、現在おおむね良好な状態にあるものの、望ましくない状態の水浴場もみられるので、昭和40年代当初の良好な琵琶湖(北湖)の水質を勘案し、水浴場の基準値としては、窒素が0.2mg/L以下、燐が0.01mg/L以下であると判断される。
(4)水産
水中の窒素及び燐の濃度が上昇すると、藻類の大量発生、貧酸素水塊の発生等の現象が生じ、水産生物の繁殖・生育に影響を与える。
窒素及び燐の濃度が低レベルの湖沼では、マス等のサケ科魚類やアユが、中レベルのところでは、ワカサギがそれぞれ多くなっているのに対し、窒素及び燐の濃度が高レベルの湖沼では、コイ、フナなど汚染に強いとされる種類が大部分を占めている。
したがって、水産生物を代表魚種として(i)サケ科魚類及びアユ(ii)ワカサギ(iii)コイ、フナの3つのグループに分けて検討した。
また、水産用水の環境基準としては、それぞれの水産生物が生息するために望ましいレベルを設定するとの考えに基づき、自然の繁殖・生育(再生産)が行われる条件となるよう留意した。
(i)水産1種(サケ科魚類、アユ型)
ヒメマスなどのサケ科魚類やアユは清浄な水を好むが、これらの生息する代表的な湖としては、中禅寺湖、琵琶湖などがある。
中禅寺湖では、富栄養化に伴い、魚類がヒメマスからワカサギに移行しつつあり、望ましい水質ではなくなっている。一方、琵琶湖の北湖では、アユの生息にとっておおむね望ましい水質にある。
これらの点を勘案して、水産1種の基準値としては、窒素が0.2mg/L以下、燐が0.01mg/L以下であると判断される。
(ii)水産2種(ワカサギ型)
ワカサギの生産が高い代表的な湖としては、諏訪湖、八郎湖などがある。しかし、八郎湖では近年、生産が低下しており、好ましい条件ではなくなっている。また、諏訪湖では、生産が横ばい傾向にあるものの、これは種苗放流により維持されているものであり、自然の繁殖・生育条件を確保するためには水質を改善する必要がある。
これらの点を勘案し、水産2種の基準値としては、窒素が0.6mg/L以下、燐が0.05mg/L以下であると判断される。
(iii)水産3種(フナ・コイ型)
窒素及び燐の濃度の上昇に伴い、水産生物のうちコイ・フナの占める割合と量は、増加する傾向にあるが、窒素が1mg/L、燐が0.1mg/Lを超えると障害が生じてくる。
これらの濃度を超えている例としては、児島湖、手賀沼、印旛沼などがあるが、経年的にみるといずれも生産量は横ばいないし低下の傾向にあり、手賀沼や印旛沼では魚肉への着臭や斃死等の障害も発生している。
以上の点を勘案し、水産3種の基準値としては、窒素が1mg/L以下、燐が0.1mg/L以下であると判断される。
(5)農業用水
水稲は農業用水中の窒素(特にアンモニア性窒素)濃度が高いと、栄養生長期(苗を本田に移植後約40日間)に過繁茂となり病害を受けやすくなる。また穂くび分化期に多量の窒素があると下部節間が伸び過ぎて倒伏したり登熟不良となる。これらの結果、水稲の減収を招く。
以上の点と農業用水基準の値を勘案して、その基準値としては、窒素が1mg/L以下であると判断される。
(6)工業用水
水域が富栄養化すると藻類の増殖のため、水が濁り、工業用水としての利用に障害を生ずる。工業用水としての利用がある霞ヶ浦、琵琶湖等の主要な湖沼についてその水質をみると、おおむね窒素が1.0mg/L以下、燐が0.1mg/L以下であり障害も生じていない。以上の点などから工業用水の基準値としては、窒素が1mg/L以下、燐が0.1mg/L以下であると判断される。
(7)環境保全
富栄養化が進行すると藻類等の異常繁殖や大型の水草の繁茂に至り、それらが腐敗し悪臭を放つ等、国民の日常生活において不快感を与える。我が国の湖沼のうち、このような状況にあるのは、印旛沼、児島湖等である。これらの湖沼の水質を勘案し、環境保全上の観点からその基準値としては、窒素が1mg/L以下、燐が0.1mg/L以下であると判断される。
(中略)
4 その他
水質汚濁が極めて著しいため、環境基準の達成が困難と考えられる水域については、当面、施策実施上の暫定的な改善目標値を設定するなど、達成に向けて段階的に改善を図るものとする。
(2)基準値の適用範囲について
(排水基準に係る答申抜粋)
2 窒素及び燐に係る排水基準(抄)
(中略)
(2)排水基準の対象水域は、富栄養化しやすい湖沼(窒素及び燐が流入した場合に藻類等が増殖しやすい湖沼をいう。)及びこれに流入する公共用水域とし、具体的な湖沼の確定は次の考え方により行う。
1)藻類の増殖は湖沼の水利特性等の影響を受けるが、とりわけ重要なものは水の滞留の程度であり、藻類(プランクトン)が生息するのは平均的な水の滞留日数がほぼ3~4日以上の湖沼であると考えられる。
このため、富栄養化しやすい湖沼は、湖沼における水の滞留性を示す年間回転数(湖沼への水の年間総流入量を湖沼の容積で除して得られる値)を主要な指標とし、さらに湖沼の水深、ダムの操作の実態、その他の条件も加味して、判定することとする。
2)我が国の湖沼の中には、藻類の増殖にとって窒素及び燐の両者が制限的になっている湖沼と、燐のみが制限的になっている湖沼が存在するものと考えられる。
このため、i)燐の排水基準は、富栄養化しやすい湖沼のすべてを対象とするが、ii)窒素の排水基準は、ア)湖沼水の平均的な窒素/燐比が20以下であり、かつ、燐の濃度が0.02mg/L以上である湖沼及びイ)それ以外の湖沼で溶存無機態窒素の挙動、AGP試験等からみて窒素が制限的となっていると判定されるものを対象とする。
ただし、このことは、窒素の排水基準が適用されない湖沼について、湖沼水の窒素濃度を増大させてもよいということを意味するものではない。
(以下略)
(環境基準の改正に係る局長通知抜粋)
2 類型指定について(抄)
窒素及びりんに係る環境基準の水域類型の指定に関する手続等は従来と同様であるが、告示別表2の1の(2)のイの備考の2において示されたとおり、水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用するものとする。この場合において、水域類型の指定を行うべき湖沼の条件は水質汚濁防止法施行規則第1条の3第1項第1号、全窒素の項目の基準値を適用すべき湖沼の条件は同条第2項第1号とそれぞれ同様である。
(以下略)
(排水基準に係る局長通知抜粋)
第三 規則改正府令関係
窒素又は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合の具体的な条件については、答申において示された科学的判断を踏まえ、規則改正府令による改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第1条の3において次のように規定された。
(一)燐に係る令第3条第1項第13号の場合は、水の滞留時間が4日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が9,000mg/Lを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)及びこれに流入する公共用水域に、燐を含む水が工場又は事業場から排出される場合とすることとされた(規則第1条の3第1項)。
(二)窒素に係る令第3条第1項第13号の場合は、前項に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が20以下であり、かつ、水の燐含有量が0.02mg/L以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの及びこれに流入する公共用水域に、窒素を含む水が工場又は事業場から排出される場合とすることとされた(規則第1条の3第2項)。
なお、富栄養化以外の観点から水質目標が定められている場合もあることから、この規定は、直ちに、この条件に該当しない湖沼の窒素濃度を増大させてもよいということを意味するものではないことに留意されたい。
5.参考資料
・窒素・燐等水質目標検討会(1980)湖沼の燐に係る水質目標についての検討結果、水質汚濁研究第3巻第3号、pp.143-158 https://doi.org/10.2965/jswe1978.3.143
・窒素・燐等水質目標検討会(1982)湖沼の窒素に係る水質目標についての検討結果、水質汚濁研究第5巻第5号、pp.295-306 https://doi.org/10.2965/jswe1978.5.295
・昭和57年11月18日・中央公害対策審議会「湖沼の窒素及び燐に係る環境基準及びその測定方法について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・昭和59年9月5日・中央公害対策審議会「窒素及び燐に係る排水基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・昭和58年1月28日・環境庁水質保全局長「水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について」(環水管第10号) 【NIES保管ファイル】
・昭和60年6月26日・環境庁水質保全局長「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(環水規第135号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000118.html 【NIES保管ファイル】
・昭和60年7月15日・環境庁水質保全局長「水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について」(環水管第152号) 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・松村隆(1983)湖沼の窒素及びリンに係る環境基準について、公害と対策、19(3), pp.255-260
・横尾和伸(1983)湖沼の窒素及びりんに係る環境基準の設定、水道協会雑誌、52(4)、pp.55-59
・根井寿規(1983)環境基準設定と今後の対応、産業と環境、83(2)、pp.18-21
・坂本充(2015)わが国の湖沼富栄養化に係る環境基準の設定経過と運用上の課題、水環境学会誌、38(5)、pp.163-167
○海域:水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数、n-ヘキサン抽出物質(油分等)
1.基準値
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | COD | DO | 大腸菌数 | n-ヘキサン抽出物質(油分等) | ||
| A | 水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 7.8以上8.3以下 | 2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 | 検出されないこと |
| B | 水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの | 7.8以上8.3以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | 検出されないこと |
| C | 環境保全 | 7.0以上8.3以下 | 8mg/L以下 | 2mg/L以上 | - | - |
(備考)
1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。
2 (略)
3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
(注)
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
2.測定方法
・pH:日本産業規格K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置※1によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・COD:日本産業規格K0102の17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法※2)
・DO:日本産業規格K0102の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置※1によりこれと同程度の計測結果の得られる方法
・大腸菌数:昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表10に掲げる方法
・n-ヘキサン抽出物質(油分等):昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表14に掲げる方法
※1 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。
※2 アルカリ性法とは次のものをいう。
試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mLを加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/L)10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。
COD(O2mg/L)=0.08×〔(b)-(a)〕×fNa2S2O3×1000/50
(a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(mL)
(b):蒸留水について行なった空試験値(mL)
fNa2S2O3:チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価
3.設定経緯
(当初)
昭和45年3月31日・水質審議会答申
昭和45年4月21日・閣議決定(大腸菌群数及びn-ヘキサン抽出物質(油分等)を除く)
昭和45年5月29日・大腸菌群数の追加
昭和46年5月25日・n-ヘキサン抽出物質(油分等)の追加
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号
(改定:大腸菌数)
令和3年7月19日・中央環境審議会答申
令和3年10月7日・環境省告示第62号(令和4年4月1日施行)
4.基準値の根拠の概要
(1)水素イオン濃度(pH)(審議会配付資料抜粋)
河口等淡水が流入する個所を別にすれば、海域のpHは一般的に7.8~8.3の範囲にあり、A、Bの基準値はこの自然条件を参考に決定したものである。この範囲であれば水産生物の生育にも支障がないと考えられる。
また、海域のpHが自然条件と大幅にかわるためには、工場排水等の流入の場合、相当高い負荷量があると考えられるが、環境保全の点で7.0~8.3の範囲であれば、ほぼ問題ないと考えられる。
(2)化学的酸素要求量(COD)(審議会配付資料抜粋)
水産用水の点では、栄養源とする赤潮の発生を防止することが1つの目安と考える必要があり、そのためには、停滞条件下にある水域において常時一定量以上の栄養分の供給を防止することが必要であると考えられる。目につく赤潮は、珪藻では数千細胞/mLにより認められるといわれているから、一応1,000/mL以下にすれば赤潮は防止出来るとし、1,000/mLに含まれる成分量を計算したところ、炭素0.83ppm、窒素0.15ppm、燐0.02ppmに相当した。このうち炭素0.83ppmということをCODで表現すると1ppmとなる。また、塩分1.8%の海水30℃、溶存酸素量は約6.5ppmであり、もしCOD 3ppmがその酸素を消費するとしても、酸素量が一応残される限度としては3ppmである。これらの2点からして、一般水域については2ppm以下とする。
また、のり漁場については、次のアルカリ性法の資料を参考としている。即ち、パルプ排水ではCOD 4~6ppmの範囲では2時間の自然天日干出により、芽傷みを生ずる。発酵排水はCOD 0.4ppm以上で糸状菌の発生を助長する。CODの高い所は糸状菌による病害が多い。以上の点を参考にして水産2級の基準値は3ppmとしている。
工業用水としてはアルカリ性法で3ppm以下で十分であると考えられる。
環境保全の面では、日常生活において不快感が生じない限度として8ppm以下とした。
(3)溶存酸素(DO)(審議会配付資料抜粋)
海域のDOは、塩素イオンの存在により、河川、湖沼よりも一般に低いと言われており、また、水産についてはDO 5ppm以上で十分と考えられる。
なお、環境保全の点では、河川同様、臭気限度として2ppmを採用した。
(4)大腸菌数
(当初設定時)(大腸菌群数)(審議会配付資料抜粋)河川と同様の考え方で基準値を定めた。ただし、生食用カキの養殖場については、米国における輸入カキの輸入許可の基準に対する「厚生省令」の定めるところにより、特に70MPN/100mL以下と定めている。
(令和3年・改定時)
河川の項を参照。
(5)n-ヘキサン抽出物質(油分等)(審議会配付資料抜粋)
海域における油濁が問題とされたのは、主として石油系油分による異臭魚の発生であり、従来からその被害防止のため石油系油分を中心として水質規制が行われてきた。
石油系油分濃度と魚体への着臭の関係については、科学技術庁の研究報告によれば、着臭限界は0.01~0.1ppmとされている(付表2(略))。なお、石油精製排水のn-ヘキサン可溶性物質と水の着臭についての通産省のデータによればその着臭限界は0.2~3ppmである(付表1(略))。水産庁のデータによれば0.008~0.1ppmである(付表3(略))。このように環境濃度はできるだけ低くする必要があるが、低い濃度まで石油系油分を定量的に分離測定する公定の測定方法がないので、当面、検定方法はJIS K0102(改正案)による方法とし、基準値は「検出されないこと」とする。しかし今後、着臭のメカニズムがなお一層明らかになり、測定技術が開発されれば、この環境基準項目、基準値および測定方法は変更されるものである。検出限界はJISの改正により0.5ppm(検水量10Lのとき)とする。
環境基準値を海域のみに適用したのは、河川、湖沼ではn-ヘキサンに抽出される物質として石油系油分以外の各種の有機物が対象になる可能性がある。これらの有機物はBODや窒素などの他の項目で代表できると思われる。
5.参考資料
・昭和45年3月31日・経済企画庁国民生活局「環境基準に係る具体的数値の設定について(案)」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和45年3月・経済企画庁国民生活局「(参考)水質環境基準の基準値の説明」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・昭和46年3月・経済企画庁国民生活局「水質汚濁に係る環境基準の項目追加についての説明」(水質審議会配付資料) 【NIES保管ファイル】
・平成30年10月31日・中央環境審議会水環境部会生活環境項目環境基準専門委員会(第9回)資料2「生活環境項目環境基準における大腸菌群数について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y0916-9/mat02.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月19日・中央環境審議会「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(第2次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0301.pdf 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・環境庁水質保全局水質管理課(1975)新訂・水質汚濁防止法の解説、中央法規出版、pp.30-66 【NIES保管ファイル】
○海域:全窒素及び全燐
1.基準値
| 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全燐 | ||
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| Ⅱ | 水産1種、水浴及びⅢ以下に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Ⅲ | 水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く) | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| Ⅳ | 水産3種、工業用水、生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
(備考)
1 基準値は、年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
(注)
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
生物生息環境保全:年間を通じて底生生物が生息できる限度
2.測定方法
・全窒素:日本産業規格K0102の45.4又は45.6に定める方法
・全燐:日本産業規格K0102の46.3に定める方法
3.設定経緯
平成5年6月10日・中央公害対策審議会答申
平成5年8月27日・環境庁告示第65号
4.基準値の根拠の概要(基準値の適用範囲を含む)
(1)環境基準値について(答申抜粋)
(1)環境基準の設定の基本的考え方
海域の窒素・燐濃度が高くなると、クロロフィル-a濃度及びCODが増加し、透明度及び夏季底層の溶存酸素量が低下するというように、窒素・燐の濃度と海域の水質指標との間に一定の量的関係があることが過去の調査結果から認められる。このような窒素・燐の濃度と水質の各指標との量的関係や利水障害との関係等をもとに、海域の利用目的を勘案しつつ環境基準の設定を行うこととする。
この場合、年間を通した海域の窒素・燐の挙動等を勘案して、水域の栄養度を的確に把握するための指標として、海水中の全窒素(T-N)及び全燐(T-P)の濃度を用い、その表層における年間平均値を用いれば水域の状況を代表しうると考えられる。また、環境基準の水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る観点から、植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれのある海域について行うことが適当である。
なお、海水に含まれる窒素と燐の比(以下「海水のN/P比」という。)が植物プランクトンの増殖に必要な窒素と燐の比(以下「植物プランクトンのN/P比」という。)と常に大きく異なる場合には、窒素又は燐のいずれか一方が植物プランクトンの増殖を制限する可能性がある。しかし、海域の場合は、海水のN/P比が同じ水域内においても季節的・場所的に変動しており、植物プランクトンのN/P比との間に一定の大小関係を見いだすことはできないことから、窒素又は燐のいずれか一方のみが植物プランクトンの増殖に影響しているとは言えない。また海水のN/P比が通常の値から大きくはずれた場合には、健全な海域の生態系の維持という観点から支障を生ずるおそれがあり、これらのことを考慮すれば、環境基準は窒素及び燐の両者について設定することが適当である。
(2)海域の利用目的と望ましい窒素及び燐の濃度レベル
海域の利用目的に応じた望ましい窒素及び燐の濃度レベルについては、以下のとおりとすることが適当である。
ア 自然環境保全
水域が富栄養化すると植物プランクトンの増殖により透明度が低下し、自然景観が悪化するなど自然探勝等の利用上好ましくない状態になる。
我が国において透明度が十分に維持されている水域として海中公園地区の水質データを整理すると、清澄な水質を確保するためには10m程度以上の透明度を目標とすることが適当である。さらに、日本周辺の外洋域の窒素及び燐の濃度も参考にしつつ、自然探勝等のための環境保全上の望ましい水質レベルを設定すると、概ね、窒素(表層の全窒素の年平均値をいう。本章において以下同じ。)が0.2mg/L以下、燐(表層の全燐の年間平均値をいう。本章において以下同じ。)が0.02mg/L以下である。
イ 水浴
水浴場についても、水域の富栄養化に伴う透明度の低下や水浴障害が生じないよう、現在良好な環境が維持されている水浴場における水質のレベルを目標とすることが適当である。
既存の水浴場近傍の平均的な透明度は6m程度以上であり、このときの水質データや、植物プランクトンの増殖により水浴ができなくなるという障害が認められたときの水質データを総合的に勘案すると、水浴のために確保すべき望ましい水質レベルは、概ね窒素が0.3mg/L以下、燐が0.03mg/L以下である。
ウ 生物生育環境保全
水域の富栄養化が進行すると、いわゆる内部生産により有機物が増加して底層の貧酸素化が進行することにより、水生生物、特に底生生物の生息環境に悪影響を及ぼして、ひいては海域全体の生態系への影響をもたらす。このため、環境保全の条件としては、底生生物が生息可能な溶存酸素量を、底層水において年間を通して最低限の濃度で確保できることを目標として掲げることとする。
内湾の底生生物の生息可能な溶存酸素量としては、いくつかの種では4mL/L(約5.7mg/L)以下でも生息に何らかの影響がみられ、2mL/L(約2.9mg/L)以下になると、ほとんどの種で影響が認められる。また、溶存酸素量が3mL/L(約4.3mg/L)以下では、底生生物群集の種類数、密度あるいは種の多様性が著しく低いレベルにあるという知見もある。
これらの結果から、底層の溶存酸素量が2~3mL/L以下になると底生生物への影響が生じると考えられる。したがって、最低限確保すべきレベルとして夏季においても底層の溶存酸素量で2mL/L以上を確保することを目標とすると、窒素及び燐のレベルとしては概ね窒素が1.0mg/L以下、燐が0.09mg/L以下である。
エ 水産
富栄養化の進行に伴う漁獲物組成の変化をみると、富栄養化が進行した海域ではプランクトン食性のイワシ類、コノシロや懸濁物食性のアサリなど、栄養段階の低い種類の漁獲が多くなるとともに、底層の貧酸素化の影響を受けてエビ類・カニ類を中心とする栄養段階の高い底生魚介類の漁獲が減少する傾向にある。
既往の知見並びに東京湾、大阪湾及び広島湾における主な魚介類の漁獲量と水質との関係に関する検討結果等から、富栄養化の進行に伴い漁獲量の増減が比較的明瞭にみられる水産生物の抽出等を行い、水産に係る望ましい水質レベルを検討した。その結果、以下の3つの水質ランクで漁業形態や生態系の状況が分類され、窒素及び燐の濃度レベルが下がると、魚種組成が多様化し生態系のバランスが良くなる方向に変化すると判断された。
(ア)水産1種(窒素0.3mg/L以下、燐0.03mg/L以下)
この海域は、底魚類(クロダイ、ハモ等)、甲殻類(エビ類、カニ類)、頭足類(タコ類、イカ類)、貝類(ハマグリ、アカガイ等)等の底生魚介類が豊富である。特に、他の海域と比較して、エビ類やカニ類の底層の貧酸素化の影響を受けやすい水産生物種の漁獲が多い。
このことは、漁獲物組成が特定の種類に著しく片寄ることなく均衡化していることを表すもので、このような場では多様な水産生物がバランス良く安定して生息していると考えられる。また、ベントス食性のエビ類やカニ類を含む底生魚介類等の栄養段階の高い水産生物が多く漁獲されることは、食物連鎖を通じて海域の生物生産が有効に利用されていることを示し、正常な内湾生態系を呈する最も望ましい海域環境といえる。
(イ)水産2種(窒素0.6mg/L以下、燐0.05mg/L以下((ア)の濃度範囲を除く。))
この海域は、イワシ類、コノシロ、スズキ、カレイ類といった浮魚から底魚までの魚類、水産動物のシャコ、ナマコ等の漁獲がみられ、魚類を中心とした水産生物が多獲される。しかしながら、エビ類、カニ類等の底層の貧酸素化の影響を受けやすい種類の漁獲量は少なく、このような一部の底生魚介類にとって本海域の水質環境は好ましくない。
(ウ)水産3種(窒素1.0mg/L以下、燐0.09mg/L以下((ア)及び(イ)の濃度範囲を除く。))
この海域では、イワシ類、コノシロ、スズキ等の魚類、アサリ等の貝類の漁獲がみられるが、漁獲の中心は大阪湾ではプランクトン食性のイワシ類等、東京湾では懸濁物食性のアサリ等で、これら特定種による漁獲が大部分を占めている。底生魚介類の漁獲量はかなり減少し、本海域の水質環境は多くの底生魚介類にとって好ましくない。
このように、ここではイワシ類やアサリのような低栄養段階に属する特定種が卓越するため生態系としてのバランスは良いとはいえず、不安定な内湾生態系を呈する。
(ウ)を超える窒素及び燐の濃度の海域は、夏季底層に常時貧酸素水塊の形成がみられ、青潮によるアサリのへい死のような水産障害が頻繁に起こり得る環境である。
以上のことを踏まえれば、水産に係る望ましい水質レベルは上記の3つのランクに分けて設定することが適当である。
なお、上記以外の水産生物のうち、カキについてみると、富栄養化により単位面積当りの生産量や成長量の低下を招くなどの影響があるが、広島湾における生産状況等から判断して、好適な水質としては概ね上記(ア)(ただし窒素が0.2mg/L以上、燐が0.02mg/L以上)又は(イ)のランクである。また、ノリについてみると。比較的富栄養化した海域で生産されるが、赤潮による窒素及び燐の消費等に伴い色落ち等の障害がみられ、既往の研究事例及びノリ漁場の水質等から判断して、ノリ生産にとって平均的な水質は概ね上記(イ)又は(ウ)のランクである。
オ 工業用水
海水の工業用水としての用途は主に冷却用水であるが、製塩業等の原料用水等としても利用されている。富栄養化した水域では、原料用水として利用する際のろ過器の目詰まり等の障害が生じる。
現在工業用水として利用されている水域の水質の状況、現行の海域の環境基準の設定状況等を勘案すると、工業用水としては、概ね窒素が1.0mg/L以下、燐0.09mg/Lの水質で差し支えないと判断される。
(中略)
(5)類型指定に当たっての基本的考え方
環境基準値が定められれば、国又は都道府県において水域ごとに環境基準の類型指定が行われることになるが、その際には以下の点に留意する必要がある。
ア 水域類型の指定は、富栄養化の防止を図る必要がある海域のすべてについて行う必要があるが、富栄養化が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある海域を優先して行う必要がある。
イ 当該水域の将来の利用目的については、現在の利水状況だけでなく過去の利水状況も参考としつつ、各地域の関係者の意見等を踏まえて設定する必要がある。
ウ 当該水域における水質の現状、人口・産業の動向、達成の方途等を踏まえ、将来の水質の見通しを明らかにしつつ、環境基準の達成期間を設定する必要がある。その際、富栄養化の進行が著しく、環境基準を速やかに達成することが困難と考えられる水域については、当面、施策実施上の暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図る必要がある。
エ この他、以下の点に留意すべきである。
(ア)窒素及び燐は一時生産者である植物プランクトンの栄養として海域の生態系の維持に必要であり、極端に濃度を低くする必要はないが、逆に窒素及び燐の濃度が低い海域であってもその海域固有の生態系が維持されているので、濃度を増加させることがよいというわけでもない。
このようなことを勘案すると、Ⅰ類型の環境基準については、自然環境保全の利水を優先させる必要がある海域や、現状の低濃度の窒素・燐のレベルを維持することで現在の水産としての利用や生態系の維持を図る必要があると考えられる海域を対象に設定することが適当である。
(イ)富栄養化が進んだ海域では、特に湾奥部等で流入河川や気象・海象等の影響を受け空間的・季節的な濃度変動が大きくなりやすい。したがって、類型指定の水域区分、監視地点の配置、監視結果の評価に当たっては、水域区分ごとの窒素及び燐の濃度レベルを総体として把握できるよう配慮する必要がある。なお、窒素及び燐の濃度の年間平均値を的確に把握するため、水域の特性を勘案しつつ、各監視地点において、年間を通して各月1回以上測定を行うことが望ましい。
(ウ)窒素及び燐は、現行の環境基準対象項目であるCODの濃度レベルとも関係があるので、窒素及び燐の類型指定を行う際には、現行のCODの環境基準の類型区分及び水域区分との関連を踏まえて類型及び水域区分を設定することが望ましい。その際、現行のCODの環境基準の水域区分が設定されてからの利水や水質の状況の変化等を勘案し、必要に応じ現行の水域区分を併せて見直す必要がある。
(2)基準値の適用範囲について
(答申抜粋)
3.海域の窒素及び燐に係る排水基準
(1)排水基準の対象項目
2の(1)(略)で述べたような理由から、富栄養化の要因物質である窒素及び燐のいずれについても、その濃度を抑制すべきであり、排水基準の対象項目は窒素含有量及び燐含有量とするのが適当である。
(2)排水基準を適用する水域
水質汚濁防止法に基づく一律排水基準は、全国のどの公共用水域への排出であろうと、特定事業場から公共用水域に排出される「排出水」に対し、いわばナショナルミニマムとして、全国一律に適用されている。
なお、湖沼の窒素及び燐に係る排水基準については、「湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある場合として総理府令で定める場合におけるものに限る。」との一定の局面限定がなされているが、これは、窒素又は燐はそれ自体が直ちに水質汚濁による被害を生ずる物質ではなく、現在までの知見によると「湖沼植物プランクトンの著しい増殖」を通じて生活環境に係る被害が生ずることが明らかになっていることから、このような事態をもたらすおそれがあるという局面に限って排水規制の対象にすることとしたものである。
海域に係る窒素及び燐についても、湖沼と同様に、窒素又は燐はそれ自体が直ちに水質汚濁による被害を生ずる物質ではなく、現在までの知見によると植物プランクトンの著しい増殖を通じて生活環境に係る被害が生ずると考えられることから、このような事態をもたらすおそれがあるという局面に限って排水規制の対象とすることが適当であると考えられる。
このため、海域の富栄養化のおそれを表す指標について検討を行ったところ、その結果は次のとおりであった。
ア 海水交換は内湾・内海の物質収支を支配するとりわけ重要な要因のひとつであるため、海水交換の指標である平均滞留日数、潮汐交換率等について検討を行った。その結果、これらの指標は一義的にその数値を定めにくく、規制対象に係る海域の特定のための指標として用いるのは困難であると考えられた。
イ このため、次式で定義される閉鎖度指標を取り上げて検討したところ、次のことが分かった。
閉鎖度指標=
S:当該海域の内部の面積
W:当該海域の入口の幅
D1:当該海域の最深部の水深
D2:当該海域の入口の最深部の水深
(ア)閉鎖度指標≧1を基準とすると、海域の富栄養化により生ずる現象のひとつである貧酸素水塊の発生海域の大半が抽出される。
(イ)また、閉鎖度指標≧1の海域を見ると、概ねその海水交換は閉鎖度指標に依存し、計算された減衰率(海水交換の指標)は低い値(海水交換が悪い)を示す。
これらのことから、海域が富栄養化するおそれがあるかどうかは、閉鎖度指標により概ね判断することが可能であり、富栄養化のおそれのある海域の閉鎖度指標は概ね1以上であると考えられた。
しかしながら、閉鎖度指標が1未満の海域においても、例外的ではあるが、貧酸素水塊の発生等が報告されている。これは、閉鎖性の低い海域であっても、潮流、海域、躍層の発達等の状況によって海水交換が悪くなる場合があるためと考えられる。
以上の点を踏まえると、排水基準を適用する水域は、富栄養化のおそれのある海域(窒素及び燐が流入した場合に植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある海域をいう。)及びこれに流入する公共用水域とすることが適当である。この場合において、富栄養化のおそれのある海域は、「閉鎖度指標≧1」を基準として判定することとする。
ただし、この基準に合致しない海域であっても、当該海域の諸特性からみて、富栄養化のおそれがあると判断される場合にあっては、排水基準を適応することができるものとする。
なお、全国の海域の中で対象海域を確定する必要があることから、対象海域の規模は、原則として、その面積が5km2以上であることとする。
(環境基準の改正に係る局長通知抜粋)
2 水域類型の指定について
海域の窒素及び燐に係る環境基準の水域類型の指定に関する手続き等は従来と同様であり、環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令第159号)の別表(略)に掲げる公共用水域以外の公共用水域については、同政令の定めるところにより都道府県知事が水域類型指定を行うこととされているので、該当水域が属する区域を管轄する都道府県におかれてはその推進を図られたい。その際、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)の第1の2によるほか、以下に掲げる事項に留意されたい。
(1)水域類型の指定は、告示別表2の2のイの備考の2において示されたとおり、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとするが、その海域の要件は平成5年8月27日総理府令第39号をもって改正された水質汚濁防止法施行規則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号と同様であること。
(排水基準に係る局長通知抜粋)
第三 規則改正府令関係
(一)窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合については、規則改正府令による改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第1条の3において、窒素又は燐を含む水が工場又は事業場から次のいずれかの公共用水域に排出される場合とした(窒素、燐とも同じ。)。
ア 次の算式により計算した値が1.0以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。)その他の水が滞留しやすい海域
この式において、S、W、D1及びD2は、それぞれ次の値を表すものとする。
S:当該海域の面積(単位 平方キロメートル)
W:当該海域と他の海域との境界線の長さ(単位 キロメートル)
D1:当該海域の最深部の水深(単位 メートル)
D2:当該海域と他の海域との境界における最深部の水深(単位 メートル)
イ アの海域に流入する公共用水域
(二)なお、水の塩素イオン濃度が9,000ミリグラム/リットルを超える湖沼については、内湾・内海で増殖する海洋植物プランクトンと同じ種の植物プランクトンが増殖することから、海域に含めて取り扱うこととした。
5.参考資料
・平成4年9月・海域に係る窒素・りん等水質目標検討会「海域に係る窒素・りん等水質目標検討調査結果報告書」 【NIES保管ファイル】
・平成5年6月10日・中央環境審議会「海域の窒素及び燐に係る環境基準等の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年6月10日・中央環境審議会「海域の窒素及び燐に係る環境基準等の設定に関する参考資料」 【NIES保管ファイル】
・平成5年9月10日・環境庁水質保全局長「水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件の施行等について」(環水管第121号) https://www.env.go.jp/hourei/01/000047.html 【NIES保管ファイル】
・平成5年9月10日・環境庁水質保全局長「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(環水規第255号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000121.html 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・早水輝好(1994)海域の富栄養化対策の推進(Ⅰ)、水利科学、37(6)、pp.31-57 https://doi.org/10.20820/suirikagaku.37.6_31 【NIES保管ファイル】
・早水輝好(1994)海域の富栄養化対策の推進(Ⅱ)、水利科学、38(1)、pp.78-99 https://doi.org/10.20820/suirikagaku.38.1_78 【NIES保管ファイル】
○湖沼、海域:底層溶存酸素量(底層DO)
1.基準値
| 類型 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 基準値 |
|---|---|---|
| 底層溶存酸素量 | ||
| 生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 |
| 生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/L以上 |
| 生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 |
(備考)
1 基準値は日間平均値とする。
2 (略)
2.測定方法
日本産業規格K0102の32に定める方法又は昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表13に掲げる方法※
※底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。
3.設定経緯
平成27年12月7日・中央環境審議会答申
平成28年3月30日・環境省告示第37号
4.基準値の根拠の概要
(平成27年・基準値設定時)(答申抜粋)
2.生活環境項目としての環境基準の検討について(抄)
(中略)
(2)今回の検討事項
1)生活環境項目環境基準における課題
生活環境項目環境基準が最初に設定されてから40年以上が経ち、この間、環境基準を達成するために水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法等に基づく各種施策が総合的に進められてきたところである。
COD、全窒素及び全燐の環境基準は環境水中の酸素を消費する有機汚濁物質及び富栄養化をもたらす栄養塩類の指標として設定され、負荷削減のための排水基準及び総量規制基準の設定とあわせて、環境水の状況を表しつつ対策と結びつける役割を担ってきた。全国の公共用水域におけるCOD、全窒素及び全燐の環境基準達成率は年々上昇傾向にあり、COD、全窒素及び全燐の環境基準は水質改善のために大きな役割を果たしてきたところである。
一方で、貧酸素水塊の発生や藻場・干潟等の減少、水辺地の親水機能の低下等の課題が残されており、水生生物の生息環境や水辺地の親水機能などを評価するには、従来の汚濁負荷削減を中心とした水質汚濁防止対策の効果を把握するために指標としているCOD、全窒素、全燐のみでは不十分であり、新たな指標が必要である。
こういった状況を踏まえ、これまで規制対象となっていた有機汚濁物質、窒素及び燐だけでなく、水生生物の生息への影響等を直接判断できる指標や国民が直感的に理解しやすい指標など、水環境の状態をより直接的に表すことができる指標を導入し、総合的な対策の効果を適切に評価することで、水環境保全の取組を一層推進していくことが必要である。
なお、水辺空間については、人と水とのふれあいが希薄になっており、内閣府が実施した水に関する世論調査(平成20年6月調査)によれば、全体的に身近な水辺の環境に満足している人が少なく(40.7%)、特に大都市(東京23区及び政令指定都市)では身近な水辺環境に満足している人は32.6%と少ない。一方で、生活環境項目の達成状況は、河川で生物化学的酸素要求量(BOD)が9割以上、海域でCODが8割程度となっており、このように水環境に関する国民の実感と比べて乖離している。環境基準の指標や目標が、水環境の実態を表していない、あるいは国民の実感にあった分かりやすい指標となっていないといった指摘がある(「今後の水環境保全の在り方について」平成23年3月今後の水環境保全に関する検討会)。
2)基本的考え方
上記の課題を踏まえ、今回、以下の視点に着目して、良好な水環境の実現に向けた施策を効果的に推進していくため、新たな指標の検討を行う。
①魚介類等の水生生物の生息・再生産や海藻草類等の水生植物の生育に対して直接的な影響を判断できる指標
公共用水域における水質改善の取組については、これまで、その効果を判断する指標として環境基準が設定されているCOD、全窒素及び全燐を主に用いてきており、水質の改善に一定の役割を果たしてきたところである。
しかし、COD、全窒素及び全燐の指標だけでは、その高低のみをもって生物の生息環境が良好であるかを必ずしも十分に表しきれていないことから、水生生物の生息・生育の場の保全・再生の観点から、水環境の実態をより適切に表す指標を検討する。
②国民が直感的に理解しやすい指標
水環境の保全を進めるに当たっては、一人一人が身近な水環境の魅力やそれが抱えている問題に気づき、主体的に活動することが重要であり、国民の水への関心をより一層高めていくことが求められている。そのため、水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい指標を検討する。
3)検討対象項目
上記の基本的考え方を踏まえ、望ましい水環境の状態を表す指標として底層溶存酸素量及び透明度を検討対象項目とした。
①底層溶存酸素量
魚介類を中心とした水生生物の生息が健全に保たれるためには、水質や底質等の様々な環境要素が適切な状態に保たれていることが重要であり、このうち、底層溶存酸素量は、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つである。
全国の海域の底層溶存酸素量の状況については、閉鎖性海域以外の海域では底層溶存酸素量が4mg/L以下になる地点はほとんどみられない。一方、主な閉鎖性海域においては、特に湾奥で夏季に底層溶存酸素量が2mg/L以下になる地点がみられる。また、湖沼についても、底層溶存酸素量が2mg/L以下になる地点は少なくない。
このような底層溶存酸素量の低下は、有機汚濁物質の流入や富栄養化による有機物の増加(内部生産)に伴う酸素消費量の増加のほか、干潟等の減少に伴う浄化機能の低下、人工的な深堀り跡等における底層への酸素供給量の低下、水温上昇に伴う底層への酸素供給の阻害など、様々な原因により生じていると考えられる。
海域においては、底層溶存酸素量が一定レベル以下まで低下すると、それ自体が底層を利用する水生生物の生息を困難にさせる上、生物にとって有害な硫化水素を発生させて水生生物の大量斃死を引き起こすことがある。例えば、東京湾では、夏季には広範囲に貧酸素水塊が発生し、海底の水生生物が死滅したり、生息海域が狭められたりする。また、底層の貧酸素水塊の表層への上昇(青潮の発生)によりアサリなどの干潟生物の大量斃死も起きている。このように底層溶存酸素量の低下は、無生物域の形成や青潮などを引き起こし、海域の生態系に悪影響を与える可能性がある。また、底層溶存酸素量の低下により、底質から栄養塩が溶出するなど内部負荷が増加し、海域の富栄養化が促進される。このような栄養塩の増加は、植物プランクトンの異常増殖(赤潮発生等)のリスクを高める可能性がある。
湖沼においても底層溶存酸素量の一定レベル以下までの低下は、それ自体が水生生物の生息を困難にさせる上、底質から栄養塩を溶出させるなど内部負荷増加を促進させる影響が大きいと考えられている。溶出した栄養塩が表層水に供給されると、それを栄養源にして植物プランクトン(微細藻類(アオコ)を含む)が異常発生して浄水過程におけるろ過障害、水道水におけるかび臭などの障害を生じさせるおそれがある。また、水道水の着色障害等を引き起こす鉄及びマンガンは、溶存酸素の欠乏による酸化還元電位の低下により溶出する可能性が高いとされている。
以上を踏まえ、水生生物の生息の場の保全・再生、ひいては健全な水環境保全の観点から、魚介類等の水生生物の生息に対する直接的な影響を判断できる指標として、海域及び湖沼を対象に底層溶存酸素量の目標設定(目標の位置付け及び目標値)の検討を行う。
(中略)
3.底層溶存酸素量の目標設定の検討について(抄)
(1)底層溶存酸素量の目標設定の基本的考え方
水域の底層を生息域とする魚介類等の水生生物や、その餌生物が生存できることはもとより、それらの再生産が適切に行われることにより、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、底層溶存酸素量の目標設定の検討を行った。また、海水の水平方向の交換や鉛直方向の混合が生じにくい水域等の夏季に極端に貧酸素化する場所では、貧酸素耐性を有する小型多毛類等も生息できず、いわゆる無生物域となることがあり、底層溶存酸素量の目標設定の検討にあたっては、このような場を解消するための観点も考慮した。
(2)貧酸素耐性評価値の導出方法
1)活用する知見
底層溶存酸素量の低下が魚介類等の水生生物に与える影響の多くは、急性影響によるものと考えられるため、貧酸素に関する急性影響試験(以下、「貧酸素耐性試験」という。)により評価される致死濃度に着目し、関連する文献等の知見を活用する。致死濃度は、感受性の特に高い個体の生存までは考慮しないものとして、24時間の曝露時間における95%の個体が生存可能な溶存酸素量(24hr-LC5:以下、「貧酸素耐性評価値」という。)として整理した。
貧酸素耐性評価値(24hr-LC5)の算出にあたっては、ロジスティック回帰等の統計的手法や対数近似法を使って直接貧酸素耐性評価値が求められている場合は、その値をそのまま貧酸素耐性評価値(24hr-LC5)とし、24時間の曝露時間における50%が致死する溶存酸素量(24hr-LC50)、1時間の曝露時間における50%が致死する溶存酸素量(1hr-LC50)の知見が得られた場合には、これらの間に一定の関係が認められることから、換算式を用いて貧酸素耐性評価値を算出した。
また、実際の底層溶存酸素量と生息分布の関係から、どの程度の溶存酸素量で生息するかを示唆している現場観測の知見もある。このような知見は、ある底層溶存酸素量においてある水生生物種が観測された旨の観測結果が存在することを示すものであり、貧酸素耐性評価値と必ずしも一致するわけではないが、実環境における溶存酸素量が水生生物の生息に与える影響に関する知見は重要であることから、これらの知見も活用した。
対象とする水生生物は、我が国の公共用水域(海域または湖沼)に生息する魚介類のうち、その生活史のいずれかの段階で水域の底層を利用する種とした。
2)発育段階別の貧酸素耐性評価
魚介類の個体群が維持されるためには、生息域が確保されるのみならず、再生産も適切に行われる必要がある。魚介類は、稚魚、未成魚及び成魚の段階(以下、「生息段階」という。)と比べて、浮遊生活をする仔魚や幼生、あるいは底生生活をはじめたばかりという発育段階の初期は、環境の変化に対して受動的にならざるを得ない段階(以下、「再生産段階」という。)であり、貧酸素に対して影響を受けやすいことに留意して、貧酸素耐性の評価を以下のとおり整理した。
①生息段階
魚類については、稚魚・未成魚・成魚の貧酸素耐性評価値を、甲殻類については、未成体・成体の貧酸素耐性評価値を、生息段階の評価値として扱う。
②再生産段階
魚類については、卵・仔魚の貧酸素耐性評価値を、甲殻類については、幼生・稚エビ・稚ガニの貧酸素耐性評価値を、再生産段階の評価値として扱う。甲殻類については、現在得られている実験文献等による稚エビ・稚ガニの貧酸素耐性評価値は、幼生等の発育段階初期から未成体・成体の段階のうち、最も高い溶存酸素量を必要とすることから、これを再生産段階の貧酸素耐性評価値として扱う。
魚類については、卵や仔魚等の発育段階初期の貧酸素耐性評価値が貧酸素耐性試験や現場観測等から得られていない。
他方、米国環境保護庁(2000)において、魚介類等の貧酸素耐性について知見が得られている全魚類のうち、LC50が求められているデータを、発育段階別に抽出した結果(暴露時間が24時間以下のもの)を見ると、24hr-LC50から24hr-LC5への算出方法と同様の考え方により求めたLC5の差は0.92mg/Lとなっている。このことを踏まえ、再生産段階の貧酸素耐性評価値は、生息段階の貧酸素耐性評価値に1mg/Lを加えた値として推定した。
なお、今後、魚類の再生産段階の貧酸素耐性評価値が貧酸素耐性試験や現場観測等から得られる場合には、甲殻類と同様に基本的にその値を用いることが適当である。
(3)底層溶存酸素量の目標値
得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえ(参考資料参照(略))、①水生生物の生息の場を確保する観点、②水生生物の再生産の場を確保する観点、③無生物域を解消する観点の3つの観点から目標値を設定することが適当である。
1)目標値:4.0mg/L以上
・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域
・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域
この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性が低い水生生物が生息できる場を保全・再生する範囲とする。
得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、底層溶存酸素量が4.0mg/L以上あれば、ほとんどの水生生物種について、生息はもとより再生産ができる場を保全・再生することができるものと考えられる。
2)目標値:3.0mg/L以上
・生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域
・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域
この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性が低い水生生物を除き、水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生する範囲とする。
得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、底層溶存酸素量が4.0mg/L以上必要な水生生物を除き、水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生することができるものと考えられる。
3)目標値:2.0mg/L以上
・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域
・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域
・無生物域を解消する水域
この目標値を設定する範囲は、生息段階、又は再生産段階において貧酸素耐性が高い水生生物が生息及び再生産できる場を保全・再生する範囲、または、小型多毛類等も生息できない無生物域を解消するため、最低限の底層溶存酸素量を確保する範囲とする。
得られた貧酸素耐性評価値等を踏まえると、貧酸素耐性が高い水生生物が生息できる環境であり、また、小型多毛類等が生息でき、無生物域が解消される水域として、底層溶存酸素量2.0mg/L以上を最低限度とすることが考えられる。
(4)底層溶存酸素量の目標の設定
底層溶存酸素量の低下は、魚介類等の水生生物の生息そのものに影響するとともに、青潮の発生等により生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがある。このため、水生生物の保全等の観点から、海域及び湖沼において、底層溶存酸素量を環境基本法第16条に規定する環境基準として以下のとおり設定し、必要な施策を総合的にかつ有効適切に講ずることにより、その確保に努めることとすることが適当である。
(中略)
なお、底層溶存酸素量は、既存の環境基準項目であるCOD、全窒素、全燐等と一定の関連性が見られるものの、目標設定の目的や設定方法が異なることから、既存の環境基準の類型指定を参考にしつつも、基本的にはこれらとは別に類型指定を検討することが適当と考えられる。
(中略)
(6)底層溶存酸素量の各水域における類型指定の方向性
類型指定は、底層の貧酸素化の防止により、水生生物の保全・再生を図る必要がある水域について行うが、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行するおそれがある閉鎖性海域及び湖沼を優先すべきである。
類型指定の検討にあたっては、各地域の意見を踏まえた上で、以下の点に留意して実施することが適当である。
①水域の底層溶存酸素量の状況や、現状及び必要に応じて過去も含めた水生生物の生息状況等を踏まえたうえで、保全・再生すべき水生生物対象種(以下、「保全対象種」という。)の選定を行い、その保全対象種の生息・再生産の場を保全・再生する水域の範囲を設定することを基本とする。その際、水域の範囲は、生息段階、再生産段階の2つの観点から設定し、水域毎の水生生物の生息状況等に即した類型指定を行う。また、無生物域を解消する水域の設定については、底層が無酸素状態になっている、あるいは無酸素状態になるおそれがあるところで、無生物域の解消のために最低限の溶存酸素量を確保する必要がある範囲について類型指定を行う。
なお、基準値の検討にあたり、今回知見が収集された水生生物種以外の水生生物を保全対象種として検討する場合には、今回示した貧酸素耐性評価値の導出方法(参考資料参照(略))を参考とする。
②以下の範囲は必ずしも類型指定を行う必要はない。
○自然的要因による水深の深い範囲や、成層、底質の環境が水生生物の生息に適さない範囲等、設定する保全対象種が生息・再生産の場として底層の利用が困難な範囲
○ダムの死水域に代表されるような、構造物等により底層が構造上貧酸素化しやすくなっている範囲であって、その利水等の目的で、水生生物が生息できる場の保全・再生を図る必要がないと判断される範囲
なお、具体的な類型指定の手順については、図1(略)のような流れを想定しているが、詳細については、実際の類型指定を行う際に検討する。
(中略)
(7)底層溶存酸素量の監視及び評価方法
底層溶存酸素量の監視及び評価方法については、以下の点を基本とする。
1)測定地点
測定地点(環境基準点及び補助地点)は、保全対象種の生息及び再生産、底層溶存酸素量等の水域の状況等を勘案して、水生生物の保全・再生を図る範囲を適切に評価できる地点を設定する。なお、測定水深については、可能な限り海底又は湖底直上で測定することが望ましいが、底泥の巻き上げや地形の影響等のためこれにより難い場合には、海底又は湖底から1m以内の底層とする。
2)測定頻度
既存の環境基準と同様に、年間を通じ、原則として月1日以上測定することとし、底層溶存酸素量が低下する時期には測定回数を増やすことを考慮する。また、底層溶存酸素量の日間平均値を適切に把握するため、可能であれば、複数回の測定や、水生生物の生息・再生産の場を保全・再生するうえで重要な地点においては連続測定を行うことが望ましい。
3)評価方法
底層溶存酸素量の目標値は、急性影響の視点(24時間の低溶存酸素耐性試験にもとづき、95%の個体の生存が可能な溶存酸素量(LC5))から設定しているため、日間平均値が底層溶存酸素量の目標値に適合していることをもって評価する。
なお、保全対象種の利用水域は面的な広がりを有すること、底層溶存酸素量は季節的な変化が大きいことなどを踏まえ、時間的、空間的な観点からの評価方法は今後国において検討する必要がある。
(以下略)
(令和3年・類型指定時)(答申抜粋)
2.類型指定等に関する事項について(抄)
(1)類型指定の基本的考え方について
平成27年答申において、「COD、全窒素及び全燐の環境基準が水質改善のために大きな役割を果たしてきたところである。一方で、貧酸素水塊の発生や藻場・干潟等の減少、水辺地の親水機能の低下等の課題が残されており、水生生物の生息環境や水辺地の親水機能などを評価するには、従来の汚濁負荷削減を中心とした水質汚濁防止対策の効果を把握するために指標としているCOD、全窒素、全燐のみでは不十分であり、新たな指標が必要である。」とされ、平成28年3月に環境基準として底層溶存酸素量が設定された。
また、平成27年答申では、「類型指定は、底層の貧酸素化の防止により、水生生物の保全・再生を図る必要がある水域について行うが、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行するおそれがある閉鎖性海域及び湖沼を優先すべきである。」とされたところであるが、底層溶存酸素量は新しい指標として定められたことから、個別水域における類型指定及びその後の評価結果等を踏まえ、その意義や活用策を地域の関係者に段階的に浸透させつつ、効果的な対策を検討し講じていくことが想定されるため、個別の湾や湖沼において、現に底層の貧酸素化が著しく進行しているか、進行するおそれがある水域を優先して類型指定する方法も考えられる。また、底層溶存酸素量の低下は、水生生物の健全な生息に影響を及ぼすことから、生物多様性の観点からも、類型指定を進めていくことが重要である。
(中略)
(3)評価方法について
評価方法について、平成28年報告において、以下の2点が示されている。
Ⅰ.底層溶存酸素量について
1.底層溶存酸素量の評価方法
(1)日間平均値の年間における評価方法について
答申に記載された内容をもとに、次のとおりまとめた。
1)評価方法の考え方
底層溶存酸素量の年間における評価について、連続測定を実施する場合は、目標値を下回る観測結果(日間平均値)が2日以上続いた場合は「非達成」、そうでない場合は「達成」と評価する。連続測定を実施しない場合は日間平均値の年間最低値により評価する。
[中略]
(2)複数の環境基準点をもつ水域における評価の方法
1)底層溶存酸素量の達成評価の考え方
U.S.EPA(2007)によると、底層溶存酸素量のような水質項目は時間的また空間的にも変化するため、健全な生態系といえどもすべての地点とすべての時間で目標値を上回るとは限らないとされている。すなわち、底層溶存酸素量が目標値を下回る場所が少なかったり、一時的であったり、速やかに回復するのであれば、それは生態系の劣化をもたらさないと考えられる。このことから、底層溶存酸素量の一時的かつ部分的な低下が生じたとしても、当該水域全体の個体群維持に問題が生ずる可能性は低いと考えられる。
ただし、個体群の維持が可能な最低限度の水域割合及び期間割合を求めることは、水生生物種や対象水域の特性によって異なるため極めて困難である。
以上のことから、底層溶存酸素量の基準値の達成評価を考える上では、当該水域における保全対象種の個体群の維持を目的とする場合、類型あてはめを行った対象水域のすべて測定地点(環境基準点)で、またすべての期間で基準値に適合しなくても、目的は達成できると考えられる。
2)底層溶存酸素量における評価の方法
1)を踏まえ、底層溶存酸素量の評価方法として、個々の測定地点(環境基準点)について、目標値に適合しているか否かの判断はするが、類型指定より区分された水域ごとに達成又は非達成の評価はせず、水域内の全ての測定地点(環境基準点)うち、目標値に適合している測定地点(環境基準点)数の割合で評価す方法が適当であると考えられた。[後略]資料:「底層溶存酸素量及び沿岸透明度の評価方法等について」(平成28年11月1日、第42回中央環境審議会水環境部会資料)
この評価方法による評価の例が平成28年報告に示されたが、底層溶存酸素量は季節的な変動が大きいということを踏まえ、どの地点でどのような適合状況であるかをより具体的に把握することが可能となるよう、図表を用いて月ごとの適合状況を含めて示す方法の例を次頁からの二重枠内「評価方法の例(仮想水域)(略)」に示す。
この例で示した仮想水域では水域内に4つの類型が存在し、生物1類型については2つの水域区分に分かれている。参考表1(略)においては、各測定地点の一番右の欄がその測定地点の適合状況であり、これが100%の場合、当該測定地点(環境基準点)が基準に適合していると判断する。区分された水域(以下「水域区分」という。)内における全測定地点のうち環境基準に適合している測定地点の割合が、その水域区分の達成率となる。さらに、当該水域全体における[適合した測定地点の数]の[当該水域の全測定地点数]に対する割合が、一番右下の水域全体の達成率となる。
参考表2(略)については、連続測定を行った場合の例であり、2日間以上目標値を下回る結果が頻出した時期について説明を付すなど適合しなかった状況について具体的に把握できるようにする。
(4)目標とする達成率の設定及びその達成期間について
達成期間については、平成28年報告では以下のとおり示されている。
(3)底層溶存酸素量の達成期間の取扱い
1)既存の生活環境項目環境基準の達成期間
[略]
2)底層溶存酸素量の達成期間
(2)1)に記載のとおり、水域における底層溶存酸素量は、個体群の維持が可能である限り、必ずしもすべての地点で、またすべての期間で底層溶存酸素量の基準値を常に上回る必要はないと言える。しかし、個体群の維持が可能な最低限度の水域割合及び時間的割合は、保全対象や対象水域の特性によって異なるため、国が一律に求めることは困難である。
また、底層溶存酸素量の改善には、長期的な改善計画等(水質総量削減(環境省)、海の再生プロジェクト(国土交通省、海上保安庁)、藻場・干潟ビジョン(水産庁)等)も視野に入れ、対象水域ごとに適切な改善手法を検討することが必要と考えられる。
以上より、達成率や達成期間等に係る目標の設定ついて、事前の関連調査及び改善手法とその進捗度合を踏まえた上で、類型区分された水域ごとに検討することが適当と考えられる。資料:「底層溶存酸素量及び沿岸透明度の評価方法等について」(平成28年11月1日、第42回中央環境審議会水環境部会資料)
底層溶存酸素量は新しい基準であるため、類型指定された後、当該水域の底層溶存酸素量を評価するための測定地点を設定することが必要となる。
類型指定された後、最初の5年間程度の中で底層溶存酸素量の状況に照らして、保全対象種の生息状況の健全性についても可能な限り把握する。この間に把握した情報等を踏まえ、各水域区分における保全対象種を中心とした水生生物の生息が健全に保たれることを目指し、目標とする各水域区分の達成率を設定する。達成期間については、関係機関間での改善対策も把握した上で、直ちに達成する、又は、5年から10年程度で達成するとする。若しくは、目標の達成に10年程度以上の長期を要すると考えられる場合には、10年程度以内に目指す暫定的な目標(達成率又は地点別適合状況等)を柔軟に設定し、必要な施策に段階的に取り組むことも可能とする。なお、達成期間(暫定的な目標に係る期間を含む。)が10年又は10年に近い場合には、必要に応じて中間的な評価を行うことが望ましい。また、保全対象種の生息状況の健全性について新たな知見が得られた場合には、測定地点、目標とする達成率、達成期間について、必要な見直しを行うことが望ましい。
5.参考資料
・平成27年12月7日・中央環境審議会「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」(参考資料を含む) http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成28年11月1日・中央環境審議会水環境部会(第42回)資料5「底層溶存酸素量及び沿岸透明度の評価方法等について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y090-42/mat05.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和3年7月30日・中央環境審議会「底層溶存酸素量に係る環境基準の水域類型の指定について(答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t09-r0304.pdf 【NIES保管ファイル】
④地域環境目標
○沿岸透明度
1.概要
平成27年12月7日の中央環境審議会答申において、「底層溶存酸素量」について環境基準として設定することが適当とする一方で、「沿岸透明度」について、「環境基準として、政府が目標を定め、必要な施策を講じてその確保に努めるものとして位置づけるよりも、むしろ、地域の合意形成により、地域にとって適切な目標を(地域環境目標(仮称))として設定することが適当と考えられる。」とされ、「目標値設定に係る考え方及び手順については、国として整理を行った上で示すことが望ましい。」とされた。
これを踏まえ、その趣旨について平成28年3月30日に事務連絡で環境省より地方公共団体に通知され、平成30年7月12日に「沿岸透明度の目標設定ガイドライン」が公表された。
2.設定経緯
平成27年12月7日・中央環境審議会答申
平成28年3月30日・環境省水・大気環境局水環境課事務連絡
平成30年7月12日・「沿岸透明度の目標設定ガイドライン」公表
3.目標値の根拠等の概要(答申抜粋)
2.生活環境項目としての環境基準の検討について(抄)
(中略)
(2)今回の検討事項
1)生活環境項目環境基準における課題(略・底層溶存酸素量の項目を参照)
2)基本的考え方(略・底層溶存酸素量の項目を参照)
3)検討対象項目(抄)
上記の基本的考え方を踏まえ、望ましい水環境の状態を表す指標として底層溶存酸素量及び透明度を検討対象項目とした。
(中略)
②透明度
海藻草類の生育によって形成される藻場や湖沼の沈水植物帯等は、水生生物の生息の場であるとともに、富栄養化の原因となる栄養塩類を吸収するなどの水質浄化機能、及び物質循環機能を有している。
海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育は、物理的要因(水中光量、付着基盤、水温等)、化学的要因(栄養塩濃度)及び水理学的要因(流れ、波浪等)など様々な影響を受ける。このうち、一定以上の水中光量を得るために必要な透明度を確保することは、水生植物の生育に不可欠である。
沿岸域の透明度の状況については、海域についてはほとんどの地点が2m以上であるのに対し、湖沼については1m未満の地点が少なくない。
透明度が低下し、光合成が妨げられれば、水生植物群落の衰退につながるのみならず、水質浄化機能を損なうおそれがある。
また、親水利用の観点からも、自然探勝や水浴など一定の透明度が求められる場合、透明度が低下することにより、それらの利用に影響を与える場合があり、良好な水辺地を損なうおそれがある。
以上を踏まえ、海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育の場の保全・再生、ひいては健全な水環境の保全の観点から、また、良好な親水利用の場を保全する観点から、水生植物の生育に対して直接的な影響を判断でき、かつ国民が直感的に理解しやすい指標として、海域及び湖沼を対象に透明度の目標設定の検討を行う。ただし、各水域に応じて生物生産性や生物多様性が確保された豊かな水域を目指すことが重要であり、そのためには、その水域に応じた適切な透明度を確保することが肝要である。
なお、水生植物の保全の観点からは、沿岸に水生植物が生育することが多いこと、また、親水利用の場の保全の観点からも、水浴や眺望など、沖合ではなく沿岸水域を対象とするものであることから、指標としての名称は「沿岸透明度」とすることが適当である。
(中略)
4.沿岸透明度の目標設定の検討について
(1)沿岸透明度の目標設定の基本的考え方
1)水生植物の保全・再生
海藻草類及び沈水植物等の水生植物の生育の場の保全・再生の観点から、維持することが望ましい環境上の条件として、沿岸透明度の目標設定の検討を行った。
2)親水利用の場の保全
保全対象とする親水利用の目的として、①自然探勝に利用される水域で、自然環境保全上高い透明度が求められる場所における親水利用、②水浴、眺望などの日常的な親水行為(以下、「日常的親水」という。)の対象になる場所における親水利用、に分類した。海域及び湖沼における親水利用として勘案すべき水浴は、水浴場における水浴に限らず、水辺空間とのふれあいの観点から日常生活の中で行われる行為として広くとらえることが適当と考えられる。これらの親水利用の場の保全を目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、沿岸透明度の目標設定の検討を行った。
(2)沿岸透明度の目標値の導出方法
1)水生植物の保全・再生
海域においては海藻草類を対象に、湖沼においては沈水植物を対象に、それぞれの分布下限水深において生育に必要な水中光量を確保できる沿岸透明度の条件について求めた。
①活用する海藻草類の知見
水生植物の生育に必要な最低光量を確保することができる水深は、透明度と水生植物の種によって異なる。そのため、水生植物の生育に必要な種ごとの必要最低光量をもとに、水生植物に求められる種ごとの分布下限水深とそれに必要な透明度の関係式を求めた。
②活用する沈水植物の知見
沈水植物は、必要最低光量の知見が得られなかったことから、沈水植物の分布下限水深に関する知見とその場(近傍を含む)の透明度のデータを活用して、水生植物の分布下限水深と必要な透明度の関係式を直接求めた。
2)親水利用の場の保全
親水利用の場の保全の観点からは、自然環境保全及び日常的親水それぞれの利用目的に対し、望ましい透明度を検討した。
既存の環境基準の設定の検討資料のうち透明度をもとに基準値を設定した資料、親水利用に関連する既往の指標等、現状の透明度と親水利用等の関係に係るデータを活用した。
(3)沿岸透明度の目標値
1)水生植物の保全・再生
①海藻草類に係る沿岸透明度の目標値
(2)1)①に記載した導出方法の考え方に基づき、次のとおり、海藻草類の種ごとに、求められる分布下限水深から必要な透明度の目標値を算出する関係式についてまとめた。まず、水中の光量の減衰についてLambert-Beerの法則に従って水深と水中光量の関係式を求め、Poole and Atkins(1929)に従って透明度と減衰係数の関係式を求めた。これらの2つの式より、ある水中光量における透明度と水深の関係式を求めた。これに、海藻草類の種ごとの必要最低光量をあてはめ、生育に必要な年間平均透明度と分布下限水深の関係を求めると、アマモ・アラメ・カジメのそれぞれについて下表のような関係式が得られる。
種名 年間平均透明度と分布下限水深の関係 アマモ 年間平均透明度=0.95×分布下限水深 アラメ 年間平均透明度=0.83×分布下限水深 カジメ 年間平均透明度=0.64×分布下限水深 なお、アマモについて得られた上記の関係式は、実際の藻場で観測された分布下限水深と透明度の関係と概ね一致しており、上記の関係式は妥当なものであると考えられる。
②沈水植物に係る沿岸透明度の目標値
海藻草類の必要光量は、ほぼ単一種で構成される藻場で計測された光量を用いているため、種ごとの必要光量として整理した。しかし、沈水植物については、深場の車軸藻類などの例を除くと、多くの場合で複数種が混生して分布している。このため、沈水植物の生育を確保する透明度は、種ごとではなく沈水植物としてまとめて生育に必要な透明度を導出し、以下のとおり年平均透明度と分布下限水深の関係式を求めた。
沈水植物の種類 年間平均透明度と分布下限水深の関係 維管束植物車軸藻類 年間平均透明度=0.64×分布下限水深 2)親水利用の場の保全
①自然環境保全に係る沿岸透明度
海域公園地区や湖沼AA類型に指定されている湖沼のように清澄な水質を確保すべき水域の透明度は、海域については概ね10m程度、湖沼については、6~7m程度となっている。
②日常的親水に係る沿岸透明度
水浴については、水浴場水質判定基準を踏まえると、水浴場開設前又は開設期間中における水浴場内の望ましい透明度は「全透(または1m以上)」である。また、水浴場近傍海域の透明度は、平均的には6m程度、最低で2m程度であると考えられる。
眺望については、東京湾の赤潮判定の目安や琵琶湖の淡水赤潮発生時の透明度のデータを勘案すると、少なくとも1.5m以上は必要であると考えられる。
全国の公共用水域の透明度とその地点または近傍における親水利用の関係に係るデータによると、全体として、湖沼については透明度と親水利用行為の間に目立った傾向は見られなかった。海域については、透明度と多くの親水利用行為との間に目立った傾向は見られなかったが、ダイビング及び水中展望については、現在、他の親水利用行為より高い透明度の水域において利用がみられる(湖沼における利用は11m(1か所のみ)、海域における利用は平均8~9m程度)。なお、このデータはあくまで各測定地点又はその近傍における現在の透明度と親水利用の状況を整理したものであり、各親水利用行為における「望ましい」透明度を整理したものでないことに留意が必要である。
(4)沿岸透明度の目標の位置付け
水生植物の保全の観点からの沿岸透明度については、一定の知見が得られたものの、目標値については、保全対象となる水生植物に対して、保全する水域ごとに、地域の意見等を踏まえて目標分布下限水深(以下、目標水深という)を検討し、目標値となる透明度を計算式により導出することとなり、地域の実情に応じて相当幅広い範囲で目標値が設定されることが想定される。この場合、従来の環境基準に設けられている「類型」とは異なる考え方となる。
また、親水利用の場の保全の観点については参考となる知見が得られたものの、①自然環境保全、②日常的親水のいずれも、同様な親水利用を行う場合であっても、求められる透明度は水域によって異なることが考えられる。
このため、沿岸透明度については、水環境の実態を国民が直感的に理解しやすい指標であることに鑑み、水生植物の目標水深や親水利用の目的に応じた指標として設定することは有効であると考えられるものの、上記を踏まえると、環境基本法に規定する環境基準として、政府が目標を定め、必要な施策を講じてその確保に努めるものとして位置付けるよりも、むしろ、地域の合意形成により、地域にとって適切な目標(地域環境目標(仮称))として設定することが適当と考えられる。
それぞれの地域において、藻場等の水生植物の保全・再生する水域や親水利用が行われる地点の水質の状態を把握しつつ地域の実情に応じた目標値を設定し、その達成や維持を目指して様々な対策が進められることが期待される。
(5)沿岸透明度の目標値の設定
これまでの内容を踏まえると、水生植物の保全の観点からの沿岸透明度の目標値および親水利用の場の保全の観点からの沿岸透明度の目標値は、それぞれ次のとおり設定することが適当である。
①水生植物の保全の観点からの沿岸透明度の目標値
保全対象となる水生植物に対して、保全する水域ごとに、地域の意見等を踏まえて目標水深を検討し、保全対象種の生育に必要な透明度を以下の計算式から導出することにより、目標値を設定する。
(目標値の算出方法)
1)目標値(以下Xという)は、水生植物の生育の場を保全・再生する水域における保全対象種の必要透明度(年間平均値)とする。
2)Xは、保全対象種の必要光量に応じて、以下の式により計算し小数第2位を切り上げた値とする。
ただし、Z(m)は、保全対象種の目標水深(水深の設定は年間平均水位を基準)とする。
<保全対象種の必要光量ごとの計算式>
(海域)
①アマモを保全対象種として設定した場合 目標水深Zに対する透明度:X=0.95×Z
②アラメを保全対象種として設定した場合 目標水深Z’に対する透明度:X=0.83×Z’
③カジメを保全対象種として設定した場合 目標水深Z’’に対する透明度:X=0.64×Z’’
(湖沼)
保全対象種をクロモ、エビモ等(維管束植物)、シャジクモ、ヒメフラスコモ等(車軸藻類)の沈水植物に設定した場合 目標水深Z’’’に対する透明度:X=0.64×Z’’’
②親水利用の場の保全の観点からの沿岸透明度の目標値
親水利用については、以下のような親水利用行為の例やこれまでに得られた全国的な知見、当該水域の過去及び現在の透明度等を参考としつつ、水域の利水状況や特性、地域住民等のニーズ等に応じて目標値を設定する。
(親水利用の例)
- 自然環境保全:自然再生活動、環境教育等が行われている。
- 眺望(景観):景観としての利用がある。
- ダイビング:ダイビング場が存在している。
- 水浴:水浴場が存在している。
- 親水(水遊び):泳ぐことはしないが、水には触れるといった利用がある(親水公園等)。
- 散策:水には触れないが(触れる可能性はあるが、主たる目的ではない)、周辺を散策するなど、水面を眺めるといった利用がある(キャンプ、サイクリングなども含まれる)
- 釣り:岸で釣りを行う、又は船を用いて釣りを行う。
- 船:ボート、ヨット、遊覧船等による湖面の利用がある(ボート貸し出し、定期遊覧船の運行がある)。
(6)測定方法
沿岸透明度の測定方法については、以下の通りとすることが適当である。
項目 測定方法 沿岸透明度 別紙2に掲げる方法 (7)沿岸透明度の各水域における目標値設定の方向性(抄)
沿岸透明度の目標値の当てはめについては、水生植物の生育の場を保全・再生する水域又は親水利用のための水質を特に確保すべき水域を対象として、それぞれの水域ごとに特定し、以下の点に留意して目標値を設定することが適当である。
1)現地調査等により、各水域の現状の透明度を把握する。既存の測定点において過去から測定を行っている場合にはその測定結果も活用する。併せて測定地点における水深を測定する。
2)水生植物の保全・再生の観点からの沿岸透明度については、魚介類等水生生物の生息・産卵場確保、水質浄化機能、物質循環機能の確保等の観点から保全対象種を選定し、その生育の場を保全・再生すべき水域を設定する。その上で、その水域ごとに目標水深を設定し、各地域の幅広い関係者の意見等を踏まえて、透明度の目標値を導出することを基本とする。目標水深については、水生植物の生育の場の現状又は過去の分布状況や、自然再生に係る関連計画等の状況を踏まえて目標値を設定する。
3)親水利用の場の保全の観点からの透明度については、親水利用行為を踏まえて、その範囲を設定し、水域の利水状況、水深、水質などの特性、地域住民等のニーズ等に応じて目標値を設定する。目標とする透明度は、各地域の幅広い関係者の意見等を踏まえて合意形成を図った上で、現状及び過去の当該水域の状況も考慮しつつ設定する。例えば、水域ごとの親水利用の目的に照らし、現状の透明度の維持や過去の透明度の回復なども考えられる。
4)水生植物の保全の観点と親水利用の場の保全の観点について、両方が重なる範囲においては、目標値の高い方を当該範囲の目標値として設定することが望ましいが、各地域の幅広い関係者の意見等を踏まえて、適切な透明度を設定する。
目標値の設定の検討の際は、場所によっては底泥の巻き上げ等の自然的要因等により透明度が低くなることに留意する。
なお、具体的な目標値設定の手順については、図2(略)のような流れを想定している。目標値設定に係る考え方及び手順については、国として整理を行った上で示すことが望ましい。
(中略)
(8)沿岸透明度の監視及び評価方法
沿岸透明度の監視及び評価方法については、以下の点を基本とすることが適当である。
1)測定地点
測定地点は、目標値を当てはめる水域における水生植物の生育環境、親水利用行為、透明度の状況、水深等を勘案して、適切に評価できる地点(代表点もしくは複数点)を設定する。
2)測定頻度
年間を通じ、原則として月1日以上測定する。
3)評価方法
水生植物の保全・再生の観点からの沿岸透明度の目標値は、年間平均透明度と分布下限水深の関係式から求めるものである。このため、目標を達成しているかどうかの評価は、年間平均値が沿岸透明度の目標値を下回らないことをもって目標を達成しているものと評価すべきである。また、親水利用の場の保全の観点においても、親水利用の行為が期間限定で行われることも想定されるが、眺望など年間を通した利用も考慮されうることから、年間平均値で評価して差し支えないと考えられる。
(中略)
(別紙2)沿岸透明度の測定方法(抄)
1 器具
原則として直径30cmの白色円板(透明度板、セッキー円板)を用いる。白色の色調の差は透明度にそれほど影響しないが、円板の反射能は透明度に微妙に影響するので、表面が汚れたときは磨くか塗り直しをする。
(中略)
2 測定
直射日光を避けながら船の陰等で測定するように心がける。白色円板を静かに水中に沈めて見えなくなる深さと、次にこれをゆっくり引き上げて見え始めた深さとを反復して確かめて平均し、測定結果をメートル(m)で表示する。
錘(おもり)は、通常2kg程度であるが、流れがあってロープが斜めになるような場合には、錘を重くする等してロープが垂直になるようにする。
4.参考資料
・平成27年12月7日・中央環境審議会「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて(答申)」(参考資料を含む) http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成28年3月30日・環境省水・大気環境局水環境課事務連絡「地域環境目標「沿岸透明度」について」 http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成28年11月1日・中央環境審議会水環境部会(第42回)資料5「底層溶存酸素量及び沿岸透明度の評価方法等について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y090-42/mat05.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成30年7月・環境省水・大気環境局水環境課「沿岸透明度の目標設定ガイドライン」 http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/04.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成30年7月・環境省水・大気環境局水環境課「沿岸透明度の目標設定ガイドライン(概要版)」 http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/03.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成30年7月・環境省水・大気環境局水環境課「沿岸透明度の目標設定ガイドライン(資料編)」 http://www.env.go.jp/water/transparency/pdf/05.pdf 【NIES保管ファイル】
(4)生活環境の保全に関する環境基準(水生生物保全関係)及び要監視項目
①設定の考え方
(平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」より)(抜粋)
4.水生生物の保全に係る水質目標
この項では、環境基準等の水質目標の設定にあたり、その基本的考え方をまず示した上で、目標値導出についての詳細を述べる。
(1)水質目標の設定に当たっての基本的考え方
水生生物保全の観点からの水質目標の設定は、諸外国の環境保全行政において採用されている考え方を参考に、我が国の水生生物を保全する環境管理施策を適切に講じる観点から行うこととする。
①目指すべき保全の水準
水生生物の保全に係る水質目標では、公共用水域における水生生物の生息の確保という観点から世代交代が適切に行われるよう、水生生物の個体群レベルでの存続への影響を防止することが必要であることから、特に感受性の高い生物個体の保護までは考慮せず、集団の維持を可能とするレベルで設定するものとする。
また、目標値は、水質による水生生物への影響(リスク)を未然に防止する観点から環境水中の濃度レベルを導出するものとし、水生生物にとっての「最大許容濃度」や「受忍限度」といったものではなく、維持することが望ましい水準として設定することが適当である。
目標を最大許容限度及び受忍限度として採る場合には、その限度までは汚染することもやむを得ない、あるいは、その限度まで我慢しなければならない水準となるし、またその限度を超えるならば直ちに水生生物にある程度以上の影響を及ぼすという性格を持つ。環境基準等の水質目標は、水生生物の集団維持の最低限度としてではなく、より積極的にこの保護を図るという観点の性格を持つべきである。このため、この数値を超える水域であっても、直ちに水生生物にある程度以上の影響を及ぼすといった性格をもつものではない。
②目標値の導出
水生生物の生息は、開発行為による生息場の消失等の多様な要因によって影響を受けることから、化学物質の生態系への影響の程度を実環境において定量的に分離・特定することは困難である。したがって、目標値を導出するためには、個別物質ごとに代表的な生物種について、半数致死濃度等(毒性値)に係る再現性のある方法によって得られたデータをもとに、試験生物への毒性発現が生じないレベルを確認し、その結果に、種差等に関する科学的根拠を加味して演繹的に求めることが適当である。
化学物質については、毒性の程度はもとより、その数や環境への排出の形態、環境中の挙動、影響に至るメカニズム、発現する影響の内容が物質ごとに大きく異なるため、環境中に排出されうる物質ごとに検討するものとする。
水生生物の保全の観点からは、当該水域に生息する魚介類の餌となる生物の個体数に影響が出れば、当該水域に生息する魚介類の生息にも影響が生じることから、評価対象とする生態影響は、魚介類及び餌生物双方の生息に直接関係する、死亡、成長・生長、行動、忌避、繁殖、増殖等の影響内容に関するものとする。
また、公共用水域において通常維持されるべき水質の水準を検討するものであることから、基本的に慢性影響の観点から目標値を導出することが妥当である。また、科学的知見に基づき、同一区分内の生物種による感受性の相違等を考慮することにより、同一区分内で最も感受性が高い生物種に影響を及ぼさない濃度を目標値として導出することとする。
③対象とする試験生物及び水域区分
目標値は科学的根拠に基づいて設定する必要があることから、我が国に生息する魚介類及びその餌生物等に係る化学物質の用量反応関係に関する既存試験結果の中から、科学的に信頼性のおける文献のみを収集・評価し、利用することが妥当である。また、魚介類のみならず、餌生物についても評価の対象とする。
水生生物については、淡水域及び海域でそれぞれ生息する種も異なり、また、化学物質の毒性発現についても異なると考えられることから、まず大きく主たる生息域によって淡水域と海域に区分するものとする。
淡水域については、河川と湖沼での生息種を明確に区分することは困難であるため、河川と湖沼と区別せず淡水域として一括するものとする。他方、淡水域に生息する魚介類が冷水域と温水域では異なっていることから、淡水域の生息域を水温を因子として2つに区分することが適当である。ただし、通し回遊魚については、主たる生息域で区分することが適当である。
海域については、生息域が広範にわたり、生息域により水生生物をグルーピングすることは困難であることから、当面、一律の区分とすることが適当である。
なお、淡水域・海域とも、特に、産卵場及び感受性の高い幼稚仔等の時期に利用する水域についてはより厳しい目標をあてはめることがあり得るものである。
以上の考え方による、我が国における水生生物保全の観点からの水域区分は以下の通りとすることが適当である。
淡水域(河川及び湖沼)
A イワナ・サケマス域 イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 A-S イワナ・サケマス特別域 イワナ・サケマス域に生息する水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 B コイ・フナ域 コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 B-S コイ・フナ特別域 コイ・フナ域に生息する水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 海域
G 一般海域 海生生物の生息域 S 特別域 海生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 (2)目標値の導出方法
目標値の導出は、国際的にも定着した最新の化学物質による生態影響の評価方法を用いることとし、現時点で利用可能な内外の科学的データを収集・整理し、委員の専門的知見に基づき検討・評価を行い、我が国の環境を保全する上で適切な水質目標値を導出するものとする。その際、我が国の水生生物の生態特性や我が国の環境管理制度の特徴を踏まえることとする。
ア.水質目標の優先検討対象物質
水生生物の保全の観点からの目標値を優先的に検討すべき物質は、リスクの蓋然性が高いものとして、以下の要件を満たす物質とすることが適当である。
①水生生物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質、すなわち、水生生物に有害な物質(関係法令等により規制等が行われている物質や、専門家による有害性の指摘がなされている物質等)
であり、かつ、
②その化学物質が有する物理化学的特性、その製造、生産、使用状況からみて、水環境中で広範にあるいは継続して存在するもの。すなわち、水生生物が継続して暴露しやすい物質
イ.毒性評価文献の範囲
検討対象物質に係る水生生物の毒性評価に係る内外の知見を可能な限り広く収集することとし、目標値が我が国における水生生物保全の観点から導出されるものであることから、目標値の導出を行う毒性評価文献の範囲は、我が国に生息する有用動植物及びその餌生物(元来我が国に生息する水生生物で、かつ、通常の実験等に供される水生生物種(例:OECDテストガイドライン推奨種の一つであるメダカ)を含む。)を対象としたものとすることが妥当である。
また、評価の対象となる文献は、魚介類及び餌生物の、死亡、成長・生長、行動、忌避、繁殖、増殖等の影響内容に関するものとする。
ウ.評価の考え方
評価対象となる毒性試験結果は、専門家による信頼性及び目標値導出への利用可能性の評価を経て、信頼性があり、エンドポイントや暴露期間等が本検討の内容と合致しており、目標値導出に利用可能と判断されたもののみ、目標値の導出に用いるものとする。
エ.目標値導出の手順等
評価対象となる毒性試験結果を、水域区分ごとに魚介類とその餌生物に分類し、魚介類に慢性影響を生じないレベルとして算出される「最終慢性毒性値(魚介類)」と餌生物が保全される「最終慢性毒性値(餌生物)」の小さい方の数値を採用し、目標値とする。
目標値は、慢性影響の観点から設定するものであることから、原則として信頼できる慢性毒性値のみを目標値の導出に用いるものとし、信頼できる慢性毒性値が得られない場合には、米国EPAにおいて利用されている手法と同様に、信頼できる急性毒性試験結果に、急性慢性毒性比(急性毒性値と慢性毒性値との比)を用いて慢性毒性値を求めるものとする。
急性慢性毒性比は、魚類、甲殻類及び藻類の急性慢性毒性比に係るこれまでの知見、当該評価対象物質について得られている毒性試験結果から導出可能な急性慢性毒性比等を総合的に勘案し、専門家の判断により、適切な値を用いることとする。
また、急性毒性及び慢性毒性双方の信頼できる試験結果が得られている場合は、急性毒性試験結果は用いない。なお、目標値の導出にあたっては、魚介類は水産資源としての重要性があることから、少なくとも淡水域・海域それぞれについて1種以上の魚介類の信頼できる毒性値が得られていることを必要条件とする(魚介類の信頼できる毒性値がいずれの水域においても得られない場合には、目標値は導出しない)。
i)最終慢性毒性値(魚介類)の算出
同一水域区分内の魚介類に係る毒性試験結果から得られる慢性毒性値の最小値に着目して最終慢性毒性値を導出する。
毒性試験結果が得られた魚介類が、当該水域区分において最も感受性が強いとは限らないことから、最終慢性毒性値に種比を用いて目標値を導出するものとする。
種比は、最終慢性毒性値の導出に用いた毒性試験の生物種、信頼できる毒性試験結果の数、試験結果間のばらつき(例:OECDテストガイドライン推奨種等、毒性データが多い種の毒性値のばらつき)、対象物質の蓄積性等を総合的に勘案し、専門家の判断の上で決定する。
なお、脆弱な個体までの保護を目的とするものではないことから、いわゆる安全係数は適用しない。
ii)最終慢性毒性値(餌生物)の算出
餌生物については、一般的に魚介類が単一の生物のみを餌生物としているとは考えがたいこと等を考慮し、米国EPAが採用している手法と同じ手法として、まず同じ属の生物を用いた毒性値の幾何平均値をとった上で、属間の最小値を「最終慢性毒性値(餌生物)」とする。
iii)目標値の導出
こうして算出された魚介類についての最終慢性毒性値と餌生物についての最終慢性毒性値の小さい方の数値を採用し、目標値とする。
なお、この手順を踏んで導出された目標値については、公表されている各種科学文献に示された毒性情報及び毒性値との比較を行い、専門家の観点から、妥当な水準であるかの検証を総合的に行うことが必要である。
5.環境基準等の設定
水生生物の保全の観点からの水質目標は、従来の人にとっての有害物質と同様に、環境管理施策やモニタリングの必要性に応じて、環境基準項目、要監視項目等の位置づけをすることが適当である。
(1)水生生物の保全の観点からの環境基準等の位置づけ
「環境基準」については、環境基本法第16条第1項において、政府は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」、すなわち環境基準を定めることとされている。この中で「生活環境」とは、同法第2条第3項において、「生活環境」には「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む」と定義されている。
水生生物の保全の観点からの環境基準等の水質目標の設定は、生活環境という概念の中心にある有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生育環境の保護を対象とするものである。
したがって、水生生物の保全の観点から設定される環境基準は、環境基本法上の環境基準のいわゆる生活環境項目として位置づけることができる。
なお、水生生物への蓄積を通じた人の健康に与える影響への懸念があれば、別途、健康項目としての基準の設定の要否を検討すべきものと考えられる。
(2)環境基準設定の判断
施策の必要性に応じて、当該目標値を、環境基準項目又は要監視項目として位置づけるか否かを判断するものとする。
環境基準項目は、水環境の汚染を通じ人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがあり、また、水質汚濁に関する施策を総合的にかつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質であることから、公共用水域において、全国的に目標値を超える地点があるもの、また、目標値に近いレベルになる蓋然性があるものとする。
また、公共用水域等における検出状況(目標値の超過及び目標値の10%値の超過等のメルクマール)等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、引き続き環境中の検出状況等に関する知見の集積に努めるべきと判断されるものについては、水質環境基準の健康項目における取扱と同様に、「要監視項目」として位置づけ、継続して公共用水域等の水質測定を行い、その推移を把握していくことが適当である。
要監視項目は、監視対象として選定するものであることから、目標値に近くなる可能性が乏しいものを除き、幅広く選定するものとする。
なお、検出状況等から判断した結果、要監視項目にも該当しないこととなった化学物質に係る目標値についても、その根拠とともに公表し、水質汚染事故時等において水生生物への影響の程度を判定する指標として用いることが望ましい。
(3)監視及び評価
水生生物の保全の観点からの水質目標については、公共用水域での検出状況によって、全国的な監視を必要とするものがあり得る。この場合、以下により、監視及び評価を行うことが適当である。
ア.監視
①測定地点
測定地点の選定に当たっては、水生生物の生息状況等を勘案し、水域内の既存の環境基準点・補助点等を活用しつつ、水域の状況を把握できる適切な地点を選定して行う。
②測定回数
既存生活環境項目と同様に、年間を通じ、原則として月1日以上採水分析することが適当である。
③調査時期や頻度の変更
水生生物の生息状況、農薬散布等発生源の状況等により特定の時期等に着目する必要がある場合、凍結等水域の状況が調査に不適当な時期がある場合等にあっては、水質濃度の時期的変動の有無等を勘案し、必要な対策につなげられるよう、調査時期や頻度を変更することも考えられる。
イ.評価
本検討においては、目標値の導出にあたって慢性影響に着目していることから、評価は年平均値で行うものとする。
なお、重金属のように、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等において検出される可能性がある物質については、評価及び対策の検討に当たって十分考慮する必要がある。
(4)類型あてはめ
ア.類型あてはめに当たっての考え方
水生生物の保全に係る環境基準が定められた場合、国又は都道府県により水域ごとに環境基準の類型指定が行われることになるが、その際の基本的な考え方を以下に示す。
①あてはめが必要な水域
水域類型のあてはめは、水産を利水目的としている水域のみならず、水生生物の保全を図る必要がある水域のすべてにつき行うものである。その際、当該化学物質による水質汚濁が著しく進行しているか、又は進行するおそれがある水域を優先することが望ましい。
水生生物が全く生息しないことが確認される水域及び水生生物の生息に必要な流量、水深等が確保されない水域については、その要因を検討することが重要であり、一義的に水質環境基準の水域類型の指定を検討する必要はない。なお、当該要因の解決等により、水生生物の生息が可能となった場合には、当然、類型あてはめを行うことが必要である。
重金属のように、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等において検出される可能性がある物質であって、当該水域において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されると判断される場合には、あてはめに当たって十分考慮する必要がある。
②あてはめを行う水域区分
効率的な監視・評価を行う観点から、従来の生活環境項目に係る水域区分を最大限活用することが望ましい。
いわゆる汽水域については、河川(淡水域)に区分されることになる。水生生物の生息という観点からは特異的環境とも考えられるが、他方、汽水域を定義する塩分濃度等が明確に規定されておらず、正確に汽水域を特定するのが困難であり、目標値を設定することができないことから、従来の取扱に従うものとする。
また、塩水湖を、淡水域とするか海水域とするかについては、当該水域における水生生物の生息状況からより適切な類型をあてはめるものとする。
産卵場及び幼稚仔の生息の場について、その水域を厳密化するあまり、河川のごく一部を細切れに(パッチ状に)区分することは、実際の水環境管理に当たって混乱が生じる恐れがあることから、淀み等の部分のみにあてはめるのではなく、これらが連続するような場合には一括してあてはめることが望ましい。
③達成期間
当該水域における水質の現状、人口・産業の動向、基準の達成の方途等を踏まえ、将来の水質の見通しを明らかにしつつ、環境基準の達成期間を設定する必要がある。ただし、環境基準を速やかに達成することが困難と考えられる水域については、当面、施策実施上の暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図るものとする。
(以下略)
(参考資料)
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考5)毒性評価文献の範囲 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-05.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考6)目標値検討に用いるエンドポイントと影響内容 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-06.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考7)急性影響、慢性影響について https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-07.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考8)物質選定の考え方 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_08.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考9)毒性試験結果の評価項目及び留意事項 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-09.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考10)最終慢性毒性値導出手順について https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-10.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考11)生物種による感受性の相違(種比)について https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-11.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考12)急性慢性毒性比(ACR)の適用について https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-12.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考13)「生活環境」の範囲について https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-13.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考14)水生生物保全環境基準設定までの流れ https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-14.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考15)類型あてはめについて https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-15.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考19)諸外国における水生生物の保全に係る環境基準の設定状況 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-19.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考20)水生生物の保全に係る水質環境基準について(検証) https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_20.pdf 【NIES保管ファイル】
(平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」より)(抜粋)
当部会としては、今後の水生生物保全に係る水質目標の設定等をより適切で合理的なものとするため下記の点が考慮されるべきであると判断するのでここに特に申し添えておきたい。
記
1.専門委員会における水質目標値の検討に当たっては、利用可能な科学的文献から得られた毒性情報に基づきその妥当性を総合的に検証するとともに、目標値導出の手順についても常に国内外の動向及び科学的な知見の向上を踏まえて必要な見直しを行うものとする。
2.環境省は他の行政機関、民間事業者を含め広く関係者の協力を得つつ、今後とも水環境中の汚染物質の水生生物への影響に関する科学的情報(実環境中における汚染物質の化学形態や他物質の共存状況等による毒性変化及び水生生物の生息状況を含む。)の集積を図り、今後の専門委員会の調査・審議に有効に活用されるよう努める必要がある。
(参考資料)
・平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku.pdf 【NIES保管ファイル】
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
○総括表
| 項目 | 基準値(類型ごとに異なる) | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 全亜鉛 | 0.01~0.03mg/L以下 | 平成15年11月5日 | |
| ノニルフェノール | 0.0006~0.002mg/L以下 | 平成24年8月22日 | |
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 0.006~0.05mg/L以下 | 平成25年3月27日 |
○河川
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
(備考)
1 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
○湖沼
河川と同じ
○海域
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||
| 生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
(評価方法)(常時監視等の処理基準抜粋)
第2 水質汚濁防止法関係
1.常時監視(法第15条関係)(抄)
(中略)
2)生活環境の保全に関する環境基準
①BOD、CODの環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価
(中略)
イ.水生生物保全環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。なお、当該水域における検出状況が、明らかに人為的原因のみならず自然的原因も考えられる場合や、河川の汽水域において海生生物が優占して生息する情報がある場合には、これらのことを踏まえて判断すること。
ウ.複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
(中略)
2.測定計画(法第16条関係)(抄)
(中略)
イ.測定頻度
(ア)環境基準項目
(中略)
イ)生活環境の保全に関する環境基準項目については、次によることとする。
a.通年調査
環境基準点、利水上重要な地点等で実施する調査にあっては、年間を通じ、月1日以上、各日について4回程度採水分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。なお、底層溶存酸素量の調査に当たって、可能であれば、水生生物の生息・再生産の場を保全・再生するうえで重要な地点においては連続測定調査を行うことが望ましい。
b.通日調査
a.の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあっては、年間2日程度は各日につき2時間間隔で13回採水分析することとする。
c.一般調査
前記以外の地点で補完的に実施する調査にあっては、年間4日以上採水分析することとする。
(以下略)
(参考資料)
・令和3年10月7日・環境省水・大気環境局長「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(環水大水発第2110073号・環水大土発第2110073号) https://www.env.go.jp/hourei/add/e82.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○全亜鉛
1.測定方法
日本産業規格K0102の53に定める方法
2.設定経緯
平成15年9月12日・中央環境審議会答申
平成15年11月5日・環境省告示第123号
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状(亜鉛として)
・融点:419.5~419.8℃
・沸点:907.0~908.0℃
・比重:7.140~7.142
・蒸気圧:0.13kPa(487℃)、7.99E-23mmHg(25℃、計算値)
・水溶解度:不溶、343,000mg/L
・n-オクタノール/水分配係数:-0.47(計算値)
・空気中で加熱すると容易に燃焼。
・直接塩素、硫黄と反応。
・酸、アルカリに溶けて水素を発生。
・海洋水中の濃度は、表層濃度が低く、深度が増すにつれ途中から一定濃度の分布となる栄養塩と相関性のあるパターンを示す。自然水中に亜鉛が存在することはまれであるが、水中の濃度は、鉱山排水、工場排水の混入、または亜鉛メッキ鋼管からの溶出等に起因する。アルカリ性で、水酸化亜鉛として沈殿するが、過剰のアルカリで溶解する。リン酸の存在でリン酸亜鉛として沈殿する。硫化水素と反応し、中性溶液から硫化亜鉛として沈殿するが、酸性になると溶解する。
(2)生産量等
(平成12年)
・国内生産量:654,384t、輸出量:51,096,000kg(合金を除く)、輸入量:67,562,440kg(合金を除く)。
(3)主な用途
・亜鉛鉄板、亜鉛板、黄銅(真鍮)、伸銅品、亜鉛合金ダイカスト、写真製版、亜鉛華、亜鉛末等。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・水道水質基準 1.0mg/L以下
・水質汚濁防止法一律排水基準 5mg/L(亜鉛含有量)
・水産用水基準 0.001mg/L(淡水域)、0.005mg/L(海域)
・米国EPAの水生生物保全に係る水質クライテリア 淡水CMC 65μg/L(硬度50mg CaCO3/L)、淡水CCC 65μg/L(硬度50mg CaCO3/L)
・カナダにおける水生生物ガイドライン 30μg/L
・英国の法令で定められた環境基準 感受性の高い水生生物(例えばサケ類)に対して淡水年平均値8μg/L(硬度0~50mgCaCO3/L)、他の水生生物(例えばコイ類)に対して淡水年平均値75μg/L(硬度0~50mgCaCO3/L)、海生生物に対して年平均値40μg/L
5.環境中における検出状況(設定時)
<淡水域>
・常時監視(平成3~12年度):10,231(検出地点)/20,164(測定地点)、検出範囲1~13,000μg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:30μg/L)超過2,294地点(11.4%)、10%値超過10,079地点(50.0%)
・要調査項目(平成12年度):39(検出地点)/65(測定地点)、検出範囲5~190μg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:30μg/L)超過6地点(9.2%)、10%値超過39地点(60.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):1,021(検出地点)/1,892(測定地点)、検出範囲1~1,300μg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:30μg/L)超過299地点(15.8%)、10%値超過1,007地点(53.2%)
<海域>
・常時監視(平成3~12年度):793(検出地点)/4,684(測定地点)、検出範囲1~480μg/L、目標値(水域区分G:20μg/L)超過179地点(3.8%)、10%値超過787地点(16.8%)
・要調査項目(平成12年度):2(検出地点)/11(測定地点)、検出範囲10~38μg/L、目標値(水域区分G:20μg/L)超過1地点(9.1%)、10%値超過1地点(9.1%)
・独自調査結果(平成4~13年度):104(検出地点)/210(測定地点)、検出範囲1~61μg/L、目標値(水域区分G:20μg/L)超過31地点(14.8%)、10%値超過99地点(47.1%)
・常時監視(平成3~12年度):793(検出地点)/4,684(測定地点)、検出範囲1~480μg/L、目標値(水域区分S:10μg/L)超過418地点(8.9%)、10%値超過793地点(16.9%)
・要調査項目(平成12年度):2(検出地点)/11(測定地点)、検出範囲10~38μg/L、目標値(水域区分S:10μg/L)超過2地点(18.2%)、10%値超過2地点(18.2%)
・独自調査結果(平成4~13年度):104(検出地点)/210(測定地点)、検出範囲1~61μg/L、目標値(水域区分S:10μg/L)超過56地点(26.7%)、10%値超過102地点(48.6%)
6.基準値の根拠の概要
(1)基準値の設定手順(専門委員会報告より)
1)イワナ・サケマス域(水域区分Aおよび水域区分A-S)
【水域区分A】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類では、信頼できる慢性毒性値がSalvelinus fontinalis(イワナ類)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、本水域区分の魚介類の最終慢性毒性値は、Salvelinus fontinalis(イワナ類)で得られている慢性毒性値310 μg/L(14日間NOEC)に種比「10」を用いて算出した数値(31μg/L)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではEpeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値が30μg/L(4週間NOEC成長低下)であり、この値を最終慢性毒性値(餌生物)とする。
なお、複数の信頼できる急性毒性値が得られており、Selenastrum属(緑藻類)の15μg/L(24時間増殖速度EC50)、Ceriodaphnia属(ミジンコ類)の65μg/L(48時間死亡LC50)から、急性慢性毒性比(藻類4、甲殻類10)を用いて算出される慢性毒性値は、それぞれ16μg/L、6.5μg/Lと、30μg/Lよりも低い値となるが、信頼できる慢性毒性値から得られる30μg/Lを用いるものとする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Aにおいては、餌生物であるEpeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
【水域区分A-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の幼稚仔の毒性値は急性毒性、慢性毒性ともに得られていないため、成体の最終慢性毒性値(31μg/L)を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は30μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分A-Sにおいては、餌生物であるEpeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
2)コイ・フナ域(水域区分Bおよび水域区分B-S)
【水域区分B】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域においては、我が国に生息する魚介類の信頼できる毒性値は得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物では、Epeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値が30μg/L(4週間NOEC成長低下)であり、この値を最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分Bにおいては、餌生物であるEpeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
【水域区分B-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域においては、我が国に生息する魚介類の幼稚仔の信頼できる毒性値は得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Bの餌生物の最終慢性毒性値は30μg/Lであり、この値を水域区分B-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分B-Sにおいては、餌生物であるEpeorus属(ヒラタカゲロウ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
3)海域
【水域区分G】
○最終慢性毒性値(魚介類)
我が国の海域に生息する魚介類の信頼できる毒性値は、成体では得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物の慢性毒性値が得られていないことから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(餌生物)を算出する。Nitzschia属(珪藻類)の急性毒性値65μg/L(4日間IC50増殖阻害)を藻類の急性慢性毒性比「4」で除した16μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分Gにおいては餌生物であるNitzschia属(珪藻類)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
【水域区分S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
海域の魚介類の幼稚仔の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
魚介類の急性毒性値の最小値であるStrongylocentrotus purpuratus(ウニ類)の急性毒性値97.2μg/L(96時間LC50死亡)を採用することとする。この値は、クルマエビ類の急性毒性値4,800μg/L(96時間LC50死亡)に比べて小さな値となっており、亜鉛に対するウニ類の感受性はクルマエビ類より高いと判断されることから、種比「1」及び魚類の急性慢性毒性比「10」で除した9.7μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Gの餌生物の最終慢性毒性値は16μg/Lであり、この値を水域区分Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分Sにおいては、Strongylocentrotus purpuratus(ウニ類)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した10μg/Lを目標値案とする。
(2)環境基準項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域における亜鉛の検出については、公共用水域常時監視結果等多くの調査結果がある。目標値と公共用水域等における検出状況を比較すると、全国的な調査である公共用水域常時監視結果において、亜鉛は公共用水域等において目標値を超過する地点が、平成3年度から12年度までの10年間で、淡水域でのべ20,164地点中のべ2,294地点あり、海域ではのべ4,684地点中、一般海域の目標値を超過する地点がのべ179地点、特別域の目標値を超過する地点がのべ418地点ある。
このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとする。
7.参考資料
・平成15年5月8日・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(第5回)参考17「検討対象物質に係る検出状況」 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その1) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月12日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/t094-h1504.pdf 【NIES保管ファイル】
○ノニルフェノール
1.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表11に掲げる方法
2.設定経緯
平成24年3月7日・中央環境審議会答申
平成24年8月22日・環境省告示127号
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・ノニルフェノールは、直鎖のノニル基、または分岐ノニル基がフェノール環に結合した環式有機化合物であり、示性式はC6H4(OH)C9H19で示される。ノニルフェノールにはノニル基の分枝の違い及び置換位置の違いにより理論上211種の異性体が存在する。市販の分岐型ノニルフェノールの多くは、フェノールとプロピレン3量体とのフリーデル-クラフト反応により合成され、主成分は分岐型4-ノニルフェノールであり、その他に、2-置換体、3-置換体、2,4-ジノニル置換体などが含まれる。
・融点:約-8℃※1,2
・沸点:293-297℃※1、293-297℃※2
・比重:0.95g/cm3(20℃)※2
・蒸気圧:0.072Pa(25℃、外挿値)※1
・解離定数(pKa):11.06※1、10.7±1
・logKow:3.80~4.77※1,2
・水溶解度:6,237μg/L(pH7.0)
・ヘンリー定数:0.111Pa-m3/mol
・生物分解性(好気的):BOD 0%(試験期間:2週間、被験物質:100ppm、活性汚泥:30ppm)。ノニルフェノールで馴化した汚泥を用いた場合には、ノニルフェノールは40日間で78%が分解される。
・生物分解性(嫌気的):調査した範囲内では報告されていない。
・化学分解性(加水分解性):一般的な水環境中では加水分解されない。
・生物濃縮性:環境中の水生生物相において、低~中程度。
・土壌吸着性:-
※1:CASRN:84852-15-3、※2:CASRN:25154-52-3
(2)環境中での動態
平成14年度から平成21年度に調べられた我が国の淡水域からは、最大で8.4μg/Lのノニルフェノールが検出され、検出下限値0.01~0.1μg/Lの範囲の中での検出率は、各年度ともに10%を超える。環境中からは分岐型の4-ノニルフェノールの異性体が主に検出されている。
水環境中に検出されるノニルフェノールは、ノニルフェノールが排出されたものと、ノニルフェノールエトキシレートとして排出されたものが分解過程を経て副生成したものとがある。
ノニルフェノールエトキシレートのアルキル基は分岐型であることから、微生物分解を受けにくく、生分解はエトキシ基の側から進行する。
環境中に放出されたノニルフェノールエトキシレートは、好気性の環境条件下において、微生物の作用等によって段階的にエトキシ基が外れ、ノニルフェノールジエトキシレート(NP2EO)やノニルフェノールモノエトキシレート(NP1EO)が生成する。
ノニルフェノールジエトキシレート(NP2EO)やノニルフェノールモノエトキシレート(NP1EO)は、これまでの知見からは、嫌気的な状況が生じる環境下で、ノニルフェノールに分解されるものと考えられる。
ノニルフェノールエトキシレートの自然界での発生は知られておらず、全て人為発生源からのものである。
(3)生産量等
<生産量・輸入量(推定値)>
・生産量:8,000t(平成19年)、8,000t(平成20年)、6,000t(平成21年)
<化審法製造・輸入数量>
(ノニルフェノール)
・製造数量及び輸入数量の合計:9,480t(平成18年度)、8,619t(平成19年度)
(ノニルフェノールエトキシレート)
・製造数量及び輸入数量の合計:6,844t(平成19年度)、5,482t(平成20年度)、5,326t(平成21年度)
※製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す
(4)主な用途
・ノニルフェノールは、約50年間にわたり、トリス(ノニルフェニル)フォスファイト(TNPP)、ノニルフェノールエトキシレート(NPnEO)類及びノニルフェノール-ホルムアルデヒド縮合樹脂の原料として用いられている。ノニルフェノールは、プロピレンの三量体のノネンとフェノールの反応により工業的に合成され、そのうち、約6割が界面活性剤用途とされている。日本界面活性剤工業会ホームページによれば、2000年に日本では16,500tのノニルフェノールが生産され、そのうち、約56%に当たる9,276tが界面活性剤原料として、エチレンオキサイドを付加(ノニルフェノール1mol当たり平均約10molを付加)して、26,127tの非イオン界面活性剤ポリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテル(以下、ノニルフェノールエトキシレート(NPnEO)という)が国内で生産されている。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・U.S. EPA Clean Water Act Aquatic life criteria
(淡水CMC)28μg/L
(淡水CCC)6.6μg/L
(海(塩)水CMC)7μg/L
(海(塩)水CCC)1.7μg/L
・英国環境庁 UK Standard Surface Water
(Inland/ Other surface waters)AA-EQS 0.3μg/L(4-nonylphenol)、MAC-EQS 2.0μg/L(4-nonylphenol)
・カナダ Environment Canada Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life
(Freshwater (Long Term))1.0μg/L(Nonylphenol and its ethoxylates)
(Marine (Long Term))0.7μg/L(Nonylphenol and its ethoxylates)
・ドイツ連邦環境庁 Water Framework Directive Annual average EQS
(Watercourses and lakes)0.3μg/L(4-nonylphenol)
(Transitional and coastal waters)0.3μg/L(4-nonylphenol)
・ドイツ連邦環境庁 Water Framework Directive MAC-EQS
(Watercourses and lakes)2μg/L(4-nonylphenol)
(Transitional and coastal waters)2μg/L(4-nonylphenol)
5.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(ノニルフェノール)
(平成17年度)
届出:(大気)784kg、(公共用水域)5.0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)2,700kg、(当該事業所外への移動)75,890kg
届出排出量:789kg、届出外推計排出量:27kg、合計:816kg
(平成18年度)
届出:(大気)340kg、(公共用水域)10kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)2,000kg、(当該事業所外への移動)68,681kg
届出排出量:350kg、届出外推計排出量:6kg、合計:356kg
(平成19年度)
届出:(大気)235kg、(公共用水域)8.6kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)1,900kg、(当該事業所外への移動)55,496kg
届出排出量:244kg、届出外推計排出量:0kg、合計:244kg
(平成20年度)
届出:(大気)86kg、(公共用水域)1.8kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)6.2kg、(当該事業所外への移動)40,920kg
届出排出量:88kg、届出外推計排出量:2,426kg、合計:2,514kg
(平成21年度)
届出:(大気)501kg、(公共用水域)2.1kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0.2kg、(当該事業所外への移動)39,206kg
届出排出量:503kg、届出外推計排出量:3,136kg、合計:3,639kg
(ノニルフェノールエトキシレート)
(平成17年度)
届出:(大気)4,258kg、(公共用水域)43,553kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)74,845kg、(当該事業所外への移動)454,343kg
届出排出量:47,811kg、届出外推計排出量:748,022kg、合計:795,833kg
(平成18年度)
届出:(大気)1,474kg、(公共用水域)32,113kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)54,422kg、(当該事業所外への移動)362,849kg
届出排出量:33,587kg、届出外推計排出量:688,147kg、合計:721,734kg
(平成19年度)
届出:(大気)1,527kg、(公共用水域)49,239kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)50,569kg、(当該事業所外への移動)259,843kg
届出排出量:50,765kg、届出外推計排出量:1,023,766kg、合計:1,074,531kg
(平成20年度)
届出:(大気)384kg、(公共用水域)38,826kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)40,998kg、(当該事業所外への移動)195,236kg
届出排出量:39,210kg、届出外推計排出量:823,508kg、合計:862,718kg
(平成21年度)
届出:(大気)371kg、(公共用水域)28,523kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)28,290kg、(当該事業所外への移動)177,581kg
届出排出量:28,894kg、届出外推計排出量:994,514kg、合計:1,023,408kg
6.環境中における検出状況(設定時)
(平成17~21年度)
<淡水域>
・検出範囲:0.001~5.5µg/L
・生物A目標値(0.6µg/L)超過:2,861地点中65地点(2.3%)、10%値(0.06µg/L)超過:2,861地点中520地点(18.2%)
・生物特A目標値(1µg/L)超過:2,861地点中28地点(0.98%)、10%値(0.1µg/L)超過:2,861地点中358地点(12.5%)
・生物B、生物特B目標値(2µg/L)超過:2,861地点中3地点(0.1%)、10%値(0.2µg/L)超過:2,861地点中200地点(7.0%)
<海域>
・検出範囲:0.03~0.48µg/L
・生物A目標値(0.7µg/L)超過:277地点中0地点(0%)、10%値(0.07µg/L)超過:277地点中16地点(5.8%)
・生物特A目標値(1µg/L)超過:277地点中0地点(0%)、10%値(0.1µg/L)超過:277地点中112地点(4.3%)
7.基準値の根拠の概要
(1)基準値の設定手順(専門委員会報告より)
○淡水域
【生物A】
目標値:1µg/L
目標値導出の概要:ニジマス(代表種、全長約5cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)95.1µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
基準値:0.6µg/L
基準値導出の概要:ニジマス(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)6µg/Lに基づいて、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物B】
基準値:2µg/L
基準値導出の概要:(「生物特B」の無影響導出値を「生物B」の水質目標値として採用。)
【生物特B】
基準値:2µg/L
基準値導出の概要:メダカ(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)22µg/Lに基づいて、他種の慢性影響に対する毒性試験結果が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
○海域
【生物A】
基準値:1µg/L
基準値導出の概要:マダイ(代表種、全長約2.5cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)118µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
基準値:0.7µg/L
基準値導出の概要:マダイ(代表種、全長約6.3mm仔魚)の2日間半数致死濃度(LC50)71µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから種比「10」で除して水質目標値とした。
(2)環境基準項目等の設定根拠(答申抜粋)
3 検討結果(抄)
(中略)
(2)環境基準項目等の検討
公共用水域におけるノニルフェノールの検出については、公共用水域要調査項目調査結果等多くの調査結果がある。公共用水域の海域における調査地点は、平成17年度から平成21年度の近年5年間でのべ277地点あり、目標値を超過する地点はなかったが、淡水域における調査地点は平成17年度から平成21年度の近年5年間でのべ2,861地点(以下「全地点」という。)あり、目標値と淡水域における検出状況を比較すると、生物Aの目標値を超過する地点が全地点中のべ28地点、生物特Aの目標値を超過する地点が全地点中のべ65地点、生物B及び生物特Bの目標値を超過する地点が全地点中3地点であった。
このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとする。
(中略)
5.今後の課題
(1)科学的知見の追加に伴う見直し
環境基準項目及び要監視項目並びに基準値及び指針値については、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続して行っていくべきである。そのためには、まず、水生生物と化学物質に関する科学的知見を今後とも集積していく必要がある。その際、検討の対象とする物質の水環境中での動態や当該物質の前駆物質等に関する知見も含め知見の集積を行うことが必要である。
また、内分泌かく乱作用を介した水生生物への影響については、現在、試験法の開発が進められているところであり、評価の手法に関しては確立されていない状況にある。このため、今回のノニルフェノールに係る水質目標値の設定については内分泌かく乱作用についての評価は行っていない。ただし、今後、科学的知見の集積が進み、内分泌かく乱作用についての評価が可能となった時点において、水質目標値の見直しの必要性を検討していくことが必要である。
(2)適切な環境管理施策の検討
環境基準の設定の結果、現況の公共用水域において環境基準の維持・達成を図るための措置が必要な場合には、水質汚濁防止法に基づく排水基準の設定等、汚染要因や対象項目の特性に応じた様々な環境基準の維持・達成に必要な環境管理施策を適切に講じていくことが必要である。
なお、ノニルフェノールについては、環境中でノニルフェノールエトキシレートの生物分解により生成するものもあることから、今後の環境管理施策の検討に当たってはこれを十分考慮した上で行う必要がある。
8.参考資料
・平成24年3月7日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-2303.pdf 【NIES保管ファイル】
○直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
1.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表12に掲げる方法
2.設定経緯
平成24年12月27日・中央環境審議会答申
平成25年3月27日・環境省告示30号
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・融点:198.5℃※1、>300℃※2、144℃※3
・沸点:444℃(分解)※1
・密度:1.0(20℃、60%スラリー)※2
・蒸気圧:2.3×10-15mmHg(25℃)※2(MPBPWINにより計算)
・解離定数(pKa):現時点では得られていない
・オクタノール/水分配係数(logKow):0.45※2、1.96※2、3.32※4
・水溶解度:2.0×105mg/L(25℃)※2、2.5×105mg/L(20℃)※4
・ヘンリー定数:6.38×10-3Pa-m3/mol(25℃)※4(HENRYWINにより計算)
・生物分解性(好気的):良分解性 BOD 73%、HPLC 98%(試験期間:4週間、被験物質濃度:100mg/L、活性汚泥濃度:30mg/L)※3
・生物分解性(嫌気的):分解され難い※5
・化学分解性(加水分解性):加水分解を受けやすい化学結合はないので、水環境中では加水分解されない※5
・光分解性:水面では紫外線によって光分解される※2
・生物濃縮性(BCFss):鎖長平均10.8(L/kg)、11.7(L/kg)、11.4(L/kg)、10.6(L/kg)(試験生物:ファットヘッドミノー)※6
※1:CASRN:85117-50-6 C10-14 Sodium alkyl benzene sulfonate
※2:CASRN:25155-30-0 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
※3:CASRN:2211-98-5 p-ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
※4:CASRN:68411-30-3 Benzene sulfonic acid, C10-13 Alkyl derivs., Sodium salts(混合物)
※5:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)
※6:商用LAS(C10-13)
(2)環境中での動態
平成19年度から平成23年度に調べられた我が国の淡水域からは、各年度の最大値として、70~19,000μg/LのLASが検出され、検出下限値0.01~100μg/Lの範囲の中での検出率は、各年度ともに30%を超える。環境中からは、アルキル基の炭素数が10から13のLAS同族体が検出されている。
好気的条件下では、LASのアルキル基末端のメチル基が酸化(ω-酸化)されてカルボキシル基を生じ、スルホフェニルカルボン酸(Sulphophenyl Carboxylic Acid(SPC))となり、さらにアルキル基の酸化短縮(β-酸化)が炭素数4~5まで続いた後にベンゼン環の開裂を経て、最終的には二酸化炭素、水及び硫酸イオンに分解される。分解過程で生成した有機物の一部は、低級脂肪酸などに変換され、微生物に同化される。
C10、C11及びC12成分を含有する市販のLASの河川水中での生分解特性としては、8日後にはC10-LASの5-スルホフェニル異性体(炭素数10のアルキル基の末端から5番目の位置の炭素でベンゼン環に結合した構造のLAS)及びC11-LASの5-及び6-スルホフェニル異性体のみが残存し、末端メチル基がスルホフェニル基から最も離れて存在する異性体が最も分解しやすい。生分解はアルキル基の炭素数が多い長鎖同族体(C13、C14)、アルキル基がより外側の炭素でベンゼン環へ結合している外部位置異性体ほど分解されやすい。
LASの河川・湖沼水中の懸濁物質(吸着媒体)への吸着は、有機炭素含有率が高い吸着媒体ほど吸着量が多いという実験結果が得られている。河川水中のLASは、10~45%が懸濁物質に吸着して存在し、炭素数別ではC10からC12の大部分が溶存態、C13の40~60%が懸濁態として存在している。底質中では全LAS量の99%以上が吸着態として存していた。底質中におけるLASの分解速度は、水中よりも2桁以上遅いと報告されている。
(3)生産量等
<化審法に基づく製造輸入数量>
・生産量a):85,749t(平成15年度)、87,026t(平成16年度)、62,088t(平成17年度)
・輸出量a):2,245t(平成15年度)、3,266t(平成16年度)、386t(平成17年度)
・輸入量a):3,272t(平成15年度)、3,573t(平成16年度)、5,472t(平成17年度)
a)LAS塩純分換算トン
<化学物質の製造・輸入量に関する実態調査>
直鎖アルキル(C=6~14)ベンゼンスルホン酸及びその塩(K、Na、Li、Ca)として、平成13年度、平成16年度及び平成19年度における製造(出荷)及び輸入量は10,000~100,000t/年未満である。
(4)主な用途
本物質の主な用途は、約8割が家庭の洗濯用洗剤、2割弱がクリーニング、厨房や車両の洗浄などに使用される業務用洗浄剤であり、わずかではあるが繊維を染色加工する際の分散剤や農薬などの乳化剤に使用されている。家庭の台所用洗剤にはほとんど使われなくなっている。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
米国、英国、カナダ、ドイツ、オランダではLASに対する水生生物保全に関する水質目標値は設定されていない。
5.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成18年度)
届出:(大気)1,478kg、(公共用水域)41,459kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)11,602kg、(当該事業所外への移動)272,378kg
届出排出量:42,937kg、届出外推計排出量:11,561,463kg、合計:11,604,400kg
(平成19年度)
届出:(大気)1,336kg、(公共用水域)34,019kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)15,877kg、(当該事業所外への移動)352,039kg
届出排出量:35,355kg、届出外推計排出量:13,087,756kg、合計:13,123,111kg
(平成20年度)
届出:(大気)889kg、(公共用水域)21,429kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)19,496kg、(当該事業所外への移動)326,648kg
届出排出量:22,318kg、届出外推計排出量:17,182,022kg、合計:17,204,340kg
(平成21年度)
届出:(大気)1,030kg、(公共用水域)17,282kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)21,803kg、(当該事業所外への移動)361,839kg
届出排出量:18,312kg、届出外推計排出量:15,643,438kg、合計:15,661,750kg
(平成22年度)
届出:(大気)694kg、(公共用水域)18,722kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)34,597kg、(当該事業所外への移動)250,830kg
届出排出量:19,415kg、届出外推計排出量:15,048,229kg、合計:15,067,644kg
6.環境中における検出状況(設定時)
(平成19~23年度)
<淡水域>
・検出範囲:0.05~19,000µg/L
・生物A目標値(30µg/L)超過:891地点中41地点(4.6%)、10%値(3µg/L)超過:573地点中195地点(34%)
・生物特A目標値(20µg/L)超過:891地点中63地点(7.1%)、10%値(2µg/L)超過:573地点中230地点(40.1%)
・生物B目標値(50µg/L)超過:891地点中30地点(3.4%)、10%値(5µg/L)超過:573地点中156地点(27.2%)
・生物特B目標値(40µg/L)超過:891地点中35地点(3.9%)、10%値(4µg/L)超過:573地点中180地点(31.4%)
<海域>
・検出範囲:0.19~1.9µg/L
・生物A目標値(10µg/L)超過:22地点中0地点(0%)、10%値(1µg/L)超過:22地点中1地点(4.5%)
・生物特A目標値(6µg/L)超過:22地点中0地点(0%)、10%値(0.6µg/L)超過:22地点中1地点(4.5%)
7.基準値の根拠の概要
(1)基準値の設定手順(専門委員会報告より)
○淡水域
【生物A】
目標値:30µg/L
目標値導出の概要:ニジマス(代表種、全長約5cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)3,000μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:20µg/L
目標値導出の概要:ニジマス(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)150μg/Lに基づいて、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物B】
目標値:50µg/L
目標値導出の概要:メダカ(代表種、全長約2cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)4,600μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特B】
目標値:40µg/L
目標値導出の概要:メダカ(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)389μg/Lに基づいて、他種の慢性影響に対する毒性試験結果が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
○海域
【生物A】
目標値:10µg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約5cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)1,300μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:6µg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約7mm仔魚)の2日間半数致死濃度(LC50)550μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
(2)環境基準項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域における直鎖アルキルベンゼンスルホン酸の検出については、公共用水域要調査項目調査結果等多くの調査結果がある。公共用水域の海域における調査地点は、平成19年度から平成23年度の近年5年間でのべ22地点あり、目標値を超過する地点はなかったが、淡水域における調査地点は平成19年度から平成23年度の近年5年間でのべ891地点(以下「全地点」という。)あり、目標値と淡水域における検出状況を比較すると、生物Aの目標値を超過する地点が全地点中のべ41地点、生物特Aの目標値を超過する地点が全地点中のべ63地点、生物Bの目標値を超過する地点が全地点中30地点、生物特Bの目標値を超過する地点が全地点中35地点であった。
このため、全国的な環境管理施策を講じて、公共用水域における濃度の低減を図ることが必要であり、環境基準項目として設定することとする。
8.参考資料
・平成24年12月27日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2411.pdf 【NIES保管ファイル】
④要監視項目及び指針値(一覧)(令和3年10月7日現在)
○総括表
| 項目 | 指針値 | 通知日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロロホルム | 0.006~3 mg/L以下 | 平成15年11月5日 | |
| フェノール | 0.01~2 mg/L以下 | 平成15年11月5日 | |
| ホルムアルデヒド | 0.03~1 mg/L以下 | 平成15年11月5日 | |
| 4-t-オクチルフェノール | 0.0004~0.004 mg/L以下 | 平成25年3月27日 | |
| アニリン | 0.02~0.1 mg/L以下 | 平成25年3月27日 | |
| 2,4-ジクロロフェノール | 0.003~0.03 mg/L以下 | 平成25年3月27日 |
○河川
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 指針値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 4-t-オクチルフェノール | アニリン | 2,4-ジクロロフェノール | ||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.7mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.006mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 3mg/L以下 | 0.08mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.004mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.003mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
(備考)基準値は、年平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
○湖沼
河川と同じ
○海域
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 指針値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 4-t-オクチルフェノール | アニリン | 2,4-ジクロロフェノール | ||
| 生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.8mg/L以下 | 2mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.0009mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.8mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.0004mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
⑤項目ごとの指針値及び設定根拠
○クロロホルム
1.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2及び5.3.1に定める方法
2.設定経緯
平成15年9月12日・中央環境審議会答申
平成15年11月5日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発031105001・環水管発031105001)
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・無色透明の重い揮発性液体。
・特異な臭気を有し、味はかすかに甘い。
・融点:-63.5℃
・沸点:61.2℃
・比重:1.484(20/20℃)
・蒸気圧:21.3kPa(0.3mmHg)(20℃)、32.7kPa(245mmHg)(30℃)
・解離定数:解離基なし
・水溶解度:8,000mg/L(20℃)
・n-オクタノール/水分配係数:1.97
・土壌吸着性:Koc=45
・蓄積性:1.47~4.7、4.1~13
・BOD分解率:0%
・生物分解性:難分解
・加水分解性:加水分解を受けやすい化学結合なし
・嫌気的分解性:嫌気性条件下で分解するとの報告
・非生物的分解性:OHラジカルとの反応性:対流大気圏での半減期は80~160日
(2)生産量等
(平成12年)
・国内生産量:37,000t(推定)、輸出量は68,650kg、輸入量は60,772,523kg
(3)主な用途
・フッ素系冷媒、フッ素系樹脂の製造、溶剤(ゴム、グッタペルカ、鉱油、ロウ、アルカロイド、酢酸、メチルセルロース、ニトロセルロース)、有機合成、アニリンの検出、血液防腐用、医薬反応溶媒、農薬反応溶媒、試薬。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・要監視項目 0.06mg/L以下
・水道水質基準 0.06mg/L以下
・水産用水基準 0.01mg/L(淡水域)、0.06mg/L(海域)
・カナダにおける水生生物ガイドライン 1.8μg/L(淡水域)
・英国の法令で定められた環境基準 12μg/L(淡水年平均値)、12μg/L(海域年平均値)
5.環境中における検出状況(設定時)
<淡水域>
・要監視項目汚染状況解析調査(平成6~12年度):104(検出地点)/4,299(測定地点)、検出範囲0.1~60μg/L、目標値(水域区分A:700μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):17(検出地点)/516(測定地点)、検出範囲2~83μg/L、目標値(水域区分A:700μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過1地点(0.2%)
・要監視項目汚染状況解析調査(平成6~12年度):104(検出地点)/4,299(測定地点)、検出範囲0.1~60μg/L、目標値(水域区分A-S:6μg/L)超過37地点(0.9%)、10%値超過46地点(1.1%)
・独自調査結果(平成4~13年度):17(検出地点)/516(測定地点)、検出範囲2~83μg/L、目標値(水域区分A-S:6μg/L)超過17地点(3.3%)、10%値超過17地点(3.3%)
・要監視項目汚染状況解析調査(平成6~12年度):104(検出地点)/4,299(測定地点)、検出範囲0.1~60μg/L、目標値(水域区分B、B-S:3000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):17(検出地点)/516(測定地点)、検出範囲2~83μg/L、目標値(水域区分B、B-S:3000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
<海域>
・要監視項目汚染状況解析調査(平成6~12年度):38(検出地点)/915(測定地点)、検出範囲0.2~38μg/L、目標値(水域区分G、S:800μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):1(検出地点)/79(測定地点)、検出範囲25~25μg/L、目標値(水域区分G、S:800μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
6.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(専門委員会報告より)
1)イワナ・サケマス域(水域区分Aおよび水域区分A-S)
【水域区分A】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値は、Oncorhynchus mykiss(ニジマス)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値66,800μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した668μg/Lを本水域区分の最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではCerio daphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値が3,400μg/L(9日NOEC繁殖)であり、この値を最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分Aにおいては、魚介類であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した700μg/Lを目標値案とする。
【水域区分A-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類では、信頼できる慢性毒性値がOncorhynchus mykiss(ニジマス)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、本水域区分の魚介類の最終慢性毒性値は、Oncorhynchus mykiss(ニジマス)で得られている慢性毒性値59μg/L(胚からふ化後4日までNOEC死亡)に種比を「10」を用いて算出した5.9μg/Lとする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は3,400μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分A-Sにおいては、魚介類であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した6μg/Lを目標値案とする。
2)コイ・フナ域(水域区分Bおよび水域区分B-S)
【水域区分B】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域においては、我が国に生息する魚介類の信頼できる毒性値は得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではCerio daphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値が3,400μg/L(9日NOEC繁殖)であり、この値を最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分Bにおいては、餌生物であるCerio daphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した3,000μg/Lを目標値案とする。
【水域区分B-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域においては、我が国に生息する魚介類の幼稚仔の信頼できる毒性値は得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Bの餌生物の最終慢性毒性値はであり、この値を水域区分B-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分B-Sにおいては、餌生物であるCerio daphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した3,000μg/Lを目標値案とする。
3)海域
【水域区分G】
○最終慢性毒性値(魚介類)
海域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値は、Penaeus merguiensis(クルマエビ類)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値81,500μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した815μg/Lを本水域区分の最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物では、Skeletonema属(珪藻類)の慢性毒性値(2データ)を幾何平均して得られる216,000μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Gにおいては、魚介類であるPenaeus merguiensis(クルマエビ類)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した800μg/Lを目標値案とする。
【水域区分S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
我が国の海域に生息する魚介類の信頼できる毒性値は、幼稚仔では得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Gの餌生物の最終慢性毒性値は216,000μg/Lであり、この値を水域区分Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
本水域区分Sの水質目標値は、餌生物で得られた216,000μg/Lが対象となるものの、この値はクルマエビ類から得られた水域区分Gでの目標値(800μg/L)に比べて大きい。したがって、水域区分Sの目標値は一般海域での目標値案とする。
(2)要監視項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域におけるクロロホルムの検出については、要監視項目汚染状況解析調査結果等多くの調査結果がある。目標値と公共用水域等における検出状況を比較すると、クロロホルムは公共用水域等において一般水域の目標値より低いレベルで検出されているが、イワナ・サケマス特別域の目標値については、これを超過する地点がある。
クロロホルムについては、既に人の健康の保護の観点から設定された要監視項目に位置づけられていることから、水生生物の保全の観点からも当面監視を継続することとし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられる。
7.参考資料
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その1) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月12日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/t094-h1504.pdf 【NIES保管ファイル】
○フェノール
1.測定方法
平成15年11月5日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発031105001・環水管発031105001)の付表1に掲げる方法
2.設定経緯
平成15年9月12日付け中央環境審議会答申
平成15年11月5日付け環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発031105001・環水管発031105001)
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・白色結晶塊状で、完全に純粋でないものは淡紅色。
・大気中から水分を吸収して液化。
・灼くような味があり、特異臭。
・アルコール、水、エーテル、クロロホルム、グリセリン、アルカリに可溶。
・融点:40.85℃
・沸点:182℃
・比重:1.071
・蒸気圧:27Pa(0.2mmHg、20℃)
・解離定数:pKa=9.89(20℃)
・水溶解度:6,700mg/L(16℃)
・n-オクタノール/水分配係数:1.46
・土壌吸着性:Koc=39 or 91
・蓄積性:2.656(計算値)
・BOD分解率:85%
・生物分解性:良分解
・加水分解性:加水分解を受けやすい化学結合なし
・嫌気的分解性:嫌気的条件下における分解性は遅いと報告あり
・非生物的分解性:
a. OHラジカルとの反応性:大気中半減期は15時間と報告あり
b. NO3ラジカルとの反応性:大気中半減期は15分と報告あり
(2)生産量等
(平成12年)
・国内生産量:915,668tで、輸出量は131,925,753kg、輸入量は977,149kg(輸出入とも石炭酸およびその塩)。
(3)主な用途
・主用用途:消毒剤、歯科用(局部麻酔剤)、ピクリン酸、サリチル酸、フェナセチン、染料中間物の製造、合成樹脂(ベークライト)および可塑剤、2,4-PA原料、合成香料、ビスフェノールA、アニリン、2,6-キシレノール(PPO樹脂原料)、農薬、安定剤、界面活性剤。フェノールを原料とした物質としては、p-フェノールスルホン酸、2-フェノキシエタノール等が存在。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・水道水質基準 0.005mg/L以下(フェノール類として)
・排水基準 5mg/L(フェノール類含有量として)
・U.S. EPA GoldBook 淡水急性毒性10,200μg/L、淡水慢性毒性2,560μg/L、海水急性毒性5,800μg/L
・カナダにおける飲料水ガイドライン 2μg/L
・カナダにおける水生生物ガイドライン 4μg/L(淡水域)
・英国環境庁が運用上使用する環境基準 淡水・海水で30μg/L(年平均値)、300μg/L(最大値)
5.環境中における検出状況(設定時)
<淡水域>
・常時監視(フェノール類)(平成3~12年度):1,117(検出地点)/9,959(測定地点)、検出範囲2~2000μg/L、目標値(水域区分A:50μg/L)超過29地点(0.3%)、10%値超過938地点(9.4%)
・化学物質と環境(平成8、10年度):18(検出地点)/23(測定地点)、検出範囲0.03~1.47μg/L、目標値(水域区分A:50μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成12年度):12(検出地点)/65(測定地点)、検出範囲0.03~0.21μg/L、目標値(水域区分A:50μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):94(検出地点)/921(測定地点)、検出範囲0.03~60μg/L、目標値(水域区分A:50μg/L)超過1地点(0.1%)、10%値超過55地点(6.0%)
・独自調査結果(フェノール類)(平成4~13年度):13(検出地点)/55(測定地点)、検出範囲5~6μg/L、目標値(水域区分A:50μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過2地点(3.6%)
・常時監視(フェノール類)(平成3~12年度):1,117(検出地点)/9,959(測定地点)、検出範囲2~2000μg/L、目標値(水域区分A-S、B-S:10μg/L)超過286地点(2.9%)、10%値超過1,117地点(11.2%)
・化学物質と環境(平成8、10年度):18(検出地点)/23(測定地点)、検出範囲0.03~1.47μg/L、目標値(水域区分A-S、B-S:10μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成12年度):12(検出地点)/65(測定地点)、検出範囲0.03~0.21μg/L、目標値(水域区分A-S、B-S:10μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):94(検出地点)/921(測定地点)、検出範囲0.03~60μg/L、目標値(水域区分A-S、B-S:10μg/L)超過17地点(1.8%)、10%値超過59地点(6.4%)
・独自調査結果(フェノール類)(平成4~13年度):13(検出地点)/55(測定地点)、検出範囲5~6μg/L、目標値(水域区分A-S、B-S:10μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過13地点(23.6%)
・常時監視(フェノール類)(平成3~12年度):1,117(検出地点)/9,959(測定地点)、検出範囲2~2000μg/L、目標値(水域区分B:80μg/L)超過11地点(0.1%)、10%値超過513地点(5.2%)
・化学物質と環境(平成8、10年度):18(検出地点)/23(測定地点)、検出範囲0.03~1.47μg/L、目標値(水域区分B:80μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成12年度):12(検出地点)/65(測定地点)、検出範囲0.03~0.21μg/L、目標値(水域区分B:80μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):94(検出地点)/921(測定地点)、検出範囲0.03~60μg/L、目標値(水域区分B:80μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過28地点(2.9%)
・独自調査結果(フェノール類)(平成4~13年度):13(検出地点)/55(測定地点)、検出範囲5~6μg/L、目標値(水域区分B:80μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過2地点(3.6%)
<海域>
・常時監視(フェノール類)(平成3~12年度):48(検出地点)/1,934(測定地点)、検出範囲0.3~920μg/L、目標値(水域区分G:2000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過1地点(0.0%)
・化学物質と環境(平成8、10年度):21(検出地点)/33(測定地点)、検出範囲0.03~1.21μg/L、目標値(水域区分G:2000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成12年度):2(検出地点)/11(測定地点)、検出範囲0.04~0.04μg/L、目標値(水域区分G:2000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):14(検出地点)/22(測定地点)、検出範囲0.04~0.17μg/L、目標値(水域区分G:2000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・常時監視(フェノール類)(平成3~12年度):48(検出地点)/1,934(測定地点)、検出範囲0.3~920μg/L、目標値(水域区分S:200μg/L)超過1地点(0.0%)、10%値超過7地点(0.4%)
・化学物質と環境(平成8、10年度):21(検出地点)/33(測定地点)、検出範囲0.03~1.21μg/L、目標値(水域区分S:200μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成12年度):2(検出地点)/11(測定地点)、検出範囲0.04~0.04μg/L、目標値(水域区分S:200μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):14(検出地点)/22(測定地点)、検出範囲0.04~0.17μg/L、目標値(水域区分S:200μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
6.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(専門委員会報告より)
1)イワナ・サケマス域(水域区分Aおよび水域区分A-S)
【水域区分A】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値は、ニジマス1種で得られており、そのうち最小値であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の急性毒性値5,000μg/L(48時間LC50死亡)に種比「10」及び急性慢性毒性値「10」を用いて算出した50μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値から得られる1,240μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分Aにおいては、魚介類のOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した50μg/Lを目標値案とする。
【水域区分A-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類で得られている信頼できる慢性毒性値はニジマス1種で得られており、そのうち最小であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)で得られている慢性毒性値(90日間NOEC死亡)118μg/Lに種比「10」を用いて算出した11.8μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は1,240μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分A-Sにおいては魚介類のOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した10μg/Lを目標値案とする。
2)コイ・フナ域(水域区分Bおよび水域区分B-S)
【水域区分B】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値はコイ、メダカの2種で得られており、そのうち、最小値は、Cyprinus carpio(コイ)の急性毒性値8,000μg/L(48時間TLm死亡)であり、コイは本水域区分での代表種であることから、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した80μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値から得られる1,240μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Bにおいては魚介類のCyprinus carpio(コイ)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した80μg/Lを目標値案とする。
【水域区分B-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類では、信頼できる慢性毒性値はコイとメダカの2種で得られており、最小値はCyprinus carpio(コイ)の慢性毒性値110μg/L(60日間MATC複合影響(生残と成長影響))である。コイは代表種であることから、種比「10」を用いて算出した11μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Bの餌生物の最終慢性毒性値は1,240μg/Lであり、この値を水域区分B-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分B-Sにおいては魚介類のCyprinus carpio(コイ)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した10μg/Lを目標値案とする。
3)海域
【水域区分G】
○最終慢性毒性値(魚介類)
海域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値は、Pagrus major(マダイ)の急性毒性値15,200μg/L(96時間LC50死亡)を用いるが、マダイの他にタラ類、ウニ類で信頼できる急性毒性値が得られていることから、種比を考慮せず、急性慢性毒性比「10」を用いて算出した1,520μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではBalanus属(蔓脚類)の慢性毒性値(2データ)を幾何平均して得られる3,162μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Gにおいては魚介類のPagrus major(マダイ)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した2,000μg/Lを目標値案とする。
【水域区分S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値は、Pagrus major(マダイ)の急性毒性値2,000μg/L(48時間LC50死亡)を採用することとする。
最終急性毒性値は、マダイの他にタラ類、ウニ類で信頼できる急性毒性値が得られていることから、種比を考慮せずにマダイの値(2,000μg/L)とする。
したがって、本水域区分の魚介類の最終慢性毒性値はマダイで得られている急性毒性値(2,000μg/L)に急性慢性毒性比「10」を用いて算出した200μg/Lとする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Gの餌生物の最終慢性毒性値(FCV)は3,162μg/Lμg/Lであり、この値を水域区分Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Sにおいては魚介類のPagrus major(マダイ)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した200μg/Lを目標値案とする。
(2)要監視項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域におけるフェノールの検出については、公共用水域常時監視結果等多くの調査結果があるものの、公共用水域常時監視においては、水質汚濁防止法に基づく排水基準項目であるフェノール類について測定しており、フェノール単体を対象として設定した目標値との比較を行うことが困難である。
また、フェノール単体については、地方公共団体独自で行った調査があり、その調査結果には、コイ・フナ域の目標値以上の値を検出してはいないものの、イワナ・サケマス域の目標値やイワナ・サケマス特別域及びコイ・フナ特別域の目標値以上の値を検出した地点がある。今後、地点周辺の水域の特性等を考慮して調査を行う必要があり、また、フェノール単体での全国的な調査は実施されていないことから、早急に全国的な調査を実施することとし、その結果をもって更なる全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられる。
このため、要監視項目として設定するものとする。
7.参考資料
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その2) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月12日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/t094-h1504.pdf 【NIES保管ファイル】
○ホルムアルデヒド
1.測定方法
平成15年11月5日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発031105001・環水管発031105001)の付表2に掲げる方法
2.設定経緯
平成15年9月12日・中央環境審議会答申
平成15年11月5日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発031105001・環水管発031105001)
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・ホルマリンは40%前後~50%のホルムアルデヒド水溶液を指す。
・水溶液中では水和したメチレングリコール及びその重合体の形で存在。不溶性となって析出しやすいので、普通0~13%のメタノールを加え、CH2(OH)OCH3の形で安定化。
・水溶液は無色透明で、窒息性の刺激臭。
・中性または弱酸性の反応を呈す。
・融点:-92℃
・沸点:19.5℃
・比重:0.815
・蒸気圧:1.33kPa(-88℃)、3.89E+3mmHg(25℃)
・解離定数:解離基なし
・水溶解度:400,000mg/L
・n-オクタノール/水分配係数:0.35(実測値)
・蓄積性:3.162(計算値)
・BOD分解率:91%
・生物分解性:良分解
・加水分解性:報告なし
・非生物的分解性:
a. OHラジカルとの反応性:半減期は19時間(汚染された大気)、半減期は清浄な大気の半分(汚染された大気)
b. 直接光分解による反応:半減期は6時間
(2)生産量等
(平成12年)
・国内生産量:1,234,264t、輸出量741,062kg、輸入量1,363kg(輸出入量ともホルムアルデヒド)。
(3)主な用途
・石炭酸系・尿素系・メラミン系合成樹脂原料、ポリアセタール樹脂原料、界面活性剤、ヘキサメチレンテトラミン、ペンタエリスリトール原料、農薬、消毒剤、その他一般防腐剤、有機合成原料、ビニロン、パラホルムアルデヒド。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・英国の法令で定められた環境基準 年平均値5μg/L、最大値(MAC)50μg/L
5.環境中における検出状況(設定時)
<淡水域>
・化学物質と環境(平成7年度):0(検出地点)/6(測定地点)、検出範囲ND~NDμg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:1000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成11年度):64(検出地点)/130(測定地点)、検出範囲1~12μg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:1000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):1(検出地点)/18(測定地点)、検出範囲6~6μg/L、目標値(水域区分A、A-S、B、B-S:1000μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
<海域>
・化学物質と環境(平成7年度):0(検出地点)/5(測定地点)、検出範囲ND~NDμg/L、目標値(水域区分G:300μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成11、12年度):47(検出地点)/237(測定地点)、検出範囲1~5μg/L、目標値(水域区分G:300μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・独自調査結果(平成4~13年度):0(検出地点)/4(測定地点)、検出範囲ND~NDμg/L、目標値(水域区分G:300μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・化学物質と環境(平成7年度):0(検出地点)/5(測定地点)、検出範囲ND~NDμg/L、目標値(水域区分S:30μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
・要調査項目(平成11、12年度):47(検出地点)/237(測定地点)、検出範囲1~5μg/L、目標値(水域区分S:30μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過2地点(0.8%)
・独自調査結果(平成4~13年度):0(検出地点)/4(測定地点)、検出範囲ND~NDμg/L、目標値(水域区分S:30μg/L)超過0地点(0.0%)、10%値超過0地点(0.0%)
6.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(専門委員会報告より)
1)イワナ・サケマス域(水域区分Aおよび水域区分A-S)
【水域区分A】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域においては、我が国に生息する魚介類の信頼できる毒性値は、成体では得られていない。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物の慢性毒性値が得られていないことから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(餌生物)を算出する。Daphnia属(ミジンコ類)における急性毒性値(2データ)を幾何平均して得られる12,969μg/Lに、急性慢性毒性比「10」を用いて算出した1,297μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
水域区分Aにおいては餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の急性毒性値から得られる最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した1,000μg/Lを目標値案とする。
【水域区分A-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類で信頼できる急性毒性値がイワナ類及びニジマスで得られているが、ニジマスについては成長段階が不明であることから、目標値案の導出には用いないものとする。したがって、Salvelinus fontinalis(イワナ類)の急性毒性値157,000μg/L(48時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した1,570μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は1,297μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分A-Sにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した1,000μg/Lを目標値案とする。
2)コイ・フナ域(水域区分Bおよび水域区分B-S)
【水域区分B】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値はAnguilla rostrata(ウナギ類)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値329,650μg/L(48時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した3,297μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の急性毒性値(2データ)を幾何平均して得られる12,969μg/Lに、急性慢性毒性比「10」を用いて算出した1,297μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Bにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の急性毒性から得られる1,297μg/Lを有効数字1桁で四捨五入した1,000μg/Lを目標値案とする。
【水域区分B-S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値は、Corbicula manilensis(シジミ類)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値95,000μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した9,500μgμg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Bの餌生物の最終慢性毒性値は1,297μg/Lであり、この値を水域区分B-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
○目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分B-Sにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した1,000μg/Lを目標値案とする。
3)海域
【水域区分G】
○最終慢性毒性値(魚介類)
海域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値は、Pagrus major(マダイ)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値33,600μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した336μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
海域の餌生物の信頼できる毒性値は得られていない。
○目標値案
水域区分Gにおいては、魚介類であるPagrus major(マダイ)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した300μg/Lを目標値案とする。
【水域区分S】
○最終慢性毒性値(魚介類)
海域の魚介類の幼稚仔の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。
急性毒性値は、Pagrus major(マダイ)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、急性毒性値2,600μg/L(48時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した26μg/Lを最終慢性毒性値(魚介類)とする。
○最終慢性毒性値(餌生物)
海域の餌生物の信頼できる毒性値は得られていない。
○目標値案
水域区分Sにおいては、魚介類であるPagrus major(マダイ)の急性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
(2)要監視項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域におけるホルムアルデヒドの検出については、要調査項目存在状況調査結果等複数の調査結果がある。目標値と公共用水域等における検出状況を比較すると、目標値の超過はみられなかったが、海域において、目標値の10%値の超過がみられた。
このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとする。
7.参考資料
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku_2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その2) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月11日・中央環境審議会水環境部会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/houkoku.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年9月12日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t094-h1504/t094-h1504.pdf 【NIES保管ファイル】
○4-t-オクチルフェノール
1.測定方法
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)の付表1に掲げる方法
2.設定経緯
平成24年12月27日・中央環境審議会答申
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)
3.基礎情報(設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・融点:85℃、84~85℃、80℃
・沸点:279℃、277℃
・密度:0.95(20℃)
・蒸気圧:4.78×10-4mmHg(25℃)、<0.075mmHg(20℃)
・解離定数(pKa):10.33(25℃)(計算値)
・オクタノール/水分配係数(logKow):5.3(計算値)
・水溶解度:<100mg/L(20℃)
・ヘンリー定数:<1.3×10-6Pa-m3/mol(水溶解度<100mg/L、蒸気圧4.78×10-4mmHgによる計算結果)
・生物分解性(好気的):BOD 0%、GC(-)%(試験期間:2週間、被験物質濃度:100mg/L、活性汚泥濃度:30mg/L)
・化学分解性(加水分解性):加水分解しない
・生物濃縮性(BCF):113~469(試験生物:コイ、試験期間:8週間、試験濃度:100μg/L)、12~135(試験生物:コイ、試験期間:8週間、試験濃度:10μg/L)
・土壌吸着性(Koc):10,000(計算値)
(2)環境中での動態
平成19(2007)年度から平成23(2011)年度に調べられた我が国の淡水域からは、最大で0.96μg/Lの4-t-オクチルフェノールが検出され、検出下限値0.00001~0.5μg/Lの範囲の中での検出率は、各年度ともに30%を超える。
環境中で検出される4-t-オクチルフェノールは、4-t-オクチルフェノールエトキシレートとして排出されたものが分解過程を経て副生成したものが多いと推定される。また、水環境中では馴化した微生物により徐々に生分解されると考えられる。なお、水面に存在するオクチルフェノールの30%は1日で光分解され、日当たりのよい浅瀬(水深20~25cm)の半減期は13.9時間とされている。
(3)生産量等
<化審法に基づく製造・輸入数量>
・製造・輸入数量:27,192t(平成19年度)、17,970t(平成20年度)、20,876t(平成21年度)
<化学物質の製造・輸入量に関する実態調査>
モノアルキル(C=3~9)フェノールの平成16年度における製造(出荷)及び輸入量は10,000~100,000t/年未満、平成19年度は100,000~1,000,000t/年未満である。
<化学工業統計、貿易統計>
・生産量a):15,000t(平成21年)、15,000t(平成22年)、-c)(平成23年)
・輸入量b):3,909t(平成21年)、4,117t(平成22年)、6,431t(平成23年)
・輸出量b):9,030t(平成21年)、10,492t(平成22年)、2,960t(平成23年)
a) 推定値
b) オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩
c) 公表されていない
(4)主な用途
・4-オクチルフェノールの主な用途は、接着剤、印刷インクやワニスに用いられる油溶性フェノール樹脂の原料並びに工業用の界面活性剤として用いられるポリ(オキシエチレン)オクチルフェニルエーテルの原料である。
4.毒性情報及び各種基準値(設定時)
・英国環境庁 UK Standard Surface Water AA-EQS
(Inland surface waters)0.1µg/L(Octylphenolとして)
(Other surface waters)0.01µg/L(Octylphenolとして)
・ドイツ連邦環境庁 Water Framework Directive Annual average EQS
(Watercourses and lakes)0.1µg/L
(Transitional and coastal waters)0.01µg/L
5.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(p-オクチルフェノール)
(平成18年度)
届出:(大気)295.1kg、(公共用水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)130.2kg、(当該事業所外への移動)199,091kg、
届出排出量:295.1kg、届出外推計排出量:0kg、合計:295.1kg
(平成19年度)
届出:(大気)358.1kg、(公共用水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)96.1kg、(当該事業所外への移動)172,125kg、
届出排出量:358.1kg、届出外推計排出量:0kg、合計:358.1kg
(平成20年度)
届出:(大気)170.6kg、(公共用水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0.2kg、(当該事業所外への移動)37,868kg、
届出排出量:170.6kg、届出外推計排出量:0kg、合計:170.6kg
(平成21年度)
届出:(大気)174.0kg、(公共用水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0.1kg、(当該事業所外への移動)35,263kg、
届出排出量:174.0kg、届出外推計排出量:0kg、合計:174.0kg
(平成22年度)
届出:(大気)308.6kg、(公共用水域)0kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)0.1kg、(当該事業所外への移動)48,201kg、
届出排出量:308.6kg、届出外推計排出量:0kg、合計:308.6kg
(オクチルフェノールエトキシレート)
(平成18年度)
届出:(大気)900.3kg、(公共用水域)2,245kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)7,032kg、(当該事業所外への移動)91,574kg、
届出排出量:3,146kg、届出外推計排出量:197,060kg、合計:200,206kg
(平成19年度)
届出:(大気)65.9kg、(公共用水域)1,328kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)6,818kg、(当該事業所外への移動)82,103kg、
届出排出量:1,393kg、届出外推計排出量:229,854kg、合計:231,247kg
(平成20年度)
届出:(大気)49.3kg、(公共用水域)1,370kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)4,047kg、(当該事業所外への移動)83,311kg、
届出排出量:1,420kg、届出外推計排出量:235,476kg、合計:236,896kg
(平成21年度)
届出:(大気)12.4kg、(公共用水域)944kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)5,661kg、(当該事業所外への移動)85,850kg、
届出排出量:957kg、届出外推計排出量:411,296kg、合計:412,253kg
(平成22年度)
届出:(大気)22.3kg、(公共用水域)1,120kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)13,731kg、(当該事業所外への移動)62,982kg、
届出排出量:1,142kg、届出外推計排出量:201,554kg、合計:202,696kg
6.環境中における検出状況(設定時)
(平成19~23年度)
<淡水域>
・検出範囲:0.003~0.96µg/L
・生物A目標値(1µg/L)超過:1,932地点中0地点(0%)、10%値(0.1µg/L)超過:1,929地点中1地点(0.1%)
・生物特A目標値(0.7µg/L)超過:1,932地点中41地点(2.1%)、10%値(0.07µg/L)超過:1,929地点中52地点(2.7%)
・生物B目標値(4µg/L)超過:1,932地点中0地点(0%)、10%値(0.4µg/L)超過:1,929地点中3地点(0.2%)
・生物特B目標値(3µg/L)超過:1,932地点中0地点(0%)、10%値(0.3µg/L)超過:1,929地点中5地点(0.3%)
<海域>
・検出範囲:0.006~0.1µg/L
・生物A目標値(0.9µg/L)超過:253地点中0地点(0%)、10%値(0.09µg/L)超過:253地点中1地点(0.4%)
・生物特A目標値(0.4µg/L)超過:253地点中0地点(0%)、10%値(0.04µg/L)超過:253地点中3地点(1.2%)
7.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(専門委員会報告より)
○淡水域
【生物A】
目標値:1μg/L
目標値導出の概要:ニジマス(代表種、全長約4cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)131μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:0.7μg/L
目標値導出の概要:ニジマス(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)7.2μg/Lに基づいて、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物B】
目標値:4μg/L
目標値導出の概要:メダカ(代表種、全長約2cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)363μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特B】
目標値:3μg/L
目標値導出の概要:メダカ(代表種、胚から稚魚期)の初期生活段階試験により得られた成長への影響を及ぼさない無影響濃度(NOEC)33.4μg/Lに基づいて、他種の慢性影響に対する毒性試験結果が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
○海域
【生物A】
目標値:0.9μg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約2cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)85.2μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:0.4μg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約8mm仔魚)の2日間半数致死濃度(LC50)44.4μg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから種比「10」で除して水質目標値とした。
(2)要監視項目等の設定根拠(答申抜粋)
公共用水域における4-t-オクチルフェノールの検出については、公共用水域要調査項目調査結果等多くの調査結果がある。目標値と公共用水域における平成19年度から平成23年度の検出状況を比較すると、4-t-オクチルフェノールは公共用水域において一般域の目標値より低いレベルで検出されているが、淡水域の生物特Aの目標値については、これを超過する地点が1地点ある。また、淡水域及び海域において目標値の10%値の超過がみられた。
このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとする。
8.参考資料
・平成24年12月27日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2411.pdf 【NIES保管ファイル】
○アニリン
1.測定方法
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)の付表2に掲げる方法
2.設定経緯
平成24年12月27日・中央環境審議会答申
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)
※水質目標値としては以下の答申において提示
平成15年9月12日・中央環境審議会答申
3.基礎情報(要監視項目設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・融点:-6℃、-5.98℃
・沸点:184.1℃、184~186℃、184.4℃
・密度:1.0217(20℃)
・蒸気圧:0.68mmHg(25℃)(=90 Pa)、0.49mmHg(25℃)
・解離定数(pKa):4.87(25℃)、4.60(25℃)
・オクタノール/水分配係数(logKow):0.90、0.84
・水溶解度:3.6×104mg/L(25℃)
・ヘンリー定数:2.3×10-6atm-m3/mol(水溶解度3.6×104mg/L、蒸気圧0.68mmHgによる計算結果)
・生物分解性(好気的):良分解性、BOD(NH3)85%、TOC 99%、HPLC 100%
・生物分解性(嫌気的):生分解しない
・化学分解性(加水分解性):水環境中では加水分解されない
・生物濃縮性(BCF):3.2(計算値)
・土壌吸着性(Koc):70(計算値)
(2)環境中での動態
平成14年度から平成20年度に調べられた我が国の淡水域からは、最大で、180μg/Lのアニリンが検出され、検出下限値0.02~0.06μg/Lの範囲の中での検出率は、13~46%の範囲である。
ヘンリー定数を基にした水中から大気中へのアニリンの揮散について、モデル河川(水深1m、流速1m/秒、風速3m/秒)での半減期は12日、また、モデル湖水(水深1m、流速0.05m/秒、風速0.5m/秒)での半減期は131日と見積もられている。
アニリンの非解離状態での土壌吸着係数Kocの値は45であるが、解離定数pKaが4.60であることから、酸性に傾いた環境水中では部分的にプロトン付加体の状態で存在するので、懸濁物質及び底質汚泥に吸着されやすいと推定される。
水環境中に排出されたアニリンは、主に生分解により水中から除去されると推定される。なお、日射量が多い場合には、表層水中での光分解による除去の可能性もある。
(3)生産量等
<化審法に基づく製造輸入数量>
本物質の化審法に基づき公表された平成21年度における製造・輸入数量は294,943tであり、平成22年度は321,138tである。
<化学物質の製造・輸入量に関する実態調査>
本物質の平成13年度、平成16年度及び平成19年度における製造(出荷)及び輸入量はそれぞれ100,000~1,000,000t/年未満である。
<化学工業統計、貿易統計>
・生産量:293,332t(平成21年度)、362,445t(平成22年度)、334,986t(平成23年度)
・輸入量(t):220t(平成21年度)、1,392t(平成22年度)、1,570t(平成23年度)
(4)主な用途
・アニリンは、他の化学物質の原料として用いられ、主に硬質ウレタンフォームや接着剤・塗料などの原料であるジフェニルメタンジイソシアネート(MDI)の原料として使用されている。この他、染料、医薬品、農薬やゴム製品をつくる化学物質の原料に使われているほか、化審法の分解度試験において微生物による分解性を判断する標準物質とされている。
4.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
・カナダ Environment Canada Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life
(Freshwater)2.2μg/L※1
・ドイツ連邦環境庁 Water Framework Directive Annual average EQS
(Water courses and lakes)0.8μg/L
(Transitional and coastal waters)0.08μg/L
※1:オオミジンコ(Daphnia magna)を用いた繁殖に対する14日間LOEC 21.8μg/Lに安全係数0.1を考慮して算出。
5.環境への排出等の状況(PRTR)(要監視項目設定時)
(平成18年度)
届出:(大気)3,130kg、(公共用水域)28,437kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)2,277kg、(当該事業所外への移動)871,824kg、
届出排出量:31,567kg、届出外推計排出量:2kg、合計:31,569kg
(平成19年度)
届出:(大気)3,064kg、(公共用水域)27,017kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)1,747kg、(当該事業所外への移動)827,564kg、
届出排出量:30,081kg、届出外推計排出量:2,284kg、合計:32,365kg
(平成20年度)
届出:(大気)2,912kg、(公共用水域)10,128kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)1,728kg、(当該事業所外への移動)581,462kg、
届出排出量:13,040kg、届出外推計排出量:1,750kg、合計:14,790kg
(平成21年度)
届出:(大気)2,698kg、(公共用水域)10,014kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)975kg、(当該事業所外への移動)456,972kg、
届出排出量:12,712kg、届出外推計排出量:1,731kg、合計:14,443kg
(平成22年度)
届出:(大気)3,124kg、(公共用水域)7,590kg、(土壌)0kg、(埋立)0kg、(下水道への移動)1,047kg、(当該事業所外への移動)554,798kg、
届出排出量:10,715kg、届出外推計排出量:1,035kg、合計:11,750kg
6.環境中における検出状況(要監視項目設定時)
(平成14、17~20年度)
<淡水域>
・検出範囲:0.02~180μg/L
・検出下限:0.02~0.06μg/L
・生物A、生物特A、生物B、生物特B目標値(20μg/L)超過:280地点中1地点(0.4%)、10%値(2μg/L)超過:280地点中2地点(0.7%)
注1 検出下限値未満のデータは、不検出として取り扱っている。
注2 検出下限値が水質目標値又は10%値よりも大きいデータはなかった。
<海域>
・検出範囲:0.02~0.39μg/L
・検出下限:0.02~0.06μg/L
・生物A、生物特A目標値(100μg/L)超過:76地点中0地点(0%)、10%値(10μg/L)超過:76地点中0地点(0%)
注1 検出下限値未満のデータは、不検出として取り扱っている。
注2 検出下限値が水質目標値又は10%値よりも大きいデータはなかった。
7.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(要監視項目設定時)(専門委員会報告より)
○淡水域
【生物A】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性値を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。最小値であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の急性毒性値33,500μg/L(96時間LC50死亡)に、に種比「10」及び急性慢性毒性比「23」を用いて算出した146μg/Lを本水域区分の最終慢性毒性値(魚介類)とする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値(3データ)を幾何平均して得られる17μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分Aにおいては餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値を幾何平均して得られる最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
【生物特A】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。最小値であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の急性毒性値20,400μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「23」を用いて算出した89μg/Lを本水域区分の最終慢性毒性値(魚介類)とする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は17μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分A-Sにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値を幾何平均して得られる最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
【生物B】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値はメダカ、コイ類、フナの3種で得られており、そのうち、最小値は、Oryzias latipes(メダカ)の27,200μg/L(96時間LC50死亡)であるが、コイ・フナ域の代表種であるコイ類の急性毒性値126,500μg/L(48時間LC50死亡)の1/5倍で1/10に達しないことから、代表種であるコイ類の急性毒性値(126,500μg/L)に種比「10」及び急性慢性毒性比「23」を用いて算出した550μg/Lとする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物では、Daphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値(3データ)を幾何平均して得られる17μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分Bにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値を幾何平均して得られる最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
【生物特B】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値は、メダカ、フナで得られており、最小値はOryzias latipes(メダカ)の108,000μg/L(96時間LC50死亡)である。メダカのアニリンに対する感受性は成体の毒性値では、コイ・フナ域の代表種であるコイ類の1/5程度で1/10倍には達しないことから、種比「10」及び急性慢性毒性比「23」を用いて算出した数値(47μg/L)とする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Bの餌生物の最終慢性毒性値は17μg/Lであり、この値を水域区分B-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分B-Sにおいては、餌生物であるDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値を幾何平均して得られた最終慢性毒性値(餌生物)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
○海域
【生物A】
目標値:100μg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約3cmの稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)12,700µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:100μg/L
目標値導出の概要:海域「生物A」の無影響導出値を「生物特A」の水質目標値として採用。
(2)要監視項目等の設定根拠
(平成15年・目標値設定時)(答申抜粋)
公共用水域におけるアニリンの検出については、要調査項目存在状況調査結果等複数の調査結果がある。目標値と公共用水域等における検出状況を比較すると、アニリンは淡水域では目標値及び目標値の10%値の超過はみられなかった。
このため、全国的な環境管理施策及び監視は現時点では必要はなく、各種調査において検出された場合に環境の状況を判断する際のクライテリアの一つとして公表することが妥当である。
なお、海域での目標値が導出されていないことから、海生生物を用いた毒性試験を早急に実施し、毒性評価を行う必要がある。
(平成25年・要監視項目設定時)(答申抜粋)
公共用水域におけるアニリンの検出については、公共用水域要調査項目調査結果がある。目標値と平成15年答申以降の公共用水域における検出状況を比較すると、アニリンは海域においては目標値を超過する地点はなかった。また、淡水域においては、平成17年度に目標値を超過する地点が1地点みられるが、同地点で平成18、19、20年度においても調査が行われており、同地点で継続的な超過は見られない。また、淡水域において平成19年度に目標値の10%値の超過が見られたが当該地点は目標値を超過した地点と同じ地点である。
このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとする。
8.参考資料
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その1) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成24年12月27日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2411.pdf 【NIES保管ファイル】
○2,4-ジクロロフェノール
1.測定方法
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)の付表3に掲げる方法
2.設定経緯
平成24年12月27日・中央環境審議会答申
平成25年3月27日・環境省水・大気環境局長通知(環水大水発第1303272号)
※水質目標値としては以下の答申において提示
平成15年9月12日・中央環境審議会答申
3.基礎情報(要監視項目設定時)
(1)物性・物理化学的性状
・融点:43℃、45℃、42~43℃
・沸点:210℃、209~210℃、209~210℃
・密度:1.38(60℃)
・蒸気圧:0.067mmHg(25℃)
・解離定数(pKa):7.89
・オクタノール/水分配係数(logKow):3.23、3.06
・水溶解度:5.5×103mg/1000g(25℃)、4.5×103mg/L(20℃)
・ヘンリー定数:3.2×10-6atm-m3/mol(水溶解度4.5×103mg/L、蒸気圧0.067mmHgによる計算結果)
・生物分解性(好気的):BOD 0%、TOC 2%、HPLC 9%(試験期間:4週間、被験物質濃度:100 mg/L、活性汚泥濃度:30mg/L)
・生物分解性(嫌気的):馴化した微生物では分解し、4-クロロフェノールが主に生成する。
・化学分解性(加水分解性):加水分解しないと予想される
・生物濃縮性(BCF):7.1~69(試験生物:コイ、試験期間:8週間、試験濃度:30μg/L)、10~55(試験生物:コイ、試験期間:8週間、試験濃度:3μg/L)
・土壌吸着性(Koc):490(計算値)
(2)環境中での動態
平成14年度から平成23年度に調べられた我が国の淡水域からは、最大で、0.88μg/Lの2,4-ジクロロフェノールが検出され、検出下限値0.001~1μg/Lの範囲の中での検出率は0~7%の範囲である。
大気に放出された場合には、光化学反応により生じる水酸基(OH)ラジカルと反応し、半減期5日程度で分解する。2,4-ジクロロフェノールは酸性物質(pKa、7.8)であり、その化学形態(解離したイオンと中性分子の割合)は、環境媒体のpHによって異なる。
本物質の環境中への発生源の可能性として、除草剤の2,4-D(2,4-Dichloro phenoxy acetic acid;2,4-ジクロロフェノキシ酢酸)、その塩類及びそのエステル類の分解やフェノール含有水の塩素化が挙げられている。
底質への吸着の割合もpHに依存する。多くの生物分解の試験により、嫌気的にも好気的にも微生物により分解することが知られている。
水中では、光反応により生じる酸化剤(一重項酸素、水酸基ラジカル)との反応のほか、直接的に光分解される。
(3)生産量等
<化学物質排出把握管理促進法(化管法)>
本物質の製造・輸入量区分は1t以上100t未満である。
<ファインケミカルマーケットデータ>
平成10年における生産量、輸入品は、それぞれ200t、20~30tとされており、平成9年においても生産量、輸入品ともに同数量とされている。
(4)主な用途
・一般分析(試薬)、除草剤の合成中間体、農薬(殺虫剤、除草剤)・染料原料とされている。
4.毒性情報及び各種基準値(要監視項目設定時)
・英国環境庁 UK Standard Surface Water AA-EQS
(Inland surface waters)20μg/L※1
(Other surface waters)20μg/L※1
・カナダ Environment Canada Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life
(Freshwater)0.2(Dichloro phenols)※2
・ドイツ連邦環境庁 Water Framework Directive Annual average EQS
(Water courses and lakes)10μg/L
(Transitional and coastal waters)1μg/L
・オランダ国立健康環境研究所
MPC 15μg/L(Dichlorophenols)、Target value 0.2μg/L(Dichlorophenols)
※1:20μg/L導出の根拠は記載されていないが、同国のWater R&D Technical Reportでは、ニジマス(Onchrhynchus mykiss)胚から稚魚までの死亡に対する85日間LOEC 0.18mg/Lに安全係数10を除して20μg/Lを算出している。
※2:オオクチバス(Micropterus salmoides)を用いて異臭障害を調べた結果(0.4μg/L)を2で除した値。
5.環境中における検出状況(要監視項目設定時)
(平成14~21年度)
<淡水域>
・検出範囲:0.01~0.88µg/L
・生物A目標値(30µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)、10%値(3µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)
・生物特A目標値(3µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)、10%値(0.3µg/L)超過:1,785地点中2地点(0.1%)
・生物B目標値(30µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)、10%値(3µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)
・生物特B目標値(20µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)、10%値(2µg/L)超過:1,785地点中0地点(0%)
<海域>
・検出範囲:(未検出)
・生物A目標値(20µg/L)超過:181地点中0地点(0%)、10%値(2µg/L)超過:181地点中0地点(0%)
・生物特A目標値(10µg/L)超過:181地点中0地点(0%)、10%値(1µg/L)超過:181地点中0地点(0%)
6.指針値の根拠の概要
(1)指針値の設定手順(要監視項目設定時)(専門委員会報告より)
○淡水域
【生物A】
目標値:30μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類の慢性毒性値は得られていないが、信頼できる急性毒性値が得られていることから、急性毒性値及び急性慢性毒性比を用いて最終慢性毒性値(魚介類)を算出する。急性毒性値は、Oncorhynchus mykiss(ニジマス)を用いた1種類の毒性試験で得られている。急性毒性値2,600μg/L(96時間LC50死亡)に、種比「10」及び急性慢性毒性比「10」を用いて算出した26μg/Lを本水域区分の最終慢性毒性値(魚介類)とする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値(7データ)を幾何平均して得られる837μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分Aにおいては、魚介類であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した30μg/Lを目標値案とする。
【生物特A】
目標値:3μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
イワナ・サケマス域の魚介類では、信頼できる慢性毒性値がはOncorhynchus mykiss(ニジマス)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、本水域区分の魚介類の最終慢性毒性値は、Oncorhynchus mykiss(ニジマス)で得られている慢性毒性値26μg/L(胚からふ化後4日までNOEC死亡)に種比「10」を用いて算出した2.6μg/Lとする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
水域区分Aの餌生物の最終慢性毒性値は837μg/Lであり、この値を水域区分A-Sの最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)の値を比較し、水域区分A-Sにおいては、魚介類であるOncorhynchus mykiss(ニジマス)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した3μg/Lを目標値案とする。
【生物B】
目標値:30μg/L
目標値導出の概要:メダカ(代表種、被鱗体長約1.6cm)の4日間半数致死濃度(LC50)3,400µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特B】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:
・最終慢性毒性値(魚介類)
コイ・フナ域の魚介類では、信頼できる慢性毒性値がCarassius auratus(フナ)を用いた1種類の毒性試験で得られている。したがって、本水域区分の魚介類の最終慢性毒性値はCarassius auratus(フナ)で得られている慢性毒性値170μg/L(胚からふ化後4日までNOEC死亡)に種比「10」を用いて算出した17μg/Lとする。
・最終慢性毒性値(餌生物)
餌生物ではDaphnia属(ミジンコ類)の慢性毒性値(7データ)を幾何平均して得られる837μg/Lを最終慢性毒性値(餌生物)とする。
・目標値案
最終慢性毒性値(魚介類)と最終慢性毒性値(餌生物)を比較し、水域区分B-Sにおいては、魚介類であるCarassius auratus(フナ)の慢性毒性値から得られた最終慢性毒性値(魚介類)を有効数字1桁で四捨五入した20μg/Lを目標値案とする。
○海域
【生物A】
目標値:20μg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約3cm稚魚)の4日間半数致死濃度(LC50)1,890µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
【生物特A】
目標値:10μg/L
目標値導出の概要:マダイ(代表種、全長約9mm仔魚)の2日間半数致死濃度(LC50)1,400µg/Lに基づいて、推定係数「10」、および、他種の毒性値が得られていないことから、種比「10」で除して水質目標値とした。
(2)要監視項目等の設定根拠
(平成15年・目標値設定時)(答申抜粋)
公共用水域における2,4-ジクロロフェノールの検出については、要調査項目存在状況調査結果等多くの調査結果がある。目標値と公共用水域等における検出状況を比較すると、目標値及び目標値の10%値の超過はみられなかった。
このため、全国的な環境管理施策及び監視は現時点では必要はなく、各種調査において検出された場合に環境の状況を判断する際のクライテリアの一つとして公表することが妥当である。
(平成25年・要監視項目設定時)(答申抜粋)
公共用水域における2,4-ジクロロフェノールの検出については、公共用水域要調査項目調査結果等多くの調査結果がある。目標値と平成15年答申以降の公共用水域における検出状況を比較すると、2,4-ジクロロフェノールは目標値の超過はみられなかったが、生物特Aの目標値の10%値の超過が2地点みられた。
このため、当面監視を行うこととし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられることから、要監視項目として設定することとする。
7.参考資料
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(別紙1)各物質の目標値導出根拠(その2) http://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_05-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考16)各物質の物理化学的性状等 https://www.env.go.jp/info/iken/h150610a/a-5-16.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考17)検討対象物質に係る検出状況 https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年6月・中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会「水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について(第一次報告)」(参考18)公共用水域における亜鉛の検出状況等について https://www.env.go.jp/council/09water/y094-06/mat_18.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成24年12月27日・中央環境審議会「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2411.pdf 【NIES保管ファイル】
(5)地下水の水質汚濁に係る環境基準及び要監視項目
①設定の考え方
(平成9年3月6日・中央環境審議会「地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定について(答申)」より)(抜粋)
2.設定の基本的考え方
環境基準には、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準と生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準がある(環境基本法第16条第1項)が、地下水の水質の汚濁に関しては、汚染の現状等を踏まえ、人の健康を保護する観点からまず環境基準の設定を行うべきである。
地下水質環境基準の設定内容としては、人体への有害性や我が国における使用状況、地下水における検出状況等を総合的に考慮して、人の健康を保護する上で対応が必要な物質を対象に、地下水の水質保全を図る観点から各種対策を講じる際の目標となるべき一律の数値を物質ごとに設定することが適当である。
なお、地下水はこれまで基本的には清浄であるべきものとして認識されていることから、清浄な状態のまま保全されることが望ましく、地下水質環境基準の設定が基準値まで汚染を許容することではないという考え方に留意すべきである。
3.対象項目及び基準値
地下水質環境基準の対象項目等については、地下水と公共用水域が一つの水循環系を構成しており既に設定されている公共用水域の水質の汚濁に係る環境基準(以下、「公共用水域水質環境基準」という。)の考え方と整合性が保たれるべきであるとの基本的考え方のもと、要監視項目など地下水の特性等から留意すべき物質等についても検討した結果、現段階においては以下のように考えることが適当である。
(1)対象項目
地下水質環境基準の対象項目としては、公共用水域水質環境基準の健康項目として既に設定されており、地下水質の評価基準項目としてこれまで地下水質の常時監視が行われている、カドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の23項目(注:答申当時)とすることが適当である。
これら項目については、公共用水域水質環境基準の健康項目として、科学的知見の現状や内外の検討の動向を踏まえ、水道水質に関する基準項目を中心に類似又は関連する化合物で対応を要すると考えられる項目を含め我が国における当該物質の生産・使用状況や公共用水域等における検出状況等を勘案しつつ平成5年に追加・見直しが行われたものである。
なお、要監視項目など地下水の特性等から留意すべきその他の物質等については、現在さまざまな観点から知見の集積等が図られつつあることから、引き続き検討を進めることが必要である。
(2)基準値
地下水質環境基準の対象項目ごとの基準値は、公共用水域水質環境基準の健康項目において既に設定されている基準値と同じ一律の値とすることが適当である。
これら基準値については、我が国、米国及び国際機関において検討され集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況等をもとに、飲料水経由の影響等から検討された結果定められているものである。また、これら基準値は主として長期的摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、長期間にわたる平均的なレベルを基準値以下に維持する必要があると考えることが適当である。
なお、これら23項目については、最新の知見に基づき再度情報の整理を行った結果、基準値等に関し、特段、変更等を行うに十分な情報は得られておらず、現段階で変更の必要性は認められない。
4.適用の在り方
人の健康を保護する観点からは、いかなる地下水においても環境基準項目に関して基準値を超える状態が存在することは望ましいものではない。また、地下水と公共用水域は一体として一つの水循環系を構成していることから、全公共用水域に適用している公共用水域水質環境基準の健康項目の考え方と整合性が保たれるべきである。したがって、その用途等を問わず、現在利用されていないものも含め、すべての地下水について地下水質環境基準を適用することが適当である。
また、すべての地下水に適用することは、人の健康保護に関する環境基準について健康への影響という観点から広く見た場合、飲料水経由の影響に加え、地下水の養魚用水としての利用に伴う魚介類経由の食物摂取による影響等も考慮すべき要素であること、さらには人の健康保護に関する環境基準の設定が実質的に広く有害物質による環境汚染の防止に資することも念頭におくことが望ましいと考えられることからも適当であると判断できる。
この考え方に基づき、砒素等の地質等に起因するもっぱら自然的原因による汚染(以下、「自然汚染」という。)についても地下水質環境基準を適用することが適当である。これは人の健康に影響があるものとして汚染が存在することを明らかにすること等を通じて、人間生活の安全性を環境面から確保する意味からも意義を有するものであると考えることができる。ただし、自然汚染については、その評価及び対策の在り方の検討に際して配慮することが必要である。
5.達成期間の考え方
本報告で検討している地下水質環境基準は人の健康保護に係るものであることから、達成期間の考え方は「直ちに達成され維持されるように努める」とすることが適当である。これは、公共用水域水質環境基準の健康項目と同じ考え方であり整合性が保たれるものである。この場合、汚染された地下水の浄化等の対策については、現在の技術水準において相当の期間を要することが想定されるが、このことを地下水質環境基準の達成期間の考え方に反映することは適当ではないと考えるべきである。
しかしながら、自然汚染については汚染が地質等に起因するものであり、利水時の浄化対策は考えられるものの地下水そのものへの対策は一般に困難であること等から、具体的な達成期間は設けないことが適当である。
なお、汚染された地下水の浄化等の対策の実施にあたっては、当該地下水の現在の用途及び将来想定されうる用途等を考慮することが肝要である。
6.測定及び評価の考え方
地下水質の測定は、地下水の流れの状況や利用の状況、地下水質環境基準の対象物質の使用の状況等を勘案して、既に平成元年度から運用されている現行の地下水質調査方法に定める区分(地域の全体的な地下水質の状況の把握を目的とした「概況調査」、概況調査等により新たに発見された汚染についてその範囲の確認を目的とした「汚染井戸周辺地区調査」、汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な監視等を目的とした「定期モニタリング調査」の3区分)に従い、当該状況を的確に把握できる適切な地点において行うことが適当である。この場合、一定の代表的な地点において長期的な観点から水質の経年的変化を把握することにも配慮することが望ましい。なお、測定は既存の井戸において行うことを基本とするが、必要に応じ新たな観測井を設置することも考慮する必要がある。
測定の頻度については、地下水が表流水と異なり一般に流動が緩やかであること等を勘案し、調査区分ごとに地域の状況に応じて測定頻度を設定することが適当である。なお、季節的な変動も考慮することが望ましい場合があることに留意すべきである。
地下水質環境基準を達成しているか否かの判断については、基準値が長期的摂取に伴う健康影響を考慮して決められている項目は基本的に年間平均値で行うことが適当である。ただし、急性毒性が懸念されるシアンについては最高値で判断することが適当である。基準値が「検出されないこと」とされているものについては年間を通してすべての測定値が不検出であることをもって基準達成と判断することが適当である。
また、毎年の測定結果における地下水質環境基準の達成状況については、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測定結果について基準値を超過した検体の割合(超過率)で評価することが適当である。なお、全体的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とすることが適当であり、その他の調査区分については、それぞれの目的を勘案して評価を行う必要がある。この場合、地下水質の測定では測定点が一定しないこと等に留意し、汚染の傾向の評価に当たっては長期的な観点から行うことが必要である。
地下水質の測定及び評価については、当面、上記の考え方に基づいて行うことが適当であるが、より適切な地下水質の監視の在り方を確立するために、今後、地下水の水質、流動、地質等の地下水に係る科学的知見の充実に努めるべきである。また、その上で、地下水質に係る全般的な評価を行うために、環境基準の達成状況を把握するための地域を代表する地下水質の測定点(以下、「地下水質環境基準点」という。)を定めて水質の監視を行うことについても、できる限り早期に検討することが望ましい。
なお、地下水質環境基準の対象項目に係る測定方法については、既に公共用水域水質環境基準に係る測定方法が設定されており、これと同じものとすることが適当である。
7.見直しの考え方
地下水質環境基準は、以下の点などを考慮し、適宜見直しを行うことが必要であると考えるべきである。なお、その際には、汚染物質の拡散が期待しにくい等の地下水の特性を十分踏まえるとともに、水循環の視点から公共用水域水質環境基準との関連、整合性に留意する必要がある。
(1)科学的な判断の向上に伴い人の健康保護の観点から必要と考えられる基準値の変更
(2)科学的な判断の向上に伴い人の健康保護の観点から必要と考えられる項目の追加、削除
(3)水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴い人の健康保護の観点から必要と考えられる項目の追加、削除
(参考資料)
・平成9年3月6日・中央環境審議会「地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
(解説文献)
・森岡泰裕(1997)地下水の水質保全に関する制度および技術の最近の動向、資源環境対策、33、pp.881-886
・環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室(2019)地下水保全と持続可能な地下水利用のために、生活と環境、64(2)、pp.11-15
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
| 項目 | 基準値 | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 平成23年10月27日 | 改定 |
| 全シアン | 検出されないこと (検出限界0.1mg/L) | 平成9年3月13日 | |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 | 令和3年10月7日 | 改定(令和4年4月1日施行) |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 総水銀※ | 0.0005mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| アルキル水銀※ | 検出されないこと (検出限界0.0005mg/L) | 平成9年3月13日 | |
| PCB | 検出されないこと (検出限界0.0005mg/L) | 平成9年3月13日 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| クロロエチレン※(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 当初要監視項目。当初「塩化ビニルモノマー」から平成28年3月29日に名称変更。 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 改定 |
| 1,2-ジクロロエチレン※ | 0.04mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 当初シス体のみから変更 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成26年11月17日 | 改定 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| チウラム | 0.006mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 平成9年3月13日 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |
| ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更 |
| ほう素 | 1mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 当初要監視項目から変更・改定 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 平成21年11月30日 | 当初要監視項目から変更 |
| ダイオキシン類※※ | 1 pg-TEQ/L以下 | 平成11年12月27日 |
※ クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)及び1.2-ジクロロエチレンのうちトランス体については、公共用水域については要監視項目とされている。
※※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定。
(備考)
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2.「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
(評価方法)
(常時監視等の処理基準抜粋)
第2 水質汚濁防止法関係
1.常時監視(法第15条関係)(抄)
(中略)
(3)測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場合
1)人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準
①水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の達成状況は、同一測定点(公共用水域にあっては、当該測定点は表層における地点とする。)における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、測定値が定量下限値未満であった検体については、定量下限値を用いて平均値を算出することとする。
②ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判断する。
③さらに総水銀については、告示別表1備考1及び地下水告示別表備考1において、総水銀に係る基準値については、年間平均値として達成、維持することとされているが、年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に定量下限値未満が含まれていない場合には、総検体の測定値がすべて0.0005mg/Lであることをいい、定量下限値未満が含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であることをいうものとする。
④地下水の環境基準達成状況の評価は、地下水質調査方法に示す調査区分ごとに、毎年の測定結果について、検出の有無とともに、基準値の超過状況(基準値を超過した測定地点の割合または本数)で行うこと。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。なお、地域の全体的な汚染の状況は概況調査における評価を基本とし、その他の調査区分における評価については、それぞれ調査目的を勘案して行うこと。
⑤自然的原因による検出値の評価
ア.公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合は、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮すること。
イ.ふっ素及びほう素は自然状態で海水中に高濃度で存在していることから、汽水域等において環境基準を超過している水域が多く存在する。環境基準を超過している汽水域等については、海水の影響の程度を把握し、その他の水域とは別に整理することとする。汽水域等における海水の影響の程度の把握方法及び測定結果の整理の方法についての詳細は「汽水域等における「ふっ素」及び「ほう素」濃度への海水の影響程度の把握方法について」(平成11年3月12日環水企第89-2号、環水管第68-2号)によること。
(中略)
2.測定計画(法第16条関係)(抄)
(中略)
③測定頻度
ア.概況調査
(ア)年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年1回以上実施することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。
(イ)定点方式については、地下水の流動、利水状況及び汚染物質の使用状況等を考慮して、測定計画に根拠等を示した上で、測定頻度を減らすことができる。
イ.汚染井戸周辺地区調査
(ア)汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。1地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだけ短期間に行うことが望ましい。
(イ)地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが望ましい。
ウ.継続監視調査
(ア)対象井戸について、年1回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。
(イ)地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、測定計画に具体的に根拠を示した上で、複数年に1回の測定とすることができる。
(ウ)汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、複数年に1回の測定とする、または、継続監視調査を終了することができる。
(エ)汚染源における浄化対策の実施等により継続監視調査を終了する場合には、測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。
(以下略)
(参考資料)
・令和3年10月7日・環境省水・大気環境局長「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(環水大水発第2110073号・環水大土発第2110073号) https://www.env.go.jp/hourei/add/e82.pdf 【NIES保管ファイル】
(公共用水域の水質のダイオキシン類の常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
1.常時監視の調査測定方法(抄)
(中略)
地下水質の常時監視については「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について(平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通知)の別紙「地下水」質調査方法」に準じて行うこととする。
公共用水域の水質及び地下水質に係るダイオキシン類の測定は、日本工業規格K0312に定める方法によることとし、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」(平成13年5月31日環水企第92号環境省環境管理局水環境部長通知)を参考にして、水環境中のダイオキシン類監視の適切な実施を図ることとする。
2.調査測定結果の評価方法
水質環境基準の達成状況は、測定地点ごとに年間平均値により評価することとする。
(参考資料)
・平成13年5月31日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」(環水企93号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000166.html 【NIES保管ファイル】
・平成14年7月22日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準の改正について」(環水企118号) https://www.env.go.jp/hourei/05/000167.html 【NIES保管ファイル】
・平成17年6月29日・環境省環境管理局水環境部長「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について」(環水企発第050629003号・環水土発第050629003号) http://www.env.go.jp/air/tech/suisitukizyunkaisei0506h17.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成20年4月1日・環境省水・大気環境局長「「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」の一部改正について(通知)」(環水大発第080401002号・環水土発第080401001号) http://www.env.go.jp/air/dioxin/suisitu0804h20.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○カドミウム
1.基準値
(当初)0.01mg/L以下
(現行)0.003mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
(改定)
平成23年7月22日・中央環境審議会答申
平成23年10月27日・環境省告示第95号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
・当初:設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
・改定時:人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
9.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○全シアン
1.基準値
検出されないこと(定量限界0.1mg/L)
2.測定方法
日本産業規格K0102の38.1.2(日本産業規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
7.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○鉛
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の54に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○六価クロム
1.基準値
(当初)0.05mg/L以下
(現行)0.02mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の65.2(日本産業規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)
1 日本産業規格K0102の65.2.1に定める方法による場合
原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。
2 日本産業規格K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(日本産業規格K0102の65.の備考11のb)による場合に限る。)
試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
3 日本産業規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合
2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
3.設定経緯
(当初)
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
(改定)
令和3年7月19日・中央環境審議会答申
令和3年10月7日・環境省告示第63号(令和4年4月1日施行)
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
9.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○砒素
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○総水銀
1.基準値
0.0005mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
7.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○アルキル水銀
1.基準値
検出されないこと(検出限界0.0005mg/L)
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
7.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○PCB
1.基準値
検出されないこと(定量限界0.0005mg/L)
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
7.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○ジクロロメタン
1.基準値
0.02mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○四塩化炭素
1.基準値
0.002mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
1.基準値
0.002mg/L以下
2.測定方法
平成9年3月13日・環境庁告示第10号付表に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成16年2月26日・中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省環境管理局水環境部長通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
(改定:環境基準項目)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第79号
(「塩化ビニルモノマー」から名称変更)
平成28年3月29日・環境省告示第31号
4.基礎情報
(公共用水域の要監視項目(塩化ビニルモノマー)の項参照)
5.毒性情報及び各種基準値
(公共用水域の要監視項目(塩化ビニルモノマー)の項参照)
6.環境中における検出状況
(公共用水域の要監視項目(塩化ビニルモノマー)の項参照)
7.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(公共用水域の要監視項目(塩化ビニルモノマー)の項参照)
(平成21年・改定時)(答申抜粋)
ア 基本的な整理
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域における自治体の水質測定計画による調査及び環境省が実施した要監視項目等存在状況調査の結果(以下「公共用水域水質測定結果」という。)によると、現行の指針値を超過したものが、平成16年度、17年度、18年度にそれぞれ1箇所あるが、これらは、全て同一の地点における事例で、地下においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解したものが雨水管より漏洩したものであり、現地では既に漏洩防止策を講じ現在は指針値の超過は見られなくなっている。また、このほかには指針値を超える検出は、平成19年度に1箇所見られるが、同箇所で継続的な超過はみられない。現行指針値の10%を超えるものが毎年ある(1から10箇所)。
また、都道府県の地下水測定計画に基づく測定結果及び自治体独自で実施している地下水の水質調査結果(以下「地下水水質測定結果」という。)によると、指針値の超過事例が毎年あり(17から58箇所)、現行指針値の10%を超えるものは、平成16年度以降毎年数十箇所ある。これらのほとんどが、嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられるが、トリクロロエチレン等の汚染事例から推測すれば、同様の原因による塩化ビニルモノマーによる地下水汚染がさらにあるのではないかと懸念される。
このようなことから、当該物質について、公共用水域に関しては、引き続き要監視項目とし検出状況の把握につとめる必要がある。その際には、汚染された地下水の湧出による影響がないかあるいは工場事業所等からの排水等の影響がないか十分に留意すべきである。また地下水に関しては、あらたに地下水環境基準項目とすべきである。
イ 基準値等
現行の要監視項目としての指針値を改訂する新たな知見は平成16年答申後になく、現行の指針値である0.002mg/Lを公共用水域における要監視項目の指針値とするとともに、地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
(平成28年・名称変更時)(審議会配付資料抜粋)
平成21年11月、地下水環境基準の項目として「塩化ビニルモノマー」が追加され、基準値が0.002mg/L以下と定められた。
これを受けて、平成25年10月7日、環境大臣から中央環境審議会(以下「中環審」という。)会長に対し、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」諮問が行われ、中環審における審議及びパブリックコメント手続を経て、平成27年12月28日に「塩化ビニルモノマー」を土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質に追加することが適当である旨の答申がなされた。その際、パブリックコメントにおいて「塩化ビニルモノマー」の用語についての意見が提出され、特定有害物質等として用いる名称については、環境省において検討することとされた。
土壌汚染対策法の特定有害物質については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令で用いられている名称を採用することとしていることや、本物質による地下水の汚染事例は、ほとんどが嫌気性条件下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したものによると考えられることを踏まえ、特定有害物質の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」とし、平成28年3月24日付けで「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」(平成28年政令第74号)を公布した。同様に、平成28年3月29日付けの告示「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成28年3月環境省告示第30号)において、土壌環境基準の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と定めるとともに、同日付けの告示「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成28年3月環境省告示第31号)において、地下水環境基準のうち、「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更した。
8.参考資料
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別添) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/betten.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙1) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成16年2月26日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第1次答申)」(別紙2) http://www.env.go.jp/council/toshin/t090-h1510/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成28年5月25日・中央環境審議会水環境部会(第41回)資料3「地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更について」 https://www.env.go.jp/council/09water/y090-41/mat03.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,2-ジクロロエタン
1.基準値
0.004mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○1,1-ジクロロエチレン
1.基準値
(当初)0.02mg/L以下
(現行)0.1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
(改定)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第79号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
・当初:設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
・改定時:人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
9.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○1,2-ジクロロエチレン
1.基準値等
0.04mg/L以下
2.測定方法
シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
(当初:シス体のみ)
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
(改定:シス体とトランス体)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第79号
4.基礎情報
(人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)(シス-1,2-ジクロロエチレン)及び要監視項目(トランス-1,2-ジクロロエチレン)の項参照)
5.毒性情報及び各種基準値
(人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)(シス-1,2-ジクロロエチレン)及び要監視項目(トランス-1,2-ジクロロエチレン)の項参照)
6.環境への排出等の状況(PRTR)
(人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)(シス-1,2-ジクロロエチレン)及び要監視項目(トランス-1,2-ジクロロエチレン)の項参照)
7.環境中における検出状況
(人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)(シス-1,2-ジクロロエチレン)及び要監視項目(トランス-1,2-ジクロロエチレン)の項参照)
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(設定の考え方並びに人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)(シス-1,2-ジクロロエチレン)及び要監視項目(トランス-1,2-ジクロロエチレン)の項参照)
(平成21年・改定時)(答申抜粋)
ア 基本的整理
公共用水域における各異性体の平成10年度以降の自治体の測定による検出状況は、シス及びトランス両異性体とも環境基準値等を超えるものはないが、シス体は環境基準値の10%の値を超過する検出が数箇所で毎年見られている一方で、トランス体は指針値の10%の値の超過も見られていない。
PRTRによる公共用水域への排出量(平成13年度から平成19年度)が、シス体で3,414から7,461kg/年(下水道からの排出量を除く場合、113から514kg/年)、トランス体で10から40kg/年で推移しているが、現在、両異性体ともに意図された製造はほぼ行われておらず、他の化学物質を製造する際に副生成されているものが主と考えられる。
一方、シス体が検出された箇所でトランス体の測定を同時に行っている箇所は数箇所しかないが、それらの箇所でシス体及びトランス体それぞれの濃度を足し合わせてもシス体の現行基準値あるいはトランス体の現行指針値である0.04mg/Lを超えるものはない。
なお、副生成される過程でのシス体、トランス体別の生成割合は不明であるが、両者の生成過程が同じであることを考えれば、シス体が基準値の10%を超えて検出された地点では、トランス体が検出される可能性は完全には否定できない。少なくともシス体が基準値の10%を超えて検出された地点でのトランス体の監視の強化を図るべきである。
地下水においては、地下水水質測定結果によれば、シス体は過去5年間毎年超過が見られ、トランス体は過去5年間で平成16年度及び平成17年度にそれぞれ1箇所の超過が見られる。基準値等の10%を超える検出はシス体、トランス体共に毎年継続して確認されている。
地下水における1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体)はトリクロロエチレン等が嫌気性条件下にある地下水中で分解して生成した可能性があり、トランス体が存在する場合には、多くの場合シス体も存在する状況が見られる。また同一地点同サンプルのシス体及びトランス体の測定結果において、異性体個別では基準値及び指針値を超えないものの、両異性体の和が0.04mg/Lを超える箇所が過去5年間で3箇所あった。
以上のことから、公共用水域においては今後とも、シス-1,2-ジクロロエチレンについては健康保護に係る水質環境基準項目としトランス-1,2-ジクロロエチレンについては要監視項目とする必要がある。一方、地下水においては、現行のシス-1,2-ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を地下水環境基準項目とすべきである。これに伴い、トランス-1,2-ジクロロエチレンについては地下水に関する要監視項目から削除すべきである。
イ 基準値について
地下水環境基準値はWHO飲料水水質ガイドライン第3版及び平成20年の水道水質基準の改定を踏まえ、シス体及びトランス体の和で0.04mg/Lとすることが適当である。なお、公共用水域における基準項目であるシス体の基準値及び要監視項目であるトランス体の指針値は引続き0.04mg/Lとすることが適当である。具体的な導出根拠は以下のとおり。
ウ 基準値の導出根拠
Barnesら(1985)のマウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験による雄マウスの血清中酵素の増加等を根拠としたNOAEL 17mg/kg/dayから不確実係数1,000(短期実験を考慮)を適用して、TDI 0.017mg/kg/dayと算定した。水の寄与率10%、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.04mg/L以下とした。
9.参考資料
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.80-85 【NIES保管ファイル】
・平成4年3月・日本水環境学会「平成3年度環境庁委託業務水質環境基準検討調査(項目追加情報整備調査)報告書」、pp.86-91 【NIES保管ファイル】
・平成4年12月2日・中央公害対策審議会水質部会健康環境基準専門委員会(第7回)資料4「検討対象項目ごとの基本的情報及び対処方針(案)」 【NIES保管ファイル】
・平成5年1月18日・中央公害対策審議会水質部会(第51回)参考資料2「環境基準項目についての検討概要」 【NIES保管ファイル】
・平成9年3月6日・中央環境審議会「地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月15日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,1,1-トリクロロエタン
1.基準値
1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
9.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○1,1,2-トリクロロエタン
1.基準値
0.006mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○トリクロロエチレン
1.基準値
(当初)0.03mg/L以下
(現行)0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
(当初)
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
(改定)
平成26年9月11日・中央環境審議会答申
平成26年11月17日・環境省告示127号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
・当初:設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
・改定時:人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照
9.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○テトラクロロエチレン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○1,3-ジクロロプロペン
1.基準値
0.002mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○チウラム
1.基準値
0.006mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○シマジン
1.基準値
0.003mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○チオベンカルブ
1.基準値
0.02mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○ベンゼン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○セレン
1.基準値
0.01mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
3.設定経緯
平成9年3月6日・中央環境審議会答申
平成9年3月13日・環境庁告示第10号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
8.参考資料
(設定の考え方及び人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
○硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
1.基準値
10mg/L以下
2.測定方法
硝酸性窒素にあっては日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては日本産業規格K0102の43.1に定める方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第16号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(当初:要監視項目)
(平成11年・環境基準設定時)(答申抜粋)
2.基本的考え方(抄)
(中略)
2-3 環境基準の適用に当たっての考え方
(1)基本方針
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準については、健康への影響という観点から広く見た場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響、水域からの大気への循環等も考慮する必要があること、さらに、人の健康の保護に関する環境基準の設定が、実質的に水生生物等への影響を含め広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭におくことが望ましいと考えられることから、これまでどおり河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当と考えられる。
また、地下水と公共用水域は一体として一つの水循環系を構成していることから、全公共用水域に適用している水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の考え方と整合性が保たれるべきであり、地下水についても公共用水域に適用する環境基準と同じ基準を適用することが適当である。
(中略)
3.個別項目ごとの評価(抄)
(中略)
Waltonら(1951)による硝酸性窒素濃度と乳児におけるメトヘモグロビン血症発生との関連に関する調査結果をもとに、水道水質基準も勘案し、指針値を現行のとおり硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の合計で10mgN/Lとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されていることから、環境基準健康項目とする。
なお、定量的評価が定まっていないものの亜硝酸性窒素単独での毒性についても指摘されていることから、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」で環境基準健康項目とすることにより行われるモニタリングの中で亜硝酸性窒素単独での濃度も明らかにし、公共用水域等における亜硝酸性窒素単独での状況の把握に努めることが重要である。
(以下略)
8.参考資料
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○ふっ素
1.基準値
0.8mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の34.1(日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及び日本産業規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第16号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(平成11年・環境基準設定時)(答申抜粋)
2.基本的考え方(抄)
(中略)
2-3 環境基準の適用に当たっての考え方
(1)基本方針
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準については、健康への影響という観点から広く見た場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響、水域からの大気への循環等も考慮する必要があること、さらに、人の健康の保護に関する環境基準の設定が、実質的に水生生物等への影響を含め広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭におくことが望ましいと考えられることから、これまでどおり河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当と考えられる。
また、地下水と公共用水域は一体として一つの水循環系を構成していることから、全公共用水域に適用している水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の考え方と整合性が保たれるべきであり、地下水についても公共用水域に適用する環境基準と同じ基準を適用することが適当である。
(中略)
3.個別項目ごとの評価(抄)
(中略)
斑状歯発生の予防の観点から、水道水質基準も勘案し、指針値を現行のとおり0.8mg/Lとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、フッ素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されており、海域以外でも指針値を超えるレベルで検出されているところがあることから、環境基準健康項目とする。
なお、海域におけるフッ素は2-3(2)の特例に該当することから、海域には環境基準を適用しないこととする。また、海域以外においても、汽水域において明らかに海水の影響により基準値を超過した場合、その他明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。
(以下略)
8.参考資料
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○ほう素
1.基準値
(当初)0.2mg/L
(現行)1mg/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成5年1月18日・中央公害対策審議会答申
平成5年3月8日・環境庁水質保全局長通知(環水管第21号)
(改定:環境基準項目)
平成11年2月2日・中央環境審議会答申
平成11年2月22日・環境庁告示第16号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(平成11年・環境基準設定時)(答申抜粋)
2.基本的考え方(抄)
(中略)
2-3 環境基準の適用に当たっての考え方
(1)基本方針
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準については、健康への影響という観点から広く見た場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響、水域からの大気への循環等も考慮する必要があること、さらに、人の健康の保護に関する環境基準の設定が、実質的に水生生物等への影響を含め広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭におくことが望ましいと考えられることから、これまでどおり河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当と考えられる。
また、地下水と公共用水域は一体として一つの水循環系を構成していることから、全公共用水域に適用している水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の考え方と整合性が保たれるべきであり、地下水についても公共用水域に適用する環境基準と同じ基準を適用することが適当である。
(中略)
3.個別項目ごとの評価(抄)
(中略)
Price(1996)によるラットの生殖毒性試験をもとに、現行の指針値の根拠であるTDI(1日耐容摂取量)0.088mg/kg/dayを0.096mg/kg/dayに変更し、さらに、厚生省が平成6~9年に行ったマーケットバスケット調査(日常摂取する各種の食品(約90種類)を市場(マーケット)より購入し、各々の平均摂取量を試料として、食品経由の各汚染物質のヒトへの暴露量を明らかにする調査)の結果を踏まえて飲料水経由でのほう素の暴露寄与率を40%として、指針値を現行の0.2mg/Lから1.0mg/Lに変更することとする。
この指針値と公共用水域等における検出状況を比較すると、ほう素は公共用水域等において比較的広くかつ高いレベルで検出されており、海域以外でも指針値を超えるレベルで検出されているところがあることから、環境基準健康項目とする。
なお、海域におけるほう素は2-3(2)の特例に該当することから、海域には環境基準を適用しないこととする。また、海域以外においても、汽水域において明らかに海水の影響により基準値を超過した場合、その他明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に当たってこのことを十分考慮する必要がある。
(以下略)
8.参考資料
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/089902-1.html 【NIES保管ファイル】
・平成11年2月2日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」(別添1)検出率が高い7項目に関する毒性評価の詳細 http://www.env.go.jp/council/former/tousin/0899021a.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,4-ジオキサン
1.基準値
0.05mg/L以下
2.測定方法
昭和46年12月28日・環境庁告示第59号付表8に掲げる方法
3.設定経緯
(当初:要監視項目)
平成16年2月26日中央環境審議会答申
平成16年3月31日・環境省通知(環水企発040331003・環水土発040331005)
(改定:環境基準項目)
平成21年9月15日・中央環境審議会答申
平成21年11月30日・環境省告示第79号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境への排出等の状況(PRTR)
7.環境中における検出状況
8.基準値の根拠の概要
(当初:要監視項目)
(平成21年・環境基準設定時)(答申抜粋)
(1)平成16年答申において課題としてあげられた事項についての検討(抄)
(中略)
②1,4-ジオキサンについて
ア 基本的な整理
平成16年度以降の公共用水域等での状況は、公共用水域水質測定結果によると、平成18年度に2箇所現行の指針値超過事例があり、現行指針値の10%値を超えるものが平成16年度以降毎年ある(1から10個所)。地下水水質測定結果によると、平成16年度に13箇所、平成19年度に1箇所現行指針値超過事例があり、現行指針値の10%値を超えるものが平成16年度以降毎年ある(1から43箇所)。このほか、これまで現行指針値を超える汚染により水道の取水が停止された事例も複数あり、水道の取水停止につながるおそれのあった公共用水域等への流出事例もある。
PRTRデータによると公共用水域への排出量も多く、当該物質の特性を見ると水へ混合しやすく大気への揮発性は低い。また水環境中での分解性も低い。このため、一度排出された場合には大気への揮発や水環境中での分解による濃度低減は生じにくい。
このようなことから、当該物質については健康保護に係る水質環境基準項目および地下水環境基準項目とすべきである。
イ 基準値
現行の要監視項目の指針値として設定している、0.05mg/Lを、健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
(中略)
(2)WHO飲料水水質ガイドライン及び水道水質基準の改定等を踏まえた検討(抄)
①1,4-ジオキサンについて
ア 基準値について
WHO飲料水水質ガイドライン第3版第1次追補におけるガイドライン値の設定根拠は、水道水質基準の改訂の際の検討の根拠と同一の健康影響評価も基にして設定されている。具体的には、同一試験についてマルチステージモデルを使用した手法と、TDIを使用した手法と二通りの評価を行っているが、結果はほぼ等しいとしている。
また、水道水質基準の平成20年の改定の際の検討においては、従前の水道水質基準設定の評価と食品安全委員会による清涼飲料水に係る当該物質の健康影響評価の結果に若干の違いがあるが、同一試験に係る評価方法の違いに起因していることから、当該物質の基準値を変更していない。
以上のことから、従来より要監視項目の指針値として設定していた、0.05mg/Lを、健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当である。
イ 基準値の導出根拠
Yamazakiら(1994)のラットを用いた飲水投与試験での肝腫瘍発症率に線型マルチステージモデルを適用した発がんリスク10-5相当用量として、2.1μg/kg体重/日と算定。これに、体重50kg、飲用水量2L/dayとして、基準値を0.05mg/Lとした。
(以下略)
9.参考資料
・平成21年9月15日・中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第2次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/t09-h2104/t09-h2104.pdf 【NIES保管ファイル】
○ダイオキシン類
1.基準値
1pg-TEQ/L以下
2.測定方法
日本産業規格K0312に定める方法
3.設定経緯
平成11年12月10日・中央環境審議会答申
平成11年12月27日・環境庁告示第68号
4.基礎情報
5.毒性情報及び各種基準値
6.環境中における検出状況
7.基準値の根拠の概要(答申抜粋)
3.対象項目及び基準値
(略:人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)の項参照)
4.適用のあり方
ダイオキシン類の水質環境基準については、人の健康の保護という観点から見た場合、飲料水経由の影響に加え、魚介類経由の食物摂取による影響等も考慮する必要があることから、これまでの健康項目に係る水質環境基準と同様に、河川、湖沼、海域を問わず全ての公共用水域に適用することが適当である。
また、地下水については、人の健康を保護する観点から、従来の水質環境基準と同様に、現に飲用に供されている地下水のみならず、全ての地下水に適用することが適当である。
8.参考資料
・平成11年12月10日・中央環境審議会「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定、特定施設の指定及び水質排出基準の設定等について(答申)」(別添1)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質の汚濁に係る環境基準の設定について http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=1398&hou_id=1904 【NIES保管ファイル】
④要監視項目及び指針値(一覧)(令和3年10月7日現在)
| 項目 | 指針値 | 通知日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/L以下 | 平成16年3月31日 | 改定 |
| イソキサチオン | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ダイアジノン | 0.005mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| イソプロチオラン | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| プロピサミド | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| EPN | 0.006mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 | 平成11年2月22日 | 改定 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| クロルニトロフェン(CNP) | - | 平成6年3月15日 | 改定(指針値削除) |
| トルエン | 0.6mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| キシレン | 0.4mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| ニッケル | - | 平成11年2月22日 | 改定(指針値削除) |
| モリブデン | 0.07mg/L以下 | 平成5年3月8日 | |
| アンチモン | 0.02mg/L以下 | 平成16年3月31日 | 当初設定→指針値削除→再設定 |
| エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| 全マンガン | 0.2mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| ウラン | 0.002mg/L以下 | 平成16年3月31日 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下(暫定)(PFOSとPFOAの合計値) | 令和2年5月28日 |