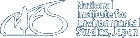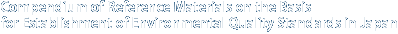Chapter 1. Air
(1) Overview
(a) Outline of Environmental Quality Standards, etc., for Air Pollution
Environmental quality standards for air pollution can be broadly divided into two categories, namely, “air pollutants” such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide emitted from combustion and other processes, and “hazardous air pollutants”* such as heavy metals and hazardous chemical substances.
The "air pollutants" are sometimes referred to as classical or traditional air pollutants. In Japan, sulfur dioxide is known as the cause of asthma in Yokkaichi, one of four major industrial pollution cases, which led to the establishment of Japan’s first environmental quality standards in 1969. Nitrogen dioxide and carbon monoxide are also typical air pollutants. Photochemical oxidants are substances generated in the atmosphere. Health damage from “photochemical smog” became a serious issue in Japan after 1970, triggering the establishment of related environmental quality standards.
With regard to particulate matter, suspended particulate matter (SPM) was the subject of standards in Japan in the initial period. In other countries, standards have been set separately for PM10, which contains coarse particles, and PM2.5 for fine particles. In Japan, an environmental quality standard for fine particulate matter (PM2.5) was established in 2009.**
Hazardous air pollutants are often emitted when substances themselves are used, while heavy metals are sometimes emitted as impurities of raw materials and unintentional emissions from processes such as refining. Dioxins are emitted as byproducts associated with combustion and other processes. Efforts to address hazardous air pollutants began in the 1990s. After the introduction of countermeasures in accordance with 1996 amendments to the Air Pollution Control Act, “priority substances” were identified in an advisory report that year by the Central Council for the Environment, and the establishment of environmental quality standards was initiated.
In establishing environmental quality standards for air pollution, an emphasis is placed on epidemiological findings about the ambient environment. However, since epidemiological studies may not always be available, toxicological findings from animal testing and, for hazardous air pollutants, epidemiological findings about workers, are also used. These findings are reviewed by experts concerning exposure levels, data reliability, etc., and utilized by applying uncertainty factors where necessary. Also, different approaches are used when determining the standard values, with a toxicity threshold in some cases, and no threshold in others.
With regard to hazardous air pollutants, even for substances for which environmental quality standards have not been established due to limited data related to hazard assessment and other factors, target values that serve as guidelines for reducing health risks (i.e., guideline values) are established sequentially from among priority substances.
In the case of air pollutants, the effects of short-term versus long-term exposure are often different. Therefore, standard values can be established for just one of these, or different values for each. In this case, it is necessary to pay attention to the evaluation method for those standard values.
At present, all environmental quality standards and guideline values related to air pollution are established from the perspective of protecting human health. In the initial period, some substances have been considered for their effects on the living environment, such as impacts on flora and reduced visibility, but no standards have been set for the conservation of the living environment.
*The Air Pollution Control Act defines a “hazardous air pollutant” as “a substance that is likely to harm human health if it is ingested continuously and that causes air pollution (other than soot and smoke, specified particulates, and mercury and mercury compounds).”
**PM2.5 is defined as “particulate matter suspended in the atmosphere, which is collected after removing larger particles using a partitioning device capable of separating particles with an aerodynamic diameter of 2.5 μm at a rate of 50%,” and PM10 has the same definition, simply replacing “2.5 μm” with “10 μm.” On the other hand, SPM is defined as “particulate matter suspended in the atmosphere with a particle diameter of 10 μm or less,” and different methods are used for collecting particles. Therefore, particles collected and measured as SPM can be considered to be particles with intermediate size distribution between PM2.5 and PM10, including PM2.5 and some of PM10.
(b) History of Establishment of the Standards
Initial Stages of Establishment
Among environmental quality standards for air pollution, the following five items were established in the initial period, i.e., sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO), suspended particulate matter (SPM), photochemical oxidants (Ox) and nitrogen dioxide (NO2).
With regard to sulfur dioxide, “Environmental Quality Standards for Sulfur Oxides” were adopted by cabinet decision on February 12, 1969. After the Environment Agency was established, its Director-General consulted the Central Council for Environmental Pollution Control, an advisory body, in September 1971 on “Establishing environmental quality standards for air pollution.” Based on the resulting advisory report, Cabinet approved amendments to the standards on May 15, 1973.
In response to these consultations, an expert committee was launched by the Council’s Air Quality Committee to consider the setting of environmental quality standards. Following the committee’s report in March 1973, the Council’s advisory report was issued on April 26, 1973, entitled “Revision of environmental quality standards relating to sulfur oxides and establishment of environmental quality standards relating to nitrogen oxides and photochemical oxidants.”
With regard to nitrogen dioxide, an expert committee was established in October 1970 to start deliberations under the Living Environment Council, an advisory body to the Minister of Health and Welfare. Its deliberations were taken over by the Central Council for Environmental Pollution Control, and a report by the expert committee was completed in June 1972, also including photochemical oxidants, leading to the advisory report mentioned above.
With regard to carbon monoxide, the Living Environment Council was consulted in January 1969, and based on the report of an expert committee, the Council submitted an advisory report in December that year, after which environmental quality standards were established by cabinet decision on February 20, 1970.
With regard to suspended particulate matter, the Central Council for Environmental Pollution Control, which took over the deliberations, submitted an advisory report in December 1971 based on a December 1970 report submitted by an expert committee to the Living Environment Council, and public notification by the Environment Agency of its environmental quality standard was issued on January 11, 1972.
On May 8, 1973, after these deliberations, environmental quality standards for carbon monoxide, suspended particulate matter, nitrogen dioxide, and photochemical oxidants were issued by public notification by the Environment Agency as “Environmental Quality Standards for Air Pollution.” On May 16 that year, revised environmental quality standards for sulfur dioxide, which had obtained Cabinet approval the previous day, were added to the notification.
Subsequently, for nitrogen dioxide, it was determined to be necessary to make a “scientific judgment” as stipulated in Article 9, Paragraph 3 of the Basic Act on Environmental Pollution Control to reflect developments and advances in scientific knowledge since the expert committee report of 1972. On March 28, 1977, the Central Council for Environmental Pollution Control was consulted on the conditions for determining the effects of nitrogen dioxide on human health. The expert committee established within the Council met 49 times over the course of about a year, and compiled a report in March 1978, upon which the Council submitted its advisory report on March 22 that year. In response, the environmental quality standards were revised, and on July 11, 1978, a new public notification was issued as “Environmental Quality Standards for Nitrogen Dioxide.”
In addition, the establishment of environmental quality standards for lead and hydrocarbons was considered. In August 1976, an advisory report stating that “as long as atmospheric lead concentrations are maintained at the current level, there is no need to set environmental quality standards for lead,” and an advisory report establishing guidelines on atmospheric hydrocarbon concentrations to prevent the generation of photochemical oxidants was compiled, and prefectures and ordinance-designated cities were notified.
Subsequent Establishments and Revisions
There were no subsequent revisions relating to air pollutants except for measurement methods, but environmental quality standards for particulate matter (PM2.5) were established in 2009.
Measures to deal with pollution caused by hazardous chemical substances including heavy metals (i.e., countermeasures for hazardous air pollutants) were introduced with amendments to the Air Pollution Control Act in 1996. Prior to this, on September 20, 1995, the Central Council for the Environment was consulted on “future measures to address hazardous air pollutants,” and in response to several resulting advisory reports, environmental quality standards for benzene, trichloroethylene, tetrachloroethylene and dichloromethane were established sequentially from 1997 onward. Among these, the standard value for trichloroethylene was revised in 2018.
In addition, although environmental quality standards have not been established due to limited data related to hazard assessments and other factors, from the perspective of reducing health risks, target values which are expected to function as indicators for assessing atmospheric monitoring and for efforts by businesses to control emissions, have been determined as guideline values for acrylonitrile and ten other substances sequentially since 2003 in response to advisory reports by the Central Council for the Environment in order to help reduce health risks caused by hazardous air pollutants in the environment. The basic approach for establishing guideline values was first described in July 2003 in the seventh advisory report by the Council, entitled “The Future Approach in Health Risk Assessments for Hazardous Air Pollutants.” Subsequently, it has been revised sequentially.
With regard to environmental quality standards for dioxins, a public notification was issued on December 27, 1999, in accordance with Article 7 of the Act on Special Measures against Dioxins, in response to the fifth advisory report issued on the same day as part of the above-mentioned deliberations on hazardous air pollutants.
(c) Reference
・大気汚染防止法令研究会(1984)逐条解説・大気汚染防止法、ぎょうせい、pp.309-336 【NIES保管ファイル】
・昭和51年8月17日・環境庁大気保全局長「「大気中鉛の健康影響について及び光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(中央公害対策審議会答申)」について」(環大企第220号) https://www.env.go.jp/hourei/04/000104.html 【NIES保管ファイル】
・平成8年10月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/02.pdf 【NIES保管ファイル】
(2)大気汚染物質に係る環境基準及び指針
①設定の考え方
(大気汚染防止法令研究会(1984)逐条解説・大気汚染防止法(ぎょうせい)より)(抜粋)
第3部 環境基準解説
第一章 環境基準の意義と性格(抄)
(中略)
これまで、大気汚染に係る健康影響に関する概念の整理は種々試みられており、次に、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい」環境上の条件を考える上で参考になる例を2、3掲げることとする。
まず、昭和38年、WHOの大気汚染物質に関する専門委員会は、大気汚染のガイドとして濃度、暴露時間及びそれに相当する影響について、次のような4つのカテゴリーを示している。
<レベルⅠ>ある値又はそれ以下の値ならば、現在の知見によると、直接的にも間接的にも影響(反射又は適応若しくは防御反応の変化を含めて)が観察されない濃度と暴露時間との組み合わせ
<レベルⅡ>ある値及びそれ以上の値ならば、感覚器官の刺激、草木の損害、視程の減少又はその他の環境への悪影響が起こりそうな濃度と暴露時間の組み合わせ
<レベルⅢ>ある値及びそれ以上の値ならば、重要な生理機能の阻害又は慢性疾患若しくは生命の短縮に導く可能性のある諸変化が起こりそうな濃度と暴露時間の組み合わせ
<レベルⅣ>ある値及びそれ以上の値ならば、住民のうち敏感な集団に急性疾患又は死亡が起こりそうな濃度と暴露時間との組み合わせ
また、昭和53年、二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会(中央公害対策審議会)は、専門委員会報告の提出の際の付言の中で、大気汚染の健康影響の程度を次のような六段階に分類して、概念の整理を行っている。
①現在の医学・生物学的方法では全く影響が観察されない段階
②医学・生物学的な影響は観察されるが、それは可逆的であって、生体の恒常性の範囲内にある段階
③観察された影響の可逆性が明らかでないか、あるいは生体の恒常性の保持の破綻、疾病への発展について明らかでない段階
④観察された影響が疾病との関連で解釈される段階
⑤疾病と診断される段階
⑥死
もちろん、これはあくまでも委員会としての考察の材料として利用したものであり、それぞれの段階の境界は明確でなく、かつ、連続的でもなく、むしろ重複するものであり、専門委員会の得ている健康への影響の知見が、どの段階に属するかを明示することもまた困難なことが多い。しかし、概念的にいえば、③を健康な状態からの偏りと考えることができる。
環境基準の設定は、公害対策に関する重要事項として環境庁長官が中央公害対策審議会に諮問し、その答申を得て、環境庁告示をもって示される。同審議会においては、基準を設定する項目につき、それぞれ、関連分野の専門家で構成する専門委員会を設け、①人の健康に及ぼす影響、②人以外の生物に及ぼす影響、③生活環境に及ぼす影響に分けて科学的知見の集積からなるクライテリア(判定条件)を検討するほか、汚染の実態等の分析及び測定方法を検討し、基準の設定のための答申の基礎資料となる報告書を作成する。また、人の健康影響に関しては、①動物実験、②人の志願者による実験、③疫学調査等の入手可能な資料が利用される。
(以下略)
(参考資料)
・大気汚染防止法令研究会(1984)逐条解説・大気汚染防止法、ぎょうせい、pp.309-336 【NIES保管ファイル】
・WHO (1964) Atmospheric pollutants report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series No.271 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40578/WHO_TRS_271.pdf?sequence=1&isAllowed=y 【NIES保管ファイル】
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
| 物質 | 環境上の条件(基準値) | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 二酸化いおう(SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であること。 | 昭和48年5月16日 | 改定 |
| 一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 昭和48年5月8日 | |
| 浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 昭和47年1月11日 | |
| 光化学オキシダント(Ox) | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | 昭和48年5月8日 | |
| 二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | 昭和53年7月11日 | 改定 |
| 微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 | 平成21年9月9日 |
(注)上記環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
(評価方法)(常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視(抄)
1.測定対象
主として、窒素酸化物、粒子状物質その他の大気汚染防止法に基づく規制がなされている物質に関して大気汚染状況を把握するため、環境基準が設定されている以下に掲げる物質について測定を実施する。
二酸化硫黄
一酸化炭素
浮遊粒子状物質
光化学オキシダント
二酸化窒素
また、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについての大気汚染状況を適切に評価するため、その生成の原因となる非メタン炭化水素についても測定を実施する。
(中略)
3.測定頻度
原則として、年間を通じて連続的に測定を行うものとする。
(中略)
6.測定値の取扱い及び評価
(1)評価の対象としない測定値等
ア 測定局が、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による工業専用地域(旧都市計画法(大正8年法律第36号)による工業専用地域を含む。)、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立地、原野、火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置されている場合の当該測定局における測定値
イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反映していないと認められる場合における当該測定値
ウ 1日平均値に係る1時間値の欠測が1日(24時間)のうち4時間を超える場合における当該1日平均値
(2)常時監視結果の評価
常時監視の結果は、環境基準により測定局ごとに短期的評価・長期的評価を行うこととし、以下による。
ア 短期的評価
大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合は、環境基準が1時間値又は1時間値の1日平均値についての条件として定められているので、定められた方法により連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間についてその評価を行う。
イ 長期的評価
大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえで評価を行う場合は、測定時間、日における特殊事情が直接反映されること等から、次の方法により長期的評価を行う。
①二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質
年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外して評価を行う。ただし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。
②二酸化窒素
年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。
(中略)
Ⅲ 微小粒子状物質に係る常時監視(抄)
1.測定対象
平成21年9月に環境基準が設定された微小粒子状物質、いわゆるPM2.5について測定を実施する。
(中略)
7.測定値の取扱い及び評価
(1)評価の対象としない測定値等
ア 測定局が、都市計画法の規定による工業専用地域(旧都市計画法による工業専用地域を含む。)、港湾法の規定による臨港地区、道路の車道部分その他埋立地、原野、火山地帯等通常住民が生活しているとは考えられない地域、場所に設置されている場合の当該測定局における測定値
イ 測定値が、測定器に起因する等の理由により当該地域の大気汚染状況を正しく反映していないと認められる場合における当該測定値
ウ 1日平均値に係る欠測が1日(24時間)のうち4時間を超える場合における当該1日平均値。また、1年平均値の計算においては、有効測定日が250日に満たないもの
(2)常時監視結果の評価
微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価を行うものとする。
長期基準に関する評価は、測定結果の1年平均値を長期基準(1年平均値)と比較する。
短期基準に関する評価は、測定結果の1日平均値のうち年間98パーセンタイル値を代表値として選択して、これを短期基準(1日平均値)と比較する。
なお、評価は測定局ごとに行うこととし、環境基準達成・非達成の評価については、長期基準に関する評価と短期基準に関する評価を各々行った上で、両方を満足した局について、環境基準が達成されたと判断する。
(参考資料)
・平成28年9月26日・環境省水・大気環境局長「「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正等について」(環水大大発第1609263号・環水大自発第1609261号)別添 https://www.env.go.jp/air/osen/law22_kijun/hannei_2.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○二酸化いおう
1.基準値
(当初:いおう酸化物として)
人の健康に関するいおう酸化物に係る環境基準は、次のいずれをも満たすものとする。
(1)(ア)年間を通じて、1時間値が0.2ppm以下である時間数が、総時間数に対し、99%以上維持されること
(イ)年間を通じて、1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が、総日数に対し、70%以上維持されること
(ウ)年間を通じて、1時間値が0.1ppm以下である時間数が、総時間数に対し、88%以上維持されること
(2)年間を通じて、1時間値の平均値が0.05ppmをこえないこと
(3)いずれの地点においても、年間を通じて、大気汚染防止法に定める緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数が、総日数に対し、その3%をこえず、かつ、連続して3日以上続かないこと
(現行:二酸化いおうとして)
1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
2.測定方法
溶液導電率法又は紫外線蛍光法
3.設定経緯
(当初)
昭和43年1月・生活環境審議会公害部会環境基準専門委員会報告
昭和43年7月15日・生活環境審議会答申
昭和44年2月12日・閣議決定
(改定)
昭和48年3月31日・中央公害対策審議会大気部会いおう酸化物に係る環境基準専門委員会報告
昭和48年4月26日・中央公害対策審議会答申
昭和48年5月15日・閣議了解
昭和48年5月16日・環境庁告示第35号
4.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(専門委員会報告抜粋)
1)亜硫酸ガス測定値の評価
従来一般に亜硫酸ガスの影響として受けとられているものは、亜硫酸ガス、硫酸ミスト、その他の硫黄酸化物等の影響によるものであり、更にこれ等は浮遊微粒子と共存、又は微粒子表面への附着又は吸着により、その影響を強めることがある。亜硫酸ガスのみの濃度測定にはロザリニン比色法が共存成分の影響を受けることが少なく最も信頼性ある測定値を与えるものであり、この方法の連続比色記録法もあるが、現在わが国で広く利用されている方法はPbO2法と導電率法による記録方式である。PbO2法はある地域の汚染状況とその年次的傾向について定性的に比較値を知るのに便利であり、導電率法は濃度の変化を自動的に記録するのに便利であるが、亜硫酸ガス濃度以外に他の導電性物質の影響も受ける可能性がある。従って本委員会は本法により得られた濃度は亜硫酸ガス濃度指数として解釈すべきものとした。将来は亜硫酸ガス、その他の成分個々の測定によって判定することが望ましいが、現在の段階ではこの濃度指数により環境を判断することにした。
2)亜硫酸ガスによる大気汚染の性状の判断のための尺度
本委員会は、環境基準とは健康の保持のための基準であるとの立場にたち、人の健康を中心としての判断が、他の立場からの判断に優先すべきものであると考えた。
よって本委員会は、まず内外の研究、調査の資料を集める事により、地域環境大気の亜硫酸ガスによる汚染が、どの様な影響をひき起すかの判断のための尺度を与えるための、添附資料(略)を作成した。
資料は、調査、研究の一覧表であり、地域住民の疫学的研究、人への亜硫酸ガス暴露実験、動物への亜硫酸ガス暴露実験、そして参考として植物発育への影響の4分類にしてまとめたものである。
亜硫酸ガスの人の健康に与える影響として本委員会は、地域住民への平均的影響の推定、即ち重要な生理機能の好ましからざる反応と疾病の発生状態と共に、大気汚染に敏感に反応する集団又は感受性の高い集団、例えば、年少者及び老人という年令による人口集団、慢性の呼吸器又は循環器疾患等の病人集団への影響とを注目すべきものとした。
3)人の健康を保持するための閾濃度についての勧告
本委員会は2項の地域環境の"大気汚染の性状の判定のための尺度"のほか、人の健康を保持するための閾値を勧告し、大気汚染対策のための一つの医学的指針を示すことにした。このため、我国における最近の若干の調査結果を中心とし添附資料(略)を利用して閾値を求めた。
大阪市における調査によれば、亜硫酸ガス濃度の1時間値の24時間平均値が0.1ppm以上で死亡数の増大を来たす傾向を示し、日平均値或は月平均値0.08ppm以上は、ともに感受性の強い学童の肺機能を低下させ、3日平均値0.05ppm以上で、死亡数が増大する傾向が認められた。
時間的濃度変化の大きい四日市市においては、年間を通じて日最高値(1時間値)の平均が0.1ppmで、また1時間値の24時間平均濃度の10%が0.07ppmを超えると、気道炎症の有病率が2倍以上に増加し、学童の気道性疾患による欠席率が、前1週間の平均値が0.09ppmを超えたとき平常時の3倍となる。
一方、大気汚染の地域住民の健康への影響の有力な判断として閉塞性呼吸器疾患の有症率の増加が利用される。現在、世界各国でBritish Medical Research Councilが発表した面接方法による慢性気管支炎症の疫学的研究がひろく実施されており、我国においても同じ方法を用いて調査が行われている。現在まで得られた結果によれば、1時間値の24時間平均濃度の年間平均濃度が約0.05ppmを超える地区では上述の疫学調査方法で定義される慢性気管支炎の有症率が約5%になり、汚染のまだ生じていない地区と比較すると約2倍に達している。
すなわち、我々が現在知り得ることが出来た亜硫酸ガスの影響、殊に亜硫酸ガス濃度指数と影響との関係についての資料にもとづくかぎり、疫学的立場から
(1)病人の症状の悪化が疫学的に証明されない事
(2)死亡率の増加が証明されない事
(3)閉塞性呼吸器疾患の有症率の増加が証明されない事
(4)年少者の呼吸機能の好ましからざる反応ないし障害が疫学的に証明されない事
等の諸条件を考慮して亜硫酸ガス濃度指数で表した閾値は次の如くである。
すなわち、1時間毎に1時間の空気を採取して測定する場合には
24時間平均1時間値に対し 0.05ppm
1時間値に対し 0.1ppm
である。
この閾値は、実行可能な限りの努力を払うことによって、地域環境の大気汚染を軽減し亜硫酸ガス濃度指数をこの値以下にする様にするために与えられたものである。
(答申抜粋)
第2 環境基準に係る具体的条件
1 環境基準は、閾濃度を基礎的な尺度として、いおう酸化物による汚染の濃度並びに時間及び出現の頻度に係る条件を具体的数値によって示すものとする。
なお、閾濃度は、これまでの疫学的調査研究によってその濃度以下では住民の健康に影響を及ぼしていると推定される事実が証明されない最大汚染水準についての尺度を示すものである。したがって環境基準に係る具体的条件は、この尺度に合致する条件を年間を通じて実現可能なかぎり最大限に確保することを原則とし、その汚染に係る濃度が緊急時の条件に該当する事態の発生は最小限にとどめるように定めるものとする。
(注1)閾濃度については、昭和43年1月、生活環境審議会公害部会の環境基準専門委員会が報告したところによる。
(注2)「緊急時の条件に該当する事態」とは、ばい煙の排出の規制等に関する法律(以下「ばい煙規制法」という。)第21条第1項に定める事態をいい、大気汚染防止法の施行後は同法第17条第1項に定めるところによる。なお現行ばい煙規制法ではいおう酸化物の大気中における含有率が0.2ppm以上である状態が3時間以上継続し、又は0.3ppm以上である状態が2時間以上継続した場合であって、著しい気温の逆転現象が認められるような場合等をいうものとされている(同法施行規則第14条参照)。
2 上記の見地から、現段階において得られた調査研究の成果及び国際的視野のもとで入手し得る知見を基として、いくつかの前提を設け、いおう酸化物に係る環境基準についての具体的な条件を設定すると、別記に示すとおりとなる。
なおこの条件は、いおう酸化物に係る測定技術の進歩、人体等に対する影響についての知見の進展、防止技術の開発等に伴って、今後も定期的に検討を加えられ、必要に応じて改訂されるべきものとする。
(別記)
(1)環境基準は、原則として次の条件を満たすものであること。
(ア)年間を通じて、総時間数に対し、1時間値が0.2ppm以下である時間数が少なくとも99%以上維持され、かつ、1時間値の年平均値が0.05ppmをこえないこと。
(イ)年間を通じて、総日数に対し、1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が少なくとも70%ないし80%以上維持されること。
(ウ)年間を通じて、総時間数に対し、1時間値が0.1ppm以下である時間数が少なくとも88%ないし93%以上維持されること。
(2)(1)のほかに、いずれの地点においても、年間を通じて、総日数に対し、緊急時の措置を必要とする程度の汚染の日数がその3%をこえず、かつ、連続して3日以上続かないこと。
(注)「緊急時の措置を必要とする程度の汚染」については、第2の1の(注2)参照。
(昭和48年・改定時)
(専門委員会報告抜粋)
3.二酸化いおうの影響
すでに二酸化いおうはそれ自身、大脳生理学的反応、気道抵抗の増大、上気道の病理組織学的変化、呼吸器の細菌、ウイルスによる感染に対する抵抗性の低下等の影響を及ぼすことが、実験室における研究により証明されている。
地域環境における二酸化いおうの住民に対する影響については、生活環境審議会環境基準専門委員会が、昭和43年1月の報告において提案した次の如き条件は支持されるべきものと考える。すなわち、
(1)病人の症状の悪化が疫学的に証明されないこと
(2)死亡率の増加が証明されないこと
(3)慢性閉塞性呼吸器症状の有症率の増加が証明されないこと
(4)年少者の呼吸機能の好ましからざる反応ないし障害が疫学的に証明されないこと
である。
これらは人の健康の障害の防止をめやすとした最低限の条件である。われわれはこの条件をみたし、かつ、これに加えるに、現在までに知り得た知識に基づく限り、二酸化いおうが人の健康に好ましからざる影響を及ぼすことのない条件を考慮することにした。
この場合、われわれは大気汚染の影響は濃度と暴露時間の組み合わせで定まること、影響を受ける側の素因、状態が無視できないこと、さらにわが国においては二酸化いおう汚染に暴露される人口の数と密度が大きいことに留意した。とくに、大気汚染に敏感に反応する集団または感受性の高い集団、例えば年少者、老人という年令による人口集団、慢性の呼吸器または循環器疾患等の病人集団への影響は注目されなければならない。
すでに述べたように、二酸化いおうの人の健康に対する影響はまず呼吸器系への障害として出現するが、そのためには浮遊粒子状物質の存在が重要な意味をもつことが実験室及び地域社会における調査研究により証明されている。また二酸化いおうによる呼吸器への影響は窒素酸化物、とくに二酸化窒素によって加重されることが実験室における人についての研究において証明されている。
生活環境審議会環境基準専門委員会報告においては、わが国における当時の調査結果を次のごとく整理している。
大阪市における調査によれば亜硫酸ガス濃度の1時間値の24時間平均値が0.1ppm以上で死亡数の増大をきたす傾向を示し、日平均値あるいは月平均値0.08ppm以上はともに感受性の強い学童の肺機能を低下させ、3日平均値0.05ppm以上で死亡数が増大する傾向が認められた。
時間的濃度変化の大きい四日市市においては、年間を通じて日最高値(1時間値)の平均値が0.1ppmで、また1時間値の24時間平均値の10%が0.07ppmを超えると、気道炎症の有症率が2倍以上に増加し、学童の気道性疾患による欠席率が前一週間の平均値が0.09ppmを超えたとき平常時の3倍となる。
地域住民を対象とした英国医学研究委員会(British Medical Research Council)方式による疫学的調査によれば、1時間値の年間平均値が約0.05ppmを超える地区では慢性気管支炎症状の有症率が約5%になり、汚染のまだ生じていない地区と比較すると約2倍に達している。
これらの調査結果に加えるものとして、本専門委員会が注目した調査結果は次の如くである。
北九州地区における調査によれば、二酸化鉛法による昭和35~42年にわたる平均値で1.04 mgSO3/100cm2/日の地区においては0.53mgSO3/100cm2/日の地区に比べ、学童の喘息様症状の訴え率が2倍に認められた。二酸化鉛法による測定値から溶液導電率法による測定値への対応をみることは一般的には困難であるが、一応我が国における各地の測定値の平均的対応からみると、これらの地区における二酸化いおう濃度は、それぞれ0.033~0.036ppmおよび0.017~0.019ppmに相当する。
二酸化いおう汚染が急激に悪化した場合の過剰死亡についての大阪市における調査によれば、二酸化いおう濃度6日間平均値が0.12ppmの高濃度汚染がみられたときに、とくに循環器系疾患を有する者に死亡率が増大した。
閉塞性呼吸器疾患ないし症状の有症率調査は、英国医学研究委員会方式によって、山口県はじめ各地で続行されているが、その結果はそれぞれの地域の二酸化いおう濃度の年平均値と単純性慢性気管支炎症状(「せき」と「たん」が3ヶ月以上毎日出る症状)有症率との間には関連性があることが示されている。その結果のうち注目すべきものには次のものがある。
兵庫県赤穂市および大阪府における調査にあっては、40才以上の成人につき、「せき」と「たん」が3ヶ月以上毎日出る単純性慢性気管支炎症状有症率は、二酸化鉛法で年平均値1.0mgSO3/100cm2/日以下の地区では約3%であるが、それ以上の値を示す地区では二酸化鉛方による測定値と有症率との間には正の関連性がみられた。なお、二酸化鉛法1.0mgSO3/100cm2/日は溶液導電率法で0.032~0.035ppmに相当する。
全国6カ所におけるばい煙等影響調査にあっては、30才以上の家庭婦人についてのものであるが、上述と同じ症状の有症率3%は、二酸化鉛法による値が5ヶ月平均で約0.7mgSO3/100cm2/日であり、この値は溶液導電率法で0.022~0.025ppmに相当する。
以上の閉塞性呼吸器症状の有症率調査にみられたように、40才以上の成人の「せき」と「たん」が3ヶ月以上毎日出る症状の有症率約3%は、二酸化いおうによる汚染が軽微またはほとんど無い地区においてみられると考えられる。
なお、成人女子の有症率は成人男子に比べ、低位にあることが広く認められている。
四日市市における閉塞性呼吸器疾患の新規患者の発生数(3年移動平均値)とその年の二酸化いおう濃度の年平均値とは、おおむね0.04ppmをこえたところでは濃度と発生患者数は正の関連性があり、かつ、1時間平均値0.1ppmを超えた回数が年間おおむね10%以上測定されたところで、新規患者数は1時間平均値0.1ppmを超えた回数と正の関連性が認められた。
年少者の呼吸機能とくに閉塞性機能低下と二酸化いおう濃度との関係は各地の調査で確かめられている。
4.地域環境大気中の二酸化いおう濃度条件
われわれは上述の二酸化いおうの測定方法と人の健康への影響に関する資料に基づき総合的に判断した結果、地域環境大気中の二酸化いおうについて、人の健康を保護するうえで維持されるべき濃度条件を次のとおり提案する。
すなわち、1時間毎に1時間の空気を採取して溶液導電率法により測定した場合には
(1)24時間平均1時間値に対し、0.04ppm
(2)1時間値に対し、0.1ppm
である。
この値は実行可能な限りの努力を払うことによって、地域環境の二酸化いおうによる大気汚染を軽減し、この値以下にするために与えられたものである。
(以下略)
(答申抜粋)
いおう酸化物に係る環境基準の改定について(抄)
(中略)
本答申においては、専門委員会報告で示された判定条件は、現在までに得られた知見にもとづき、かつ十分な安全を見込んだうえで総合的に判断されたものであり、適当と認められるので、人の健康に関する二酸化いおうに係る環境基準(以下単に「環境基準」という)は、大気汚染防止行政の目標として別紙のように定めるべきものと考える。
(中略)
(別紙)二酸化いおうに係る環境基準(案)
1.環境基準値
人の健康に関する二酸化いおうに係る環境基準は、次のいずれの条件についても維持されるものとする。
(1)1時間値の1日平均値が、0.04ppm以下であること。
(2)1時間値が0.1ppm以下であること。
(以下略)
5.参考資料
・昭和43年1月・生活環境審議会公害部会環境基準専門委員会「環境基準専門委員会報告書(硫黄酸化物)」 【NIES保管ファイル】
・昭和43年7月15日・生活環境審議会「いおう酸化物による大気汚染防止のための環境基準の設定について(答申)」【NIES保管ファイル】
・昭和48年3月31日・中央公害対策審議会大気部会いおう酸化物に係る環境基準専門委員会「いおう酸化物に係る環境基準についての専門委員会報告」 【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・中央公害対策審議会「いおう酸化物に係る環境基準の改定ならびに窒素酸化物および光化学オキシダントに係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・環境庁大気保全局(1973)いおう酸化物に係る環境基準専門委員会の提案した判定条件(人の健康を保護するうえで維持されるべき濃度条件)の根拠について、環境保健レポート、22、pp.57-58 【NIES保管ファイル】
6.解説文献
・香川順(1987)我が国の二酸化硫黄の環境基準設定の基になった健康影響に関する知見の出典等について、空気清浄、25(2)、pp.13-22 【NIES保管ファイル】
・鈴木武夫・石川清文・山本弘(1970)亜硫酸ガス(いおう酸化物)の環境基準設定のための資料と考察、大気汚染研究、5(3)、pp.315-357 https://doi.org/10.11298/taiki1966.5.315
○一酸化炭素
1.基準値
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
2.測定方法
非分散型赤外分析計を用いる方法
3.設定経緯
昭和44年9月・生活環境審議会公害部会一酸化炭素環境基準専門委員会報告
昭和44年12月22日・生活環境審議会答申
昭和45年2月20日・閣議決定
昭和48年5月8日・環境庁告示第25号
4.基準値の根拠の概要
(専門委員会報告抜粋)
3 CO汚染の人の健康と福祉に及ぼす影響(資料2参照(略))
現在までにえられた知識に基づくかぎり、COは紫外線の吸収や視程の減少を生ずることなく、また、大気中での他の汚染物質との間に大気汚染として有害な化学反応を起こすことは証明されていない。さらに現在各地で測定されている程度のCOの濃度では、植物または家畜、家きん類に対する被害は証明されていない。
3-1 人の健康に及ぼすCOは体内で発生する微量のCO(内因性COという。)と比較的多量の体外からもちこまれるCOである。
このCOが人の健康に影響を及ぼす機構は次の三つのいずれかまたは全部が考えられる。
(1)CO血球素(COHb)の生成による組織への酸素運搬機能の阻害
(2)COのHb以外のある種の生体内構成物質(たとえば酵素等)との結合または反応による生理機能障害
(3)肺胞におけるCOHbの解離阻害
3-2 公衆衛生学的立場から、COの影響の防止のために次の諸条件を考慮した。
(1)COの影響のうち臨床所見または主観的所見、すなわち中毒症状を現すようなことは絶対に許されるべきことではない。
(2)大気汚染としてのCO汚染で人の体内にとりこまれたCOはもちろんのこと、喫煙、暖房、厨房によってとりこまれたCO、そして内因性COは、生理的にすみやかに体外に除去されることが重要である。
(3)CO汚染がとくにモータリゼーションの進展とともに進行している現在では、日常生活活動および生産活動の有力な手段である自動車運転操作等に悪影響を与えるおそれがある。
(4)また、とくに病弱者集団、特別の疾病集団、幼少年または老人等の年令集団への影響に注目しなければならない。
3-3 以上の条件に沿って、われわれの集めることができた資料に基づいて、重要なCOの人への影響とその汚染条件を述べると次のごとくになる。
(1)内因性COの肺胞での解離を阻害することなく、完全に生理学的に解離を円滑に進行させるためには、吸入空気のCO濃度は5ppmを下回ることが望ましい。
(2)喫煙、暖房、厨房および大気汚染におけるCO汚染等から吸収されたCOをすみやかに体外に排除するためには、環境大気中のCOは可及的に低濃度でなければならない。たとえば、1時間値の平均CO濃度20ppmの空気を8時間の間呼吸してCOHbが増加した人のCOHb量※が、もとの値までに回復するためには、1時間値5ppm程度以下のところに少なくとも8時間以上居ることが必要である。この状態を1時間値の24時間平均値に換算すると10ppm程度となる。
※ COHb量とはCOHbの容量が全Hbの容量に対して占める割合である。
(3)時間識別能の低下はCOHb量が2%に達すると出現する。たとえば、24時間CO汚染空気を呼吸する場合に、COHb量を2%以下に維持するためにはCO濃度の1時間値の24時間平均は10ppm以下でなければならない。また、1時間だけCO汚染空気を呼吸する場合には、1時間値55ppm以下であることがのぞましい(この際、暴露前後のCO濃度は5ppm以下であることを予想した値である。)。
(4)心筋梗塞発症患者には1時間値の24時間平均濃度10ppmのCO汚染が数日間続くとCOによる悪影響が現われる。
(5)COHb量が5%に達すると、精神神経機能が低下すること、貧血者、重要臓器の循環障害者の死期が早まることが認められている。このCOHb量5%は30ppm 8時間で生ずる。
4 環境大気中のCO濃度条件
われわれは環境大気中のCO濃度条件を次のとおり提案する。
(1)連続する8時間における1時間値の平均は20ppm以下であること。
(2)連続する24時間における1時間値の平均は10ppm以下であること。
以上の(1)および(2)の条件を同時に満たさなければならない。
(注)この濃度は0℃、1気圧に換算してえられたものとする。
(答申抜粋)
環境基準は、一酸化炭素による影響の特性にかんがみ、年間を通じて常に次の1および2の条件が維持されるものとする。
1 連続する8時間における1時間値の平均は、20ppm以下であること。
2 連続する24時間における1時間値の平均は、10ppm以下であること。
5.参考資料
・昭和44年9月・生活環境審議会公害部会一酸化炭素環境基準専門委員会「一酸化炭素による環境汚染の環境基準に関する専門委員会報告」 【NIES保管ファイル】
・生活環境審議会(1972)一酸化炭素による大気汚染防止のための環境基準の設定について(答申)、大気汚染研究、7(4)、pp.762-763 https://doi.org/10.11298/taiki1966.7.762
・生活環境審議会公害部会一酸化炭素環境基準専門委員会(1972)資料1 一酸化炭素(CO)による大気汚染の測定と人への影響、大気汚染研究、7(4)、pp.671-694 https://doi.org/10.11298/taiki1966.7.671
・生活環境審議会公害部会一酸化炭素環境基準専門委員会(1972)資料2 一酸化炭素(CO)による大気汚染の測定と人への影響、大気汚染研究、7(4)、pp.695-743 https://doi.org/10.11298/taiki1966.7.695
・生活環境審議会公害部会一酸化炭素環境基準専門委員会(1972)資料3 一酸化炭素による大気汚染防止のための環境基準の設定について、大気汚染研究、7(4)、pp.744-761 https://doi.org/10.11298/taiki1966.7.744
○浮遊粒子状物質
1.基準値
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
(備考:浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。)
2.測定方法
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
3.設定経緯
昭和45年12月25日・生活環境審議会公害部会環境基準浮遊ふんじん専門委員会報告
昭和46年12月22日・中央公害対策審議会答申
昭和47年1月11日・環境庁告示第1号
4.基準値の根拠の概要
(専門委員会報告抜粋)
ここにいう浮遊粒子状物質とは、その化学的性質を考慮することなく、また生成過程を問わず粒径10ミクロン(μ)以下の粒子状物質をいう。
これらの粒子状物質は土砂のまきあげ等自然現象によるものがあるが、現在地域大気汚染を起こしている汚染物として注目される粒子状物質の大部分は、その原因が石炭・石油系燃料、廃棄物の燃焼等の燃焼過程及び生産過程からの漏洩等にもとめられ、さらに自動車排気中の粒子状物質が加わると考えられる。
これらの粒子状物質は、その粒径の大きさに従って空気中の滞留時間は異なる。例えば、比重1の球形粒子では粒径が10μ以上のものはすみやかに、10μ以下1μ以上のものは空気の動きと異なる動きをする程度で沈降するが、1μ以下のものは沈降速度が非常に小さく、空気の動きに従って移動すると考えられる。かつ一方で、10μ以上の粒子状物質は鼻腔及び咽喉頭でほとんど捕捉されるが、5μまでは90%が気道及び肺胞に沈着し、5μ以下の粒子については0.5までは沈着率は次第に減少し、0.5μで25~30%の沈着率を示す。これより小さい粒子については沈着率は再び増加する。また肺胞沈着率は2~4μの間の粒子がもっとも大で、0.4μの粒子で最低となる。そして0.4μ以下の粒子の沈着率は再び増加すると考えられる。なお、この呼吸器沈着率は呼吸量と呼吸数によって影響を受ける。
以上の理由によって、地域大気汚染における浮遊粒子状物質とは、直径10μ以下のものをいうことにした。なお、ここでいう浮遊粒子状物質は、その物理的性状に着目し、化学的性状については考慮しないことにした。
(中略)
3.浮遊粒子状物質の人の健康と福祉に及ぼす影響において注目すべきこと
現在までにえられた知識にもとづく限り、浮遊粒子状物質の影響のうちとくに注目すべきものは次のとおりである。
3-1 浮遊粒子状物質の濃度が600μg/m3(1,200~300μg/m3)となると視程は2km以下となり、地域住民の中に不快、不健康感を訴えるものが増加する。また交通事故発生の増加に留意せねばならないとされている。150μg/m3(300~75μg/m3)となると視程は8km以下となり、有視界飛行は困難となるとされている。
3-2 年平均値(24時間値)100μg/m3の地区での非伝性呼吸器症状(例えば慢性気管支炎症状)の有症率がそれ以下の地区に比べ増加がみられる。
3-3 年平均値(24時間値)100μg/m3の地区に居住する学童の気道抵抗の増加がみられる。
3-4 24時間平均値150μg/m3、1時間平均値300μg/m3の状態が出現すると病弱者、老人の死亡数が増加する。
3-5 米国における研究によれば年平均値80μg/m3から100μg/m3に増加すると全死亡率の上昇がみられた。
3-6 英国における研究によれば平均値140μg/m3から60μg/m3に改善されたとき地域の「たん」の排出量の著明な減少がみられた。
なお、(3-2)、(3-3)、(3-4)はいずれもいおう酸化物濃度指標の値がすでに設定した環境基準値をこえている地区におけるものである。
むずび(抄)
地域環境大気中の浮遊粒子状物質の濃度条件について、我々は上述の測定方法と影響の資料にもとづき、次のとおり提案する。
それは、
(1)連続する24時間の平均1時間値 100μg/m3以下
(2)1時間値 200μg/m3以下
であって、上述の両条件が常に満足されなければならない。
(以下略)
(答申抜粋)
浮遊粒子状物質に係る環境基準(以下単に「環境基準」という)は、人の健康の保護の見地から大気汚染防止の目標として別紙のように定めることが適当であると考える。
(中略)
別紙 浮遊粒子状物質に係る環境基準(抄)
第1 定義
「浮遊粒子状物質」とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径10ミクロン(μ)以下のものをいう。
第2 環境基準値
環境基準は常に次の(1)および(2)の条件が維持されるものとする。
(1)連続する24時間における1時間値の平均は0.10mg/m3以下であること。
(2)いずれの1時間値にあっても0.20mg/m3以下であること。
(以下略)
5.参考資料
・昭和45年12月25日・生活環境審議会公害部会浮遊ふんじん環境基準専門委員会「浮遊粒子状物質による環境汚染の環境基準に関する専門委員会報告」 【NIES保管ファイル】
・昭和46年12月22日・中央公害対策審議会「浮遊粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・生活環境審議会浮遊粉じん環境基準専門委員会(1973)浮遊粒子状物質による大気汚染の環境基準設定のための資料、大気汚染研究、8(1)、pp.1-75 https://doi.org/10.11298/taiki1966.8.1
6.解説文献
・浜中裕徳(1972)浮遊粒子状物質の環境基準の設定について、環境保健レポート、9、pp.13-17 【NIES保管ファイル】
○光化学オキシダント
1.基準値
1時間値が0.06ppm以下であること。
(備考:光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成された酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。)
2.測定方法
(当初)中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法または電量法
(現行)中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
3.設定経緯
昭和47年6月20日・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会報告
昭和48年4月26日・中央公害対策審議会答申
昭和48年5月8日・環境庁告示第25号
平成8年10月25日・環境庁大気保全局長通知(環大企第346号・環大規第211号)(測定法改定)
4.基準値の根拠の概要
(専門委員会報告抜粋)
1 はしがき(抄)
(中略)
大気中で二酸化窒素と炭化水素の共存のもとで、光化学反応により生成される物質として現在注目されているのは次の如きものである。すなわちオゾン(O3)、二酸化窒素、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)およびその同族体、過酸化物等の酸化性物質、ホルムアルデヒド、アクロレイン等の還元性物質、エーロゾル、そして影響についての証明は未知であるが、注目されなければならない活性の強い遊離基がある。これ等が総合して起した影響が、一般に光化学オキシダントの影響と称せられている。
光化学オキシダントの影響は粘膜刺激症状、人の呼吸器への激しい影響、その他の臓器、組織への影響等人の健康への影響のほか、ゴムのひび割れ、植物への悪影響、農作物被害、衣類の退色などが観察されている。
われわれは光化学反応によって生成される酸化性物質のうち二酸化窒素を除いたものを光化学オキシダントとする。これは後述する中性ヨウ化カリウム溶液を用いる測定方法によるものであり、この場合の測定値の殆どはオゾンによるものであることが確認されている。従って、われわれはここでは光化学オキシダントの大部分はオゾンであるとの認識のもとに、光化学反応生成汚染物質の指標としての光化学オキシダントについての環境基準に関して勧告することにした。
(中略)
3 人に対する影響(抄)
3-2 光化学オキシダントの影響
(中略)
光化学オキシダントの大部分がオゾンであるのでオゾンの影響を見ると次の如くである。
動物実験でみるかぎり、オゾンは上気道摂取率は低く、容易に呼吸器深部に到達する。1ppm 4時間暴露で、暴露後20時間後に軽度の肺水腫がみられ、長期間暴露で、気管支炎、細気管支炎、肺気腫、肺線維症、腺腫がみられる。0.25~0.5ppm、3時間暴露で気流抵抗上昇がみられる。1ppm 1時間暴露で肺細胞の構成蛋白質の変化を推定せしめる影響が認められる。運動負荷した動物においてオゾンの毒性は増加する。
オゾンにおける細菌感染の感受性増加は二酸化窒素と同様であり、0.08ppm 3時間ですでに認められている。また気管支喘息の発症の原因となる可能性は二酸化窒素よりも、より強いことが動物実験では確かめられている。
一方、動物実験では急性暴露に対して耐性の出現が認められるが、慢性暴露については不明である。
人に対してのオゾン暴露実験では、急性暴露で、0.1ppm 1時間までは明らかな影響は認められず、0.5~1.0ppm、1~2時間で気道抵抗増加、肺の一酸化炭素拡散能低下、肺活量低下が認められ、かつ運動負荷によりこれらの症状が悪化する。以上は平均的な反応であるが、個人差があり、感受性の高い者の存在に注意せねばならないことが指摘されている。
人に対するオゾンの長期暴露では0.2ppm以下は明らかな影響が工場労働者には認められず、0.3ppmで鼻及び咽頭刺激があり、0.5ppm 1日3時間、1週間6日、12週間暴露で肺換気能の低下が認められている。
また、0.02ppmで人はオゾンの臭いを感ずる。
以上が実験室の研究結果であるが、現実に光化学オキシダントが発生し、かつ他の大気汚染物質が存在するときの住民に対する影響は次の如くである。
米国における研究によれば0.05ppm 4時間で植物被害がみられ、短時間0.1ppm以上で眼の刺激症状が出現し、喘息患者の発作頻度がピーク濃度0.13ppmで増加する。それは大体1時間平均濃度で、0.05~0.06ppmに相当する。また慢性呼吸器疾患の症状悪化が1時間平均濃度0.2~0.7ppmで出現するが、1時間平均濃度0.06ppmでは出現しないとの報告もある。運動選手(クロスカントリー競技)の記録が出発前1時間の平均濃度0.03~0.30ppmで統計学的に有意に低下する。
わが国での光化学オキシダントの地域住民への影響の報告は未だ充分ではない。光化学オキシダント濃度0.10ppm程度で農作物、植物への被害、眼の刺激症状の訴えが市民より自治体当局へ報告されている。オゾンの動物実験でみられたように運動時の影響は無視できないものがあり、運動中の学生の被害報告がしばしば行なわれている。昭和46年夏大阪府下南部地域において、いわゆる光化学スモッグ発生時に運動中の選手にはげしい眼および呼吸器刺激症状と臨床検査の異常所見を伴う患者が発生した。
その際のそれぞれの汚染物質の濃度は1時間値でオゾンが0.2ppm以上、二酸化いおうが0.05ppm以上、硫酸ミストが6~10μg/m3、二酸化窒素が0.05ppmであった。
(中略)
4 むすび(抄)
地域環境大気中の二酸化窒素、光化学オキシダントの年間を通じて常に維持されるべき濃度条件について、われわれは前述の測定方法と人の健康への影響の資料にもとづき次の通り提案する。
(中略)
(2)光化学オキシダントについては、短時間暴露の影響を防止するということに着目して1時間(平均)値0.06ppm以下であること。
(以下略)
(答申抜粋)
専門委員会報告で示された判定条件は、光化学反応により二次的に生成される汚染物質のうち光化学オキシダントに着目し、現在までに得られた知見にもとづき、かつ十分な安全を見込んだうえで総合的に判断されたものであり、適当と認められるので、人の健康に関する光化学オキシダントに係る環境基準(以下単に「環境基準」という)は、大気汚染防止行政の目標として別紙のように定めるべきものと考える。
(中略)
(別紙)光化学オキシダントに係る環境基準(案)
1.定義
光化学オキシダントとは、オゾン、PANおよびその同族体、過酸化物等、光化学反応により二次的に生成される酸化性物質であって、中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するもののうち二酸化窒素を除いた物質を総称する。
2.環境基準値
人の健康に関する光化学オキシダントに係る環境基準は次の条件について維持されるものとする。
1時間値が0.06ppm以下であること。
(以下略)
5.参考資料
・昭和47年6月20日・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会「窒素酸化物等に係る環境基準についての専門委員会報告」 【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・中央公害対策審議会「いおう酸化物に係る環境基準の改定ならびに窒素酸化物および光化学オキシダントに係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・環境庁大気保全局「窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会の提案した判定条件(人の健康を保護するうえで維持されるべき濃度条件)について」【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・環境庁大気保全局「窒素酸化物等に係る環境基準の設定について(資料)」【NIES保管ファイル】
・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会(1972)窒素酸化物等に係る環境基準に関する資料、大気汚染研究、7(3)、pp.33-155
○二酸化窒素
1.基準値
(当初)
1時間値の1日平均値が0.02ppm以下であること。
(現行)
1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
2.測定方法
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
3.設定経緯
(当初)
昭和47年6月20日・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会報告
昭和48年4月26日・中央公害対策審議会答申
昭和48年5月8日・環境庁告示第25号
(改定)
昭和53年3月20日・中央公害対策審議会大気部会二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会報告
昭和53年3月22日・中央公害対策審議会答申
昭和53年7月11日・環境庁告示第38号
4.基準値の根拠の概要
(当初設定時)
(専門委員会報告抜粋)
1 はしがき(抄)
ここにいう窒素酸化物等とは窒素酸化物(NOx)、光化学オキシダント、オゾン等をいうことにする。
窒素酸化物のうち、人および人の環境への影響を考えて注目すべきものは一酸化窒素と二酸化窒素である。窒素酸化物は土壌微生物の代謝等自然現象としても発生し、これまでの測定によれば二酸化窒素の自然大気中の濃度は0.003ppm程度以下である。またオゾンは成層圏よりの降下等によって地表面で0.05ppm程度以下存在する。
一酸化窒素(NO)は火力発電所、炉作業等のいわゆる固定発生源および自動車等のいわゆる移動発生源で高温に空気が熱せられることにより発生し、大気中に放出される。大気中で一酸化窒素は酸化され、二酸化窒素(NO2)が生成される。一方、窒素酸化物は上記発生源のほか化学工業における硝化工程等より直接大気中に放出される。上述の諸原因により、窒素酸化物は地域大気汚染及び局所大気汚染をひきおこす。わが国では窒素酸化物による大気汚染は最近10年間に急速に悪化している。
二酸化窒素と炭化水素ことに不飽和炭化水素が共存して、太陽光に照射されると、大気汚染物質が二次的に生成される。二酸化いおうがあると酸化され、硫酸ミストが生成される。この場合光化学反応による大気汚染はさらに悪化された状態となる。
現在一般的に一酸化窒素と二酸化窒素を総合して窒素酸化物と称しているが、窒素酸化物は人の健康への影響は勿論のこと、視程の障害、大気の着色(赤褐色)等を起すのである。
われわれが現在もっている人への影響に関する知識は主として二酸化窒素についてのものであり、一酸化窒素についての知識は未だ不充分であるので、ここでは二酸化窒素についての環境基準に関して勧告することにした。しかし一酸化窒素については、将来の研究の発展に伴い、一酸化窒素の環境基準の設定に必要な資料の充実に期待したい。
(中略)
3 人に対する影響(抄)
3-1 窒素酸化物の影響
一酸化窒素の影響については、その実験手法の困難さのためもあって、未だ充分な知見は得られていない。動物を極端に高濃度の一酸化窒素に暴露すると、中枢神経系の障害に原因が求められる麻痺、けいれんがみられる。また血球素との親和性が強く、試験管実験で一酸化炭素の数百倍であるとされており、一酸化窒素血球素およびメトヘモグロビンの生成が著しい高濃度の動物実験において認められている。人に対しては充分な知識はないが、将来の研究の発展によって、一酸化窒素は二酸化窒素よりも重視せねばならないことになるかもしれないと考える。
二酸化窒素は浮遊粒子状物質の存在の有無と関係なく、呼吸器深部に容易に到達する性質をもっている。一方浮遊粒子状物質と共存するとき、気道の気流抵抗の増加という生体反応でみると二酸化窒素と浮遊粒子状物質は相加作用をもつことが人の実験で確かめられている。
従って、二酸化窒素は古くより呼吸器刺激ガスとして知られ、その中毒は職業病として注目されてきた。動物実験でも、職業病でも高濃度の急性二酸化窒素中毒による死因は肺水腫等であり、慢性影響では慢性気管支炎、肺気腫の発病が憂慮されている。
人は二酸化窒素0.12ppmで臭いを感知する。この嗅覚値は二酸化いおうが共存する場合は低くなる。
二酸化窒素16.9ppm 10分間で人の気道の気流抵抗に有意の上昇がみられる。また気流抵抗の増加という反応でみると二酸化いおうと二酸化窒素は相加的作用が認められる。
動物実験では0.5ppm 4時間暴露で、肺細胞への影響がみられ、0.5ppm 数カ月間暴露で細気管支炎、肺気腫の発症が認められる。
動物実験では二酸化窒素に暴露すると肺炎桿菌、インフルエンザウイルスに対する感受性が高まること、生存期間の短縮、生菌排除能の減弱等が指摘されている。例えば0.5ppm 12カ月暴露で肺炎桿菌に感染させると致死率増大、生菌排除能減弱が認められている。
二酸化窒素10ppm 1日2時間暴露で、インフルエンザウイルスを感染させると間質性肺炎像がみられ、その病理学的所見は暴露日数の増加により高度となる。また0.5ppm 6カ月間暴露すると末梢気管支の上皮細胞の反応性増殖が認められ、肺気腫を軽度に認めることができる。これにインフルエンザウイルスを感染させると肺炎像は高度となり、かつ末梢気管支上皮細胞の腺腫様増殖がみられるようになる。この腺腫様増殖には注目せねばならない。
二酸化窒素が気管支喘息の発症の原因となる可能性が動物実験では示されている。また、一酸化炭素が共存するとき一酸化炭素血球素の生成が高まることが動物実験で報告されている。
地域住民に対し現在程度の濃度で急性または慢性の影響が、どの程度出現しているかの研究は少ない。
米国で二酸化いおう汚染が殆んどなく二酸化窒素及び硝酸塩汚染のある地区の学童のインフルエンザ感染率及び欠席率の上昇が報告されている。この場合の二酸化窒素濃度は0.062~0.109ppm、浮遊硝酸塩は3.8μg/m3又はそれ以上であった。チェコスロバキアで二酸化いおう汚染と二酸化窒素汚染の共存する地区の学童についての調査が行なわれている。
すでに述べたように二酸化窒素は二酸化いおうと相加作用があることに注目せねばならない。わが国の現状からみて二酸化窒素のみの汚染は例外的局所汚染にすぎない。多くの場合は両者は共存するのであるから、二酸化窒素の環境基準に関する検討は二酸化いおうの存在を無視して行なうことはできない。
わが国の慢性気管支炎の有症率の疫学調査は最近数年間に多くの知見を提供している。この知見の中でまず40才以上の成人の慢性気管支炎の有症率は、非大気汚染地区で約3%であることに注目することにする。東京都の男子自治体職員の慢性気管支炎の有症率(1968~1971)は、二酸化いおうの24時間平均濃度の年間平均値が0.05ppm以下の地区における持続的"せき"と"たん"(単純性慢性気管支炎)の有症率が5%以上を示しており、この場合の二酸化窒素の24時間平均濃度の年間平均値は0.042ppm以上であった。
また1970年より1971年の冬季に行われた全国6カ所の30才以上の家庭の主婦の持続性"せき"と"たん"の有症率調査によれば、有症率と二酸化窒素濃度は高い水準の関連性を示した。この時の二酸化窒素濃度は調査月間をはさむ3カ月にわたり各月8~72時間の測定が行われた。持続性"せき"と"たん"の有症率が4%をこえた地域の二酸化窒素濃度は1時間値の上述の測定期間中での平均濃度で0.029ppmであった。なお、成人女子の有症率は成人男子に比べ、低位にあることが広く認められている。
(中略)
4 むすび(抄)
地域環境大気中の二酸化窒素、光化学オキシダントの年間を通じて常に維持されるべき濃度条件について、われわれは前述の測定方法と人の健康への影響の資料にもとづき次の通り提案する。
(1)二酸化窒素については、その影響とくに慢性影響が憂慮されていること、さらに二酸化いおうとの相加作用があることに注目して1時間値の24時間平均値0.02ppm以下であること。
(以下略)
(答申抜粋)
この報告(専門委員会報告)においては、現在人への影響に関する知識は主として二酸化窒素についてのものであり、一酸化窒素についての知識は未だ不十分であるので、二酸化窒素についての判定条件が提案された。本答申においては、この判定条件は、現在までに得られた知見にもとづき、かつ十分な安全を見込んだうえで総合的に判断されたものであり、適当と認められるので、人の健康に関する二酸化窒素に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)は、大気汚染防止行政の目標として別紙のように定めるべきものと考える。
なお、一酸化窒素については今後の知見の進展をまって検討する。
(中略)
(別紙)二酸化窒素に係る環境基準(案)
1.環境基準値
人の健康に関する二酸化窒素に係る環境基準は、次の条件について維持されるものとする。
1時間値の1日平均値が0.02ppm以下であること。
(以下略)
(昭和53年・改定時)
(答申抜粋)
昭和52年3月28日付け環大企第59号諮問第49号で諮問のあった二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について、中央公害対策審議会は、大気部会に専門委員会を設置し、検討を行った結果、別添の報告がとりまとめられた。その概要と結論は、下記のとおりである。
本審議会は、これを審議した結果、内容を了承したので答申する。
政府においては、この報告を参考とし、現在の二酸化窒素に係る環境基準について、公害対策基本法第9条第3項の規定の趣旨にのっとり、適切な検討を加えられたい。
(中略)
本専門委員会は、現時点で利用可能な知見に基づいて判定条件を提示した。これを基礎に地域の人口集団の健康を保護するための指針を考察したい。
本専門委員会は、地域の人口集団に疾病やその前兆とみなされる影響が見い出されないだけでは十分ではないと考え、更にそれ以前の段階である健康な状態からの偏りについても留意した。指針はこうした健康影響に関する条件に対応するものであり、また現在わが国で見い出される大気汚染の状況を念頭に置いたものである。
しかし、現在の環境大気で見い出される程度の低濃度領域における生体影響に関する知見は、未だ十分満足し得るものは得られていない。このため環境大気中の二酸化窒素による汚染と人口集団の健康影響との関係の評価にあたっては、現時点の知見によって解明された部分を明確にすると共に、なお残された不確定さを考慮した上、これまでの生物医学の研究や経験を基礎に総合的に判断を行った。そして、この場合、人に関する利用可能な知見があればこれを重要視した。
さらに、大気汚染の人および人口集団の健康への影響は各種の段階の健康影響として観察され得るが、汚染と健康影響との関係は複雑である。二酸化窒素を含む環境大気の汚染の場合はすでに記した二酸化窒素の環境大気中の挙動の複雑さが更にこれに加わる。
大気汚染の暴露は、比較的に濃度の高い大気汚染物質への短時間暴露と低濃度の長期間暴露とに分けられる。そして暴露の作用は一般的に前者にあっては明白な健康への作用として観察されるが、後者にあっては個人について汚染物質との関係を明白に示すことは困難な事が多く、むしろ地域診断、すなわち疫学的研究によって人口集団の健康への作用によって判断されることが多い。この健康への作用は人の汚染物質への感受性に影響を及ぼしている諸要因が加わることによって多くの段階の健康影響として観察される。
そして急性の影響として観察されるものにも短時間暴露の結果としてみられるもの以外に長期間の低濃度暴露の作用の蓄積または潜在的な健康影響が何らかの原因によって表面化し、急性の反応として観察されることもあろう。こうした原因の一つの例には長期間低濃度暴露下での短時間の急性暴露もあろう。長期間暴露の影響として観察されるものにも長期間暴露によるもの以外に短時間の高濃度暴露のくり返しによるものと思われるものがある。これらの暴露条件の組合せの上で、大気汚染の人または人口集団への作用がみられるわけであるが、大気汚染の暴露条件の組合せと影響との関係を具体的かつ一般的に説明することは現在では困難であり、個々の事例ごとに判断せざるを得ない。
こうした観点にたって、環境大気中の二酸化窒素の人または人口集団への影響を判断する場合の基礎となる暴露条件を現在一般的に行われている短期暴露と長期暴露に分けて考察すれば次の通りである。
①短期暴露による影響
動物に対する短期暴露の実験室的研究から、呼吸器の感染抵抗性の減弱や肺の形態学的変化が観察され、二酸化窒素の影響は、短期暴露によっても起こると考えられる。こうした知見のうちで、肺の形態学的変化が0.5ppm 4時間の暴露で観察されたと報告されており、現在それ以下の濃度では、影響が報告されていない。
人の臭覚や、暗順応の変化など人の中枢神経系への影響が0.1ppm付近で、臭覚については直ちに、暗順応については、5分間の暴露で観察されたと報告されている。こうした影響が人の健康との関連でどのような意味を有しているかの評価は、現在、定着しているとは言えないが、0.1ppm付近の短時間暴露によって生体反応が観察されることを示している。
これまでに、二酸化硫黄など種々の汚染物質について行われた気道過敏性に対する影響についての研究は、低濃度の二酸化窒素については、十分ではなく、影響の評価の方法を含め更に検討を加える必要がある。しかし、すでにぜん息患者の気管支収縮剤に対する反応の増加が0.1ppmまたは0.2ppm 1時間暴露後に観察されている。しかし、健康人では類似の反応は5ppm 2時間暴露ではみられず、7.5ppm 2時間暴露で観察される。
肺機能のうち、気道抵抗の変化は、慢性気管支炎患者について1.6~2.0ppmの30回暴露で観察される。健康人については、2.5ppm 2時間暴露後に観察されているが、0.5ppm 30分暴露では、運動を負荷しても影響は観察されていない。これらの結果は、二酸化窒素の短期暴露による肺機能への影響の作用レベルを提示していると考えられる。
以上の動物実験、人の志願者に対する研究による短期暴露の影響を考察した場合、単一の知見のみから指針を直接的に導き出すことは困難である。したがって動物実験の結果から得られた0.5ppmを起点に人に対する知見を総合的に考察することが必要である。WHO(世界保健機関)の窒素酸化物に係る環境保健クライテリア専門家会議は二酸化窒素単独暴露の場合、動物実験の知見から0.5ppmを好ましくない影響の観察される最低レベルと考え、これに安全率を見込むことによって、公衆の健康保護に必要な暴露レベルは、1時間値0.10~0.17ppm以下であるとしている。
なお、現時点で短期暴露による影響を地域の人口集団について観察した報告はほとんどないため、次のような報告は、人口集団への短期暴露の影響を考察する場合に、参考として利用することができると思われる。すなわち、すでに記したように米国におけるTNT製造工場周辺の疫学調査で見出された学童の急性呼吸器疾患罹患率の増加が調査地域の1時間濃度の年間90%値に相当する0.15ppm以上の濃度の2~3時間くり返し暴露による可能性もあるとの指摘が、研究者自身によってなされている。また、英国の調査では料理のためにガスを使用している家庭と電気を使用している家庭の6~11歳の児童の呼吸器症状や疾患は、ガスを使用している家庭に高率に見られ、その原因としてガス燃焼から生じる窒素酸化物が考えられている。そして、他の報告によれば厨房でガスを使用した場合、室内の二酸化窒素濃度は0.05~0.15ppmである。
②長期暴露による影響
動物を用いた長期暴露の実験室的研究からは、呼吸器の感染抵抗性の減弱が0.5ppm 3ヶ月以上の暴露で観察されたと報告され、肺の形態学、生理学、生化学的変化は、0.3~0.5ppm程度から観察されたとする報告が多い。更に、最近、極く微小な肺の形態学的変化が血液の生化学的変化と共に、0.12ppm 35日暴露で認められたと報告されている。しかし、0.1ppm程度の長期暴露で、変化が見い出されないとする報告もあり、0.1ppm以下では変化が見い出されたとする報告はない。
動物を用いた長期暴露実験のこれまでの成果で、なお不十分な情報は、低濃度下の暴露期間の延長、他の汚染物質の共存および加齢などの諸要素である。しかし、他の実験、例えば、加齢による二酸化窒素の影響に対する修復反応の開始の遅れや肺の還元型グルタチオンの消長にみられる生化学的変化などの知見から判断した場合、暴露期間の延長は、影響の悪化を起こす可能性がある。こうした要素を考慮した場合、長期暴露の指針は、動物実験で見い出された濃度レベルを起点として、より低いレベルに求められるであろう。
一方、環境大気中の二酸化窒素濃度と地域の人口集団の健康影響に着目した疫学的調査については、次の通りである。
米国における疫学的調査によれば、環境大気中二酸化窒素濃度の年平均値0.06~0.08ppm以上の地域では年平均値0.03ppmの地域に比べ、学童の急性呼吸器疾患罹患率が高いことが報告されている。この調査でとり上げられた健康影響の指標は、呼吸器系疾患である。
わが国各地の成年を対象とした疫学的調査の結果から、環境大気中二酸化窒素濃度の年平均値0.02~0.03ppm以上の地域において、二酸化窒素濃度と持続性せき・たんの有症率との関連があると判断される。
しかし、米国でなされた類似の疫学的調査の持続性せき・たんを中心にして得られた慢性呼吸器症状の結果では環境大気中の二酸化窒素濃度の年平均値が、おおむね0.05ppm以上の地域とそれ以下の地域で、差は見い出されなかったとする報告もなされている。
これらの調査でとり上げられた健康影響の指標は、せき・たん等呼吸器症状の訴えを中心として集計されており、その一部には、呼吸器系疾患も含まれていると考えらえる。
わが国の小学生を対象とし、末梢気道の肺機能変化に着目した疫学的調査の結果から、二酸化窒素濃度の年平均値0.04ppm程度の都市において各調査日の特定の時間帯の二酸化窒素濃度(0.02~0.29ppm)と、一部の感受性の高いと思われる者の肺機能に個人正常調節機能範囲で相関を見い出している。
米国における疫学的研究とわが国の研究を対比した場合、米国における研究は、汚染の程度の異なる地域の呼吸器症状有症率の差を比較しているのに対し、わが国の持続性せき・たんに注目した疫学的研究は、多くの地域の調査結果を総合し、大気汚染のほとんどない都市の持続性せき・たんの有症率を参考とし、二酸化窒素濃度と有症率との関連の有無が認められる濃度を推定している点に相異があろう。更に、健康影響の指標も米国とわが国では異なる。すなわち持続性せき・たんをとらえている場合もわが国の調査の場合、"1年に3ヶ月以上持続性せき・たん"を指標として採用しているのに対し、米国の場合は、"1年に3ヶ月以上の持続性せき・たんが少なくとも2か年または、3か年にわたっているもの"あるいは、"持続性せき・たんに息切れが加わったもの"を指標として採用している場合が多く、健康指標としては、米国の方がより症状の重いものをとらえている。
また、他の汚染物質の濃度などの大気環境因子その他の環境因子にも差があり、わが国の疫学的研究の成果は米国のそれとは、独立して評価することが可能である。
疫学的研究の結果を考察する場合、動物実験の結果との対応を評価する必要がある。しかし、すでに記したように、疫学的研究と動物実験の結果を単純に対応させる事は困難である。わが国の疫学的研究において利用されている持続性せき・たん症状の発生を直接的に説明し得る動物実験の知見は少ない。しかし、多くの動物実験で証明された二酸化窒素の呼吸器に対する作用から判断して、大気中二酸化窒素が、他の汚染物質と共に人口集団のうちに見い出される持続性せき・たんの発生に一定の役割を果たしている可能性を否定することはできないと考える。
③指針の提案
以上の動物実験、人の志願者における研究、疫学的研究などの成果を総合的に判断し、本専門委員会は、地域の人口集団の健康を適切に保護することを考慮し、環境大気中の二酸化窒素濃度の指針として、次の値を参考とし得ると考えた。
短期暴露については1時間暴露として0.1~0.2ppm
長期暴露については、種々の汚染物質を含む大気汚染の条件下において、二酸化窒素を大気汚染の指標として着目した場合、年平均値として0.02~0.03ppm
(環境庁大気保全局長通知抜粋)
二酸化窒素に係る環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下と改定された。
この環境基準は、答申で示された判定条件及び指針が現在の時点における二酸化窒素の人の健康影響に関する最新・最善の科学的・専門的判断であり、また、それは公害対策基本法第9条第1項に規定する人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい水準を示すものと判断し、答申で提案された幅をもった指針に即して改定されたものである。
環境基準は、従前と同様に1時間値の1日平均値を用いたが、1日平均値の年間98%値と年平均値は高い関連性があり、1日平均値で定められた環境基準0.04~0.06ppmは年平均値0.02~0.03ppmにおおむね相当するものであるとともに、この環境基準を維持した場合は、短期の指針として示された1時間値0.1~0.2ppmをも高い確率で確保することができるものである。
(以下略)
5.参考資料
・昭和47年6月20日・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会「窒素酸化物等に係る環境基準についての専門委員会報告」 【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・中央公害対策審議会「いおう酸化物に係る環境基準の改定ならびに窒素酸化物および光化学オキシダントに係る環境基準の設定について(答申)」 【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・環境庁大気保全局「窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会の提案した判定条件(人の健康を保護するうえで維持されるべき濃度条件)について」【NIES保管ファイル】
・昭和48年4月26日・環境庁大気保全局「窒素酸化物等に係る環境基準の設定について(資料)」【NIES保管ファイル】
・昭和53年7月17日・環境庁大気保全局長「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(環大企第262号) https://www.env.go.jp/hourei/01/000062.html 【NIES保管ファイル】
・昭和53年・環境庁大気保全局「二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会の検討経過と主な議論の内容」 【NIES保管ファイル】
・中央公害対策審議会大気部会窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会(1972)窒素酸化物等に係る環境基準に関する資料、大気汚染研究、7(3)、pp.33-155
・環境庁大気保全局(1977)WHO窒素酸化物に関する環境保健クライテリア(草案)第7章の仮訳、官公庁公害専門資料、12(1)、pp.98-102
・中央公害対策審議会大気部会二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会(1978)二酸化窒素に係る判定条件等についての専門委員会報告、大気汚染学会誌、13(3-5)、pp.118-196 https://doi.org/10.11298/taiki1978.13.118
・中央公害対策審議会大気部会二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会(1978)二酸化窒素に係る判定条件等についての専門委員会報告について(付言)、大気汚染学会誌、13(3-5)、pp.197-199 https://doi.org/10.11298/taiki1978.13.197
・中央公害対策審議会(1978)二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について(答申)、大気汚染学会誌、13(3-5)、pp.112-117 https://doi.org/10.11298/taiki1978.13.112
○微小粒子状物質
1.基準値
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
(備考:微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。)
2.測定方法
微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法。
3.設定経緯
平成21年9月・中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会報告
平成21年9月3日・中央環境審議会答申
平成21年9月9日・環境省告示第33号
4.基準値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
5.環境基準の設定に当たっての指針値に関する検討(抄)
5.1.長期基準及び短期基準の必要性
微小粒子状物質リスク評価手法専門委員会報告において示されているように、微小粒子状物質等の大気汚染物質の濃度と人口集団の健康影響指標との関連において、長期曝露では、より低濃度で慢性影響が起こり、短期曝露では、より高濃度で急性影響が起こると考えられる場合には、それぞれの健康影響について環境基準を定めることが妥当であると考えられる。
微小粒子状物質については、長期曝露による健康影響と短期曝露による健康影響の両者が示されている。長期曝露による健康影響については、国内外で実施された10年以上の観察期間を持つコホート研究において、長期曝露に伴って発現する循環器疾患や呼吸器疾患の死亡リスクの上昇や症状、機能変化等の種々の健康影響の存在が示されている。短期曝露による健康影響についても、同様に微小粒子状物質への短期的な曝露に伴って発現すると考えられる健康影響が疫学知見や毒性学知見から示されている。
一般に、地域における微小粒子状物質の長期平均濃度(年平均値等)と短期平均濃度(日平均値等)の高濃度出現頻度の間には、経験的に高い相関がみられる。すなわち、長期平均濃度又は短期平均濃度の高濃度出現頻度に関する一方の基準を定めて、一方の平均濃度をその基準以下に低減する対策を図ることにより、もう一方の平均濃度に関しても低減効果が一定程度作用し、濃度分布全体が引き下げられることが期待される。しかしながら、発生源、地理的条件及び気象条件等の違いにより、同じ長期平均濃度でも、短期平均濃度の変動がない地域や大きい地域がある。図5.1(略)に概念的な説明を示したように、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期平均濃度に関する基準(以下「長期基準」という。)のみを設定した場合には、変動が大きい地域では高濃度出現時に健康への悪影響が観察される可能性がある(図の点線囲み部分(略))ので、曝露濃度分布のうち、高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期平均濃度に関する基準(以下「短期基準」という。)を長期基準と併せて設定することによって、微小粒子状物質の長期曝露及び短期曝露に関して地域の人口集団の健康の適切な保護が図られるものと考える。
(中略)
5.4.長期基準及び短期基準の指針値
5.4.1.主要な観点
次に、長期基準及び短期基準の指針値を導出するに当たっての主要な観点を示した。
○PM2.5の健康影響については閾値の有無を明らかにすることができない状況であり、そのため多くの疫学研究の対象地域における濃度範囲の下限付近やそれを下回る濃度領域における健康リスクの大きさは、一般人口集団及び感受性の高い者・脆弱性を有する者を含む集団においても明確ではない。
○我が国の人為起源由来粒子の影響がないと考えられる地域のPM2.5濃度測定結果は、年平均6~12μg/m3であり、この濃度領域においても閾値の有無は明らかではないことからいくらかの健康リスクが存在する可能性は否定できないが、その健康リスクの存在を明確にすることはできない。この点に関して、現時点までの疫学知見において存在することが示唆される健康リスクを低減する観点から指針値を導くことが適切である。
○疫学研究における濃度範囲全域をみた場合に、PM2.5への長期曝露による死亡及び死亡以外のエンドポイントに関するリスク上昇は相対リスク(10μg/m3上昇当たり)としてほとんどが1.5以下であり、多くは1.1~1.4程度であった。
○また、PM2.5への短期曝露による死亡及び死亡以外のエンドポイントに関するリスク上昇は超過リスク(10μg/m3上昇当たり)として、多くが数パーセントである。
○この相対リスクは他の曝露要因・リスクファクターと比較して必ずしも大きくはなく、集団を構成する個人の個別的な因果関係を推測できるものではないが、公衆衛生の観点から低減すべき健康リスクを示すものである。大気汚染による曝露は、人の嗜好や生活パターンによらずすべての者に健康影響を及ぼしうるものであって、避けることが困難である。
○公衆衛生の観点からは、大気汚染物質の影響に対してより敏感であり、また、より大きな健康リスクを生じうると考えられる感受性の高い者や脆弱性を有する者の健康影響にも慎重に配慮することが必要である。
○指針値の検討において、その根拠となる疫学研究で示されている微小粒子状物質の健康影響に関しては、想定されるメカニズムに関連する毒性学研究やその他の多くの疫学知見によって支持されるものであり、近年それらの知見は更に充実している。定量的評価の対象となりうる疫学知見は必ずしも多くはないが、それを支持する多くの毒性学知見と疫学知見が存在する。
○循環器疾患への影響に関しては、国内知見では関連が必ずしも明確ではない等日米の疫学研究の結果が異なる可能性も示されている。この相違については、日本と米国のリスクファクターの分布や疾病構造の違いによって結果に差が生じているものと解釈できる。短期曝露と死亡に関する疫学知見では国外知見と同じように急性心筋梗塞死亡リスク上昇がみられること、将来の日本の疾病構造やリスクファクターの分布が米国に近づく可能性もあることから、現時点で発現している健康リスクの大きさは異なるものの、国内外の疫学知見や種々の毒性学知見を踏まえ、国内でも同様の影響が生じる可能性がある。
○大気汚染の人及び人口集団の健康への影響は各種の段階の健康影響として観察されうるが、大気汚染物質と健康影響は両者とも多様性があり、その関係は複雑である。微小粒子状物質と共存大気汚染物質の濃度は相関する場合があるために、疫学知見において両者の影響を明確に分離することが困難な場合が多い。一方で、微小粒子状物質と共存大気汚染物質の影響を区別できる知見が存在する。これらの点について、微小粒子状物質濃度を低減することによって微小粒子状物質の健康リスクが低減するだけでなく、微小粒子状物質の原因物質である共存大気汚染物質の濃度の低減も期待できることから、これらの大気汚染物質の健康リスクを低減させる効果をもたらすことが期待される。
○コホート研究における曝露評価においては、調査期間のうちのどの期間を曝露期間とするかによっても、濃度-反応関係に関わる検討結果が変わりうる。しかしながら、現時点では、どの期間の曝露が最も健康影響と関係するかについて明らかとなっていない。また、長期曝露に関する国内外の疫学調査に関する多くの対象地域において、微小粒子状物質を含めた大気汚染物質濃度が低下傾向にある。このことが、長期曝露による健康影響が観察される濃度の評価を更に不確かにする。
○微小粒子状物質の濃度には測定誤差や推計誤差が含まれる。また、疫学研究の対象集団の曝露量には大気環境中濃度の空間分布や種々の曝露量を規定する要因に関わる変動が加わる。
なお、長期基準及び短期基準の指針値における微小粒子状物質とは、第1章(略)における検討を踏まえてPM2.5のことをいう。
5.4.2.長期基準の指針値
長期基準の知見の評価に基づき、国内外の長期曝露研究から一定の信頼性を持って健康リスクの上昇を検出することが可能となる濃度を、健康影響が観察される濃度水準として、次に示すように整理した。
国内の死亡に関するコホート研究からは、PM2.5濃度推計誤差も考慮して、20μg/m3を健康影響が観察される濃度水準とみなせる。
国外、特に米国における死亡に関するコホート研究からは、15~20μg/m3の濃度範囲を超える領域では健康影響が観察される。
国内の死亡以外の疫学研究からは25μg/m3を健康影響が観察される濃度水準であると考えられる。
国外の死亡以外の疫学研究からは15μg/m3を健康影響が観察される濃度水準であると考えられる。
コホート研究においては、調査観察期間のうちのどの期間を曝露期間とするかによっても、濃度-反応関係に関わる検討結果が変わりうる。各コホート研究で示されている濃度の経年変化の傾向等から推測すると、観察期間中の最も濃度が高い期間と最も濃度が低い期間の平均濃度を比較すると、曝露期間選択の違いによってPM2.5濃度としておおむね2~3μg/m3の変動幅を考慮する必要がある。
我が国における微小粒子状物質の健康影響が観察されるとみなせる濃度水準は20μg/m3であり、現時点では循環器疾患に対する健康リスクの状況は米国とは異なっているものの、人種差や微小粒子状物質の成分の差によって健康影響が異なることは明らかではない。また、微小粒子状物質の健康影響は、想定されるメカニズムに関連する多くの毒性学知見や疫学知見によって支持されるものであり、その知見の質や量から科学的信頼性は年々増している。したがって、国内知見を重視して考えると指針値を検討するための出発点となる濃度は20μg/m3であるが、知見が充実している国外知見から見いだされる健康影響が観察される濃度水準は15μg/m3であり、この濃度水準にも考慮すべきである。
その上で、主要な観点として前述した内容と健康影響が観察される濃度水準に加えて疫学知見に特有な不確実性が存在することにも考慮して総合的に評価した結果、長期基準として年平均値15μg/m3が最も妥当であると判断した。
5.4.3.短期基準の指針値
短期曝露による健康影響がみられた国内外の複数都市研究から導かれた98パーセンタイル値は39μg/m3を超えると考えられた。
日死亡、入院・受診、呼吸器症状や肺機能などに関して、有意な関係を示す単一都市研究における98パーセンタイル値の下限は30~35μg/m3の範囲と考えられた。
健康影響がみられた疫学研究における98パーセンタイル値は、年平均値15μg/m3に対応する国内のPM2.5測定値に基づく98パーセンタイル値の推定範囲に含まれていた。
以上のことから、長期基準の指針値である年平均値15μg/m3と併せて、日平均値35μg/m3を短期基準の指針値とすることが最も妥当であると判断した。
5.4.4.指針値の提案
本専門委員会は、現時点で収集可能な国内外の科学的知見から総合的に判断し、地域の人口集団の健康を適切に保護することを考慮して微小粒子状物質に係る環境基準設定に当たっての指針値としての環境濃度を次のように提案する。
長期基準の指針値 年平均値15μg/m3以下
短期基準の指針値 日平均値35μg/m3以下
長期基準及び短期基準の指針値としての環境濃度は、様々な重篤度の健康影響に関して、現時点では我が国における人口集団の健康の保護のために維持されることが望ましい水準である。
(中略)
7.まとめと今後の課題
7.1.まとめ(抄)
(中略)
微小粒子状物質に係る環境基準の達成状況の評価は、次の考え方を基本に行うことを提案する。
①長期基準に関する評価は、測定結果の年平均値を長期基準(年平均値)と比較する。
②短期基準に関する評価は、測定結果の1日平均値のうち年間98パーセンタイル値を代表値として選択して、これを短期基準(日平均値)と比較する。
(以下略)
5.参考資料
・平成21年9月・中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会「中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会報告」(その1) https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h2102/01-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月・中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会「中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会報告」(その2) https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h2102/01-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月・中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会「中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会報告」(その3) https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h2102/01-3.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成21年9月3日・中央環境審議会「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h2102/t07-h2102.pdf 【NIES保管ファイル】
④指針
○非メタン炭化水素
1.指針
光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。
2.測定方法
(標準測定法)大気中炭化水素をガスクロマトグラフにより分離し、非メタン炭化水素及びメタンの各々を水素炎イオン化検出器で検出する測定方式(直接法)
(その他の測定法)試料大気中の全炭化水素濃度を測定し、ガスクロマトグラフ分離によりメタン濃度を測定した上で非メタン炭化水素濃度を算出する測定方式(差量法)
3.設定経緯
昭和51年7月30日・中央公害対策審議会大気部会炭化水素に係る環境基準専門委員会報告
昭和51年8月13日・中央公害対策審議会答申
昭和51年8月17日・環境庁大気保全局長通知(環大企第220号)
4.指針値の根拠等の概要
(答申抜粋)
1.はじめに
本専門委員会は炭化水素が光化学オキシダント注)生成の主要な原因物質であることに着目して、考察を行った。したがって各種炭化水素それ自体の健康影響及び植物影響等は別個の課題である。
一般に炭化水素とは、炭素原子と水素原子からなる化合物を指す。これらは炭素原子のつながり方によって鎖式化合物と環式化合物に大別され、前者は炭素原子間の結合がすべて単結合である飽和炭化水素(パラフィン系炭化水素)と炭素骨格に二重結合、三重結合を含む不飽和炭化水素(オレフィン系炭化水素及びびアセチレン系炭化水素)に分類される。一方後者の環式化合物には、芳香族炭化水素とそれ以外の脂環族炭化水素(シクロパラフィン系炭化水素等)が含まれる。これらの他に、炭化水素分子の中にハロゲン、酸素、水酸基、アミノ基等を含む誘導体の系列がある。
大気中の炭化水素は多数の複雑な混合物であるが、そのうちメタンのバックグラウンド濃度は、1.0~1.5ppm程度とされ、全炭化水素量のかなりの部分を占めている。しかし、メタンの光化学反応性は無視出来るので、本専門委員会では水素炎イオン化検出器に応答する炭化水素のうち、メタンを除いた炭化水素(非メタン炭化水素)濃度と光化学オキシダント濃度との量的関係を明らかにする作業を中心に検討を行った。
注)大気中で、炭化水素の窒素酸化物の共存のもとで、光化学反応により、オゾン、二酸化窒素、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)及びその同族体、過酸化物等の酸化性物質、ホルムアルデヒド、アクロレイン等の還元性物質、エーロゾル、活性の強い遊離基等の生成が確認され、人体等に対する影響が注目されている。
これらの物質のうち、中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離する酸化性物質から、二酸化窒素を除いたものを光化学オキシダントと称し、これについては人の健康を保護する観点から環境基準が定められており、これは同時に大気中における光化学反応の程度を表わす有効な指標の一つである。なお、スモッグチャンバー実験等では光化学オキシダントを代表するものとしてその主成分であるオゾンを測定する場合が多い。
2.光化学大気汚染における炭化水素の関与-主として光化学オキシダントの生成について-(抄)
2-1 光化学反応過程の概要
光化学大気汚染とは大気中の炭化水素と窒素酸化物の混合系が太陽光(特に紫外線)照射を受け、光化学オキシダント等の2次生成物を生じたものである。環境大気中での光化学大気汚染の反応機構は極めて複雑であるが、これまでのスモッグチャンバー実験等の結果から、反応過程の特徴は以下の様に要約できる。
(a)一酸化窒素の二酸化窒素への酸化の促進
(b)炭化水素類の減少
(c)アルデヒド類の増加
(d)オゾンの増加
(e)二酸化窒素の減少
(f)ナイトレート類の増加
(g)エーロゾル類の増加
しかしながら環境大気中の光化学反応は、炭化水素、窒素酸化物の外に、共存する二酸化硫黄などの物質も関与し、反応系全体のプロセスは極めて複雑である。
大気中の炭化水素-窒素酸化物系光化学反応の進行の程度を表わす指標として、一般的には反応過程における、①二酸化窒素の最高濃度が出現するまでの時間、②二酸化窒素の生成速度、③オゾンの生成速度、④オゾンの最高濃度、⑤オゾンのドーセイジ(dosage)注)等が用いられており、②、③、④、⑤が高いほど、又、①が短いほど光化学反応性は大きいと評価される。
これらの指標の大きさは反応初期における炭化水素濃度及び窒素酸化物濃度、炭化水素と窒素酸化物の濃度比、炭化水素の種類、大気の温度、湿度、照射強度等によって左右されることは、内外の多くの研究によって知られているところである。
注)オゾンの濃度とその出現時間に着目した量である。
2-2 炭化水素類の光化学反応性の評価
個別の炭化水素の光化学反応性は、前節で述べたような所定の条件下においては、オゾン最高濃度、オゾンのドーセイジ、二酸化窒素最高濃度の出現時間、オゾン生成速度、二酸化窒素の生成速度等の指標で相対的に評価される。
炭化水素類のうち、光化学反応性の小さいものは炭素原子数3以下の飽和炭化水素、ベンゼン、アセチレン等であり、逆に反応性の大きいものは、オレフィン系炭化水素、アルキル置換基を多く含む芳香族炭化水素等である。
しかし、これまでの光化学反応性の評価は、ほぼ1日以内の反応を対象にしていることが多いので、更に長時間の反応を考えるときには、これまでの知見で十分とは言えない。比較的反応性の小さいとされている成分でも、1日以上の長時間の反応では無視し得なくなる可能性がある。反応性の大きい成分では概して消滅が早いけれども、反応性の小さい成分は比較的長時間、反応に関与することから、総合的にはそれらの影響が必ずしも小さくならないことが報告された。このように実際の大気の光化学反応性の評価は困難な要素が多く、今後なお検討すべき問題が残されていると言える。
非メタン炭化水素を対象として、光化学オキシダントとの関係を見たのは、メタンが全炭化水素のかなりの部分を占めるにもかかわらず、その光化学反応性が無視できるとの判断からである。一方上述の知見によれば、長時間の反応を考慮した場合、従来反応性が低いとされていた成分も無視し得ないこととなり、環境大気中に存在するメタン以外の光化学反応性の異なる多種類の炭化水素を包括的に、非メタン炭化水素として取り扱うことは妥当であると言える。
(中略)
5.非メタン炭化水素と光化学オキシダントの定量的な関係について(抄)
5-4 非メタン炭化水素と光化学オキシダントの定量的関係の評価
5-4-1 結果の概要
非メタン炭化水素と光化学オキシダントの定量的関係を把握するため前節までに述べたようなスモッグチャンバー実験、数値計算及び環境大気の測定結果の解析といった調査研究手法により得られた結果を光化学オキシダント0.1ppm程度における非メタン炭化水素との関係を中心に要約すると次のようになる。
(a)スモッグチャンバー実験の進展に応じて光化学反応の特性に推定し得るようになってきた。それによると、照射光及び温度がオゾン生成に大きく影響すること、また炭化水素の初期濃度、組成、窒素酸化物の初期濃度及び炭化水素と窒素酸化物の初期濃度比もオゾン生成の重要な要素であることが判明している。
スモッグチャンバー実験によって、オゾンの最大濃度を0.1ppm以下に抑制しうる炭化水素と窒素酸化物の初期濃度比、あるいは炭化水素初期濃度を推定した報告はあるが、直ちに環境大気に適用するには問題があると考えられる。
(b)移動用スモッグチャンバーを用いた照射実験から得られた結果は次のとおりである。第1に非メタン炭化水素が高濃度になるにつれて、オゾン最高濃度も高くなる傾向にあることであり、第2に非メタン炭化水素がおよそ0.4ppmC以下ではオゾン最高濃度0.1ppm以上は出現していないことである。
ただし、この結果についてはスモッグチャンバー実験と同様に環境大気中の反応に適用するには問題があると思われる。
(c)光化学反応をモデル化して数値計算を行い、炭化水素及び窒素酸化物の初期濃度とオゾンの生成濃度の関係を極く低濃度範囲まで推定する試みがあり、理論的には可能である。しかし計算に用いる素反応や反応速度定数等のパラメーターになお問題があって広く一致した結果は得られていない。
(d)環境測定データを上限曲線法により解析した結果から非メタン炭化水素と光化学オキシダントとの関係については次のように言える。すなわち、光化学オキシダントの0.06ppm注)に対応する非メタン炭化水素値の範囲を求めると0.20~0.31ppmCとなる。
5-4-2 今後に検討を要する問題点
現在までのところ、5-4-1の(a)、(b)、(c)の実験的な手法から得られた結果を直接利用するには極く低濃度域での知見が十分ではないことなどから適切ではないであろう。さらに環境大気を対象とする場合は、反応物質(自然及び人工)の発生形態及び反応過程における各成分の移流・拡散や日射強度、気温、湿度等の各条件が複雑に変化するので、これらの諸要素を併せて考察する必要がある。
一方、環境測定データを上限曲線法によって解析した結果から、光化学オキシダントの日最高1時間値に対応する非メタン炭化水素の限界値を定めることにも問題は多い。すなわち、非メタン炭化水素と光化学オキシダントの定量的関係の解明のために上限曲線法を適用することの本質的難点のほかに、検討に耐えうるだけの測定データ数が必要である。しかし、残念ながら我が国におる非メタン炭化水素測定はその緒についたばかりであり、測定データが乏しかったことも否めない。したがって、前述の環境測定データの解析はあくまで現時点で利用可能な限りの測定データを用いたものであり、今後、非メタン炭化水素の測定方法の改善を含めて測定体制が全国的に整備され、測定データが蓄積されることを期待したい。
上限曲線法の難点の一つとされる窒素酸化物濃度の影響は、排出規制の進展とともに検討を要する課題である。さらに非メタン炭化水素に関しても量及び成分組成の変化を考慮した解析が行われなければならない。このように今後の調査研究によって、炭化水素類の組成を含めて、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び光化学オキシダントの三者の定量的関係が環境大気と同じレベルで明らかにされなければならない。
注)光化学オキシダントの標準測定方法として、通常採用されている中性緩衝10%ヨウ化カリウム溶液を吸収液とする自動計測器による測定値は校正方法の相違により差が生ずる。そしてこれまで一般に採用されてきた等価溶液を用いる静的校正法による値は、より真値を表わし得ると判断される動的校正法に比して約30%高い値を示すことが判明したので、環境測定データの解析に当っては補正して評価することが適切であると判断される。したがって、光化学オキシダントに係る環境基準の1時間値0.06ppmは現行測定法(静的校正法)によれば、おおむね0.08ppmに相当する。
6.むすび
本専門委員会は光化学オキシダントの生成を防止するために必要な環境大気中の炭化水素の濃度レベルについて考察してきたが、その結果をまとめると次のごとくである。
光化学大気汚染は大気中の炭化水素と窒素酸化物の混合系に太陽光が照射して、光化学オキシダント等の生成物質を生じたものであるが、その生成は反応物質の濃度レベルのみならず、気象条件に大きく依存している注)。
注)高濃度の光化学オキシダントの発生しやすい気象条件として、我が国において現在までに報告されたところでは、地域によって多少の差はあるものの、気温20℃以上(日中)、風速5m/sec以下、日射量40カロリー/cm2/hrが3時間以上(9時から15時)というのが一つの目安とされており季節でいえばおおむね4月から9月頃までの期間に当たる。
炭化水素はその種類により光化学反応性が異なることが知られているが、反応性の評価の方法にはいまだ問題が残されていることや、炭化水素の種類毎に基準を設定することは現実的でないことなどの理由により、光化学オキシダントとの濃度レベルの対応関係を見るためには、炭化水素を非メタン炭化水素として包括的に考えることが適当であると判断された。
そこで、光化学オキシダントと非メタン炭化水素の定量的関係を得るため、現在までに様々な手法によって調査研究された結果を評価した。
スモッグチャンバー実験等の実験室的研究は光化学反応機構や反応物質と生成物質の関係については有用な知見を提供するが、環境大気中での複雑な現象を定量的に説明するためにはいまだ種々の点で問題を残している。したがって、現段階では環境測定を解析した結果を重視して考えた。
環境測定データの解析は、いわゆる上限曲線法により光化学オキシダントと非メタン炭化水素の関係を見たものであるが必ずしも有効なデータ数がそろっていたとは言えない。しかし、南関東地域、東京都及び大阪府の環境測定データを主として解析した結果、広域的な光化学大気汚染発生問題を含めて、都市地域についてはある程度の定量的な関係は示し得たと考える。また、光化学オキシダント生成に及ぼす炭化水素以外の窒素酸化物の役割も定量的に解明すべく環境測定データの解析を試みたが、現在のところは困難であると判断せざるをえない。
このような上限曲線法による特定地域の解析結果を全国に拡大適用することは問題が残されているが、当面、この結果を利用することにした。
本専門委員会は現時点までに得られた資料を総合的に判断して、光化学オキシダント生成防止のための必要条件としての環境大気中の非メタン炭化水素濃度レベルの指針としては、次のような数値が適当であると考える。光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。
なお、上記の数値は前述のような種々の状況下で得られたものである。したがって、本報告書で指摘された課題を含めて、光化学大気汚染対策の基本となる諸問題については、更に、今後調査研究を進め新しい知見を求める必要がある。
(通知抜粋)
2 大気中炭化水素濃度の指針が環境基準ではなく、指針とされたのは、この指針が光化学オキシダントの環境基準を達成するうえでの炭化水素排出抑制にあたつての行政上の目標であり、炭化水素それ自身の健康影響に基づいたものでない点で、従来の大気汚染に係る環境基準とは性格が異なるため、別の用語を採用されたものである。
しかしながら、指針も行政上の目標である点は、環境基準と同一であること、また、環境基準と同様、規制基準ではないことに留意されたい。
3 大気中炭化水素濃度の指針が幅をもつて設定されたのは、環境大気中での光化学オキシダント生成については、炭化水素のほか気象要素等多くの要因が関係する等により、指針値を一つの値として特定することは無理があると判断されたことによるものであること。
5.参考資料
・中央公害対策審議会大気部会炭化水素に係る環境基準専門委員会(1977)光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針に関する報告(参考資料)、大気汚染研究、12(5-6)、pp.274-374 https://doi.org/10.11298/taiki1966.12.274
・中央公害対策審議会(1977)光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(答申)、大気汚染研究、12(5-6)、pp.261-274 https://doi.org/10.11298/taiki1966.12.261
・昭和51年8月17日・環境庁大気保全局長「「大気中鉛の健康影響について及び光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について(中央公害対策審議会答申)」について」(環大企第220号) https://www.env.go.jp/hourei/04/000104.html 【NIES保管ファイル】
・平成22年3月・環境省水・大気環境局「環境大気常時監視マニュアル第6版」(資料2)環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について(昭和52年3月29日環大企第61号) https://www.env.go.jp/air/osen/manual_6th/mats.pdf 【NIES保管ファイル】
(3)有害大気汚染物質に係る環境基準
①設定の考え方
(平成8年1月30日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中間答申)」より)(抜粋)
4.環境目標値設定の考え方
国は、有害大気汚染物質のうち物質の有害性に関する知見や我が国の大気環境における検出状況から健康リスクが高いと評価される物質については、定量的な評価結果に基づいて環境目標値を定めることが適当である。
なお、有害大気汚染物質には、ある曝露量以下では影響が起こらないとされる物質、すなわち閾値がある物質と、微量であってもがんを発生させる可能性が否定できない物質、すなわち閾値がない物質の2つがあるが、環境目標値の設定に当たっては、これらの性質に応じて設定することが必要である。
閾値がある物質については、物質の有害性に関する各種の知見から人に対して影響を起こさない最大の量(最大無毒性量)を求め、それに基づいて環境目標値を定めることが適切である。
これに対し、閾値のない物質については、曝露量から予測される健康リスクが十分低い場合には実質的には安全とみなすことができるという考え方に基づいてリスクレベルを設定し、そのレベルに相当する環境目標値を定めることが適切である。この場合、国内外で検討・評価・活用されている10-5の生涯リスクレベル等を参考にし、専門家を含む関係者の意見を広く聴いて、目標とすべきリスクレベルを定めることが必要である。
また、このような有害大気汚染物質の環境目標値については、閾値のない物質が多くあること、低濃度長期曝露による健康影響が懸念される物質であることなど、従来の環境基準設定物質とは異なる性質を有する物質であることに留意しつつ、環境基本法に基づく環境基準とすることを含め、その設定を検討する必要がある。
(参考資料)
・平成8年1月30日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中間答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/int0801.pdf 【NIES保管ファイル】
(平成8年10月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」より)(抜粋)
1.閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて(抄)
(中略)
閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについては、別添1の健康リスク総合専門委員会報告のとおり、現段階においては、生涯リスクレベル10-5(10万分の1)を当面の目標に、有害大気汚染物質対策に着手していくことが適当である。
ただし、この目標とすべきリスクレベルは、そのレベルまでの有害大気汚染物質による大気汚染を容認することを意味するものではなく、閾値のない物質については、環境基本法の理念にのっとり、環境への負荷をできる限り低減することを旨として対策を講じていくべきことを特に強調する。
(別添1)閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて(中央環境審議会大気部会健康リスク総合専門委員会報告)(抄)
5.目標とすべきリスクレベルについて
閾値のない物質について目標とすべきリスクレベルを設定するに当たっては、社会的受容可能性等を考慮して総合的に判断されるべきものと考えられる。
この際、有害大気汚染物質対策の推進に当たっては、対策が手遅れにならないよう健康影響の未然防止に重点を置いていること、科学的知見の充実を図りながら可能な対策から着実に実施していくことを重視していること等をも併せて留意する必要がある。
また、目標とすべきリスクレベルを踏まえて設定される環境基準は、「維持されることが望ましい」基準であり、かつ、「政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保されるように努めなければならない」と規定されているように、行政施策の達成目標となるものである。このような法的位置付けも踏まえて目標とすべきリスクレベルを考える必要がある。
さらに、ここで考えるリスクレベルは政策目標(環境基準)の基礎、すなわち個々の物質の健康リスクを公平に評価するための共通の物差しとなるべきものであり、排出等の抑制のための技術的可能性等をも勘案して個別物質毎に決定される排出抑制基準値や自主管理目標値とは異なるものである。したがって、リスクレベルは個別物質毎に考える必要はなく、一律に定めてよいと考えられる。
なお、このようなリスクレベルは、有害大気汚染物質のうち健康リスクが高いと考えられるため優先的に対策に取り組むべき物質を選定する際に、健康リスクが高いかどうかを判断する基準にも利用することができる。
以上の考え方を踏まえ、大気環境分野で用いられているリスクレベルの国際的動向、水質保全の分野ですでに採用されているリスクレベル、自然災害等のリスク、関係者から聴取した意見等を勘案すれば、10-6から10-5を目標にすることが考えられるが、現段階においては、生涯リスクレベル10-5(10万分の1)を当面の目標に、有害大気汚染物質対策に着手していくことが適当と考えられる。
このリスクレベルを目標として施策を展開していくに当たっては、常に新しい知見を充実させながら健康影響の未然防止の立場に立って対処することが重要であり。また、国民、事業者等の関係者がリスクに対する理解を深めていくことができるよう各種の情報が適切に提供されることも重要である。
なお、有害大気汚染物質については、次世代への影響や生態系への影響など現在の科学的知見では十分な評価が困難な問題もあり、これらの課題についても調査研究を進めることが望まれる。
人の健康に対するリスクは低い方が望ましいことは当然のことであり、今回低減する目標とすべきリスクレベルは、あくまでそのリスクレベルを超えるような汚染が生じている有害大気汚染物質について、その低減を図るに当たり、当面目標とすべきレベルを明らかにしたものである。したがって、現在、目標とすべきリスクレベルの汚染が生じていない物質について、そのレベルまで汚染が進むことを容認するものではなく、継続的な環境負荷低減の努力を行うことが望まれる。
特に、今回提言するリスクレベルは各物質一律のリスクレベルであり、多数の有害大気汚染物質全体としてみた場合は、複数の物質に曝露することによってより高いリスクが生ずるおそれがあるため、社会の各主体は、個々の物質について自主的に可能な限りの環境負荷低減の努力を行い、有害大気汚染物質総体としてのリスクを低減することが望まれる。
このように閾値のない物質については、環境基本法の理念にのっとり、環境への負荷をできる限り低減することを旨として対策を講じていくべきことを特に強調したい。
(資料1)我が国における事故等による死亡数、死亡率(略)
(資料2)大気環境分野におけるリスクレベル(略)
(資料3)我が国における農薬・食品添加物の分野のリスクレベル、水質・飲料水の分野におけるリスクレベル、その他の分野のリスクレベルの例(略)
(資料4)専門家を含む関係者からのヒアリング結果の要点(略)
(参考資料)
・平成8年10月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成8年10月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」(別添1)閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて(中央環境審議会大気部会健康リスク総合専門委員会報告) https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/02-1.pdf 【NIES保管ファイル】
②環境基準項目及び基準値(一覧)並びに評価方法(令和3年10月7日現在)
(環境基準項目及び基準値(一覧))
| 物質 | 環境上の条件(基準値) | 告示日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 | 平成9年2月4日 | |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.13mg/m3以下であること。 | 平成30年11月19日 | 改定 |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 | 平成9年2月4日 | |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 | 平成13年4月20日 | |
| ダイオキシン類※ | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 | 平成11年12月27日 |
※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設定。
(注)上記環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
(評価方法)
(常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
Ⅳ 有害大気汚染物質等に係る常時監視(抄)
(中略)
3.測定頻度等
長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質等の常時監視においては、原則として年平均濃度を求めるものとする。
有害大気汚染物質等の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季節変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、これらの変動が適切に平均化されるよう、原則として月1回以上の頻度で測定を実施するものとする。その際、連続24時間のサンプリングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さらに、サンプリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化することが望ましい。
サンプリング方法及び対象物質によっては、連続24時間のサンプリングによると破過する場合があるが、この場合はサンプリングを数回に分けて連続して行うものとする。
(中略)
6.測定値の取扱い及び評価
(1)評価の対象としない測定値等
Ⅱの6.(1)ア及びイの例による。
(2)年平均値の算出
測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用いるものとし、環境基準値が設定されている物質については基準値との比較によってその評価を行うものとする。測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の1/2として年平均値の算出に用いるものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合又は欠測が多く測定値の得られた季節が偏っている場合等は、結果の評価に際し留意する必要がある。
(3)異常値の取扱い
これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリング時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとする。
なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定を行うことが望ましい。
(参考資料)
・平成28年9月26日・環境省水・大気環境局長「「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正等について」(環水大大発第1609263号・環水大自発第1609261号)別添 https://www.env.go.jp/air/osen/law22_kijun/hannei_2.pdf 【NIES保管ファイル】
(大気のダイオキシン類の常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
4.測定頻度等
長期曝露による健康リスクが懸念されているダイオキシン類の大気汚染状況の常時監視においては、原則として年平均濃度を求めるものとする。
ダイオキシン類の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季節変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、季節変動が適切に平均化されるよう、季節毎に測定を実施することが望ましいが、少なくとも夏期及び冬期に測定を実施するものとする。その際、原則として年度をとおして1週間サンプリング手法により測定することが望ましい。
(中略)
7.測定値の取扱い及び評価(抄)
(中略)
(2)年平均値の算出
測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用いるものとし、環境基準値との比較によってその評価を行うものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合等は、結果の評価に際して留意する必要がある。
(3)異常値の取扱い
これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリング時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとする。
なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定を行うことが望ましい。
(参考資料)
・平成13年5月21日・環境省環境管理局長「ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づく大気のダイオキシン類による汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」(環管総第145号)(最終改正:平成17年6月29日) 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの基準値及び設定根拠
○ベンゼン
1.基準値
1年平均値が0.003mg/m3以下であること
2.測定方法
キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
3.設定経緯
平成8年9月・ベンゼンに係る環境基準専門委員会報告
平成8年10月18日・中央環境審議会答申
平成9年2月4日・環境庁告示第4号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・常温・常圧で無色透明な液体、特異な芳香臭を持つ可燃性物質
・融点:5.5℃、沸点:80.1℃、比重:0.87865(20℃)
・蒸気圧:100(20℃)(気中飽和濃度(25℃):120,000ppm)
・溶解度:水にわずかに溶ける(25℃で1.8g/L)、油に易溶
・換算係数:1 ppm=3.2mg/m3(20℃)、1 mg/m3=0.31ppm(25℃)
(2)生産量等
(平成6年)
・生産量:3,620,241t(純ベンゼン)、529,988t(粗製ベンゼン)
・輸出量:172,000t
・輸入量:54,668t
(3)用途
・合成原料、溶剤、抽出剤等広範な用途。ガソリン中にも含まれる。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ1
・U.S. EPA グループA
・ACGIH グループA1
・日本産業衛生学会 第1群
(2)大気に関する基準
・WHO欧州地域事務局ガイドライン ユニットリスク4×10-6(1μg/m3)
・U.S. EPA ユニットリスク8.1×10-6(1μg/m3)
・オランダの基準 target value 1μg/m3, limit value 10μg/m3(guide value 5μg/m3)
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 10ppm(32mg/m3)(改定作業中)
・ACGIH TLV-TWA 0.3ppm (0.96mg/m3)(提案中)
6.環境中における検出状況(設定時)
(昭和55年度以降の調査結果)
<一般環境>
(全体)109地点(72市町村)で<0.64~34.4μg/m3(幾何平均値5.3μg/m3、算術平均値7.3μg/m3)
(人口100万人~)19地点(8市町村)で2.5~24.1μg/m3(幾何平均値7.3μg/m3、算術平均値9.0μg/m3)
(人口30~100万人)16地点(10市町村)で2.1~34.4μg/m3(幾何平均値6.3μg/m3、算術平均値8.3μg/m3)
(人口10~30万人)24地点(11市町村)で1.3~25.3μg/m3(幾何平均値6.3μg/m3、算術平均値8.3μg/m3)
(人口3~10万人)36地点(29市町村)で<0.64~21.8μg/m3(幾何平均値4.6μg/m3、算術平均値6.8μg/m3)
(人口~3万人)14地点(14市町村)で1.5~6.5μg/m3(幾何平均値2.8μg/m3、算術平均値3.3μg/m3)
<ベンゼンを取り扱う工場・事業場周辺>
・18地点で4.0~23.0μg/m3(幾何平均値9.8μg/m3、算術平均値11.4μg/m3)
<都市部の道路沿道>
・4.2~34.5μg/m3(算術平均値14.8μg/m3)
7.基準値の根拠の概要
(専門委員会報告抜粋)
近年の大気環境中のベンゼン等の有機塩素化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が収集されているが、なお不明確な点があり、今後の解明を待つべき課題が少なくない。ここでは、現在までに得られた上述の健康影響に係る知見から本専門委員会で行った評価と提案を述べる。
(1)発がん性について
ベンゼンには、急性毒性、慢性毒性に加えて発がん性がある。発がん性については、ヒトにおいて急性骨髄性白血病に関する十分な疫学的証拠がある。その他、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫等を起こす可能性がある。
(2)閾値の有無について
動物実験及びin vitro(生体外における)の実験等より総合的に判断すると、ベンゼンには遺伝子障害性があり、染色体異常を引き起こす可能性がある。このため、発がん性に関する定量的評価にあたっては微量であってもがんを発生させる可能性が否定できず、閾値がないと考えることが適当な物質(閾値のない物質)として取り扱うことが妥当である。
(3)量-反応関係について
ベンゼンの発がん性について、量-反応関係を明らかにした疫学研究の代表的なものとして、Pliofilm製造工場労働者に関する研究が挙げられる。この研究対象者の曝露量の推定には確定的なものがなく、種々の評価が試みられている(CrumpとAllen 1984、Rinskyら 1987、Paustenbachら 1992)。いずれも一定の評価を得て妥当なものであるが、Rinskyらによる曝露推定は、全体的に調査対象者の曝露を過小評価していた可能性がある。
(4)数理モデルについて
ベンゼンに関する疫学データは、過去のヒトにおける曝露データであることから、個々の曝露の形態は様々で、たとえ累積曝露が同じ程度であっても曝露濃度や曝露期間が異なっている。動物実験におけるデータの精度・均一性と異なるこのようなデータの性質を考えると、低濃度への外挿にあたっては平均曝露量と相対リスクを用いる数理モデルを使用することが望ましい。従って、ここでは複雑な関数を用いるモデルによる評価は必ずしも妥当ではなく、家庭の少ない単純なモデルで、WHO欧州地域事務局でも採用されている平均相対リスクモデル(average relative risk model)の使用が適切である。
(5)指針の提案について
ベンゼンの発がん性についての量-反応関係及び数理モデルの評価結果から、リスク評価に用いたデータ等の不確実性を考慮した上で、生涯曝露に関するユニットリスクとして3×10-6~7×10-6の範囲で提案する。
(以下略)
(答申抜粋)
1.閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて
本年1月の中央環境審議会中間答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」では、「閾値(その曝露量以下では影響が起こらないとされる値)がある物質については、物質の有害性に関する各種の知見から人に対して影響を起こさない最大の量(最大無毒性量)を求め、それに基づいて環境目標値を定めることが適切である。これに対し、閾値がない物質については、曝露量から予測される健康リスクが十分低い場合には実質的には安全とみなすことができるという考え方に基づいてリスクレベルを設定し、そのレベルに相当する環境目標値を定めることが適切である。」としている。
閾値のない物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについては、別添1(略)の健康リスク総合専門委員会報告のとおり、現段階においては、生涯リスクレベル10-5(10万分の1)を当面の目標に、有害大気汚染物質対策に着手していくことが適当である。
ただし、この目標とすべきリスクレベルは、そのレベルまでの有害大気汚染物質による大気汚染を容認することを意味するものではなく、閾値のない物質については、環境基本法の理念にのっとり、環境への負荷をできる限り低減することを旨として対策を講じていくべきことを特に強調する。
(中略)
3.ベンゼンに係る環境基準について
ベンゼンに係る大気環境基準の設定の基礎となるベンゼンに係るユニットリスク(汚染物質が1μg/m3含まれている大気を一生涯を通じて人が吸入した場合のがんの発生確率の増加分)については、別添3(略)の環境基準専門委員会報告において3×10-6~7×10-6とされたところである。
このユニットリスクと上記1.において適当と認めたリスクレベル(10-5)に基づき、ベンゼンに係る大気環境基準の設定に当たっての指針となる値を求めると、1~3μg/m3になる。
一方、我が国におけるベンゼンの大気環境濃度は、これまでの測定結果によると、一般環境では検出限界(0.64μg/m3)未満~34.4μg/m3、その平均値(幾何平均値)は5.3μg/m3、工場等の周辺環境では4.0~23.0μg/m3 、その平均値(同上)は9.8μg/m3とのデータが示されている。このように、ベンゼンの現状の大気環境濃度は、上述の指針となる値の幅のレベルよりも全体として高い濃度レベルにあると考えられる。
このようなベンゼンに係る大気環境の現状をも踏まえると、ベンゼンに係る大気環境基準の設定に当たっての指針値は、ベンゼンによる現状の大気汚染を着実に改善していく見地から、年平均値として3μg/m3(0.003 mg/m3)以下とし、これを当面の目標にベンゼンの大気中への排出抑制対策を講じていくことが適当である。
(以下略)
8.参考資料
・平成8年9月・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会「ベンゼンに係る環境基準専門委員会報告」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/02-3.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成8年10月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○トリクロロエチレン
1.基準値
(当初)1年平均値が0.2mg/m3以下であること
(現行)1年平均値が0.13mg/m3以下であること
2.測定方法
キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
3.設定経緯
(当初)
平成8年12月9日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会報告
平成8年12月18日・中央環境審議会答申
平成9年2月4日・環境庁告示第4号
(改定)
平成30年9月・中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告
平成30年9月20日・中央環境審議会答申
平成30年11月19日・環境省告示第100号
4.基礎情報(改定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・クロロホルム様臭を有する揮発性の無色透明の液体で、不燃性、水に難溶であり、アルコール、エーテルその他の有機溶剤と混和
・比重:1.4642(20/4℃)
・融点:-84.8℃
・沸点:86.9℃
・蒸気圧:100Pa(39℃)
・蒸気密度:4.53(空気=1)
・溶解度:水にわずかに可溶(25℃で1.1g/L)、各種有機溶剤に易溶
・分配係数:logPow 2.61
・換算係数:1ppm=5.38 mg/m3(25℃)、1mg/m3=0.186ppm(25℃)
(2)生産量等
(平成28年度)
・製造・輸入量:43,071t
(3)用途
・工業用洗浄剤(金属脱脂洗浄等)、反応溶剤(ゴム等)、化学品原料等
5.毒性情報及び各種基準値(改定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC(2014) グループ1
・ACGIH(2007) A2
・日本産業衛生学会(2016) 第1群
(2)大気に関する基準
・トリクロロエチレンに関して、我が国の大気環境基準と同様の基準を設定している国は、米国や欧州で存在しない。
・WHO欧州事務局や欧州事務局やU.S. EPAは定量的なリスク評価を行っているもの、ユニットリスクや参照濃度を示しているのみである。
(3)職業曝露に関する基準
・ACGIH TLV-TWA(2007) 10ppm(54mg/m3)
・ACGIH TLV-STEL(2007) 25ppm(135mg/m3)
・日本産業衛生学会許容濃度(1998) 25ppm(135mg/m3)
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度(2009) 10ppm(54mg/m3)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(改定時)
届出排出量
(平成24年度)大気:3,079t、公共用水域:3t、土壌:0t、埋立:0t、届出移動量:1,645t
(平成25年度)大気:3,037t、公共用水域:2t、土壌:0t、埋立:0t、届出移動量:1,604t
(平成26年度)大気:2,830t、公共用水域:2t、土壌:0t、埋立:0t、届出移動量:1,554t
(平成27年度)大気:2,665t、公共用水域:2t、土壌:0t、埋立:0t、届出移動量:1,446t
(平成28年度)大気:2,536t、公共用水域:2t、土壌:0t、埋立:0t、届出移動量:1,399t
7.環境中における検出状況(改定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成24年度)地点数:367、検体数:4,404、平均:0.50、最小:0.010、最大:10
(平成25年度)地点数:369、検体数:4,436、平均:0.53、最小:0.0059、最大:16
(平成26年度)地点数:364、検体数:4,368、平均:0.51、最小:0.0078、最大:20
(平成27年度)地点数:353、検体数:4,236、平均:0.48、最小:0.0060、最大:11
(平成28年度)地点数:356、検体数:4,273、平均:0.40、最小:0.0060、最大:11
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成28年度)
(一般環境)地点数:254、平均:0.37、最小:0.0060、最大:5.0
(固定発生源周辺)地点数:39、平均:0.64、最小:0.011、最大:11
(沿道)地点数:63、平均:0.37、最小:0.0080、最大:3.1
(沿道かつ固定発生源周辺)地点数:0、平均:‐、最小:‐、最大:‐
(全体)地点数:356、平均:0.40、最小:0.0060、最大:11
8.基準値の根拠の概要
(当初設定時)(専門委員会報告抜粋)
近年の大気環境中のトリクロロエチレン等の有機化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が収集されているが、なお不明確な点があり、今後の解明を待つべき課題が少なくない。ここでは、現在までに得られた上述の健康影響に係る知見から本専門委員会で行った評価と提案を述べる。
(1)発がん性について
疫学的研究にはトリクロロエチレンの発がん性を肯定するもの、否定するものが相混じり、現時点ではヒトに対するトリクロロエチレンの発がん性に関する疫学的証拠は必ずしも十分とはいえないと考えられることから、今後とも発がん性に関する疫学研究に注目する必要がある。一方、動物を用いたトリクロロエチレンの発がん性実験ではB6C3F1マウスに肝がんの発生を促すということについての証拠は十分であるが、ラットに肝がんを起こすという証拠はなく、その毒性に種差(マウスとラット)が存在することが明らかとなっている。
(2)発がん性以外の毒性について
トリクロロエチレン曝露により現れる一般毒性の主なものは、急性毒性としては皮膚・粘膜に対する刺激作用と麻酔作用(中枢神経抑制作用)である。
慢性毒性としては、高濃度において肝・腎障害が認められることがある。比較的低濃度の長期間曝露では神経系への影響として現われることが一般的である。
(3)閾値の有無について
トリクロロエチレンの発がん性はgenotoxic(initiator)というよりもepigenetic(promoter)な機構によるもので、細胞毒性を示すほどの大量かつ長期間の投与によって初めて発現すると考えられる。したがって、ヒトに対して発がん性があるとしても、トリクロロエチレンには遺伝子障害性がないと思われることから、その発がん性には閾値があるとして取り扱うことが妥当である。
(4)量-反応アセスメントについて
トリクロロエチレンの毒性には代謝経路や代謝活性に関して種差があることや、低濃度のトリクロロエチレンによる健康影響は主として神経系の影響であること等から、ヒトの神経機能に対する慢性影響を用いて量-反応アセスメントを行うことが適当と考えられる。
AhlmarkとForssman及びLiuらの報告、ACGIHが評価した文献、WHOが行った主要な文献の評価、WHO欧州地域事務局の評価を総合的に判断すると、LOAELに相当する気中濃度は200mg/m3(37ppm)前後の濃度域に存在すると考えることが妥当である。
不確実係数としては、労働環境で得られたデータを一般環境に外挿すること、NOAELではなくLOAELを用いること等を考慮して、総合的な係数として1,000を用いることが適当と考える。
(5)曝露アセスメントについて
トリクロロエチレンの物理・化学的性質、排出経路や、これまでの環境中の濃度の調査結果を考慮すると、トリクロロエチレンの曝露はほとんどが空気由来であり、特に、固定発生源の周辺環境での曝露が問題になると考えられる。
(6)指針としての環境濃度の提案について
低濃度長期曝露による健康影響を未然に防止する観点から、トリクロロエチレンの長期曝露に係る指針として年平均値0.2mg/m3(2×102μg/m3)以下の環境濃度を提案する。
(平成30年・改定時)(専門委員会報告抜粋)
(4)量-反応関係の評価
発がん性及び発がん性以外の健康影響に関する量-反応関係について、曝露レベルや影響のみられた気中濃度等の情報が得られた疫学知見を基に検討を行った。
発がん性(腎臓がんのリスク増加)については、量-反応関係における情報が不十分な知見や、量-反応関係の推定を行うことが適切でない知見であった。労働者を対象とした神経系の影響(自覚的神経症状)に関する複数の疫学研究では、種々の自覚的神経症状(頭痛、めまい、酩酊感、疲労感等)の報告に一貫性があり、気中濃度や尿中TCA濃度のデータが比較的広範囲にわたり、さらに濃度依存性も観察されていることから、有病の状況と併せて量-反応関係の推定を行うことが可能であった。その他の健康影響に関しては、量-反応関係の推定を行うにはまだ検討が必要な知見や、トリクロロエチレンの曝露との関連性が明らかでない知見であった。以上より、神経系への影響(自覚的神経症状)を用いて量-反応関係の推定を行い、評価値を算出することが適当であると考えた。
(5)有害性に係る評価値の算出
エンドポイントとして神経系の影響(自覚的神経症状)を用いて、量-反応関係を推定し、評価値を算出することとした。
自覚的神経症状については労働者を対象とした広範囲な調査研究が報告されており、それらを参考に評価値算出の出発点として、当該影響がみられると考えられる最小の気中濃度レベル(POD)を検討した。
環境基準専門委員会報告(1996)以降、新たに曝露濃度等の情報が報告されている自覚的神経症状の知見は得られなかったことから、環境基準専門委員会報告(1996)と同じ知見を基にPODを検討することとした。具体的には、Ahlmark and Fossman(1951)、Grandjeanら(1955)、Bardodej and Vyskocil(1951)、Liuら(1988)、WHO(1981)に示されている量-反応関係を示すデータを参考とすることになるが、環境基準専門委員会報告(1996)において検討された考え方を否定する理由はないため、同じ考え方により、PODとなる影響がみられると考えられる最小の気中濃度レベルは、200 mg/m3前後の濃度域に存在するものと考える。
今回、新たに得られた知見を加えた上で、環境基準専門委員会報告(1996)における考え方を参考にするとともに、POD(自覚的神経症状がみられると考えられる最小の気中濃度レベル)の設定にヒトの労働環境におけるデータを用いていることも含めて、下記の(ア)から(エ)を考慮して不確実係数等(労働環境から一般環境における連続曝露への換算及び影響の重大性を考慮するための係数を含む)を設定することとする。
(ア)一般環境には労働環境とは異なり、乳幼児、高齢者などの高感受性者が存在すること
(イ)労働環境における曝露は労働時間に限定した曝露であり、一般環境における連続曝露への換算が必要なこと
(ウ)NOAELを明確に示すことは困難であることから、影響がみられると考えられる最小の気中濃度レベルを評価値算出の出発点(POD)とすること
(エ)発がん性について新たな情報が得られたこと、及び過敏症症候群との関連性があると考えられること
以上の(ア)から(エ)での考え方や判断を踏まえると、疫学知見により得られたデータを用いる場合には不確実な要素が多く、(ア)から(エ)で共通する要素もあることから、これらを分離して論じることは難しいと考え、不確実係数等については、環境基準専門委員会報告(1996)と同様に総合的な係数として設定することとする。今回、新たに得られた知見を加えた上で総合的に判断した結果、本委員会は、環境基準専門委員会報告(1996)で用いた値(1,000)より大きい値として、総合的な係数は1,500とすることが適当であると考える。
これを適用して評価値を算出すると0.13 mg/m3となる。
(6)指針としての環境濃度の提案
本委員会は、有害大気汚染物質の低濃度長期曝露による健康影響を未然に防止する観点から、トリクロロエチレンの環境基準設定に当たっての指針として、年平均値0.13mg/m3以下の環境濃度を提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成8年12月9日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会「トリクロロエチレンに係る環境基準専門委員会報告」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/03-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成8年12月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第三次答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/03.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成30年9月・中央環境審議会大気・騒音振動部会有害性大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会「今後の有害大気汚染物質対策あり方について(第十一次報告)(トリクロロエチレンに係る健康リスク評価について)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/110002.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成30年9月20日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十一次答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/110002.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○テトラクロロエチレン
1.基準値
1年平均値が0.2mg/m3以下であること
2.測定方法
キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
3.設定経緯
平成8年12月9日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会報告
平成8年12月18日・中央環境審議会答申
平成9年2月4日・環境庁告示第4号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・クロロホルム様臭をもつ無色透明の液体で、不燃性、水に難溶
・比重:1.62(20℃)
・融点:-22℃
・沸点:121.1℃
・蒸気圧:19hPa(20℃)
・蒸気密度:5.8(空気=1)
・溶解度:水に難溶(20℃で150mg/L)、各種有機溶剤に易溶
・分配係数:logPow=2.86
・換算係数:1 ppm=6.78mg/m3(25℃)、1 mg/m3=0.147ppm(25℃)
(2)生産量等
(平成6年)
・生産量:57,780t
・輸出量:10,789t
・輸入量:696t
(3)用途
・ドライクリーニング用として天然及び合成繊維の洗浄、プラスチック等の脱脂洗浄剤、乾燥剤、一般溶剤、ペイントリムーバー、石鹸溶剤、セルロースエステル及びエーテルの混合物溶剤、駆虫剤、有機合成中間体等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC(1995) グループ2A
・ACGIH(1993) グループA3
・日本産業衛生学会(1972) 第2群B
(2)大気に関する基準
・環境庁大気環境指針(1993) 230μg/m3(年平均)
・WHO欧州地域事務局大気質ガイドライン(1987) 5mg/m3(24時間平均)
・オランダの基準 target value 25μg/m3(年平均)、guide value 1,000μg/m3(年平均)、limit value 2,000μg/m3(年平均)
(3)職業曝露に関する基準
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度 50ppm(340mg/m3)
・日本産業衛生学会許容濃度(1972) 50ppm(340mg/ m3)
・ACGIH TLV-TWA(1993) 25ppm(170mg/m3)
6.環境中における検出状況(設定時)
<一般環境>(昭和55年~昭和60年度)
(全体)169地点(123市町村)で0.013~10μg/m3(幾何平均値0.50μg/m3、算術平均値0.97μg/m3)
(人口100万人~)36地点(10市町村)で0.17~5.6μg/m3(幾何平均値0.79μg/m3、算術平均値1.3μg/m3)
(人口30~100万人)23地点(17市町村)で0.04~2.5μg/m3(幾何平均値0.52μg/m3、算術平均値0.79μg/m3)
(人口10~30万人)26地点(23市町村)で0.022~3.3μg/m3(幾何平均値0.38μg/m3、算術平均値0.78μg/m3)
(人口3~10万人)40地点(35市町村)で0.013~10μg/m3(幾何平均値0.52μg/m3、算術平均値1.4μg/m3)
(人口~3万人)44地点(38市町村)で0.09~2.6μg/m3(幾何平均値0.37μg/m3、算術平均値0.54μg/m3)
<固定発生源周辺>(昭和58年~平成7年度)
・446地点で<0.01~34,000μg/m3
7.基準値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
近年の大気環境中のテトラクロロエチレン等の有機化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が収集されているが、なお不明確な点があり、今後の解明を待つべき課題が少なくない。ここでは、現在までに得られた上述(略)の健康影響に係る知見から本専門委員会で行った評価と提案を述べる。
(1)発がん性について
疫学研究ではテトラクロロエチレンとの関連が示唆されるがんとして、肝がん、非ホジキンリンパ腫、食道がん、子宮頸部がん等が挙げられている。これらの研究はテトラクロロエチレンのヒトに対する発がん性を裏付ける証拠としては十分とはいえないものの、今後とも発がん性に関する疫学研究に注目する必要がある。
動物実験では、吸入曝露で雌雄のマウスに肝細胞がん及び肝細胞腺腫を引き起こし、雌雄のラットに単核球性白血病を引き起こす。また、有意ではなかったが、雄ラットに腎腺腫・腺がんの増加が報告されている。
(2)発がん性以外の毒性について
テトラクロロエチレンの急性毒性としては皮膚・粘膜への刺激作用と麻酔作用(中枢神経抑制作用)が主要症状である。労働環境等において、手のしびれ、頭痛、記憶障害、肝機能障害等の症状が報告されている。
テトラクロロエチレンの慢性毒性としては、神経系への影響や、肝障害、腎障害等の報告がある。
(3)閾値の有無について
テトラクロロエチレンは発がん性については、動物実験では証明されているものの疫学的にはその証拠は必ずしも十分とはいえず、ヒトに対するテトラクロロエチレンの発がん性について結論を得るには未だ検討を要すると思われる。また、発がん性があるとしても遺伝子毒性がないと思われることから、その発がん性には閾値があるとして取り扱うことが妥当と考えられる。
(4)量-反応アセスメントについて
テトラクロロエチレンの毒性については、環境中濃度では発がん性以外の毒性で評価することが適当である。テトラクロロエチレンの一般毒性については、代謝経路や代謝活性に関して質的な種差があることから、ヒトの毒性データに基づいて量―反応アセスメントを行うことが適当である。
テトラクロロエチレンの慢性影響(神経系の影響、腎障害)に関するデータを中心に、種々のデータから総合的に判断すると、LOAELに相当する気中濃度は、200mg/m3(30ppm)前後の濃度域に存在すると考えることが妥当である。
不確実係数としては、労働環境で得られたデータを一般環境に外挿すること、NOAELではなくLOAELを用いること等を考慮して、総合的な係数として1,000を用いることが適当と考える。
(5)曝露アセスメントについて
テトラクロロエチレンの物理・化学的性質、排出経路や、これまでの環境中の濃度の調査結果を考慮すると、テトラクロロエチレンの曝露はほとんど空気由来であり、特に、固定発生源の周辺環境での曝露が問題になると考えられる。
(6)指針としての環境濃度の提案について
低濃度長期曝露による健康影響を未然に防止する観点から、テトラクロロエチレンの長期曝露に係る指針として年平均値0.2mg/m3(2×102μg/m3)以下の環境濃度を提案する。
(以下略)
8.参考資料
・平成8年12月9日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会「テトラクロロエチレンに係る環境基準専門委員会報告」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/03-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成8年12月18日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第三次答申)」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/03.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○ジクロロメタン
1.基準値
1年平均値が0.15mg/m3以下であること
2.測定方法
キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
3.設定経緯
平成12年11月20日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会報告
平成12年12月19日・中央環境審議会答申
平成13年4月20日・環境省告示第30号
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・エタノール様臭の無色透明な液体で、不燃性、水に一部可溶であり、アルコール、エーテルその他の通常の有機溶媒と混和
・対流圏中のジクロロメタンの2~2.5%が成層圏に移行し、光酸化および光分解を受けるが、オゾン層は破壊しない
・比重:1.326(20℃)
・融点:-96.8℃
・沸点:39.8℃
・蒸気圧:506.5hPa(20℃)
・溶解度:水に一部可溶(25℃で13,030mg/L)、各種有機溶剤に易溶
・分配係数:logPOW=1.25
・換算係数:1ppm=3.47mg/m3(25℃、1,013hPa)、1mg/m3=0.288ppm(25℃、1,013hPa)
(2)生産量等
(平成7年)
・製造量:100,200t
・輸入量:600t
・使用量:95,800t
(3)用途
・洗浄および脱脂溶剤、塗料剥離剤、エアゾール、噴射剤、ポリウレタン発泡助剤、工業用プロセス溶剤、医薬中間体等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB2、生涯リスク:4.7×10-7(1μg/m3)(IRIS)
・ACGIH グループA3
・日本産業衛生学会 第2群B
・DFG カテゴリー3
(2)大気に関する基準
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン 3,000μg/m3(24時間平均)
・オランダの基準 target value 20μg/m3(年平均)
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 50ppm(170mg/m3)(暫定値)
・ACGIH TLV-TWA 50ppm(174mg/m3)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成10年度)(PRTRパイロット事業報告書)
・点源及び非点源からの排出量:1,440t(調査物質中の上位から3位)
・大気への排出がほぼ100%
7.環境中における検出状況(設定時)
<一般環境>(平成10年度)
(全体)213地点(196市町村)で0.28~110μg/m3(幾何平均値2.1μg/m3、算術平均値3.5μg/m3)
(人口100万人~)27地点(26市町村)で0.72~12μg/m3(幾何平均値3.4μg/m3、算術平均値4.6μg/m3)
(人口30~100万人)56地点(43市町村)で0.54~110μg/m3(幾何平均値2.9μg/m3、算術平均値5.5μg/m3)
(人口10~30万人)52地点(50市町村)で0.42~19μg/m3(幾何平均値2.3μg/m3、算術平均値3.2μg/m3)
(人口3~10万人)65地点(64市町村)で0.34~7.1μg/m3(幾何平均値1.4μg/m3、算術平均値2.0μg/m3)
(人口~3万人)13地点(13市町村)で0.28~4.9μg/m3(幾何平均値1.0μg/m3、算術平均値1.6μg/m3)
<工場・事業場の周辺環境>
・69地点で0.3~13μg/m3(幾何平均値2.4μg/m3、算術平均値3.6μg/m3)
<道路沿道>
・49地点で0.3~9.6μg/m3(幾何平均値2.4μg/m3、算術平均値3.2μg/m3)
<敷地境界>(昭和55年~平成7年度)
・91地点で0.06~9,500μg/m3(幾何平均値37.5μg/m3、算術平均値383μg/m3)
8.基準値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
近年、大気環境中の有機化合物の測定および健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が集積されつつある。とりわけジクロロメタンについては、発がんの種差の原因および発がんメカニズムに焦点を当てた研究が進行中であり、ヒトの発がんについての結論を求めることは時期尚早である可能性を十分認識しつつ、ここでは、現在までに得られた上述(略)の健康影響に係る知見から本専門委員会で行った評価と提案を述べる。
(1)発がん性について
疫学的研究からはジクロロメタンがヒトに発がん性を示すという十分な証拠があるとはいえないこと、動物実験ではマウスにおいて発がん性を有することは明らかであるものの、ラット、ハムスターに対する発がん性は明らかでなく、発がん性の種差が大きいこと、ヒトの遺伝子障害性については、低濃度曝露レベルで発現する可能性を示す機会は小さいと考えられることから、ヒトの発がんの可能性を完全に除外はできないものの、その可能性は小さいと判断する。
(2)発がん性以外の毒性について
ジクロロメタンの急性毒性としては、中枢神経に対する麻酔作用がある。労働環境等においては、はきけ、だるさ、めまい、四肢のしびれなどの症状が報告されている。なお、これら発がん性以外の毒性は、有機溶剤としてのジクロロメタン自体の毒性と、COHb形成による相対的な低酸素状態の相互作用として発揮されると考えられる。また、生殖毒性として、非常な高濃度吸収がある場合にのみ、ヒトで精巣毒性を発揮する可能性がある。
(3)量-反応アセスメントについて
ジクロロメタンの用量-反応アセスメントにあたっては、発がん性に関する知見をどのように扱うかについて特に熟慮を要するが、ジクロロメタンについては、現時点では、ヒトの発がんの可能性を完全に除外はできないものの、その可能性は小さいと判断する。したがって、発がんの可能性を完全に除外できないことに留意しつつも、発がん性以外の健康影響に関するデータを基本として量-反応アセスメントを実施することが適当である。また、代謝経路や代謝活性に関して種差が大きいことから、ヒトのデータを基本として量-反応アセスメントを行うことが適当である。
ジクロロメタンの発がん性以外の毒性(神経系への影響等)に関するヒトのデータを中心に判断すると、労働者でおそらく健康への悪影響が見られないと期待できる濃度レベルは、300mg/m3程度の濃度域に存在すると考えることが妥当である。
不確実係数については、NOAELを明確に示すことは困難であり、可能性は小さいもののヒトにおける発がん性を完全に除外することはできないことや限定的ではあるが生殖影響の報告があることにも配慮するとともに、ヒトの個体差、労働環境で得られたデータを一般環境に外挿することを考慮し、総合的な係数として、2,000を用いることが適当と考える。
(4)曝露アセスメント
ジクロロメタンの物理・化学的性質、排出経路や、これまでの環境中の濃度の調査結果を考慮すると、ジクロロメタンの曝露はほとんど空気由来であり、特に、固定発生源の周辺環境での曝露が問題になると考えられる。
(5)指針としての環境濃度の提案について(抄)
以上より、低濃度長期曝露による健康影響を未然に防止する観点から、ジクロロメタンの長期曝露に係る指針として、年平均値0.15mg/m3(1.5×102μg/m3)以下の環境濃度を提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成12年11月20日・中央環境審議会大気部会環境基準専門委員会「ジクロロメタンに係る環境基準専門委員会報告」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1420.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成12年12月19日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1420.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○ダイオキシン類
1.基準値
1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること
2.測定方法
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
3.設定経緯
平成11年10月・中央環境審議会大気部会ダイオキシン類環境基準専門委員会報告
平成11年12月10日・中央環境審議会答申
平成11年12月27日・環境庁告示第68号
4.基礎情報
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
(物理化学的性状)(平成24年の資料より)
ダイオキシン類は、通常は無色の固体で、水に溶けにくく、蒸発しにくい反面、脂肪などには溶けやすいという性質を持っている。また、ダイオキシン類は他の化学物質や酸、アルカリにも簡単に反応せず、安定した状態を保つことが多いのですが、太陽光の紫外線で徐々に分解されるといわれている。
(環境中での挙動等)(設定時)
ダイオキシン類のうちポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)の主要な発生源については、燃焼発生源と非燃焼発生源に大別され、日本国内においては、現時点では都市ごみ焼却からの発生量が最大の寄与を占めると考えられている。
大気中に放出されたダイオキシン類(特に、PCDD+PCDF)は、主に乾性・湿性沈着によって地表ないし農作物表面に到達すると考えられる。土壌に到達したダイオキシン類は主に粒子状物質に吸着して水域や底質に分配され、最終的に土壌及び底質が環境中における最大のシンク(降下、蓄積場所)になると推定されるが、これらの環境挙動は、現時点においても不明な点が多い状況である。
ダイオキシン類は環境中で一般に非常に安定で、長期間残留すると考えられている。大気、土壌あるいは底質いずれの環境媒体中でもダイオキシン類の分解は起こるが、その速度は非常に緩やかであると考えられる。したがって、環境中に放出されたダイオキシン類は、環境内での移動は起こるが、環境中の総量変化は小さく、長期間にわたって残留する可能性がある。
コプラナーPCBについては、PCDD及びPCDFと同様の発生源も一部考えられるものの、全体としてみると、その発生源は不明な部分が大きく、また、各環境媒体中濃度、異性体の割合、物性の相違なども考えられることから、上述の経路以外での挙動に関する知見が必要であると考えられる。しかし、現時点ではそうした知見は不足しており、今後の更なる調査研究が望まれる。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
環境庁・厚生省の合同審議会から、「ダイオキシンの耐容一日摂取量(TDI)について」が報告された。このTDIについては、1998年のWHO専門家会合におけるTDI見直しの考え方等を踏まえつつ、ダイオキシン類の毒性には直接的な遺伝子傷害性がないと判断し、動物を用いた各種毒性試験結果から推定したヒトでの最小毒性量(LOAEL)に不確実係数を適用する方法が用いられている。この際、ダイオキシン類のように蓄積性が高く、その程度に大きな種差が見られる物質については、TDIを求めるには一日あたりの摂取量でなく、体内負荷量に着目する方が適当であるとされ、各種毒性試験の結果を総合的に判断し、おおむね86ng/kg前後がTDIの算定根拠とする体内負荷量とされた。以上より、当面の間のダイオキシン類のTDIは、既存の科学的知見を対象とした論議を踏まえ、86ng/kgの体内負荷量の値に対応する人の一日摂取量を求め、不確実係数の10を適用し、コプラナーPCBも含め、4pg-TEQ/kg/日とすることが適当とされたものである。また、TDIは生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値であって、一時的に多少超過しても健康を損なうものではないことに留意する必要があるとされているところである。
6.環境中における検出状況(設定時)
<PCDD+PCDF>(平成10年度緊急全国一斉調査)(濃度:pg-TEQ/m3)
・地点数:387、:平均値:0.22、中央値:0.15、範囲:0.0~1.8
<コプラナーPCB>(平成10年度緊急全国一斉調査)(濃度:pg-TEQ/m3)
・地点数:100、平均値:0.013、中央値:0.011、範囲:0.0~0.074
<合計(共通地点のみ)>(平成10年度緊急全国一斉調査)(濃度:pg-TEQ/m3)
・地点数:100、平均値:0.23、中央値:0.17、範囲:0.0017~0.70
<PCDD+PCDF>(平成10年度緊急全国一斉調査)(濃度:pg-TEQ/m3)
(重点地域を含む発生源周辺)地点数:138、平均値:0.25、中央値:0.17、範囲:0.00030~1.8
(大都市地域)地点数:118、平均値:0.22、中央値:0.15、範囲:0.00050~1.1
(中小都市地域)地点数:118、平均値:0.18、中央値:0.13、範囲:0.0~0.86
(バックグラウンド地域)地点数:7、平均値:0.013、中央値:0.0062、範囲:0.0~0.067
(沿道)地点数:3、平均値:0.44、中央値:0.60、範囲:0.00093~0.72
(沿道後背地)地点数:3、平均値:0.44、中央値:0.61、範囲:0.014~0.70
<PCDD+PCDF+コプラナーPCB>(平成10年度緊急全国一斉調査)(共通して測定している地点のみ)(濃度:pg-TEQ/m3)
(重点地域を含む発生源周辺)地点数:64、平均値:0.25、中央値:0.19、範囲:0.015~0.70
(大都市地域)地点数:26、平均値:0.21、中央値:0.18、範囲:0.0050~0.53
(中小都市地域)地点数:6、平均値:0.20、中央値:0.15、範囲:0.0017~0.66
(バックグラウンド地域)地点数:4、平均値:0.021、中央値:0.0058、範囲:0.0018~0.071
7.基準値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
3.1.大気経由割合に関する検討
2.2.3.(略)では摂取態様別の類型群を想定し、各群についてダイオキシン類の吸収量の推計を行ったが、この各群についてダイオキシン類の総吸収量のうち大気経由による吸収量の割合(大気経由割合)を算出し、大気経由吸収量の幅について検討を行った。
その結果、各群の総吸収量に対する大気経由割合は、偏りの小さい類型群a)を示していると考えられる類型群を中心に見ると、
PCDD+PCDF:8.9~30.2%程度
コプラナーPCB:0.3~1.7%程度
PCDD+PCDF+コプラナーPCB:4.0~16.5%程度
であった。これより、ダイオキシン類総吸収量に占める大気経由割合は、おおよそ5%~15%程度と推定される。
この割合をTDI 4pg-TEQ/kg/日に対応する吸収量2pg-TEQ/kg/日b)に乗じて得た大気経由の吸収量は、0.10~0.30 pg-TEQ/kg/日と算出される。
(脚注)
a)基本ケース、ケース1(専門委員会報告別紙1(略)及び別紙2(略)参照)の組み合わせをもとに、その割合を検討した。
b)TDIに対応する吸収量について:TDIは摂取量を対象とした値であり、その導出に当たっては吸収率を50%と見積もっている。このため、吸収量で考える場合は、4pg-TEQ/kg/日の50%の2pg-TEQ/kg/日がTDIに対応する。
3.2.人への曝露に関する試算
ダイオキシン類の環境中の挙動に関する知見は未だに十分とはいえない。しかしながら、人への曝露を検討する上での一助とするため、参考までに現段階において可能な範囲で、ダイオキシン類の人への曝露に関する試算を行った(別紙3及び参考資料2(略))。
(1)環境中挙動モデルについて
ダイオキシン類の環境中の挙動に関する試算を行うには、非定常多媒体の運命予測等の環境中挙動モデルを用いる予測・推定手法などを用いることが必須と考えられる。その一方、その結果について慎重に判断し、適切な推定を試みることが必要である。本試算では、現状から将来にわたるダイオキシン類の各媒体濃度の減少の大きさ、減少に要する時間等に関する概略値を環境中挙動モデルから導くこととした。なお、本試算については、今後の環境挙動調査や環境モニタリングの結果等を踏まえ、適宜、検証し、精査することが望ましい。
(2)人への曝露に関する試算
(1)の環境中挙動モデルで導いた各媒体間の減少率比を用い、現状のダイオキシン類の大気環境濃度が一定の減少を示した場合の平均大気環境濃度の減少率を試算した。また、これをもとに、2.2.2.(2)(略)の想定摂取態様別の類型群について、環境媒体中濃度が各媒体間減少率比に従って減少した場合に、総吸収量がどのように変化(減少)するかについての試算を行った。
本試算に伴う不確実性には十分留意する必要があるが、ダイオキシン類の大気環境目標濃度を0.6pg-TEQ/m3以下とし、大気環境濃度が低減した場合、環境及び食品から摂取に偏りのある群の最大値ケース(現状の想定総吸収量2.71pg-TEQ/kg/日)については、TDI 4pg-TEQ/kg/日に対応する吸収量である2pg-TEQ/kg/日を下回った。なお、本最大値ケースは食品、大気、土壌の全てについて、曝露評価を行う目的で大きな摂取の偏りを想定した類型であり、現実的な組み合わせとしては一般的に想定し難いものと考えられる。また、一般生活環境群の総吸収量については、1.06~1.42 pg-TEQ/kg/日から、0.81~1.10pg-TEQ/kg/日に低下すると試算された。
3.3.諸外国の曝露評価に関する事例
諸外国の曝露評価に関する事例はPCDD+PCDFに関するものが多く、コプラナーPCBを含めた知見については不足している。以下の検討においてはこの点に留意する必要がある。
諸外国の政府レベルにおいては、大気環境基準や指針値に相当するものが設定されている事例は、現在把握している限りは無い。一方、米国カリフォルニア州においてPCDD+PCDFについて"Hot Spots"Programの中で非発がんの参照曝露レベルを3.5×10-6μg/m3としているなどの例がある。諸外国の大気環境濃度データについては測定地点の分類方法等を考慮すると、単純には比較できないと思われるが、報告例としては、PCDD+PCDFについて、都市地域と分類されているデータを中心に見ると、米国で平均0.1pg-TEQ/m3程度、ドイツで0.07~0.35 pg-TEQ/m3程度、オランダでは概ね0.1 pg-TEQ/m3以下の範囲に、英国では、概ね1.8 pg-TEQ/m3以下(平均0.17pg-TEQ/m3)程度などの例がある。
曝露経路別の曝露評価を行った事例として、PCDD+PCDFについては、米国、カナダ、ドイツ等のものがある。どの事例においても、食品からの曝露量がその多くを占めている。米国EPAが試算したものからは平均すると大気経由割合は2%弱であり、カナダの事例で、一般的な場合、食品のうち魚の摂取が多い場合、発生源近傍における場合について試算したものからは、大気経由割合は1~8%程度であった。ドイツの事例では、大気経由割合は2~5%程度であった。諸外国では、大気経由の一般的な摂取割合は概ね1%~5%程度で、これは大気経由の摂取量が食品経由のそれに比して相対的に小さいものとなってきていることとも関連していると思われる。この摂取割合について、吸収率を勘案し、吸収量ベースでの大気経由割合を求めると2~10%弱程度になると考えられる。TDI 4pg-TEQ/kg/日に対応する吸収量(2pg-TEQ/kg/日)にこの割合を乗じると0.04~0.20pg-TEQ/kg/日弱程度となる。しかしながら、これらの知見については、上に述べたようにコプラナーPCBが含まれた評価が少ないこと、大気環境濃度データと発生源の種類等との関連が必ずしも明確ではないことなどに十分注意を払うべきである。
食品についての調査事例では、調査年度にかなり幅がある点に注意が必要であるが、摂取量は概ね100pg-TEQ/日~300pg-TEQ/日程度との報告が多く、欧米では、乳製品や肉類等の寄与割合大きい傾向にあって、一部の国では、野菜、穀類や油等の割合が高い事例もある。調査手法、調査年度やTEQの算出方法の相違などから単純には比較できないが、我が国ではおおむね100pg/日程度との報告があった。また、食品経由の摂取量は近年、減少傾向にあるとの報告が数例ある。
3.4.環境基準値の算定
3.1.の結果により、大気経由割合は、偏りの小さい類型群を中心にみると、吸収量について、おおむね5%~15%程度であると推定され、この割合をTDI 4pg-TEQ/kg/日に対応する吸収量2pg-TEQ/kg/日に乗じると、大気経由のダイオキシン類の吸収量は、おおむね0.10~0.30pg-TEQ/kg/日となる。
さらに、3.2.における検討及び我が国における大気環境中のダイオキシン類濃度の現状等も踏まえ、人の健康を保護する見地から総合的に判断すると、大気の汚染に係る環境基準は、長期的に摂取される場合において0.6pg-TEQ/m3以下とすることが適当である。
(以下略)
8.参考資料
・平成11年10月・中央環境審議会大気部会ダイオキシン類環境基準専門委員会「大気の汚染に係るダイオキシン類環境基準専門委員会報告」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1499.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成11年12月10日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第五次答申)(大気の汚染に係るダイオキシン類の環境基準及び排出抑制対策のあり方)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/1499.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成20年3月・環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室・大気環境課「ダイオキシン類に係る大気環境測定マニュアル」 https://www.env.go.jp/air/osen/manual/manual.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成24年3月・環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室「ダイオキシン類(2012)」 http://www.env.go.jp/air/dioxin/2012pamph.pdf 【NIES保管ファイル】
(4)有害大気汚染物質に係る指針値
①設定の考え方
(令和2年8月20日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」(別添3)今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(改定版)(中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告)より)(抜粋)
第1 有害大気汚染物質の指針値について(抄)
(中略)
2.指針値の性格と機能
(1)指針値の性格
指針値は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し評価した結果として設定されるものである。基本的には、大気経由の長期的曝露による健康影響を未然に防止する観点から設定されるものであり、さらに不確実係数を十分に見込んだ評価値、あるいは数理モデルにより十分に安全性を考慮して算出した評価値に基づくものであることから、指針値を短期的に上回る状況があっても、直ちに人の健康に悪影響を及ぼすものではないと考えられる。
また、指針値は、有害性評価に係る知見の制約のもとに定められた値であると判断すべきであり、新しい知見やデータの集積に伴い、随時、見直していく必要がある。
指針値はこのような性格を有するものの、健康リスク低減の観点から、このレベルが達成できるように排出抑制に努めるべきものとして理解することが妥当である。なお、大気環境モニタリング結果等が指針値を下回ったとしても、引き続き排出抑制の努力が望まれることに注意すべきである。
(2)指針値の機能
指針値は、健康リスクを低減する観点から科学的知見を集積し評価した結果として設定されるものであることから、現に行われている大気環境モニタリング結果等の評価指標や事業者による排出抑制努力の評価指標としての機能を果たすことが期待される。このほか、国、地方公共団体及び事業者の連携による地域主体の自主的な取組を実施するうえでの指標となることが期待される。これらの機能は、相互に関連しつつ有害大気汚染物質の大気経由の曝露による健康リスクの低減に資するものであると考えられる。
なお、指針値が設定されている物質については、大気環境モニタリング結果等から、排出抑制効果を検証・評価することとされているが、指針値が設定されている物質の大気中の平均濃度はおおむね減少傾向を示しており、指針値設定が排出抑制に効果的に貢献していることが確認されている。
(中略)
第2 有害大気汚染物質の健康リスク評価の手順について(抄)
1.背景
有害大気汚染物質の指針値設定に当たっては、有害性に関する疫学研究、動物実験、有害影響の発現メカニズムや遺伝子障害性等リスク評価に必要な科学的知見の収集・整理を行い、これらを基に、適切な用量反応評価手法を検討して、曝露の状況も踏まえつつ、健康リスク評価作業を実施してきた。
現時点で環境目標値が設定されていない優先取組物質や、将来新たに優先取組物質に選定された検討対象物質について環境目標値を設定する際、その多くは有害性に係る評価値(以下「評価値」という。)を算出するための人に関する疫学研究の知見がない、あるいは、定量評価に用いることのできる人のデータが得られないことが予想される。このような場合は、動物実験の知見を用いて人へ外挿することにより評価値を算出することが必要となる。
このため、第七次答申において動物実験の知見の人への外挿方法、不確実係数の設定等有害性評価の方法を中心として、指針値の性格やその設定手順等が示され、これを踏まえ、クロロホルム、1,2-ジクロロエタンの指針値は、動物実験のデータに基づき設定された。
2.「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定経緯
第七次答申で示された「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(別紙「指針値算出の具体的手順」を含む。)は、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価を行う上での基礎となる考え方を明示したものであり、環境目標値のうち、指針値の設定に当たって数値の算出に必要となる有害性評価に係る定量的データの科学的信頼性やその設定手順、指針値の性格、指針値の機能等、指針値に係る諸事項について定められた。
第八次答申で別紙の「指針値算出の具体的手順」が一部改定、第十次答申において、「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」及び「別紙指針値算出の具体的手順」が改定され、「指針値算出の具体的手順」は、「指針値設定のための評価値算出の具体的手順」とされた。
今般、第十次答申で示された「今後の課題」等に対応するため、全体構成の再整理を行い、本文と別紙の用語の精査を行うとともに、曝露評価について、付属資料として収集する情報を整理する等「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の一部を改定することとした。
<経緯>
・第七次答申(平成15年7月)「今後の有害大気汚染物質に係る健康リスク評価のあり方について」策定
・第八次答申(平成18年11月)「別紙指針値算出の具体的手順」の一部改定
・第十次答申(平成26年4月)「今後の有害大気汚染物質に係る健康リスク評価のあり方について」の一部改定
3.指針値設定のための有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方
(1)健康リスク評価の方法について
有害大気汚染物質の健康リスク評価に当たっては、有害性評価とこれに基づく評価値の算出及び曝露評価、並びにこれらの結果の比較から大気経由の曝露による健康リスクの程度の把握を行う。その際、別紙「指針値設定のための健康リスク評価の具体的手順」及びその付属資料(略)に従うものとする。
(2)健康リスク評価に必要な科学的知見及び基本的な考え方
評価値の算出に必要となる定量的データは、主に疫学研究と動物実験から得られるが、このうち疫学研究は人から直接得られるものであることから優先性が高い。
一方、動物実験の知見の場合、定量的データが比較的豊富に得られていても、現時点では、それを人に外挿し、評価値を算出するには不確実性が大きい場合が多い。動物実験の知見に基づく評価値の算出に当たっては、当該物質の体内動態、有害影響の発現メカニズム等の知見を収集し、観察された有害影響の作用様式の人との共通性、人への外挿手法の妥当性について検証の上、慎重に行うことが重要である。
評価値の算出に用いられる定量的な知見の科学的根拠の確実性※については、次のⅠ、Ⅱ、Ⅲの3区分に分類されると考えられる。
※ 第十次答申における「「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定について」においては、有害性を評価するに当たって、定量的で、かつ大気汚染物質の曝露と健康影響の関連性が相当に確からしい疫学研究や動物実験の知見について「確実」とし、「確実性」についても、同様の趣旨で用いられた。本報告(令和2年3月25日)においてもこれを踏襲している。
Ⅰ.確実性の高い科学的根拠を有する疫学研究又は動物実験の知見
Ⅱa.相当の確実な根拠を有する疫学研究の知見であるが、不確実性の要因を除くために、当該疫学研究における曝露評価及び交絡因子の調整等のさらなる科学的知見の充実を要するもの
Ⅱb.相当の確実な根拠を有する動物実験の知見であるが、不確実性の要因を除くために、観察された有害影響の作用様式の解明及び人への外挿手法等のさらなる科学的知見の充実を要するもの
Ⅲa.疫学研究の知見のうちⅡaの水準に達しないもの(Ⅱaの水準に達しない要因としては、例えば、対象者が少ない、対象集団が偏っているといった不確実性が存在すること等があげられる)
Ⅲb.動物実験の知見のうちⅡbの水準に達しないもの(Ⅱbの水準に達しない要因としては、例えば、観察された有害影響の作用様式が人と共通でないこと等があげられる)
このうち、Ⅰ又はⅡa、Ⅱbに該当する知見が得られる物質については、指針値を設定することとする。なお、Ⅰに該当する知見が得られる物質については、必要に応じ、環境基準の設定について検討される対象となる。Ⅲa、Ⅲbに該当する知見にとどまる物質については、指針値の設定の対象とはならないが、このような知見も、有害性に関する相対的な程度を把握するための一定の参考となる情報である。したがってこれを「参考情報」として、有害性に係るデータ等を、その根拠を含めて示していくことには意義があると考えられる。
今後、有害大気汚染物質の指針値の設定を行う上では、以下のような基本的考え方に立脚する。
①科学的知見を収集、整理し、常にアップデートするよう引き続き努めていくとともに、
②科学的知見についてさらなる充実を要する状況にある物質についても、現時点で得られている知見をもとに、一定の評価を与えていく手法を導入する。
有害性評価に用いうる科学的知見が新たに得られた場合には、諸外国において実施された科学的根拠やリスク評価手法が確認できる評価例を参照しつつ、順次、迅速に指針値を設定・改定していくことが求められる。
また、指針値を設定しようとする物質の曝露評価に当たっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条第1項に基づき地方公共団体が実施している有害大気汚染物質の大気環境モニタリングなどの現時点の大気中濃度に関する知見や、その物質の起源に関する知見をデータの信頼性を考慮しつつ収集する。
(中略)
(別紙)指針値設定のための健康リスク評価の具体的手順
1.有害性評価
(1)定性評価
評価対象物質に関する情報に基づき、発がん性、発がん性以外の有害性別に定性評価に資する文献を抽出、整理する。また、当該物質の代謝・体内動態、遺伝子障害性等の有害性評価に必要な文献も整理する。これらの文献をもとに定性評価を行う。
(2)定量評価に資する知見の整理
(1)で整理された文献から、発がん性、発がん性以外の有害性別に定量評価に資する可能性のある知見を抽出、整理する。
(3)評価値算出の基本的な考え方
①適切な知見の抽出
(2)で整理された知見の中から、後述の「付属資料1有害性評価に資する疫学知見の抽出の考え方(略)」、「付属資料2 有害性評価に資する動物実験知見の抽出の考え方(略)」を参照し、知見の科学的根拠の確実性及びデータの信頼性、妥当性、適切性についての必要な確認を行い、評価値を算出するための鍵となる知見(キースタディ)を抽出する。
②知見の科学的根拠の確実性
①で抽出した知見が、本文第2 3.(2)に示された3つの区分のいずれに相当するか確認する。評価値は、原則として、Ⅰ又はⅡa・Ⅱbに相当する科学的に確実な根拠を有する知見を選択し、そのデータから算出することとする。
③疫学知見の優先性
適切な疫学知見が存在する場合には、動物実験及び人志願者実験の知見に優先してこれを有害性評価に用いる。「有害大気汚染物質」が大気汚染防止法第2条第15項において「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と規定されていることから、長期曝露影響の疫学知見を優先する。
適切な疫学知見が得られない場合には、動物実験の知見に基づく有害性評価を検討する。その際、確実性の高い定性的な疫学知見は、動物実験の知見に基づく有害性評価を行うにあたり参考とする。人志願者実験の知見の中で、確実性の高いものがあれば、その利用も検討する。
④吸入曝露の知見に基づく算出
吸入曝露とそれ以外の曝露経路による知見が得られる場合は、原則として吸入曝露から得られた知見を重視して算出する。
動物実験の知見に基づく評価において、やむを得ず経口曝露実験の知見を用いて評価値を算出する場合には、曝露経路換算の考え方について、「付属資料4 動物実験の知見に基づく評価値算出の具体的手順4-1実験曝露濃度(用量)の換算及び補正(略)」を参照する。
⑤慢性又は亜慢性曝露の知見に基づく算出
動物実験の知見に基づく評価においては、原則として慢性曝露実験、あるいは亜慢性曝露実験の知見に基づき評価を行う。やむを得ず曝露期間が一定未満の曝露実験の知見を用いて評価値を算出する場合には、曝露期間補正の考え方について、「付属資料4 動物実験の知見に基づく評価値算出の具体的手順4-3 発がん性以外の有害性及び閾値のある発がん性に係る評価値の動物実験の知見に基づく算出ii)不確実係数等の設定(e)曝露期間の差(略)」を参照する。
⑥発がん性と発がん性以外の有害性
評価値の算出は、発がん性及び発がん性以外の有害性について行う。この場合において、発がん性及び発がん性以外の有害性に係る評価値がともに算出可能な場合は、両者の評価値を算出する。一方の有害性に関してのみ、適切な疫学研究の知見が存在する場合には、他方の有害性に関する動物実験の知見に基づく評価値算出の必要性を十分吟味した上で、疫学研究に基づく評価値のみを算出することもできることとする。
⑦大気経由の曝露情報利用
評価値の算出において利用する曝露に関する情報は、原則として大気経由の曝露のみを取り扱うこととする。
なお、他の経路による曝露(経口曝露、経皮曝露)の影響が極めて重要と考えられる場合には、必要に応じて他の経路からの曝露量を考慮に入れた適切な評価値の算出を検討する。
⑧発がん性の閾値の有無の判断
発がん性の閾値の有無の判断に関する検討については、発がん性を有する化学物質を、遺伝子障害性の有無とその発がん性への関与の程度により、閾値の有無に関して「付属資料3 発がん性の閾値の有無の判断に関する考え方(略)」に記した3区分に類型化し、ユニットリスクあるいは無毒性量(NOAEL、No Observed Adverse Effect Level)等を求め、評価値を算出する。
⑨有害性の評価値の算出方法
発がん性について閾値がないと判断される場合は、疫学研究に係るデータではベンゼンの例に習い平均相対リスクモデル等の数理モデルを用い、動物実験に係るデータでは観察された用量反応関係から導かれたベンチマーク濃度からの低濃度直線外挿法等適切な方法を検討する。また、閾値があると判断される場合や発がん性以外の有害性についてはNOAEL等を不確実係数で除する方法によることとする(ただし、疫学研究のデータではNOAEL等が求められないことが多いため、労働者等でおそらく悪影響が見られないと期待できる濃度を使用)。発がん性以外の有害性に係る短期曝露実験により、長期曝露影響を示唆する知見や不可逆かつ重大な影響を示唆する知見が得られた場合には、評価値の算出において、当該知見の考慮の必要性を検討する。
動物実験の知見からの評価値の算出手順については、「付属資料4 動物実験の知見に基づく評価値算出の具体的手順(略)」に詳述する。
2.曝露評価
指針値を設定しようとする物質については、健康リスクの評価や排出抑制等の対策の検討に資するために、現時点での大気中濃度に関する知見及び起源に関する知見を収集し、曝露評価を行う。さらに、必要に応じて大気以外の経路による曝露量の情報も収集する。
一般環境大気に係る曝露評価は、大気環境モニタリング結果を用いて行う。発生源の周辺環境に係る曝露評価は、大気環境モニタリング結果、環境省委託調査等で収集された知見のうち信頼性の高いデータを用いて行う。
発生源近傍の汚染状況や年平均濃度の把握の確実性を高める等の必要性がある場合は、環境動態モデル等の活用も検討する。
曝露評価については、「付属資料5 曝露評価の考え方(略)」に詳述する。
3.指針値の提案
指針値の提案に当たっては原則として、発がん性に係る評価値及び発がん性以外の有害性に係る評価値がともに算出される物質については両者のうち低い方の数値を採用し、また、両者のうち一方の有害性に係る評価値のみが算出される場合には当該算出された数値を採用する。
指針値を提案する物質については、採用した数値と現時点の曝露評価の結果を比較して大気経由の曝露による健康リスクの程度を把握し、当該物質の健康リスクを評価する。
本文第2 3.(2)のⅠに相当する知見に基づき有害性が評価され、指針値が提案された物質については、大気以外からの曝露の考慮を特に要しないか、又は、その評価が既に定まっている場合には、指針値を定めた上で、さらに必要に応じ、環境基準の設定について検討の対象とすることとする。大気以外からの曝露についてなお検討を要する場合には、指針値の設定に留めることとする。
(参考資料)
・平成15年7月31日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」(別添1)今後の有害大気汚染物質に係る健康リスク評価のあり方について(中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会) https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_01.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月8日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第八次答申)」(別添1)指針値算出の具体的手順の一部改定について(中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会) https://www.env.go.jp/council/toshin/08-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成26年4月30日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)」(別添1)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定について(中央環境審議会大気・騒音振動部会健康リスク総合専門委員会) https://www.env.go.jp/press/files/jp/24460.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和2年8月20日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」(別添3)今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(改定版)(中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会) https://www.env.go.jp/press/108315/1203.pdf 【NIES保管ファイル】
②環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)及び評価方法(令和3年10月7日現在)
(項目及び指針値(一覧))
| 物質 | 指針値 | 通知日 | 指針値が示された答申※ | 指針値設定の際に用いられたガイドラインが示された答申※ |
|---|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | 1年平均値が2μg/m3以下であること。 | 平成15年9月30日 | 第七次答申 | 第七次答申 |
| アセトアルデヒド | 1年平均値が120μg/m3以下であること。 | 令和2年8月20日 | 第十二次答申 | 第十二次答申 |
| 塩化ビニルモノマー | 1年平均値が10μg/m3以下であること。 | 平成15年9月30日 | 第七次答申 | 第七次答申 |
| 塩化メチル | 1年平均値が94μg/m3以下であること。 | 令和2年8月20日 | 第十二次答申 | 第十二次答申 |
| クロロホルム | 1年平均値が18μg/m3以下であること。 | 平成18年12月20日 | 第八次答申 | 第八次答申 |
| 1,2-ジクロロエタン | 1年平均値が1.6μg/m3以下であること。 | 平成18年12月20日 | 第八次答申 | 第八次答申 |
| 水銀※※ | 1年平均値が40ngHg/m3以下であること。 | 平成15年9月30日 | 第七次答申 | 第七次答申 |
| ニッケル化合物 | 1年平均値が25ngNi/m3以下であること。 | 平成15年9月30日 | 第七次答申 | 第七次答申 |
| ヒ素及び無機ヒ素化合物 | 1年平均値が6ngAs/m3以下であること。 | 平成22年10月15日 | 第九次答申 | 第八次答申 |
| 1,3-ブタジエン | 1年平均値が2.5μg/m3以下であること。 | 平成18年12月20日 | 第八次答申 | 第八次答申 |
| マンガン及び無機マンガン化合物 | 1年平均値が140ngMn/m3以下であること。 | 平成26年5月1日 | 第十次答申 | 第十次答申 |
※平成7年9月20日に環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」に対する答申を示す。
※※水銀については、平成27年の大気汚染防止法改正により、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための排出規制が導入され、同法に基づく「有害大気汚染物質」からは削除されたが、環境中の水銀による健康リスクの低減を図ることは水俣条約の趣旨からも重要であることから、そのための指針となる数値(指針値)については維持し、大気モニタリングの評価や事業者による排出抑制努力の指標として引き続き活用することとされた。
(評価方法)(常時監視に関する事務の処理基準抜粋)
Ⅳ 有害大気汚染物質等に係る常時監視(抄)
1.測定対象
(中略)
クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化合物については、原則として粒子状の物質に限る。水銀及びその化合物については、原則としてガス状のものに限る。
ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物並びに水銀及びその化合物については、個別の物質によって健康リスクが異なると思われるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定を実施することが困難であるため、それぞれの金属及びその化合物ごとに、当該金属化合物の全量又は当該金属及びその化合物の全量(金属換算値)を測定するものとする。クロム及び三価クロム化合物並びに六価クロム化合物については、現時点では測定が困難であるため、当面、クロム及びその化合物の全量(クロム換算値)を測定するものとする。
(中略)
3.測定頻度等
長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質等の常時監視においては、原則として年平均濃度を求めるものとする。
有害大気汚染物質等の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係しているため、季節変動、週内変動及び日内変動が認められる。常時監視に当たって、これらの変動が適切に平均化されるよう、原則として月1回以上の頻度で測定を実施するものとする。その際、連続24時間のサンプリングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さらに、サンプリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化することが望ましい。
サンプリング方法及び対象物質によっては、連続24時間のサンプリングによると破過する場合があるが、この場合はサンプリングを数回に分けて連続して行うものとする。
(中略)
6.測定値の取扱い及び評価
(1)評価の対象としない測定値等
Ⅱの6.(1)ア及びイの例による。
(2)年平均値の算出
測定結果を評価する際には、地点ごとに、測定値を算術平均して求めた年平均値を用いるものとし、環境基準値が設定されている物質については基準値との比較によってその評価を行うものとする。測定値が検出下限値未満のときは、検出下限値の1/2として年平均値の算出に用いるものとする。十分な測定頻度で測定を実施できなかった場合又は欠測が多く測定値の得られた季節が偏っている場合等は、結果の評価に際し留意する必要がある。
(3)異常値の取扱い
これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が得られた場合又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、その測定値は異常値である可能性がある。このときは、サンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析という一連の作業に問題がないかを確認し、問題がない場合には、サンプリング時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がなかったかを確認するものとする。以上の情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とするものとする。
なお、異常値の可能性がある測定値が得られた場合には、可能な限り速やかに再測定を行うことが望ましい。
(参考資料)
・平成27年1年23日・中央環境審議会「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策について(答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/25919.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成28年9月26日・環境省水・大気環境局長「「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について」の一部改正等について」(環水大大発第1609263号・環水大自発第1609261号)別添 https://www.env.go.jp/air/osen/law22_kijun/hannei_2.pdf 【NIES保管ファイル】
③項目ごとの指針値及び設定根拠
○アクリロニトリル
1.指針値
1年平均値が2μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成15年7月31日・中央環境審議会答申
平成15年9月30日・環境省環境管理局長通知(環管総発第030930004号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・水及びアセトン、ベンゼンに可溶であり、メタノール、トルエン、キシレン、酢酸エチル、四塩化炭素、エチルエーテル、石油エーテル等と混合
・比重:0.8060(20℃)
・融点:-83.55℃
・沸点:77.3℃
・蒸気圧:83mmHg(20℃)
・水に対する溶解度:7.35g/100g water(20℃)
・分配係数:logPow=0.12
・換算係数:1ppm=2.17mg/m3(25℃)、1mg/m3=0.461ppm(25℃)
(2)生産量等
(平成12年)
・生産量:732,089t
・輸出量:134,497t
・輸入量:114,713t
(3)用途
・アクリル系合成繊維、炭素繊維、合成ゴム、ABS樹脂、AS樹脂、接着剤、塗料、有機合成原料として使用。その他、天然樹脂の変成剤などにも使用。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ2B
・U.S. EPA グループB1、ユニットリスク:6.8×10-5(1μg/m3)(IRIS)
・ACGIH グループA3
・日本産業衛生学会 第2群A
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン ユニットリスク:2×10-5(1μg/m3)
(2)大気に関する基準
・オランダの基準 limit value 1μg/m3、target value 0.1μg/m3
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 2.0ppm(4.3mg/m3)
・ACGIH TLV-TWA 2.0ppm(4.3mg/m3)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成13年度)届出排出量(大気):880t、届出排出量(合計):952t、届出外推計排出量:956t
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成9年度)地点数:283、検体数:1696、平均:0.21、最小:0.020、最大:5.8
(平成10年度)地点数:319、検体数:3305、平均:0.21、最小:0.0050、最大:2.6
(平成11年度)地点数:332、検体数:3564、平均:0.17、最小:0.0025、最大:2.5
(平成12年度)地点数:338、検体数:3701、平均:0.15、最小:0.0047、最大:2.2
(平成13年度)地点数:359、検体数:3840、平均:0.14、最小:0.00015、最大:1.6
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成13年度)
(全地区)地点数:359、平均:0.14、最小:0.00015、最大:1.6
(一般環境)地点数:231、平均:0.12、最小:0.0036、最大:1.2
(沿道)地点数:56、平均:0.11、最小:0.010、最大:0.29
(発生源周辺)地点数:72、平均:0.21、最小:0.00015、最大:1.6
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(1)主な知見
O'berg(1980)など、アクリロニトリルがヒトに対して発がん性を有する可能性を示唆する限定的な疫学データがある一方で、Collins et al(1989)、Swaen et al(1992)のように、それを否定する疫学的証拠及びレビューが多数報告されている。
Jakubowski et al.(1987)の報告では、ヒト志願者(男性6人)に対して2.3および4.6ppmのアクリロニトリルを8時間吸入させて尿中への代謝物排泄を調べたが、その際志願者は従来アクリロニトリル曝露によって起こることが知られていた頭痛、吐き気、脱力などの自覚症状を一切訴えなかった。
Sakurai et al(1978)は1975年から1976年にかけて、当時日本に存在した7つのアクリル繊維製造会社が所有する8つの工場のうち、最も小さな2つを除いた6工場で、アクリロニトリルの健康影響に関する断面疫学調査を実施し、この研究結果から4ppm程度以下の曝露では、肝機能異常を含め通常の臨床化学検査によって検出されるような健康障害は起こらないことがわかった。
Kaneko and Omae(1992)が報告した自覚症状検査は、対象工場のほぼ全アクリロニトリル作業者に対して行われ、当時客観的な諸検査では変化が無かったが自覚症状の有意の増加があったことが明らかになっている。
Muto et al(1992)が1988年に日本のアクリル繊維製造7工場で、アクリロニトリル作業者157人と対照作業者537人を対象に行った肝機能及び自覚症状調査では、アクリロニトリルによると考えられる影響を見出すことはできなかった。この調査時のアクリロニトリル曝露濃度は0.53ppm(=1.15mg/m3、N=113、0.01~2.80ppm)であった。
(2)指針値算出の考え方
アクリロニトリルの慢性影響に関するデータを中心に、種々のデータから総合的に判断すると、労働者についておそらく健康への悪影響が見られないと期待できるレベルとして1mg/m3とする。
不確実係数については、一般的な不確実係数の考え方を基本に、さらにヒトの労働環境におけるデータを用いて、一般環境における数値に換算するための係数を含めることとし、
・一般環境には労働環境と違い、乳幼児、高齢者などの高感受性者が存在すること
・労働環境(一般に1日8時間、週40時間の断続曝露)と一般環境では曝露時間及び曝露の状況が異なること
・労働者におそらく健康への悪影響がみられないと期待できる濃度を使用し、また可能性は小さいもののヒトの発がん性を完全に除外することはできないこと
等の点を考慮し、総合的な係数として500を用いることが適当と考える。
(3)指針値
以上より、アクリロニトリルの指針値は年平均値2μg/m3以下とする。
(中略)
(別添2-1)アクリロニトリルに係る健康リスク評価について
(中略)
4.総合評価
アクリロニトリルの量反応アセスメントについては、以下の理由より、発がん性について十分考慮しつつ、ヒトの発がん性以外の毒性に関するデータを基本として量-反応アセスメントを実施することが適当である。
・アクリロニトリルの疫学的知見からはアクリロニトリルが人に発がん性を示すという適切な証拠があるとはいえないこと
・動物実験ではラットおよびマウスに発がん性を有する十分の証拠はあること
・ヒトに対する遺伝子障害性については、in vivoの成績が不明確であること
・発がんに関与すると思われるCEOの代謝に種差があること
アクリロニトリルの慢性影響に関するデータを中心に、種々のデータから総合的に判断すると、労働者についておそらく健康への悪影響が見られないと期待できるレベルとして1mg/m3とする。
(以下略)
9.参考資料
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」(別添2-1)アクリロニトリルに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02-1.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月31日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/t07-h1503.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○塩化ビニルモノマー
1.指針値
1年平均値が10μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法/固体吸着-加熱脱着法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成15年7月31日・中央環境審議会答申
平成15年9月30日・環境省環境管理局長通知(環管総発第030930004号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・水にはわずかに溶解し、高温強アルカリ下ではHClを失う
・安定性としては、直射日光及び酸素のもとでは不安定であり、400℃以上でアセチレンと塩酸に分離
・比重:0.912~0.983
・融点:-160~-153.8℃
・沸点:-14~-13.4℃
・蒸気密度:2.150
・蒸気圧:2,660mmHg(25℃)、2,530(20℃)
・溶解度:水にわずかに溶解(0.11g/100g(25℃))
・分配係数:logPow 1.58(22℃)
・換算計数:1ppm=2.59mg/m3、1mg/m3=0.389ppm(20℃、1,013hPa)
(2)生産量等
(平成12年)
・生産量:3,031,692t
・輸出量:574,595t
・輸入量:11,028t
(3)用途
・ポリ塩化ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン-塩化ビニル共重合体の合成等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ1
・U.S. EPA グループA、ユニットリスク:4.4×10-6(1μg/m3)(IRIS)
・ACGIH グループA1
・日本産業衛生学会 第1群
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン ユニットリスク:1×10-6(1μg/m3)
(2)大気に関する基準
・オランダの基準 target value 1μg/m3
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 2.5ppm(6.5mg/m3)(暫定値)
・ACGIH TLV-TWA 1ppm(2.6mg/m3)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成13年度)届出排出量(大気):805t
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成9年度)地点数:287、検体数:1815、平均:0.19、最小:0.0077、最大:8.5
(平成10年度)地点数:324、検体数:3422、平均:0.22、最小:0.0091、最大:9.7
(平成11年度)地点数:330、検体数:3575、平均:0.17、最小:0.0079、最大:7.0
(平成12年度)地点数:336、検体数:3686、平均:0.16、最小:0.0022、最大:12
(平成13年度)地点数:360、検体数:3869、平均:0.11、最小:0.0025、最大:7.0
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成13年度)
(全地区)地点数:360、平均:0.11、最小:0.0025、最大:7.0
(一般環境)地点数:231、平均:0.062、最小:0.0025、最大:1.6
(沿道)地点数:56、平均:0.047、最小:0.0061、最大:0.2
(発生源周辺)地点数:72、平均:0.33、最小:0.0025、最大:7.0
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(1)主な知見
Nicholsonら(1984)は、米国の2つのポリ塩化ビニル工場に5年以上従事(平均曝露期間18年)した従業員491人(Niagara Falls 296人、死亡数44人、肝血管肉腫6例、West Verginia 195人、死亡数36人、肝血管肉腫4例)について検討し、SMRは、全がん142(観察地(Obs.):28、期待値(Exp.):19.7)、肝・胆道系がん2,380(Obs.:10、Exp.:0.42)であった。これに対し、WHO(1987)は、平均塩化ビニルモノマー曝露量を2,050mg/m3と見積もり、塩化ビニルモノマー曝露による肝・胆道系がん死亡のユニットリスクを3.6×10-7/μg/m3、全がん死亡のユニットリスクを4.5×10-7/μg/m3と推定した。また、WHO(1987)は、Nicholson(1984)が報告を行っている12のコホートから、肝・胆道系がん死亡についてユニットリスクを7.2×10-7/μg/m3と算定した。
US Equitable Environmental Health Study(USEEHS)は、米国の37の塩化ビニルおよびポリ塩化ビニル工場で1年以上従事した10,173人についての調査(1973年以前の従業年数は平均8.7年)である。WHO(1987)は、Barnes(1976)のデータを用いて、荷重曝露量を650ppm(1,665μg/m3)と見積もり、USEEHSの平均9年間曝露のデータからユニットリスクを0.75×10-8/μg/m3と推定した。これに、直線的量-反応関係を用いると、肝血管肉腫のユニットリスクは4.7×10-7/μg/m3と算出される。
Foxら(1976)は、英国のポリ塩化ビニル製造男性作業者7,409人の死因について検討し、SMRを全死因75.4、全がん90.7、原発性肝がん140.8(Obs.:1、Exp.:0.71)、他の肝がん322.6(Obs.:3、Exp.:0.93)とした。これに対して、Clement Associates(1987)は曝露量によるグループ分けを行って曝露量等の検討を行い、高濃度曝露群について、累積曝露量として2,244ppm-yearsと推定した。なお、高濃度曝露群のSMRは1,538(Obs.:2、Exp.:0.13)であった。以上の見積もりをもとに、肝がん(肝血管肉腫)のユニットリスクは1.1×10-6/μg/m3と算定される。
Simonatoら(1991)は、肝がんと塩化ビニルモノマー曝露との量反応関係及び肝以外のがんの調査を目的としたIARCのコーディネートした欧州の大規模コホート研究を実施し、SMRを肝がんで286.95(Obs.:24、Exp.:8.4、95%CI 186-425)とした。肝がんの過剰死亡は最初の曝露からの時間、雇用期間及び推定曝露量ランク及び推定曝露量と明らかな関連を示した。他の部位のがんについては、肺がんでは過剰死亡はなく、脳及びリンパ腺では曝露変数と明確な関連はなかった。この報告では肝がんについて累積曝露量で分類し、対応する相対リスクが算定されている。累積曝露量を250、1,250、4,000、8,000、12,000ppm-yearsと仮定すると、それに対応する肝がんの相対リスク(15 years of latency)が1、1.2、4.6、12.2、17.1であることから、肝がんのユニットリスクは、順に、6.2×10-8、3.5×10-7、5.4×10-7、5.2×10-7/μg/m3と算定される。
(2)指針値算出の考え方
上述の報告を考慮して算定結果を採用すると、ユニットリスクは3.6×10-7~1.1×10-6/μg/m3であり、概ねオーダーが一致している。肝血管肉腫を中心とする肝・胆道系がんに着目してリスクを総合的に判断すると、曝露評価における不確実性を考慮して、ユニットリスクとして得られたレンジの最大値にほぼ一致する、1.0×10-6程度が妥当なレベルと考えられる。
(3)指針値
以上より、塩化ビニルモノマーの指針値は、生涯リスクレベル10-5に相当する値として年平均値10μg/m3以下とする。
(中略)
(別添2-2)塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について
(中略)
(1)発がん性について
ヒトに対して発がん性を持っていることを示唆する疫学的データが相当数蓄積されており、塩化ビニルモノマーは人に対して発がん性があると評価できる。その標的臓器としては、肝・胆道系、脳神経系、呼吸器系、増血器系等が示唆され、特に、肝血管肉腫の高い発生率が報告されている。
動物を用いた実験では、ラット、マウス、ハムスターに対して、特に吸入曝露による腫瘍の発生が報告されており、種特異性がみられるが、全般的にみて、塩化ビニルモノマーを動物に経気道的に曝露した場合、発がん性を示すと評価できる。
(2)発がん性以外の毒性について
ヒトの慢性影響としては、門脈圧亢進、Raynaud現象、指端骨溶解症、強皮症様皮膚変化等が見られる。
また、塩化ビニルモノマー曝露によるヒトにおける奇形発生については、十分評価できるデータはなく、今後のデータの蓄積が期待される。
胎児への影響については、妊娠ラットに塩化ビニルモノマーを曝露した実験で、新生仔にヘパトーマが高率に発生したが、出産後も塩化ビニルモノマーに曝露しているため、胎仔への影響として評価するのは適当でなく、今後この面での研究が期待される。
(3)閾値の有無について
遺伝子障害性を持つことは多くの報告から明らかであるため、塩化ビニルモノマーについては、閾値がないとするのが妥当である。
(4)用量-反応アセスメント
塩化ビニルモノマーの毒性については、以下の事項を考慮して、動物実験データを参考にしつつ、疫学データを基本とし、閾値のない発がん性に関して量-反応アセスメントを行うことが適当である。
・塩化ビニルモノマーが遺伝子障害性を持つことを示す多くの証拠があることから、閾値のない発がん性として取り扱うことが妥当であること
・多くの疫学的研究報告がなされているが、疫学的研究における曝露量の評価の不確実性を考慮し、リスクアセスメントに際しては補足的に動物実験データを参照することが望ましいと考えられること
(5)指針の提案について
総合的に検討した結果、塩化ビニルモノマーのユニットリスクとして、1.0×10-6/μg/m3を、指針値として、生涯リスクレベル10-5に相当する値として年平均値10μg/m3以下を提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」(別添2-2)塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月31日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/t07-h1503.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○クロロホルム
1.指針値
1年平均値が18μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法/固体吸着-加熱脱着法/固体吸着-溶媒抽出法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成18年11月8日・中央環境審議会答申
平成18年12月20日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第061220001号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・揮発性を有する無色透明の液体で、蒸気には甘味がある
・常温で日光に長時間さらされたり、暗所でも空気が存在すると徐々に分解し、有毒なホスゲンを生じる
・比重:1.484(20/20℃)
・融点:-63.5℃
・沸点:61~62℃
・蒸気圧:21.3kPa(20℃)
・溶解性:7.2~9.3g/L(25℃)
・分配係数:logPow=1.97
・換算係数:1ppm=4.90mg/m3、1mg/m3=0.204ppm(25℃、l,013hPa)
(2)生産量等
(平成15年度)
・製造量及び輸入量の合計値:53,883t
(3)用途
・主に化学品の製造原料として使用され、フッ素系冷媒やフッ素樹脂の原料、医薬品(消毒剤)、ゴムやロウなどの溶剤、抽出溶媒等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ2B
・EU カテゴリー3
・U.S. EPA グループB2
・ACGIH グループA3
・DFG カテゴリー4
・NTP クライテリアR
・日本産業衛生学会 第2群B
(2)大気に関する基準
該当なし
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度(2005) 3ppm(14.7mg/m3)
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度 10ppm
・ACGIH TWA(2002) 10ppm(49mg/m3)
・DFG MAK(2005) 2.5mg/ m3
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成15年度)
届出排出量(大気):1,293t(55%がパルプ・紙・紙加工品製造業、18%が化学工業、5%が電気機械器具製造業)、
届出排出量(大気と水域合計):1,455t
廃棄物移動量:2,396t
届出外推計排出量:318t(245tが裾切り未満の事業所、57tが家庭。家庭からの排出+その他の排出を77tが水道由来でそのうち70tが大気排出と推定)
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成12年度)地点数:346、検体数:3,810、平均:0.35、最小:0.019、最大:4.7
(平成13年度)地点数:350、検体数:3,779、平均:0.29、最小:0.006、最大:3.1
(平成14年度)地点数:354、検体数:3,982、平均:0.27、最小:0.039、最大:4.2
(平成15年度)地点数:371、検体数:4,313、平均:0.24、最小:0.027、最大:2.3
(平成16年度)地点数:366、検体数:4,239、平均:0.26、最小:0.063、最大:1.8
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成16年度)
(全地区)地点数:366、平均:0.26、最小:0.063、最大:1.8
(一般環境)地点数:229、平均:0.24、最小:0.069、最大:1.7
(沿道)地点数:65、平均:0.24、最小:0.063、最大:1.3
(発生源周辺)地点数:72、平均:0.34、最小:0.082、最大:1.8
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
3.2 クロロホルム
近年、大気環境中の有機化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が集積されているが、なお不明確なところもあり、今後の解明を待つべき課題が少なくないことを十分認識しつつ、現段階でのクロロホルムの健康影響に関する知見から、現時点におけるクロロホルムのヒトヘの健康影響に関する判定条件について、以下の評価を行った。
(1)発がん性について
①発がん性に係る定性評価について
ヒトの疫学研究について、WHO(2004)やUSEPA(2001)によると、クロロホルムを含む塩素処理水の長期間摂取と膀胱がんの増加に関し、クロロホルム以外の副産物を考慮する必要があるため、クロロホルムのみの発がん性についての解明は不可能であるとしている。
その一方、動物実験による研究については、マウスに対する経口投与実験(NCI(米国国立がん研究所)1976; Roeら1979)及び吸入曝露実験(Naganoら1998、のちにYamamotoら(2002)として発表)において、尿細管腫瘍あるいは肝細胞腫瘍の発生が有意に増加したとする知見があり、また、ラットに対する経口投与実験(NCI1976; Jorgensonら1985)においても、尿細管腫瘍の発生が有意に増加したとする知見があることなど、発がん性を示す十分な証拠があると考えられる。
また、発がんのメカニズムについては、WHO(2004)やUSEPA(2001)によると、代謝産物が肝臓及び腎臓において細胞毒性を発現し、その修復過程において細胞増殖を介するメカニズムが強く示唆されているとともに、マウス及びラットとヒトとの間に、代謝メカニズムや発がんメカニズムの違いを示す明確な知見はなかった。以上の報告等から、クロロホルムは、ヒトに対する発がん性に関する情報が必ずしも十分ではないものの、ヒトヘの発がん性の可能性があると判断した。
②閾値の有無について
USEPA(2001)によると、クロロホルムは、多くの変異原性試験で陰性であり、陽性の結果となった試験の多くに疑問が存在し、クロロホルムには強い遺伝子障害性はなく、クロロホルムやその代謝物はDNAと容易に結合しないとされている。
このように、クロロホルムは、直接の遺伝子障害性はないか、あっても弱いものであり、発がん性に係る閾値が存在するものと判断した。
③発がん性に係る定量評価について
ヒトの疫学研究では、量-反応関係を示す十分な知見がない。
動物実験の研究では、発がんリスクに係る既存の定量評価として、WHO(2000)によるラットにおける腎腫瘍の発症をエンドポイントとしてのユニットリスク4.2×10-7/(μg/m3)とカリフォルニア州環境保護庁(CalEPA; 2005)による同じくラットにおける腎腫瘍の発症をエンドポイントとしてのユニットリスク5.3×10-6/(μg/m3)の2つが示されている。これらの定量評価は、経口曝露のデータから吸入曝露へ換算しリスク評価を行っている。
(2)発がん性以外の有害性について
①発がん性以外の有害性に係る定性評価について
吸入曝露による急性毒性として、ヒトの疫学研究から、麻酔作用が認められ、稀に肝壊死、腎尿細管壊死による肝不全、腎不全や心筋の断裂、不整脈等による心不全が認められている。
慢性毒性としては、動物実験では、Larsonら(1994a,b; 1996)、Templinら(1996a; 1998)、Kasaiら(2002)、Yamamotoら(2002)等の多くの研究において、吸入曝露及び経口投与のいずれにおいても、肝臓・腎臓内の組織学的な変化、血清中の酵素レベルの変動、鼻腔における骨化・壊死・増生・化生等が認められている。さらに、吸入曝露実験では、肝臓及び腎臓の重量変化も認められている。
動物実験で見られたこれらの発がん性以外の有害性については、代謝メカニズムや有害性の発現メカニズムに関する種差の存在を積極的に示す知見はないことから、ヒトにおいても発現する可能性があるものと考えられる。
生殖発生毒性に関する目立った知見はない。
②発がん性以外の有害性に係る定量評価
発がん性以外の有害性に係る定量評価では、WHO(2004)がイヌ経口投与における肝脂肪嚢胞をエンドポイントとして耐容濃度(TC)140μg/m3を、CalEPA(2000)がラット吸入曝露における肝臓および腎臓の病理学的変化のLOAELから、Chronic Referenced Exposure Level 300μg/m3を提言している。
日本産業衛生学会は、マウス吸入曝露におけるNOAELから、許容濃度14.7mg/m3を提言している。
吸入曝露実験による鼻腔影響に関しては、Yamamotoら(2002)によるBDF1マウスで骨肥厚(骨化)、嗅上皮の萎縮及び呼吸上皮化生が観察された25mg/m3(6時間/日、5日/週、2年)がLOAELであり、肝細胞増殖(LI)に関しては、Templinら(1998)によるBDF1マウスでの25mg/m3(6時間/日、5日/週、13週)がNOAELと考えらえる。
(3)定量的データの科学的信頼性について
クロロホルムに係る発がん性及び発がん性以外の有害性については、(1)及び(2)で記載したとおり、実験動物を用いた吸入曝露実験では、量-反応関係を示す知見が幾つか存在する。その中でも、曝露点が多数あり、量-反応関係が明確であるとともに最新のデータであることなどの観点から、Yamamotoら(2002)の発がん性及び鼻腔の骨肥厚、萎縮及び嗅上皮の呼吸上皮化生に関する定量的データが、相当の確度を有する数値と判断できる。
しかしながら、観察された有害影響の発現メカニズムについて、さらなる科学的知見の充実を要するため、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中央環境審議会:第7次答申)」における定量的データの科学的信頼性Ⅱに該当すると判断し、指針値を提案することとした。
(4)指針値の提案について(抄)
①発がん性に係るリスク評価について
クロロホルムに係る発がん性については、(3)に記載したとおり、科学的信頼性について相当の確度を有するYamamotoら(2002)による定量的データを用いて、リスク評価を行うことが適当であり、雄マウスの腎がんが有意な増加を示さない濃度である5ppm(25mg/m3)をNOAELとし、種差、個体差及び発がんの影響の重大性を考慮した不確実係数に加え、断続曝露から連続曝露への補正を加味した総合的な係数(1,400)を用いた結果、有害性に係る評価値は、18μg/m3と算出された。
②発がん性以外の有害性に係るリスク評価について
クロロホルムに係る発がん性以外の有害性については、(3)に記載したとおり、科学的信頼性について相当の確度を有するYamamotoら(2002)による定量的データを用いて、リスク評価を行うことが適当であり、雄マウスの鼻腔の骨肥厚、萎縮及び嗅上皮の呼吸上皮化生を引き起こす最低濃度である5ppm(25mg/m3)をLOAELとし、LOAELを用いること、種差並びに個体差を考慮した不確実係数に加え、断続曝露から連続曝露への補正を加味した総合的な係数(1,400)を用いた結果、有害性に係る評価値は18μg/m3と算出された。
③指針値の提案について
発がん性に係る評価値及び発がん以外の有害性に係る評価値は、ともに18μg/m3と算出された。よって、クロロホルムの指針値を年平均値18μg/m3以下とすることを提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」(別添2-2)クロロホルムに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-4.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月8日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第八次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/08.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,2-ジクロロエタン
1.指針値
1年平均値が1.6μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法/固体吸着-加熱脱着法/固体吸着-溶媒抽出法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成18年11月8日・中央環境審議会答申
平成18年12月20日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第061220001号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・クロロホルム様の臭気がある物質で、常温常圧下では無色油状の液体
・無水状態では鉄、銅は腐食しないが、アルミニウムに対しては強い溶解性あり
・揮発性が高く、引火性があり、煙の多い炎を伴って燃焼
・比重:1.2569(20/4℃)
・融点:-35℃
・沸点:83℃
・蒸気圧:8.5kPa(20℃)
・溶解性:8.69g/L(20℃)
・分配係数:logPow=1.76
・換算係数:1ppm=4mg/m3、1mg/m3=0.25ppm(25℃、1,013hPa)
(2)生産量等
(平成15年度)
・製造量及び輸入量の合計値:796,298t
(3)用途
・主に塩化ビニルモノマーやエチレンジアミン等の合成原料の他、フィルム洗浄剤、有機溶剤、殺虫剤、ビタミン抽出剤、燻蒸剤など
・1,2-ジクロロエタンを原料として生産される化学物質は、1,1,1-トリクロロエタン、エチレンジアミン、塩化ビニリデン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなど
・かつてはガソリンのアンチノック液としても使用されていたが、毒性や引火性を有するため、使用は減少
・1,2-ジクロロエタンの自然起源は知られていない
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ2B
・EU カテゴリー2
・U.S. EPA( グループB2, Inhalation Unit Risk 2.6×10-5/(μg/m3)(IRIS)
・ACGIH グループA4
・日本産業衛生学会 第2群B
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン ユニットリスク:2×10-6/(μg/m3)
(2)大気に関する基準
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン 70μg/m3(24時間平均)
・オランダの基準 limit value 1μg/m3、target value 0.1μg/m3
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 10ppm(40mg/m3)
・ACGIH TWA 10ppm(40mg/m3)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成15年度)
届出排出量(大気):603t(約80%が化学工業から排出。その他、倉庫業、その他の製造業、金属製品製造業、石油製品・石炭製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、パルプ・紙・紙加工品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、輸送用機械器具製造業、電気業から排出)
届出排出量(大気と水域合計):607t
廃棄物移動量:1,171t
届出外推計排出量:40t(届出対象業種の裾切り以下の事業所からの排出。大部分が大気排出と推定)
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成12年度)地点数:335、検体数:3,690、平均:0.19、最小:0.0075、最大:2.7
(平成13年度)地点数:349、検体数:3,739、平均:0.14、最小:0.0055、最大:1.9
(平成14年度)地点数:356、検体数:4,011、平均:0.13、最小:0.016、最大:1.3
(平成15年度)地点数:367、検体数:4,268、平均:0.13、最小:0.0075、最大:4.4
(平成16年度)地点数:366、検体数:4,230、平均:0.15、最小:0.0045、最大:2.7
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成16年度)
(全地区)地点数:366、平均:0.15、最小:0.0045、最大:2.7
(一般環境)地点数:229、平均:0.13、最小:0.0045、最大:1.7
(沿道)地点数:66、平均:0.11、最小:0.0075、最大:0.33
(発生源周辺)地点数:71、平均:0.24、最小:0.0047、最大:2.7
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
近年、大気環境中の有機化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が集積されているが、なお不明確なところもあり、今後の見解を待つべき課題が少なくないことを十分認識しつつ、現段階の1,2-ジクロロエタンの健康影響に関する知見から、現時点における1,2-ジクロロエタンのヒトヘの健康影響に関する判定条件について、以下の評価を行った。
(1)発がん性について
①発がん性に係る定性評価について
ヒトの疫学研究について、Benson&Teta(1993)によると、1,2-ジクロロエタン等による膵臓がんやリンパ・造血器系腫瘍の標準化死亡比(SMR)が有意に高まるという報告がある。
動物実験について、Naganoら(1998)は、ラットやマウスに1,2-ジクロロエタンを吸入曝露させた実験で、ラットの雄で乳腺の線維腺腫、雌で乳腺の腺がん、腺腫及び線維腺腫、皮下組織の線維腫等の発生率に有意な増加を認めた。マウスでは雄で肝臓の血管肉腫の発生率に有意な増加を認め、雌では肺の細気管支・肺胞上皮がん等の発生率に有意な増加傾向を認めた。これらの結果から、1,2-ジクロロエタンはラット及びマウスにおいて、発がん性を示す十分な証拠があると考えられる。
また、マウスやラットとヒトとの間に、1,2-ジクロロエタンに係る代謝メカニズムや発がんメカニズムの違いを示す明確な知見やヒトヘの発がん性を否定する目立った知見はなかった。
以上の報告等から、1,2-ジクロロエタンは、職業曝露等によるヒトヘの発がん性に関する情報が必ずしも十分ではないものの、ヒトヘの発がん性の可能性があると判断した。
②閾値の有無について
1,2-ジクロロエタンは、複数の知見から、動物実験によるin vitroの遺伝子障害性試験では、変異原性試験や染色体異常試験で陽性と判断できる。また、動物実験によるin vivoの遺伝子障害性試験では、小核試験では陰性を示すが、DNA障害性試験では陽性と判断できる。
このように、1,2-ジクロロエタンはin vivo及びin vitroのいずれにおいても遺伝子障害性を有すると判断できることから、発がん性に係る閾値はないものと判断した。
③発がん性に係る定量評価について
ヒトの疫学研究では、量-反応関係を示す知見が乏しい。
発がんリスクに係る既存の定量評価では、主にNCI(1978)の経口投与による発がん性試験結果が採用されているが、投与経路が吸入曝露ではないため、経口曝露のデータから吸入曝露へ換算してリスク評価を行っている。
これに対して、前述のNaganoら(1998)のデータは吸入曝露の実験であり、より信頼性の高い研究であると考えられ、現時点ではNaganoらの研究を根拠にリスク評価を行うのが最も妥当であると判断した。
(2)発がん性以外の有害性について
①発がん性以外の有害性に係る定性評価について
ヒトの疫学研究から、高濃度の曝露による急性毒性として、神経系、肺、肝臓及び腎臓への顕著な影響が示唆され、同様の影響は比較的低濃度の職業曝露等でも報告されており、さらに、早産、心臓及び神経管奇形のリスクの増加に係る報告もある。
実験動物を用いた吸入曝露実験では、高濃度曝露で死亡した動物の肺、肝臓、腎臓で変性が認められた。一方、比較的低濃度を長期間にわたって曝露させた実験の殆どで、曝露に関連した影響は認められていない。国際機関の評価では、慢性吸入曝露の実験結果に基づき、肝臓やその他の臓器の病理学的組織変化が認められない濃度からNOAELを設定している。
生殖発生毒性については、動物実験では、催奇形性があるとした証拠はなく、経口投与および吸入曝露のいずれでも生殖発生毒性が認められないことを考慮すると、ヒトヘの生殖発生毒性については、現時点で十分な証拠があるとは言えないと判断した。
②発がん性以外の有害性に係る定量評価について
国際機関等の定量的リスク評価の結果は、慢性曝露実験によるNOAELが10ppm(40mg/m3)から100ppm(400mg/m3)までの範囲となっている。WHOが根拠として採用した研究は30年以上前のものであり、実験施設や曝露条件の精度などの点において、1980年以降の論文を根拠としたCalEPAやU.S.DHHSの評価の方が、信頼性が高いと考えられる。CalEPAが根拠としたSpreaficoらの研究では、著者自身が50ppm以上の群で肝酵素の有意な上昇(肝毒性の兆候)が見られたことの解釈に慎重であることから、NOAELを10ppmとすることに疑問が残る。
したがって、3機関の中では、Cheeverら(1990)のSDラットを用いた2年間の吸入曝露実験を根拠としたU.S.DHHSの評価が妥当であると判断した。
(3)定量的データの科学的信頼性について
1,2-ジクロロエタンに係る発がん性及び発がん性以外の有害性について、(1)及び(2)に記載したとおり、実験動物を用いた吸入曝露実験では、量-反応関係を示す知見が幾つか存在している。その中でも、発がん性については、量-反応関係を評価する上での十分なデータが存在し、かつ低濃度吸入曝露実験であるNaganoら(1998)の研究に関する定量的データが、発がん性以外の有害性については、影響の毒性学的意義が明確であり、かつ量-反応関係を評価する上での十分なデータが存在するCheeverら(1990)の雌雄ラットの諸臓器への影響に関する定量的データが相当の確度を有する数値と判断できる。
しかしながら、両方の研究ともに有害影響の発現メカニズムやヒトヘの外挿についてさらなる科学的知見の充実を要するため、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中央環境審議会:第7次答申)」における定量的データの科学的信頼性Ⅱに該当すると判断して、指針値を提案することとした。
(4)指針値の提案について(抄)
指針値の算出については、「指針値算出の具体的手順(改訂)」に従い、発がん性に係るリスク評価、発がん性以外の有害性に係るリスク評価について検討したうえで、実施することとしている。
①発がん性に係るリスク評価について
1,2-ジクロロエタンに係る発がん性については、(3)に記載したとおり、科学的信頼性について相当の確度を有するNaganoら(1998)による定量的データ(詳細データは同一の研究を報告した中央労働災害防止協会日本バイオアッセイセンター(1991)を参照した。)を用いて、リスク評価を行うことが適当である。具体的には、雌ラットの乳腺腫瘍(腺がん、腺腫、線維腺腫)をエンドポイントとしてベンチマーク濃度(BMC)を求め、低濃度域に直線外挿した結果、ユニットリスクは6.1×10-6/(μg/m3)と算出され、1,2-ジクロロエタンの発がん性に係る評価値は、10-5の生涯過剰発がんリスクに対応する大気中濃度として、1.6μg/m3と算出された。
②発がん性以外の有害性に係るリスク評価について
1,2-ジクロロエタンに係る発がん性以外の有害性については、(3)に記載したとおり、科学的信頼性について相当の確度を有するCheeverら(1990)による定量的データを用いて、リスク評価を行うことが適当である。具体的には、諸臓器への影響が認められなかった濃度である50ppm(200mg/m3)をNOAELとし、種差、個体差を考慮した不確実係数に加え、断続曝露から連続曝露への補正も加味した総合的な係数(480)を用いた結果、有害性に係る評価値は、420μg/m3と算出された。
③指針値の提案について
以上より、発がん性に係る評価値と発がん性以外の有害性に係る評価値は、それぞれ、1.6μg/m3、420μg/m3と算出された。よって、指針値の算出手順に基づき、両値を比較し低い方の数値を採用することにより、1,2-ジクロロエタンの指針値を年平均値1.6μg/m3以下とすることを提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」(別添2-3)1,2-ジクロロエタンに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-5.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月8日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第八次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/08.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○水銀
1.指針値
1年平均値が40ngHg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:金アマルガム捕集法
分析方法:冷原子吸光法
3.設定経緯
平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成15年7月31日・中央環境審議会答申
平成15年9月30日・環境省環境管理局長通知(環管総発第030930004号)
(注)水銀については、平成27年の大気汚染防止法改正により、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するための排出規制が導入され、同法に基づく「有害大気汚染物質」からは削除されたが、環境中の水銀による健康リスクの低減を図ることは水俣条約の趣旨からも重要であることから、そのための指針となる数値(指針値)については維持し、大気モニタリングの評価や事業者による排出抑制努力の指標として引き続き活用することとされた。
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・金属水銀は、常温で液体である唯一の金属で、常温でも飽和蒸気濃度が非常に高い
・融点:-38.89~-38.87℃
・沸点:356.58~356.9℃
・比重:13.546~14.2
・飽和蒸気濃度:13.2mg/m3(20℃)
・水への溶解度:水に不溶
(2)生産量等
(平成12年)
・生産量:93,483kg(供給量)
・輸出量:38,851kg
・輸入量:6,901kg
(3)用途
・HC電池、水銀塩類(昇汞、銀朱など)、蛍光灯、体温計及び計量器、電機機器用、アマルガム(歯科用、合金用)、合成化学用(触媒)、苛性ソーダ製造用、塩素電解用など
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ3
・U.S. EPA グループD
(2)大気に関する基準
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン 1μg/m3(年平均)
(3)職業曝露に関する基準
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度
0.05mg/m3(水銀として、水銀及びその無機化合物(硫化水素を除く))
0.01mg/m3(水銀として、アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものに限る)
・日本産業衛生学会 0.025mg/m3(水銀蒸気)
・ACGIH TLV-TWA 0.025mg/m3(水銀蒸気を含む無機水銀)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成13年度)届出排出量(大気):325kg、届出排出量(合計):4,659kg、届出外推計排出量:1,112kg
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成9年度)地点数:13、検体数:65、平均:2.8、最小:2.0、最大:4.0
(平成10年度)地点数:179、検体数:1697、平均:2.8、最小:0.27、最大:10
(平成11年度)地点数:260、検体数:2704、平均:2.9、最小:0.050、最大:50
(平成12年度)地点数:283、検体数:3003、平均:2.6、最小:0.14、最大:15
(平成13年度)地点数:281、検体数:3056、平均:2.3、最小:0.22、最大:6.0
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成13年度)
(全地区)地点数:281、平均:2.3、最小:0.22、最大:6.0
(一般環境)地点数:197、平均:2.2、最小:0.22、最大:4.3
(沿道)地点数:33、平均:2.6、最小:0.83、最大:6.0
(発生源周辺)地点数:51、平均:2.4、最小:0.45、最大:4.1
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(1)主な知見
Fawerら(1983)は、各種の水銀作業従事者26名の手の振戦を加速度計で測定し、対照群25名と比較したところ、最も加速度の大きい周波数が有意に高周波側にシフトしていた。曝露濃度は0.026mg/m3(TWA)で平均15.3年、尿中水銀濃度は作業者で20μg/gCre(Creatinine)、対照は6.0μg/gCreであった。
Ngimら(1992)は、歯科医98名と対照者54名とを対象に神経行動学的検査を行ない、finger tapping、視覚-運動機能、短期記憶など多くの項目に有意差を見出した。ほとんどの対象者では、歯科医としての就業期間(平均5.5年、最大24年)を通じて曝露濃度に大きな変化はなかったと推測している。気中水銀濃度は0.014mg/m3(TWA)と報告されているが、尿中水銀についての記載はない。
Langworthら(1997)は、スウェーデンの歯科医及び歯科看護婦22名ずつを調査した。パーソナルサンプラーで測定した水銀曝露量は1.8μg/m3(歯科医)、2.1μg/m3(歯科看護婦)であった。全血水銀濃度は18nmol/L(平均、以下同じ。換算すると3.6ng/mL)、血漿水銀濃度は5.1nmol/L(1ng/mL)、尿中水銀濃度は3.0nmol/mmol Cre(5.3μg/gCre)であった。3つのアンケート調査、Q16、Eysenck Personality Inventory(EPI)、Profile of Mood Scales(POMS)の内Q16では訴えのある症状数が性・年齢を揃えた対照群に比べて多かった。しかし、水銀の曝露指標との関連は弱く、著者らは他の仕事と関連する要因(例えばストレス)の反映か、もしくは偶然であろうとしている。なお、尿中アルブミンやN-acetyl-β-glucose-aminidase(NAG)の濃度は対照と差がなかった。
(2)指針値算出の考え方
優先取組物質となっているのは水銀及びその化合物であることから、両方について知見を集積してきたところであるが、一般大気環境中の水銀は、その大部分が水銀蒸気として存在し、他の化学形態は極めて微量であること等から、大気からの曝露が問題となるのは水銀(水銀蒸気)のみである。
以上から、指針値は水銀(水銀蒸気)について設定することとした。
考慮すべき影響は、慢性曝露による影響、特に中枢神経系における影響であると考えられる。これに関する報告をまとめると、職業曝露におけるLOAELに相当する気中濃度は14~26μg/m3の範囲にあると考えられる。さらに、曝露濃度の測定精度・曝露期間や問題とされた症状等の重症度、加えて尿中の水銀レベルから気中濃度への推定を行っている報告が有ることを考慮した上で総合的に判断すると、LOAELに相当する気中濃度は20μg/m3と考えることが可能である。
不確実係数としては、労働環境におけるデータを用いて一般環境における指針値を算出すること、NOAELを明確に示すことは困難でありLOAELに相当する気中濃度を用いて算出すること、仔は成獣よりも水銀蒸気に対して敏感な可能性が示唆されており、一般環境には乳幼児や高齢者などの一般的な考え方でも高感受性者と考えられる者が存在することなどの点を総合的に考慮し、トータルで不確実係数として500を用いることが適当であると考える。
(3)指針値
以上より、水銀の指針値は年平均値0.04μgHg/m3以下とする。
(中略)
(別添2-3)水銀に係る健康リスク評価について(抄)
4.総合評価
(中略)
(1)水銀蒸気の毒性及び閾値の有無について
水銀蒸気が発がん性を有するという確実な証拠はない。水銀蒸気の発がん性以外の影響については、急性の影響として、呼吸器系及び尿細管障害等が報告されている。また、慢性影響として、神経系、腎、免疫系、生殖等への影響の報告がある。このため、水銀蒸気の毒性については、閾値があるとして取り扱うことが妥当と考えられる。
(2)量-反応アセスメントについて
水銀蒸気の吸入曝露による慢性影響に関するデータを総合的に判断すると、LOAELに相当する気中濃度は、20μg/m3前後に存在すると考えることが妥当である。不確実係数としては、労働環境におけるデータを用いて一般環境における指針値を算出すること、NOAELを明確に示すことは困難でありLOAELに相当する気中濃度を用いて算出すること、仔は成獣よりも水銀蒸気に対して敏感な可能性が示唆されており、一般環境には乳幼児や高齢者などの一般的な考え方でも高感受性者と考えられる者が存在すること、などの点を総合的に考慮し、トータルで不確実係数として500を用いることが適当であると考える。
なお、日本人は欧米人に比し食事から多くのメチル水銀等を摂取しており、異なる化学形態の水銀への複合的な曝露を踏まえたリスク評価が望まれるが、このような毒性機序に基づいて評価を行うだけの知見が不足している。このため、本委員会においては、大気中の水銀の大半を占め、しかも、大気からの寄与が大きいとされる水銀蒸気の吸入曝露による影響を中心に評価を行うこととした。
(3)曝露アセスメントについて
化学形態別、媒体別の曝露状況を踏まえ、吸入曝露で重要となるのは、水銀蒸気と考えた。また、アマルガム及び喫煙からの水銀蒸気の摂取については、現時点における正確な曝露量を把握できないこと等を踏まえ、環境目標の設定にあたっては考慮しないものとした。
(4)指針としての環境濃度の提案について
長期曝露による健康影響を未然に防止する観点から、水銀蒸気の長期曝露に係る指針値として、年平均値0.04μg/m3以下を提案する。
ちなみに、NO(A)ELに相当する気中濃度をほぼ2μg/m3と示している研究がひとつあったが、労働環境から一般環境に外挿することと、一般的な個体差から不確実係数を50とすると、2μg/m3から計算すれば上述の指針値と同じ年平均値0.04μg/m3以下となる。しかしながら、新生仔期動物の曝露に対する感受性が高いというデータもあり、その定量的評価が定まっていないことは、今後の検討に際して考慮すべき点と考えられる。
(以下略)
9.参考資料
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」(別添2-3)水銀に係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02-3.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月31日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/t07-h1503.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成27年1年23日・中央環境審議会「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀の大気排出対策について(答申)」 http://www.env.go.jp/press/files/jp/25919.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第5部第2章)大気中の水銀の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-5-2.pdf 【NIES保管ファイル】
○ニッケル化合物
1.指針値
1年平均値が25ngNi/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:①フィルタ捕集-ふっ化水素酸・硝酸・過塩素酸法/(フィルタ捕集-塩酸・過酸化水素水法/フィルタ捕集-硝酸・塩酸(王水)法)、②フィルタ捕集-圧力容器法、③フィルタ捕集-溶媒抽出法
分析方法:①誘導結合プラズマ発光分析法/電気加熱原子吸光法/フレーム原子吸光法/(誘導結合プラズマ質量分析法)、②誘導結合プラズマ質量分析法/誘導結合プラズマ発光分析法/電気加熱原子吸光法/フレーム原子吸光法、③誘導結合プラズマ発光分析法/電気加熱原子吸光法/フレーム原子吸光法
※いずれの測定方法においても事前の回収率確認は必要事項であるが、括弧内の方法は特に注意を要するもの。
3.設定経緯
平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成15年7月31日・中央環境審議会答申
平成15年9月30日・環境省環境管理局長通知(環管総発第030930004号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・融点:1,555℃(Merck Index 11th Ed.)、1,455℃(Patty)
・沸点:2,837℃
・比重:8.90(20℃)
・蒸気圧:1.000mmHg(1,810℃)
(2)生産量等
(平成12年)
・生産量:36,230t
・輸出量:963t(ニッケルの塊)
・輸入量:57,894t(ニッケルの塊)
(3)用途
・ステンレス鋼と種々の耐熱・耐蝕合金の製造、溶接、メッキ、触媒、蓄電池等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC (ニッケル化合物)グループ1、(金属ニッケル)グループ2B
・U.S. EPA (精錬粉じん)グループA(ユニットリスク:2.4×10-4(1μg/m3)(IRIS))、(二硫化三ニッケル)グループA(ユニットリスク:4.8×10-4(1μg/m3)(IRIS))
・ACGIH (金属ニッケル)グループA5、(水溶性ニッケル)グループA4、(難溶性ニッケル)グループA1、(二硫化三ニッケル)グループA1
・日本産業衛生学会 (ニッケル化合物)第1群、(ニッケル(金属))第2群B
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン (ニッケル精錬粉じん)ユニットリスク:3.8×10-4(1μg/m3)
(2)大気に関する基準
(情報なし)
(3)職業曝露に関する基準
・日本産業衛生学会許容濃度 1mg/m3
・ACGIH TLV-TWA 1.5mg/m3(金属ニッケル)、0.1mg/m3(水溶性ニッケル)、0.2mg/m3(難溶性ニッケル)、0.1mg/m3(二硫化三ニッケル)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成13年度)
届出排出量(大気):1.5t(ニッケル)、11.5t(ニッケル化合物)
届出排出量(合計):25t(ニッケル)、256t(ニッケル化合物)
届出外推計排出量:1,518t(ニッケル)、292t(ニッケル化合物)
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng-Ni/m3)
(平成9年度)地点数:248、検体数:1608、平均:9.5、最小:1.0、最大:393
(平成10年度)地点数:270、検体数:2801、平均:7.3、最小:1.4、最大:72
(平成11年度)地点数:274、検体数:2972、平均:6.0、最小:1.3、最大:43
(平成12年度)地点数:285、検体数:3063、平均:6.4、最小:0.50、最大:47
(平成13年度)地点数:275、検体数:2994、平均:6.2、最小:0.15、最大:44
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng-Ni/m3)
(平成13年度)
(全地区)地点数:275、平均:6.2、最小:0.15、最大:44
(一般環境)地点数:192、平均:5.2、最小:0.15、最大:23
(沿道)地点数:31、平均:6.7、最小:2.1、最大:26
(発生源周辺)地点数:52、平均:9.7、最小:1.5、最大:44
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(1)主な知見
WHO欧州大気質ガイドライン(Air Quality Guidelines for Europe;WHO 2000)では、ノルウェイ、カナダ、英国の3つのニッケル精錬所の情報からユニットリスク(UR)を算定している。すなわち、
・Kristiansand精錬所のデータ(Magnusら, 1982)によると、鼻と喉頭のがんの平均の相対危険度は3.7となる。初期の曝露濃度は、1970年代前半の測定値の0.1~0.8mg/m3よりはるかに高く3mg/m3以上であった可能性が高い。更に曝露期間が一生の4分の1とすると平均の1日当たり生涯曝露濃度は164g/m3となる。そこでKristiansand精錬所のデータによるURは5.9×10-4/μg/m3である。
・Copper Cliff精錬所のデータ(Chovilら, 1981)でも上と同じように計算できる。すなわち相対危険度は8.7で、平均曝露期間が6年で、時間加重平均で100mg/m3程度の曝露を毎日8時間受けると、平均の1日当たり生涯曝露濃度は1.9mg/m3となる。そこでURは1.5×10-4/μg/m3である。
・さらにClydach精錬所の疫学データ(Dollら, 1977)では平均の曝露期間が10.5年、平均曝露濃度が10mgNi/m3以上とすると、平均の1日当たり生涯曝露濃度は329g/m3となる。肺がんの相対危険度は6.2と推定されている(Dollら, 1977)から、ニッケルによる肺がんによる死亡の増加URは5.7×10-4/μg/m3である。
以上から、3ヵ所の精錬所のデータから計算されたURの範囲は1.5×10-4~5.7×10-4/μg/m3で比較的近い値であり、これらの幾何平均値を求め、ニッケル精錬粉塵の1μg/m3に対して、生涯リスクを3.8×10-4としている(10-5リスクは0.025μg/m3)。
(2)指針値算出の考え方
ニッケル精錬所以外ではヒトの発がんに関する報告がないこと、発がんに関連するニッケル化合物の化学形態が決定されていないことなど、いくつかの問題点はあるものの、3つのニッケル精錬所で働く労働者を対象とした研究より、WHO(2000)はニッケル化合物の発がんに対するユニットリスク値として3.8×10-4/μg/m3を算出しており、これを採用することが適当と考える。
(3)指針値
以上よりニッケル化合物の指針値は、生涯リスクレベル10-5に相当する値として年平均値0.025μgNi/m3以下とする。
(中略)
(別添2-4)ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(抄)
(中略)
4.総合評価
ニッケル精錬所で働く労働者において、肺および鼻腔がんが起こることはこれまでの疫学研究で明らかである。ニッケル精錬所で発生する物質としては、金属ニッケル、ニッケル酸化物、ニッケル硫化物、水溶性ニッケル化合物、ニッケルカルボニルの他に、使用する鉱石によりクロム、砒素、マンガン、コバルト、銅、鉄などがあり、さらに精錬過程では硫酸や亜硫酸も現れる。これらがニッケルの健康影響評価を難しくしていることは否めない。このうち、金属ニッケルについては疫学研究で発がん性を示す根拠は見つかっていない。
3つのニッケル精錬所で働く労働者を対象とした研究より、WHO(2000)はニッケル化合物の発がんに対するユニットリスク値として3.8×10-4/μg/m3を公表(1987年には4×10-4/μg/m3)しており、これより10-5リスクとして年平均値0.025μgNi/m3以下が算出される。この値はEPA(IRIS 1992)が算出した値と大体似通っている。しかしながら、以下の問題点も指摘されている。すなわち、①ニッケル精錬所以外ではヒトの発がんに関する報告がない、②発がんに関連するニッケル化合物の化学形態が決定されていない、および③ニッケル化合物間に相互作用が考えられる。また、④ニッケルの精錬過程においてラテライト鉱では少量のクロムを含み、その他の鉱石(硫化鉱、砒化鉱)では砒素の混入がありうるが、これらの金属と肺がんとの関連に言及しているデータはない。その上、⑤硫酸や亜硫酸はこれら精錬過程で現れるので、鼻腔がんに関連した可能性もあろう。
このような状況下で"ニッケル化合物の一般環境における指針値"を設定するに当たり、以下に示す選択肢が可能となる。
(1)上述の問題点にもかかわらず、ニッケル化合物のヒトへの発がん影響を鑑み、一般環境にニッケル精錬所から得られた0.025μgNi/m3を外挿する。
(2)発がん性研究に疑義があるとして、動物実験結果から算出された非がん毒性の水溶性ニッケル化合物のRfC 0.17μgNi/m3を用いる。
(3)EPA(IRIS)は、2003年現在ニッケル精錬粉塵硫化ニッケルについては発がん性ありとしているが、経口吸入によるRfCを定めていない。したがって、我が国においても同様に指針値を設定しない。
IARC(1989)は最終的な安全性の観点において、全てのニッケル化合物をひとつのグループとして扱い、もっとも重篤な影響が出た化学形態の場合の結果に従って評価すべきとしている。また、NIOSHもニッケル精錬作業者の疫学デ-タと動物実験デ-タから「反証がない以上、金属ニッケルと全ての無機ニッケル化合物は浮遊性の時は発がん性があると考えるべきである」としている。この認識下で非発がん性データ由来のRfC値を選択することには多少抵抗があろう。
一方、我が国における大気モニタリングの最近の調査では、2001年度のデータで一般環境のニッケル化合物の平均濃度が0.0052μgNi/m3(192地点、範囲0.00015~0.023μgNi/m3)および沿道で0.0067μgNi/m3(31地点、0.0021~0.026μgNi/m3)であり、発生源周辺52地点ですら平均0.0097μgNi/m3(範囲0.0015~0.044μgNi/m3)であった。これらの化学形態を分析した報告はないが、我が国における目標達成の実行性とともにヒトにおけるニッケル化合物の発がん性を重視すると、精錬所という特殊な環境下での発がん性データから得られた年平均値0.025μgNi/m3以下を指針値として一般環境に外挿することに現段階で問題があるとは思われない。これにより、我が国の大気からのニッケル化合物曝露による有害影響の予防・防止が機能すると期待される。但し、今回の設定はニッケル精錬作業者の発がんに関する疫学的研究に対して科学的反証がこれまでなされていなかったことを前提としており、今後ニッケル化合物の有害性に関する新たな知見の集積が図れた場合、それに即した指針値の見直しが行われるべきである。
9.参考資料
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」(別添2-4)ニッケル化合物に係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/mat_02-4.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成15年7月31日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」 https://www.env.go.jp/council/toshin/t07-h1503/t07-h1503.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第5部第1章)大気粉じん中の重金属類の測定方法(多元素同時測定方法) https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-5-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○ヒ素及び無機ヒ素化合物
1.指針値
1年平均値が6ngAs/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:①フィルタ捕集-圧力容器法、②フィルタ捕集-硝酸・硫酸法
分析方法:①誘導結合プラズマ質量分析法/水素化物発生原子吸光法/水素化物発生誘導結合プラズマ発光分析法、②水素化物発生原子吸光法/水素化物発生誘導結合プラズマ発光分析法
3.設定経緯
平成22年10月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成22年10月15日・中央環境審議会答申
平成22年10月15日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第101015002号、環水大大発第101015004号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
①ヒ素
・第15族元素の半金属としての性質があり、主に3価と5価の化合物をつくる
・単体としてのヒ素は通常銀灰色の結晶
・比重:5.72
・融点:817℃(35.5気圧)
・昇華点:615℃
・他にも黄色、黒色の同素体がある
②ヒ化水素
・沸点:-2.5℃
・気体で、速やかに酸化される
③ヒ酸
・比重:2.0~2.5
・通常、H3AsO4・1/2H2Oの無色吸湿性の結晶で水、アルカリ、グリセリンに溶ける
④三酸化二ヒ素
・常温で固体、無定形と結晶がある
・融点:275℃(立方晶系)、融点:313℃(単斜晶系)
・沸点は465℃
・溶解度:2.1g/100mL(常温の水)、溶ける速度は遅い
・水に溶けると弱酸の亜ヒ酸(As(OH)3)になる
・塩酸、硫酸、水酸化ナトリウムに溶解
(2)生産量等
(平成18年)
・国内生産量:推定40t(金属ヒ素)、約50t(ヒ酸)(化学工業日報社2008)
・輸入量:金属ヒ素・三酸化二ヒ素・ヒ化水素合計で906t(ヒ素換算)((独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構2008)。
(3)用途
・液晶用ガラス原料、化合物半導体・シリコン半導体材料、木材防腐剤、ヒ酸塩(特にヒ酸石灰、ヒ酸鉛)原料、医薬品原料、その他染料の原料等
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ1
・U.S. EPA グループA
・ACGIH グループA1
・日本産業衛生学会 第1群
(2)大気に関する基準
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン Inhalation Unit Risk 1.5×10-3/(μg/m3)(生涯リスク10-5に相当する濃度:6.6ng/m3)
・EU Target Value 6ng/m3(PM10(1年以上の平均値)中の総含有量として)
・U.S. EPA Inhalation Unit Risk 4.3×10-3/(μg/m3)(生涯リスク10-5に相当する濃度2ng/m3)(無機ヒ素)、RfC 5×10-5mg/m3(ヒ化水素)
(3)職業曝露に関する基準
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度 (砒素として)0.003mg/m3(砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。))
・日本産業衛生学会許容濃度 0.003mg/m3(生涯リスク10-3の濃度)、0.0003mg/m3(生涯リスク10-4の濃度)
・ACGIH
ヒ素及び無機ヒ素化合物:TLV-TWA 0.01mg/m3(ヒ素として)
ヒ化水素:TLV-TWA 0.005ppm(0.016mg/m3)
・U.S.OSHA PEL 8-hour TWA 0.01mg/m3(無機ヒ素化合物)、0.5mg/m3(有機ヒ素化合物)
・U.S.NIOSH REL 0.002mg/m3、IDLH 5mg/m3
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成20年度)
届出排出量(大気):5.3t(99%以上を非鉄金属製造業が占める。その他、窯業・土石製品製造業、化学工業、一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)など)
届出外推計排出量:0.5t
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成16年度)地点数:308、検体数:3,489、平均:1.8、最小:0.22、最大:15
(平成17年度)地点数:343、検体数:3,890、平均:1.9、最小:0.23、最大:18
(平成18年度)地点数:349、検体数:3,866、平均:2.2、最小:0.14、最大:70
(平成19年度)地点数:344、検体数:3,867、平均:1.9、最小:0.14、最大:31
(平成20年度)地点数:344、検体数:3,712、平均:1.6、最小:0.14、最大:30
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成20年度)
(全地区)地点数:344、平均:1.6、最小:0.14、最大:30
(一般環境)地点数:221、平均:1.3、最小:0.14、最大:8.8
(沿道)地点数:66、平均:2.6、最小:0.26、最大:30
(発生源周辺)地点数:47、平均:1.5、最小:0.30、最大:9.6
注)発生源周辺は、測定対象物質のいずれかを製造・使用等している工場・事業場の周辺で行われたモニタリング結果である。必ずしも、ヒ素を製造・使用等している工場・事業場の周辺とは限らない。
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(1)発がん性について
①発がん性に係る定性評価について
ヒ素及び無機ヒ素化合物の曝露については、以下の理由により、ヒトへの発がん性の明らかな証拠がある。特にその吸入曝露については、ヒトの肺への発がん性の明らかな証拠がある。
・多数の疫学研究において、高濃度のヒ素及び無機ヒ素化合物を含む粉じんに曝露した労働者集団での肺がんの過剰死亡が、また、無機ヒ素化合物を含む治療薬を投与された患者群や無機ヒ素化合物を含む飲料水を飲んだ住民での膀胱、肺、皮膚がんの過剰死亡が、それぞれ認められていること。
・多数の動物実験において、無機ヒ素化合物の生体内代謝物である一部の有機ヒ素化合物の経口投与によって発がん性や発がん促進作用が認められていること。
・動物実験及びin vitro実験において、無機ヒ素化合物の生体内代謝物である有機ヒ素化合物は強力な遺伝子障害作用のみならず遺伝子発現障害作用を有することが示されていること。
②閾値の有無について
無機ヒ素化合物については、以下のとおり、遺伝子障害性を示す証拠がある一方で、遺伝子の変異を伴わない発がんメカニズムの存在を示唆する証拠もあることから、これらの科学的知見から閾値の有無について明確な結論を下すことは現段階では困難である。しかしながら、発がん性を有することは明らかであり、遺伝子障害性を有することを示す多くの科学的証拠が得られている現状を踏まえれば、リスク評価に当たって、ヒ素及び無機ヒ素化合物の発がん性には閾値がないと仮定して算出するのが妥当である。
・職業曝露を受けた労働者において、十分とは言えないものの、遺伝子障害性が認められていること。また、動物実験及びin vitro実験において遺伝子障害性が報告されていることから、発がん性に閾値が存在しない可能性があること。
・動物実験及びin vitro実験において、無機ヒ素化合物及びその代謝物のタンパク質への結合による生体機能調節、酸化ストレスの誘発などの影響による発がんメカニズムの存在が示唆されており、発がん曝露量に閾値が存在する可能性もあるものの、閾値を明確に示す証拠は十分得られていないこと。
③発がん性に係る定量評価について
ヒ素及び無機ヒ素化合物に係る発がん性については、銅製錬所等の労働者を対象とした多数の疫学研究において吸入曝露による様々な臓器のがん死亡が報告されている。中でも肺がんによる死亡については、米国ワシントン州Tacomaの銅製錬所等の3つのコホート研究において用量-反応関係を示す十分なデータがあることから、当該知見を用いて用量-反応アセスメントを行うこととした。なお、職業曝露以外についても、製錬所近隣地域等におけるいくつかの研究でがん死亡リスクの増加が示唆されたが、いずれも定量評価に用いるには不十分であった。
(2)発がん性以外の有害性について
急性毒性については、ヒトが高濃度のヒ素化合物の粉塵や蒸気を吸入した場合、消化器症状、中枢・末梢神経障害、鼻粘膜や呼吸器の刺激症状を示すことが報告されている。また、ヒト及び動物実験において、ヒ化水素への曝露での溶血作用が認められている。
慢性毒性については、ヒトで鼻及び呼吸器の粘膜刺激症状や慢性気管支炎が報告されている。実験動物については、ヒ化水素での脾臓の肥大及び血液毒性が報告されている。
生殖発生毒性については、ヒトについては妊娠中に曝露した労働者での影響の報告があるが、証拠は限定的と言える。実験動物では、無機ヒ素化合物での発生毒性について1件の報告があり、発生毒性を有する可能性が示唆される。
しかしながら、発がん性以外のヒトへの有害性に係るいずれの知見も曝露評価が不十分なこと等から、用量-反応アセスメントを行うことは困難である。また、動物実験データではヒ化水素での知見があるが、環境大気中において人がヒ化水素に曝露することは考えにくく、定量評価を行う知見としては不適切と判断した。さらに、動物実験の生殖発生毒性も報告数が少なく十分な証拠があるとは言えない。このように、吸入曝露による発がん性以外の有害性に係る適切な低濃度曝露領域における定量的データは、ヒト及び動物実験ともに得られなかった。
また、前述(1)③のとおり、発がん性についてヒトの定量的データを用いて用量-反応アセスメントが可能であることから、指針値算出手順に従えば必ずしも発がん性以外の有害性に係る評価値を算出する必要はない。以上のことから、発がん性以外の有害性について用量-反応アセスメントは行わないこととした。
(3)定量的データの科学的信頼性について
ヒ素及び無機ヒ素化合物に係る発がん性の定量的データについては、ヒトの発がん性について十分な定量的データが存在し、その科学的信頼性については相当の確度を有する疫学研究であると考えられる。しかしながら、曝露量推定に用いている尿中ヒ素濃度が食品や飲料水などの吸入以外の経路からのヒ素化合物の摂取の影響を受けることや、労働者が装着していた呼吸用保護具は装着の仕方によってその有効性に個人差があるなど、これらの疫学研究では労働者の曝露濃度の推定に関していくつかの不確実性が存在する。
以上のことから、定量的データの科学的信頼性は相当の確度を有するものの、曝露評価についてはいくつかの不確実性が存在し、さらなる科学的知見の充実を要することから、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中央環境審議会:第7次答申)」における定量的データの科学的信頼性Ⅱaに該当すると判断して、指針値を提案することとした。
(4)指針値の提案について(抄)
一般集団におけるヒ素曝露は、大部分が食品や飲料水の摂取による経口曝露である。ヒ素の経口曝露による健康影響としては、がんを始めとする様々な症状が認められている。一方、ヒ素を吸入した場合にも、労働者の疫学知見ではがんなど明らかな健康影響が認められている。
吸入曝露では肺がん、皮膚がんなど、経口曝露では膀胱がん、肺がん、皮膚がんなどが認められ多臓器にがんが発症するが、曝露経路によって発がんの様相は異なっている。曝露経路による発症メカニズムの違いは不明な点があるものの、高濃度の吸入曝露の条件下では肺がんの発症が疫学的に明らかであることから、有害大気汚染物質の健康リスクを低減する観点から、疫学知見により認められる吸入曝露による肺がん過剰死亡をエンドポイントとして指針値を検討することは妥当であると判断した。
なお、飲料水の摂取によるヒ素への曝露による健康影響については既に別途評価が行われ水質基準が設定されており、食品についても別途評価されつつある。ヒ素の曝露形態に鑑みれば、今後、これらの評価を踏まえた総合的な曝露経路の検討も考慮すべきであろう。
①発がん性に係るリスク評価について
ヒ素及び無機ヒ素化合物の発がん性については、米国ワシントン州Tacomaの銅製錬所等の3つのコホートに関する知見が最も信頼性のある定量データであることから、これらのコホート研究から求めた肺がん過剰死亡をエンドポイントとしたユニットリスクを求めた。ユニットリスクの算出に当たっては、Anacondaコホートについては最新の曝露評価による解析結果を用いて本委員会でユニットリスクを算出し、またTacoma及びRönnskärコホートについてはそれぞれの最新のリスク解析の結果を採用し、それらのユニットリスクの幾何平均ユニットリスクを求めた。Anaconda、Tacoma、Rönnskärコホートのユニットリスクは、それぞれ4.1×10-3、1.28×10-3、0.89×10-3/(μg/m3)である。それらを統合したユニットリスク(幾何平均)は、1.7×10-3/(μg/m3)と算出された。
以上により、ヒ素及び無機ヒ素化合物の発がん性に係る評価値は、10-5の生涯過剰発がんリスクに対応する大気中濃度として、6.0ng-As/m3と算出される。
②発がん性以外の有害性に係るリスク評価について
前述(2)のとおり、十分な定量的データがないこと等から、発がん性以外の有害性に係る評価値は算出しないこととした。
③指針値の提案について
以上より、ヒ素及び無機ヒ素化合物の指針値を年平均値6ng-As/m3以下とすることを提案する。ただし、測定分析の効率性を考慮し、本指針値案との比較評価に当たっては、当面、全ヒ素の濃度測定値をもって代用することで差し支えない。
(以下略)
9.参考資料
・平成22年10月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「ヒ素及びその化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/16392.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成22年10月15日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第九次答申)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/16390.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第5部第1章)大気粉じん中の重金属類の測定方法(多元素同時測定方法) https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-5-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○1,3-ブタジエン
1.指針値
1年平均値が2.5μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告
平成18年11月8日・中央環境審議会答申
平成18年12月20日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第061220001号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・常温常圧下では弱い芳香を有する無色の気体
・化学反応性に富み、熱又は酸素の存在下で容易に重合する
・可燃性が強く、空気と接触すると爆発性過酸化物を生成する
・比重:0.650(-6/4℃)
・融点:-108.966℃
・沸点:-4.5℃(760mmHg)
・蒸気圧:281kPa(25℃)
・溶解性:水に対して微溶〔735mg/L(25℃)〕。エタノール、エーテル、ベンゼン等の有機溶剤に対して可溶。アセトンには極めてよく溶ける。
・分配係数:logPow=1.99
・換算係数:1ppm=2.21mg/m3、1mg/m3=0.45ppm(25℃、1,013hPa)
(2)生産量等
(平成15年度)
・製造量及び輸入量の合計値:1,461,061t
(3)用途
・合成ゴム(SBR、NBR、BR、CR等)の原料、樹脂(ABS樹脂、MBS樹脂)の原料、合成ゴムラテックスの原料など
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC グループ2A
・EU カテゴリー1
・U.S. EPA Inhalation Unit Risk 3×10-5/(μg/m3)(0.08/ppm)(IRIS)
・ACGIH グループA2
・日本産業衛生学会 第1群
(2)大気に関する基準
・英国大気質基準 1ppb(2.25μg/m3)
(3)職業曝露に関する基準
・ACGIH TWA 2 ppm(4.4mg/m3)
・DFG 人に対する発がん物質であることを理由に許容濃度を定めず、技術指針を提示している
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成15年度)
届出排出量(大気):287t(大部分が化学工業からの排出。その他、ゴム製品製造業、食料品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、石油製品・石炭製品製造業等から排出)
届出排出量(大気と水域合計):292t、廃棄物移動量:11t
届出外推計排出量:4,966t(自動車等の移動発生源)、109t(家庭(たばこの煙))で、その多くが大気中に排出されたと推定
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成12年度)地点数:348、検体数:3,847、平均:0.32、最小:0.0039、最大:2.3
(平成13年度)地点数:378、検体数:4,087、平均:0.33、最小:0.0055、最大:3.3
(平成14年度)地点数:388、検体数:4,379、平均:0.26、最小:0.0050、最大:1.6
(平成15年度)地点数:402、検体数:4,664、平均:0.29、最小:0.0060、最大:2.1
(平成16年度)地点数:397、検体数:4,600、平均:0.26、最小:0.0060、最大:1.5
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成16年度)
(全地区)地点数:397、平均:0.26、最小:0.0060、最大:1.5
(一般環境)地点数:226、平均:0.20、最小:0.0060、最大:1.5
(沿道)地点数:102、平均:0.37、最小:0.0065、最大:1.0
(発生源周辺)地点数:69、平均:0.30、最小:0.030、最大:1.5
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
近年、大気環境中の有機化合物の測定及び健康影響に関する研究の進歩は著しく、多くの知見が集積されているが、なお不明確なところもあり、今後の見解を待つべき課題が少なくないことを十分認識しつつ、現段階の1,3-ブタジエンの健康影響に関する知見から、現時点における1,3-ブタジエンのヒトヘの健康影響に関する判定条件について、以下の評価を行った。
(1)発がん性について
①発がん性に係る定性評価について
ヒトの疫学研究について、Delzellら(2001)は、スチレンーブタジエンゴム(SBR)合成工場に1年以上勤務した経験を有する男性を対象とした疫学調査の結果、1,3-ブタジエンの累積曝露量や100ppmを超える高濃度曝露の頻度に応じて、白血病による死亡の相対リスク(RR)は増加し、明確な量-反応関係が認められたとしている。また、Downら(1987)の報告等では、ブタジエンモノマー製造工場で、1,3-ブタジエンに曝露されていた作業者では、非ホジキンリンパ腫(リンパ肉腫、細網肉腫)の標準化死亡比(SMR)の増加が報告されており、これらの疫学研究から、1,3-ブタジエンの累積曝露量とリンパ造血器系の悪性腫瘍による死亡率との間に、概ね因果関係の視点を満たしていることが認められる。
動物実験の研究について、米国のNational Toxicology Program(NTP; 1984,1993)及びMelnickら(1990)等の研究から、複数の系統のマウス及びラットに対する慢性吸入曝露実験において、複数の臓器に腫瘍の発生増加が認められ、マウスでは、複数の系統においてリンパ造血器系の悪性腫瘍を含む多種の腫瘍の発生増加が認められる。
マウス及びラットとヒトとの間に、1,3-ブタジエンに係る代謝メカニズムや発がんメカニズムの違いを明確に示す知見はなく、エポキシド化合物への代謝能に係る実験動物の種差、系統差が腫瘍発生における感受性の種差と整合していると認められる。
以上の報告等から、1,3-ブタジエンは、ヒトの発がん性が強く示唆された。
②閾値の有無について
1,3-ブタジエンの遺伝子障害性に係るヒトのin vivo試験において、十分とは言えないものの、高濃度の曝露下において、染色体異常などの項目で遺伝子障害性を示唆する報告がある。
ヒトのリンパ球等を用いた多くのin vitro試験で、1,3-ブタジエンの代謝産物であるモノエポキシド及びジエポキシドが遺伝子障害性を示す結果が報告されている。
以上の報告等から、1,3-ブタジエンは、生体内での代謝を通じて遺伝子障害性を有すると考えられ、発がん性に係る閾値はないものと判断した。
③発がん性に係る定量評価について
1,3-ブタジエンの発がん性に係る定量評価については、1990年代半ばまでは、動物実験データに基づくリスク評価が主流であったが、近年、ヒトの疫学データに基づくリスク推定が行われている。
ECHC(1999)は、DelzellらのSBR合成工場に関する研究結果のオリジナルデータを使用し、交絡要因を考慮した上で、白血病死亡の相対リスク(RR)を説明する最適なモデルを決定し、発がんポテンシーとして白血病のTC01(死亡率が1%増加する曝露濃度)を1.7mg/m3と決定した。このカナダの評価は、WHO(2001)にも用いられている。
また、USEPA(2002)は、前述のECHC(1999)の評価をモデル決定に利用しつつも幾つかの独自の考慮を加えて、発がんポテンシーをLEC01(死亡リスクが1%増加するとされる暴露濃度の95%信頼下限値)を0.56mg/m3と算出するとともに、ユニットリスクを0.08/ppmと推定している。
さらに、スウェーデンのカロリンスカ研究所(2004)は、DelzellらのSBR合成工場に関する研究を基礎として、新しい曝露推定量を用いて量-反応関係を推定し、平均相対リスクモデルを適用し、白血病死亡に対するユニットリスクを0.0088/ppmと推定している。
(2)発がん性以外の有害性について
急性毒性については、Wilson(1944)によると、1,3-ブタジエンの高濃度急性曝露により、中枢神経の抑制作用及び眼、呼吸器の粘膜と皮膚に対する刺激作用があることが知られている。一方、Himmelsteinら(1997)によると、1,3-ブタジエンは事故災害的な曝露を除けば、近代の労働環境の日常的な曝露条件下では、刺激作用や中枢神経抑制作用はおそらく認められないとされている。
慢性毒性については、ヒトの疫学研究では、わずかな血液学的所見の変化などごく限られた報告のみである。一方、Melnickら(1990)による実験動物を用いた慢性吸入曝露実験では、曝露65週の時点で貧血やMCV(平均赤血球容積)の増加など、造血器に対する影響等が報告されている。
生殖発生毒性に関連する報告は、全て動物実験によるものである。催奇形性や発生毒性を明確に示すデータは存在しない。一方、NTP(1993)では、雌マウスの卵巣萎縮の増加が比較的低濃度の曝露で観察されているが、雌マウスの老齢期の影響であるため、これらの低濃度曝露の範囲では繁殖に影響を与える可能性は低いことから、生殖発生毒性を総合的に評価する上では、影響の重大性は低いと判断された。
(3)定量的データの科学的信頼性について
1,3-ブタジエンに係る発がん性については、(1)で記載したとおり、疫学研究で量-反応関係を示す知見が幾つか存在する。その中でも、最も規模が大きく、詳細な曝露評価や共存物質等に対する適切な補正がなされているDelzellらのSBR合成工場に関する研究を基礎として、新しい曝露推定量を用いて量-反応関係を推定したスウェーデンのカロリンスカ研究所(2004)に係る定量的データが、相当の確度を有する疫学研究に基づいて算出された数値と判断できる。しかしながら、曝露に関する情報が最近収集したものであり、観察された有害影響の発現メカニズムについて、さらなる科学的知見の充実を要するため、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中央環境審議会:第7次答申)」における定量的データの科学的信頼性Ⅱに該当すると判断して、指針値を提案することとした。
(4)指針値の提案について(抄)
指針値の算出については、「指針値算出の具体的手順(改訂)」に従い、発がん性に係るリスク評価、発がん性以外の有害性に係るリスク評価について検討したうえで、実施することとしている。
①発がん性に係るリスク評価について
1,3-ブタジエンに係る発がん性については、(3)に記載したとおり、科学的信頼性について相当の確度を有するスウェーデンのカロリンスカ研究所(2004)による定量的データを用いて、リスク評価を行うことが適当である。
具体的には、リンパ造血器系の悪性腫瘍をエンドポイントに採用して、平均相対リスクモデルを用いた結果、有害性に係る評価値は、10-5の生涯過剰発がんリスクに対応する大気中濃度として、2.5μg/m3と算出された。
量-反応関係について直線関係を想定した回帰直線の傾きを0.0038/ppm-year、1μg/m3の連続的な職業性曝露から一般環境下での連続曝露への変換を行った累積曝露量を0.15ppm・year、バックグラウンドの白血病生涯累積死亡率を0.007とし、平均相対リスクモデルを用いると、
ユニットリスク = 0.007×(1+0.0038×0.15-1)/1 = 0.40×10-5/(μg/m3)
リスクレベルを10-5に該当する濃度 = 10-5/(0.40×10-5) = 2.5μg/m3
②発がん性以外の有害性に係るリスク評価について
1,3-ブタジエンに係る発がん性以外の有害性については、(2)で記載したとおり、動物実験において、雌マウスの卵巣萎縮をエンドポイントとする知見等、量-反応関係を評価できる知見がいくつか存在するが、実験が行われた曝露濃度の範囲では繁殖に影響を与える可能性は低く、発がん性以外の有害性に係る評価値を算出する必要性は極めて低いことから、有害性に係る評価値については算出しなかった。
③指針値の提案について
以上より、1,3-ブタジエンの指針値を年平均値2.5μg/m3以下とすることを提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」(別添2-4)1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-6.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月8日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第八次答申)」 http://www.env.go.jp/council/toshin/08.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○マンガン及び無機マンガン化合物
1.指針値
1年平均値が140 ng Mn/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:①フィルタ捕集-ふっ化水素酸・硝酸・過塩素酸法/(フィルタ捕集-塩酸・過酸化水素水法/硝酸・塩酸(王水)法)、②フィルタ捕集-圧力容器法
分析方法:①誘導結合プラズマ発光分析法/電気加熱原子吸光法/フレーム原子吸光法/(誘導結合プラズマ質量分析法)、②誘導結合プラズマ質量分析法/誘導結合プラズマ発光分析法/電気加熱原子吸光法/フレーム原子吸光法
※いずれの測定方法においても事前の回収率確認は必要事項であるが、括弧内の方法は特に注意を要するもの。
3.設定経緯
平成26年4月・中央環境審議会大気・騒音振動部会健康リスク総合専門委員会報告
平成26年4月30日・中央環境審議会答申
平成26年5月1日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第1405011号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・鉄に類似した灰白色の金属であるが、鉄よりも硬くて脆く、電気的には、鉄よりもさらに陽性
・酸に溶けやすく、空気中では表面が酸化を受ける
・α型、β型、γ型、δ型の4つの同素体があり、比電気抵抗が異なる
・マンガン粉末は火源の存在により爆発の危険性があり、水または水蒸気と反応して水素を生ずる
・アルミニウム粉じんと激しく反応して火災や爆発をもたらす可能性がある
・マンガン及びその化合物の物理化学的性質は以下の通り。
(マンガン)融点:1,244℃、沸点:1,962℃、蒸気圧:1mmHg(1,292℃)、水溶性:分解
(塩化マンガン(Ⅱ))融点:650℃、沸点:1,190℃、蒸気圧:10mmHg(778℃)、水溶性:723g/L(25℃)
(硫酸マンガン(Ⅱ))融点:700℃、沸点:850℃、水溶性:520g/L(5℃)
(四酸化三マンガン)融点:1,564℃、水溶性:不溶
(二酸化マンガン)融点:535℃で酸素原子を消失
(過マンガン酸カリウム)融点:<240℃(分解)、水溶性:63.8g/L(20℃)
(ホウ酸マンガン(8水和物))融点:-、水溶性:不溶
(炭酸マンガン(Ⅱ))融点:分解、水溶性:不溶
(メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル)融点:1.5℃、沸点:449℃、蒸気圧:4.7×10-2mmHg(20℃)、水溶性:不溶
(マンネブ)融点:200℃で分解、蒸気圧:7.5×10-8mmHg(25℃)、水溶性:6.0mg/L(25℃)、分配係数:0.62(推定値)
(マンコゼブ)融点:172℃で分解、蒸気圧:1.32×10-10mmHg(25℃)、水溶性:6.2mg/L(pH7.5、25℃)、分配係数:1.33
(2)生産量等
・輸入量:949,690t(平成20年、原料(鉱石、フェロマンガン等)のみ)
・輸入量:784.2千t(平成23年、原料の他に半製品を含み、また原料等からマンガンへの重量換算率が異なる)
(3)用途
・ステンレス、特殊鋼の脱酸及び添加材、アルミニウム、銅などの非鉄金属の添加材及び溶接棒の被覆材用であり、化学用は全体の5%前後である。
・塩化マンガン(Ⅱ)は、染色工業・医薬品、塩化物合成の触媒、塗料乾燥剤等、硫酸マンガン(Ⅱ)は、乾燥剤(塗料や印刷用インキ)、窯業用顔料、金属防錆、肥料(マンガン肥料)、農薬等、四酸化三マンガンは、乾電池、リチウムイオン電池、フェライト、二酸化マンガンは、乾電池、リチウムイオン電池、酸化剤(有機溶剤製造)、フェライト、ガラス工業(着色及び脱色)等、過マンガン酸カリウムは、マンガン・鉄などの除去剤、臭気・有機物の除去剤、繊維・樹脂・油脂などの漂白剤等、ホウ酸マンガンは、ワニス、油などの乾燥剤、炭酸マンガン(Ⅱ)はマンガン塩原料、飼料添加剤、顔料、マンガン、フェライト等の製造に使用されている。
・メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル(MMT)は、米国、カナダ等ではガソリンのオクタン価向上剤としての使用があったが、日本では、MMTがエンジン内で燃焼したときに生じるマンガン粒子がエンジン部材に堆積し悪影響を及ぼすとの問題が指摘されており、使用されたとの実績を示す報告はない。
・マンネブ、マンコゼブは果樹、野菜、花き等の農薬(殺菌剤)として使用されており、散布などの際に一部が大気へも侵入していると考えられるが、ほとんどが土壌に付着していると考えられる。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・U.S. EPA グループD
(2)大気に関する基準
・WHO欧州事務局大気質ガイドライン 0.15μg/m3
・U.S. EPA IRIS 0.05μg/m3(RfC)
・U.S.DHHS, ATSDR 0.3μg/m3(MRL)
・カナダ保健省 0.05μg/m3(RfC)
・カリフォルニア州EPA 0.09μg/m3(REL)
(3)職業曝露に関する基準
・労働安全衛生法作業環境評価基準管理濃度 マンガン及びマンガン化合物(塩基性酸化マンガン化合物は除く) 0.2mg/m3(マンガンとして)
・労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則抑制濃度 マンガン及びマンガン化合物(塩基性酸化マンガン化合物は除く) 0.2mg/m3(マンガンとして)
・日本産業衛生学会許容濃度 マンガン及びマンガン化合物(有機マンガン化合物は除く) 0.2mg/m3(総マンガンとして)
・OSHA PEL マンガン及び無機マンガン化合物、フューム 5mg/m3(天井値、マンガンとして)
・NIOSH REL マンガン及び無機マンガン化合物、フューム 1mg/m3(時間荷重平均値、マンガンとして)、3mg/m3(短時間限界値、マンガンとして)
・ACGIH TLV-TWA マンガン(元素及び無機マンガン化合物)TLV-TWA 0.1mg/m3(吸引性粒子状物質 (inhalable particulate matter))、TLV-TWA 0.02mg/m3(吸入性粒子状物質 (respirable particulate matter))
・DFG MAK マンガン及び無機マンガン化合物、フューム 0.2mg/m3(inhalable、マンガンとして)、0.02mg/m3(respirable、マンガンとして)
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成23年度)
(マンガン)届出排出量(大気):46.1t(12t強(約26%)が輸送機械器具製造業から排出。その他、非鉄金属製造業、一般機械器具製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、化学工業から排出)、届出外推計排出量:1.1t(石炭火力発電所からの排出)
(有機マンガン化合物)届出排出量(土壌):2,413t(マンガン換算300t)
7.環境中における検出状況(設定時)
<一般環境(経年変化)>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成19年度)地点数:292、検体数:3,504、平均:28、最小:0.55、最大:390
(平成20年度)地点数:282、検体数:3,384、平均:30、最小:0.33、最大:230
(平成21年度)地点数:275、検体数:3,300、平均:27、最小:0.92、最大:390
(平成22年度)地点数:270、検体数:3,240、平均:25、最小:1.1、最大:280
(平成23年度)地点数:252、検体数:3,024、平均:25、最小:1.7、最大:160
<一般環境(地域分類別)>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:ng/m3)
(平成23年度)
(全地区)地点数:252、平均:25、最小:1.7、最大:160
(一般環境)地点数:165、平均:20、最小:1.7、最大:59
(発生源周辺)地点数:55、平均:38、最小:5.0、最大:160
(沿道)地点数:32、平均:29、最小:10、最大:90
<発生源周辺>環境省及び地方公共団体の調査結果
(平成15年~平成21年度)
(事業場敷地内)53地点の幾何平均(53地点で合計82回測定された24時間平均値の幾何平均値)で150ng/m3、最大値は22,000ng/m3
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
(3)知見の科学的根拠の確実性について
マンガン及び無機マンガン化合物に係る発がん性以外の有害性については、(2)(略)に記載したとおり、人の神経行動学的機能への影響について、十分な定量的データのある知見として、Roelsら(1992)及びLucchiniら(1999)が存在する。このうち、労働者の曝露期間がより長く、多岐にわたる神経行動学的検査項目が実施され、より低濃度で影響のみられたLucchiniら(1999)の報告を、相当の確実な根拠を有する疫学研究の知見と判断した。
しかしながら、職業性曝露集団であること、過去の高濃度曝露による影響が関与している可能性を排除できないことなどについての不確実性が存在する。
このことから、知見の科学的根拠の確実性については相当の確実な根拠を有する疫学知見であるが、いくつかの不確実性が存在し、さらなる科学的知見の充実を要するものであることから、「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(平成26年3月3日改定)」における科学的知見の確実性Ⅱaに該当すると判断した。
(4)指針値の提案について(抄)
マンガンは人の必須微量元素であり、摂取されるマンガンは、食品や飲料水の経口摂取によるものが大部分である。しかしながら、労働者等における疫学知見では、吸入曝露により神経系への影響など明らかな健康影響が認められている。
吸入曝露した労働者等の疫学研究では、比較的低濃度においても神経行動学的検査によって神経系への影響が検出されていることから、疫学知見により認められる吸入曝露による神経行動学的機能への影響の発生をエンドポイントとして指針値を検討することは妥当であると判断した。
なお、飲料水の摂取によるマンガンへの曝露による健康影響については既に別途評価が行われ水質基準が設定されており、食事からの摂取量についても日本人の食事摂取基準で評価が行われている。マンガンの曝露形態を鑑みれば、今後、これらの評価を踏まえた総合的な曝露評価の検討も考慮すべきであろう。
①発がん性に係るリスク評価について
人への発がん性の明らかな証拠が得られていないこと、(1)①(略)のとおり、疫学研究及び動物実験ともに十分な定量的データがないことから、発がん性に係る評価値は算出しないこととした。
②発がん性以外の有害性に係るリスク評価について
マンガン及び無機マンガン化合物については、(2)(略)のとおり、相当の確実な根拠を有する疫学研究の知見であるLucchiniら(1999)によるリスク評価を行うことが適当であり、労働者において神経行動学的検査成績の有意な低下を引き起こす平均濃度である96.7μg/m3(総粉じん)をLOAELとし、職業曝露から一般環境への曝露の補正(8時間/24時間×240日/365日)を行うと、21μg/m3となる。LOAELからNOAELへ外挿するための不確実係数は、軽微な神経行動学的機能への影響をみていることを考慮し、著者からの指摘(Lucchini私信(2012)。詳細は別紙36ページ(略)を参照)も参考として5とし、個体差(乳幼児や高齢者等を含む。)を考慮した不確実係数として10を用いて不確実係数の積を50とする。また、男性労働者の生殖能への影響や胎児期の子宮内曝露が小児の早期の知能発達に影響を及ぼす可能性が示唆されていること、及び実験動物においても雄の生殖能への影響及び児への影響がみられていること、さらに、飲水曝露ではあるが、小児の神経行動の発達に影響を及ぼす可能性を示唆する知見があることを考慮し、健康リスクの低減の観点から、影響の重大性を考慮した係数として3を設定することが適切と考える。
以上より、総合的な係数として150を用い、マンガン及び無機マンガン化合物の発がん性以外の有害性に係る評価値は0.14μg/m3と算出される。
③指針値の提案について
以上より、マンガン及び無機マンガン化合物の指針値を年平均値0.14μgMn/m3以下とすることを提案する。ただし、測定分析の効率性を考慮し、本指針値との比較評価に当たっては、当面、総粉じん中のマンガン(全マンガン)の大気中濃度測定値をもって代用することで差し支えない。
(以下略)
9.参考資料
・平成26年4月・中央環境審議会大気・騒音振動部会健康リスク総合専門委員会「マンガン及びその化合物に係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/24461.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成26年4月30日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)」 https://www.env.go.jp/press/files/jp/24404.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第5部第1章)大気粉じん中の重金属類の測定方法(多元素同時測定方法) https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-5-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○塩化メチル
1.指針値
1年平均値が94μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:容器採取法
分析方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
3.設定経緯
令和2年8月・中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告
令和2年8月20日・中央環境審議会答申
令和2年8月20日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第2008201号)
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・密度:0.920g/cm3(20℃)、0.911g/cm3(25℃)(液体)、1.74~2.3g/L(0℃、101.3kPa)(気体)
・融点:-97~-97.7℃
・沸点:-23.73~-24.22℃
・蒸気圧:約480~510kPa(20℃)、573~575kPa(25℃)
・溶解性:水に易溶(4.579~7.250g/L(25℃)、4.800~5.325g/L(25℃))、液状では一般の有機溶剤と混じり合う
・オクタノール/水分配係数:logPow=0.91(25℃)
・換算係数:1 ppm=2.064mg/m3、1mg/m3=0.4845ppm(25℃、1,013hPa)
・ヘンリー則定数:4.15~6.05kPa-m3/mol、8.82×10-3atm-m3/mol
(2)生産量等
(平成30年)
・国内生産量:209,136t
・輸出量:23t(塩化メチルと塩化エチルの合計)
(3)用途
・主にシリコーン樹脂の合成原料として使用され、この他にメチルセルロース、界面活性剤や農薬の原料、ポリスチレン・フォーム等の発泡剤、ブチルゴム反応溶媒として使用される。
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC(1999) グループ3
・U.S. EPA(2001) グループD
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成29年度)
届出排出量(大気):880t(63.6%がプラスチック製品製造業から排出。その他、化学工業、非鉄金属製造業から排出)、届出外推計排出量:0t
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化(全体)>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成25年度)地点数:324、検体数:3,896、平均:1.5、最小:0.12、最大:6.3
(平成26年度)地点数:323、検体数:3,876、平均:1.5、最小:0.13、最大:8.5
(平成27年度)地点数:318、検体数:3,816、平均:1.5、最小:0.11、最大:8.0
(平成28年度)地点数:330、検体数:3,961、平均:1.5、最小:0.37、最大:5.2
(平成29年度)地点数:334、検体数:4,008、平均:1.4、最小:0.36、最大:4.9
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成29年度)
(一般環境)地点数:240、平均:1.4、最小:0.36、最大:4.9
(固定発生源周辺)地点数:35、平均:1.6、最小:1.1、最大:4.8
(沿道)地点数:57、平均:1.3、最小:0.47、最大:3.0
(沿道かつ固定発生源周辺)地点数:2、平均:1.3、最小:1.2、最大:1.4
(全体)地点数:334、平均:1.4、最小:0.36、最大:4.9
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
5.1 発がん性以外の有害性に係る評価値の算出について
塩化メチルについては、ヒトへの発がん性以外の有害性を示す可能性が高いものの、疫学研究では量-反応関係を示す十分な知見が得られていない。このため、発がん性以外の有害性に係る評価値を疫学研究に基づいて算出することは困難である。
一方、動物実験では、発がん性以外の有害性に関する一定の知見が得られており、かつ、発がん性以外の有害性に係るメカニズムについて明確な種間差を示す知見がみられないことから、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十次答申)」(平成26年4月中央環境審議会)により改定された「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(以下「ガイドライン」という。)に定める「指針値設定のための評価値算出の具体的手順」(以下「評価値算出手順」という。)に従い、動物実験の結果をヒトに外挿することにより、有害性に係る評価値を算出することとする。
当該値の算出に当たっては、実験動物の知見のなかで最も低濃度で小脳の組織への影響(顆粒層細胞の変性、萎縮)が認められたLandryら(1985)のC57BL/6マウスを使用した11日間の吸入曝露実験結果を用いることとする。C57BL/6マウスは塩化メチルへの曝露による影響について、他の系統のマウスよりも高感受性であるが、発生メカニズムが他の動物種(ヒトを含む。)やマウスの系統と異なるとの知見は得られていないため、評価値の算出に適用可能と考える。
Landryら(1985)の実施した吸入曝露実験のうち、1日当たりの曝露時間が22時間/日のものが一般環境下の曝露状況に近いものと言えるため、この曝露条件で得られたNOAEL 50ppmを評価値の算出に用いることとする。
小脳の組織への影響(顆粒層細胞の変性、萎縮)をエンドポイントとしたNOAELを50ppm(103mg/m3)とし、一般環境中での慢性曝露を想定して断続曝露から連続曝露に換算(×22時間/24時間。連続11日間の曝露のため、休日の補正はない。)した45ppm(94mg/m3)と、不確実係数としては、種間差として10、種内差(個体差)として10、曝露期間が短いことを考慮して係数10(これらの係数の積として1,000)を用いることが適当と考える。不確実係数(種間差、種内差(個体差)、曝露期間)設定については、評価値算出手順に基づき、以下の考え方により設定した。
評価値算出手順では、動物実験の結果をヒトに外挿する場合に、人間は実験動物より感受性が高いとの仮定のもとに種間差の不確実係数として、デフォルト10を採用している。WHO(1999)では種間差の10(デフォルト)を、トキシコキネティクス(TK;体内動態)に基づく係数103/5=4とトキシコダイナミクス(TD;生体との反応性)に基づく係数102/5=2.5に分ける考え方を示しており、評価値算出手順も、ヒトと実験動物の感受性の違いに応じて個別に検討することができるものとしている。塩化メチルでは、種間差のTK、TDに関する明らかな知見が得られなかったことを踏まえ、総合的に考えて10を種間差の不確実係数とすることが適切と考えた。
種内差(個体差)については、評価値算出手順では、これを平均的な人間集団のNOAELを感受性の高い集団に外挿するために設定する係数とし、デフォルト10としている。さらに、科学的に説明が可能な根拠がある場合には、10より小さい係数を用いることがあるとしている。ヒトではGSTT1遺伝子多型による酵素活性の差によって、呼気、血液中の塩化メチル濃度等の個人差があると考えられているため、これを踏まえると種内差(個体差)に10を用いることが適切と考えた。
曝露期間については、評価値算出手順では、指針値は生涯曝露を考慮した慢性影響を指標とするため、慢性曝露実験、あるいは亜慢性曝露実験の知見に基づき評価を行う、としているが、やむを得ず短期間の曝露実験の知見を用いて有害性評価を行う場合には、最大10の不確実係数を考慮する必要があるとしている。Landryら(1985)の吸入曝露実験は11日間と短期間であるため、不確実係数として10を用いることが適切と考えた。
5.2 指針値の提案について(抄)
発がん性以外の有害性に係る評価値は、Landryら(1985)の知見を基に、一般環境中での慢性曝露を想定して断続曝露のNOAELを連続曝露に換算し、不確実係数1,000(各種不確実係数の積)で除して94μg/m3と算出された。
発がん性に係る評価値は算出されず、発がん性以外の有害性に係る評価値は94μg/m3と算出されたことから、塩化メチルの指針値を年平均値94μg/m3以下とすることを提案する。
(以下略)
9.参考資料
・令和2年8月中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会「塩化メチルに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/press/108315/1201.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和2年8月20日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」 https://www.env.go.jp/press/108315/1200.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第2部第1章)大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)の測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-2-1.pdf 【NIES保管ファイル】
○アセトアルデヒド
1.指針値
1年平均値が120μg/m3以下であること
2.測定方法
試料採取方法:①固相(DNPH)捕集-溶媒抽出法、②溶液(DNPH)吸収-溶媒抽出法
分析方法:①ガスクロマトグラフ質量分析法/ガスクロマトグラフ(熱イオン化検出器法)/高速液体クロマトグラフ法/高速液体クロマトグラフ質量分析法、②高速液体クロマトグラフ法
3.設定経緯
令和2年8月・中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会報告
令和2年8月20日・中央環境審議会答申
令和2年8月20日・環境省水・大気環境局長通知(環水大総発第2008201号)
注)平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会報告でも指針値が検討されたが、評価値の算出方法についてWHOが異なる見解を書簡で示していることを受け、「WHOの書簡に示された内容の趣旨を早急に確認したうえで改めて指針値の算定方法の検証を行い、アセトアルデヒドの指針値の提案を行うことが適当である。」とされた。
4.基礎情報(設定時)
(1)物理化学的性状及び環境中での挙動等
・刺激性で息が詰まる臭いがあり、薄い濃度ではフルーティーな香りを持つ無色の揮発性の物質
・高い引火性及び可燃性を有し、水、ジエチルエーテル、エタノール等の一般的な溶剤と自由に混和
・比重:0.788
・融点:-123.5℃
・沸点:20.2℃
・蒸気圧:101.3kPa(20.16℃)
・溶解性:水、ジエチルエーテル、エタノール等の溶媒と自由に混和
・オクタノール/分配係数:logPow=0.63
・換算係数:1ppm=1.80mg/m3、1mg/m3=0.56ppm(25℃、1,013hPa)
(2)生産量等
(平成30年)
・国内生産量:88,519t(経済産業省 2018)
(3)用途
・合成原料(酢酸エチル、酢酸、過酢酸、無水酢等)
・防腐剤や防かび剤、写真現像用の薬品等
・合板の接着剤等(ホルムアルデヒドの代替品として)
5.毒性情報及び各種基準値(設定時)
(1)発がん性に関する評価
・IARC(1999) グループ2B
アルコール飲料の摂取に伴うアセトアルデヒドについてはグループ1に分類(IARC 2012)。
6.環境への排出等の状況(PRTR)(設定時)
(平成29年度)
届出排出量(大気):61.3t(約90%が化学工業から排出。その他に繊維工業、プラスチック製品製造業、輸送機械器具製造業、窯業・土石製品製造業等からの排出)
届出外推計排出量:2,129t(自動車からの排出)、248t(たばこからの排出)
7.環境中における検出状況(設定時)
<経年変化(全体)>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成25年度)地点数:304、検体数:3,648、平均:2.2、最小:0.48、最大:10
(平成26年度)地点数:296、検体数:3,552、平均:2.1、最小:0.63、最大:8.9
(平成27年度)地点数:305、検体数:3,660、平均:2.2、最小:0.52、最大:12
(平成28年度)地点数:305、検体数:3,660、平均:2.1、最小:0.41、最大:9.1
(平成29年度)地点数:314、検体数:3,768、平均:2.2、最小:0.33、最大:7.5
<地域分類別>(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)(濃度:μg/m3)
(平成29年度)
(一般環境)地点数:193、平均:2.1、最小:0.37、最大:7.5
(固定発生源周辺)地点数:23、平均:2.0、最小:1.3、最大:4.5
(沿道)地点数:95、平均:2.4、最小:0.33、最大:7.0
(沿道かつ固定発生源周辺)地点数:3、平均:4.3、最小:2.2、最大:7.4
(全体)地点数:314、平均:2.2、最小:0.33、最大:7.5
8.指針値の根拠の概要(専門委員会報告抜粋)
5.1 発がん性に係るリスク評価について
アセトアルデヒドの発がん性に係るリスク評価については、前述のとおり、現在得られている知見からは、量-反応評価を行うことが困難であるため、評価を行うことはできないと判断する。
しかし、これまでに得られている知見からは、ヒトへの発がん性が示唆されるため、今後の研究の進歩によって、発がんに係る量-反応評価を行うことのできる新しい知見が集積された場合には、発がん性に係るリスク評価の実施について改めて検討する必要がある。
5.2 発がん性以外の有害性に係る評価値の算出について
アセトアルデヒドについては、ヒトへの発がん性以外の有害性を示す可能性が高いものの、ヒトの疫学研究では量-反応関係を示す十分な知見が得られていないため、当該疫学研究から発がん性以外の有害性に係る評価値を算出することは困難である。
一方、動物実験では、既に発がん性以外の有害性に関する一定の知見が得られており、かつ、発がん性以外の有害性に係るメカニズムには明確な種間差が認められないことから、評価値算出手順に従い、動物実験の結果をヒトに外挿することにより、有害性に係る評価値を算出することとする。また、日本人の約半数は、代謝酵素の活性の違いによりアセトアルデヒドを代謝する速度が遅く、体内のアセトアルデヒド濃度が高い状態で維持されることが想定されていることから、有害性評価を行う際には、当該代謝活性の違いに伴うリスクの増加についても考慮に入れて検討を行った。
当該値の算出に当たっては、Dormanら(2008)のラットへの13週間の吸入曝露実験の結果を用いることとする。具体的には、当該動物実験の結果において、ラットの鼻腔上皮の変性の発生が見られなかった50ppm(90mg/m3)をNOAELとし、一般環境中での慢性曝露を想定して断続曝露から連続曝露に換算(6時間/24時間×5日/7日)した8.9ppm(16mg/m3)と、不確実係数として、トキシコダイナミクス(感受性(生体との反応性))の差を踏まえた種間差2.5、種内差(個体差)として10、影響の重大性に関する係数として、発がんの恐れを考慮して係数5(これらの係数の積として125)を用いることが適当と考える。
不確実係数(種間差、種内差(個体差)等)及び影響の重大性に関する係数の設定については、評価値算出手順に基づき、以下の考え方により設定した。
種間差については、トキシコキネティクス(TK:体内動態)とトキシコダイナミクス(TD:生体との反応性)に分けて設定することが可能である。ヒト及びラットの鼻腔内における空気の流れとアセトアルデヒドが鼻腔上皮に吸着した後の動態をCFD・PBPKモデルを用いて検討した結果(Teeguardenら 2008)、アセトアルデヒドへの曝露濃度が同じ条件で、ヒトの鼻腔上皮におけるアセトアルデヒドやH+の濃度はラットよりも低いことから、ヒトのTKに関する感受性は実験動物と同じか低い場合に相当するとして、TK=1、TD=2.5を種間差の不確実係数とすることが妥当と考えた。
また、種内差(個体差)については、次のように考えた。
CFD・PBPKモデルによる検討結果(Teeguardenら2008)では、ヒトの鼻腔におけるアセトアルデヒド代謝によるクリアランスや鼻腔組織でのH+産生(酸性化)に対するALDH2の寄与は小さいと推定されている。しかしながら、日本人の40%がアセトアルデヒドの代謝活性が低いALDH2変異型を保有すること、Aldh2ノックアウトマウスでは野生型マウスと比べて鼻腔組織(呼吸上皮)におけるびらんや変性の発生率、傷害の程度が大きいとの報告があることを踏まえると、種内差(個体差)に10を用いることが適切と考えた。
なお、U.S.NRC(2009)では、Dormanら(2008)のラットを用いた13週間の吸入曝露期間をさらに延長してもNOAEL(50ppm)の濃度では傷害の発生はないと考えられることから曝露期間に関する不確実性は不要と考えたと説明されている。ここでもこの考え方に従い、曝露期間の差による不確実係数を不要とした。
また、影響の重大性に関する係数については、アセトアルデヒドは発がん性が示唆されるものの、発がん性に係るリスク評価が不可能であり、かつ、発がん性に係る動物実験の多くで、鼻腔上皮の変性が過形成や化生を経て腫瘍へと進行することが示されていることから、発がんの恐れを考慮して設定することが適当と考えた。
なお、本評価文書案では、Appelmanら(1982, 1986)等よりも低い曝露濃度段階(50ppm)を含み、曝露期間も13週間と長く、鼻腔内の病理組織分析も詳細に報告されているDormanら(2008)を量-反応関係の評価に用いたこと、及びTeeguardenら(2008)によるヒト及びラットの鼻腔内のアセトアルデヒドの動態の検討結果を種間差の不確実係数(TK、TD)に用いたことによって、不確実係数がU.S.EPA(1991)、WHO(1995)、カナダ環境省・保健省(2000)等の耐容濃度等の算出時よりも小さくなった。
5.3 指針値の提案について(抄)
発がん性以外の有害性に係る評価値は、Dormanら(2008)の知見を基に、一般環境中での慢性曝露を想定して断続曝露のNOAELを連続曝露に換算し、不確実係数等で除して120μg/m3と算出された。
発がん性に係る評価値は算出されず、発がん性以外の有害性に係る評価値は120μg/m3と算出されたことから、アセトアルデヒドの指針値を年平均値120μg/m3以下とすることを提案する。
(以下略)
9.参考資料
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-2.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成18年11月・中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、及び1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について」(別添2-1)アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について https://www.env.go.jp/air/kijun/toshin/08-3.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和2年8月・中央環境審議会大気・騒音振動部会有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会「アセトアルデヒドに係る健康リスク評価について」 https://www.env.go.jp/press/108315/1202.pdf 【NIES保管ファイル】
・令和2年8月20日・中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」 https://www.env.go.jp/press/108315/1200.pdf 【NIES保管ファイル】
・平成31年3月・環境省水・大気環境局大気環境課「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル、排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル、排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル、排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル」(第4部第1章)大気中のホルムアルデヒド及びアセトアルデヒドの測定方法 https://www.env.go.jp/air/osen/manual2/pdf_rev201903/01_chpt1-4-1.pdf 【NIES保管ファイル】