2025/05/075分で読めます
気候変動の影響を、私たちはどのように“実感”できるのでしょうか。国環研の「生物季節モニタリング」は、市民の手で生きものの季節の変化を記録し、気候の変化を“見える化”する全国的な取り組みです。自然へのまなざしを未来につなぐ、新たな観測のかたちに迫ります。
桜の開花やウグイスの初鳴きなど、生きものたちの活動には季節のリズムが反映されています。こうした「生物季節」は、気候変動の影響を鋭敏に捉える自然からのメッセージであり、その変化を観察することは、気候変動の実態を身近に理解する上で大きな意味を持ちます。

1953年から2020年まで、日本では気象庁が全国の気象台や測候所で多様な生物季節のデータを蓄積してきました。しかし2021年からは観測種目が大幅に縮小されました。
このような状況を受け、国環研では、過去の観測の流れを引き継ぎつつも、新たな形での長期観測体制を築くため、市民と連携した「生物季節モニタリング」を2021年度にスタートさせました。
この取り組みは、気候変動の影響を科学的に把握するための手段であると同時に、四季の移ろいに心を寄せる日本人の感性や、自然との関わりを大切にする文化を再確認する機会でもあります。俳句や歳時記、農業や地域の祭りなど、日本には自然の変化を丁寧に見つめる文化があります。生物季節の観測を通じて、そうした文化や価値観をささえる「生き物を意識する機会」を多くの方と共有することも、本プロジェクトの大切な目的のひとつです。
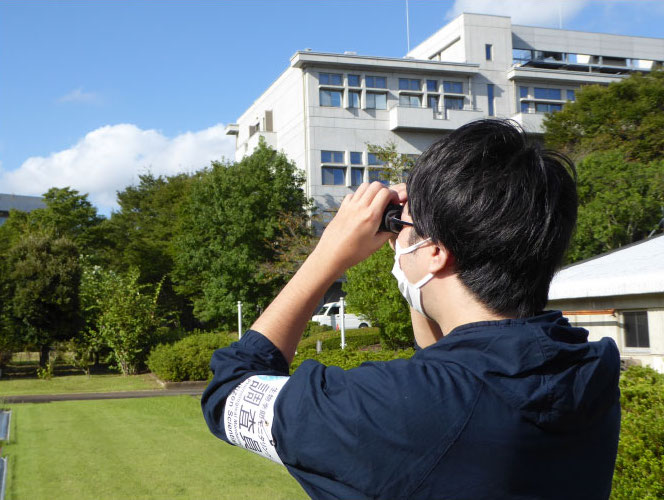
「生物季節モニタリング」では、気象庁がかつて使用していた観測マニュアルをベースに、市民にも扱いやすくアレンジした調査マニュアルを作成しています。このマニュアルは、株式会社建設環境研究所の支援のもとデザインされ、専門的な内容をわかりやすく、視覚的にも親しみやすい形にまとめられています。
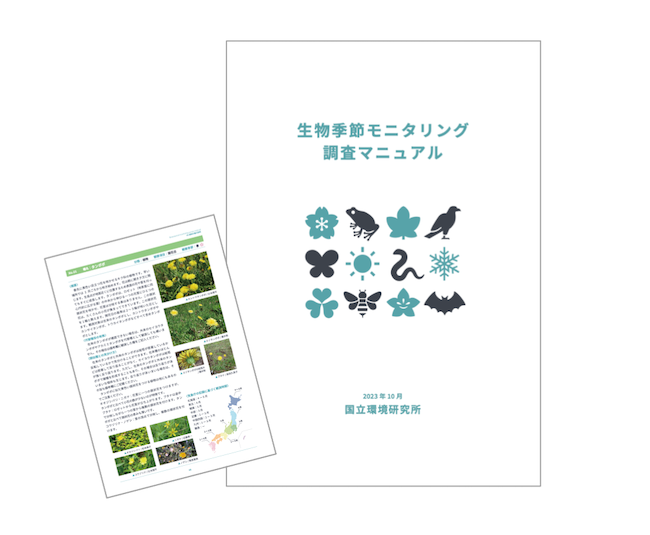
調査対象となるのは、植物32種目と動物34種目です。市民調査員は、身近に観察できる生物を選び、開花日、初鳴き日、初見日などを記録します。観察結果は、国環研の担当者に報告され、確認、整理、統合ののち、全国規模での集計・解析に活用されます。
参加者は、オンラインから誰でも登録可能で、必要なマニュアルや資料もすべて公開されています。初心者でも安心して始められる設計となっており、日常の中で気軽に取り組めるのが特徴です。
2021年度の開始以来、市民調査員から7,000件以上の報告があり、都市部から農山村まで、全国各地で多様な生物季節現象のデータが蓄積されつつあります。
また、活動の広がりに合わせて、ニュースレター「いきものこよみ」をこれまでに10回発行しています。調査の進捗や、観察された生きもののトピック、季節の自然に関するコラムなどを掲載し、調査員の方々の学びを促進しています。
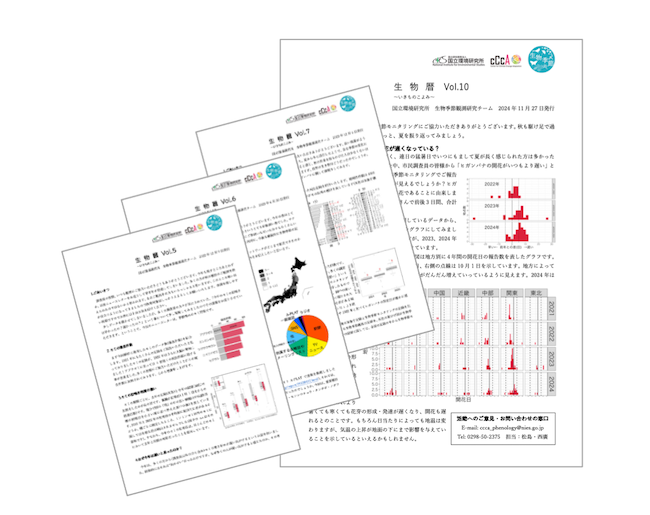
さらに、市民調査で得られたデータを活用した研究として、2024年には「アブラゼミの初鳴き」に関する気象要因の分析結果が公表されました。この研究では、気温や降水量といった要因が、アブラゼミの鳴き始めにどのように影響するかを科学的に明らかにし、都市における生物の季節変化を理解する手がかりとして注目されました。
「生物季節モニタリング」は今後、さらに多くの人々の参加を促し、全国的なデータネットワークへと発展することを目指しています。学校教育や地域活動との連携を深め、より多様な参加の形を広げていくことが課題です。また、スマートフォンアプリやAIを活用した観察支援、画像認識技術の導入など、新たな技術の活用も模索されています。
さらに、2025年4月からは、「国立環境研究所生物季節モニタリングデータの公開及び利用に関する規約」に基づき、収集したデータの公開を本格的に開始しました。これにより、参加者のプライバシーに配慮しつつ、集められた観測データを広く科学研究や行政施策に活用できる仕組みが整いました。
市民と研究者が協力して築くこのモニタリング体制は、気候変動時代における新たな「環境観察のかたち」です。日々の暮らしの中で自然の変化に目を向けることが、地球の未来を考える第一歩となる──そんなメッセージを、多くの人に届けていきたいと考えています。