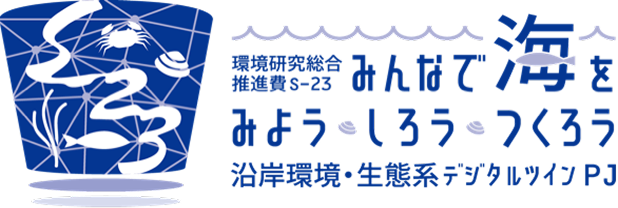PROJECTプロジェクト
テーマ04
自然共生サイト・内湾における
低次−高次生態系網の
数理モデルの開発
BACKGROUND背景
沿岸域は、生物生産性が高く、多様な生物種が豊富に存在し、「生物多様性の要」となる海域です。
しかし、これらの海域は、人間活動の影響を受けやすく、近年では窒素・リン(栄養塩)流入の減少、気候変動などの
環境変化により、生態系が変化しています。一方、生態系の変化は、
環境と多様な生物の絡み合いの結果であり、その仕組みの解明と予測は困難を極めます。
この困難の解決に向け、テーマ4では 「生息環境」、「植物プランクトンー動物プランクトンー小型魚介類ー大型魚介類の食物網」、
「各生物の生理生態」を調べ、これら要素をコンピュータ上で相互作用させた
仮想生態系:「低次-高次生態系網モデル」を構築します。
このモデルを活用し、生態系の変化と、そのカギとなる要素を明らかにすることを目指します。
しかし、これらの海域は、人間活動の影響を受けやすく、近年では窒素・リン(栄養塩)流入の減少、気候変動などの
環境変化により、生態系が変化しています。一方、生態系の変化は、
環境と多様な生物の絡み合いの結果であり、その仕組みの解明と予測は困難を極めます。
この困難の解決に向け、テーマ4では 「生息環境」、「植物プランクトンー動物プランクトンー小型魚介類ー大型魚介類の食物網」、
「各生物の生理生態」を調べ、これら要素をコンピュータ上で相互作用させた
仮想生態系:「低次-高次生態系網モデル」を構築します。
このモデルを活用し、生態系の変化と、そのカギとなる要素を明らかにすることを目指します。
METHOD方法
数理モデル・現地調査・室内実験を突き合わせ、生態系を紐解く
テーマ4は3つのサブテーマから構成され、数理モデル化、フィールド調査、室内実験を駆使して、浅場(干潟・藻場)と内湾(東京湾・大阪湾など)における水質、生物種、捕食・被食関係を解明し、浅場と内湾の仮想生態系をコンピュータ上に構築します。
SUB-THEMEサブテーマ
サブテーマ01
低次−高次生態系網の数理モデル化
生態系を構成する主要生物の代謝、生活史、生息環境と,生物間の食う食われる関係を定式化します。また、サブテーマ2、3、テーマ2から得られた知見を統合し、実海域に適用させた低次-高次生態系網モデルを開発します。
研究メンバーサブテーマ02
自然共生サイトにおける生態系網の観測・実験による評価
干潟・浅場での生物種・量の構成、食う食われる関係、生息環境を観測・実験から推定します。また、干潟・浅場が沖合の生物生産に与える寄与を推定します。
研究メンバーサブテーマ03
閉鎖性内湾における生態系網の観測・実験による評価
東京湾・大阪湾などの生物種・量の構成、食う食われる関係、環境との関係を観測・文献調査から推定します。特に東京湾では、1970年代~現在にわたる生物データから生態系と外部環境の関係性を推定します。
研究メンバーGOAL目標
~生物多様性の保全に向けた環境政策の立案に貢献する~
低次-高次生態系網モデルは、環境変化や環境政策による多様な生物群の応答を予測します。
また、生物多様性保全の観点から、効果的な環境政策の立案に貢献することを目指しています。
また、生物多様性保全の観点から、効果的な環境政策の立案に貢献することを目指しています。